

yomitaos
@chsy7188
居場所を増やすために始めてみました。居心地のよい場所にしたいですね。
- 2026年2月16日
 家族葉真中顕読み終わった@ 自宅尼崎連続変死事件は、日本という「家族愛」を過剰に神聖視する国だからこそ起こった事件だと考えている。私は抽象的な愛という概念を盾に人を動かそうとする連中が嫌いなので、「自分だけは絶対に騙されない」と信じたい思いが強い。 しかしこの本を読み通して思ったのは、この渦中にあっては何もできず、ガラス玉の眼で易々諾々と首謀者の命令に従っていくことになるんだろうなという諦念だった。 事後だから言えることだが、家族の問題を警察に相談しても意味がない。彼らは民事不介入を盾に動こうとしない。警察は正義のためにあるのではなく、警察組織というある種の家族の論理を全うするためにある。家族を守るためにルールを逸脱することは滅多にない。 作中にも出てくる言葉で印象的なのが、とある女が述べた以下のセリフ。誰かを操るには、考えさせてはいけない。人形にしてしまわないといけない。そんな含蓄のこもった言葉だと思う。 「考えては駄目よ。迷っても駄目。自分で決断しても駄目。人は、自分で考えてなにかを決めるとき孤独になってしまうの。あなたが寂しくなかったのは、考えなかったからよ。なにも自分で決めなかったから。だから、いい人生だったの」
家族葉真中顕読み終わった@ 自宅尼崎連続変死事件は、日本という「家族愛」を過剰に神聖視する国だからこそ起こった事件だと考えている。私は抽象的な愛という概念を盾に人を動かそうとする連中が嫌いなので、「自分だけは絶対に騙されない」と信じたい思いが強い。 しかしこの本を読み通して思ったのは、この渦中にあっては何もできず、ガラス玉の眼で易々諾々と首謀者の命令に従っていくことになるんだろうなという諦念だった。 事後だから言えることだが、家族の問題を警察に相談しても意味がない。彼らは民事不介入を盾に動こうとしない。警察は正義のためにあるのではなく、警察組織というある種の家族の論理を全うするためにある。家族を守るためにルールを逸脱することは滅多にない。 作中にも出てくる言葉で印象的なのが、とある女が述べた以下のセリフ。誰かを操るには、考えさせてはいけない。人形にしてしまわないといけない。そんな含蓄のこもった言葉だと思う。 「考えては駄目よ。迷っても駄目。自分で決断しても駄目。人は、自分で考えてなにかを決めるとき孤独になってしまうの。あなたが寂しくなかったのは、考えなかったからよ。なにも自分で決めなかったから。だから、いい人生だったの」 - 2026年2月14日
 まず牛を球とします。柞刈湯葉読み終わった@ 自宅
まず牛を球とします。柞刈湯葉読み終わった@ 自宅 - 2026年2月12日
 夜の道標芦沢央読み終わった@ 自宅子どもが理不尽な目に遭う物語は本当につらい。まだひとりの人間として生きていけず、それ故に身近な大人の示す道しるべに従っていかないといけない。 道を示すし従わなければ怒るのに、その結果失敗しても責任を取ってくれるわけではない。そうして落ちぶれた子どもを、国や社会が掬い上げてくれるかというと、そんなことに期待もできない。 世の中で正しいとされている生き方から外れてしまった子どもが起こしたcrimeは本当はsinであり、それは個人に帰することのできないものなのではないか。そんなことを読後に感じた。 あまりにも残酷な仕打ちを受ける子どもと、醜悪の権化のような大人が出てきて、精神的なダメージがとても大きい物語であるため、体調の良いときに読み始めることをおすすめする。
夜の道標芦沢央読み終わった@ 自宅子どもが理不尽な目に遭う物語は本当につらい。まだひとりの人間として生きていけず、それ故に身近な大人の示す道しるべに従っていかないといけない。 道を示すし従わなければ怒るのに、その結果失敗しても責任を取ってくれるわけではない。そうして落ちぶれた子どもを、国や社会が掬い上げてくれるかというと、そんなことに期待もできない。 世の中で正しいとされている生き方から外れてしまった子どもが起こしたcrimeは本当はsinであり、それは個人に帰することのできないものなのではないか。そんなことを読後に感じた。 あまりにも残酷な仕打ちを受ける子どもと、醜悪の権化のような大人が出てきて、精神的なダメージがとても大きい物語であるため、体調の良いときに読み始めることをおすすめする。 - 2026年2月12日
 寝ながら学べる構造主義内田樹読み始めた@ 自宅
寝ながら学べる構造主義内田樹読み始めた@ 自宅 - 2026年2月11日
 日本人が立ち返る場所内田樹,養老孟司読み終わった@ 自宅
日本人が立ち返る場所内田樹,養老孟司読み終わった@ 自宅 - 2026年2月5日
 魂婚心中芦沢央読み終わった@ 自宅芦沢央は現代もののミステリ作家というイメージだったが、この本で描かれているのはSF的世界。しかしいつものどんでん返しは共通しており、今回もしっかり騙された。 Googleの奴隷としての仕事「SEO」と、死後の量刑を決めるための閻魔帳との組み合わせには思わず笑ってしまった。どうしたらこんなネタを思いつけるのか。
魂婚心中芦沢央読み終わった@ 自宅芦沢央は現代もののミステリ作家というイメージだったが、この本で描かれているのはSF的世界。しかしいつものどんでん返しは共通しており、今回もしっかり騙された。 Googleの奴隷としての仕事「SEO」と、死後の量刑を決めるための閻魔帳との組み合わせには思わず笑ってしまった。どうしたらこんなネタを思いつけるのか。 - 2026年2月4日
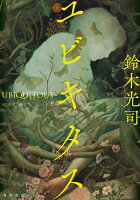 ユビキタス鈴木光司読み終わった@ 自宅人間はなんでこうも偉そうなのか。自然を調伏できると思い込んでいるし、動物を隷属できるつもりでふるまっているが、一度牙を剥かれると人間のような軟弱な生き物などあっという間に滅びてしまうだろう。 常日頃からそんなことを考えている自分としては、この作品で描かれる「植物支配世界」はじゅうぶんにあり得ることだと思える。むしろそうなってくれると面白い。 ホラーの名作「リング」を超える恐怖と帯で謳われているが、これは言い得て妙。人間を主人公として考えるならホラーだが、植物に隷属させられるものとして扱うならSFとして読める。多くの人は前者として読むだろうから、これは恐怖以外の何物でもない。 個人的に大好きな「ループ」とある意味で双璧を成す、大型SF作品として楽しめる傑作だと思う。
ユビキタス鈴木光司読み終わった@ 自宅人間はなんでこうも偉そうなのか。自然を調伏できると思い込んでいるし、動物を隷属できるつもりでふるまっているが、一度牙を剥かれると人間のような軟弱な生き物などあっという間に滅びてしまうだろう。 常日頃からそんなことを考えている自分としては、この作品で描かれる「植物支配世界」はじゅうぶんにあり得ることだと思える。むしろそうなってくれると面白い。 ホラーの名作「リング」を超える恐怖と帯で謳われているが、これは言い得て妙。人間を主人公として考えるならホラーだが、植物に隷属させられるものとして扱うならSFとして読める。多くの人は前者として読むだろうから、これは恐怖以外の何物でもない。 個人的に大好きな「ループ」とある意味で双璧を成す、大型SF作品として楽しめる傑作だと思う。 - 2026年1月27日
 失われた貌櫻田智也読み終わった@ 自宅年間8万人以上もの行方不明届が出されている日本。悪しき戸籍制度により逃げることなど叶わないと思いきや、案外多くの人が失踪を遂げているのだと驚いた。失踪欲のある自分は、それを材に取ったこの小説を楽しみにしていた。 うるさいくらい「どんでん返し」が宣伝文句として謳われておりウンザリしていたが、しっかり騙された。というより、思いつきもしなかったというのが正直なところ。事件当事者たちが行動するにあたっての、論理と情緒のバランスが絶妙だった。なるほど、非常識で非論理的ではあるが、心理的には納得できる。 失踪するに足る理由を見出した時点で、この物語には成功を約束されていたのかもしれない。
失われた貌櫻田智也読み終わった@ 自宅年間8万人以上もの行方不明届が出されている日本。悪しき戸籍制度により逃げることなど叶わないと思いきや、案外多くの人が失踪を遂げているのだと驚いた。失踪欲のある自分は、それを材に取ったこの小説を楽しみにしていた。 うるさいくらい「どんでん返し」が宣伝文句として謳われておりウンザリしていたが、しっかり騙された。というより、思いつきもしなかったというのが正直なところ。事件当事者たちが行動するにあたっての、論理と情緒のバランスが絶妙だった。なるほど、非常識で非論理的ではあるが、心理的には納得できる。 失踪するに足る理由を見出した時点で、この物語には成功を約束されていたのかもしれない。 - 2026年1月8日
 1兆円を盗んだ男マイケル・ルイス読み終わった@ 自宅目の前で溺れているひとりの子供を助けるより、将来低い確率で起こる災害で命を落とす大勢の人を助けること、そのために大金を稼いで寄付する。それは一見間違っていなそうだけれど、何か人間として、大きな欠陥を抱えているように感じられる。 この社会で生きていると、測定できないことは無価値なんだろうかと途方に暮れることがある。測定できないのは計測する側の能力や技術が不足しているだけかもしれないし、そもそも計測できるものに必ず価値があるわけでもない。追い続ける指標が、ただ計測しやすかたっただけという、それこそ無意味な設定であったこともある。WEB企業に長く在籍している自分には、それが実感としてある。 禁錮25年という重罪を課されたサム・バンクマン・フリードは、効果的利他主義という歪んだ思想のもと、マネーゲームで得た利益を寄付に回していたが、その額を正確に把握していないし、それによって何人を救えたのかも分かっていない。 溺れた子供は体温のある生きた人間だが、確率上存在する犠牲者の数は、ただの数字でしかない。データベース上のその数字が増えていればそれで良しというのは、本当に世の中を良くしていると言えるのだろうか? 本書では莫大な金が動いていく様を克明に描いているが、カネを持ってる人がさらに潤っているだけで、世界は少しも良くなっていないように思う。いま世界を席巻している効果的利他主義者のふるまいが、心底気持ち悪くて吐き気がする。
1兆円を盗んだ男マイケル・ルイス読み終わった@ 自宅目の前で溺れているひとりの子供を助けるより、将来低い確率で起こる災害で命を落とす大勢の人を助けること、そのために大金を稼いで寄付する。それは一見間違っていなそうだけれど、何か人間として、大きな欠陥を抱えているように感じられる。 この社会で生きていると、測定できないことは無価値なんだろうかと途方に暮れることがある。測定できないのは計測する側の能力や技術が不足しているだけかもしれないし、そもそも計測できるものに必ず価値があるわけでもない。追い続ける指標が、ただ計測しやすかたっただけという、それこそ無意味な設定であったこともある。WEB企業に長く在籍している自分には、それが実感としてある。 禁錮25年という重罪を課されたサム・バンクマン・フリードは、効果的利他主義という歪んだ思想のもと、マネーゲームで得た利益を寄付に回していたが、その額を正確に把握していないし、それによって何人を救えたのかも分かっていない。 溺れた子供は体温のある生きた人間だが、確率上存在する犠牲者の数は、ただの数字でしかない。データベース上のその数字が増えていればそれで良しというのは、本当に世の中を良くしていると言えるのだろうか? 本書では莫大な金が動いていく様を克明に描いているが、カネを持ってる人がさらに潤っているだけで、世界は少しも良くなっていないように思う。いま世界を席巻している効果的利他主義者のふるまいが、心底気持ち悪くて吐き気がする。 - 2026年1月7日
 ちひろさん 10安田弘之読み終わった@ 自宅共感力に乏しい自分が、漫画を読んで感情を揺さぶられることはほとんどない。「ちひろさん」は、そんな私が唯一涙する漫画だ。実在の人物に憧れることなどないが、ちひろさんのようにはなりたい。それは彼女が、私の理想とする生き方を貫いているから。 ちひろさんは、世間で良しとされている不都合に抵抗し続けている。笑顔でNOを突きつける。ニコニコと中指を突き立てる。 この世界は、求めていないのに発信してくる奴が多すぎて煩すぎる。毎日ウンザリする。ちひろさんは社会とつながることを拒絶してはいないけれど、付き合い方を弁えている。 何があっても嘘をついてはいけない?それは状況によるでしょう?際限なく距離を詰めてくる人には、嘘で対処することも必要だ。ちひろさんは、出会う人それぞれに、個別のやり方で誠実に対応してる。属性や肩書き、性別、年齢で決めつけない。成熟した人間とは、そのような態度で臨める人のことを指すのだと思う。 コミックは完結してしまったが、ちひろさんは今もどこかでさらさらと生きている。そう信じられるような、物語強度のある作品だ。彼女のように生き抜いていきたい。
ちひろさん 10安田弘之読み終わった@ 自宅共感力に乏しい自分が、漫画を読んで感情を揺さぶられることはほとんどない。「ちひろさん」は、そんな私が唯一涙する漫画だ。実在の人物に憧れることなどないが、ちひろさんのようにはなりたい。それは彼女が、私の理想とする生き方を貫いているから。 ちひろさんは、世間で良しとされている不都合に抵抗し続けている。笑顔でNOを突きつける。ニコニコと中指を突き立てる。 この世界は、求めていないのに発信してくる奴が多すぎて煩すぎる。毎日ウンザリする。ちひろさんは社会とつながることを拒絶してはいないけれど、付き合い方を弁えている。 何があっても嘘をついてはいけない?それは状況によるでしょう?際限なく距離を詰めてくる人には、嘘で対処することも必要だ。ちひろさんは、出会う人それぞれに、個別のやり方で誠実に対応してる。属性や肩書き、性別、年齢で決めつけない。成熟した人間とは、そのような態度で臨める人のことを指すのだと思う。 コミックは完結してしまったが、ちひろさんは今もどこかでさらさらと生きている。そう信じられるような、物語強度のある作品だ。彼女のように生き抜いていきたい。 - 2025年12月19日
 新しいリベラル橋本努,金澤悠介読み終わった@ 自宅
新しいリベラル橋本努,金澤悠介読み終わった@ 自宅 - 2025年12月19日
- 2025年12月18日
 陰謀論と排外主義 分断社会を読み解く7つの視点古谷経衡,山崎リュウキチ,清義明,藤倉善郎,藤倉善郎ほか,藤倉善郎他,選挙ウォッチャーちだい,黒猫ドラネコ読み終わった@ 自宅
陰謀論と排外主義 分断社会を読み解く7つの視点古谷経衡,山崎リュウキチ,清義明,藤倉善郎,藤倉善郎ほか,藤倉善郎他,選挙ウォッチャーちだい,黒猫ドラネコ読み終わった@ 自宅 - 2025年12月17日
 ソーシャルメディア・プリズムクリス・ベイル,松井信彦読み終わった@ 自宅
ソーシャルメディア・プリズムクリス・ベイル,松井信彦読み終わった@ 自宅 - 2025年12月16日
 過疎ビジネス横山勲読み終わった@ 自宅ふるさと納税という仕組み自体が気に食わない。どう考えても政府側の利権で動いてる制度でしかないのに、お得だからという理由で使っている人たちの気がしれないと今も思っている。その企業版があるということは、この本で取り上げられている一連の事件で初めて知った。 どちらも公金を使うという意味でもっと敏感にならないといけないが、この企業版の杜撰な設計には呆れるほかない。カネを持ってる企業が節税&利益還流を狙って寄付を行い、手を組んだコンサルが自社利益になるようにターゲットと自治体を喰いものにする。ここ10年ほどでもっとも穢らわしい、産業廃棄物のようなビジネスだ。 もっとも腐っているのは自治体もそうで、最終決定権が自治体の長(と議会)あるのだから、コンサルだけが悪いというわけではない。結局のところしわ寄せが来るのはその自治体に住まう人たちだから、皆で争っていかなければ太刀打ちできない。つまるところ、民主主義が求められる。 強権的で極右の高市政権を支持する人が多くを占めるこの国に、もっとも欠けているのが民主主義だから、この事件はけっして人ごとではない。自分たちが住む自治体で同じことが起こったとき、強権を振りかざし詭弁を弄する長に立ち向かえるだろうか。 この事件で最後まで権力を手放そうとしなかった町長は、結果的に選挙で敗退した。しかし、首位との差は400票程度で、投票者の内、4割近くの住民はこの愚かな長をそれでも支持している。 報道が機能しているこの町ですらこの数字だとすると、私の住んでいる自治体では現職が支持され続けることになりそうだ。
過疎ビジネス横山勲読み終わった@ 自宅ふるさと納税という仕組み自体が気に食わない。どう考えても政府側の利権で動いてる制度でしかないのに、お得だからという理由で使っている人たちの気がしれないと今も思っている。その企業版があるということは、この本で取り上げられている一連の事件で初めて知った。 どちらも公金を使うという意味でもっと敏感にならないといけないが、この企業版の杜撰な設計には呆れるほかない。カネを持ってる企業が節税&利益還流を狙って寄付を行い、手を組んだコンサルが自社利益になるようにターゲットと自治体を喰いものにする。ここ10年ほどでもっとも穢らわしい、産業廃棄物のようなビジネスだ。 もっとも腐っているのは自治体もそうで、最終決定権が自治体の長(と議会)あるのだから、コンサルだけが悪いというわけではない。結局のところしわ寄せが来るのはその自治体に住まう人たちだから、皆で争っていかなければ太刀打ちできない。つまるところ、民主主義が求められる。 強権的で極右の高市政権を支持する人が多くを占めるこの国に、もっとも欠けているのが民主主義だから、この事件はけっして人ごとではない。自分たちが住む自治体で同じことが起こったとき、強権を振りかざし詭弁を弄する長に立ち向かえるだろうか。 この事件で最後まで権力を手放そうとしなかった町長は、結果的に選挙で敗退した。しかし、首位との差は400票程度で、投票者の内、4割近くの住民はこの愚かな長をそれでも支持している。 報道が機能しているこの町ですらこの数字だとすると、私の住んでいる自治体では現職が支持され続けることになりそうだ。 - 2025年12月16日
 怪獣を解剖する 下(2)サイトウ・マド読み終わった@ 自宅「人のためになることをする」 「この世界を少しでも良いものにする」 大方の仕事はそのための手段として存在していて、永遠に完成しないピラミッドのレンガひとつ分くらいの活躍しかできずに、人は一生を終える。それの何と美しいことか。 ただ、その目的を叶えるスパンは人によって違う。目の前の人を救いたい樋口、自分がいなくなった後も活きる研究がしたい本多、100年以上先まで見据えた環境改善を望む金子。みんな大目的は一緒なのに、そのために取りたい行動が噛み合わず険悪な空気になる。 これって、誰しもが仕事で経験することの縮図なのではと思った。怪獣の後始末というエンタメを通して働くことの意味を問う、極上のお仕事マンガだ。
怪獣を解剖する 下(2)サイトウ・マド読み終わった@ 自宅「人のためになることをする」 「この世界を少しでも良いものにする」 大方の仕事はそのための手段として存在していて、永遠に完成しないピラミッドのレンガひとつ分くらいの活躍しかできずに、人は一生を終える。それの何と美しいことか。 ただ、その目的を叶えるスパンは人によって違う。目の前の人を救いたい樋口、自分がいなくなった後も活きる研究がしたい本多、100年以上先まで見据えた環境改善を望む金子。みんな大目的は一緒なのに、そのために取りたい行動が噛み合わず険悪な空気になる。 これって、誰しもが仕事で経験することの縮図なのではと思った。怪獣の後始末というエンタメを通して働くことの意味を問う、極上のお仕事マンガだ。 - 2025年12月16日
 フェイク・マッスル日野瑛太郎読み終わった@ 自宅スポーツとは、そもそもが不平等なものだと思う。筋肉のつきやすさは個人差が大きく、健康的な食事や生活が続けられるかどうかには金が関わってくる。そうして「ナチュラル(ノン・ドーピング)」でベストな体をつくりあげられるのは、限られた人間だけだろう。だから、心身への悪影響を鑑みた上でドーピングに手を出すのは悪いことではないと考えていた。 この小説は、とある男性アイドルに持ち上がったドーピング疑惑を、週刊誌記者が潜入取材で暴いていくという筋書きだ。意外な結末を迎えることへの驚きもあるが、面白いのは、なんとかドーピングの事実を拾い上げるためにアイドルの尿を得ようと立ち回るという、記者として必死に動いている様が滑稽なところだ。主人公が真面目で好感が持てることもあり、ついつい肩入れしたくなってくる。 この結末を予想できる人は、たぶん筋肉をつけるということを科学的に考えられる人だと思う。読み終えてなお、ドーピングが悪いものとは思えない。が、違法なドーピング薬を密売している側は確実に悪だろう。題材が突飛なので見落としそうになるが、悪を追う正統派ミステリとして楽しめる快作だ。 ※欠点として挙げるなら、警察など公権力側がポンコツすぎる。ご都合主義感があるのは否めなかった。
フェイク・マッスル日野瑛太郎読み終わった@ 自宅スポーツとは、そもそもが不平等なものだと思う。筋肉のつきやすさは個人差が大きく、健康的な食事や生活が続けられるかどうかには金が関わってくる。そうして「ナチュラル(ノン・ドーピング)」でベストな体をつくりあげられるのは、限られた人間だけだろう。だから、心身への悪影響を鑑みた上でドーピングに手を出すのは悪いことではないと考えていた。 この小説は、とある男性アイドルに持ち上がったドーピング疑惑を、週刊誌記者が潜入取材で暴いていくという筋書きだ。意外な結末を迎えることへの驚きもあるが、面白いのは、なんとかドーピングの事実を拾い上げるためにアイドルの尿を得ようと立ち回るという、記者として必死に動いている様が滑稽なところだ。主人公が真面目で好感が持てることもあり、ついつい肩入れしたくなってくる。 この結末を予想できる人は、たぶん筋肉をつけるということを科学的に考えられる人だと思う。読み終えてなお、ドーピングが悪いものとは思えない。が、違法なドーピング薬を密売している側は確実に悪だろう。題材が突飛なので見落としそうになるが、悪を追う正統派ミステリとして楽しめる快作だ。 ※欠点として挙げるなら、警察など公権力側がポンコツすぎる。ご都合主義感があるのは否めなかった。 - 2025年12月15日
 ポルターガイストの囚人上條一輝読み終わった@ 自宅「深淵のテレパス」でリング以来の衝撃を受けた、上條一輝によるシリーズ続編。超能力と科学という食い合わせの悪い題材とホラー要素を混ぜて、ここまで納得感のある物語にできることに驚いたわけだが、本作でもその能力は如何なく発揮されているのを確認した。 このシリーズの主要人物には、オカルト畑の人間とアンチオカルトの人間が同じチームメンバーとして活躍する。当然相反する主張をして険悪なムードになったりもするのだが、怪異に対してどちら側も、比較的納得できる見解を出すのがポイントだ。 メインを張るあしや超常現象調査班のふたりが中庸を維持しようとしていることもあり、結果起こった事象に対して幅広い検討余地が残される。ある意味で、昨今の考察ブームに乗っかっているとも言えるが、陰謀論とも相性がいいことを引き合いに出して牽制を入れているのも良い。澤村伊智や小野不由美のような批評眼が強いのかなと感じられた。 帯文によると、次の作品でこのシリーズは完結するそうだ。だらだらと長引かせず、ピシッと終えてくれるのも嬉しい。この作家の物語は、これからもずっと読んでいきたい。
ポルターガイストの囚人上條一輝読み終わった@ 自宅「深淵のテレパス」でリング以来の衝撃を受けた、上條一輝によるシリーズ続編。超能力と科学という食い合わせの悪い題材とホラー要素を混ぜて、ここまで納得感のある物語にできることに驚いたわけだが、本作でもその能力は如何なく発揮されているのを確認した。 このシリーズの主要人物には、オカルト畑の人間とアンチオカルトの人間が同じチームメンバーとして活躍する。当然相反する主張をして険悪なムードになったりもするのだが、怪異に対してどちら側も、比較的納得できる見解を出すのがポイントだ。 メインを張るあしや超常現象調査班のふたりが中庸を維持しようとしていることもあり、結果起こった事象に対して幅広い検討余地が残される。ある意味で、昨今の考察ブームに乗っかっているとも言えるが、陰謀論とも相性がいいことを引き合いに出して牽制を入れているのも良い。澤村伊智や小野不由美のような批評眼が強いのかなと感じられた。 帯文によると、次の作品でこのシリーズは完結するそうだ。だらだらと長引かせず、ピシッと終えてくれるのも嬉しい。この作家の物語は、これからもずっと読んでいきたい。 - 2025年12月13日
 嘘と隣人芦沢央読み終わった@ 自宅明確な悪意を持った凶悪な犯人による事件……は起こらない。芦沢央の小説に散々騙されてきた人なら、これは周知のことだろう。本書でもその路線は同様で、大抵の事件は保身・取り繕い・誤魔化し・見栄・承認欲求から起こる。それも悲惨なかたちで。 定年退職を迎えた元警察官の主人公が、親切心から関わるのはストーカーやマタハラ・パワハラ、嫌がらせなど、誰しもが経験してしまうような身近な事件ばかり。しかし内実を探っていくと、最初の火種は悪意とも呼べないような小さなできごとから始まっていたことがわかる。 凶悪犯のようなモンスターであれば、「自分とは違う生き物」として切り離して考えることができる。しかし芦沢央の作品に出てくる加害者は、未来の自分だと思えてくる。何だったら、ずっと蓋をしてた過去の自分の姿だったりもする。 仕事で誤発注を誤魔化した経験のある人や、実際の出来事を10倍盛りくらいにしてツイートしたことのある人は、読みながら目を泳がせてしまうかもしれない。心当たりのある人に、ぜひ読んでもらいたい。胃が痛い。
嘘と隣人芦沢央読み終わった@ 自宅明確な悪意を持った凶悪な犯人による事件……は起こらない。芦沢央の小説に散々騙されてきた人なら、これは周知のことだろう。本書でもその路線は同様で、大抵の事件は保身・取り繕い・誤魔化し・見栄・承認欲求から起こる。それも悲惨なかたちで。 定年退職を迎えた元警察官の主人公が、親切心から関わるのはストーカーやマタハラ・パワハラ、嫌がらせなど、誰しもが経験してしまうような身近な事件ばかり。しかし内実を探っていくと、最初の火種は悪意とも呼べないような小さなできごとから始まっていたことがわかる。 凶悪犯のようなモンスターであれば、「自分とは違う生き物」として切り離して考えることができる。しかし芦沢央の作品に出てくる加害者は、未来の自分だと思えてくる。何だったら、ずっと蓋をしてた過去の自分の姿だったりもする。 仕事で誤発注を誤魔化した経験のある人や、実際の出来事を10倍盛りくらいにしてツイートしたことのある人は、読みながら目を泳がせてしまうかもしれない。心当たりのある人に、ぜひ読んでもらいたい。胃が痛い。 - 2025年12月13日
 絶望はしてません斎藤美奈子読み終わった@ 自宅
絶望はしてません斎藤美奈子読み終わった@ 自宅
読み込み中...
