

鳥澤光
@hikari413
- 2026年2月24日
 うた子と獅子男古谷田奈月
うた子と獅子男古谷田奈月 - 2026年2月19日
 西高東低マンション武塙麻衣子
西高東低マンション武塙麻衣子 - 2026年2月15日
 地域の私生活99 非首都圏アンソロジーランタン,ブルキッド,ブックプランパン,omyo,Sanho,具本媛読むマンガ読んだマンガ2026
地域の私生活99 非首都圏アンソロジーランタン,ブルキッド,ブックプランパン,omyo,Sanho,具本媛読むマンガ読んだマンガ2026 - 2026年2月14日
 【推しの子】 16赤坂アカ×横槍メンゴ読み終わった再読再々読読むマンガ読んだマンガ2026マンガは一気読みに限るな! とおして読むのは久しぶりで、繰り返し読むことで物語の立体感が増えていく感じが楽しい。何度読んでもMEMちょが好きだ。
【推しの子】 16赤坂アカ×横槍メンゴ読み終わった再読再々読読むマンガ読んだマンガ2026マンガは一気読みに限るな! とおして読むのは久しぶりで、繰り返し読むことで物語の立体感が増えていく感じが楽しい。何度読んでもMEMちょが好きだ。 - 2026年2月14日
 迷うことについてレベッカ・ソルニット,東辻賢治郎読み終わった読む本読んだ本2026今まさに読みたい言葉が書いてありそうな本が目の前に置かれていて、ありがたいことだと感謝しながら付箋を貼るのを我慢しながら読んでいたら、私が買った本だと夫が言う。そうね。そうか。 それで今日は『迷うことについて』を読むことになった。 読みはじめて、舌が真っ青になった外国製のお菓子(ハロウィンでもらった)のことを思い出したけど、40年以上前のことだし色のほかになにも思い出せ……香り? というより香料のバランスのようなものは思い出せるな……! 魔女の格好をしたこと、ふたつ上の姉がお姫様なのがずるいと泣いたことも思い出した。記憶と記憶のつながりはいつでも不思議で楽しい。と思っていたら《青い染料を溶かしたカクテルが供され、飲んだ者は皆その後何日も青い小便をした。》(P176)とあってますます楽しい。
迷うことについてレベッカ・ソルニット,東辻賢治郎読み終わった読む本読んだ本2026今まさに読みたい言葉が書いてありそうな本が目の前に置かれていて、ありがたいことだと感謝しながら付箋を貼るのを我慢しながら読んでいたら、私が買った本だと夫が言う。そうね。そうか。 それで今日は『迷うことについて』を読むことになった。 読みはじめて、舌が真っ青になった外国製のお菓子(ハロウィンでもらった)のことを思い出したけど、40年以上前のことだし色のほかになにも思い出せ……香り? というより香料のバランスのようなものは思い出せるな……! 魔女の格好をしたこと、ふたつ上の姉がお姫様なのがずるいと泣いたことも思い出した。記憶と記憶のつながりはいつでも不思議で楽しい。と思っていたら《青い染料を溶かしたカクテルが供され、飲んだ者は皆その後何日も青い小便をした。》(P176)とあってますます楽しい。 - 2026年2月11日
 青い花ノヴァーリス,青山隆夫読む本読んだ本2026なぜこれを読んでいないのか、何年も、何度も思いっぱなしだったのをついに読み始め。自然科学的想像力に私が抱く憧れのはじまりはどこだろう。一番近くは幻想文学だと思うけど、古いほうも同じだろうか。あるいは動物誌かも。
青い花ノヴァーリス,青山隆夫読む本読んだ本2026なぜこれを読んでいないのか、何年も、何度も思いっぱなしだったのをついに読み始め。自然科学的想像力に私が抱く憧れのはじまりはどこだろう。一番近くは幻想文学だと思うけど、古いほうも同じだろうか。あるいは動物誌かも。 - 2026年2月8日
 光と糸ハン・ガン,斎藤真理子読み終わった読む本読んだ本2026東京に(も)雪が降ったことで『すべての、白いものたちの』を読み返したくなり、他の本を読んでいたら夜になって、暗澹たる気持ち(選挙のせい)のまま手に取った黒いほうの本。 「本が出たあと」で時間が止まり、「声(たち)」に静かな勇気をもらう。《この世界であと一日生きる》ことをがんばるための。「北向きの部屋」など家や部屋について書かれたものは大好物。庭の記録がすばらしくてこの本をすすめたい人の顔がいくつも浮かぶ。
光と糸ハン・ガン,斎藤真理子読み終わった読む本読んだ本2026東京に(も)雪が降ったことで『すべての、白いものたちの』を読み返したくなり、他の本を読んでいたら夜になって、暗澹たる気持ち(選挙のせい)のまま手に取った黒いほうの本。 「本が出たあと」で時間が止まり、「声(たち)」に静かな勇気をもらう。《この世界であと一日生きる》ことをがんばるための。「北向きの部屋」など家や部屋について書かれたものは大好物。庭の記録がすばらしくてこの本をすすめたい人の顔がいくつも浮かぶ。 - 2026年2月8日
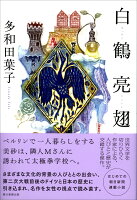 白鶴亮翅多和田葉子読む本読んだ本2026
白鶴亮翅多和田葉子読む本読んだ本2026 - 2026年2月7日
 弔いのひ間宮改衣読み終わった読む本読んだ本2026きっと好きだとすすめられて、ときどき笑いながら、《分かり合えないまま亡くなった父》が私にもいるけど、優しく懐かしく思い出すことがないのを確認するように読む。
弔いのひ間宮改衣読み終わった読む本読んだ本2026きっと好きだとすすめられて、ときどき笑いながら、《分かり合えないまま亡くなった父》が私にもいるけど、優しく懐かしく思い出すことがないのを確認するように読む。 - 2026年2月6日
 時里二郎詩集時里二郎読む本読んだ本2026《王の歌を、その佶屈とした筆跡をまねてその中に閉じ込めてみると、不思議に、光のない眼の奥にかがよう心の裡が透けて見えてくる心地がしておれを惑わせた。》P17「星痕観測」
時里二郎詩集時里二郎読む本読んだ本2026《王の歌を、その佶屈とした筆跡をまねてその中に閉じ込めてみると、不思議に、光のない眼の奥にかがよう心の裡が透けて見えてくる心地がしておれを惑わせた。》P17「星痕観測」 - 2026年2月3日
- 2026年1月30日
 下駄で歩いた巴里林芙美子,立松和平読む本読んだ本2026何人もの作家になぜ小説を書くのかをきいてきたけど、すごくしっくりくる答えがこの本に書いてあった。 《何か愉しいのだ。小説を書いていると、恋びとが待ってくれているように愉しくなる。娘の頃から書を読むことが好きであったが、こんな愉しさがあったからこそ、自殺もせずに無事に来たのだと思う。私はいったい楽天家でしめっぽい事がきらいだが、そのくせ、孤独を全我としている。私の文学はあこがれ飢えることによって、ここまで来たような気がする。いまでも、私の目標は常に飢え、常に憧れることだ。》P284-286「文学・旅・その他」 それにしても家にあった林芙美子本たちはどこへ旅立ってしまったのかな、1冊も見つからなくてびっくりしている。
下駄で歩いた巴里林芙美子,立松和平読む本読んだ本2026何人もの作家になぜ小説を書くのかをきいてきたけど、すごくしっくりくる答えがこの本に書いてあった。 《何か愉しいのだ。小説を書いていると、恋びとが待ってくれているように愉しくなる。娘の頃から書を読むことが好きであったが、こんな愉しさがあったからこそ、自殺もせずに無事に来たのだと思う。私はいったい楽天家でしめっぽい事がきらいだが、そのくせ、孤独を全我としている。私の文学はあこがれ飢えることによって、ここまで来たような気がする。いまでも、私の目標は常に飢え、常に憧れることだ。》P284-286「文学・旅・その他」 それにしても家にあった林芙美子本たちはどこへ旅立ってしまったのかな、1冊も見つからなくてびっくりしている。 - 2026年1月28日
- 2026年1月21日
 細長い場所絲山秋子読み終わった読む本読んだ本2026@ 八重洲ブックセンター阿佐ヶ谷
細長い場所絲山秋子読み終わった読む本読んだ本2026@ 八重洲ブックセンター阿佐ヶ谷 - 2026年1月18日
 かかとを失くして 三人関係 文字移植多和田葉子読み終わった読む本読んだ本2026
かかとを失くして 三人関係 文字移植多和田葉子読み終わった読む本読んだ本2026 - 2026年1月18日
 エクソフォニー多和田葉子読み終わった読む本読んだ本2026
エクソフォニー多和田葉子読み終わった読む本読んだ本2026 - 2026年1月15日
 怪談の真髄春日武彦読み終わった読む本読んだ本2026ラフカディオ・ハーンに興味を持ったことがなかったけど、春日先生の新刊なのでもちろん読む。意外に知っている怪談が少なくなくて、小学校の授業で読んだり聞いたりしたものもあるから物語の強度に感じ入る。 妖怪の気持ちや望むことを考えてみる、というのが、精神科医の筆者ならではでおもしろい。ここ数年、春日先生は幼少期の思い出をたびたび書かれていてそれの鮮明さが恐ろしくもかわいらしい。人の記憶って、と考えてみるにはあまりに遠い知性のピカピカさ! でも本になったおかげでそれを文字で読めるのだからありがたいね。
怪談の真髄春日武彦読み終わった読む本読んだ本2026ラフカディオ・ハーンに興味を持ったことがなかったけど、春日先生の新刊なのでもちろん読む。意外に知っている怪談が少なくなくて、小学校の授業で読んだり聞いたりしたものもあるから物語の強度に感じ入る。 妖怪の気持ちや望むことを考えてみる、というのが、精神科医の筆者ならではでおもしろい。ここ数年、春日先生は幼少期の思い出をたびたび書かれていてそれの鮮明さが恐ろしくもかわいらしい。人の記憶って、と考えてみるにはあまりに遠い知性のピカピカさ! でも本になったおかげでそれを文字で読めるのだからありがたいね。 - 2026年1月8日
 言葉と歩く日記多和田葉子読み終わった再読再々読読む本読んだ本2026一月一日からはじまる日記だから、これまたお正月に読むのにぴったり。「勝手にアンソロジー」シリーズの「正月」に入れたくなる。大晦日の最後の瞬間の過ごし方が書いてあるのがすごくいい。言葉について考えることがかなりストレートに表現されていて、ドイツ語を知らなくてもこんなにおもしろい。読むのは確か二度目。
言葉と歩く日記多和田葉子読み終わった再読再々読読む本読んだ本2026一月一日からはじまる日記だから、これまたお正月に読むのにぴったり。「勝手にアンソロジー」シリーズの「正月」に入れたくなる。大晦日の最後の瞬間の過ごし方が書いてあるのがすごくいい。言葉について考えることがかなりストレートに表現されていて、ドイツ語を知らなくてもこんなにおもしろい。読むのは確か二度目。 - 2026年1月7日
 世界99 下村田沙耶香読み終わった読む本読んだ本2026
世界99 下村田沙耶香読み終わった読む本読んだ本2026 - 2026年1月3日
 剃刀日記石川桂郎読み終わった読む本読んだ本2026作家に対してうすぼんやり冬のイメージを持っていたけど、この短篇集ではお正月や大晦日の話も多くてあながち間違ってはいなかったもよう。『妻の温泉』とは発表年や描かれる時期も違うのだけど、こちらは短篇の終わり方の尋常ならざる旨さにニマニマしながら読んだ。人の内外の景色の描写も絶妙で、仮想の空間のようにも読める(時代の隔たりもあってか)場所の眺め方も気持ちがいい。 《おおどかな裡にもどこか淋しさのある牡丹の花》「秋の花」P71 という文から「おおどか」という言葉を知った。知らない人の優しい顔が浮かんでくるようないい響き。 《母が私にそっと握らしたのは空色の切符でした。》「堤防」P62 《山葵でなしに生姜と小指半分ほどの葱をそえて、きのう入った船から上げたばかりだというその鰹の身は、恰度夕陽をうけた深海の彩をしています。》「堤防」P63
剃刀日記石川桂郎読み終わった読む本読んだ本2026作家に対してうすぼんやり冬のイメージを持っていたけど、この短篇集ではお正月や大晦日の話も多くてあながち間違ってはいなかったもよう。『妻の温泉』とは発表年や描かれる時期も違うのだけど、こちらは短篇の終わり方の尋常ならざる旨さにニマニマしながら読んだ。人の内外の景色の描写も絶妙で、仮想の空間のようにも読める(時代の隔たりもあってか)場所の眺め方も気持ちがいい。 《おおどかな裡にもどこか淋しさのある牡丹の花》「秋の花」P71 という文から「おおどか」という言葉を知った。知らない人の優しい顔が浮かんでくるようないい響き。 《母が私にそっと握らしたのは空色の切符でした。》「堤防」P62 《山葵でなしに生姜と小指半分ほどの葱をそえて、きのう入った船から上げたばかりだというその鰹の身は、恰度夕陽をうけた深海の彩をしています。》「堤防」P63
読み込み中...

