真魚
@ms_mn
会社員。読書記録として使っています。
好きなジャンル: 短歌、俳句、現代詩、美術批評、写真集、アメリカ文学、日本の古典など。
仕事用: データ解析、マーケティングなど。
- 2025年6月25日
- 2025年6月25日
 すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読み終わった
すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読み終わった - 2025年6月25日
 ギリシャ語の時間ハン・ガン,斎藤真理子読み終わった恋人を目にしたマルケスと、弟子を口にしたソクラテス。 古代ギリシア語では美しさと厳しさと高潔さ、静けさは同じ単語だった、韓国語で光=明るさと色彩とが同じ意味であるのと似て、というエピソードのように、記憶のどこかに静かに沈んでたまに戻ってきそうな、物哀しく冷たいけれど印象的な描写がたくさんあった。 吐き気が止まらない時期もあったし、(遺伝ではなくおそらく失明はしないはずだけれど)目がものすごく悪いしどんどん暗い場所が見えなくなっているので、シジュウカラの場面はリアルに怖かった。 死んだ言語と生きている言語、言語と社会、言語と感受、表象とイメージ、といった哲学的な問いがふたりの人物のモノローグを中心に漂っていて、無意識の意図に見えるというか、判別しきれないような方法で構成されている。 “明るくも暗くもあって、少しぼやけている"というのがしっくりくる読後感でした。
ギリシャ語の時間ハン・ガン,斎藤真理子読み終わった恋人を目にしたマルケスと、弟子を口にしたソクラテス。 古代ギリシア語では美しさと厳しさと高潔さ、静けさは同じ単語だった、韓国語で光=明るさと色彩とが同じ意味であるのと似て、というエピソードのように、記憶のどこかに静かに沈んでたまに戻ってきそうな、物哀しく冷たいけれど印象的な描写がたくさんあった。 吐き気が止まらない時期もあったし、(遺伝ではなくおそらく失明はしないはずだけれど)目がものすごく悪いしどんどん暗い場所が見えなくなっているので、シジュウカラの場面はリアルに怖かった。 死んだ言語と生きている言語、言語と社会、言語と感受、表象とイメージ、といった哲学的な問いがふたりの人物のモノローグを中心に漂っていて、無意識の意図に見えるというか、判別しきれないような方法で構成されている。 “明るくも暗くもあって、少しぼやけている"というのがしっくりくる読後感でした。 - 2025年6月14日
 夕暮れに夜明けの歌を奈倉有里読み終わった読んでよかった。表面的な…世界史的な時系列の理解はあったけど、ロシア文学もロシアの社会事情もうっすらとした知識と理解しかなく、地理関係も曖昧だったので。子どもの頃、米原万里さんのエッセイが好きだったので気軽な感じで最初は手に取りました。 回顧録的エッセイに登場する人物たちは、それぞれ広大なロシアの、特色ある地域の出身で、生身の人生を歩んでいることが描かれていて、乏しい知識でも境遇をリアルに想像することができた。 学生生活のディテールも具体的で、寮に家電がないとか大学がお城で建物は素晴らしいけど大学図書館が充実していないとか、政治的な理由でカリキュラムが影響を受けるとか…気が沈む内容を文学と愛が彩ってくれるおかげで、苦しいけど読み通すことができた。 ロシア語やロシア文学という懸命になれるもの(文字通り命がけだろう)と出会えた作者を羨む一方で、こんなにもひたむきな人だから出会えたんだろうなぁと思う。 民族、宗教、言語、金銭的格差という諍いのもとになりやすいテーマは、日常生活の延長であるゆえに避けることができない、ということを思い出させてくれる良書でした。
夕暮れに夜明けの歌を奈倉有里読み終わった読んでよかった。表面的な…世界史的な時系列の理解はあったけど、ロシア文学もロシアの社会事情もうっすらとした知識と理解しかなく、地理関係も曖昧だったので。子どもの頃、米原万里さんのエッセイが好きだったので気軽な感じで最初は手に取りました。 回顧録的エッセイに登場する人物たちは、それぞれ広大なロシアの、特色ある地域の出身で、生身の人生を歩んでいることが描かれていて、乏しい知識でも境遇をリアルに想像することができた。 学生生活のディテールも具体的で、寮に家電がないとか大学がお城で建物は素晴らしいけど大学図書館が充実していないとか、政治的な理由でカリキュラムが影響を受けるとか…気が沈む内容を文学と愛が彩ってくれるおかげで、苦しいけど読み通すことができた。 ロシア語やロシア文学という懸命になれるもの(文字通り命がけだろう)と出会えた作者を羨む一方で、こんなにもひたむきな人だから出会えたんだろうなぁと思う。 民族、宗教、言語、金銭的格差という諍いのもとになりやすいテーマは、日常生活の延長であるゆえに避けることができない、ということを思い出させてくれる良書でした。 - 2025年6月8日
 そっと 静かにハン・ガン,古川綾子読み終わった
そっと 静かにハン・ガン,古川綾子読み終わった - 2025年6月4日
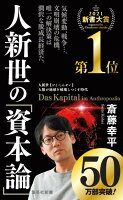 人新世の「資本論」斎藤幸平読み終わった・わりとピュアにネガティヴ・エミッション・テクノロジーやジオエンジニアリングを信じていたので、「先進国を優先して外部を犠牲にする、民主主義を否定する閉鎖的技術」とかなり批判的に記載されていたことがショッキングでした。 ・これまで存在していた労働、過剰生産、人権、格差、オーバーツーリズムや貿易といったイシューをシングルではなく大きく結ぶのが環境問題である、という提案は納得感あり。 ・協同組合によってエッセンシャル・ワークの地位や労働環境が改善できるという論は実践に値すると思う。ただ労働組合が有形無実となっている現代においては既存の組織の拡張よりも新しい枠組みのほうが効果が出る可能性もありそう。 ・現実にコモンが拡張した際に本当に国家の介入なして市民が管理できるか、また当該市民団体が権威化せずにすむのかは要検討な主張だと思う。 ・あとがきの「3.5%の人が行動すれば社会変容は可能だという説がある、あなたも3.5%になろう」という呼びかけは希望が持てた。
人新世の「資本論」斎藤幸平読み終わった・わりとピュアにネガティヴ・エミッション・テクノロジーやジオエンジニアリングを信じていたので、「先進国を優先して外部を犠牲にする、民主主義を否定する閉鎖的技術」とかなり批判的に記載されていたことがショッキングでした。 ・これまで存在していた労働、過剰生産、人権、格差、オーバーツーリズムや貿易といったイシューをシングルではなく大きく結ぶのが環境問題である、という提案は納得感あり。 ・協同組合によってエッセンシャル・ワークの地位や労働環境が改善できるという論は実践に値すると思う。ただ労働組合が有形無実となっている現代においては既存の組織の拡張よりも新しい枠組みのほうが効果が出る可能性もありそう。 ・現実にコモンが拡張した際に本当に国家の介入なして市民が管理できるか、また当該市民団体が権威化せずにすむのかは要検討な主張だと思う。 ・あとがきの「3.5%の人が行動すれば社会変容は可能だという説がある、あなたも3.5%になろう」という呼びかけは希望が持てた。 - 2025年6月1日
 少年が来るハン・ガン,井手俊作読み終わった・通常では考えつかないほどの暴力を人間は発案し、かつ振るうことができる ・悪夢のほうが現実であること ・熱病のような連帯と善き存在になること ・PTSDという言葉が知られていなかった時代の拷問、絶望とアルコール中毒 ・ほとんど全ての国や地域で、人権は所与のものではなく勝ち取られたものであったこと ・劣悪な労働環境とブラックリスト ・学歴は資産の証明であったこと ・尊厳を奪う、壊す、奪われない、奪えないもの
少年が来るハン・ガン,井手俊作読み終わった・通常では考えつかないほどの暴力を人間は発案し、かつ振るうことができる ・悪夢のほうが現実であること ・熱病のような連帯と善き存在になること ・PTSDという言葉が知られていなかった時代の拷問、絶望とアルコール中毒 ・ほとんど全ての国や地域で、人権は所与のものではなく勝ち取られたものであったこと ・劣悪な労働環境とブラックリスト ・学歴は資産の証明であったこと ・尊厳を奪う、壊す、奪われない、奪えないもの - 2025年5月26日
- 2025年5月25日
 「人生の地図」のつくり方橋本努読み終わった
「人生の地図」のつくり方橋本努読み終わった - 2025年5月13日
- 2025年5月11日
 声影記小原奈実読み終わった
声影記小原奈実読み終わった - 2025年5月3日
 ソーンダーズ先生の小説教室 ロシア文学に学ぶ書くこと、読むこと、生きることジョージ・ソーンダーズ,柳田麻里,秋草俊一郎気になる
ソーンダーズ先生の小説教室 ロシア文学に学ぶ書くこと、読むこと、生きることジョージ・ソーンダーズ,柳田麻里,秋草俊一郎気になる - 2025年5月3日
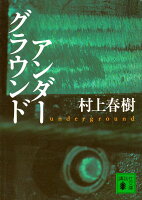 アンダーグラウンド村上春樹読み終わった2025年は地下鉄サリン事件から30年というので初めて読みました。サリン事件のことは「かつて世間を震撼させたオウム真理教による大規模なテロ」という程度の理解で、前情報なしに読み始めたら、ものすごい衝撃でした。 こんなのがあった後でも被害者の方が地下鉄通勤してたの?自分もよく何も知らずに毎日電車に乗れたものだね? 事件の全貌を知らなくても読めるように、実行犯の詳細/時系列/サリンという物質とは/コリンエステラーゼとは…といった説明があり、路線別の構成になっている。後世にこの事件が振り返られることを想定されているし、振り返るべき事件だという意図が読める。 ふつうに暮らしてふつうに通勤したり、駅で勤務している何千人もの生活がある日、突然に、変わってしまう。亡くなった方々には当然声がないのに、生き残った人たちの限られた証言だけで既にものすごい群像劇でした。 いろんな業界業種のさまざまな年齢の人々の来し方が記載されていて、当時の地下鉄や自衛隊、病院といった組織の構造についても言及がある。分厚さ以上の重みのある書籍でした。 人間存在や個人への信頼を感じることができたけど、副次的な効果として、官公庁や警察といった官僚組織への信頼はまったく失われました。ビューロクラシーやセクショナリズムには弊害しかないように思う。 中高生から定年後再雇用の人まで、その時刻に電車に乗り合わせた、あるいは近くで働いていたというだけで被害に遭われた、それがまさに無差別テロということなんだと、やっと理解できた気がします。 過去に村上春樹の代表的な小説をいくつか読んだだけでは「こういう作風でノーベル賞候補になるのかな?」とピンと来ていなかったのですが、『アンダーグラウンド』は別格でした。大規模な調査と努力と社会への視線がある。高度経済成長期、バブル期とその爪痕を抱えた不況社会という日本の近現代そのものを内包した叙述だった。すごい本でした。読んで良かった。
アンダーグラウンド村上春樹読み終わった2025年は地下鉄サリン事件から30年というので初めて読みました。サリン事件のことは「かつて世間を震撼させたオウム真理教による大規模なテロ」という程度の理解で、前情報なしに読み始めたら、ものすごい衝撃でした。 こんなのがあった後でも被害者の方が地下鉄通勤してたの?自分もよく何も知らずに毎日電車に乗れたものだね? 事件の全貌を知らなくても読めるように、実行犯の詳細/時系列/サリンという物質とは/コリンエステラーゼとは…といった説明があり、路線別の構成になっている。後世にこの事件が振り返られることを想定されているし、振り返るべき事件だという意図が読める。 ふつうに暮らしてふつうに通勤したり、駅で勤務している何千人もの生活がある日、突然に、変わってしまう。亡くなった方々には当然声がないのに、生き残った人たちの限られた証言だけで既にものすごい群像劇でした。 いろんな業界業種のさまざまな年齢の人々の来し方が記載されていて、当時の地下鉄や自衛隊、病院といった組織の構造についても言及がある。分厚さ以上の重みのある書籍でした。 人間存在や個人への信頼を感じることができたけど、副次的な効果として、官公庁や警察といった官僚組織への信頼はまったく失われました。ビューロクラシーやセクショナリズムには弊害しかないように思う。 中高生から定年後再雇用の人まで、その時刻に電車に乗り合わせた、あるいは近くで働いていたというだけで被害に遭われた、それがまさに無差別テロということなんだと、やっと理解できた気がします。 過去に村上春樹の代表的な小説をいくつか読んだだけでは「こういう作風でノーベル賞候補になるのかな?」とピンと来ていなかったのですが、『アンダーグラウンド』は別格でした。大規模な調査と努力と社会への視線がある。高度経済成長期、バブル期とその爪痕を抱えた不況社会という日本の近現代そのものを内包した叙述だった。すごい本でした。読んで良かった。 - 2025年3月30日
- 2025年3月28日
 たましひの薄衣菅原百合絵読んでる
たましひの薄衣菅原百合絵読んでる - 2025年3月24日
 土左日記堀江敏幸読み終わった旅行記だし、好きな李禹煥のドローイングがカバーだし、と思って飛行機の機内で読み始めた。 視点の揺らぎを強調する補足と、ひらがなの本編が意欲的で面白かった。 会社員の悲哀や都会の人間関係やしがらみ、肉親の死、晩年、芸術への自負と苦しみ、信頼できない人々に囲まれる道中、といった現代人にも共感可能な要素も思ったより多く、するする読めました。
土左日記堀江敏幸読み終わった旅行記だし、好きな李禹煥のドローイングがカバーだし、と思って飛行機の機内で読み始めた。 視点の揺らぎを強調する補足と、ひらがなの本編が意欲的で面白かった。 会社員の悲哀や都会の人間関係やしがらみ、肉親の死、晩年、芸術への自負と苦しみ、信頼できない人々に囲まれる道中、といった現代人にも共感可能な要素も思ったより多く、するする読めました。 - 2025年3月2日
 リサーチのはじめかたクリストファー・レア,トーマス・S・マラニー,安原和見読み終わった「良い研究とは何か」という一貫した姿勢で、とても勉強になった。これは大学はいったときに読みたかった。社会人だけどこれから生かせることもあるでしょう。
リサーチのはじめかたクリストファー・レア,トーマス・S・マラニー,安原和見読み終わった「良い研究とは何か」という一貫した姿勢で、とても勉強になった。これは大学はいったときに読みたかった。社会人だけどこれから生かせることもあるでしょう。 - 2025年3月1日
読み込み中...





