

pamo
@pamo
趣味は読書です。
- 2026年1月20日
 円卓西加奈子読み終わった感想小学3年生「こっこ」が見る、難しく醜く、美しい世界。 小学生の日常は自宅と学校の往復だけ。でも、そこにいる人たちはだれもが個性に富み、日々の生活はこっこの屈折した性格のおかげでツッコミどころだらけ。 ・ 登場人物が多いのでふとすると話に置いていかれてしまうのだけど、その全員が「この物語に登場する意味がある」人物で、そのことがそのまま「こっこに関わるすべての人がこっこの人生を形作っている」こと、「すべての人に唯一無二の個性があり、生きる意味があること」を表している。 小学生なりに、人生の上手くいかなさ、世の中の理不尽さにどう折り合いをつけて生きていくかを模索する姿に胸がギュッとなる。特に親友「ぽっさん」とこっことの、「こっこが格好良いと思っていても、真似してはいけないことがある」という議論は『カラマーゾフの兄弟』の大審問に匹敵する名シーン…はさすがに言い過ぎかもしれないが、でも「小学生が経験する、最初の<大審問>」を描いていると思う。「たとえ善の心であっても、自分の思いのままではいけない」「自分の思いのままを行動に表すならば、その責任は自分に返ってくる」子どもには難しいことを、こっこは親友たちと学んでいく。そして、「他者からの<思いのまま>を差し向けられる」という体験を通して、こっこは傷つき、大人になる。 ・ これからも長い人生が待っている「こっこ」の物語をどんなふうに閉じるのか…そのエンディングのカタルシスにもやられる。 この先もこっこには大変な人生が待っていることを、大人である私たちは知っている。 でも、この本を閉じるとき、こっこの生活を彩るさまざまな希望に、私の心まで救われる。
円卓西加奈子読み終わった感想小学3年生「こっこ」が見る、難しく醜く、美しい世界。 小学生の日常は自宅と学校の往復だけ。でも、そこにいる人たちはだれもが個性に富み、日々の生活はこっこの屈折した性格のおかげでツッコミどころだらけ。 ・ 登場人物が多いのでふとすると話に置いていかれてしまうのだけど、その全員が「この物語に登場する意味がある」人物で、そのことがそのまま「こっこに関わるすべての人がこっこの人生を形作っている」こと、「すべての人に唯一無二の個性があり、生きる意味があること」を表している。 小学生なりに、人生の上手くいかなさ、世の中の理不尽さにどう折り合いをつけて生きていくかを模索する姿に胸がギュッとなる。特に親友「ぽっさん」とこっことの、「こっこが格好良いと思っていても、真似してはいけないことがある」という議論は『カラマーゾフの兄弟』の大審問に匹敵する名シーン…はさすがに言い過ぎかもしれないが、でも「小学生が経験する、最初の<大審問>」を描いていると思う。「たとえ善の心であっても、自分の思いのままではいけない」「自分の思いのままを行動に表すならば、その責任は自分に返ってくる」子どもには難しいことを、こっこは親友たちと学んでいく。そして、「他者からの<思いのまま>を差し向けられる」という体験を通して、こっこは傷つき、大人になる。 ・ これからも長い人生が待っている「こっこ」の物語をどんなふうに閉じるのか…そのエンディングのカタルシスにもやられる。 この先もこっこには大変な人生が待っていることを、大人である私たちは知っている。 でも、この本を閉じるとき、こっこの生活を彩るさまざまな希望に、私の心まで救われる。 - 2025年12月17日
 存在の耐えられない軽さ (池澤夏樹=個人編集 世界文学全集 1-3)ミラン・クンデラ,西永良成読み終わった感想図書館本チェコの名文学。人生哲学と幸福論を、男女の心のすれ違いになぞらえて捉えた名文学ーーーかと思いきやまさかの「犬」小説だった。 ・ 脳外科医のモテモテプレイボーイ、トマーシュ。 彼のワンナイトの相手のはずが、あれよあれよと運命の相手となってゆく女性テレザ。 トマーシュの愛人で、前衛的な芸術家・自由人のサビナ。 3人の情事が、ソ連に占領された20世紀チェコの抑圧の歴史の中で「幸福とは何か」を問う。 女の影が常にちらつくトマーシュにヘラってしまうテレザ、飄々と愛人の余裕をかましながらも孤独なサビナ。 それぞれの「存在の耐えられない軽さ」は、まるで帝国に翻弄されて存在を耐えられないチェコという小国の存在そのもの。 ・ しかし。この大長編小説いちばんの泣きどころは、まさかのテレザの愛犬だった…!!テレザとワンちゃんとの関係性、愛犬が教えてくれた無私の愛に泣ける…!! 愛人をとおして、浮気相手をとおして、愛犬をとおして、テレザが見つけた「幸福」「愛情」とは…!! ・ 一章が短くて読みやすいものの、「先が気になる!」という感じがなくてなかなか開く気にならず、かーなーりー時間がかかった。読み始めたらサクサク進むけど読むまでが大変…。 でも途中で挫折するのは悔しい、この物語の結末を見届けたい、と思わせられる不思議な魅力のある一冊。 ラストの読後感がとても良かったので、「がんばって読み切って良かった」と思った。
存在の耐えられない軽さ (池澤夏樹=個人編集 世界文学全集 1-3)ミラン・クンデラ,西永良成読み終わった感想図書館本チェコの名文学。人生哲学と幸福論を、男女の心のすれ違いになぞらえて捉えた名文学ーーーかと思いきやまさかの「犬」小説だった。 ・ 脳外科医のモテモテプレイボーイ、トマーシュ。 彼のワンナイトの相手のはずが、あれよあれよと運命の相手となってゆく女性テレザ。 トマーシュの愛人で、前衛的な芸術家・自由人のサビナ。 3人の情事が、ソ連に占領された20世紀チェコの抑圧の歴史の中で「幸福とは何か」を問う。 女の影が常にちらつくトマーシュにヘラってしまうテレザ、飄々と愛人の余裕をかましながらも孤独なサビナ。 それぞれの「存在の耐えられない軽さ」は、まるで帝国に翻弄されて存在を耐えられないチェコという小国の存在そのもの。 ・ しかし。この大長編小説いちばんの泣きどころは、まさかのテレザの愛犬だった…!!テレザとワンちゃんとの関係性、愛犬が教えてくれた無私の愛に泣ける…!! 愛人をとおして、浮気相手をとおして、愛犬をとおして、テレザが見つけた「幸福」「愛情」とは…!! ・ 一章が短くて読みやすいものの、「先が気になる!」という感じがなくてなかなか開く気にならず、かーなーりー時間がかかった。読み始めたらサクサク進むけど読むまでが大変…。 でも途中で挫折するのは悔しい、この物語の結末を見届けたい、と思わせられる不思議な魅力のある一冊。 ラストの読後感がとても良かったので、「がんばって読み切って良かった」と思った。 - 2025年12月17日
 存在の耐えられない軽さ (池澤夏樹=個人編集 世界文学全集 1-3)ミラン・クンデラ,西永良成読んでる心に残る一節引用 人間の時間は円環状になって回るのではなく、前方に直線に進む。だからこそ人間は幸福になることができないのだ。幸福とは反復の欲望のことなのだから。 (p.345)
存在の耐えられない軽さ (池澤夏樹=個人編集 世界文学全集 1-3)ミラン・クンデラ,西永良成読んでる心に残る一節引用 人間の時間は円環状になって回るのではなく、前方に直線に進む。だからこそ人間は幸福になることができないのだ。幸福とは反復の欲望のことなのだから。 (p.345) - 2025年12月12日
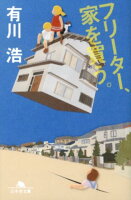 フリーター、家を買う。有川浩読み終わった感想図書館本今更ながら初めて読んだ。当時の時代を象徴するものが多様に織り込まれていて、面白い! やっぱり話題書は話題書なだけあって、けっきょく読むと楽しめるんだよなぁ。 序盤からなかなかの悲劇がたたみかけるんだけど、一歩ずつ解決していく主人公たちをどんどん好きになる。 それぞれのキャラクターが完璧ではなく、清濁合わせながらもただ「人間」として生きているのだと感じさせる。 きっと現実にも同じような問題を抱える家庭はたくさんあって、でも「間に合わなかった」家庭もたくさんあるのだろう。全てがうまくいっていく本作はあくまでファンタジーだなぁと感じさせるけど、でもファンタジーじゃなきゃ希望がない。
フリーター、家を買う。有川浩読み終わった感想図書館本今更ながら初めて読んだ。当時の時代を象徴するものが多様に織り込まれていて、面白い! やっぱり話題書は話題書なだけあって、けっきょく読むと楽しめるんだよなぁ。 序盤からなかなかの悲劇がたたみかけるんだけど、一歩ずつ解決していく主人公たちをどんどん好きになる。 それぞれのキャラクターが完璧ではなく、清濁合わせながらもただ「人間」として生きているのだと感じさせる。 きっと現実にも同じような問題を抱える家庭はたくさんあって、でも「間に合わなかった」家庭もたくさんあるのだろう。全てがうまくいっていく本作はあくまでファンタジーだなぁと感じさせるけど、でもファンタジーじゃなきゃ希望がない。 - 2025年12月3日
 読み終わった感想図書館本図書館で厄年に関する本を探していたのだけど、女性向けの本が少ないことに驚き。こういうスピリチュアルとか占いみたいなものって女性の方が好みそうなのに、男性著者による男性向けの本の方が多かった。 紹介される事例も男性向けのものが多く、厄年の元となった宗教も、ずっと男性本位な歴史があったことが垣間見えた。(どんな宗教も男尊女卑なところがあるので仕方ないのだけど。) そしてこの著者の本、他に「女はすべからく結婚すべし」というタイトルのものもあり、この時代にはまぁ出せない本だなぁー!と笑ってしまった。でも「多様性」「なんでもあり」によってかえって行きづらさを感じる人にはむしろ響くのかも。
読み終わった感想図書館本図書館で厄年に関する本を探していたのだけど、女性向けの本が少ないことに驚き。こういうスピリチュアルとか占いみたいなものって女性の方が好みそうなのに、男性著者による男性向けの本の方が多かった。 紹介される事例も男性向けのものが多く、厄年の元となった宗教も、ずっと男性本位な歴史があったことが垣間見えた。(どんな宗教も男尊女卑なところがあるので仕方ないのだけど。) そしてこの著者の本、他に「女はすべからく結婚すべし」というタイトルのものもあり、この時代にはまぁ出せない本だなぁー!と笑ってしまった。でも「多様性」「なんでもあり」によってかえって行きづらさを感じる人にはむしろ響くのかも。 - 2025年12月3日
- 2025年12月3日
- 2025年12月3日
 長女はなぜ「母の呪文」を消せないのか大美賀直子読み終わった感想図書館本立て続けに母娘問題の本を読んだので記憶が混同してるかもしれないけど… 「円満な家庭」を維持するために役割を演じ続けることは、客観的に見ればほほえましくて良い家庭のように感じられるけど、本人にとっては「いつも本当の自分ではいられない、演じ続けなければならない」地獄になる。 「長女」が母親に求められるものは(長男にまた別の重荷があるように)独特で、それは長女にしか分からないかもしれない。 「女の子がいたら」と願う母親の気持ちはすごく自然なことでよく理解できるけど、「いたら」どうしたいの?…その答えは、もうこれからの時代では通用しないのだ。
長女はなぜ「母の呪文」を消せないのか大美賀直子読み終わった感想図書館本立て続けに母娘問題の本を読んだので記憶が混同してるかもしれないけど… 「円満な家庭」を維持するために役割を演じ続けることは、客観的に見ればほほえましくて良い家庭のように感じられるけど、本人にとっては「いつも本当の自分ではいられない、演じ続けなければならない」地獄になる。 「長女」が母親に求められるものは(長男にまた別の重荷があるように)独特で、それは長女にしか分からないかもしれない。 「女の子がいたら」と願う母親の気持ちはすごく自然なことでよく理解できるけど、「いたら」どうしたいの?…その答えは、もうこれからの時代では通用しないのだ。 - 2025年12月3日
 母と娘の「しんどい関係」を見直す本石原加受子読み終わった感想図書館本母と娘って、不思議な関係だ。 友達であり理解者でありケア要員であり、家父長制の家庭の中で唯一の味方でもある。そしてそれが故に、毒々しい関係をはらむこともある。多かれ少なかれ、全ての母娘関係にそれは影響するんじゃないだろうか。 「自分はこれかもしれない」「自分はこれではないな」いろいろと我が身を重ねながら読むことができる本だった。
母と娘の「しんどい関係」を見直す本石原加受子読み終わった感想図書館本母と娘って、不思議な関係だ。 友達であり理解者でありケア要員であり、家父長制の家庭の中で唯一の味方でもある。そしてそれが故に、毒々しい関係をはらむこともある。多かれ少なかれ、全ての母娘関係にそれは影響するんじゃないだろうか。 「自分はこれかもしれない」「自分はこれではないな」いろいろと我が身を重ねながら読むことができる本だった。 - 2025年12月3日
 倫理的なサイコパス尾久守侑読み終わった感想図書館本精神科医でありながら文筆家である二足の草鞋、自己の二面性がおもしろく軽妙でスラスラ読める。 「精神科医と患者(クライアント)」の関係であってもどの声がけがどのように作用するかはやってみなくちゃ分からなくて、それは日常の人との会話でも同じことなので「医者でもそうなのだな」と思った。 あとは少なからず自分の作品を発信する活動をする身としては、この方の自意識過剰っぷりには共感で笑った。表現をする道を選ぶ人間って、なんでこう難儀なんだろう。
倫理的なサイコパス尾久守侑読み終わった感想図書館本精神科医でありながら文筆家である二足の草鞋、自己の二面性がおもしろく軽妙でスラスラ読める。 「精神科医と患者(クライアント)」の関係であってもどの声がけがどのように作用するかはやってみなくちゃ分からなくて、それは日常の人との会話でも同じことなので「医者でもそうなのだな」と思った。 あとは少なからず自分の作品を発信する活動をする身としては、この方の自意識過剰っぷりには共感で笑った。表現をする道を選ぶ人間って、なんでこう難儀なんだろう。 - 2025年12月3日
 商人ねじめ正一読み終わった感想図書館本面白すぎ!!大当たり!! 最近、落語を聞くようになったので江戸町人の暮らしに興味が湧いて借りてみた一冊。 ・ 主人公は、江戸の町で鰹節屋さんのせがれとして生まれた少年。 父親がしんだら途端に、今まで良くしてくれていた取引先が波が引いたようにいなくなり、跡取りの兄とともに粗末に扱われ、仕事人としての辛酸を舐める。 仕事、結婚、出産、子供、親、友情、恋愛、差別、コンプレックス……。 20〜30代に経験することの全てが一冊の本に凝縮されている。 涙が止まらないほどの悲しい展開が続くのに、それでもカラリとした読後感なのはやはり江戸っ子の物語。 今年一番かもしれない一冊。
商人ねじめ正一読み終わった感想図書館本面白すぎ!!大当たり!! 最近、落語を聞くようになったので江戸町人の暮らしに興味が湧いて借りてみた一冊。 ・ 主人公は、江戸の町で鰹節屋さんのせがれとして生まれた少年。 父親がしんだら途端に、今まで良くしてくれていた取引先が波が引いたようにいなくなり、跡取りの兄とともに粗末に扱われ、仕事人としての辛酸を舐める。 仕事、結婚、出産、子供、親、友情、恋愛、差別、コンプレックス……。 20〜30代に経験することの全てが一冊の本に凝縮されている。 涙が止まらないほどの悲しい展開が続くのに、それでもカラリとした読後感なのはやはり江戸っ子の物語。 今年一番かもしれない一冊。 - 2025年12月3日
- 2025年11月27日
 食べることと出すこと頭木弘樹読み終わった感想図書館本大学生で潰瘍性大腸炎を発症し、難病になってしまった著者のエッセイ。とにかく下痢になる。下痢になるから食べるものにデリケートになるし、出かけるときもトイレ主体の行動になる。 そうすると気軽に人と食事に行けない。「一口でいいから食べてみなよ」と勧められるものも口に入れられない。人と同じものを食べないと、途端に人の輪から外れてしまう、 食べられないことの苦しみは社会性の苦しみだ。排泄をコントロールできない苦しみは、一人前の人としてコントロールすべきことをできない苦しみだ。 (程度はちがえど、私もアレルギーなどで同じ社会性の苦しみを味わったことがある。) そして難病の恐ろしいところは、私の持っているアレルギーや尿意とかとは違って、「今日はお休み」がないこと。24時間365日家事労働に追われるのと似ている。少しのつらさでも、ひとときも休みがないことが精神を追いつめる。 この病気にかかる人は、繊細で慎重な性格の人が多いという。でもそれは、病気がその性格をつくる。人の性格は病気や症状でかんたんに変えられてしまう。
食べることと出すこと頭木弘樹読み終わった感想図書館本大学生で潰瘍性大腸炎を発症し、難病になってしまった著者のエッセイ。とにかく下痢になる。下痢になるから食べるものにデリケートになるし、出かけるときもトイレ主体の行動になる。 そうすると気軽に人と食事に行けない。「一口でいいから食べてみなよ」と勧められるものも口に入れられない。人と同じものを食べないと、途端に人の輪から外れてしまう、 食べられないことの苦しみは社会性の苦しみだ。排泄をコントロールできない苦しみは、一人前の人としてコントロールすべきことをできない苦しみだ。 (程度はちがえど、私もアレルギーなどで同じ社会性の苦しみを味わったことがある。) そして難病の恐ろしいところは、私の持っているアレルギーや尿意とかとは違って、「今日はお休み」がないこと。24時間365日家事労働に追われるのと似ている。少しのつらさでも、ひとときも休みがないことが精神を追いつめる。 この病気にかかる人は、繊細で慎重な性格の人が多いという。でもそれは、病気がその性格をつくる。人の性格は病気や症状でかんたんに変えられてしまう。 - 2025年11月12日
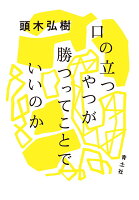 読み終わった感想図書館本おもしろい!noteでも読めるそうなのでぜひ。 大「言語化」時代、口のうまいやつが評価をされる。得をする。口下手はそれだけで能力が低いかのように扱われる。単に、じっくりと言葉を選んでいたり、言葉にできないことに向き合っているだけなのに。 …という著者の指摘には全力でうなずきながらも、でもそれもやっぱり「口の立つやつ」の立場で「口下手にもいいことあるよ」って慰めてるだけだよなぁー…持てる者が持たざる者に同情しているだけというか、そこにも欺瞞があるというか。 その他、とにかく「うんうん、そうそう」と思うことばかり。 軽やかな語り口で読みやすいエッセイ。 他の著書も読んでみようと思った。
読み終わった感想図書館本おもしろい!noteでも読めるそうなのでぜひ。 大「言語化」時代、口のうまいやつが評価をされる。得をする。口下手はそれだけで能力が低いかのように扱われる。単に、じっくりと言葉を選んでいたり、言葉にできないことに向き合っているだけなのに。 …という著者の指摘には全力でうなずきながらも、でもそれもやっぱり「口の立つやつ」の立場で「口下手にもいいことあるよ」って慰めてるだけだよなぁー…持てる者が持たざる者に同情しているだけというか、そこにも欺瞞があるというか。 その他、とにかく「うんうん、そうそう」と思うことばかり。 軽やかな語り口で読みやすいエッセイ。 他の著書も読んでみようと思った。 - 2025年10月28日
 オードリー・タン 自由への手紙オードリー・タン,クーリエ・ジャポン編集チーム読み終わった感想図書館本私が旅行で見た台湾は「古き良き雑多な夜市」と「10年前の東京みたいな都会感」だった。 この本を読むと、台湾のぜんぜん違う姿が見えてくる。 フィンランドの例なんかを見ても、つくづく人口が少ない国の国民の一体感、強国の脅威にたいする危機感、それゆえのIT転換への素早さ・機敏性を感じる。 日本はどうなってゆくのか、考えさせられる一冊だった。
オードリー・タン 自由への手紙オードリー・タン,クーリエ・ジャポン編集チーム読み終わった感想図書館本私が旅行で見た台湾は「古き良き雑多な夜市」と「10年前の東京みたいな都会感」だった。 この本を読むと、台湾のぜんぜん違う姿が見えてくる。 フィンランドの例なんかを見ても、つくづく人口が少ない国の国民の一体感、強国の脅威にたいする危機感、それゆえのIT転換への素早さ・機敏性を感じる。 日本はどうなってゆくのか、考えさせられる一冊だった。 - 2025年10月16日
 しずく西加奈子読み終わった買った感想ちょっと良すぎる。西加奈子さんの作品、大好き。 「女性2人」の短編オムニバス。それは友情だったり、親子だったり。 人生のなか、生活のなかで溜まっていく澱のようなものを、爽やかに受け入れながら生きていくような、吹き抜ける風のような作品たち。 また何度でも読み直したい。 なぜか家にあったけど、あってよかった。
しずく西加奈子読み終わった買った感想ちょっと良すぎる。西加奈子さんの作品、大好き。 「女性2人」の短編オムニバス。それは友情だったり、親子だったり。 人生のなか、生活のなかで溜まっていく澱のようなものを、爽やかに受け入れながら生きていくような、吹き抜ける風のような作品たち。 また何度でも読み直したい。 なぜか家にあったけど、あってよかった。 - 2025年9月22日
- 2025年8月15日
 誘拐された西欧、あるいは中欧の悲劇ミラン・クンデラ,阿部賢一読み終わった感想図書館本面白かった。評論かと思って手に取ったら、中身は中央ヨーロッパの先人たちの講演・演説を収録したような本。 西欧になりきれず、さりとて旧ソ連圏の東欧でもない。国境は列強の気まぐれによって恣意的に引き直され、国は簡単に滅ぼされる。 そんな不信感・不安感のなかで、それでも列強に吸収されるのではなく一つの国民・民族として独立することを選んだ中欧の国々。 その国で生きてきた人から見た「国」というものの不確かさ、グローバリズムに対する猜疑心が感じられる。 大国ドイツの文化圏に染まった方が良いか。それとも弱小国家であろうと独自の文化圏を維持するべきか。どちらの方が国は発展するのか、先進国から取り残されないか、攻め滅ぼされないか。少数言語を使い続けるべきか、話者の多い言語を取り入れるべきか。 かつて日本もその悩みを持ち、明治維新やGHQ占領時代を乗り越えてきたことを思えば他人事ではない。 カフカの作品にある暗い不安感、美しいブダペストやプラハの街並み…中欧のいろいろな文化・芸術の下地が見えてくる。
誘拐された西欧、あるいは中欧の悲劇ミラン・クンデラ,阿部賢一読み終わった感想図書館本面白かった。評論かと思って手に取ったら、中身は中央ヨーロッパの先人たちの講演・演説を収録したような本。 西欧になりきれず、さりとて旧ソ連圏の東欧でもない。国境は列強の気まぐれによって恣意的に引き直され、国は簡単に滅ぼされる。 そんな不信感・不安感のなかで、それでも列強に吸収されるのではなく一つの国民・民族として独立することを選んだ中欧の国々。 その国で生きてきた人から見た「国」というものの不確かさ、グローバリズムに対する猜疑心が感じられる。 大国ドイツの文化圏に染まった方が良いか。それとも弱小国家であろうと独自の文化圏を維持するべきか。どちらの方が国は発展するのか、先進国から取り残されないか、攻め滅ぼされないか。少数言語を使い続けるべきか、話者の多い言語を取り入れるべきか。 かつて日本もその悩みを持ち、明治維新やGHQ占領時代を乗り越えてきたことを思えば他人事ではない。 カフカの作品にある暗い不安感、美しいブダペストやプラハの街並み…中欧のいろいろな文化・芸術の下地が見えてくる。 - 2025年8月15日
 読み終わった感想図書館本このアプリで知って気になっていたら、図書館のおすすめ棚に並んでいたので。 自分自身もつながるのが嫌いで、なるべくつながらずに生きていたい。 しかし例えマイノリティでなくとも、やっぱりつながらない人はつながる人に比べてビハインドになる(学校のノートの貸し借り、ママ友の情報ネットワーク、会社の社内政治や飲みニケーション・タバコミュニケーションetc) マイノリティは、マジョリティよりもずっとそのビハインドが切実だ。 知り合いに、全国的にニュースになった大事故に巻き込まれた被害者がいる。トラウマの対処として「被害者の会」に参加していたが、しかし自身の被害は軽度だったため、重篤な被害を受けた人たちの切実ぶりを前にして引け目を感じ、その会からは遠のいてしまったそうだ。 マイノリティの支えとしてコミュニティがあるが、コミュニティというものはとかく、人との相違を感じさせることから逃れられない。 正直、読んでいて「世の中なんてそんなモンでしょ」という気持ちもある。歳をとればとるほど、今の世の中がこうなっている理由も分かってくる。 そういう意味では100%この本に賛同する気持ちにはなれないのだが、しかし自分の中に根深く染み付いた先入観に気づかせてもらえるという点では読んで良かった。 この方がこの先どのように生き、どのように考え、何を書いていくのか、気になる人だ。
読み終わった感想図書館本このアプリで知って気になっていたら、図書館のおすすめ棚に並んでいたので。 自分自身もつながるのが嫌いで、なるべくつながらずに生きていたい。 しかし例えマイノリティでなくとも、やっぱりつながらない人はつながる人に比べてビハインドになる(学校のノートの貸し借り、ママ友の情報ネットワーク、会社の社内政治や飲みニケーション・タバコミュニケーションetc) マイノリティは、マジョリティよりもずっとそのビハインドが切実だ。 知り合いに、全国的にニュースになった大事故に巻き込まれた被害者がいる。トラウマの対処として「被害者の会」に参加していたが、しかし自身の被害は軽度だったため、重篤な被害を受けた人たちの切実ぶりを前にして引け目を感じ、その会からは遠のいてしまったそうだ。 マイノリティの支えとしてコミュニティがあるが、コミュニティというものはとかく、人との相違を感じさせることから逃れられない。 正直、読んでいて「世の中なんてそんなモンでしょ」という気持ちもある。歳をとればとるほど、今の世の中がこうなっている理由も分かってくる。 そういう意味では100%この本に賛同する気持ちにはなれないのだが、しかし自分の中に根深く染み付いた先入観に気づかせてもらえるという点では読んで良かった。 この方がこの先どのように生き、どのように考え、何を書いていくのか、気になる人だ。 - 2025年8月9日
 一冊でわかるイラン史関眞興読み終わった感想図書館本一冊でわかるシリーズ。中東の歴史を見ていくと、1800年ごろまではさまざまな王朝が入り乱れ土地争いをしていて、いまに残る「イラン」等の国の形にまとまったのはごくごく最近なのだとわかる。 国民にしてみれば、それぞれの民族・宗教・部族単位でこの土地に存在してきた(ないしは遊牧生活を送っていた)のに、近代になってイキナリ「イランとしてまとまれ」「イラン国民としての意識を持て」と言われても難しいだろう。 しかし国としてまとまり発展しなければ、いつまでも大国のいいように利用されてしまう。 自分の思い描く暮らしは「国」という形ではないのに、国際社会で渡り歩くためには「国」にならなければならない。 近代国家というものが当たり前のことではないことが、中東の歴史を見るとわかってくる。 そしてつくづく、天下統一し鎖国、明治維新を経て日本という国の形を列強から脅かされずにこれた日本はかなりのレアケースなんだと感じる。もちろんその陰で排除された民族もいることは確かなのだが。
一冊でわかるイラン史関眞興読み終わった感想図書館本一冊でわかるシリーズ。中東の歴史を見ていくと、1800年ごろまではさまざまな王朝が入り乱れ土地争いをしていて、いまに残る「イラン」等の国の形にまとまったのはごくごく最近なのだとわかる。 国民にしてみれば、それぞれの民族・宗教・部族単位でこの土地に存在してきた(ないしは遊牧生活を送っていた)のに、近代になってイキナリ「イランとしてまとまれ」「イラン国民としての意識を持て」と言われても難しいだろう。 しかし国としてまとまり発展しなければ、いつまでも大国のいいように利用されてしまう。 自分の思い描く暮らしは「国」という形ではないのに、国際社会で渡り歩くためには「国」にならなければならない。 近代国家というものが当たり前のことではないことが、中東の歴史を見るとわかってくる。 そしてつくづく、天下統一し鎖国、明治維新を経て日本という国の形を列強から脅かされずにこれた日本はかなりのレアケースなんだと感じる。もちろんその陰で排除された民族もいることは確かなのだが。
読み込み中...



