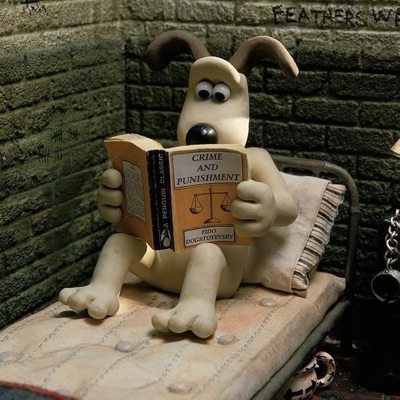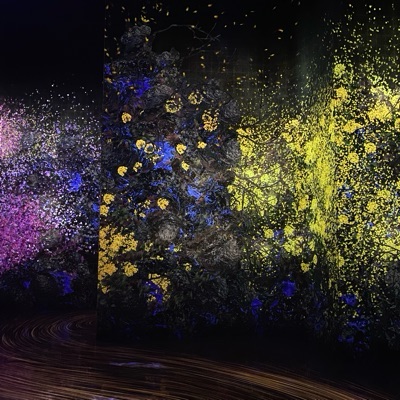本の読み方

64件の記録
 よあけ@mogumogu2026年1月27日読み終わったなぜか続編の『小説の読み方』の方を先に入手して何年か積ん読していたのだけど、時々行く本屋さんでなんとなくこちらを購入して読む。 読書好きと言いながら読むのがとても遅いこと、幼少期から本は好きだったのに、なぜかそこから深まらず、色々読むようになったのは社会人になってからなど、読書に対して勝手にコンプレックスを持っていた私にとても合っていた。 ゆっくり楽しく読めばいいんだと思えたし、技法的なことも姿勢的なことも、作家の視点であらためて言語化されると参考になることが多くて、少しずつ小説の読みの深さにも変化が起きるんじゃないかと期待している。
よあけ@mogumogu2026年1月27日読み終わったなぜか続編の『小説の読み方』の方を先に入手して何年か積ん読していたのだけど、時々行く本屋さんでなんとなくこちらを購入して読む。 読書好きと言いながら読むのがとても遅いこと、幼少期から本は好きだったのに、なぜかそこから深まらず、色々読むようになったのは社会人になってからなど、読書に対して勝手にコンプレックスを持っていた私にとても合っていた。 ゆっくり楽しく読めばいいんだと思えたし、技法的なことも姿勢的なことも、作家の視点であらためて言語化されると参考になることが多くて、少しずつ小説の読みの深さにも変化が起きるんじゃないかと期待している。





 汐見@siomi2509272026年1月14日読み終わった平野啓一郎さんの読書論。 先日、森博嗣さんの読書論を読んだこともあり比較しつつ面白く読了。 本作ではスロー・リーディングが勧められている。小説から何を読み取るのか。行間や間の取り方、心情の揺れ動きなど。単純な展開だけでなく、書かれている文章の細部に注意を払うことでより豊かな読書体験になる。 作者が何を書こうとしたかにとことん向き合うことは確かに楽しい。もちろん誤読もあり得るけど、本書ではそれを全否定することはない。誤読から生まれるものもある。 後半では、実在する小説(『こころ』『高瀬舟』『金閣寺』等。カフカや『蛇にピアス』も)の一節が掲載され、その後に平野さんによる解説が入る。 それこそ一度の読了でこの本の全てを自分に落とし込むことは難しいけど、巻末に書かれている通り、本書を読んだことで確かに今後の小説の読み方には変化があると思う。村山由佳さんの『PRIZE』を読んだ後のような感覚。 こちらは2006年出版。2009年(文庫版2022年)に続編『小説の読み方』も出版されているらしい。実際の小説の読み解きがさらに多いようなので、そちらも読んでみたい。
汐見@siomi2509272026年1月14日読み終わった平野啓一郎さんの読書論。 先日、森博嗣さんの読書論を読んだこともあり比較しつつ面白く読了。 本作ではスロー・リーディングが勧められている。小説から何を読み取るのか。行間や間の取り方、心情の揺れ動きなど。単純な展開だけでなく、書かれている文章の細部に注意を払うことでより豊かな読書体験になる。 作者が何を書こうとしたかにとことん向き合うことは確かに楽しい。もちろん誤読もあり得るけど、本書ではそれを全否定することはない。誤読から生まれるものもある。 後半では、実在する小説(『こころ』『高瀬舟』『金閣寺』等。カフカや『蛇にピアス』も)の一節が掲載され、その後に平野さんによる解説が入る。 それこそ一度の読了でこの本の全てを自分に落とし込むことは難しいけど、巻末に書かれている通り、本書を読んだことで確かに今後の小説の読み方には変化があると思う。村山由佳さんの『PRIZE』を読んだ後のような感覚。 こちらは2006年出版。2009年(文庫版2022年)に続編『小説の読み方』も出版されているらしい。実際の小説の読み解きがさらに多いようなので、そちらも読んでみたい。
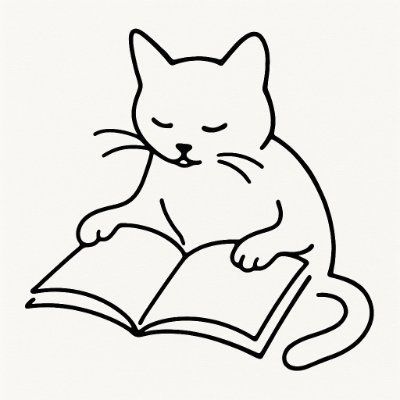



 泡沫(うたかた)@reads21512025年9月14日読み終わった本書は量より質を重視することを提唱している。どのように読むのかまたどんな読み方があるのか実際に名著などを用いて解説している。今回私が勉強になったのは小説の表現で1分野に関連する表現を続けることである。例えばある登場人物の趣味が植物を愛でることなら花の状態や庭の芝生の雰囲気や生垣の様子で心情や空気が緊張しているのかリラックスしているのかを表現するなどである。これは相手の認知している世界で自分自身の考えていることを伝えること活用できそうな気がした。
泡沫(うたかた)@reads21512025年9月14日読み終わった本書は量より質を重視することを提唱している。どのように読むのかまたどんな読み方があるのか実際に名著などを用いて解説している。今回私が勉強になったのは小説の表現で1分野に関連する表現を続けることである。例えばある登場人物の趣味が植物を愛でることなら花の状態や庭の芝生の雰囲気や生垣の様子で心情や空気が緊張しているのかリラックスしているのかを表現するなどである。これは相手の認知している世界で自分自身の考えていることを伝えること活用できそうな気がした。




 -ゞ-@bunkobonsuki2025年8月28日2000年代前半。 日本では「いかに本を速く読み、理解するか」を旨とする速読術が流行っていた。そんな時代において、著者は逆張りとも思える本を刊行する。速読に対抗して、スロー・リーディング(熟読・精読)を打ち出したのだ。 それが本書「本の読み方 スロー・リーディングの実践」である。 現代はまさに大タイパ時代。 本に限らず、あらゆるコンテンツが速読術の対象にさらされ、「いかに娯楽を速く捌くか」という境地に達している。 その中で、あえてゆっくり読むというのは勇気がいることだ。中にはゆっくり読むことしかできない人もいるだろう。だが、本書は遅読を肯定してくれる。私自身もつい先を急いで読んでしまうのだが、本書はあえて暢気に、ゆったり読んだ。
-ゞ-@bunkobonsuki2025年8月28日2000年代前半。 日本では「いかに本を速く読み、理解するか」を旨とする速読術が流行っていた。そんな時代において、著者は逆張りとも思える本を刊行する。速読に対抗して、スロー・リーディング(熟読・精読)を打ち出したのだ。 それが本書「本の読み方 スロー・リーディングの実践」である。 現代はまさに大タイパ時代。 本に限らず、あらゆるコンテンツが速読術の対象にさらされ、「いかに娯楽を速く捌くか」という境地に達している。 その中で、あえてゆっくり読むというのは勇気がいることだ。中にはゆっくり読むことしかできない人もいるだろう。だが、本書は遅読を肯定してくれる。私自身もつい先を急いで読んでしまうのだが、本書はあえて暢気に、ゆったり読んだ。

 喜楽@kiraku2025年8月12日読み終わった電子書籍内容的には他の読書法の書籍と変わらず、またスローリーディングを勧める理由(速読を否定する理由)も、平野氏の意見に留まっているものが多い。つまり、平野氏は速読は嫌いでスローリーディングが好きと言っているだけ。 ただ、全体を通して読ませる文章となっており、とても読みやすく、読んでいて退屈にならなかったのは流石だった。
喜楽@kiraku2025年8月12日読み終わった電子書籍内容的には他の読書法の書籍と変わらず、またスローリーディングを勧める理由(速読を否定する理由)も、平野氏の意見に留まっているものが多い。つまり、平野氏は速読は嫌いでスローリーディングが好きと言っているだけ。 ただ、全体を通して読ませる文章となっており、とても読みやすく、読んでいて退屈にならなかったのは流石だった。

- yh@yh2025年7月26日古本寝る前@ 自宅p.155まで。スロー・リーディング実践編で、かつて読んだことのある作品が出てくると、俄然スロー・リーディングの有益さについての私的説得力が増す、ということを森鷗外「高瀬舟」の例で実感した。あと、読書感想文書くときのヒントとして、この本をすすめられるなあと思った(でも、小学生にはちょっと難しいかな。




- yh@yh2025年7月17日少し読んだ古本職場就業前p.86まで。本を「より、先へ」ではなく、「より、奥へ」読むこと。その本の以前に、背景となる本があり、その本の背景にも本がある。……となると、「奥へ」読めば、古本に向かっていくのは当然だ、という恣意的誤読の一つもしたくなる。



 きん@paraboots2025年6月21日読み終わったわたし自身、ものすごく遅読者で、人生のことあるごとに速読できる人に憧れ、たびたび試みるべく速読術の本を何冊も買ったし、実践も実際試みてきたが、正直うまくできたことは一度もない。 いまだ本を読むのは遅いし、一度読んだくらいでは頭に入らないので、大抵は二度は目を通す。 が、平野さんが推すスローリーディングは、そんなわたしのあり方を勇気づけてくれたし、なにより、スローリーディングとはただ読むのが遅いだけのわたしの読書法とは違い、より深く作品を理解する方法の一つで、本書を読むうちそれを実践したいと思えたのは大きな収穫だった。 ここに書かれる古典作品をさっそく読んでみたいと思う。
きん@paraboots2025年6月21日読み終わったわたし自身、ものすごく遅読者で、人生のことあるごとに速読できる人に憧れ、たびたび試みるべく速読術の本を何冊も買ったし、実践も実際試みてきたが、正直うまくできたことは一度もない。 いまだ本を読むのは遅いし、一度読んだくらいでは頭に入らないので、大抵は二度は目を通す。 が、平野さんが推すスローリーディングは、そんなわたしのあり方を勇気づけてくれたし、なにより、スローリーディングとはただ読むのが遅いだけのわたしの読書法とは違い、より深く作品を理解する方法の一つで、本書を読むうちそれを実践したいと思えたのは大きな収穫だった。 ここに書かれる古典作品をさっそく読んでみたいと思う。








 it_shine@it_shine2025年3月29日読み終わった前半部分は遅読の良さを語っていて、後半部分では、具体的な読みに入っていった。どう読むか。作家がどう読んでいるかというコツが書いてあって、一度では折伏し得ないことだけれど、なるほどなぁと思うことも多かった。この本を読んで、この後の人生で本の読み方は多少でも深くなるかもしれない。それは良いことだと思う。
it_shine@it_shine2025年3月29日読み終わった前半部分は遅読の良さを語っていて、後半部分では、具体的な読みに入っていった。どう読むか。作家がどう読んでいるかというコツが書いてあって、一度では折伏し得ないことだけれど、なるほどなぁと思うことも多かった。この本を読んで、この後の人生で本の読み方は多少でも深くなるかもしれない。それは良いことだと思う。
 it_shine@it_shine2025年3月28日読んでる遅読を大いに楽しみましょうと言う本。 もともと、私は読むのが遅かった。理解しようとすると、自然と遅くなる。抜き書きや、自分の考えを書きだすことにも憧れるけれど、いまだにあまり実行できていない。読書ノートは気が向いた本だけ書いている。 アンチ速読、音読の平野さんの執念を感じた。
it_shine@it_shine2025年3月28日読んでる遅読を大いに楽しみましょうと言う本。 もともと、私は読むのが遅かった。理解しようとすると、自然と遅くなる。抜き書きや、自分の考えを書きだすことにも憧れるけれど、いまだにあまり実行できていない。読書ノートは気が向いた本だけ書いている。 アンチ速読、音読の平野さんの執念を感じた。




 彼らは読みつづけた@findareading1900年1月1日かつて読んだ*読書で見つけた「読書(する人)」* 《そして何よりも、ゆっくり時間をかけさえすれば、読書は楽しい。私が伝えたいことは、これに尽きると言っていい。》 — 平野啓一郎著『本の読み方 スロー・リーディングの実践』(2006年9月、PHP新書)
彼らは読みつづけた@findareading1900年1月1日かつて読んだ*読書で見つけた「読書(する人)」* 《そして何よりも、ゆっくり時間をかけさえすれば、読書は楽しい。私が伝えたいことは、これに尽きると言っていい。》 — 平野啓一郎著『本の読み方 スロー・リーディングの実践』(2006年9月、PHP新書)