
-ゞ-
@bunkobonsuki
文庫本を中心に読んでいます。
noteでも本の感想文を書いておりますので、もし良かったら参考に。
- 2026年2月23日
 2010年代SF傑作選2伴名練,大森望2010年代のSFの傑作短編をまとめたシリーズ、第二巻。 中堅やベテランの作品が並んだ一巻と比べて、二巻ではフレッシュな顔ぶれが並ぶ。個人的には、2020年代の作家といっても違和感のないメンツである。 ギミックによる物語の仕掛けを押し出した作品が多い印象だった。同じ2010年代の作品でも、作家によって空気感や重視する部分は大きく変わるのだと感じさせられた。 2020年代も半ばを過ぎた現在、今までフィクションであった高度な人工知能が現実のものとなった。SFは世相と未来を映し出す鏡だ。2030年に編まれる短編集は、どんなものとなるのだろう。
2010年代SF傑作選2伴名練,大森望2010年代のSFの傑作短編をまとめたシリーズ、第二巻。 中堅やベテランの作品が並んだ一巻と比べて、二巻ではフレッシュな顔ぶれが並ぶ。個人的には、2020年代の作家といっても違和感のないメンツである。 ギミックによる物語の仕掛けを押し出した作品が多い印象だった。同じ2010年代の作品でも、作家によって空気感や重視する部分は大きく変わるのだと感じさせられた。 2020年代も半ばを過ぎた現在、今までフィクションであった高度な人工知能が現実のものとなった。SFは世相と未来を映し出す鏡だ。2030年に編まれる短編集は、どんなものとなるのだろう。 - 2026年2月22日
 2010年代SF傑作選 1伴名練,大森望2010年代の短編SFを二巻に渡って編んだシリーズの一巻目。 一巻ではSF冬の時代を生き抜いたSF作家たちの作品が収録されている。そのため、タイトルにある「2010年代」感は薄いかもしれない。 裏を返せば中堅・ベテランのビッグネームが並ぶということで、贅沢な一冊となっている。各作品を読んでみると、文字表現について考えたものや、人情や精神面に寄り添った作品が多く、設定そのものを押し出すというよりは設定からいかに人間模様を引き出せるか考察しているようだと感じた。
2010年代SF傑作選 1伴名練,大森望2010年代の短編SFを二巻に渡って編んだシリーズの一巻目。 一巻ではSF冬の時代を生き抜いたSF作家たちの作品が収録されている。そのため、タイトルにある「2010年代」感は薄いかもしれない。 裏を返せば中堅・ベテランのビッグネームが並ぶということで、贅沢な一冊となっている。各作品を読んでみると、文字表現について考えたものや、人情や精神面に寄り添った作品が多く、設定そのものを押し出すというよりは設定からいかに人間模様を引き出せるか考察しているようだと感じた。 - 2026年2月19日
 ゲームビジネス岡安学タイトルを見た瞬間にこう思った。 ゲームって、教養なんだ。 これまで様々なカルチャーがサブからメインに格上げされてきた。小説やテレビドラマといったジャンルもはじめは下等な娯楽として蔑まれ、それでも生き残り、ついにはメインカルチャーとして振舞えるようになった。 ゲームもその位置に立ったのだ。 そう思わされるタイトルだった。 ゲームほど成功を収めたカルチャーも珍しい。今や老若男女に膾炙したゲームという存在が、なぜ成功できたのか? 本書が教えてくれる。
ゲームビジネス岡安学タイトルを見た瞬間にこう思った。 ゲームって、教養なんだ。 これまで様々なカルチャーがサブからメインに格上げされてきた。小説やテレビドラマといったジャンルもはじめは下等な娯楽として蔑まれ、それでも生き残り、ついにはメインカルチャーとして振舞えるようになった。 ゲームもその位置に立ったのだ。 そう思わされるタイトルだった。 ゲームほど成功を収めたカルチャーも珍しい。今や老若男女に膾炙したゲームという存在が、なぜ成功できたのか? 本書が教えてくれる。 - 2026年2月18日
 「山奥ニート」やってます。石井あらたまえがきを読んだだけで面白いと確信する本がある。本書はその類の本である。 山奥に暮らすニートたち。その管理人である著者が自身の半生と山奥で暮らすまでの経緯を語る。 著者の書きぶりはとてもカジュアルだ。本の最後の方でも語られるが、世の中を変革するとか、これが正しいという思想がない。 山奥ニートの着想はPha(ギークハウスの提唱者 )に影響を受けたらしい。飾り気のない文章も、ひょっとしたら彼の影響なのかもしれない。
「山奥ニート」やってます。石井あらたまえがきを読んだだけで面白いと確信する本がある。本書はその類の本である。 山奥に暮らすニートたち。その管理人である著者が自身の半生と山奥で暮らすまでの経緯を語る。 著者の書きぶりはとてもカジュアルだ。本の最後の方でも語られるが、世の中を変革するとか、これが正しいという思想がない。 山奥ニートの着想はPha(ギークハウスの提唱者 )に影響を受けたらしい。飾り気のない文章も、ひょっとしたら彼の影響なのかもしれない。 - 2026年2月15日
 ある愛の寓話村山由佳人を愛する物語の数に比べて、物質や動物を愛する物語は少ない。ましてや性的に愛を捧げるストーリーで純文学をやってのけるのは至難の業である。 本書は、それをやってのけた。 ある愛の寓話というタイトルの通り、尋常ではない愛を描いているのだが、それらすべてが確かな愛だと思えるのだ。
ある愛の寓話村山由佳人を愛する物語の数に比べて、物質や動物を愛する物語は少ない。ましてや性的に愛を捧げるストーリーで純文学をやってのけるのは至難の業である。 本書は、それをやってのけた。 ある愛の寓話というタイトルの通り、尋常ではない愛を描いているのだが、それらすべてが確かな愛だと思えるのだ。 - 2026年2月13日
 星の見える家新津きよみ新津きよみは”予感”の名手できる。 結末を完全に書くことはしない。けれど、読者は作中人物がどうなるか知っている・・・・・・。 あえて余白を残すことで、読者の想像をかきたてる。 星の見える家は、著者の技巧が如何なく発揮された短編集である。どの短編も最後はその後を予感させる終わり方をする。読者は、作中人物たちのその後を考え、温かくなったり、苦しんだりする。 短い時間で人物の生に想いをはせられる一冊だ。
星の見える家新津きよみ新津きよみは”予感”の名手できる。 結末を完全に書くことはしない。けれど、読者は作中人物がどうなるか知っている・・・・・・。 あえて余白を残すことで、読者の想像をかきたてる。 星の見える家は、著者の技巧が如何なく発揮された短編集である。どの短編も最後はその後を予感させる終わり方をする。読者は、作中人物たちのその後を考え、温かくなったり、苦しんだりする。 短い時間で人物の生に想いをはせられる一冊だ。 - 2026年2月12日
 人類の都ジャン=バティスト・マレ,田中裕子第一次世界大戦を勃発する前の世界では、世界平和の機運が確かにあった。世界平和を願う夢想家・ヘンドリックとその義姉・オリヴィアは、建築家のアデラールとともに世界の首都<世界コミュニケーションセンター>の建設に挑む。 読んでいくうちに胸中複雑なものが去来した。ヘンドリックとアデラールは度々仲違いするのだが、アデラールが世界大戦で従軍したことをきっかけにお互いが歩み寄った。 皮肉である。ヘンドリックの願った世界が片隅に実現した瞬間だった。世界が戦争に巻き込まれていく中で、個人間の仲は癒され、融和したのだから。戦争が誰かの争いを止めることもあるのだ。
人類の都ジャン=バティスト・マレ,田中裕子第一次世界大戦を勃発する前の世界では、世界平和の機運が確かにあった。世界平和を願う夢想家・ヘンドリックとその義姉・オリヴィアは、建築家のアデラールとともに世界の首都<世界コミュニケーションセンター>の建設に挑む。 読んでいくうちに胸中複雑なものが去来した。ヘンドリックとアデラールは度々仲違いするのだが、アデラールが世界大戦で従軍したことをきっかけにお互いが歩み寄った。 皮肉である。ヘンドリックの願った世界が片隅に実現した瞬間だった。世界が戦争に巻き込まれていく中で、個人間の仲は癒され、融和したのだから。戦争が誰かの争いを止めることもあるのだ。 - 2026年2月10日
 夜のことphaシェアハウスの管理人Phaが、一人の女性に向けて小説を書くという体で、さまざまな女性との性体験を赤裸々に語る。 色んな人間が出入りするシェアハウスの管理人をやるぐらいだから、性体験の一つ二つはあるだろうと思っていた。まさか全話がそれで埋まるとは予想していなかった。 この本は元々文学フリマで頒布されたものを再編集したものだという。自身の性体験をこれだけ堂々と出せるという点で、私の中の著者に対する印象が大きく変わった一冊。
夜のことphaシェアハウスの管理人Phaが、一人の女性に向けて小説を書くという体で、さまざまな女性との性体験を赤裸々に語る。 色んな人間が出入りするシェアハウスの管理人をやるぐらいだから、性体験の一つ二つはあるだろうと思っていた。まさか全話がそれで埋まるとは予想していなかった。 この本は元々文学フリマで頒布されたものを再編集したものだという。自身の性体験をこれだけ堂々と出せるという点で、私の中の著者に対する印象が大きく変わった一冊。 - 2026年2月5日
- 2026年2月3日
 彼女たちの事情 決定版 (光文社文庫)新津きよみ人には言えない秘密を持った女たち。 その顛末を語った二十の短編集。 「決定版」とあるが、本書は元々の短編集が存在する。著者が文芸誌で掲載したもの、書き下ろしのものをまとめたミステリー・ホラー小説集に、今回新たに三編を加えた形になる。 読んだ感想は、「誇張された現実」というものだ。ミステリー・ホラーなだけあって最後にどんでん返しが待っているが、そこに至る過程は「現実にもありそう」感が半端ない。
彼女たちの事情 決定版 (光文社文庫)新津きよみ人には言えない秘密を持った女たち。 その顛末を語った二十の短編集。 「決定版」とあるが、本書は元々の短編集が存在する。著者が文芸誌で掲載したもの、書き下ろしのものをまとめたミステリー・ホラー小説集に、今回新たに三編を加えた形になる。 読んだ感想は、「誇張された現実」というものだ。ミステリー・ホラーなだけあって最後にどんでん返しが待っているが、そこに至る過程は「現実にもありそう」感が半端ない。 - 2026年1月17日
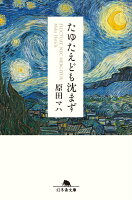 たゆたえども沈まず原田マハ日本美術がブームとなった欧州の地で、二人の日本人が浮世絵を売り捌いていた。 林忠正、加納重吉。 日本を背負って欧州の門を叩いた彼らは、ある時とある兄弟に出会う。 その兄弟の名は——ゴッホ。 後に欧州を席巻する兄・フィンセント。 兄に生涯を捧げた弟・テオ。 二人の日本人とゴッホ兄弟。彼らの"ありえたかもしれない"友情が描かれる。
たゆたえども沈まず原田マハ日本美術がブームとなった欧州の地で、二人の日本人が浮世絵を売り捌いていた。 林忠正、加納重吉。 日本を背負って欧州の門を叩いた彼らは、ある時とある兄弟に出会う。 その兄弟の名は——ゴッホ。 後に欧州を席巻する兄・フィンセント。 兄に生涯を捧げた弟・テオ。 二人の日本人とゴッホ兄弟。彼らの"ありえたかもしれない"友情が描かれる。 - 2026年1月12日
- 2026年1月10日
- 2026年1月10日
 きりぎりす改版太宰治太宰治が中期に書いた作品群をまとめた文庫本『きりぎりす』。 この作品群を通して、太宰は『晩年』の振り返りと批評を行っているのではないか。 二人の作家が手紙で交流する作品「風の便り」では、こんな文章が出てくる。 「君には未だ、君自身の印象というものが無いようにさえ見える。それでは、いつまで経っても何一つ正確に描写する事が出来ない筈です。」 この一文は『晩年』に対する太宰の自己批評にも思えてくる。『晩年』の文体は、常識的な文章であった。それを自覚した太宰は文体の確立のため、さまざまな実験を試みた。 それが、「きりぎりす」をはじめとした作品群なのだと思う。
きりぎりす改版太宰治太宰治が中期に書いた作品群をまとめた文庫本『きりぎりす』。 この作品群を通して、太宰は『晩年』の振り返りと批評を行っているのではないか。 二人の作家が手紙で交流する作品「風の便り」では、こんな文章が出てくる。 「君には未だ、君自身の印象というものが無いようにさえ見える。それでは、いつまで経っても何一つ正確に描写する事が出来ない筈です。」 この一文は『晩年』に対する太宰の自己批評にも思えてくる。『晩年』の文体は、常識的な文章であった。それを自覚した太宰は文体の確立のため、さまざまな実験を試みた。 それが、「きりぎりす」をはじめとした作品群なのだと思う。 - 2026年1月6日
 新版ことわざの論理外山滋比古古今東西に溢れることわざに対して、著者が解説と自論を繰り広げる「ことわざの論理」。この本ではとにかく色んなことわざが入っている。 馴染みのあることわざは勿論、現代ではあまり聞かなくなったことわざも収録されており、字引を見ているだけで楽しい。
新版ことわざの論理外山滋比古古今東西に溢れることわざに対して、著者が解説と自論を繰り広げる「ことわざの論理」。この本ではとにかく色んなことわざが入っている。 馴染みのあることわざは勿論、現代ではあまり聞かなくなったことわざも収録されており、字引を見ているだけで楽しい。 - 2026年1月4日
 痴人の愛改版谷崎潤一郎ハイカラを志すサラリーマンこと譲治は、少女ナオミと同棲する。西洋人のような顔立ちと体を有する彼女に譲治は複雑な想いを寄せながら、やがてナオミに隷従する道を選ぶ。 譲治は先進的を自負しているが、そのハイカラぶりはどこまでもエセが付きまとう。英語は覚えていても西洋人の女性に近づけば慌てるし、ダンスもろくに踊れなくなってしまうのだ。 一方ナオミは中々英語を覚えられずにいたが、その奔放ぶりが強まるにつれて自然に英語を覚え、西洋人との付き合い方も譲治を上回っていく。 「教訓になると思う人は、いい見せしめにしてください」 小説の最後に譲治はこう述べている。私はこの物語に、以下の教訓を読み取ろうと思う。 青は藍より出でて藍より青し。
痴人の愛改版谷崎潤一郎ハイカラを志すサラリーマンこと譲治は、少女ナオミと同棲する。西洋人のような顔立ちと体を有する彼女に譲治は複雑な想いを寄せながら、やがてナオミに隷従する道を選ぶ。 譲治は先進的を自負しているが、そのハイカラぶりはどこまでもエセが付きまとう。英語は覚えていても西洋人の女性に近づけば慌てるし、ダンスもろくに踊れなくなってしまうのだ。 一方ナオミは中々英語を覚えられずにいたが、その奔放ぶりが強まるにつれて自然に英語を覚え、西洋人との付き合い方も譲治を上回っていく。 「教訓になると思う人は、いい見せしめにしてください」 小説の最後に譲治はこう述べている。私はこの物語に、以下の教訓を読み取ろうと思う。 青は藍より出でて藍より青し。 - 2025年12月31日
 12月31日。 今年最後に紹介するのは、とある書店のお話である。「一万円選書」で知られるいわた書店の店主が自店について語ったこの本は、カテゴリーとしてはビジネス書になるだろうか。だが、そのビジネスはあまりに素朴だ。 この本では全国の本屋が悩ませる「どのように本を売るか」に対する回答を出している。曰く、「一万円を出してもらう代わりに選書する」だ。 すごくシンプルである。でも、誰もやらなかった。選書家や本屋が新設の店に対して選書することはあっても、個人に選書するサービスはなかった。このサービスが功を奏してから、続々と後追いする書店が出てきた。 本書を読んで感銘を受けたのは、本書の著者が「一万円選書」を周囲に勧めていることだ。資本主義の論理であれば、真似されにくいサービスを展開するべき、真似する同業者には鉄槌を下すべきという理論になろう。そうしないのは著者が業界全体を考えているからで、ぜひ周りに読んでもらいたいと思った。 長々と書いたが、今年も終わりが近づいた。 最後にこの本を紹介することができて幸甚である。 来年もよろしくお願いします。
12月31日。 今年最後に紹介するのは、とある書店のお話である。「一万円選書」で知られるいわた書店の店主が自店について語ったこの本は、カテゴリーとしてはビジネス書になるだろうか。だが、そのビジネスはあまりに素朴だ。 この本では全国の本屋が悩ませる「どのように本を売るか」に対する回答を出している。曰く、「一万円を出してもらう代わりに選書する」だ。 すごくシンプルである。でも、誰もやらなかった。選書家や本屋が新設の店に対して選書することはあっても、個人に選書するサービスはなかった。このサービスが功を奏してから、続々と後追いする書店が出てきた。 本書を読んで感銘を受けたのは、本書の著者が「一万円選書」を周囲に勧めていることだ。資本主義の論理であれば、真似されにくいサービスを展開するべき、真似する同業者には鉄槌を下すべきという理論になろう。そうしないのは著者が業界全体を考えているからで、ぜひ周りに読んでもらいたいと思った。 長々と書いたが、今年も終わりが近づいた。 最後にこの本を紹介することができて幸甚である。 来年もよろしくお願いします。 - 2025年12月30日
 読書についてアルトゥル・ショーペンハウアー,鈴木芳子『読書について』は、ショーペンハウアーの随筆である。当時、ドイツの文壇は退廃を極めていた。読み手はラディカルな主張を展開する新刊を好み、書き手も文章の書き方を俗に合わせる有様。 そんな時代にショーペンハウアーは文壇を敵に回すような文章を著す。同時代人、それも同業者への宣戦布告ともいうべき随筆が、『読書について』なのだ。 時代も国も違うのに、これだけ長く日本で読み継がれる随筆も珍しいのではないか。本書の主張は時代を貫く碇であり、いつどこでも人間は易々と変わらないことを感じさせる。 ただ、異論を唱えたい箇所もある。ショーペンハウアーは「悪書を駆逐し、良書だけを残すべきだ」と言う。その主張はもっともなのだが、どうやらショーペンハウアーは新刊=悪書とみなしているようなのだ。 新刊が出なくなれば本屋市場が縮小し、やがて良書も発掘されなくなるのでは・・・・・・。それだけ当時は新刊に悪書が多かったのだろうか。
読書についてアルトゥル・ショーペンハウアー,鈴木芳子『読書について』は、ショーペンハウアーの随筆である。当時、ドイツの文壇は退廃を極めていた。読み手はラディカルな主張を展開する新刊を好み、書き手も文章の書き方を俗に合わせる有様。 そんな時代にショーペンハウアーは文壇を敵に回すような文章を著す。同時代人、それも同業者への宣戦布告ともいうべき随筆が、『読書について』なのだ。 時代も国も違うのに、これだけ長く日本で読み継がれる随筆も珍しいのではないか。本書の主張は時代を貫く碇であり、いつどこでも人間は易々と変わらないことを感じさせる。 ただ、異論を唱えたい箇所もある。ショーペンハウアーは「悪書を駆逐し、良書だけを残すべきだ」と言う。その主張はもっともなのだが、どうやらショーペンハウアーは新刊=悪書とみなしているようなのだ。 新刊が出なくなれば本屋市場が縮小し、やがて良書も発掘されなくなるのでは・・・・・・。それだけ当時は新刊に悪書が多かったのだろうか。 - 2025年12月29日
- 2025年12月26日
読み込み中...




