

ノエタロス
@Di_Noel02
たぶん前世は恐竜
- 2026年2月12日
 読み終わった読みながら、先の衆院選のことを何度も想起した。 今回自民党が大勝利をおさめた原因の一つに、高市らの打ち出すキャッチーなフレーズや”受けのいい”印象に、多くの国民が引っ張られてしまったことがあるんじゃないか、と。 選挙期間中は特に、政治家たちは耳触りのいい、あるいはシンプルな言葉ばかりを吐く。 「強い」とか「豊かに」とか「ゼロにする」とか。 けれどそこから、政策として具体的な効果や正当性は見えてこない。 だのに、人々はその”わかりやすさ”に惹かれてしまう。 その片棒を担いでしまったのが、スマホやSNSだろうと思う。 政党が莫大な資金を広告に投入し、キャッチコピーだけを垂れ流す。 動画切り抜き配信者たちが、煽情的な言葉を抜粋してショート動画を作り、拡散する。 それらを見た人々は、その”わかりやすさ”に飛びついて、ますますその表面的なイメージだけを頭に浸透させる(いや、浸透「させられる」と言うべき?)。 本書で言うところの「抑鬱的快楽」と、世論をこうした方法で操作することとは、悪い意味で相性がいい。 スマホという道具が登場した時点で、こうなることは必然だったのかもしれない(とはいえ、プラットフォーム側が厳格に取り締まっていれば、もっとずっとマシだったはず)。 それでも、推薦文で書かれている通り、「尚、『哲学』は美味い‼︎」 本書を読んで、こんな時代だからこそ、哲学の必要性や可能性を痛感した。 そして「趣味」の意義も。僕自身、絵を描いたり、物語を作ったり(妄想したり)、創作が好きな人間だが、ここ最近、それらをする時間がめっきり減ったなと。 いわゆる社会人になり、日中は仕事、疲れて帰宅した後は、気づかぬうちに手がスマホへと伸びている。 その習慣から即脱却するのは難しいかもしれないが、孤独や退屈な時間を楽しみながら、創作し、哲学を手元に置きながら、生きていきたい。
読み終わった読みながら、先の衆院選のことを何度も想起した。 今回自民党が大勝利をおさめた原因の一つに、高市らの打ち出すキャッチーなフレーズや”受けのいい”印象に、多くの国民が引っ張られてしまったことがあるんじゃないか、と。 選挙期間中は特に、政治家たちは耳触りのいい、あるいはシンプルな言葉ばかりを吐く。 「強い」とか「豊かに」とか「ゼロにする」とか。 けれどそこから、政策として具体的な効果や正当性は見えてこない。 だのに、人々はその”わかりやすさ”に惹かれてしまう。 その片棒を担いでしまったのが、スマホやSNSだろうと思う。 政党が莫大な資金を広告に投入し、キャッチコピーだけを垂れ流す。 動画切り抜き配信者たちが、煽情的な言葉を抜粋してショート動画を作り、拡散する。 それらを見た人々は、その”わかりやすさ”に飛びついて、ますますその表面的なイメージだけを頭に浸透させる(いや、浸透「させられる」と言うべき?)。 本書で言うところの「抑鬱的快楽」と、世論をこうした方法で操作することとは、悪い意味で相性がいい。 スマホという道具が登場した時点で、こうなることは必然だったのかもしれない(とはいえ、プラットフォーム側が厳格に取り締まっていれば、もっとずっとマシだったはず)。 それでも、推薦文で書かれている通り、「尚、『哲学』は美味い‼︎」 本書を読んで、こんな時代だからこそ、哲学の必要性や可能性を痛感した。 そして「趣味」の意義も。僕自身、絵を描いたり、物語を作ったり(妄想したり)、創作が好きな人間だが、ここ最近、それらをする時間がめっきり減ったなと。 いわゆる社会人になり、日中は仕事、疲れて帰宅した後は、気づかぬうちに手がスマホへと伸びている。 その習慣から即脱却するのは難しいかもしれないが、孤独や退屈な時間を楽しみながら、創作し、哲学を手元に置きながら、生きていきたい。 - 2026年2月2日
 文庫 少年の日の思い出ヘルマン・ヘッセ,岡田朝雄読み終わった教科書の方(高橋健二訳)のあの名台詞「そうかそうか、つまり君はそういうやつだったんだな」が、この本(岡田朝雄訳)では、「そう、そう、きみってそういう人なの?」となっていた。 個人的には、高橋訳の「そうかそうか」の方が好み。 「そう、そう」だと、エーミールの鼻につく優等生ぶりが薄れるというか、ちょっと淡白に聴こえる。 とはいえ現在教科書に載っている訳は、岡田さんが元々の高橋さんの翻訳に修正案を出したものなので、両者ともにヘッセの作品を日本に広めた功労者だ。 タイトルも、もとは”Das Nachtpfauenauge”(クジャクヤママユ)だそうだが、新聞の連載に載せる際に”Jugendgedenken”(直訳は「青春の思い出」)へと、ヘッセ本人が変えたようだ。 やはり後者の方が良いと思う。 甘美な響きの題が、蓋を開けてみれば、優等生の標本を、そして自身の憧れだった蛾を台無しにしてしまったという苦々しい記憶……というギャップが好き。 ほんの出来心で犯してしまった子ども時代の罪と、大人になったいまも忘れられない後悔と胸の痛み。 主人公と同じように、僕もきっと一生忘れることができない。
文庫 少年の日の思い出ヘルマン・ヘッセ,岡田朝雄読み終わった教科書の方(高橋健二訳)のあの名台詞「そうかそうか、つまり君はそういうやつだったんだな」が、この本(岡田朝雄訳)では、「そう、そう、きみってそういう人なの?」となっていた。 個人的には、高橋訳の「そうかそうか」の方が好み。 「そう、そう」だと、エーミールの鼻につく優等生ぶりが薄れるというか、ちょっと淡白に聴こえる。 とはいえ現在教科書に載っている訳は、岡田さんが元々の高橋さんの翻訳に修正案を出したものなので、両者ともにヘッセの作品を日本に広めた功労者だ。 タイトルも、もとは”Das Nachtpfauenauge”(クジャクヤママユ)だそうだが、新聞の連載に載せる際に”Jugendgedenken”(直訳は「青春の思い出」)へと、ヘッセ本人が変えたようだ。 やはり後者の方が良いと思う。 甘美な響きの題が、蓋を開けてみれば、優等生の標本を、そして自身の憧れだった蛾を台無しにしてしまったという苦々しい記憶……というギャップが好き。 ほんの出来心で犯してしまった子ども時代の罪と、大人になったいまも忘れられない後悔と胸の痛み。 主人公と同じように、僕もきっと一生忘れることができない。 - 2025年12月31日
 トランスジェンダー男性のきみへザンダー・ケッグ,メガン・M.ローアー,上田勢子,周司あきら読み終わった一番の学びとしては、早く性別移行したい!といって「焦らないこと」。 僕自身も内心、「早く変わりたい」と焦ったい気持ちを抱えてしまっているが、一回移行してしまうと、当然ながらもう後には引けない。 決意は固いので後悔はしないと思うが、この移行の過程というのは、今この瞬間しか経験できないのだ。 気持ちばかりが先走ってしまうと、肝心なところを見落とし、失敗が生まれる危険性がある。 慎重になりすぎということはない、自分の心と体のことだから、何度も立ち止まって振り返って、ゆっくり考えていきながら進めていくことが、将来の自分のためにも大切なのだと、教わった。 それに、移行をしてからも、やはり様々な苦労がトランス男性には付きまとうことになる(女性との連帯が途切れるリスク、男性としての”特権”を持つことへの戸惑いなど)のだと知った。 移行できたからって、自分が望んだ通りの完璧な人生を歩めるとは限らない。 でもシスジェンダーにしろトランスジェンダーにしろ、予想通りに上手くいかないことがあるなんて、人生において当たり前のことなんだろう。 であれば、過度な期待を抱きすぎず(もちろん、それでも移行に対しある程度「今より生きやすくなる」という望みを持つことは止めないけど)、今移行中の過程も、自身の大切な人生の一部分なんだと噛み締めたい。 しばらくしたら、また焦りが出てきてしまうかもしれないが、この本を読んだことで、気持ちにブレーキをかけることができそうだ。
トランスジェンダー男性のきみへザンダー・ケッグ,メガン・M.ローアー,上田勢子,周司あきら読み終わった一番の学びとしては、早く性別移行したい!といって「焦らないこと」。 僕自身も内心、「早く変わりたい」と焦ったい気持ちを抱えてしまっているが、一回移行してしまうと、当然ながらもう後には引けない。 決意は固いので後悔はしないと思うが、この移行の過程というのは、今この瞬間しか経験できないのだ。 気持ちばかりが先走ってしまうと、肝心なところを見落とし、失敗が生まれる危険性がある。 慎重になりすぎということはない、自分の心と体のことだから、何度も立ち止まって振り返って、ゆっくり考えていきながら進めていくことが、将来の自分のためにも大切なのだと、教わった。 それに、移行をしてからも、やはり様々な苦労がトランス男性には付きまとうことになる(女性との連帯が途切れるリスク、男性としての”特権”を持つことへの戸惑いなど)のだと知った。 移行できたからって、自分が望んだ通りの完璧な人生を歩めるとは限らない。 でもシスジェンダーにしろトランスジェンダーにしろ、予想通りに上手くいかないことがあるなんて、人生において当たり前のことなんだろう。 であれば、過度な期待を抱きすぎず(もちろん、それでも移行に対しある程度「今より生きやすくなる」という望みを持つことは止めないけど)、今移行中の過程も、自身の大切な人生の一部分なんだと噛み締めたい。 しばらくしたら、また焦りが出てきてしまうかもしれないが、この本を読んだことで、気持ちにブレーキをかけることができそうだ。 - 2025年12月6日
 ももこの話さくらももこ読み終わったさくらももこはJリーグのサッカー選手だった長谷川健太と同級生だったそう。 長谷川さんは小学校時代からサッカー大好きで活躍し、頭も良く学級委員もしていたと。 それを見てももこの母は、長谷川さんを褒める一方「あんたなんて長谷川君のしてることひとつもやってないじゃない。情ないと思わないのかね」と娘に言ったらしい。 しかし彼女は、「ケンタはケンタで私は私なのだ」と、彼の行為を真似する気もなかったし、情けないことだとも思わず、反省する気もまったくなかったと。 シンプルにめっちゃかっこいい。 (いい意味で)他人に左右されないこの堂々たる姿勢、これこそ見習うべきだと思った。 もし彼女が母の文句を真に受けて、漫画家になる夢を諦めていたら、あの名作たちは生まれていなかったかもしれない。 ケンタも、ももこも、自分の大好きなもの、極めたいと思うものにとことん一直線だったから、二人ともそれぞれ夢を叶えられたんだろうなと思う。 さくらももこの魅力にまた一歩惹かれた一冊だった。
ももこの話さくらももこ読み終わったさくらももこはJリーグのサッカー選手だった長谷川健太と同級生だったそう。 長谷川さんは小学校時代からサッカー大好きで活躍し、頭も良く学級委員もしていたと。 それを見てももこの母は、長谷川さんを褒める一方「あんたなんて長谷川君のしてることひとつもやってないじゃない。情ないと思わないのかね」と娘に言ったらしい。 しかし彼女は、「ケンタはケンタで私は私なのだ」と、彼の行為を真似する気もなかったし、情けないことだとも思わず、反省する気もまったくなかったと。 シンプルにめっちゃかっこいい。 (いい意味で)他人に左右されないこの堂々たる姿勢、これこそ見習うべきだと思った。 もし彼女が母の文句を真に受けて、漫画家になる夢を諦めていたら、あの名作たちは生まれていなかったかもしれない。 ケンタも、ももこも、自分の大好きなもの、極めたいと思うものにとことん一直線だったから、二人ともそれぞれ夢を叶えられたんだろうなと思う。 さくらももこの魅力にまた一歩惹かれた一冊だった。 - 2025年11月30日
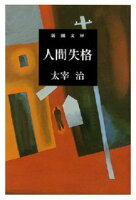 人間失格太宰治読み終わった人間を恐れながらも、人間らしくなりたい、人を信じて愛したい、しかしそれが思うようにいかず、乱れて堕ちていく葉蔵。 彼の視点を通して、俗世間のエゴイズム、醜さが描かれている。 そうして人間社会でもがき苦しみながらも、ツネ子やヨシ子といった、無垢で純粋で、「信頼の天才」と言われるような、人を疑うことを知らない存在とも出逢った。 だからこそ、単なる”絶望”とも言えず。少なくとも、葉蔵は人生の明るい側面にも微かに触れてはいるのだ、と思う。 偽善やエゴで互いを汚し合うような社会で、ちらりと光を見せられると、それに縋りつきたくなってしまうのはきっと自然なこと。 葉蔵もまた、心を押し殺す日々の中で、自分を信じてくれる人や酒、薬へと手を伸ばして生きながらえてきたんだろう。 その繊細さや儚さが、当時も現代も、読者の心を”強く”掴んでいるのかもしれない。
人間失格太宰治読み終わった人間を恐れながらも、人間らしくなりたい、人を信じて愛したい、しかしそれが思うようにいかず、乱れて堕ちていく葉蔵。 彼の視点を通して、俗世間のエゴイズム、醜さが描かれている。 そうして人間社会でもがき苦しみながらも、ツネ子やヨシ子といった、無垢で純粋で、「信頼の天才」と言われるような、人を疑うことを知らない存在とも出逢った。 だからこそ、単なる”絶望”とも言えず。少なくとも、葉蔵は人生の明るい側面にも微かに触れてはいるのだ、と思う。 偽善やエゴで互いを汚し合うような社会で、ちらりと光を見せられると、それに縋りつきたくなってしまうのはきっと自然なこと。 葉蔵もまた、心を押し殺す日々の中で、自分を信じてくれる人や酒、薬へと手を伸ばして生きながらえてきたんだろう。 その繊細さや儚さが、当時も現代も、読者の心を”強く”掴んでいるのかもしれない。 - 2025年11月19日
 異邦人カミュ読み終わった不条理小説として有名だが、個人的には悲しさや苦悩、絶望といったデカい負の感情が、不思議とそこまで感じられない終わり方だった。 あらすじだけ見ると衝撃的な話だが、文章としては淡々と、すっきりとしているし、どこか客観的で落ち着いた一人称視点*も、ショックを抑えている気がする。 面白いと思ったのが、主人公ムルソーの名は、「死」と「太陽」の合成語らしい。 結果的に最後は死刑にされるが、ムルソーとしては一貫して「嘘をつかなかった」だけ。 太陽の眩しさに目を奪われ、その光とともに不幸の闇の中に落とされてしまったけど、彼は死の瞬間までその光を手放さなかった。 この世界では「異邦人」とみなされながら、それでも自分の心を偽らなかった。 その結末に、絶望というより、いやむしろ絶望ではなく、彼の胸の内の強い輝きを見た気がした。 *→ただ、死刑を宣告された後、訪ねてきた司祭に己の死を憐れまれて、ムルソーは作中で初めて感情を爆発させる。 読んだ人の多くはそうだと思うが、もうそこでぐっとムルソーの魅力に惹き込まれた。
異邦人カミュ読み終わった不条理小説として有名だが、個人的には悲しさや苦悩、絶望といったデカい負の感情が、不思議とそこまで感じられない終わり方だった。 あらすじだけ見ると衝撃的な話だが、文章としては淡々と、すっきりとしているし、どこか客観的で落ち着いた一人称視点*も、ショックを抑えている気がする。 面白いと思ったのが、主人公ムルソーの名は、「死」と「太陽」の合成語らしい。 結果的に最後は死刑にされるが、ムルソーとしては一貫して「嘘をつかなかった」だけ。 太陽の眩しさに目を奪われ、その光とともに不幸の闇の中に落とされてしまったけど、彼は死の瞬間までその光を手放さなかった。 この世界では「異邦人」とみなされながら、それでも自分の心を偽らなかった。 その結末に、絶望というより、いやむしろ絶望ではなく、彼の胸の内の強い輝きを見た気がした。 *→ただ、死刑を宣告された後、訪ねてきた司祭に己の死を憐れまれて、ムルソーは作中で初めて感情を爆発させる。 読んだ人の多くはそうだと思うが、もうそこでぐっとムルソーの魅力に惹き込まれた。 - 2025年11月15日
 田舎医者/断食芸人/流刑地でカフカ,丘沢静也読み終わった解説にカフカは「『?』のエンターテイナー」とあるように、頭にいくつもはてなマークが浮かんでくる読後。 どデカいインパクトだけが脳内にゴロッと転がされて、気づけばそれを抱えたまま物語が終わっている。 戸惑いや動揺というには大袈裟かもしれないが、ずっと心の中に「?」が転がったまんまなので、そこに吸い寄せられ、じーっと眺めてみたり、ツンツンつついてみたり、考察のし甲斐が大いにある。 中でも『流刑地で』が強烈だった。作中に出てくる、〈馬鍬〉のついた死刑執行の装置を想像するだけで、恐怖でゾクっとする。 将校の刑の執行が、ブラックユーモアというか、皮肉たっぷりの終わり方で印象的。
田舎医者/断食芸人/流刑地でカフカ,丘沢静也読み終わった解説にカフカは「『?』のエンターテイナー」とあるように、頭にいくつもはてなマークが浮かんでくる読後。 どデカいインパクトだけが脳内にゴロッと転がされて、気づけばそれを抱えたまま物語が終わっている。 戸惑いや動揺というには大袈裟かもしれないが、ずっと心の中に「?」が転がったまんまなので、そこに吸い寄せられ、じーっと眺めてみたり、ツンツンつついてみたり、考察のし甲斐が大いにある。 中でも『流刑地で』が強烈だった。作中に出てくる、〈馬鍬〉のついた死刑執行の装置を想像するだけで、恐怖でゾクっとする。 将校の刑の執行が、ブラックユーモアというか、皮肉たっぷりの終わり方で印象的。 - 2025年10月27日
 変身フランツ・カフカ,川島隆読み終わったラストのあまりの不条理が衝撃で、ただもう開いた口が塞がらなかった。 変身が解けず、挙句家族に見捨てられたグレゴールが気の毒でならなかったが、なぜかまた読み返したくなるような、不思議な読後感。でも、家族が彼を守り抜き、最後まで見捨てないような展開になっていたら絶対つまらないし、こんな有名な作品にはなっていないんだろうなと思った。 ところで、作者のカフカは、変身した主人公の姿は、読者がそれぞれ頭の中で想像すべきだと考えていたそうだ。 この翻訳本では、「化け物じみた図体の虫けら」「かぼそい肢がたくさん(中略)チラチラうごめいていた」などと訳されているが、そこからどんな「虫けら」を思い描くのか、『変身』を読んだことのある人ひとりひとりに聞いてまわってみたい。 個人的には、「肢がたくさん」「弓なりの段々模様で区切られた丸っこい茶色の腹」という表現から、ムカデが頭に浮かんだけれど、うちの親はGだったらしい。 はたまた、キメラみたいな姿を想像する人もいるのかもしれない。 何にせよおぞましい変身であることには違いないが、こうやってあれこれ想像が膨らむのも、この作品の面白いところだと思う。
変身フランツ・カフカ,川島隆読み終わったラストのあまりの不条理が衝撃で、ただもう開いた口が塞がらなかった。 変身が解けず、挙句家族に見捨てられたグレゴールが気の毒でならなかったが、なぜかまた読み返したくなるような、不思議な読後感。でも、家族が彼を守り抜き、最後まで見捨てないような展開になっていたら絶対つまらないし、こんな有名な作品にはなっていないんだろうなと思った。 ところで、作者のカフカは、変身した主人公の姿は、読者がそれぞれ頭の中で想像すべきだと考えていたそうだ。 この翻訳本では、「化け物じみた図体の虫けら」「かぼそい肢がたくさん(中略)チラチラうごめいていた」などと訳されているが、そこからどんな「虫けら」を思い描くのか、『変身』を読んだことのある人ひとりひとりに聞いてまわってみたい。 個人的には、「肢がたくさん」「弓なりの段々模様で区切られた丸っこい茶色の腹」という表現から、ムカデが頭に浮かんだけれど、うちの親はGだったらしい。 はたまた、キメラみたいな姿を想像する人もいるのかもしれない。 何にせよおぞましい変身であることには違いないが、こうやってあれこれ想像が膨らむのも、この作品の面白いところだと思う。 - 2025年10月15日
 ぼくは恐竜探険家!小林快次読み終わった尊敬する恐竜学者のうちの一人、小林快次さん。 小林さんが発掘に携わった恐竜については、別の書籍を読んだこともあり、ある程度は知っているつもりだった。が、恐竜学者になる前のことは詳しく知らなかったので、この本で知れて満足。 大学生のとき、周囲に押されてアメリカに一年間留学するも、勉強に身が入らなかった小林さん。 しかしそれをきっかけに、もう一度アメリカできちんと古生物のことを学びたいと決意し、そこからのものすごい努力の連続に、本当に尊敬の思いを抱く。 「勉強」や「研究」というと、つい大変なイメージを抱いてしまいがちだけど、本質は「知りたい」、「謎を解き明かしたい」という好奇心や探究心から来ていて、その強い気持ちが行動を後押ししてくれるんだなと思った。 僕も既に大学を卒業してしまったが、まだまだやれることがたくさんあるなと、この本から刺激を受けた。 恐竜のために、何でも楽しんで学んで、どんどん自分の中に吸収し続けよう、と密かに決意。
ぼくは恐竜探険家!小林快次読み終わった尊敬する恐竜学者のうちの一人、小林快次さん。 小林さんが発掘に携わった恐竜については、別の書籍を読んだこともあり、ある程度は知っているつもりだった。が、恐竜学者になる前のことは詳しく知らなかったので、この本で知れて満足。 大学生のとき、周囲に押されてアメリカに一年間留学するも、勉強に身が入らなかった小林さん。 しかしそれをきっかけに、もう一度アメリカできちんと古生物のことを学びたいと決意し、そこからのものすごい努力の連続に、本当に尊敬の思いを抱く。 「勉強」や「研究」というと、つい大変なイメージを抱いてしまいがちだけど、本質は「知りたい」、「謎を解き明かしたい」という好奇心や探究心から来ていて、その強い気持ちが行動を後押ししてくれるんだなと思った。 僕も既に大学を卒業してしまったが、まだまだやれることがたくさんあるなと、この本から刺激を受けた。 恐竜のために、何でも楽しんで学んで、どんどん自分の中に吸収し続けよう、と密かに決意。 - 2025年10月8日
 生きづらさに向き合うこどもおかねともこ,フルイ・ミエコ,平井美津子読み終わった読み終わって、副題の言葉が腑に落ちたというか、じんわり温かく感じられた。 平井さんがこの本で記している、生きづらさを抱える生徒やその親たちの大半は、「家族」や「血のつながり」といった、時に支配ー被支配の関係が生じる「絆」で、がんじがらめになって苦しんできた。 大黒柱である父(夫)の言うことは絶対であり、妻や子たちは従属させられる。男の意に沿わないことをすれば虐待を受け、家を出ざるをえなかったり、あるいは出たくてもお金がなくて耐えるしかなかったりする。 離婚できても、こどもの養育費や進学費の負担に苦しむ。離婚相手が養育費を払ってくれないこともままあるそうだ。 こどもたちの狭い世界では、家庭と学校の往復が中心になってくる。 平井さんは学校で、直接的にも間接的にも、こうしたしんどい思いをしているこどもたちの存在を、何度も見聞きしてきたのだと思う。 学校も、ともすると教師と生徒の間で支配関係ができて、そこから体罰や性暴力の問題が起こったりもしてしまう。 けれど平井さんは、その子ひとりひとりに、対等な人間として真正面から話を聴き、彼らがどうすれば窮地から抜け出せるのか、一緒に考えながら伴走する人なんだなと。 「絆」というガチガチに固い結束よりも、ゆるやかに、困っているときにそっと手を差し伸べられる関係。 そんなつながりが少しずつ増えていけば、こどもにとって息のしやすい空間もちょっとずつ増えていくのかなと思った。
生きづらさに向き合うこどもおかねともこ,フルイ・ミエコ,平井美津子読み終わった読み終わって、副題の言葉が腑に落ちたというか、じんわり温かく感じられた。 平井さんがこの本で記している、生きづらさを抱える生徒やその親たちの大半は、「家族」や「血のつながり」といった、時に支配ー被支配の関係が生じる「絆」で、がんじがらめになって苦しんできた。 大黒柱である父(夫)の言うことは絶対であり、妻や子たちは従属させられる。男の意に沿わないことをすれば虐待を受け、家を出ざるをえなかったり、あるいは出たくてもお金がなくて耐えるしかなかったりする。 離婚できても、こどもの養育費や進学費の負担に苦しむ。離婚相手が養育費を払ってくれないこともままあるそうだ。 こどもたちの狭い世界では、家庭と学校の往復が中心になってくる。 平井さんは学校で、直接的にも間接的にも、こうしたしんどい思いをしているこどもたちの存在を、何度も見聞きしてきたのだと思う。 学校も、ともすると教師と生徒の間で支配関係ができて、そこから体罰や性暴力の問題が起こったりもしてしまう。 けれど平井さんは、その子ひとりひとりに、対等な人間として真正面から話を聴き、彼らがどうすれば窮地から抜け出せるのか、一緒に考えながら伴走する人なんだなと。 「絆」というガチガチに固い結束よりも、ゆるやかに、困っているときにそっと手を差し伸べられる関係。 そんなつながりが少しずつ増えていけば、こどもにとって息のしやすい空間もちょっとずつ増えていくのかなと思った。 - 2025年10月6日
 最新研究で迫る 生き物の生態図鑑きのしたちひろ読み終わった美麗でかわいらしいイラストと、分かりやすく噛み砕いた言葉で丁寧に書(描)かれている一冊。どのページも本当に面白くて、スイスイ読み進められる。 頭と体が切り離されても再生できるウミウシ、 木の枝や種のさやを楽器にして演奏するヤシオウム、 ハチと似た音を出して天敵を追い払うコウモリ、 ヒトと協力してハチの巣狩りをするミツオシエ、 熱殺蜂球でオオスズメバチを蒸し殺すミツバチなどなど…… どの生き物も個性豊かに、たくましく生きているんだなと感心する。 全部興味深かったけれど、コナガの幼虫に葉をかじられると、特別な香りを出すキャベツが驚きだった。その香りに釣られて、コナガの天敵であるコナガコマユバチがキャベツに近寄ってくるらしい。 普段食べているキャベツが、そんなに主張強めだったとは。自分は葉をかじられてダメージを受けても、少しでも多く他のキャベツが助かるように……ということなのか、力を振り絞って香りのメッセージを拡散するたくましさ、すごい。
最新研究で迫る 生き物の生態図鑑きのしたちひろ読み終わった美麗でかわいらしいイラストと、分かりやすく噛み砕いた言葉で丁寧に書(描)かれている一冊。どのページも本当に面白くて、スイスイ読み進められる。 頭と体が切り離されても再生できるウミウシ、 木の枝や種のさやを楽器にして演奏するヤシオウム、 ハチと似た音を出して天敵を追い払うコウモリ、 ヒトと協力してハチの巣狩りをするミツオシエ、 熱殺蜂球でオオスズメバチを蒸し殺すミツバチなどなど…… どの生き物も個性豊かに、たくましく生きているんだなと感心する。 全部興味深かったけれど、コナガの幼虫に葉をかじられると、特別な香りを出すキャベツが驚きだった。その香りに釣られて、コナガの天敵であるコナガコマユバチがキャベツに近寄ってくるらしい。 普段食べているキャベツが、そんなに主張強めだったとは。自分は葉をかじられてダメージを受けても、少しでも多く他のキャベツが助かるように……ということなのか、力を振り絞って香りのメッセージを拡散するたくましさ、すごい。 - 2025年9月27日
 最新版 恐竜の世界 Q&A小林快次読み終わった恐竜学検定のために借りた本。さすが小林先生……難しい問題がたくさん。ますます恐竜の学習に熱が入る。 最後には登場した恐竜の一覧がまとめられていて、見返しやすいのもGOOD。
最新版 恐竜の世界 Q&A小林快次読み終わった恐竜学検定のために借りた本。さすが小林先生……難しい問題がたくさん。ますます恐竜の学習に熱が入る。 最後には登場した恐竜の一覧がまとめられていて、見返しやすいのもGOOD。 - 2025年9月3日
 NHK子ども科学電話相談 恐竜スペシャル!NHK「子ども科学電話相談」制作班,小林快次,田中康平読み終わった最初の「恐竜図鑑の表紙はなぜティラノサウルスばかりなのか」という質問、ちょっと笑ってしまうけれど、共感。 また「オルニトミムス類は胃石があるが、走るときに邪魔にならないのか」という面白い質問も。それに対する小林先生の答えも興味深かった。走るとき、人間も前に重心が傾くが、オルニトミムスも、胃石を持つことで重心を前にいかせて走りやすくしていたんじゃないかと。植物をすりつぶすだけではない、別の役割としての胃石と考えると、なんだか新鮮。
NHK子ども科学電話相談 恐竜スペシャル!NHK「子ども科学電話相談」制作班,小林快次,田中康平読み終わった最初の「恐竜図鑑の表紙はなぜティラノサウルスばかりなのか」という質問、ちょっと笑ってしまうけれど、共感。 また「オルニトミムス類は胃石があるが、走るときに邪魔にならないのか」という面白い質問も。それに対する小林先生の答えも興味深かった。走るとき、人間も前に重心が傾くが、オルニトミムスも、胃石を持つことで重心を前にいかせて走りやすくしていたんじゃないかと。植物をすりつぶすだけではない、別の役割としての胃石と考えると、なんだか新鮮。 - 2025年9月2日
- 2025年8月27日
- 2025年8月23日
 大人のための「恐竜学」土屋健,小林快次読み終わった恐竜のことを基礎部分から学び直すのに良い一冊。もちろん詳しい人が読んでも楽しめるような、ちょっとコアな情報もある。 個人的には、アンキロサウルス類の尾の先のこぶの内部構造が実はスカスカであることから、武器ではなかったという説が驚きだった。どう見たってあんなのぶつけられたら痛そうなのに。近年発表されたズールも、種小名が「脛の破壊者」を意味するけど、実はそんなことなかった……てこと??
大人のための「恐竜学」土屋健,小林快次読み終わった恐竜のことを基礎部分から学び直すのに良い一冊。もちろん詳しい人が読んでも楽しめるような、ちょっとコアな情報もある。 個人的には、アンキロサウルス類の尾の先のこぶの内部構造が実はスカスカであることから、武器ではなかったという説が驚きだった。どう見たってあんなのぶつけられたら痛そうなのに。近年発表されたズールも、種小名が「脛の破壊者」を意味するけど、実はそんなことなかった……てこと?? - 2025年8月13日
- 2025年7月31日
- 2025年7月12日
 ぼくがスカートをはく日まめふく,エイミ・ポロンスキー,松中権,西田佳子読み終わったタイトルから察しがつく通り、トランス女性(と思われる)の子ども・グレイソンが主人公。学校の演劇のオーディションで、女神ペルセポネの役を志願したことをきっかけに、彼女が勇気を持つようになる物語。 「こうでありたい」という理想の姿と現実の自分を比べてモヤモヤしたり、まわりの人の発言で気持ちが浮き沈みしたりするグレイソンに、シンパシーを感じる。 そしてただただ、彼女の勇気に敬服する。とはいえ、解説でも書かれていたように、一番大切なのは、誰にも悩みを打ち明けられずに一人で抱え込んでいる人が、自分のまわりにいるかもしれない、という想像力を、一人ひとりが持つことなんだよな。カミングアウトする/しないは当人の自由だし、勇気=絶対ではない。いろんな生き方があるけれど、それを否定したり貶めたりすることは誰にもできない、その人だけの生き方だ。 上に「シンパシー」と書いたが、この場合必要になるのは「エンパシー」なんだろう。もちろんまったく同じ人間ではないから、想像しても分からないことだってあるとは思う。完全に理解するのも、それはそれで難しい。 でもだからこそ、暴言や暴力に頼るのではなく、対話して、ちょっとでも相手の意志を尊重しようとする力が大切になってくる。といってもそれはまさにマジョリティ側の問題であって、マイノリティにこれ以上マジョリティの前提を押し付けるのも違うと思うけれど。 大半の人は、マジョリティ性とマイノリティ性のどちらも併せ持つ。その中で、他者の痛みや苦しみから目を逸らさず、自身の立場を見つめて、何ができるのか模索していくしかないんじゃないだろうか。時間がかかるし、めんどくさいことだってあるけれど、きっとそれしかない。 排外主義は手っ取り早いが、何もかもを失うハメになるし、何も解決しない。 それに対抗するためのエンパシーを、僕も持って生きていきたい。
ぼくがスカートをはく日まめふく,エイミ・ポロンスキー,松中権,西田佳子読み終わったタイトルから察しがつく通り、トランス女性(と思われる)の子ども・グレイソンが主人公。学校の演劇のオーディションで、女神ペルセポネの役を志願したことをきっかけに、彼女が勇気を持つようになる物語。 「こうでありたい」という理想の姿と現実の自分を比べてモヤモヤしたり、まわりの人の発言で気持ちが浮き沈みしたりするグレイソンに、シンパシーを感じる。 そしてただただ、彼女の勇気に敬服する。とはいえ、解説でも書かれていたように、一番大切なのは、誰にも悩みを打ち明けられずに一人で抱え込んでいる人が、自分のまわりにいるかもしれない、という想像力を、一人ひとりが持つことなんだよな。カミングアウトする/しないは当人の自由だし、勇気=絶対ではない。いろんな生き方があるけれど、それを否定したり貶めたりすることは誰にもできない、その人だけの生き方だ。 上に「シンパシー」と書いたが、この場合必要になるのは「エンパシー」なんだろう。もちろんまったく同じ人間ではないから、想像しても分からないことだってあるとは思う。完全に理解するのも、それはそれで難しい。 でもだからこそ、暴言や暴力に頼るのではなく、対話して、ちょっとでも相手の意志を尊重しようとする力が大切になってくる。といってもそれはまさにマジョリティ側の問題であって、マイノリティにこれ以上マジョリティの前提を押し付けるのも違うと思うけれど。 大半の人は、マジョリティ性とマイノリティ性のどちらも併せ持つ。その中で、他者の痛みや苦しみから目を逸らさず、自身の立場を見つめて、何ができるのか模索していくしかないんじゃないだろうか。時間がかかるし、めんどくさいことだってあるけれど、きっとそれしかない。 排外主義は手っ取り早いが、何もかもを失うハメになるし、何も解決しない。 それに対抗するためのエンパシーを、僕も持って生きていきたい。 - 2025年6月15日
 ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 宇宙科学雑誌Newton読み終わった近年世界各地で起きている自然現象や災害などを見ていると、自然、ひいては地球への畏怖を感じる。 けれど、その地球も莫大なエネルギーを持つ太陽の威力には敵わないし、さらに太陽も天の川銀河の中で見ると一つの恒星にすぎない。 そして天の川銀河も、宇宙の中では数ある銀河のうちの一つで、その宇宙さえも、外側にまた別の宇宙が存在している(マルチバース)かもしれなくて……。 ここまで壮大だと、もはや畏怖を通り越してただただ呆然としてしまう。 138億年という悠久の時を刻む、そんな宇宙だけれど、生まれた瞬間は原子よりも小さかった。 そこから1秒の1兆分の1の、1兆分の1の、さらに1兆分の1ほどの間に、1兆の1兆倍の、1兆倍の、さらに1000万倍の大きさになった……らしい。 この急激な膨張「インフレーション」が、特に衝撃的だった。
ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 宇宙科学雑誌Newton読み終わった近年世界各地で起きている自然現象や災害などを見ていると、自然、ひいては地球への畏怖を感じる。 けれど、その地球も莫大なエネルギーを持つ太陽の威力には敵わないし、さらに太陽も天の川銀河の中で見ると一つの恒星にすぎない。 そして天の川銀河も、宇宙の中では数ある銀河のうちの一つで、その宇宙さえも、外側にまた別の宇宙が存在している(マルチバース)かもしれなくて……。 ここまで壮大だと、もはや畏怖を通り越してただただ呆然としてしまう。 138億年という悠久の時を刻む、そんな宇宙だけれど、生まれた瞬間は原子よりも小さかった。 そこから1秒の1兆分の1の、1兆分の1の、さらに1兆分の1ほどの間に、1兆の1兆倍の、1兆倍の、さらに1000万倍の大きさになった……らしい。 この急激な膨張「インフレーション」が、特に衝撃的だった。
読み込み中...



