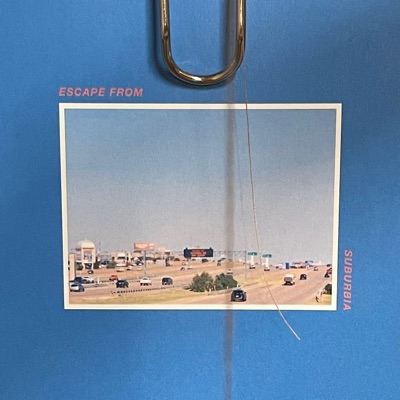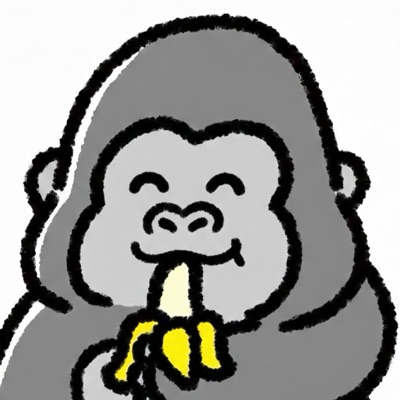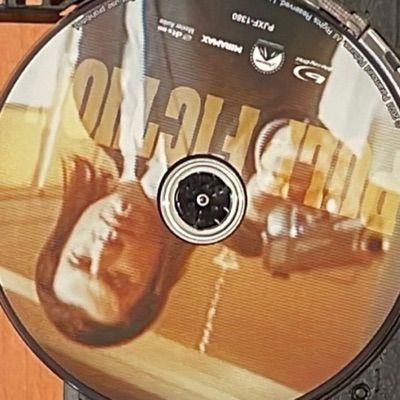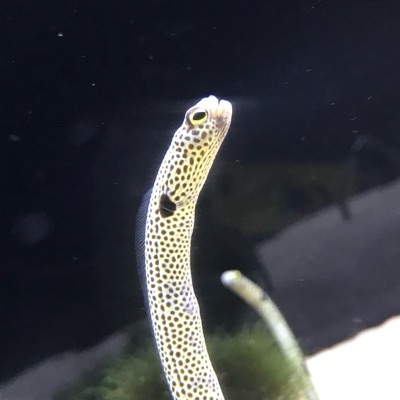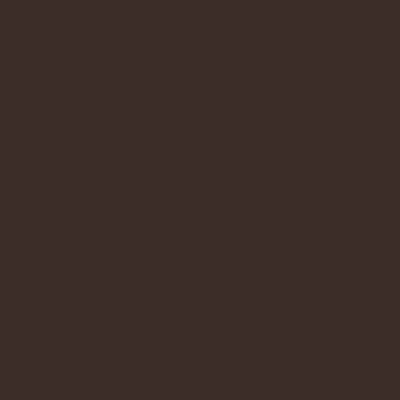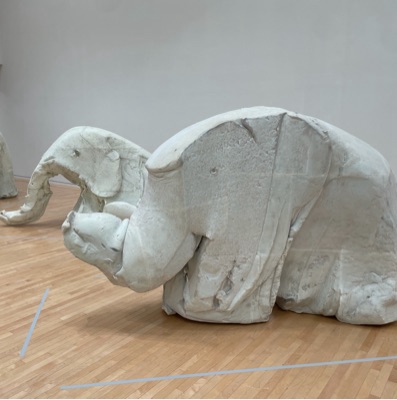異邦人

131件の記録
- はる@HALRUNMAN2026年2月21日読み終わった気になったまま、勢いで読み終えた。 もともとカフカ由来の「不条理」が好きで、より定義を深めるためその関連に触れた 不条理を認識して、真っ向から立ち向かう雰囲気と、普段個人的に感じてる人生の意味、その解釈がリンクしてて興奮した
 Chihiro@chiii_no02026年2月18日読み終わった異邦人の内容、アラブ人を殺した主人公ムルソーが裁判で死刑を宣告される話 自身の母親の死への向き合い方やアラブ人の殺害動機がいわゆる世間一般の人々からは共感され得ないもの 主人公は人間社会には適応できない存在でありながら、その「冷酷さ」(と表現されるであろう要素)はもしかしたら現代の我々にとっては少し分かる部分があるのではないか 人に寄り添わず対話をすることが面倒になる、生きようとする姿勢を感じず、いつの間にかなんか死んでましたってなってても不思議じゃない男であるばかりでなく、太陽の下でアラブ人を殺害する場面、独房を訪れた司祭との対話(最終的にムルソーの叫びに繋がる)、死刑判決をされた時の三つの箇所では強烈に生を感じたりもした にしてもこういった無神論者であり現実主義的思想の男は女を人間ならざるもの、ある種神のような存在にしがち
Chihiro@chiii_no02026年2月18日読み終わった異邦人の内容、アラブ人を殺した主人公ムルソーが裁判で死刑を宣告される話 自身の母親の死への向き合い方やアラブ人の殺害動機がいわゆる世間一般の人々からは共感され得ないもの 主人公は人間社会には適応できない存在でありながら、その「冷酷さ」(と表現されるであろう要素)はもしかしたら現代の我々にとっては少し分かる部分があるのではないか 人に寄り添わず対話をすることが面倒になる、生きようとする姿勢を感じず、いつの間にかなんか死んでましたってなってても不思議じゃない男であるばかりでなく、太陽の下でアラブ人を殺害する場面、独房を訪れた司祭との対話(最終的にムルソーの叫びに繋がる)、死刑判決をされた時の三つの箇所では強烈に生を感じたりもした にしてもこういった無神論者であり現実主義的思想の男は女を人間ならざるもの、ある種神のような存在にしがち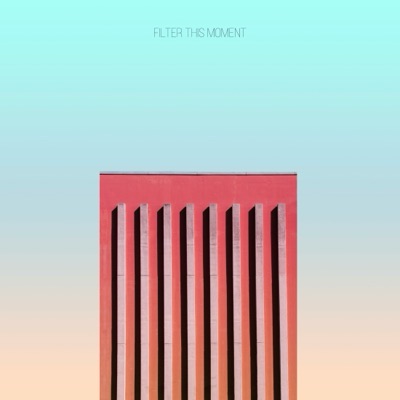 Okada@tokdtr2026年1月28日読み終わった読者が名作だと評価しても作家自身は名作だと思ってないということはありえる。多分に実験的要素を含む作品を描くのがすきで、評価を考えず自分の美意識に従って書いた その姿勢がムルソーを産んだのだと思う。世界に対するカミュの善意の表現だと捉えられる。 サルトルがカミュを「世界の不条理を描くが、そこから倫理も実践も導かない」と批判していたようだ。 カミュは倫理も実践も導かないことに価値を見出していたように思える。そういう作品だからこそ宿る芸術性があると思う。 殺人を太陽のせいとした点について非論理的で理解できず、面白くないと思った。しかし読後しばらくして上記の感想に至った。
Okada@tokdtr2026年1月28日読み終わった読者が名作だと評価しても作家自身は名作だと思ってないということはありえる。多分に実験的要素を含む作品を描くのがすきで、評価を考えず自分の美意識に従って書いた その姿勢がムルソーを産んだのだと思う。世界に対するカミュの善意の表現だと捉えられる。 サルトルがカミュを「世界の不条理を描くが、そこから倫理も実践も導かない」と批判していたようだ。 カミュは倫理も実践も導かないことに価値を見出していたように思える。そういう作品だからこそ宿る芸術性があると思う。 殺人を太陽のせいとした点について非論理的で理解できず、面白くないと思った。しかし読後しばらくして上記の感想に至った。

- junna@_book2026年1月25日読み終わった物語はムルソーの一人称で語られている。 彼は単に「自分に正直すぎる人」だと思った。 私が結末を知らずに読み進めたこともあり、 裁判の中で人間性を否定されてはいるものの、 事件自体は計画性のある残忍なものというよりかは正当防衛に近いものに思え、 (当時のフランス/アルジェリアの死刑の基準は知らないものの)極刑が言い渡されることになるとはまさか思わなかった。 判決を言い渡される時の「フランス人民の名において広場で斬首刑をうけるのだ」というセリフが非常に印象的だった。 当時の世界は、現代と比べて、典型的な感情表現をしない人を許さない世界だったのかもしれないなと思った。 自分含め世間の人は取り繕って表には出さなくても、ムルソーの正直な感覚に共感できる箇所もあると思う。

 しんどうこころ@and_gt_pf2026年1月19日読み終わった海外文学文学の素晴らしさを改めて確認させられる傑作だった。 読後、衝撃のあまりしばらく動けなくなった。 主人公の無関心と淡白な文体が生むひやりとした空気に対し、世界はまばゆく、熱く、過剰なほどに存在している。 冷たいのは人間であり、世界ではない。 前半の感覚的な日常と、後半の言葉による非日常の落差も見事。 本作は決して「感情欠如の男の末路」を悲しく描いた物語ではなく、意味づけを拒否した人間と世界とがどう反応しあうかを描いた誠実な作品だと感じた。 カミュは主人公を通じて世界の無意味性を提示し、その無意味性を正面から引き受けて生きる人間が、社会にとっていかに危険な存在になるかを描きたかったのだと思う。 読者の温度を下げるような淡々とした文体と一級品の情景描写もとても美しい。
しんどうこころ@and_gt_pf2026年1月19日読み終わった海外文学文学の素晴らしさを改めて確認させられる傑作だった。 読後、衝撃のあまりしばらく動けなくなった。 主人公の無関心と淡白な文体が生むひやりとした空気に対し、世界はまばゆく、熱く、過剰なほどに存在している。 冷たいのは人間であり、世界ではない。 前半の感覚的な日常と、後半の言葉による非日常の落差も見事。 本作は決して「感情欠如の男の末路」を悲しく描いた物語ではなく、意味づけを拒否した人間と世界とがどう反応しあうかを描いた誠実な作品だと感じた。 カミュは主人公を通じて世界の無意味性を提示し、その無意味性を正面から引き受けて生きる人間が、社会にとっていかに危険な存在になるかを描きたかったのだと思う。 読者の温度を下げるような淡々とした文体と一級品の情景描写もとても美しい。

 藍@ai_uesugi1172026年1月18日読み終わったあらすじを知っていながら未読だった作品。 やはり、嘘をついてまでして、他人や社会との繋がりを求めたくはないなと思いました。今の自分では読み解けない部分もあったので、時間をおいて再読したいですね。
藍@ai_uesugi1172026年1月18日読み終わったあらすじを知っていながら未読だった作品。 やはり、嘘をついてまでして、他人や社会との繋がりを求めたくはないなと思いました。今の自分では読み解けない部分もあったので、時間をおいて再読したいですね。 さち@chiisaxlog2026年1月15日読み終わったムルソーと自分には似ているところがあるような、ないような… 読み終えたあとも、ムルソーはどんな人間なのか?とページをめくりながらぐるぐる考える。 ムルソーはママンの埋葬のときの看護婦の言葉を聞き、「逃げ道はないのだ。」と思い、その言葉を獄中でも思い出す。これがムルソーの人生の捉え方なのかな、だから、自分の周辺で起きたらことや自分が起こしてしまったことを淡々と受け入れていて、傍から見たら無関心や無感動な人間に思えるんだろうか… カミュを読むのが初めてというのもあってか、とても難しかった。 他の作品も読んでみたい…!
さち@chiisaxlog2026年1月15日読み終わったムルソーと自分には似ているところがあるような、ないような… 読み終えたあとも、ムルソーはどんな人間なのか?とページをめくりながらぐるぐる考える。 ムルソーはママンの埋葬のときの看護婦の言葉を聞き、「逃げ道はないのだ。」と思い、その言葉を獄中でも思い出す。これがムルソーの人生の捉え方なのかな、だから、自分の周辺で起きたらことや自分が起こしてしまったことを淡々と受け入れていて、傍から見たら無関心や無感動な人間に思えるんだろうか… カミュを読むのが初めてというのもあってか、とても難しかった。 他の作品も読んでみたい…! ツナサンド@mor_1024302026年1月7日読み終わったおもしろかった(ᐢᴖ ·̫ ᴖᐢ) 「健康な人は誰でも、多少とも、愛する人の死を期待するものだ。」←超わかる 愛とか、かなしみとか、生きるうえで他者と擦り合わせなければならない一般的な感情の意味づけを怠った結果として死んだわけだから、ムルソーはただ単に怠惰な人として映った。 飾らず自然体で、無感動サイコを隠さずとも少なくない人に好かれて生きてこられたその幸運を祝いながら死になさいよと思った。
ツナサンド@mor_1024302026年1月7日読み終わったおもしろかった(ᐢᴖ ·̫ ᴖᐢ) 「健康な人は誰でも、多少とも、愛する人の死を期待するものだ。」←超わかる 愛とか、かなしみとか、生きるうえで他者と擦り合わせなければならない一般的な感情の意味づけを怠った結果として死んだわけだから、ムルソーはただ単に怠惰な人として映った。 飾らず自然体で、無感動サイコを隠さずとも少なくない人に好かれて生きてこられたその幸運を祝いながら死になさいよと思った。 ノエタロス@Di_Noel022025年11月19日読み終わった不条理小説として有名だが、個人的には悲しさや苦悩、絶望といったデカい負の感情が、不思議とそこまで感じられない終わり方だった。 あらすじだけ見ると衝撃的な話だが、文章としては淡々と、すっきりとしているし、どこか客観的で落ち着いた一人称視点*も、ショックを抑えている気がする。 面白いと思ったのが、主人公ムルソーの名は、「死」と「太陽」の合成語らしい。 結果的に最後は死刑にされるが、ムルソーとしては一貫して「嘘をつかなかった」だけ。 太陽の眩しさに目を奪われ、その光とともに不幸の闇の中に落とされてしまったけど、彼は死の瞬間までその光を手放さなかった。 この世界では「異邦人」とみなされながら、それでも自分の心を偽らなかった。 その結末に、絶望というより、いやむしろ絶望ではなく、彼の胸の内の強い輝きを見た気がした。 *→ただ、死刑を宣告された後、訪ねてきた司祭に己の死を憐れまれて、ムルソーは作中で初めて感情を爆発させる。 読んだ人の多くはそうだと思うが、もうそこでぐっとムルソーの魅力に惹き込まれた。
ノエタロス@Di_Noel022025年11月19日読み終わった不条理小説として有名だが、個人的には悲しさや苦悩、絶望といったデカい負の感情が、不思議とそこまで感じられない終わり方だった。 あらすじだけ見ると衝撃的な話だが、文章としては淡々と、すっきりとしているし、どこか客観的で落ち着いた一人称視点*も、ショックを抑えている気がする。 面白いと思ったのが、主人公ムルソーの名は、「死」と「太陽」の合成語らしい。 結果的に最後は死刑にされるが、ムルソーとしては一貫して「嘘をつかなかった」だけ。 太陽の眩しさに目を奪われ、その光とともに不幸の闇の中に落とされてしまったけど、彼は死の瞬間までその光を手放さなかった。 この世界では「異邦人」とみなされながら、それでも自分の心を偽らなかった。 その結末に、絶望というより、いやむしろ絶望ではなく、彼の胸の内の強い輝きを見た気がした。 *→ただ、死刑を宣告された後、訪ねてきた司祭に己の死を憐れまれて、ムルソーは作中で初めて感情を爆発させる。 読んだ人の多くはそうだと思うが、もうそこでぐっとムルソーの魅力に惹き込まれた。





 コサカダイキ@daiki_kosaka2025年11月19日読み終わったカミュの『異邦人』を読んでいて、一部で心が折れそうになった。笑 夢を観ているような世界観で、全くもって話が入ってこない。どこかで回収されるに違いないと思いながらも一向にそれが見えないから純粋に文体が合わないのかもと思ったが、やはり二部に入った途端ちゃんと読めるようになっていた。 我慢して読んでてよかった。笑 文学に触れることで抽象というものがどういうもので、どう面白いのか、どうすれば面白いと伝えられるのかってことがすごく明確になって良い。それが全て絵だけでできれば良いけれど、こうして他のものから構造を理解するのもアリだ。 カフカの『変身』、カミュの『異邦人』はまさにそんな構造。
コサカダイキ@daiki_kosaka2025年11月19日読み終わったカミュの『異邦人』を読んでいて、一部で心が折れそうになった。笑 夢を観ているような世界観で、全くもって話が入ってこない。どこかで回収されるに違いないと思いながらも一向にそれが見えないから純粋に文体が合わないのかもと思ったが、やはり二部に入った途端ちゃんと読めるようになっていた。 我慢して読んでてよかった。笑 文学に触れることで抽象というものがどういうもので、どう面白いのか、どうすれば面白いと伝えられるのかってことがすごく明確になって良い。それが全て絵だけでできれば良いけれど、こうして他のものから構造を理解するのもアリだ。 カフカの『変身』、カミュの『異邦人』はまさにそんな構造。 やえしたみえ@mie_e01252025年11月7日読み終わった@ 自宅一人称なのに他人事のような、でも一部は実感を伴ってる絶妙な浮遊感が、離人感が強い時の私すぎて、読んでると解離が悪化しそうで癖になる。 そもそも文章が本当に美しい。海外小説、翻訳文体大好き。 夜職の手口はいつの時代も変わらなくてウケる。りりちゃんは異邦人を参考にしてる可能性がある
やえしたみえ@mie_e01252025年11月7日読み終わった@ 自宅一人称なのに他人事のような、でも一部は実感を伴ってる絶妙な浮遊感が、離人感が強い時の私すぎて、読んでると解離が悪化しそうで癖になる。 そもそも文章が本当に美しい。海外小説、翻訳文体大好き。 夜職の手口はいつの時代も変わらなくてウケる。りりちゃんは異邦人を参考にしてる可能性がある 絵美子@835emiko2025年10月29日読み終わったじゅうぶん読んだムルソーの無関心、無感動を信じられない、とか人でなしだと思う民は息巻いて饒舌だった検事の方が共感できるのか、それは特にべつにどちらでも良いけど最後の司祭のすべての動作と台詞にはとにかく早く部屋から出て言って欲しい気持ちでいっぱいになりラストは息継ぎなしで風が吹いてゆき本当のことは口に出すと本当になりすぎると思った、みじかい小説だけど最後の3ページのためだけのこれまででした、という感じ(自分のもたぶん含められている) こんな超季節の変わり目で自律神経乱れがちな時期に読むものではないでしょうよと思いながらべつに春の麗らかな夜だって夏だって真冬だって変わらず読み返すでしょうよべつに特にべつにって話、アー
絵美子@835emiko2025年10月29日読み終わったじゅうぶん読んだムルソーの無関心、無感動を信じられない、とか人でなしだと思う民は息巻いて饒舌だった検事の方が共感できるのか、それは特にべつにどちらでも良いけど最後の司祭のすべての動作と台詞にはとにかく早く部屋から出て言って欲しい気持ちでいっぱいになりラストは息継ぎなしで風が吹いてゆき本当のことは口に出すと本当になりすぎると思った、みじかい小説だけど最後の3ページのためだけのこれまででした、という感じ(自分のもたぶん含められている) こんな超季節の変わり目で自律神経乱れがちな時期に読むものではないでしょうよと思いながらべつに春の麗らかな夜だって夏だって真冬だって変わらず読み返すでしょうよべつに特にべつにって話、アー
 モノンクル@mononcle2025年9月12日読み終わった@ 自宅読書会の課題本として読みました。 変わった人(異邦人)ムルソーを主人公にした小説で、ムルソー自身としては自分に正直に生きようとしているだけなのに、周囲には理解されず、思いがけず(太陽のせいで?)殺人まで犯してしまい、裁判で死刑を求刑されて悩み苦しみ(でもそれすら共感も理解もされず)、最期は死を待ち望む。本当はこの小説が書かれた時代背景と併せてでないと理解しがたい小説であるかもしれません。(第二次世界大戦開戦前夜に書かれています)
モノンクル@mononcle2025年9月12日読み終わった@ 自宅読書会の課題本として読みました。 変わった人(異邦人)ムルソーを主人公にした小説で、ムルソー自身としては自分に正直に生きようとしているだけなのに、周囲には理解されず、思いがけず(太陽のせいで?)殺人まで犯してしまい、裁判で死刑を求刑されて悩み苦しみ(でもそれすら共感も理解もされず)、最期は死を待ち望む。本当はこの小説が書かれた時代背景と併せてでないと理解しがたい小説であるかもしれません。(第二次世界大戦開戦前夜に書かれています)

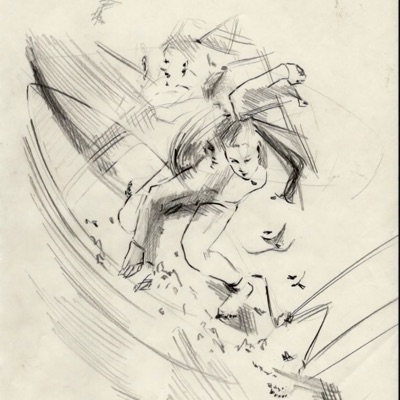 自分@Me_me2025年9月11日読み終わった肌寒い湿気た風に、ほんの少しの塩の匂い。『異邦人』を読んでまず思い浮かんだのは、そんな感触だった。乾いているのに湿っている。心地よさと不快さが同居する、矛盾した空気。その風の中でページをめくっているような読書体験だった。 主人公ムルソーは、無関心な人間に見える。母の死に涙せず、恋人に愛を告げられても「意味がない」と答え、人を撃った理由さえ「太陽のせい」だと言う。 けれど本当にそうなのだろうか。むしろ彼は、蝶の羽をむしり取ってしまう子供のように、残酷なほど純粋で、眩しいほど素直な心を持っているだけなのかもしれない。飾らず、気取らない。彼はただ、世界をそのまま受け入れているのだ。 だが社会はそれを許さない。裁判で裁かれたのは殺人そのものより、「母の死に涙しなかったこと」だった。常識や道徳という名の荒波が彼を押し流そうとする。その姿に私はぞっとした。そして、なぜか少しほっともした。 なぜなら最後にムルソーは、「世界のやさしい無関心を受け入れる」と語るからだ。そこにあったのは絶望ではなく、静かな救いだった。意味なんてなくてもいい。ただ海辺に立ち、潮風を浴びながら呼吸している。それだけで十分なのだと教えられた気がした。
自分@Me_me2025年9月11日読み終わった肌寒い湿気た風に、ほんの少しの塩の匂い。『異邦人』を読んでまず思い浮かんだのは、そんな感触だった。乾いているのに湿っている。心地よさと不快さが同居する、矛盾した空気。その風の中でページをめくっているような読書体験だった。 主人公ムルソーは、無関心な人間に見える。母の死に涙せず、恋人に愛を告げられても「意味がない」と答え、人を撃った理由さえ「太陽のせい」だと言う。 けれど本当にそうなのだろうか。むしろ彼は、蝶の羽をむしり取ってしまう子供のように、残酷なほど純粋で、眩しいほど素直な心を持っているだけなのかもしれない。飾らず、気取らない。彼はただ、世界をそのまま受け入れているのだ。 だが社会はそれを許さない。裁判で裁かれたのは殺人そのものより、「母の死に涙しなかったこと」だった。常識や道徳という名の荒波が彼を押し流そうとする。その姿に私はぞっとした。そして、なぜか少しほっともした。 なぜなら最後にムルソーは、「世界のやさしい無関心を受け入れる」と語るからだ。そこにあったのは絶望ではなく、静かな救いだった。意味なんてなくてもいい。ただ海辺に立ち、潮風を浴びながら呼吸している。それだけで十分なのだと教えられた気がした。- 本の虫になりたいひと@reaaaads38692025年9月3日読み終わったあらすじがこの本を異質なものに仕立て上げているような気がする。まるで主人公が完全なる精神疾患患者のような書き方である。あとがきにもあったが主人公は嘘がつけないだけ。人殺しはダメだがそれ以降の対応を全て「助かりたいならこっち!」と正反対のアンサーしたから、こんな結果になった。それを一部の人は精神疾患患者であるというのかもしれないけれど。 「太陽のせいだ」と言ったのも弁明の最後の方、しどろもどろになりながらじゃないか。まるであっけからんといったみたいなあらすじの書き方は本当に良くない。
- 北奏館@hokusoh2025年8月31日読み終わったカメル・ダウドのHourisゴングール賞受賞の記事から「ムルソー」を知って、遡って読んでみようと思い立った。よく考えたら読んでなかった(名著あるある)。 いざ読んでみると、よくある作品紹介は当てにならないものだなあと。やっぱり自分で読んでみないとわからないし、同じ作品でも読む人によって何が響くかは全然違うんだろうなという作品だった。少なくとも私には、殺人の動機としてよく引用される「太陽が眩しかったから」っていうのはあまり重要じゃなかった。 忘れないうちに「ムルソー」読みたい。


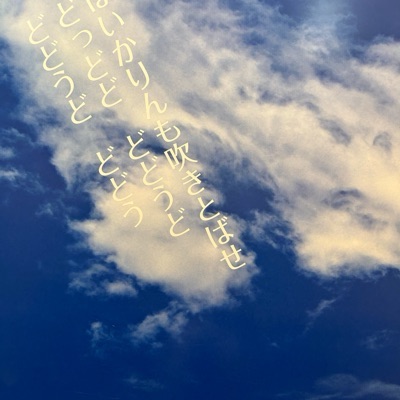
 ポン@c_f_zqxs2025年8月5日かつて読んだ感想序盤を読み進める中で、一人称視点でありながら主人公の感情描写がやけに淡白なのが気になった。中盤以降、やっぱり外の世界から見ても異常に映っていたようで、主人公は人々から糾弾され始める。でも私は、ムルソーの自分と世界に対する正直さが一貫してるとこかなり好き。ある種の爽快感がある。カミュの思想がもっと気になる作品。
ポン@c_f_zqxs2025年8月5日かつて読んだ感想序盤を読み進める中で、一人称視点でありながら主人公の感情描写がやけに淡白なのが気になった。中盤以降、やっぱり外の世界から見ても異常に映っていたようで、主人公は人々から糾弾され始める。でも私は、ムルソーの自分と世界に対する正直さが一貫してるとこかなり好き。ある種の爽快感がある。カミュの思想がもっと気になる作品。



 N@r_is_for_read2025年7月15日多分私には合わなかったのだと思うが、話の内容が中々頭に入ってこず、読むのに苦労した。 ムルソーの思考もよく分からず。 こういった名作は私にとっては難しいらしい。
N@r_is_for_read2025年7月15日多分私には合わなかったのだと思うが、話の内容が中々頭に入ってこず、読むのに苦労した。 ムルソーの思考もよく分からず。 こういった名作は私にとっては難しいらしい。
 momo(プロフィール変えました)@momo_noke2025年5月31日読み終わった主人公ムルソーが人を殺した理由を「太陽のせい」とする点は、全く理解できない。 しかし、彼は、自分が人を愛せないとか、母親が死んでも動揺しないといった感情の欠如を、偽らずに受け入れているように見えた。 社会的なルールや善意を身につけず、「こう思うべき」とされることにも従わない。 形式を拒否して、自分の感覚だけで生きようとする姿勢に、ある意味での誠実さも感じた。 不条理な世界で、自分に嘘をつかずに生きることの難しさと孤独を考えた。
momo(プロフィール変えました)@momo_noke2025年5月31日読み終わった主人公ムルソーが人を殺した理由を「太陽のせい」とする点は、全く理解できない。 しかし、彼は、自分が人を愛せないとか、母親が死んでも動揺しないといった感情の欠如を、偽らずに受け入れているように見えた。 社会的なルールや善意を身につけず、「こう思うべき」とされることにも従わない。 形式を拒否して、自分の感覚だけで生きようとする姿勢に、ある意味での誠実さも感じた。 不条理な世界で、自分に嘘をつかずに生きることの難しさと孤独を考えた。




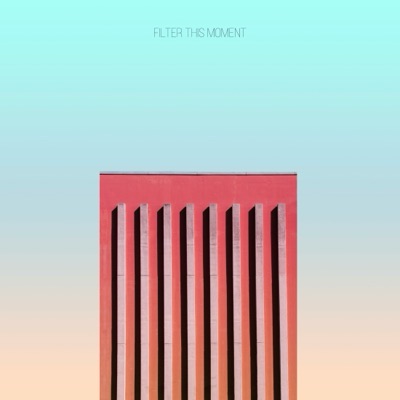
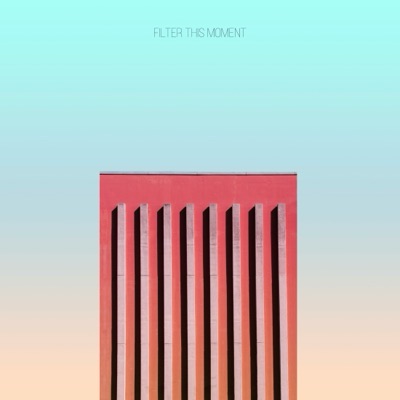
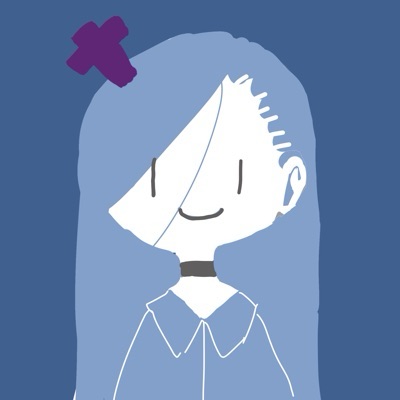 💊@Cannabi_Shabu2025年5月29日読み終わったさすが名作👍👍👍 主人公のムルソーを、最初は変人程度に思っていて、しかし結婚したがっているマリィへの返事のシーンから、彼のことが大好きになってしまいました。 この変人具合が"異邦人"なのかと思っていたら、本当にどんどん"異邦人"になってしまって、私の想像の及ばないところまで行ってしまった、、、 生きるということに関して、私はつい精神に重きを置いてしまいがちです(これは悪い思考の癖なのですが……)。 しかし彼はどこまでも現実や感覚に重きを置いていて、それが彼の生命に直結している。そして最後はあの部屋の中で、今まで愛してきたこの世界を愛し直すことである種の悟りを得たのではないか。 物質主義になってしまった現代人が、自らの死に向き合って生を愛するには、ムルソーのような過程を辿るのではないかと思わずにはいられません。 最後の一文はイエスキリストの最期を想起させました。また解説を読んでさらに好きになった小説でもあります。 この文庫本自体を買ったのは中学生のときでしたが、今読もうと思った不思議な縁に感謝します。
💊@Cannabi_Shabu2025年5月29日読み終わったさすが名作👍👍👍 主人公のムルソーを、最初は変人程度に思っていて、しかし結婚したがっているマリィへの返事のシーンから、彼のことが大好きになってしまいました。 この変人具合が"異邦人"なのかと思っていたら、本当にどんどん"異邦人"になってしまって、私の想像の及ばないところまで行ってしまった、、、 生きるということに関して、私はつい精神に重きを置いてしまいがちです(これは悪い思考の癖なのですが……)。 しかし彼はどこまでも現実や感覚に重きを置いていて、それが彼の生命に直結している。そして最後はあの部屋の中で、今まで愛してきたこの世界を愛し直すことである種の悟りを得たのではないか。 物質主義になってしまった現代人が、自らの死に向き合って生を愛するには、ムルソーのような過程を辿るのではないかと思わずにはいられません。 最後の一文はイエスキリストの最期を想起させました。また解説を読んでさらに好きになった小説でもあります。 この文庫本自体を買ったのは中学生のときでしたが、今読もうと思った不思議な縁に感謝します。 CandidE@candide_jp2025年3月23日読み終わった何度読んでも、構造的破綻があるように思う。決定的なのは、主人公ムルソーが殺人を犯すことで、自身が「他者にとっての不条理」と化すこと。これにより彼は理不尽な世界と同期してしまい、そのため終盤における「理不尽への反抗」という覚醒は、滑稽な自己矛盾でしかない。不条理が不条理に対して反抗するという無意味な構図を不条理とするのは詭弁であり、実態は、目糞鼻糞を笑う、である。 またさらに看過できないのは、主人公が示す社会規範の恣意性への理解や判断の一貫性の欠如の認識といった知的側面と、身体欲求への愚直な隷属や衝動的行動といった動物的側面との間に横たわる不自然な観念の乖離。人工味がして読みにくい。作家が人間存在の矛盾や二面性を描こうと意図したことは十分に承知しているが、そのキャラクター設定が歪で、デフォルメが鼻につく。企みはともかく、この作為的な矛盾や綻びは、おそらく原文の文体がない文体、すなわち「零度のエクリチュール」によって巧みに糊塗されコーティングされ、それは結果として作品の評価を支えるアイロニカルな魅力となり、作者のノーベル文学賞受賞と相まって好意的に解釈され続け、今日に至っているのだろうと推察する。 ロラン・バルトは「この不整合は作品の一部」と評価したが、対してサルトルは「主人公は自分自身の行動の哲学的意味を理解していない」と喝破した。この批評的対立において、私はサルトルに軍配を上げたい。芸術における構造的矛盾が常に欠陥とはなり得ないのは明白だが、上記の通り私は『異邦人』においてその説得力の欠如を指摘する。 一方で、不条理を「克服すべき課題」とするサルトルと「共生すべき条件」とするカミュという両者の哲学的姿勢について、私は断然カミュに共鳴する。それは、誤解を恐れずに言えば、日々不確実性が増す現代社会において、「不条理との終わりなき闘争」は消極的共存であり、「不条理との持続的対話」こそが積極的共存、すなわち我々の基本倫理に相応しいと愚考するからだ。この非常に困難な挑戦に際して、カミュの「反抗」こそが心の燈となる。 なお、本作の理解を深めるために、同時期に出版された『シーシュポスの神話』を併読することを強く推奨したい。これにより、カミュの哲学および『異邦人』の制作意図や背景が補完され、たとえ私のような批判的な意見を持つ偏屈者や内容に面白味を感じなかった読者においても、その文学的価値と魅力がより明瞭な形で伝わるはずだ。
CandidE@candide_jp2025年3月23日読み終わった何度読んでも、構造的破綻があるように思う。決定的なのは、主人公ムルソーが殺人を犯すことで、自身が「他者にとっての不条理」と化すこと。これにより彼は理不尽な世界と同期してしまい、そのため終盤における「理不尽への反抗」という覚醒は、滑稽な自己矛盾でしかない。不条理が不条理に対して反抗するという無意味な構図を不条理とするのは詭弁であり、実態は、目糞鼻糞を笑う、である。 またさらに看過できないのは、主人公が示す社会規範の恣意性への理解や判断の一貫性の欠如の認識といった知的側面と、身体欲求への愚直な隷属や衝動的行動といった動物的側面との間に横たわる不自然な観念の乖離。人工味がして読みにくい。作家が人間存在の矛盾や二面性を描こうと意図したことは十分に承知しているが、そのキャラクター設定が歪で、デフォルメが鼻につく。企みはともかく、この作為的な矛盾や綻びは、おそらく原文の文体がない文体、すなわち「零度のエクリチュール」によって巧みに糊塗されコーティングされ、それは結果として作品の評価を支えるアイロニカルな魅力となり、作者のノーベル文学賞受賞と相まって好意的に解釈され続け、今日に至っているのだろうと推察する。 ロラン・バルトは「この不整合は作品の一部」と評価したが、対してサルトルは「主人公は自分自身の行動の哲学的意味を理解していない」と喝破した。この批評的対立において、私はサルトルに軍配を上げたい。芸術における構造的矛盾が常に欠陥とはなり得ないのは明白だが、上記の通り私は『異邦人』においてその説得力の欠如を指摘する。 一方で、不条理を「克服すべき課題」とするサルトルと「共生すべき条件」とするカミュという両者の哲学的姿勢について、私は断然カミュに共鳴する。それは、誤解を恐れずに言えば、日々不確実性が増す現代社会において、「不条理との終わりなき闘争」は消極的共存であり、「不条理との持続的対話」こそが積極的共存、すなわち我々の基本倫理に相応しいと愚考するからだ。この非常に困難な挑戦に際して、カミュの「反抗」こそが心の燈となる。 なお、本作の理解を深めるために、同時期に出版された『シーシュポスの神話』を併読することを強く推奨したい。これにより、カミュの哲学および『異邦人』の制作意図や背景が補完され、たとえ私のような批判的な意見を持つ偏屈者や内容に面白味を感じなかった読者においても、その文学的価値と魅力がより明瞭な形で伝わるはずだ。- こよなく@funyoi2025年3月9日読み終わった自分に嘘をつかない行為が正しい生き方だから、その結果が処刑でも正しい結果ってなるの!?誠実だし異邦人だわ! 「私ははじめて、世界の優しい無関心に、心をひらいた。」お気に入りの一文。
 O@46_962025年3月8日読み終わった言葉にするのが難しくて、読了後しばらくそのままにしておいた。 今もまだわかっていないところが多い。けれど、ムルソーのこと嫌いじゃない。それは登場する判事や司祭の信仰を鬱陶しく感じる——私がキリシタンじゃないから——ことによって相対的に、というのもあるかもしれない。 ただ、それとはまた別に、私がムルソーだったかもしれないことを思う。あの法廷に立っていたのは、もしかすると私だったのかもしれない、といった風に。想像せざるを得ない。
O@46_962025年3月8日読み終わった言葉にするのが難しくて、読了後しばらくそのままにしておいた。 今もまだわかっていないところが多い。けれど、ムルソーのこと嫌いじゃない。それは登場する判事や司祭の信仰を鬱陶しく感じる——私がキリシタンじゃないから——ことによって相対的に、というのもあるかもしれない。 ただ、それとはまた別に、私がムルソーだったかもしれないことを思う。あの法廷に立っていたのは、もしかすると私だったのかもしれない、といった風に。想像せざるを得ない。


 ayk@aybooks2020年7月13日買った読み終わった感想読書日記主人公ムルソーが自らを語るストーリーでありながら、終始傍観者のような口調で進む異質さ。 近しい誰かを失った時に、必ず涙を流さなくてはいけないのか?、悲しいですと言わなくてはならないのか?、映画を見て笑い転げることは不謹慎なのか?、感情を社会に合わせるべきか、これらをムルソーは偽らない。 "不謹慎狩り" 感情は人それぞれだから、「こう思うのが正しい。こう感じない奴は異常だ。」は、社会の「不条理」なのだろう。
ayk@aybooks2020年7月13日買った読み終わった感想読書日記主人公ムルソーが自らを語るストーリーでありながら、終始傍観者のような口調で進む異質さ。 近しい誰かを失った時に、必ず涙を流さなくてはいけないのか?、悲しいですと言わなくてはならないのか?、映画を見て笑い転げることは不謹慎なのか?、感情を社会に合わせるべきか、これらをムルソーは偽らない。 "不謹慎狩り" 感情は人それぞれだから、「こう思うのが正しい。こう感じない奴は異常だ。」は、社会の「不条理」なのだろう。 央河純@qxll051900年1月1日かつて読んだムルソーは状態を理解しない。いい人だから、いい行いをする構図を見ない。いい行いをするから、いい人なのであってその逆ではない。だから、太陽が眩しかったからに論理はない。視点が違うだけで、社会はこんなにも苦しく見える
央河純@qxll051900年1月1日かつて読んだムルソーは状態を理解しない。いい人だから、いい行いをする構図を見ない。いい行いをするから、いい人なのであってその逆ではない。だから、太陽が眩しかったからに論理はない。視点が違うだけで、社会はこんなにも苦しく見える