

はるにれ
@Elms1130
- 2025年7月6日
 ハーレムの闘う本屋ヴォーンダ・ミショー・ネルソン読み終わった読書メモ図書館本マルコムXも頻繁に訪れたというニューヨーク・ハーレムの伝説の本屋。際どい仕事の経験もして、店主ルイスが店を始めたのは40代半ばになってから。世の中、若いうちに打ち込めることが見つけられる人ばかりじゃない。彼を取り巻く人たちの証言や書類・写真をコラージュ風にまとめてあり、公民権運動前後のハーレムの様子を構えずに知ることができる。 彼の本屋が若者たちに知識と夢を与えていたから当然だけど、アフリカ系アメリカ人指導者たちの暗殺など重苦しい事件を経てもなお、力強く歩んでいく人たちが描かれていて、いい終わり方だと思ったら、ヤングアダルト向けの本だった。こういう本も悪くないな。
ハーレムの闘う本屋ヴォーンダ・ミショー・ネルソン読み終わった読書メモ図書館本マルコムXも頻繁に訪れたというニューヨーク・ハーレムの伝説の本屋。際どい仕事の経験もして、店主ルイスが店を始めたのは40代半ばになってから。世の中、若いうちに打ち込めることが見つけられる人ばかりじゃない。彼を取り巻く人たちの証言や書類・写真をコラージュ風にまとめてあり、公民権運動前後のハーレムの様子を構えずに知ることができる。 彼の本屋が若者たちに知識と夢を与えていたから当然だけど、アフリカ系アメリカ人指導者たちの暗殺など重苦しい事件を経てもなお、力強く歩んでいく人たちが描かれていて、いい終わり方だと思ったら、ヤングアダルト向けの本だった。こういう本も悪くないな。 - 2025年7月3日
 ペルセポリスII マルジ、故郷に帰るマルジャン・サトラピ読み終わった読書メモ図書館本14歳でオーストリアに旅立ったマルジが気になって、続けて読んだ。 戦闘と混乱の続く故郷を離れて留学できたし、家族からは精神的な支援もある。その上、知的な努力家。そんな恵まれた彼女でも、ヨーロッパでは差別的な扱いに傷つき、文化の違いに悩んだ。帰国後は、国内の政権や大国の思惑に振り回される故郷の状況に苦しむことに。様々な経験を経て、再びイランを離れるところで、この本は終わっている。出版されてから20年以上経過した現在、彼女の周りにいた人たちはどうしているんだろう。国内に残った人も、国外へ出た人もいるのだけれど。
ペルセポリスII マルジ、故郷に帰るマルジャン・サトラピ読み終わった読書メモ図書館本14歳でオーストリアに旅立ったマルジが気になって、続けて読んだ。 戦闘と混乱の続く故郷を離れて留学できたし、家族からは精神的な支援もある。その上、知的な努力家。そんな恵まれた彼女でも、ヨーロッパでは差別的な扱いに傷つき、文化の違いに悩んだ。帰国後は、国内の政権や大国の思惑に振り回される故郷の状況に苦しむことに。様々な経験を経て、再びイランを離れるところで、この本は終わっている。出版されてから20年以上経過した現在、彼女の周りにいた人たちはどうしているんだろう。国内に残った人も、国外へ出た人もいるのだけれど。 - 2025年6月29日
 ペルセポリスI イランの少女マルジマルジャン・サトラピ読み終わった読書メモ図書館本図書館でReadsで気になっていた本を見つけて、つい借りちゃった。実はバンド・デシネ初体験。 歴史や報道の一部として見聞きしてきたイランでの出来事が、十代前半の少女の生活として描かれているのに、軽くめまいがした。デモ、革命、投獄、拷問、処刑、空襲、戦死なんて言葉が日常の中に散らばっていて、死があまりに身近。知的で気の強いマルジと一緒に最後のページまで辿り着いた時には、クタクタだった。14歳のマルジにとっては、これからが彼女の人生なんだけど。 ゴツゴツした太い線と、中間色のない白黒はっきりした絵柄が、マルジの置かれている重苦しい状況と、それに果敢に向かっていく彼女の心情を表現するのにぴったり。表紙の彼女の表情も好き。
ペルセポリスI イランの少女マルジマルジャン・サトラピ読み終わった読書メモ図書館本図書館でReadsで気になっていた本を見つけて、つい借りちゃった。実はバンド・デシネ初体験。 歴史や報道の一部として見聞きしてきたイランでの出来事が、十代前半の少女の生活として描かれているのに、軽くめまいがした。デモ、革命、投獄、拷問、処刑、空襲、戦死なんて言葉が日常の中に散らばっていて、死があまりに身近。知的で気の強いマルジと一緒に最後のページまで辿り着いた時には、クタクタだった。14歳のマルジにとっては、これからが彼女の人生なんだけど。 ゴツゴツした太い線と、中間色のない白黒はっきりした絵柄が、マルジの置かれている重苦しい状況と、それに果敢に向かっていく彼女の心情を表現するのにぴったり。表紙の彼女の表情も好き。 - 2025年6月28日
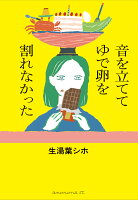 ⾳を⽴ててゆで卵を割れなかった生湯葉シホ読み終わった読書メモ人はそれぞれ違うし、完璧にわかりあえるなんてことはないに等しい。そんなの当たり前。なのに、つい同意を求めてしまうし、同意してもらうために言葉を選んでしまう。 でも、生湯葉さんは容赦ない。言葉、表情、しぐさ。季節。音。におい、味、食感。どんなシチュエーションだったか。湧き上がってくる感情、違和感。孤独。安堵。傷ついたこと、傷つけたこと。詳細にくっきりと書く。いろんな話があったけれど、簡単に共感を許さないものほど、気になったし、気に入った。
⾳を⽴ててゆで卵を割れなかった生湯葉シホ読み終わった読書メモ人はそれぞれ違うし、完璧にわかりあえるなんてことはないに等しい。そんなの当たり前。なのに、つい同意を求めてしまうし、同意してもらうために言葉を選んでしまう。 でも、生湯葉さんは容赦ない。言葉、表情、しぐさ。季節。音。におい、味、食感。どんなシチュエーションだったか。湧き上がってくる感情、違和感。孤独。安堵。傷ついたこと、傷つけたこと。詳細にくっきりと書く。いろんな話があったけれど、簡単に共感を許さないものほど、気になったし、気に入った。 - 2025年6月25日
 不完全なレンズでロベール・ドアノー,Robert Doisneau,堀江敏幸読み終わった読書メモ積読本から街歩き小説が好きだ。ウルフ「ダロウェイ夫人」、タブッキ「レクイエム」、パク・ソルメ「未来散歩練習」。挙げ出したらきりがない。 「街と人、写真をめぐる30話」という帯に惹かれて、古本屋さんで手に取った。ドアノーの案内でパリの街歩きを楽しむつもりで。残念ながら、思惑は外れてしまった。次々に繰り出される地名についていけず、圧倒されっぱなし。 ただ、人の方は写真も語りも堪能できた。不敵な面構えのピカソ。大阪弁で言うなら、「ええし」の雰囲気満点のドゥ・ブロイ。なぜだか、じじむさく見えてしまうユトリロ。対照的に、世捨て人の潔さが感じられるレオトー。 次のドアノーは街の写真集を楽しみたい。
不完全なレンズでロベール・ドアノー,Robert Doisneau,堀江敏幸読み終わった読書メモ積読本から街歩き小説が好きだ。ウルフ「ダロウェイ夫人」、タブッキ「レクイエム」、パク・ソルメ「未来散歩練習」。挙げ出したらきりがない。 「街と人、写真をめぐる30話」という帯に惹かれて、古本屋さんで手に取った。ドアノーの案内でパリの街歩きを楽しむつもりで。残念ながら、思惑は外れてしまった。次々に繰り出される地名についていけず、圧倒されっぱなし。 ただ、人の方は写真も語りも堪能できた。不敵な面構えのピカソ。大阪弁で言うなら、「ええし」の雰囲気満点のドゥ・ブロイ。なぜだか、じじむさく見えてしまうユトリロ。対照的に、世捨て人の潔さが感じられるレオトー。 次のドアノーは街の写真集を楽しみたい。 - 2025年6月22日
 音盤の来歴榎本空読み終わった読書メモずっと榎本空さんの新刊を心待ちにしていたのに、それがレコードについて書かれたものだと知った時、自分にはハードルが高過ぎるような気がした。本屋で見かけても、Readsでコメントを読ませてもらっても、気になりながら、なかなか手が出せず。でも、それは杞憂だった。早く読めば、よかった。 レコードを手に取って聴くことを通して、アメリカや沖縄で、周りの人たちとどんなふうに関わって、何を思ったのかが綴られていて、こちらも一緒に考える機会をもらえたし、もっと様々な音楽を聴きたい気持ちが湧き上がってきた。 たくさん取り上げられているブラックミュージックは、特定の文化、社会に根ざしているものだが、そこに属していない私はどう聴くのか。楽しみながら、考えていきたい。
音盤の来歴榎本空読み終わった読書メモずっと榎本空さんの新刊を心待ちにしていたのに、それがレコードについて書かれたものだと知った時、自分にはハードルが高過ぎるような気がした。本屋で見かけても、Readsでコメントを読ませてもらっても、気になりながら、なかなか手が出せず。でも、それは杞憂だった。早く読めば、よかった。 レコードを手に取って聴くことを通して、アメリカや沖縄で、周りの人たちとどんなふうに関わって、何を思ったのかが綴られていて、こちらも一緒に考える機会をもらえたし、もっと様々な音楽を聴きたい気持ちが湧き上がってきた。 たくさん取り上げられているブラックミュージックは、特定の文化、社会に根ざしているものだが、そこに属していない私はどう聴くのか。楽しみながら、考えていきたい。 - 2025年6月18日
 毎日読みますファン・ボルム,牧野美加読み終わった読書メモしばらく生活が慌ただしく、体調もなんだか微妙で、冴えない日が続いた。そんな時にも少しずつ読めて、支えになってくれた本。 書き手の方も、いろんな経験をしながら読書してきたんだろうな。通勤電車の中でも、疲れて帰宅した後でも、読み進めることができた。韓国や日本のたくさんの読者とこの喜びを共有できていると思うと、素直にとても嬉しい。
毎日読みますファン・ボルム,牧野美加読み終わった読書メモしばらく生活が慌ただしく、体調もなんだか微妙で、冴えない日が続いた。そんな時にも少しずつ読めて、支えになってくれた本。 書き手の方も、いろんな経験をしながら読書してきたんだろうな。通勤電車の中でも、疲れて帰宅した後でも、読み進めることができた。韓国や日本のたくさんの読者とこの喜びを共有できていると思うと、素直にとても嬉しい。 - 2025年6月10日
 喜べ、幸いなる魂よ佐藤亜紀読み終わった読書メモ再読した熱心な読者だとはとても言えないのに、気がついたら佐藤亜紀さんの本が本棚に並んでいた。硬派な作品が何作もある中で、この小説の伸びやかな雰囲気が今の気分だ。 初めて読んだ時は、翻弄されるヤンが気になって仕方なかったが、今回はヤネケとベギン会にじっくり向き合った。女性に自由と自立を保障するシェルターでありながら、世俗から完全に離れた修道院ではない場所。少し時代がずれていて、場所もフランドルではなくオランダだが、画家マリア・シビラ・メーリアンもプロテスタント系のコミューンに入ることで、自由を得たのを連想してしまう。今の日本では、どんなところが女性たちのアジールになっているんだろう。
喜べ、幸いなる魂よ佐藤亜紀読み終わった読書メモ再読した熱心な読者だとはとても言えないのに、気がついたら佐藤亜紀さんの本が本棚に並んでいた。硬派な作品が何作もある中で、この小説の伸びやかな雰囲気が今の気分だ。 初めて読んだ時は、翻弄されるヤンが気になって仕方なかったが、今回はヤネケとベギン会にじっくり向き合った。女性に自由と自立を保障するシェルターでありながら、世俗から完全に離れた修道院ではない場所。少し時代がずれていて、場所もフランドルではなくオランダだが、画家マリア・シビラ・メーリアンもプロテスタント系のコミューンに入ることで、自由を得たのを連想してしまう。今の日本では、どんなところが女性たちのアジールになっているんだろう。 - 2025年6月7日
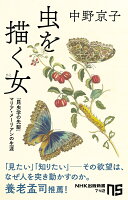 虫を描く女(ひと)中野京子読書メモ一緒に読んだメーリアンを知るきっかけになった本。旅行先でなんとなく本屋に入って、自分へのお土産として買った。絵が鮮やかで印象的だったし(なんせ虫)、文章ばかりでないから読みやすそうと思って。ドイツ語からの翻訳だったことに、今回読み直すまで気がついてなかった。いい加減だな。 こちらの方が簡潔な伝記だから、中野さんの本の方で強調して書かれていることが逆に気になった。例えば、メーリアンの容貌について。彼女は「美貌に恵まれていないという自覚」があったのではないかというのが中野さんの意見。また、絵画の種類や画材にはヒエラルキーがあるから、メーリアンが銅版画や水彩絵の具にこだわったことを惜しんでる。もしメーリアンが油彩画を描いていたら、と。 「スリナム産昆虫変態図譜」は結構なお値段がするけれど、いつか手に入れられたらいいな。
虫を描く女(ひと)中野京子読書メモ一緒に読んだメーリアンを知るきっかけになった本。旅行先でなんとなく本屋に入って、自分へのお土産として買った。絵が鮮やかで印象的だったし(なんせ虫)、文章ばかりでないから読みやすそうと思って。ドイツ語からの翻訳だったことに、今回読み直すまで気がついてなかった。いい加減だな。 こちらの方が簡潔な伝記だから、中野さんの本の方で強調して書かれていることが逆に気になった。例えば、メーリアンの容貌について。彼女は「美貌に恵まれていないという自覚」があったのではないかというのが中野さんの意見。また、絵画の種類や画材にはヒエラルキーがあるから、メーリアンが銅版画や水彩絵の具にこだわったことを惜しんでる。もしメーリアンが油彩画を描いていたら、と。 「スリナム産昆虫変態図譜」は結構なお値段がするけれど、いつか手に入れられたらいいな。
- 2025年6月7日
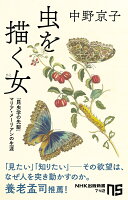 虫を描く女(ひと)中野京子読み終わった読書メモ画家マリア・シビラ・メーリアンのスケールの大きさは超弩級だ。やることなすこと、メチャクチャかっこいい。 まず、意欲が半端じゃない。虫は廃棄物から自然発生すると信じられていた時代に、虫の生態を自分の目で観察、独学で研究。52歳という年齢で南米スリナムへ渡り、過酷な環境で2年間調査を続けるなんて。そして、なんと言っても、彼女は成功者だ。帰国後「スリナム産昆虫変態図譜」を出版して、センセーションを巻き起こすことに。 これだけでもお腹いっぱいなのに、甲斐性のない夫と離婚した時の手際、南米でのインディオとの交流、プランテーション批判など、本業以外にも注目ポイントが目白押し。作者の中野京子さんはメーリアンの絵のダイナミックな構図とエネルギーに溢れた人柄を結びつけてる。確かに並外れた体力ないと、3ヶ月かけて南米行って、ジャングルの中でフィールドワークなんてできないわ。メーリアンにはなれないけれど、体力は大切しないとな。
虫を描く女(ひと)中野京子読み終わった読書メモ画家マリア・シビラ・メーリアンのスケールの大きさは超弩級だ。やることなすこと、メチャクチャかっこいい。 まず、意欲が半端じゃない。虫は廃棄物から自然発生すると信じられていた時代に、虫の生態を自分の目で観察、独学で研究。52歳という年齢で南米スリナムへ渡り、過酷な環境で2年間調査を続けるなんて。そして、なんと言っても、彼女は成功者だ。帰国後「スリナム産昆虫変態図譜」を出版して、センセーションを巻き起こすことに。 これだけでもお腹いっぱいなのに、甲斐性のない夫と離婚した時の手際、南米でのインディオとの交流、プランテーション批判など、本業以外にも注目ポイントが目白押し。作者の中野京子さんはメーリアンの絵のダイナミックな構図とエネルギーに溢れた人柄を結びつけてる。確かに並外れた体力ないと、3ヶ月かけて南米行って、ジャングルの中でフィールドワークなんてできないわ。メーリアンにはなれないけれど、体力は大切しないとな。 - 2025年6月4日
 もっと知りたいアイヌの美術山崎幸治読み終わった読書メモ図書館本著者によると、「もの」という視点から眺めたアイヌ民族の世界を紹介する入門書。 民藝運動や昭和の北海道観光ブームとの関わりは見聞きしたことがあったけれど、江戸時代後期に和人向けの工芸品が「蝦夷細工」として制作されていたことは初めて知った。文人趣味にかかわるものが多いらしく、煎茶道具が紹介されていて、びっくり。アイヌの人たちと煎茶道具かぁ。意外。 現代の作家として、「アイヌがまなざす」の表紙を制作した結城幸司さんの作品も載っている。見つけた時は、なんだか嬉しかったな。
もっと知りたいアイヌの美術山崎幸治読み終わった読書メモ図書館本著者によると、「もの」という視点から眺めたアイヌ民族の世界を紹介する入門書。 民藝運動や昭和の北海道観光ブームとの関わりは見聞きしたことがあったけれど、江戸時代後期に和人向けの工芸品が「蝦夷細工」として制作されていたことは初めて知った。文人趣味にかかわるものが多いらしく、煎茶道具が紹介されていて、びっくり。アイヌの人たちと煎茶道具かぁ。意外。 現代の作家として、「アイヌがまなざす」の表紙を制作した結城幸司さんの作品も載っている。見つけた時は、なんだか嬉しかったな。 - 2025年6月1日
- 2025年6月1日
- 2025年5月29日
- 2025年5月27日
- 2025年5月25日
 百年と一日柴崎友香読書メモ再読した説話集を読むとこの本を、この本を読むと説話集を開きたくなる。思わぬことが起こったり、人間の運命を感じたり、それぞれに内容のわかるタイトルがついていたり。 一般的な短編小説のようなストーリー展開や結末を期待しない方がいい。物語の中心にあるのは、さまざまな場所や物。その周りを時間と人間が動いていく。その不思議な感覚を味わうのが、この本を読む醍醐味じゃないかな。 好きな話がたくさんあるから、お気に入りを選ぶのは難しいけれど、きのこが出てくる最初の話は絶対に外せない。
百年と一日柴崎友香読書メモ再読した説話集を読むとこの本を、この本を読むと説話集を開きたくなる。思わぬことが起こったり、人間の運命を感じたり、それぞれに内容のわかるタイトルがついていたり。 一般的な短編小説のようなストーリー展開や結末を期待しない方がいい。物語の中心にあるのは、さまざまな場所や物。その周りを時間と人間が動いていく。その不思議な感覚を味わうのが、この本を読む醍醐味じゃないかな。 好きな話がたくさんあるから、お気に入りを選ぶのは難しいけれど、きのこが出てくる最初の話は絶対に外せない。 - 2025年5月21日
 王朝奇談集須永朝彦読み終わった読書メモ説話集は文句なく面白い。名だたる作家たちが短編の元ネタとして使うのも納得がいく。王朝奇談というだけあって、典雅な話も選ばれているけれど、私は騒々しい話に惹かれるみたい。 後半のお気に入りは、巻貝が食べられる直前に、たくさんの小さな尼の姿になって夢の中に現れ、「それぞれに泣き悲しみ、様々に掻き口説いた」という話。蛤が夢に現れた人もいるらしい。酒蒸しを作る時に、アサリが次々と口を開けていく様子を思い浮かべると、無数の尼さんが口々にしゃべっている姿と重なるかも。 貝は「生きたままのものを食うゆえに、斯様に夢にも現れるのであろう。無惨な事ではある。」と話は締めくくられている。説話集だからね。でも、活きのいい貝なんて、最近なかなか手に入らないから、尼さんたちがわーわー騒いでいる夢を見てみたい気持ちもする。
王朝奇談集須永朝彦読み終わった読書メモ説話集は文句なく面白い。名だたる作家たちが短編の元ネタとして使うのも納得がいく。王朝奇談というだけあって、典雅な話も選ばれているけれど、私は騒々しい話に惹かれるみたい。 後半のお気に入りは、巻貝が食べられる直前に、たくさんの小さな尼の姿になって夢の中に現れ、「それぞれに泣き悲しみ、様々に掻き口説いた」という話。蛤が夢に現れた人もいるらしい。酒蒸しを作る時に、アサリが次々と口を開けていく様子を思い浮かべると、無数の尼さんが口々にしゃべっている姿と重なるかも。 貝は「生きたままのものを食うゆえに、斯様に夢にも現れるのであろう。無惨な事ではある。」と話は締めくくられている。説話集だからね。でも、活きのいい貝なんて、最近なかなか手に入らないから、尼さんたちがわーわー騒いでいる夢を見てみたい気持ちもする。 - 2025年5月19日
 王朝奇談集須永朝彦読書メモ読んでる平安鎌倉時代の作品から編まれたアンソロジー。「今昔物語」のように有名な作品からあまり知られていないものまで幅広く17作品から82編が取られている。登場人物も皇族貴族の有名人から名もなき庶民まで多様。 あえて古い言葉や言い回しが使われていて、現代語訳というより編者が語り直した物語になってる。説明臭さがなく、古風な雰囲気がいい感じ。 今のところのお気に入りは、中国からわざわざ力比べに来た天狗がボコボコにされて、湯治して帰って行った話と、毎年たくさん取れていた平茸が取れなくなってしまった村で、実はその前の年に平茸たちが僧の姿で暇乞いに来ていたという話。平茸がお別れを言いに来たんだよ。義理堅くて、笑っちゃうよね。とにかく面白い。
王朝奇談集須永朝彦読書メモ読んでる平安鎌倉時代の作品から編まれたアンソロジー。「今昔物語」のように有名な作品からあまり知られていないものまで幅広く17作品から82編が取られている。登場人物も皇族貴族の有名人から名もなき庶民まで多様。 あえて古い言葉や言い回しが使われていて、現代語訳というより編者が語り直した物語になってる。説明臭さがなく、古風な雰囲気がいい感じ。 今のところのお気に入りは、中国からわざわざ力比べに来た天狗がボコボコにされて、湯治して帰って行った話と、毎年たくさん取れていた平茸が取れなくなってしまった村で、実はその前の年に平茸たちが僧の姿で暇乞いに来ていたという話。平茸がお別れを言いに来たんだよ。義理堅くて、笑っちゃうよね。とにかく面白い。 - 2025年5月18日
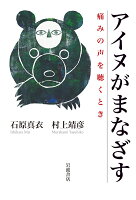 アイヌがまなざす村上靖彦,石原真衣読み終わったまた読みたい追加のメモ 印象的なまなざしを持っている表紙の作品はインタビューを受けた方のもの。行動的でインタビューも読み応えあったけれど、この表紙のまなざしは本当にいい。
アイヌがまなざす村上靖彦,石原真衣読み終わったまた読みたい追加のメモ 印象的なまなざしを持っている表紙の作品はインタビューを受けた方のもの。行動的でインタビューも読み応えあったけれど、この表紙のまなざしは本当にいい。 - 2025年5月17日
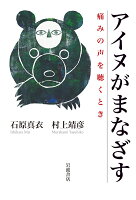 アイヌがまなざす村上靖彦,石原真衣読み終わった読書メモ図書館本行ったり来たりを繰り返して、なんとか最後までよろよろたどり着いた。 当事者の声を聞くためには、背景知識も必要だし、突きつけられた言葉を受けとめる覚悟もいる。両方とも足りていなかった。著者二人が丁寧にその人の言葉を拾い上げて、解きほぐしてくれているが、それでも「生の声」を受けとめきれていないところがかなりあると思う。 アイヌのルーツを持たない村上さんは書き手としての難しさを述べられているけれど、先住民と植民側のお二人が議論しながら書いた本があることそのものに感謝したい。アイヌの女たちが命を守り抜くためにしてきたこと、アイデンティティの問題、地域の違い、アイヌによる運動の歴史。気になったことはたくさんある。また出直してきます。
アイヌがまなざす村上靖彦,石原真衣読み終わった読書メモ図書館本行ったり来たりを繰り返して、なんとか最後までよろよろたどり着いた。 当事者の声を聞くためには、背景知識も必要だし、突きつけられた言葉を受けとめる覚悟もいる。両方とも足りていなかった。著者二人が丁寧にその人の言葉を拾い上げて、解きほぐしてくれているが、それでも「生の声」を受けとめきれていないところがかなりあると思う。 アイヌのルーツを持たない村上さんは書き手としての難しさを述べられているけれど、先住民と植民側のお二人が議論しながら書いた本があることそのものに感謝したい。アイヌの女たちが命を守り抜くためにしてきたこと、アイデンティティの問題、地域の違い、アイヌによる運動の歴史。気になったことはたくさんある。また出直してきます。
読み込み中...

