
ほんのうに
@bk_urchin
- 2026年2月22日
 〈生活ー文脈〉理解のすすめ宮内洋,打越正行,新藤慶,松宮朝読み終わった@ カフェタロー CAFÉ Tarot Veganフィールドワークにおける〈生活−文脈〉の重要性を説いた本。畑違いの領域だけど、仕事に役立つのではないかと思い購入。 目に見えた事象を自分の解釈で理解したつもりになるのではなく、相手の背景(生活環境・人間関係・地域とのつながり、地場の政治活動まで)から生まれる文脈をとらまえなければ正しい理解はできない、ということだった。 効率主義が加速して、ローデータやログはAIを使ってサマろうみたいな時流の中で、忘れてはいけない考え方だと感じる。 ビジネスだけでなく、日々の生活の中での相互理解にも必要。つい自分の物差しで断定してしまう。 読み物としては第2章沖縄ヤンキーのフィールドワークが面白かった。 沖縄の建設業の大富豪には革命ルールがない。格差の固定化を受け入れている。失業と隣合せの世界においては、保守的でなければ生きていけないので革命などは求めていない。特定の先輩との緩く長い搾取の関係に嵌まり込むことが結果的に自分を守ることに繋がる…というのが、全く想像もしてなかった文脈で印象的だった。
〈生活ー文脈〉理解のすすめ宮内洋,打越正行,新藤慶,松宮朝読み終わった@ カフェタロー CAFÉ Tarot Veganフィールドワークにおける〈生活−文脈〉の重要性を説いた本。畑違いの領域だけど、仕事に役立つのではないかと思い購入。 目に見えた事象を自分の解釈で理解したつもりになるのではなく、相手の背景(生活環境・人間関係・地域とのつながり、地場の政治活動まで)から生まれる文脈をとらまえなければ正しい理解はできない、ということだった。 効率主義が加速して、ローデータやログはAIを使ってサマろうみたいな時流の中で、忘れてはいけない考え方だと感じる。 ビジネスだけでなく、日々の生活の中での相互理解にも必要。つい自分の物差しで断定してしまう。 読み物としては第2章沖縄ヤンキーのフィールドワークが面白かった。 沖縄の建設業の大富豪には革命ルールがない。格差の固定化を受け入れている。失業と隣合せの世界においては、保守的でなければ生きていけないので革命などは求めていない。特定の先輩との緩く長い搾取の関係に嵌まり込むことが結果的に自分を守ることに繋がる…というのが、全く想像もしてなかった文脈で印象的だった。 - 2026年2月14日
 ワンルームから宇宙をのぞく久保勇貴読み終わった@ 外濠書店宇宙工学研究者の方の日常エッセイ。誕生日プレゼントに頂いた。 全然詳しくないけど、宇宙のことを考えるのが好きだ。途方もない大きな世界の話を考えると、自分のことがちっぽけに思えて気持ちが救われるから。 この本の中でもそんな諦念みたいなものはあって、あまりに膨大で予測不可能でコストもリソースも必要な宇宙と向き合う話を知れる。一方で、少しづつ前に進む可能性みたいなものも描かれていて(だからこそ人類は宇宙に行けたわけで)、諦念と希望は両立するんだと思えた。 ままならないけど、ままならないなりにやれる。上手くいくときもあるけど、駄目なときもある。それってすごい希望じゃん!と感じる。 印象に残ったのは、3マイクロニュートンだけ、太陽光圧によって背中に力がかかっているらしいということ。今自分は太陽に背中を押されてる、と思って生きていきたい。
ワンルームから宇宙をのぞく久保勇貴読み終わった@ 外濠書店宇宙工学研究者の方の日常エッセイ。誕生日プレゼントに頂いた。 全然詳しくないけど、宇宙のことを考えるのが好きだ。途方もない大きな世界の話を考えると、自分のことがちっぽけに思えて気持ちが救われるから。 この本の中でもそんな諦念みたいなものはあって、あまりに膨大で予測不可能でコストもリソースも必要な宇宙と向き合う話を知れる。一方で、少しづつ前に進む可能性みたいなものも描かれていて(だからこそ人類は宇宙に行けたわけで)、諦念と希望は両立するんだと思えた。 ままならないけど、ままならないなりにやれる。上手くいくときもあるけど、駄目なときもある。それってすごい希望じゃん!と感じる。 印象に残ったのは、3マイクロニュートンだけ、太陽光圧によって背中に力がかかっているらしいということ。今自分は太陽に背中を押されてる、と思って生きていきたい。 - 2026年2月11日
 人生が整うマウンティング大全マウンティングポリス気になる
人生が整うマウンティング大全マウンティングポリス気になる - 2026年1月25日
- 2026年1月25日
 さみしい夜のページをめくれならの,古賀史健読み終わった@ CLOVE CAFE&BAKERY 表参道急に本が読めなくなってしまった。 ショート動画は観られるのに、本を手に取る気持ちにならない。 仕事のことで脳が占領されていて、くらーい感覚。 そんな状況を打開したくてこの本を選んだ。 1作目の「さみしい夜にはペンを持て」がとても読みやすく、心にすっと寄り添ってくれたので、この本なら今の自分でも読めると思った。 前作に続き、道を照らしてくれる本だった。魚をくれるのではなく、魚の釣り方を教えてくれるような。 人生は自分で選んでいくしかなく、本を選ぶことは自分をカルチベート(この本で初めて知ったw)すること。 読みたくて買ったのに読みたい気持ちにならず罪悪感を覚えていた本を、今は読みたいと思う。
さみしい夜のページをめくれならの,古賀史健読み終わった@ CLOVE CAFE&BAKERY 表参道急に本が読めなくなってしまった。 ショート動画は観られるのに、本を手に取る気持ちにならない。 仕事のことで脳が占領されていて、くらーい感覚。 そんな状況を打開したくてこの本を選んだ。 1作目の「さみしい夜にはペンを持て」がとても読みやすく、心にすっと寄り添ってくれたので、この本なら今の自分でも読めると思った。 前作に続き、道を照らしてくれる本だった。魚をくれるのではなく、魚の釣り方を教えてくれるような。 人生は自分で選んでいくしかなく、本を選ぶことは自分をカルチベート(この本で初めて知ったw)すること。 読みたくて買ったのに読みたい気持ちにならず罪悪感を覚えていた本を、今は読みたいと思う。 - 2025年12月30日
 読み終わった@ 自宅安達茉莉子さんは「私の生活改善運動」が良かったのと、扱われているお悩みに共感できそうだったので購入。 お悩み「解決」ではなく「対話」と語られている通り、ふんわりと言葉を返していくイメージ。 悩みを楽にする方法にはアドバイスと共感の2つがあって、自分の中で散々考えて、正論もわかっていて、それでも答えが出せないものほど、誰かに共感してもらうだけで心持ちが全く変わってくる。この本の中でもお悩みに対する安達さんの共感が多く、世の中に、自分・相談主・安達さんの少なくとも3人が同じ悩みを抱えていると思えると、気が楽になる。 以下、覚えておきたかった文章−−− p28 他者の承認は、それを受け取る自分という「器」にヒビが入っていたり、そもそも器に蓋がしてあって、注がれても注がれてもなかなか溜まっていかないことがあります。私の場合ですが、そんなモードになっている時は、まず器を見直します。 p134 布団で安心してスヤリとするためには、結局気は休まらないけどベッドの上で横たわっている、そんな「予休み」のような時間もまた、必要なんだと思います。 p146 だから、もし今自分のことが嫌いでも、未来の自分が今の自分を見ていたら、きっと、ものすごく大きな声で、本当によくやっているよ!って叫んでいると思います。
読み終わった@ 自宅安達茉莉子さんは「私の生活改善運動」が良かったのと、扱われているお悩みに共感できそうだったので購入。 お悩み「解決」ではなく「対話」と語られている通り、ふんわりと言葉を返していくイメージ。 悩みを楽にする方法にはアドバイスと共感の2つがあって、自分の中で散々考えて、正論もわかっていて、それでも答えが出せないものほど、誰かに共感してもらうだけで心持ちが全く変わってくる。この本の中でもお悩みに対する安達さんの共感が多く、世の中に、自分・相談主・安達さんの少なくとも3人が同じ悩みを抱えていると思えると、気が楽になる。 以下、覚えておきたかった文章−−− p28 他者の承認は、それを受け取る自分という「器」にヒビが入っていたり、そもそも器に蓋がしてあって、注がれても注がれてもなかなか溜まっていかないことがあります。私の場合ですが、そんなモードになっている時は、まず器を見直します。 p134 布団で安心してスヤリとするためには、結局気は休まらないけどベッドの上で横たわっている、そんな「予休み」のような時間もまた、必要なんだと思います。 p146 だから、もし今自分のことが嫌いでも、未来の自分が今の自分を見ていたら、きっと、ものすごく大きな声で、本当によくやっているよ!って叫んでいると思います。 - 2025年12月28日
 私の孤独な日曜日月と文社@ 御菓子司 亀十日曜日を孤独に過ごす人たちのエッセイ集。 孤独を受け入れている人も、受け入れていない人もいる。 なるべく本音を書いてもらったという編者のコメント通り、どちらかというと、孤独でいる時間や、孤独に過ごすことになった背景に悩みながら過ごしている人が多い印象を受けた。(今の自分のアンテナがそっち寄りだからかもしれない) 著者のひとり「きのこやろう」さんの "「これでいいのか」という健全なネガティブ感情が人生を豊かにする原動力"(要約)という文章が印象に残った。 そう考えれば、孤独な日曜日にあれこれ思い悩むのも悪くない。
私の孤独な日曜日月と文社@ 御菓子司 亀十日曜日を孤独に過ごす人たちのエッセイ集。 孤独を受け入れている人も、受け入れていない人もいる。 なるべく本音を書いてもらったという編者のコメント通り、どちらかというと、孤独でいる時間や、孤独に過ごすことになった背景に悩みながら過ごしている人が多い印象を受けた。(今の自分のアンテナがそっち寄りだからかもしれない) 著者のひとり「きのこやろう」さんの "「これでいいのか」という健全なネガティブ感情が人生を豊かにする原動力"(要約)という文章が印象に残った。 そう考えれば、孤独な日曜日にあれこれ思い悩むのも悪くない。 - 2025年12月7日
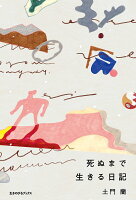 死ぬまで生きる日記土門蘭気になる
死ぬまで生きる日記土門蘭気になる - 2025年12月5日
 自分のために料理を作る山口祐加,星野概念読み終わった自分ひとりのために料理を作ることのレクチャーとカウンセリングを記録した本。おもしろかった。 この本に書かれている自炊をうまくやるためのコツは、そのまま他のことにも通ずる内容だと感じた。 "レシピをまま実行するのではなく、ロジックを理解して料理する"は、意味を考えて仕事をすると達成感や自己効力感が高まることと同じ。"できあがった料理もその過程も、気持ちの変化も含めて味わう" ことは、今ここに目を向ける瞑想と同じ効果がある。その中でも自炊は、完成まで早いし、日々の営みだから試行回数も多いし、本能的にカラダと心が満たされるし、ケアの効果が大きいんだろうな。 ただ、この本に出てくる相談者の皆さんはある程度料理スキルがあるけど自分のためには作れない、という人が多く感じてしまって、次巻があれば、もう全然自炊してません!毎日コンビニです!みたいな人の事例も読みたいな〜
自分のために料理を作る山口祐加,星野概念読み終わった自分ひとりのために料理を作ることのレクチャーとカウンセリングを記録した本。おもしろかった。 この本に書かれている自炊をうまくやるためのコツは、そのまま他のことにも通ずる内容だと感じた。 "レシピをまま実行するのではなく、ロジックを理解して料理する"は、意味を考えて仕事をすると達成感や自己効力感が高まることと同じ。"できあがった料理もその過程も、気持ちの変化も含めて味わう" ことは、今ここに目を向ける瞑想と同じ効果がある。その中でも自炊は、完成まで早いし、日々の営みだから試行回数も多いし、本能的にカラダと心が満たされるし、ケアの効果が大きいんだろうな。 ただ、この本に出てくる相談者の皆さんはある程度料理スキルがあるけど自分のためには作れない、という人が多く感じてしまって、次巻があれば、もう全然自炊してません!毎日コンビニです!みたいな人の事例も読みたいな〜 - 2025年11月27日
 老人ホームで死ぬほどモテたい上坂あゆ美読み終わった初めて短歌集を読んだ。 短歌に対して何のイメージもなかったけど、景色も、音も、手触りも、気持ちも、そのときの全てを真空パックのように閉じ込めることができるものなんだと知った。語数が限られる分、密度が濃くて、インパクトを持って頭に入ってくる。 以下が好きだった。 ・言わなければよかったことが多すぎてシャンプーノズルかすかすと押す ・今日までを生きててよかったんだよね 鳥貴の釜めしまた食べようね
老人ホームで死ぬほどモテたい上坂あゆ美読み終わった初めて短歌集を読んだ。 短歌に対して何のイメージもなかったけど、景色も、音も、手触りも、気持ちも、そのときの全てを真空パックのように閉じ込めることができるものなんだと知った。語数が限られる分、密度が濃くて、インパクトを持って頭に入ってくる。 以下が好きだった。 ・言わなければよかったことが多すぎてシャンプーノズルかすかすと押す ・今日までを生きててよかったんだよね 鳥貴の釜めしまた食べようね - 2025年11月24日
 そして誰もゆとらなくなった朝井リョウ読み終わったゆとり三部作の三冊目。 三冊目にもなってくると、も〜〜リョウってそういうとこあるよね〜、と友達感覚で読んでしまう。電車の中でニヤニヤしながら読むのも慣れた。 生きていると、自分ってなんでいつもこうなんだろう、と悲観的な気分になることがあるけれど、きっとどんな人もそういう気持ちになりながら人生を送ってるんだな、と。銀座やアメリカの話を読んでそう思えた。
そして誰もゆとらなくなった朝井リョウ読み終わったゆとり三部作の三冊目。 三冊目にもなってくると、も〜〜リョウってそういうとこあるよね〜、と友達感覚で読んでしまう。電車の中でニヤニヤしながら読むのも慣れた。 生きていると、自分ってなんでいつもこうなんだろう、と悲観的な気分になることがあるけれど、きっとどんな人もそういう気持ちになりながら人生を送ってるんだな、と。銀座やアメリカの話を読んでそう思えた。 - 2025年11月20日
 風と共にゆとりぬ (文春文庫)朝井リョウ読み終わったエッセイ読むのは2冊目。相変わらずキレッキレの文体。ニヤニヤしてしまう。 朝井リョウさんと共通点がいくつかあることを自分の誇りに思っているけれど、マシュー南が好きなこと、痔の治療歴があること、という追加の共通点が見つかってうれしい。
風と共にゆとりぬ (文春文庫)朝井リョウ読み終わったエッセイ読むのは2冊目。相変わらずキレッキレの文体。ニヤニヤしてしまう。 朝井リョウさんと共通点がいくつかあることを自分の誇りに思っているけれど、マシュー南が好きなこと、痔の治療歴があること、という追加の共通点が見つかってうれしい。 - 2025年11月18日
 らんま1/2公式ファンブック 大歓喜キャラメル・ママ,高橋留美子読んでるとりあえず、漫画家の方たちの寄稿部分を読んだ。 原作のコマをその人の絵柄で再現しているものがちらほらあって眼福〜 キャラの中ではシャンプー人気が高く、うっちゃんはあまりいなかった…うっちゃんかわいいのに!
らんま1/2公式ファンブック 大歓喜キャラメル・ママ,高橋留美子読んでるとりあえず、漫画家の方たちの寄稿部分を読んだ。 原作のコマをその人の絵柄で再現しているものがちらほらあって眼福〜 キャラの中ではシャンプー人気が高く、うっちゃんはあまりいなかった…うっちゃんかわいいのに! - 2025年11月16日
 青い壺 (文春文庫)有吉佐和子読み終わった@ カフェ青い壺が、作られてから十年間様々な人の手に渡り、そこで起こる人間模様を描いている連作短編集。 昭和特有の(?)歯に衣着せぬ物言いが、読んでいて気持ちがいい。(ストレートに伝えているけど、相手がそれを受け入れるかはまた別なので、遺恨が残らないような) 印象に残ったのは… 第七話 戦時下の食糧難の中、裕福な家庭の夫婦が想像の中でフルコースを食べる。戦時下の統制で渇いていた体に贅沢が油のように染み渡ることで、心が晴れていく様子が描かれている。 第十話 とにかく姦しい老婦たちの同窓会旅行。"行く前は不安だけど、行ってみたら(文句はあっても)楽しい"は時代問わず万人共通なんだな。 第十二話 病院の清掃婦が、患者の見舞い花から枯れそうなバラをもらい、乾燥させて、バラの花の枕を作る。狭い寝室の中の枕の甘い香りが伝わってくるような描写が印象的。 生活、仕事、文化、人間がどの話の中にも詰まっていて、読み応えのある小説だった。
青い壺 (文春文庫)有吉佐和子読み終わった@ カフェ青い壺が、作られてから十年間様々な人の手に渡り、そこで起こる人間模様を描いている連作短編集。 昭和特有の(?)歯に衣着せぬ物言いが、読んでいて気持ちがいい。(ストレートに伝えているけど、相手がそれを受け入れるかはまた別なので、遺恨が残らないような) 印象に残ったのは… 第七話 戦時下の食糧難の中、裕福な家庭の夫婦が想像の中でフルコースを食べる。戦時下の統制で渇いていた体に贅沢が油のように染み渡ることで、心が晴れていく様子が描かれている。 第十話 とにかく姦しい老婦たちの同窓会旅行。"行く前は不安だけど、行ってみたら(文句はあっても)楽しい"は時代問わず万人共通なんだな。 第十二話 病院の清掃婦が、患者の見舞い花から枯れそうなバラをもらい、乾燥させて、バラの花の枕を作る。狭い寝室の中の枕の甘い香りが伝わってくるような描写が印象的。 生活、仕事、文化、人間がどの話の中にも詰まっていて、読み応えのある小説だった。 - 2025年11月15日
 哲学の先生と人生の話をしよう國分功一郎気になる
哲学の先生と人生の話をしよう國分功一郎気になる - 2025年11月12日
 生殖記朝井リョウ読み終わった一気読みした。 共同体にバレてはいけないという本能的恐怖も、匂いが漏れないように慎重に自分を表現するうちに何が自分の本音なのか分からなくなる感覚も、初めて同じ種類の人に会ったときに、目の前の世界が開けて自分の発する言葉と内面が一致する感覚も、全部が高い解像度で記されていた。 会社という共同体に対して出稼ぎ感覚なのは尚成と同じで、うまくやって給料がもらい続けられればそれでいいと思っている。そして、出稼ぎ感覚の自分よりパフォーマンスが劣る人に対する苛立ちも正直あって、これが何なのか今まで分からなかったけど、共同体を縮小させる存在に対する本能的嫌悪感だとすると納得できる。それって出稼ぎといいながらも結局共同体の一員として役割に飲み込まれているということだ。人間すぎる〜! 尚成と颯が異なるように、カテゴライズで括れることなんて実はないのだと思う。最近出会った友達はすごく似てるけど明確に違う部分もあって、それがとてもおもしろい。他者(それも一つの共同体なんだろうか)に本音を話せると、自分の輪郭が見えてくるような感覚がある。それは自分の"しっくり"を見つけることに繋がるし、ひいては幸福感にも繋がる気がする。 マッチポンプに夢中になる尚成に恐怖を感じつつ、きみがマッチポンプしている間に、おれはおれの方法で、おれが大事にしたい共同体の中で幸せになってやるからね!って、宣言したくなるような不思議な読後感だった。
生殖記朝井リョウ読み終わった一気読みした。 共同体にバレてはいけないという本能的恐怖も、匂いが漏れないように慎重に自分を表現するうちに何が自分の本音なのか分からなくなる感覚も、初めて同じ種類の人に会ったときに、目の前の世界が開けて自分の発する言葉と内面が一致する感覚も、全部が高い解像度で記されていた。 会社という共同体に対して出稼ぎ感覚なのは尚成と同じで、うまくやって給料がもらい続けられればそれでいいと思っている。そして、出稼ぎ感覚の自分よりパフォーマンスが劣る人に対する苛立ちも正直あって、これが何なのか今まで分からなかったけど、共同体を縮小させる存在に対する本能的嫌悪感だとすると納得できる。それって出稼ぎといいながらも結局共同体の一員として役割に飲み込まれているということだ。人間すぎる〜! 尚成と颯が異なるように、カテゴライズで括れることなんて実はないのだと思う。最近出会った友達はすごく似てるけど明確に違う部分もあって、それがとてもおもしろい。他者(それも一つの共同体なんだろうか)に本音を話せると、自分の輪郭が見えてくるような感覚がある。それは自分の"しっくり"を見つけることに繋がるし、ひいては幸福感にも繋がる気がする。 マッチポンプに夢中になる尚成に恐怖を感じつつ、きみがマッチポンプしている間に、おれはおれの方法で、おれが大事にしたい共同体の中で幸せになってやるからね!って、宣言したくなるような不思議な読後感だった。 - 2025年11月10日
 時をかけるゆとり (文春文庫)朝井リョウ読み終わった@ 自宅本を読んで声を出して笑ったのは久しぶり。朝井リョウはやっぱりすごい。直木賞受賞エッセイのグッと世界に引き込まれるような空気感も、その後の痔の話のテンションで持ってく感じも、どちらも好きな文章。 面白おかしく自虐的に書いているけれども、日常も非日常も含めて輝く青春のエピソードが多く、少し寂しくもなった。俺も、中学生のとき、バッテン脱ぎかっこいいしセクシーだと思ってやっていたよ…!でも、その可笑しさを共有できるような友達が当時いたら、何倍も楽しかっただろうなあ、なんてセンチなことを考えたりもした。
時をかけるゆとり (文春文庫)朝井リョウ読み終わった@ 自宅本を読んで声を出して笑ったのは久しぶり。朝井リョウはやっぱりすごい。直木賞受賞エッセイのグッと世界に引き込まれるような空気感も、その後の痔の話のテンションで持ってく感じも、どちらも好きな文章。 面白おかしく自虐的に書いているけれども、日常も非日常も含めて輝く青春のエピソードが多く、少し寂しくもなった。俺も、中学生のとき、バッテン脱ぎかっこいいしセクシーだと思ってやっていたよ…!でも、その可笑しさを共有できるような友達が当時いたら、何倍も楽しかっただろうなあ、なんてセンチなことを考えたりもした。 - 2025年11月6日
 エクソフォニー多和田葉子気になる
エクソフォニー多和田葉子気になる - 2025年11月4日
 利他・ケア・傷の倫理学近内悠太気になる「おい、部屋を掃除しろ」というブログ記事(https://syu-m-5151.hatenablog.com/entry/2025/11/03/020316)の最後でアフィリエイトされていた。気になる
利他・ケア・傷の倫理学近内悠太気になる「おい、部屋を掃除しろ」というブログ記事(https://syu-m-5151.hatenablog.com/entry/2025/11/03/020316)の最後でアフィリエイトされていた。気になる - 2025年11月3日
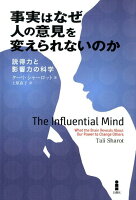 事実はなぜ人の意見を変えられないのかターリ・シャーロット,上原直子読み終わった仕事のために読んだが、日常生活にも活かせそう。 結局は脳が人間の行動を司っているので、脳の機能・特性を理解しようね、という話。事例や実験が豊富で読みやすい。 印象に残ったのは以下。 ・単に相手の論を否定するのではなく、相手と自分の共通の目的を見つけて、それを絡めて意見を伝える(例:ワクチン否定派には、ワクチンの危険性を科学的に否定するのではなく、子どもを守る=病気を防ぐためにはワクチン接種した方がよい、と伝える) ・迂闊に相手の意見を否定する論をぶつけると、相手は元々想定していなかった反論ポイントを思いついてしまう(ブーメラン効果) ・何かをしてほしいときはポジティブな情報、何かをしてほしくないときはネガティブな情報を提供する。(苦痛からは目を背ける習性があるのでネガティブ情報は行動抑止につながる) ・人間は選択を好む。「自分に委託させる」のであっても、それを相手が決めれば相手が選択したことになり納得度が高まる
事実はなぜ人の意見を変えられないのかターリ・シャーロット,上原直子読み終わった仕事のために読んだが、日常生活にも活かせそう。 結局は脳が人間の行動を司っているので、脳の機能・特性を理解しようね、という話。事例や実験が豊富で読みやすい。 印象に残ったのは以下。 ・単に相手の論を否定するのではなく、相手と自分の共通の目的を見つけて、それを絡めて意見を伝える(例:ワクチン否定派には、ワクチンの危険性を科学的に否定するのではなく、子どもを守る=病気を防ぐためにはワクチン接種した方がよい、と伝える) ・迂闊に相手の意見を否定する論をぶつけると、相手は元々想定していなかった反論ポイントを思いついてしまう(ブーメラン効果) ・何かをしてほしいときはポジティブな情報、何かをしてほしくないときはネガティブな情報を提供する。(苦痛からは目を背ける習性があるのでネガティブ情報は行動抑止につながる) ・人間は選択を好む。「自分に委託させる」のであっても、それを相手が決めれば相手が選択したことになり納得度が高まる
読み込み中...
