
まいける
@bluesky42195
- 2025年10月21日
 日本語界隈ふかわりょう,川添愛読み終わった感想「日本人の感性は、四拍子が好き!農耕民族であることが関係している。」 なるほど! 三三七拍子は四拍子。七五調も四拍子。 言語学者の川添さんと日本語に拘るふかわさんの対談。ハッとすることばかり。 「拘る」はネガティブだった言葉がポジティブになった例。「やばい」とおんなじだ。 逆に「忖度」はイメージダウンの言葉。例の事件で「流れ弾に当たって」しまった「忖度」を慰めるふかわさんが優しい。 「秋が深まる」「秋の気配」「夏の扉」とは言うけど 「夏が深まる」「夏の気配」「冬の扉」とは言わない。 日本語は曖昧で繊細だけど、頑固だと言う主張はごもっとも。 あ、そうそう「メモる」「サボる」も「る」をつけて生まれ、定着した言葉だよなあ。サボタージュだったのか! 確かに二子玉川を二子玉と略すけど祖師谷大倉を略す人はいない。 「全体主義国家は略語を多用する」という話も目から鱗だった。 川添さんとふかわさんのおかげで日本語の味がさらに深まった。
日本語界隈ふかわりょう,川添愛読み終わった感想「日本人の感性は、四拍子が好き!農耕民族であることが関係している。」 なるほど! 三三七拍子は四拍子。七五調も四拍子。 言語学者の川添さんと日本語に拘るふかわさんの対談。ハッとすることばかり。 「拘る」はネガティブだった言葉がポジティブになった例。「やばい」とおんなじだ。 逆に「忖度」はイメージダウンの言葉。例の事件で「流れ弾に当たって」しまった「忖度」を慰めるふかわさんが優しい。 「秋が深まる」「秋の気配」「夏の扉」とは言うけど 「夏が深まる」「夏の気配」「冬の扉」とは言わない。 日本語は曖昧で繊細だけど、頑固だと言う主張はごもっとも。 あ、そうそう「メモる」「サボる」も「る」をつけて生まれ、定着した言葉だよなあ。サボタージュだったのか! 確かに二子玉川を二子玉と略すけど祖師谷大倉を略す人はいない。 「全体主義国家は略語を多用する」という話も目から鱗だった。 川添さんとふかわさんのおかげで日本語の味がさらに深まった。 - 2025年10月20日
 聞いて、ヴァイオリンの詩千住真理子クラシックヴァイオリン読み終わった感想千住真理子千住真理子さん。私が敬愛するヴァイオリニスト。 なぜだかわからない。千住さんのヴァイオリンを聴くと揺さぶられる。 この本には千住さんのサインがある。2000年11月14日。千住さんのお父さんが亡くなったのがその年の9月2日。哀しみの中でサイン本を贈ってくださった。 この本には、ヴァイオリンを無邪気に楽しんだ幼少期から修行期。そしてヴァイオリンの音を聞くだけで、耳を塞ぎたくなった経験をした彼女がヴァイオリンを再開するまでの魂の彷徨が余すところなく語られている。 「いま必要とされているのは、『心を入れた音』なのだ。」 ホスピスの聴衆の、音を通して感じようとしている「人の体温」だと気づいた彼女は、息をするように、語りかける思いで演奏を進めていったという。 たくさん書きたいことがあったが、それよりも今は千住真理子さんのバッハやイザイやベートーヴェンに耳を傾けたくなった。 彼女の奏でる音楽と対話したくなった。 しっかり生きろ!と叱咤されるかもしれないけど。
聞いて、ヴァイオリンの詩千住真理子クラシックヴァイオリン読み終わった感想千住真理子千住真理子さん。私が敬愛するヴァイオリニスト。 なぜだかわからない。千住さんのヴァイオリンを聴くと揺さぶられる。 この本には千住さんのサインがある。2000年11月14日。千住さんのお父さんが亡くなったのがその年の9月2日。哀しみの中でサイン本を贈ってくださった。 この本には、ヴァイオリンを無邪気に楽しんだ幼少期から修行期。そしてヴァイオリンの音を聞くだけで、耳を塞ぎたくなった経験をした彼女がヴァイオリンを再開するまでの魂の彷徨が余すところなく語られている。 「いま必要とされているのは、『心を入れた音』なのだ。」 ホスピスの聴衆の、音を通して感じようとしている「人の体温」だと気づいた彼女は、息をするように、語りかける思いで演奏を進めていったという。 たくさん書きたいことがあったが、それよりも今は千住真理子さんのバッハやイザイやベートーヴェンに耳を傾けたくなった。 彼女の奏でる音楽と対話したくなった。 しっかり生きろ!と叱咤されるかもしれないけど。 - 2025年10月18日
 地の星宮本輝読み終わった感想宮本輝『流転の海』分厚くて、どうしようか迷ったが、一度踏み込んでしまったらやはり元には戻れなくて第二弾。 故郷、宇和島に帰った熊吾の話。 和田茂十の選挙参謀をするが、その和田茂十がガンになったり、ダンスホールをつくるが、妹の夫がホールの窓から転落して亡くなったりと身近な人が亡くなっていく。 それだけではない。幼馴染の伊佐男が部下に裏切られ、部下に殺される前に拳銃自殺を図ってしまう。これも熊吾が疑われてしまう。 大阪に戻ってまた商売を始めようとするところで終わる。 豪放磊落でチャーミングな熊吾だが、妻への暴力は読んでいてつらい。 息子(宮本輝)育っていくのが楽しみ。
地の星宮本輝読み終わった感想宮本輝『流転の海』分厚くて、どうしようか迷ったが、一度踏み込んでしまったらやはり元には戻れなくて第二弾。 故郷、宇和島に帰った熊吾の話。 和田茂十の選挙参謀をするが、その和田茂十がガンになったり、ダンスホールをつくるが、妹の夫がホールの窓から転落して亡くなったりと身近な人が亡くなっていく。 それだけではない。幼馴染の伊佐男が部下に裏切られ、部下に殺される前に拳銃自殺を図ってしまう。これも熊吾が疑われてしまう。 大阪に戻ってまた商売を始めようとするところで終わる。 豪放磊落でチャーミングな熊吾だが、妻への暴力は読んでいてつらい。 息子(宮本輝)育っていくのが楽しみ。 - 2025年10月16日
 金環日蝕阿部暁子読み終わった感想『カフネ』の読後感がよかったので、阿部曉子さんの世界にふれたくて手にした。 ひったくり犯を捕まえようとする春風と錬。冒頭場面からもう一気に後半まで読んでしまった。 「彼は平時は紳士なので安心してください」 「なら非常時の俺は何なんですか?無鉄砲の権化の春風さんに言われたくないんですけど」 春風と錬の関係も二人の持つ魅力もこの物語の推進力になっている。正義感の塊に見えるふたりのもつ冷徹さと深い闇。 「私は弱い。私は囚われている。」 それを認めることによって踏み出せる未来があるかもしれない。 北海道の豊平川、ふわりと羽根のような雪、白い冬の使者たちが舞い降りてくる空。 大好きな北海道の情景が目に浮かび、善悪で割り切れない闇から光が微かに見えてくる。 今回も阿部曉子さんに魅了された。
金環日蝕阿部暁子読み終わった感想『カフネ』の読後感がよかったので、阿部曉子さんの世界にふれたくて手にした。 ひったくり犯を捕まえようとする春風と錬。冒頭場面からもう一気に後半まで読んでしまった。 「彼は平時は紳士なので安心してください」 「なら非常時の俺は何なんですか?無鉄砲の権化の春風さんに言われたくないんですけど」 春風と錬の関係も二人の持つ魅力もこの物語の推進力になっている。正義感の塊に見えるふたりのもつ冷徹さと深い闇。 「私は弱い。私は囚われている。」 それを認めることによって踏み出せる未来があるかもしれない。 北海道の豊平川、ふわりと羽根のような雪、白い冬の使者たちが舞い降りてくる空。 大好きな北海道の情景が目に浮かび、善悪で割り切れない闇から光が微かに見えてくる。 今回も阿部曉子さんに魅了された。 - 2025年10月15日
 全ての装備を知恵に置き換えること石川直樹読み終わった感想石川直樹過保護な日本の社会に、また科学技術に頼り切った現在の世界に最も欠けていることは「全ての装備を知恵に置き換えること」 石川直樹さんが命の危機に瀕した時、「一種の快感ともいうべき電流が身体を駆け抜ける」という。未知に憧れ、旅をすることが楽しいから旅を続ける。8000メートルの山も、ユーコン川も、白夜の南極も彼のフィールドであり、知恵をフルに働かせ楽しむ場所なのだ。彼は孤高の挑戦者というより、人とのつながり、自然とのつながりを大切にする旅人なのだ。 北極でシロクマと対峙した時の緊張感が伝わってくる。恐れよりも「畏れ」を感じ、敵だとも思えない親近感すら覚えたという。 トイレの話も面白い。海、山、極地、アジアの国々。異郷の地が現実の世界へと変化する瞬間だという。マイナス40度の中でホッキョククマを警戒しながらの排泄は、安息の時間ではないに違いない。 アフガニスタンへの旅も印象深い。 「仏教破壊とテロ事件によって世界がこの国を見捨てようとも、人々の営みは確実にそこにある。」 無数の星空を見上げながら、太古から続く悠久の時に身を委ねている石川直樹さんが目に浮かぶようだ。
全ての装備を知恵に置き換えること石川直樹読み終わった感想石川直樹過保護な日本の社会に、また科学技術に頼り切った現在の世界に最も欠けていることは「全ての装備を知恵に置き換えること」 石川直樹さんが命の危機に瀕した時、「一種の快感ともいうべき電流が身体を駆け抜ける」という。未知に憧れ、旅をすることが楽しいから旅を続ける。8000メートルの山も、ユーコン川も、白夜の南極も彼のフィールドであり、知恵をフルに働かせ楽しむ場所なのだ。彼は孤高の挑戦者というより、人とのつながり、自然とのつながりを大切にする旅人なのだ。 北極でシロクマと対峙した時の緊張感が伝わってくる。恐れよりも「畏れ」を感じ、敵だとも思えない親近感すら覚えたという。 トイレの話も面白い。海、山、極地、アジアの国々。異郷の地が現実の世界へと変化する瞬間だという。マイナス40度の中でホッキョククマを警戒しながらの排泄は、安息の時間ではないに違いない。 アフガニスタンへの旅も印象深い。 「仏教破壊とテロ事件によって世界がこの国を見捨てようとも、人々の営みは確実にそこにある。」 無数の星空を見上げながら、太古から続く悠久の時に身を委ねている石川直樹さんが目に浮かぶようだ。 - 2025年10月13日
 やがて訪れる春のためにはらだみずきはらだみずき読み終わった感想認知症気味の祖母ハルのために、自分がかつて住んでいた家の庭を綺麗にしていく。荒れ放題の庭を。頼まれたわけじゃない。それは、祖母のためだけど、自分自身のためでもあったのかもしれない。 いつか祖母が戻って来られるように、小さい頃、祖母にいただいた有形無形の贈り物を自分でアレンジしていく。花屋さんをもう一度、復活させたい幼なじみたちの存在も大きい。 何より、庭に力強く生きている植物の力が彼女を変えていく。 自然の営みは人智を超えている。 「それらの花は、だれかのために咲いているわけではない。・・・けれどあたかも、自分のために健気に咲いてくれているように見える。人は花に惹かれ、癒され、ときに顔を上げる力を与えてもらう。だからこそ人は、花を愛でるのではないだろうか。」 孫と世話したミニトマトもコスモスも癒やしと力をくれている。 いい小説に出会った。まさに私花集(アンソロジー)のような。
やがて訪れる春のためにはらだみずきはらだみずき読み終わった感想認知症気味の祖母ハルのために、自分がかつて住んでいた家の庭を綺麗にしていく。荒れ放題の庭を。頼まれたわけじゃない。それは、祖母のためだけど、自分自身のためでもあったのかもしれない。 いつか祖母が戻って来られるように、小さい頃、祖母にいただいた有形無形の贈り物を自分でアレンジしていく。花屋さんをもう一度、復活させたい幼なじみたちの存在も大きい。 何より、庭に力強く生きている植物の力が彼女を変えていく。 自然の営みは人智を超えている。 「それらの花は、だれかのために咲いているわけではない。・・・けれどあたかも、自分のために健気に咲いてくれているように見える。人は花に惹かれ、癒され、ときに顔を上げる力を与えてもらう。だからこそ人は、花を愛でるのではないだろうか。」 孫と世話したミニトマトもコスモスも癒やしと力をくれている。 いい小説に出会った。まさに私花集(アンソロジー)のような。 - 2025年10月12日
 山に抱かれた家 迷い道はらだみずきはらだみずき読み終わった感想読み終えて、ふと表紙を見てみると、文哉と凪子が描かれていた。坂を下りていく凪子と振り返った後、坂を上ろうとしている文哉。象徴的な一場面が描かれていた。 文哉は、ずんずん前に進んでいく。本人は否定しても、迷いつつその場に佇んでいる凪子には眩しく取り残されている感があったのではないか。身の危険を心配され、行動も制限され、内に向かうしかなかった凪子。 凪子が以前の場所に戻り、文哉と同じように寂しさが募った。でも、文哉は凄いなあ。自分で決めた生活だから、泣いてもへこたれない。ついに自分で風呂を作りあげる。 「自分は今、幸せだ。」と。 文哉がどんどん遠くなる。親近感や憧れよりも、違う感情が芽生えてくる。文哉が書いた凪子への手紙が凪子にどう届くのか。凪子が自立の手がかりを見つければ関係はまた好転するのか。凪子の心の方が気になってしまう。 続編に期待。
山に抱かれた家 迷い道はらだみずきはらだみずき読み終わった感想読み終えて、ふと表紙を見てみると、文哉と凪子が描かれていた。坂を下りていく凪子と振り返った後、坂を上ろうとしている文哉。象徴的な一場面が描かれていた。 文哉は、ずんずん前に進んでいく。本人は否定しても、迷いつつその場に佇んでいる凪子には眩しく取り残されている感があったのではないか。身の危険を心配され、行動も制限され、内に向かうしかなかった凪子。 凪子が以前の場所に戻り、文哉と同じように寂しさが募った。でも、文哉は凄いなあ。自分で決めた生活だから、泣いてもへこたれない。ついに自分で風呂を作りあげる。 「自分は今、幸せだ。」と。 文哉がどんどん遠くなる。親近感や憧れよりも、違う感情が芽生えてくる。文哉が書いた凪子への手紙が凪子にどう届くのか。凪子が自立の手がかりを見つければ関係はまた好転するのか。凪子の心の方が気になってしまう。 続編に期待。 - 2025年10月11日
 読み終わったPHP研究所感想「秋風に揺れるすすきと母の声」 北海道のみわさんのお嬢さん、小学3年生の詠んだ俳句。「日々の忙しさの中で、家族との時間がいかに大切かを感じた」というみわさん。談話室コーナーで、ひだまりのようなエピソードを見つけた。 「たった一言に、人生が支えられていることがある。」 網走ハーフマラソンに参加した時、「○○さん、がんば」と沿道の方が声をかけてくれた。参加者名簿とゼッケンを照らし合わせてくれたのだろう。あれは力になった。小さかった娘達が網走中央公園で遊んで待っていてくれたのも嬉しい。 ヒューマンドキュメントの大野雅貴さんの「食」の本質と可能性を追究する話も深い。 栗山英樹さんの推薦書は『落日燃ゆ』 広田弘毅さんの人生。読んでみたい。 #栗山英樹 #落日燃ゆ #PHP #大野雅貴
読み終わったPHP研究所感想「秋風に揺れるすすきと母の声」 北海道のみわさんのお嬢さん、小学3年生の詠んだ俳句。「日々の忙しさの中で、家族との時間がいかに大切かを感じた」というみわさん。談話室コーナーで、ひだまりのようなエピソードを見つけた。 「たった一言に、人生が支えられていることがある。」 網走ハーフマラソンに参加した時、「○○さん、がんば」と沿道の方が声をかけてくれた。参加者名簿とゼッケンを照らし合わせてくれたのだろう。あれは力になった。小さかった娘達が網走中央公園で遊んで待っていてくれたのも嬉しい。 ヒューマンドキュメントの大野雅貴さんの「食」の本質と可能性を追究する話も深い。 栗山英樹さんの推薦書は『落日燃ゆ』 広田弘毅さんの人生。読んでみたい。 #栗山英樹 #落日燃ゆ #PHP #大野雅貴 - 2025年10月9日
 永遠のおでかけ益田ミリ読み終わった買った感想益田ミリ身近な人が亡くなるということの重みを改めて感じる。 たとえ時間が経って残酷なほど忘却を促進するにせよ。 紅白歌合戦の最中に、落ち着きのないお父さんを、もう何とかしてと思っていても、居なくなったらむしょうに寂しい。歌合戦に集中できるのに。 「父の死によって、わたしの心の中にも穴が空いたようだった。・・・のぞいても底は見えず、深さもわからない。しばらくは、その穴の前に立っただけで悲しい。」 私の両親は既に他界したが、この本を読むことによって記憶がよみがえってきた。 お風呂に薪をくべている母の姿。目を悪くして、母に新聞を読んでもらってる父の姿。孫がうまれて笑みを浮かべる父、母の顔。
永遠のおでかけ益田ミリ読み終わった買った感想益田ミリ身近な人が亡くなるということの重みを改めて感じる。 たとえ時間が経って残酷なほど忘却を促進するにせよ。 紅白歌合戦の最中に、落ち着きのないお父さんを、もう何とかしてと思っていても、居なくなったらむしょうに寂しい。歌合戦に集中できるのに。 「父の死によって、わたしの心の中にも穴が空いたようだった。・・・のぞいても底は見えず、深さもわからない。しばらくは、その穴の前に立っただけで悲しい。」 私の両親は既に他界したが、この本を読むことによって記憶がよみがえってきた。 お風呂に薪をくべている母の姿。目を悪くして、母に新聞を読んでもらってる父の姿。孫がうまれて笑みを浮かべる父、母の顔。 - 2025年10月8日
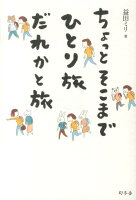 借りてきた読み終わった感想益田ミリ私は小さい頃から、チョコレートが好きだった。小さなガーナチョコが売られていた時代から。マーブル、アポロチョコ、そして頂点に立つのはコーヒービート。どんな有名メーカーの輸入チョコでも、コーヒービートに勝利したことはない。 でも、益田ミリさんがフィンランドで食べた「カフェ・カール・フェッツェル」は強敵になりそうだ。そういえば函館の「ショコラヴォヤージュ」はかなり美味しかった。 益田ミリさんは不思議な存在だ。 彼女ができないことはできないと言い切ってるところがいいのだ。謙虚。 奈良公園で修学旅行で、ひとり行動している子への目線が優しい。 「はやく『大人』という場所に逃げておいで。大人になれば少しだけ自由だよ。ひとり旅に出たって平気だよ。」とビームをおくる。 「もう金沢来ることもないかもしれんなぁ」彼女の母がポツリと言う。 寂しい一言。だからこそ旅行に誘い、時間を共にしているんだな、ミリさんは。
借りてきた読み終わった感想益田ミリ私は小さい頃から、チョコレートが好きだった。小さなガーナチョコが売られていた時代から。マーブル、アポロチョコ、そして頂点に立つのはコーヒービート。どんな有名メーカーの輸入チョコでも、コーヒービートに勝利したことはない。 でも、益田ミリさんがフィンランドで食べた「カフェ・カール・フェッツェル」は強敵になりそうだ。そういえば函館の「ショコラヴォヤージュ」はかなり美味しかった。 益田ミリさんは不思議な存在だ。 彼女ができないことはできないと言い切ってるところがいいのだ。謙虚。 奈良公園で修学旅行で、ひとり行動している子への目線が優しい。 「はやく『大人』という場所に逃げておいで。大人になれば少しだけ自由だよ。ひとり旅に出たって平気だよ。」とビームをおくる。 「もう金沢来ることもないかもしれんなぁ」彼女の母がポツリと言う。 寂しい一言。だからこそ旅行に誘い、時間を共にしているんだな、ミリさんは。 - 2025年10月7日
 雲のピアノ (わくわくライブラリー)あまんきみこあまんきみこ借りてきた読み終わった感想絵本・児童書ヒロシと妹のチカは、ピアノ調律師の青木さんと仲良し。 青木さんはピアノの病気を治す天才だから不思議な依頼がやってくる。 ねこやねずみ、きつねやうさぎたちからの依頼は、海のピアノに海のピアノ、花のピアノとそれはそれはすてきで難しいものばかり。 現実の世界からいつの間にか動物たちの世界に入ってしまうあたりあまんきみこさんの魅魔力! 子どもたちといっしょに出かけたくなる世界。 3歳から小学生までたのしめる本。 もっともっとあまんきみこさんを知りたくなる。
雲のピアノ (わくわくライブラリー)あまんきみこあまんきみこ借りてきた読み終わった感想絵本・児童書ヒロシと妹のチカは、ピアノ調律師の青木さんと仲良し。 青木さんはピアノの病気を治す天才だから不思議な依頼がやってくる。 ねこやねずみ、きつねやうさぎたちからの依頼は、海のピアノに海のピアノ、花のピアノとそれはそれはすてきで難しいものばかり。 現実の世界からいつの間にか動物たちの世界に入ってしまうあたりあまんきみこさんの魅魔力! 子どもたちといっしょに出かけたくなる世界。 3歳から小学生までたのしめる本。 もっともっとあまんきみこさんを知りたくなる。 - 2025年10月7日
 海が見える家 旅立ちはらだみずきはらだみずき借りてきた読み終わった感想『海の見える家』シリーズの最終作。 ああ、これで文哉の父が房総に移り住んだ理由も、文哉が次に山を目指した理由もはっきりした。 文哉も凪子も大切な人を亡くした喪失感と最後の言葉が無意識の底まで沈みこんで、殻をつくってしまったのだろう。 だからこそ二人は打ち解け合い、自然な呼吸ができたんだろう。 二人が新しい場所を目指すことが、とりもなおさず古い殻を脱ぎ捨てることに繋がっていくんだろうな。 納得のいくシリーズ最終作だった。 はらだみずきさんの作品にふれると、毎日丁寧に過ごしたくなる。食べ物も資源も大切にしたくなる。 小学6年生の国語の教科書に、『海のいのち』という作品があるが、それに通じるものがある。海の恵みに感謝するだけでなく、父と同じものを追い求めることで、真に父を理解すると言う意味でも。
海が見える家 旅立ちはらだみずきはらだみずき借りてきた読み終わった感想『海の見える家』シリーズの最終作。 ああ、これで文哉の父が房総に移り住んだ理由も、文哉が次に山を目指した理由もはっきりした。 文哉も凪子も大切な人を亡くした喪失感と最後の言葉が無意識の底まで沈みこんで、殻をつくってしまったのだろう。 だからこそ二人は打ち解け合い、自然な呼吸ができたんだろう。 二人が新しい場所を目指すことが、とりもなおさず古い殻を脱ぎ捨てることに繋がっていくんだろうな。 納得のいくシリーズ最終作だった。 はらだみずきさんの作品にふれると、毎日丁寧に過ごしたくなる。食べ物も資源も大切にしたくなる。 小学6年生の国語の教科書に、『海のいのち』という作品があるが、それに通じるものがある。海の恵みに感謝するだけでなく、父と同じものを追い求めることで、真に父を理解すると言う意味でも。 - 2025年10月6日
 海が見える家 逆風はらだみずきはらだみずき借りてきた読み終わった感想『海の見える家 逆風』 逆風どころではない。房総半島を大型台風が直撃した。 文哉の家も管理している別荘も屋根を飛ばされたりして大きな被害を受ける。 一夜にして被災者なった文哉。 でも、世話になっている人を探したり、屋根にブルーシートを張ったりして献身的に働く。 何よりよかったのは、台風の被害を受けたとはいえ、収穫した陸稲をみんなにふるまう場面。自分が作った初めてのお米をみんなで分かち合う。玄米塩結びをうまいうまいと食べる様が目に浮かぶ。特に別荘の被害が酷かった寺島が「芳雄さんが生きてたら、きっと喜んだと思う。こんなときに、みんなを笑わせ、勇気づけてる。さぞ誇りに思っただろうよ。」としみじみ語る。じーんときた。 文哉のこれからにさらに注目したい。
海が見える家 逆風はらだみずきはらだみずき借りてきた読み終わった感想『海の見える家 逆風』 逆風どころではない。房総半島を大型台風が直撃した。 文哉の家も管理している別荘も屋根を飛ばされたりして大きな被害を受ける。 一夜にして被災者なった文哉。 でも、世話になっている人を探したり、屋根にブルーシートを張ったりして献身的に働く。 何よりよかったのは、台風の被害を受けたとはいえ、収穫した陸稲をみんなにふるまう場面。自分が作った初めてのお米をみんなで分かち合う。玄米塩結びをうまいうまいと食べる様が目に浮かぶ。特に別荘の被害が酷かった寺島が「芳雄さんが生きてたら、きっと喜んだと思う。こんなときに、みんなを笑わせ、勇気づけてる。さぞ誇りに思っただろうよ。」としみじみ語る。じーんときた。 文哉のこれからにさらに注目したい。 - 2025年10月6日
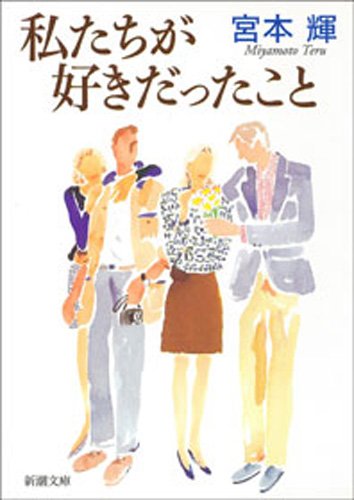 私たちが好きだったこと宮本輝読み終わった買った感想宮本輝韓国ドラマのハッピーエンド、大団円が染み付いた身体には堪える結末だった。 きっと与志に思い切り感情移入して読んでいたからだろう。 「俺たち、人の幸福のために何か手助けすることが好きなんだよ。」 こう自分に言い聞かせて、与志は愛子が自分の夢を叶えるために、愛子との生活を諦める。 愛は相手の幸福を祈ること、それが若さなのかもしれないし、現実を経済的な現実を変えることのできなかった現実の重さなのかもしれない。 不安神経症の愛子に寄り添っていた与志だけに、辛すぎる。 宮本輝さんの小説は、きっと孤独と向き合って生きろと叱咤しているのだろう。
私たちが好きだったこと宮本輝読み終わった買った感想宮本輝韓国ドラマのハッピーエンド、大団円が染み付いた身体には堪える結末だった。 きっと与志に思い切り感情移入して読んでいたからだろう。 「俺たち、人の幸福のために何か手助けすることが好きなんだよ。」 こう自分に言い聞かせて、与志は愛子が自分の夢を叶えるために、愛子との生活を諦める。 愛は相手の幸福を祈ること、それが若さなのかもしれないし、現実を経済的な現実を変えることのできなかった現実の重さなのかもしれない。 不安神経症の愛子に寄り添っていた与志だけに、辛すぎる。 宮本輝さんの小説は、きっと孤独と向き合って生きろと叱咤しているのだろう。 - 2025年10月5日
 海が見える家 それからはらだみずきはらだみずき借りてきた読み終わった感想続編でさらに面白みが増している。 それは文哉が自分にできることを次々に見つけて 自立への道を歩んでいるから。 もちろん精神的には自立している。 彼の周りの人もすばらしい。 カズさん 幸吉さん それは純粋に畑仕事や魚とり、別荘管理、そしつ姉が投げ出した店をやっているから。謙虚な彼だから周囲の人も彼を応援していく。 凪子との距離が少しずつ少しずつ縮まっているのもわくわくする。 自然農法、そして今度は陸稲に挑戦か。 野菜を収穫した喜びや育てる楽しさを伝えてくれる中学時代の友人と重なる。 そういえば子どもの頃、道で草野球していたとなりの畑では陸稲やトウモロコシが育っていた。懐かしい!
海が見える家 それからはらだみずきはらだみずき借りてきた読み終わった感想続編でさらに面白みが増している。 それは文哉が自分にできることを次々に見つけて 自立への道を歩んでいるから。 もちろん精神的には自立している。 彼の周りの人もすばらしい。 カズさん 幸吉さん それは純粋に畑仕事や魚とり、別荘管理、そしつ姉が投げ出した店をやっているから。謙虚な彼だから周囲の人も彼を応援していく。 凪子との距離が少しずつ少しずつ縮まっているのもわくわくする。 自然農法、そして今度は陸稲に挑戦か。 野菜を収穫した喜びや育てる楽しさを伝えてくれる中学時代の友人と重なる。 そういえば子どもの頃、道で草野球していたとなりの畑では陸稲やトウモロコシが育っていた。懐かしい! - 2025年10月4日
 おかあさんの目くろいけん,あまんきみこあまんきみこ読み終わった感想絵本あまんきみこさんとの出会いは谷山浩子さんの歌。 『すずかけ通り三丁目』 リサイタルでも歌ってくれた『車のいろは空のいろ』の不思議な世界。はてなアンテナの谷山浩子さんにピッタリだった。 今日、『おかあさんの目』を手に取った。 お母さんの膝の上でお母さんの瞳に映る小さなわたしを見つけるせつこちゃん。 お母さんの瞳に映る世界をふり返りふり返り確かめてにっこりしていたせつこちゃん。 でも、ある時、小さなわたしが見えなくなって、かわりにちがうものが見え始める。 あ、ミステリーではありません。 母と子 あまりに美しい姿に胸の奥までぽかぽかします。 黒井健さんのイラストがさらにかんどうを ふかめてくれます。 娘にプレゼントしよう。
おかあさんの目くろいけん,あまんきみこあまんきみこ読み終わった感想絵本あまんきみこさんとの出会いは谷山浩子さんの歌。 『すずかけ通り三丁目』 リサイタルでも歌ってくれた『車のいろは空のいろ』の不思議な世界。はてなアンテナの谷山浩子さんにピッタリだった。 今日、『おかあさんの目』を手に取った。 お母さんの膝の上でお母さんの瞳に映る小さなわたしを見つけるせつこちゃん。 お母さんの瞳に映る世界をふり返りふり返り確かめてにっこりしていたせつこちゃん。 でも、ある時、小さなわたしが見えなくなって、かわりにちがうものが見え始める。 あ、ミステリーではありません。 母と子 あまりに美しい姿に胸の奥までぽかぽかします。 黒井健さんのイラストがさらにかんどうを ふかめてくれます。 娘にプレゼントしよう。 - 2025年10月3日
 両手いっぱいの言葉寺山修司読み終わった買った感想寺山修司齋藤孝さんが推薦していたので手に取った一冊。 そもそも齋藤孝さんのイメージと寺山修司さんとイメージはあまりにもかけ離れているから興味をもったとも言える。 *親の愛情、とりわけ母親の愛情というものはいつもかなしい。いつもかなしいというのは、それがつねに「片恋」だからです。 *ただ、たしかなことは自分の未来が自分の肉体の中にしかない、ということであり、世界史は自分の血管を潜り抜けるときにはじめてはっきりとした意味を持つものだ。 *不自由を知るものでないと、自由は語れません。 *子供は子供として完成しているのであって、大人の模型ではない。 *時計の針が 前にすすむと「時間」になります 後にすすむと「思い出」になります *夢の中は治外法権である。 *いい「言葉」を沢山もつことは、銀行に沢山、預金するよりもゆたかなことである。 言葉が両手からあふれていった。 この本を片手に旅に出かけるフットワークがほしい。
両手いっぱいの言葉寺山修司読み終わった買った感想寺山修司齋藤孝さんが推薦していたので手に取った一冊。 そもそも齋藤孝さんのイメージと寺山修司さんとイメージはあまりにもかけ離れているから興味をもったとも言える。 *親の愛情、とりわけ母親の愛情というものはいつもかなしい。いつもかなしいというのは、それがつねに「片恋」だからです。 *ただ、たしかなことは自分の未来が自分の肉体の中にしかない、ということであり、世界史は自分の血管を潜り抜けるときにはじめてはっきりとした意味を持つものだ。 *不自由を知るものでないと、自由は語れません。 *子供は子供として完成しているのであって、大人の模型ではない。 *時計の針が 前にすすむと「時間」になります 後にすすむと「思い出」になります *夢の中は治外法権である。 *いい「言葉」を沢山もつことは、銀行に沢山、預金するよりもゆたかなことである。 言葉が両手からあふれていった。 この本を片手に旅に出かけるフットワークがほしい。 - 2025年10月3日
 海が見える家はらだみずきはらだみずき借りてきた読み終わった感想『山に抱かれた家』から原点に戻って『海が見える家』 あー、そうだったのか。 文哉のお父さんと三年も会ってなかったのか。 お父さんが亡くなった。寝耳に水のような、ぶっきらぼうさんから連絡。そこから物語が始まる。 父が知らない場所でどんな生活をしていたのか。 なぜ房総の海を選んだのか。 父の遺品を整理しながらだんだん謎が解けていく。 周りの人との関わり。 秘めていた想い。 そして山にも出てきた凪子との出会い。 順番が前後したからこそ 繋がった悦びが大きい! だんだん変わっていく文哉。 そして、父の見ていた風景を見ようと 父と同じ体験にトライしていく。 亡くなって初めて父の存在の大きさに気づき もっともっと父と話しておけばよかったと 後悔していた自分を思い出した。 今からでも遅くない。 父が好きだった場所を訪ね、父が好きだった本を読みたい。
海が見える家はらだみずきはらだみずき借りてきた読み終わった感想『山に抱かれた家』から原点に戻って『海が見える家』 あー、そうだったのか。 文哉のお父さんと三年も会ってなかったのか。 お父さんが亡くなった。寝耳に水のような、ぶっきらぼうさんから連絡。そこから物語が始まる。 父が知らない場所でどんな生活をしていたのか。 なぜ房総の海を選んだのか。 父の遺品を整理しながらだんだん謎が解けていく。 周りの人との関わり。 秘めていた想い。 そして山にも出てきた凪子との出会い。 順番が前後したからこそ 繋がった悦びが大きい! だんだん変わっていく文哉。 そして、父の見ていた風景を見ようと 父と同じ体験にトライしていく。 亡くなって初めて父の存在の大きさに気づき もっともっと父と話しておけばよかったと 後悔していた自分を思い出した。 今からでも遅くない。 父が好きだった場所を訪ね、父が好きだった本を読みたい。 - 2025年10月2日
 山に抱かれた家はらだみずきはらだみずき借りてきた読み終わった感想大学進学で田舎を出て、一人暮らしをした時、蚊がいないので、都会っていいなあと思った。 そういえば、故郷にはムカデもしたし、ヘビが家の中に入り込んできた。見たことはないけど、イノシシもいたらしい。 だから、限界集落に住んで、自給自足の生活をしていこうとする文哉くんには憧れの念は抱かない。でも、文哉くんの生き方を応援したくなる。梅が売れた瞬間には一緒にガッツポーズをしてしまった。 最後の凪子からの便りに救われる。 凪子がいれば心強い。 初めてのはらだみずきさん。 しっかりと土の香りがした。 地に足をつけて生きている人特有の。
山に抱かれた家はらだみずきはらだみずき借りてきた読み終わった感想大学進学で田舎を出て、一人暮らしをした時、蚊がいないので、都会っていいなあと思った。 そういえば、故郷にはムカデもしたし、ヘビが家の中に入り込んできた。見たことはないけど、イノシシもいたらしい。 だから、限界集落に住んで、自給自足の生活をしていこうとする文哉くんには憧れの念は抱かない。でも、文哉くんの生き方を応援したくなる。梅が売れた瞬間には一緒にガッツポーズをしてしまった。 最後の凪子からの便りに救われる。 凪子がいれば心強い。 初めてのはらだみずきさん。 しっかりと土の香りがした。 地に足をつけて生きている人特有の。 - 2025年10月1日
 流転の海宮本輝読み終わった買った感想宮本輝松坂熊吾の破天荒な半生。熊吾は、息子の具合が悪くなると、かかりつけの病院をこじ開け、 「もし息子が死んだら、この病院に火ィつけちゃるぞ」 と叫び、診断がくだると涙ぐんで、 「安心しました。ありがとうございました」 と言う。孫と間違えられるほど歳の離れた息子伸仁を溺愛する愛すべき親父だ。 好色で、時に暴力的で、はったり上手な熊吾は、スケールが大きい。学歴はないが、時代を読む力、勘が鋭い。そして、裏切られ騙されても、人を裏切らない。 熊吾の言葉は残るものが多い。 「何の天分もない人間は、ただのひとりもこの世におらん。」 どうやったら、懐の深い、他人の心のわかる人間に育てあげることが出来るだろうと考えた。 「(息子に)苦労させるんじゃ。辛いめに遭わせるんじゃ」 郷里に帰る松坂熊吾、房江、そして病気がちな子、伸仁。続きが楽しみ。伸仁がどう成長していくのか。
流転の海宮本輝読み終わった買った感想宮本輝松坂熊吾の破天荒な半生。熊吾は、息子の具合が悪くなると、かかりつけの病院をこじ開け、 「もし息子が死んだら、この病院に火ィつけちゃるぞ」 と叫び、診断がくだると涙ぐんで、 「安心しました。ありがとうございました」 と言う。孫と間違えられるほど歳の離れた息子伸仁を溺愛する愛すべき親父だ。 好色で、時に暴力的で、はったり上手な熊吾は、スケールが大きい。学歴はないが、時代を読む力、勘が鋭い。そして、裏切られ騙されても、人を裏切らない。 熊吾の言葉は残るものが多い。 「何の天分もない人間は、ただのひとりもこの世におらん。」 どうやったら、懐の深い、他人の心のわかる人間に育てあげることが出来るだろうと考えた。 「(息子に)苦労させるんじゃ。辛いめに遭わせるんじゃ」 郷里に帰る松坂熊吾、房江、そして病気がちな子、伸仁。続きが楽しみ。伸仁がどう成長していくのか。
読み込み中...