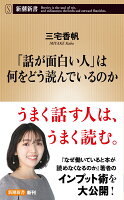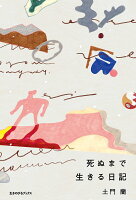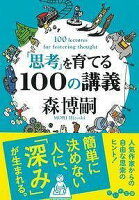萌英
@moenohon
♥️「飛ぶ教室」「西の魔女が死んだ」
- 2025年10月19日
 この世にたやすい仕事はない津村記久子読みたい
この世にたやすい仕事はない津村記久子読みたい - 2025年10月19日
- 2025年10月19日
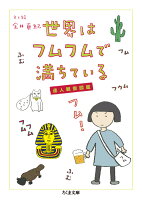 世界はフムフムで満ちている金井真紀読みたい
世界はフムフムで満ちている金井真紀読みたい - 2025年10月19日
- 2025年10月19日
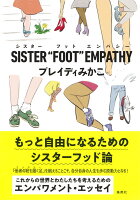 SISTER“FOOT”EMPATHYブレイディみかこ読みたい
SISTER“FOOT”EMPATHYブレイディみかこ読みたい - 2025年10月19日
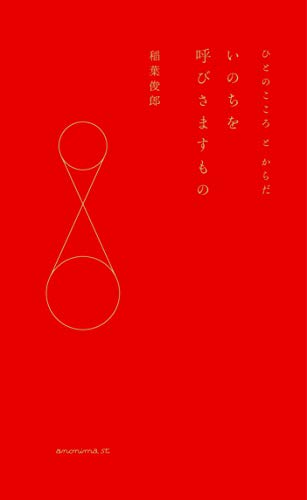 読んでる私だけでなく、どんな人でも命がけの時代を経て、今を生きている。誰ひとりとして例外はない。赤ちゃんとして生まれてきた時は、誰もが圧倒的に弱い存在だった。誰かに守られ、大切にされないと生きていることすら保てなかったはずなのだ。今、生きているということは、誰もがそうした時代を経て、生き残っているということの証でもある。 ただ、多くの人はそのことを忘れてしまっている。赤ちゃんや子どもを見て、そこに過去の自分を重ね合わせてみることは、忘れてしまった自分の来歴を思い出すためにも重要なことだ。 「自分」という存在は、思っている以上に広く深く大きな存在で、なかなかその全体像は見えにくい。頭の先から足の先まで、体の表面から内臓まで、起きている時から寝ている時まで、生まれ落ちてから死んでゆくまでを含んでいて、人類という種や、生命という流れ全体をも含んでいる。 生後すぐや数日で命を落とす場合もあれば、病気で亡くなる子どももいるし、複雑な病や障がいを多数抱えながら生きている人もいる。困難に直面し、どうしようもない大きな運命に流されるような人生を垣間見ると、ふとそうした人間の生命現象の根本について考えざるを得なくなる。 だからこそ日々の診療では、体だけを診るのではなく、心や命そのものと向き合ってきたつもりだ。自己満足かもしれないが、そう思って取り組まないと、自分自身とも折り合いがつかない。 今一度、自分自身にとって「健康」とは何か、「健康な状態」とはどういうものかを考えてみた。それは、生きる実感と生きる喜びを自然に感じている時だ。そして、周囲の人々に対して、「ありがたい」という思いが自然にふつふつと湧き起こる時でもある。 私の場合、子どもの頃は思うように体が動かず、何かをすればすぐ熱を出し、寝て過ごすだけの日も多かった。でも、そうした体の不自由さ以上に、精一杯、日々を生きていた。 誰かを恨むこともなく、誰かのせいにすることもなく、与えられた条件をまるごと受け止めながら。痛かったり苦しかったことも多かったが、すべてをありのまま受け入れ、全身全霊で生きていた。毎日が生きている実感にあふれていた。そして、同時に、周りの人々のおかげでこうして生きているのだと、どこから湧いてくるのかわからない感謝や幸福感で心は満ちていた。 傍目には、病気に苦しむかわいそうな子どもに見えたかもしれないが、自分にとっては心も体も満たされていたのだと思うし、そうした過去の自分の体験や記憶が、今の自分の「健康」への基準になっていることにも気づく。 今、私は生きていることを強く感じている。それは自分自身の力だけではなく、周囲からのあらゆる協力のおかげであることも同時に強く実感している。こうした心身の状態が、私にとっての「健康」だ。そうでない時は、生きている実感が持てないし、誰かを思いやる余裕もない。
読んでる私だけでなく、どんな人でも命がけの時代を経て、今を生きている。誰ひとりとして例外はない。赤ちゃんとして生まれてきた時は、誰もが圧倒的に弱い存在だった。誰かに守られ、大切にされないと生きていることすら保てなかったはずなのだ。今、生きているということは、誰もがそうした時代を経て、生き残っているということの証でもある。 ただ、多くの人はそのことを忘れてしまっている。赤ちゃんや子どもを見て、そこに過去の自分を重ね合わせてみることは、忘れてしまった自分の来歴を思い出すためにも重要なことだ。 「自分」という存在は、思っている以上に広く深く大きな存在で、なかなかその全体像は見えにくい。頭の先から足の先まで、体の表面から内臓まで、起きている時から寝ている時まで、生まれ落ちてから死んでゆくまでを含んでいて、人類という種や、生命という流れ全体をも含んでいる。 生後すぐや数日で命を落とす場合もあれば、病気で亡くなる子どももいるし、複雑な病や障がいを多数抱えながら生きている人もいる。困難に直面し、どうしようもない大きな運命に流されるような人生を垣間見ると、ふとそうした人間の生命現象の根本について考えざるを得なくなる。 だからこそ日々の診療では、体だけを診るのではなく、心や命そのものと向き合ってきたつもりだ。自己満足かもしれないが、そう思って取り組まないと、自分自身とも折り合いがつかない。 今一度、自分自身にとって「健康」とは何か、「健康な状態」とはどういうものかを考えてみた。それは、生きる実感と生きる喜びを自然に感じている時だ。そして、周囲の人々に対して、「ありがたい」という思いが自然にふつふつと湧き起こる時でもある。 私の場合、子どもの頃は思うように体が動かず、何かをすればすぐ熱を出し、寝て過ごすだけの日も多かった。でも、そうした体の不自由さ以上に、精一杯、日々を生きていた。 誰かを恨むこともなく、誰かのせいにすることもなく、与えられた条件をまるごと受け止めながら。痛かったり苦しかったことも多かったが、すべてをありのまま受け入れ、全身全霊で生きていた。毎日が生きている実感にあふれていた。そして、同時に、周りの人々のおかげでこうして生きているのだと、どこから湧いてくるのかわからない感謝や幸福感で心は満ちていた。 傍目には、病気に苦しむかわいそうな子どもに見えたかもしれないが、自分にとっては心も体も満たされていたのだと思うし、そうした過去の自分の体験や記憶が、今の自分の「健康」への基準になっていることにも気づく。 今、私は生きていることを強く感じている。それは自分自身の力だけではなく、周囲からのあらゆる協力のおかげであることも同時に強く実感している。こうした心身の状態が、私にとっての「健康」だ。そうでない時は、生きている実感が持てないし、誰かを思いやる余裕もない。 - 2025年10月4日
- 2025年9月5日
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広読んでる読みたい「c!」とうしろからレジーナが大声でいった。彼女がはっきり自分の意見をいうことはめったにない。自分の殻から出てきてくれるのはうれしい。 「ちょっとずるいが、正解!」ぼくは彼女めがけてお手玉を放った。
プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広読んでる読みたい「c!」とうしろからレジーナが大声でいった。彼女がはっきり自分の意見をいうことはめったにない。自分の殻から出てきてくれるのはうれしい。 「ちょっとずるいが、正解!」ぼくは彼女めがけてお手玉を放った。 - 2025年7月30日
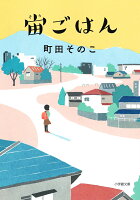 宙ごはん町田そのこ読み終わった「向こうはこっちを振り回すくせに、文句を言うと傷ついた顔するって、ずるいよね。しかもうちの母親、わたしがちょっと文句言ったら何も言えずに逃げ出しちゃったんだよ。卑法だって呆れた。でも、同じくらい、言わなきゃよかったって思った」 「そんなもんだよ。でも、宙ちゃんが後悔する必要はない。言っていいんだよ。親なんだから、子どものまっとうな意見くらい、受け止めてもらおうじゃん。あたしもね、最近は口答えするし出嘩もするようになったよ。五回に一回くらいは謝ってくれるかな。超進歩」マリーは、親のありようを受け入れた上で、向き合おうとしている。宙はそれをひしひしと感じた。この子はわたしよりもっと早いうちから苦しみ、悩んできたのだ。
宙ごはん町田そのこ読み終わった「向こうはこっちを振り回すくせに、文句を言うと傷ついた顔するって、ずるいよね。しかもうちの母親、わたしがちょっと文句言ったら何も言えずに逃げ出しちゃったんだよ。卑法だって呆れた。でも、同じくらい、言わなきゃよかったって思った」 「そんなもんだよ。でも、宙ちゃんが後悔する必要はない。言っていいんだよ。親なんだから、子どものまっとうな意見くらい、受け止めてもらおうじゃん。あたしもね、最近は口答えするし出嘩もするようになったよ。五回に一回くらいは謝ってくれるかな。超進歩」マリーは、親のありようを受け入れた上で、向き合おうとしている。宙はそれをひしひしと感じた。この子はわたしよりもっと早いうちから苦しみ、悩んできたのだ。 - 2025年6月18日
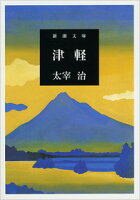 津軽太宰治読んでる
津軽太宰治読んでる - 2025年6月18日
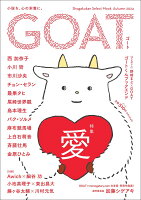 GOATチョン・セラン,小川哲,尾崎世界観,市川沙央,西加奈子読んでる
GOATチョン・セラン,小川哲,尾崎世界観,市川沙央,西加奈子読んでる - 2025年4月17日
 おちゃめなふたごブライトン,佐伯紀美子読み終わった
おちゃめなふたごブライトン,佐伯紀美子読み終わった - 2025年4月15日
 グラスホッパー (角川文庫)伊坂幸太郎読み終わった
グラスホッパー (角川文庫)伊坂幸太郎読み終わった - 2025年3月20日
- 2025年3月16日
 医者の父が息子に綴る 人生の扉をひらく鍵中山祐次郎読み終わった言い換えると、優しさとは、他者の持つ、自分とは異なる考え方や感じ方を尊重し、想像すると いうことなのだ。 いち医学生だった僕に何かができるわけではない。逆に、僕にできることはなんだろうかと考え、悩み抜いた未に出た答えが「たくさんお話をすること」だったのだ。それ以外なかったとも言えるけど。 あの患者さんとたくさんお話をしたおかげで、僕は優しさの正体に気がついたのだ。 それからは、患者さんにお会いするたびに、そして患者さんだけでなく新しく友達に出会うたびに、いつも「相手の気持ちを本気で考える」ことをやるように心がけている。いつもいつもうまくいくわけじゃないけどね。 「来年死んでしまうとしたら、君は今何をしますか?」すると、湧き上がるものがあるはずだ。 僕はこの魔法の質問をしょっちゅう自分に投げかけている。そして、きちんと自分の夢中にまっすぐ歩めるように軌道修正しているのだ。 もしこのマジック・クエスチョンで何も思わなかったなら、次の質問がある。これらに答えてほしい。 「来年目が見えなくなってしまうとしたら、今年どこで何を見たい?」「来年外に出かけられなくなってしまうとしたら、今年どこに行きたい?」 「来年何も食べられなくなるとしたら、何を食べたい?」「来年誰にも会えなくなるとしたら、今年会っておきたい人は誰?」 答えから、君が本当に見たいものや行きたいところ、食べたいものや会いたい人がわかるはずだ。 君はもしかしたらまだ考えたことがないかもしれないが、実は人間の死亡率は100%なのだ。これを書いている僕はいずれ死ぬ。そして読んでいる君もまた、必ずいつか死ぬのである。 この「人生の締め切り」が来る前に、やりたいことをやっておかねば。僕はそう思い、この本を書き始めたんだ。伝える前に死んでしまったら、何も伝えられないからね。 丸坊主になって勉強をした浪人の2年間、勉強し続けて無数の試験に合格し続けた医学部の6年。ここまで来て、医者にならない選択肢はない。 他の学部と異なり、医学部は入った時から医者になるべく職業訓練を受け続けるのだ。 「絶対に落ちることのできない試験」 そんな恐怖が、僕ら6年生を覆っていた。 僕は、朝は6時から、夜は23時まで桜ヶ丘にある医学部キャンパスの自習室にいた。 そして週末には必ず息抜きのため飲みに行った。殺気立った同級生と行っても息が詰まるので、鹿児島銀行勤めの友人と高校教師の友人とよく行ったものだった。酒を飲んだ翌日にも、必ず6時には勉強を始めた。 あっという間に12月が終わり、新しい年がやってきた。 僕が医者になるか、浪人になるかが決まる年だ。 恒例の年末年始の帰省はせず、僕は鹿児島で勉強し続けた。落ちるわけにはいかなかった。 1000を超える病気。それらの原因や症状、治療法を、自作のゴロで頭に叩き込んだ暗記は苦手だったが、そんなことは言っていられない。 「それではここで、解答をやめてください」 2007年2月19日。大きな体の試験官の太い声で、ついに3日間にわたる医師国家試験が終わった。 500問、合計16時間と15分。僕は心も体も芯からくたびれていた。この試験のために半年の間、毎日16時間ほど勉強をし続けてきた。 黒いスーツの女性が解答用紙を回収している。 頭に浮かんだのは、「大きな災害や病気、事故にあわずに試験を受けられたことへの感謝」だった。 もし大きな地震が起きたら、もし感染症が流行したら、もしホテルから試験会場までのバスが事故を起こしたら。 「医学的知識」の高い山頂に、僕はいた。一度転げたら、もう二度と到達できないだろう高み。大学での実習をし、無数の試験を受け、さらに勉強しけてやっとたどり着いた高み。 すべてのタイミングが揃い、なんとか奇跡的に登りきれたのだ。 どんな仕事も、人とつながっている。「あの人に任せれば大丈夫」という評価を少しずつ積み重ねてたどり着いた高さが、君ができる一番大きな仕事なのだ。 僕は、南日本新聞のエッセイを全力で書いた。1ヶ月に1本を書くために、丸々1ヶ月ずっと考え続けたこともあった。 そうしたら、ありがたいことに「ベスト・エッセイ2023』という本に選出してもらえたし、鹿児島の財界人が集まるところで講演する機会ももらえた。さらに鹿児島の本屋さんでは、僕の小説が出るたびに大変な数を陳列してもらえるようになったのだ。 小さな仕事の先にしか、黄金の果実はないことを知ってほしいと思う。 自分の目というフィルターを通して、起きていることを見て、自分の頭で判断する。何が正しいかわからないこの世界で、必ず自分の目で見ること。 そのためには、世界のあちこちに旅行しなければいけない。生まれ育った場所が違い、目と肌の色が違う人がどんなことを考えているのか。直接会って、君が話すんだ。そうしなければ、正しく理解をすることはできない。 そのために共通の言語を学ぶ必要がある。 つまり外国語を学ぶのだ。 上司が、「中山はこれだけ頑張っている、やらせないわけにはいかない」と思わざるを得ないような熱意だ。その熱意を示すにはどうすればいいだろうか。単純なことだ。 僕は朝一番に来て誰よりも雑用をし、夜は一番最後まで残って後輩の指導をした。そして日中の空いた時間には必ず自分の業務と直接は関係ない手術を見学した。さらに、手術ではない仕事、学会発表や論文作成といった仕事も全力でやった。 その頃、僕はそういう仕事を人の3倍やろうと思っていたし、実際に3倍くらいやっていたと思う。 そのためには夜遅くまで病院のデスクでパソコンに向かったし、休日も遊びに行かずひとり病院にいたのだが。 かくして、僕は歴代の若手外科医で初めて、腹腔鏡の大きな手術を執刀させてもらった。 怖いベテラン外科医が患者さんをはさんで向かいに立ち、僕は執刀医の位置でメスを持った。 「ここ切って」 「ここつまんでひっぱって」 言われた通りに動くのみだ。手は震えこそしなかったが、肩には信じられないほど力が入っている。 手先の器用さも、人体の構造の理解も足りない。 まさに「ここ掘れワンワン」手術だった。執刀と言っても、9割以上はベテラン外科医が行ったのだ。 それでも、手術を執刀した事実に僕の頭は沸騰した。大興奮のまま赤い顔で研修医室に戻ると、 「すごいじゃん!」「よっ、外科医!」 と拍手喝采だった。研修医室の窓からはよく晴れた空が見えた。 外科医として、小さな一歩を僕は歩み始めていた。 僕は、貯金はゼロだったが、お金を「自己投資」していた。 僕が医者になって3年目から9年目までの間、世の同世代の医者の年収の半分の額しか病院からもらわなかった。だが、僕は授業料だと思っていた。世界トップレベルの外科医から手取り足取り手術を教えてもらえるのだ。毎年何百万円を誰かに払っているつもりだった。 いつかきっと取り返せるだろうし、取り返せなくたって何千万円かの支払いで、僕は外科医としての階段を一度飛ばしで駆け上がることができるのだ。それは苦にならなかった。悩む僕に、外科の同期の医師は、「たった2年でこの病院から何か学んだつもり?」 と煽っていた。また別の同期は、 (同じところにずっといるとダメになる、澱んだ水たまりみたいに」 と言った。 当時もっとも信頼していた2学年上の本多という先輩外科医に相談したら、医局に入ったら年功序列、すべて順番待ちになる。中山の能力や努力と関係なく成長スピードが決まる。階段を一段飛ばしで上がりたいなら入っちゃダメだ。先のことは、また考えればいい」 と言った。 この一言で僕は医局に入らないことに決めた。 まるで「暗闇でジャンプ」するような気持ちだった。着地ができなければそれでゲームオーバー。 でも、前にも言ったように、「選択」とは、何かを選ぶことではない。選んだ選択肢があとから「やっぱり大正解だったな」と言えるように、人が休んでいる間におそろしいほどの努力をして現実世界を捻じ曲げることだ。 僕はその覚悟を持って、医局に入らないことを自分で決めた。 「先のことはまた考えればいい」という先輩の言葉は背中を押してくれた。 それでも、修了証をもらうと涙が出た。 果たしてそれから16年が経った。 僕は、最初の5年くらいは「なんでも人の3倍やろう」と決めた。2倍じゃ、抜きん出ることはできない。一日は24時間しかないから、僕は人の倍のスピードでやり、さらに人の倍の時間をかけた。手術の練習も、同僚が1時間やるなら僕は2時間、という具合だ。 自分の外科医としての技術を評価することは簡単ではないが、おそらく僕の技術は抜きん出ていると思う。厳しい環境で人の3倍を続けたのだから、当たり前だと思っている。 神輿に担がれていることを忘れてはならない。 僕はいただいた技術を目の前の患者さんの手術をすることで還元し、同時に全国の外科医の教育のために教科書を書いたり講演をしたりしている。加えて、医局に入り、地道に地域の医療に身を捧げながら外科医として踏ん張る医師たちを心から尊敬している。 僕みたいな利己的な人ばかりでは、この世界は成り立たないのもまた事実である。 恐ろしい会議は週に2回開催された。そのたびに腹を壊した。3年間続けると、最後のほうは不機嫌な外科医の質問を軽くかわせるようになった。 僕は、外科医として長い階段を一段ずつ登って行ったのだ。 ここで、人の何倍も、と気軽に言ったが、だいたい僕のイメージだと3倍は必要だ。人の2倍やっている人はけっこういるからだ。 たとえば、テニスのサーブの練習を人が2時間やるのなら、4時間ではたいしたことはない。でも、6時間やれば大きな差になり、「そんな人はほとんどいない」レベルになる。 勉強だって同じだ。単語帳の暗記を、2周するところ、4周やる人間はいるが、6周やる人はまずいない。 僕は消化器外科専門医試験という、合格者の平均年齢が40歳の試験勉強を33歳の頃めちゃくちゃやった。これを覚えれば受かるという教科書を、本当に6周やった。試験会場では100分の試験を30分で解き終わり、一番に会場を出た。わからない問題はなかった。 まだまだ駆け出しの新人といった扱いは変わらない。だが、雑用はできるようになった。 後輩外科医の指導、自分の手術修業、そして学会発表や論文執筆など、かなりの仕事量になり僕は毎晩23時まで医局で仕事をしていた。 超過勤務手当などない。タイムカードさえなく、実際には月28日ほど出勤していたが「月15日しか勤務していないことにせよ」というでたらめな東京都の労務管理だった。 医者3年目が終わりに近づいた1月、僕は下町の救命センターに勤務した。 当直という恐ろしい業務がある。 これは、朝8時から夕方5時まで働き、そのまま夜中の勤務が5時から翌朝8時まで続くというものだ。しかもヘトヘトになった翌朝に帰れるわけではない。そこからまた夕方5時まで働く、36時間ぶっ通しの労働である。 救命センターの当直の夜は過酷だった。 高度救急救命センターの名前の通り、この世でもっとも生命の危機に瀕した人が運ばれてくる。夜中に運ばれてくる人のうち、半数はCPA、つまり心肺停止状態であった。 「ホットライン」と呼ばれる置き型の白い電話がけたたましく鳴り、そばにいた僕はパッと受話器を取る。 「こちら••病院救命センター」 「お願いします、CPAの搬送依頼です。患者は87歳男性・・・・・」 ノートにメモをしていた僕は言葉をさえぎり「受け入れます」と言う。 「ありがとうございます、10分で到着です」 受話器を置くと、僕は大きい声で「CPA、10分後です!」と叫び駆け出す。 同期のキツネ顔がにっと笑って後ろをついてくる。 僕の記憶力は人よりはるかに悪いが、人からかけられため言葉はすべて記憶していて、心の宝箱に入れている。しょっちゅうそれを取り出しては眺め、甘いチョコレートを食べるみたいにして悦に入るのだ。 いつ死ぬかわからないが、100%死ぬことが決まっているこの世界で、君は何をして、誰を愛するのか。 今はまだよくわからないかもしれないけど、この問いは一生懸命に考えてほしいと思う。 死とは、「生きる」を鮮やかにする最高のトリガーだからだ。 僕は、来年死ぬかもしれない。今何か重大な病気にかかっているわけではないけれど、真剣にそう思っている。だからこの本を作ったのだ。 僕が死んでしまっても、君たちに伝えられるように。 立派になるかならないか、高い技術を持つか持たないかは自分しだい、とよく言われてだがそんなことはない。いかに厳しい環境に身を置くか。いかにアウェーな場所で奮闘するか。これが成長の鍵になる。 京都大学時代の師である福原俊一先生は「他流試合をせよ」といつも言っていた。なるほど、いつも自分の居心地の良いところにいると、成長はないよ、という意味だろう。 自分で操縦することはない大型豪華客船を降り、僕は小さい舟に乗りかえたのだ。 そして、フルタイムで働きつつ育児家事に加え介護、さらには夫のグチまでを聞く超人の妻に、心からの花束を贈りたい。 令和6年5月23日 茅ヶ崎駅前のスターバックスにて
医者の父が息子に綴る 人生の扉をひらく鍵中山祐次郎読み終わった言い換えると、優しさとは、他者の持つ、自分とは異なる考え方や感じ方を尊重し、想像すると いうことなのだ。 いち医学生だった僕に何かができるわけではない。逆に、僕にできることはなんだろうかと考え、悩み抜いた未に出た答えが「たくさんお話をすること」だったのだ。それ以外なかったとも言えるけど。 あの患者さんとたくさんお話をしたおかげで、僕は優しさの正体に気がついたのだ。 それからは、患者さんにお会いするたびに、そして患者さんだけでなく新しく友達に出会うたびに、いつも「相手の気持ちを本気で考える」ことをやるように心がけている。いつもいつもうまくいくわけじゃないけどね。 「来年死んでしまうとしたら、君は今何をしますか?」すると、湧き上がるものがあるはずだ。 僕はこの魔法の質問をしょっちゅう自分に投げかけている。そして、きちんと自分の夢中にまっすぐ歩めるように軌道修正しているのだ。 もしこのマジック・クエスチョンで何も思わなかったなら、次の質問がある。これらに答えてほしい。 「来年目が見えなくなってしまうとしたら、今年どこで何を見たい?」「来年外に出かけられなくなってしまうとしたら、今年どこに行きたい?」 「来年何も食べられなくなるとしたら、何を食べたい?」「来年誰にも会えなくなるとしたら、今年会っておきたい人は誰?」 答えから、君が本当に見たいものや行きたいところ、食べたいものや会いたい人がわかるはずだ。 君はもしかしたらまだ考えたことがないかもしれないが、実は人間の死亡率は100%なのだ。これを書いている僕はいずれ死ぬ。そして読んでいる君もまた、必ずいつか死ぬのである。 この「人生の締め切り」が来る前に、やりたいことをやっておかねば。僕はそう思い、この本を書き始めたんだ。伝える前に死んでしまったら、何も伝えられないからね。 丸坊主になって勉強をした浪人の2年間、勉強し続けて無数の試験に合格し続けた医学部の6年。ここまで来て、医者にならない選択肢はない。 他の学部と異なり、医学部は入った時から医者になるべく職業訓練を受け続けるのだ。 「絶対に落ちることのできない試験」 そんな恐怖が、僕ら6年生を覆っていた。 僕は、朝は6時から、夜は23時まで桜ヶ丘にある医学部キャンパスの自習室にいた。 そして週末には必ず息抜きのため飲みに行った。殺気立った同級生と行っても息が詰まるので、鹿児島銀行勤めの友人と高校教師の友人とよく行ったものだった。酒を飲んだ翌日にも、必ず6時には勉強を始めた。 あっという間に12月が終わり、新しい年がやってきた。 僕が医者になるか、浪人になるかが決まる年だ。 恒例の年末年始の帰省はせず、僕は鹿児島で勉強し続けた。落ちるわけにはいかなかった。 1000を超える病気。それらの原因や症状、治療法を、自作のゴロで頭に叩き込んだ暗記は苦手だったが、そんなことは言っていられない。 「それではここで、解答をやめてください」 2007年2月19日。大きな体の試験官の太い声で、ついに3日間にわたる医師国家試験が終わった。 500問、合計16時間と15分。僕は心も体も芯からくたびれていた。この試験のために半年の間、毎日16時間ほど勉強をし続けてきた。 黒いスーツの女性が解答用紙を回収している。 頭に浮かんだのは、「大きな災害や病気、事故にあわずに試験を受けられたことへの感謝」だった。 もし大きな地震が起きたら、もし感染症が流行したら、もしホテルから試験会場までのバスが事故を起こしたら。 「医学的知識」の高い山頂に、僕はいた。一度転げたら、もう二度と到達できないだろう高み。大学での実習をし、無数の試験を受け、さらに勉強しけてやっとたどり着いた高み。 すべてのタイミングが揃い、なんとか奇跡的に登りきれたのだ。 どんな仕事も、人とつながっている。「あの人に任せれば大丈夫」という評価を少しずつ積み重ねてたどり着いた高さが、君ができる一番大きな仕事なのだ。 僕は、南日本新聞のエッセイを全力で書いた。1ヶ月に1本を書くために、丸々1ヶ月ずっと考え続けたこともあった。 そうしたら、ありがたいことに「ベスト・エッセイ2023』という本に選出してもらえたし、鹿児島の財界人が集まるところで講演する機会ももらえた。さらに鹿児島の本屋さんでは、僕の小説が出るたびに大変な数を陳列してもらえるようになったのだ。 小さな仕事の先にしか、黄金の果実はないことを知ってほしいと思う。 自分の目というフィルターを通して、起きていることを見て、自分の頭で判断する。何が正しいかわからないこの世界で、必ず自分の目で見ること。 そのためには、世界のあちこちに旅行しなければいけない。生まれ育った場所が違い、目と肌の色が違う人がどんなことを考えているのか。直接会って、君が話すんだ。そうしなければ、正しく理解をすることはできない。 そのために共通の言語を学ぶ必要がある。 つまり外国語を学ぶのだ。 上司が、「中山はこれだけ頑張っている、やらせないわけにはいかない」と思わざるを得ないような熱意だ。その熱意を示すにはどうすればいいだろうか。単純なことだ。 僕は朝一番に来て誰よりも雑用をし、夜は一番最後まで残って後輩の指導をした。そして日中の空いた時間には必ず自分の業務と直接は関係ない手術を見学した。さらに、手術ではない仕事、学会発表や論文作成といった仕事も全力でやった。 その頃、僕はそういう仕事を人の3倍やろうと思っていたし、実際に3倍くらいやっていたと思う。 そのためには夜遅くまで病院のデスクでパソコンに向かったし、休日も遊びに行かずひとり病院にいたのだが。 かくして、僕は歴代の若手外科医で初めて、腹腔鏡の大きな手術を執刀させてもらった。 怖いベテラン外科医が患者さんをはさんで向かいに立ち、僕は執刀医の位置でメスを持った。 「ここ切って」 「ここつまんでひっぱって」 言われた通りに動くのみだ。手は震えこそしなかったが、肩には信じられないほど力が入っている。 手先の器用さも、人体の構造の理解も足りない。 まさに「ここ掘れワンワン」手術だった。執刀と言っても、9割以上はベテラン外科医が行ったのだ。 それでも、手術を執刀した事実に僕の頭は沸騰した。大興奮のまま赤い顔で研修医室に戻ると、 「すごいじゃん!」「よっ、外科医!」 と拍手喝采だった。研修医室の窓からはよく晴れた空が見えた。 外科医として、小さな一歩を僕は歩み始めていた。 僕は、貯金はゼロだったが、お金を「自己投資」していた。 僕が医者になって3年目から9年目までの間、世の同世代の医者の年収の半分の額しか病院からもらわなかった。だが、僕は授業料だと思っていた。世界トップレベルの外科医から手取り足取り手術を教えてもらえるのだ。毎年何百万円を誰かに払っているつもりだった。 いつかきっと取り返せるだろうし、取り返せなくたって何千万円かの支払いで、僕は外科医としての階段を一度飛ばしで駆け上がることができるのだ。それは苦にならなかった。悩む僕に、外科の同期の医師は、「たった2年でこの病院から何か学んだつもり?」 と煽っていた。また別の同期は、 (同じところにずっといるとダメになる、澱んだ水たまりみたいに」 と言った。 当時もっとも信頼していた2学年上の本多という先輩外科医に相談したら、医局に入ったら年功序列、すべて順番待ちになる。中山の能力や努力と関係なく成長スピードが決まる。階段を一段飛ばしで上がりたいなら入っちゃダメだ。先のことは、また考えればいい」 と言った。 この一言で僕は医局に入らないことに決めた。 まるで「暗闇でジャンプ」するような気持ちだった。着地ができなければそれでゲームオーバー。 でも、前にも言ったように、「選択」とは、何かを選ぶことではない。選んだ選択肢があとから「やっぱり大正解だったな」と言えるように、人が休んでいる間におそろしいほどの努力をして現実世界を捻じ曲げることだ。 僕はその覚悟を持って、医局に入らないことを自分で決めた。 「先のことはまた考えればいい」という先輩の言葉は背中を押してくれた。 それでも、修了証をもらうと涙が出た。 果たしてそれから16年が経った。 僕は、最初の5年くらいは「なんでも人の3倍やろう」と決めた。2倍じゃ、抜きん出ることはできない。一日は24時間しかないから、僕は人の倍のスピードでやり、さらに人の倍の時間をかけた。手術の練習も、同僚が1時間やるなら僕は2時間、という具合だ。 自分の外科医としての技術を評価することは簡単ではないが、おそらく僕の技術は抜きん出ていると思う。厳しい環境で人の3倍を続けたのだから、当たり前だと思っている。 神輿に担がれていることを忘れてはならない。 僕はいただいた技術を目の前の患者さんの手術をすることで還元し、同時に全国の外科医の教育のために教科書を書いたり講演をしたりしている。加えて、医局に入り、地道に地域の医療に身を捧げながら外科医として踏ん張る医師たちを心から尊敬している。 僕みたいな利己的な人ばかりでは、この世界は成り立たないのもまた事実である。 恐ろしい会議は週に2回開催された。そのたびに腹を壊した。3年間続けると、最後のほうは不機嫌な外科医の質問を軽くかわせるようになった。 僕は、外科医として長い階段を一段ずつ登って行ったのだ。 ここで、人の何倍も、と気軽に言ったが、だいたい僕のイメージだと3倍は必要だ。人の2倍やっている人はけっこういるからだ。 たとえば、テニスのサーブの練習を人が2時間やるのなら、4時間ではたいしたことはない。でも、6時間やれば大きな差になり、「そんな人はほとんどいない」レベルになる。 勉強だって同じだ。単語帳の暗記を、2周するところ、4周やる人間はいるが、6周やる人はまずいない。 僕は消化器外科専門医試験という、合格者の平均年齢が40歳の試験勉強を33歳の頃めちゃくちゃやった。これを覚えれば受かるという教科書を、本当に6周やった。試験会場では100分の試験を30分で解き終わり、一番に会場を出た。わからない問題はなかった。 まだまだ駆け出しの新人といった扱いは変わらない。だが、雑用はできるようになった。 後輩外科医の指導、自分の手術修業、そして学会発表や論文執筆など、かなりの仕事量になり僕は毎晩23時まで医局で仕事をしていた。 超過勤務手当などない。タイムカードさえなく、実際には月28日ほど出勤していたが「月15日しか勤務していないことにせよ」というでたらめな東京都の労務管理だった。 医者3年目が終わりに近づいた1月、僕は下町の救命センターに勤務した。 当直という恐ろしい業務がある。 これは、朝8時から夕方5時まで働き、そのまま夜中の勤務が5時から翌朝8時まで続くというものだ。しかもヘトヘトになった翌朝に帰れるわけではない。そこからまた夕方5時まで働く、36時間ぶっ通しの労働である。 救命センターの当直の夜は過酷だった。 高度救急救命センターの名前の通り、この世でもっとも生命の危機に瀕した人が運ばれてくる。夜中に運ばれてくる人のうち、半数はCPA、つまり心肺停止状態であった。 「ホットライン」と呼ばれる置き型の白い電話がけたたましく鳴り、そばにいた僕はパッと受話器を取る。 「こちら••病院救命センター」 「お願いします、CPAの搬送依頼です。患者は87歳男性・・・・・」 ノートにメモをしていた僕は言葉をさえぎり「受け入れます」と言う。 「ありがとうございます、10分で到着です」 受話器を置くと、僕は大きい声で「CPA、10分後です!」と叫び駆け出す。 同期のキツネ顔がにっと笑って後ろをついてくる。 僕の記憶力は人よりはるかに悪いが、人からかけられため言葉はすべて記憶していて、心の宝箱に入れている。しょっちゅうそれを取り出しては眺め、甘いチョコレートを食べるみたいにして悦に入るのだ。 いつ死ぬかわからないが、100%死ぬことが決まっているこの世界で、君は何をして、誰を愛するのか。 今はまだよくわからないかもしれないけど、この問いは一生懸命に考えてほしいと思う。 死とは、「生きる」を鮮やかにする最高のトリガーだからだ。 僕は、来年死ぬかもしれない。今何か重大な病気にかかっているわけではないけれど、真剣にそう思っている。だからこの本を作ったのだ。 僕が死んでしまっても、君たちに伝えられるように。 立派になるかならないか、高い技術を持つか持たないかは自分しだい、とよく言われてだがそんなことはない。いかに厳しい環境に身を置くか。いかにアウェーな場所で奮闘するか。これが成長の鍵になる。 京都大学時代の師である福原俊一先生は「他流試合をせよ」といつも言っていた。なるほど、いつも自分の居心地の良いところにいると、成長はないよ、という意味だろう。 自分で操縦することはない大型豪華客船を降り、僕は小さい舟に乗りかえたのだ。 そして、フルタイムで働きつつ育児家事に加え介護、さらには夫のグチまでを聞く超人の妻に、心からの花束を贈りたい。 令和6年5月23日 茅ヶ崎駅前のスターバックスにて
- 2025年3月15日
 生き方稲盛和夫読み終わった
生き方稲盛和夫読み終わった - 2025年3月15日
 すべてがFになる森博嗣読み終わった「西之園君」犀川は振り向いて萌絵を見た。こんなにてきぱきとものを言う犀川を、萌絵は今までに見たことがなかった。「256と256のかけ算をして」「65536」萌絵は即答した。どうして、こんな計算をしなければならないのか、彼女には理由がまるでわからない。 「よし…」犀川は萌絵をじっと見た。萌絵が初めて見る、厳しい屋川の表情だった。「いいかい?西之園君…。一昨日の午後七時から、65535時間まえはいつ?」「え?」萌絵は聞き直した。しかし、犀川は黙って彼女を見ている。 萌絵は呼吸を止めて、目を閉じた。 19を引く。24で割る。余りを覚える。今は八月…閏年があって…。 計算には八秒くらいかかった。犀川に見つめられていると思うと、いつもの彼女の実力は半分も出せなかった。 「七年まえの…二月十日の…午前四時です」 「日本では、一緒に遊ぶとき、混ぜてくれって言いますよね」犀川は突然話し出した。「混ぜるという動詞は、英語ではミックスです。これは、もともと液体を一緒にするときの言葉です。外国、特に欧米では、人間は、仲間に入れてほしいとき、ジョインするんです。混ざるのではなくて、つながるだけ・・..。つまり、日本は、液体の社会で、欧米は固体の社会なんですよ。日本人って、個人がリキッドなのです。流動的で、渾然一体になりたいという欲求を社会本能的に持っている。欧米では、個人はソリッドだから、けっして混ざりません。 どんなに集まっても、必ずパーツとして独立している…・・・・・。ちょうど、土壁の日本建築と、煉瓦の西洋建築のようです」 「死を恐れている人はいません。死にいたる生を恐れているのよ」四季は言う。「苦しまないで死ねるのなら、誰も死を恐れないでしょう?」「おっしゃるとおりです」屋川は頷く。それは自分も同感だった。 では森博嗣の本質はどこにあるのか。何が森博嗣の小説を「理系」たらしめているのか。 それは認識やリアリティに対するアプローチの仕方なのである。 森博嗣の作品は、ほとんどすべて、個人の認識や個人が感じるリアリティへの懐疑の視点が立脚点になって成立している。皆が正しいと思っているものを私たちは盲目的に正しいと肩じ、それを己の規範にしてしまいがちだ。だがそういった「常識」すらも一日己の頭を使って検証してみること。目の前に与えられたデータを客観的に見つめること。これらの行為は極めて真っ当であるはずだが、私たちは往々にしてそのことを忘れてしまう。しかし森は常にこのアプローチを忘れない。このアプローチが存在するからこそ、森の作品は理系として位置づけられるのである。
すべてがFになる森博嗣読み終わった「西之園君」犀川は振り向いて萌絵を見た。こんなにてきぱきとものを言う犀川を、萌絵は今までに見たことがなかった。「256と256のかけ算をして」「65536」萌絵は即答した。どうして、こんな計算をしなければならないのか、彼女には理由がまるでわからない。 「よし…」犀川は萌絵をじっと見た。萌絵が初めて見る、厳しい屋川の表情だった。「いいかい?西之園君…。一昨日の午後七時から、65535時間まえはいつ?」「え?」萌絵は聞き直した。しかし、犀川は黙って彼女を見ている。 萌絵は呼吸を止めて、目を閉じた。 19を引く。24で割る。余りを覚える。今は八月…閏年があって…。 計算には八秒くらいかかった。犀川に見つめられていると思うと、いつもの彼女の実力は半分も出せなかった。 「七年まえの…二月十日の…午前四時です」 「日本では、一緒に遊ぶとき、混ぜてくれって言いますよね」犀川は突然話し出した。「混ぜるという動詞は、英語ではミックスです。これは、もともと液体を一緒にするときの言葉です。外国、特に欧米では、人間は、仲間に入れてほしいとき、ジョインするんです。混ざるのではなくて、つながるだけ・・..。つまり、日本は、液体の社会で、欧米は固体の社会なんですよ。日本人って、個人がリキッドなのです。流動的で、渾然一体になりたいという欲求を社会本能的に持っている。欧米では、個人はソリッドだから、けっして混ざりません。 どんなに集まっても、必ずパーツとして独立している…・・・・・。ちょうど、土壁の日本建築と、煉瓦の西洋建築のようです」 「死を恐れている人はいません。死にいたる生を恐れているのよ」四季は言う。「苦しまないで死ねるのなら、誰も死を恐れないでしょう?」「おっしゃるとおりです」屋川は頷く。それは自分も同感だった。 では森博嗣の本質はどこにあるのか。何が森博嗣の小説を「理系」たらしめているのか。 それは認識やリアリティに対するアプローチの仕方なのである。 森博嗣の作品は、ほとんどすべて、個人の認識や個人が感じるリアリティへの懐疑の視点が立脚点になって成立している。皆が正しいと思っているものを私たちは盲目的に正しいと肩じ、それを己の規範にしてしまいがちだ。だがそういった「常識」すらも一日己の頭を使って検証してみること。目の前に与えられたデータを客観的に見つめること。これらの行為は極めて真っ当であるはずだが、私たちは往々にしてそのことを忘れてしまう。しかし森は常にこのアプローチを忘れない。このアプローチが存在するからこそ、森の作品は理系として位置づけられるのである。 - 2025年3月13日
 すべてきみに宛てた手紙長田弘読み終わった記憶は、過去のものではない。それは、すでに過ぎ去ったもののことではなく、むしろ過ぎ去らなかったもののことだ。とどまるのが記憶であり、じぶんのうちに確かにとどまって、じぶんの現在の土壌となってきたものは、記憶だ 瓦斯の煖に火が燃える ウウロン茶、風、細い夕月
すべてきみに宛てた手紙長田弘読み終わった記憶は、過去のものではない。それは、すでに過ぎ去ったもののことではなく、むしろ過ぎ去らなかったもののことだ。とどまるのが記憶であり、じぶんのうちに確かにとどまって、じぶんの現在の土壌となってきたものは、記憶だ 瓦斯の煖に火が燃える ウウロン茶、風、細い夕月 - 2025年3月12日
- 2025年3月12日
読み込み中...