

はる
@tsukiyo_0429
【読書】小説・短歌・歴史【言語】日本語教育/英会話学び直し/2021年4月から趣味でドイツ語を勉強中🇩🇪/独検3級・ゲーテA1💮【💡】読書はゆっくりペース/江戸・プロイセン・ドイツに興味があります/hanatama様フリーアイコン
- 2026年1月16日
 モモミヒャエル・エンデ,大島かおりずっと気になっていたが、読めていなかった『モモ』。 ざっくりとした内容はNHK「100分で名著」を見て知っていた。 現在、ドイツ語学習者向け『モモ』を使ってドイツ語を勉強しており、この機会に読んでみようと思い選んだ。 序盤の100ページほどを読んだ時点で、「これって本当に児童書!?」と思った。 そして『モモ』が発表されたのは1973年だと知り、さらに驚いた。 ミヒャエル・エンデを予言者のように感じてしまうほど、現代を生きる私に刺さるものがあった。 文章やストーリーは子ども向けに書かれているが、これはぜひ大人に読んでもらいたい作品だ。 時間泥棒である「灰色の男たち」は、人々から時間を奪っていく。 街の人たちは無駄を嫌い、予定を詰め込み、いつも忙しくイライラしている。 子どもたちでさえ、遊ぶ面白さよりも「将来の役に立つかどうか」が全てになっている。 大切な人との会話、触れ合い、自分を慈しむ時間。 そういうものがどんどん剥ぎ落とされ、1秒の時間も無駄にしないことが良しとされ、時間に振り回されながら生きている人々。 その姿が、現代の我々と重なった。 「仕事に役立つことをしろ」 「無駄なことをするな」 「タイパを考えろ」 そんな言葉が溢れている私たちの日常に必要な物語だと思った。 特に印象的だったのは、「時間の花」だ。 自分自身の時間というものを、こんなにも美しく、儚く描くことができるのかと驚いた。 物語の最後には、『作者のみじかいあとがき』が載っている。 このあとがきを読むと、子どもたちに向けたミヒャエル・エンデのあたたかい眼差しを感じることができる。 ぜひ最後まで読んでほしい箇所だ。 日常を過ごしていく中で一度立ち止まり、自分にとっての時間とは何か、大切にしたいものは何かを考えたくなる作品だった。 . 時間をケチケチすることで、ほんとうはぜんぜんべつのなにかをケチケチしているということには、だれひとり気がついていないようでした。じぶんたちの生活が日ごとにまずしくなり、日ごとに画一的になり、日ごとに冷たくなっていることを、だれひとりみとめようとはしませんでした。 (P106) . 「時間がない」、「ひまがない」——こういうことばをわたしたちは毎日聞き、じぶんでも口にします。いそがしいおとなばかりではありません、子どもたちまでそうなのです。けれど、これほど足りなくなってしまった「時間」とは、いったいなになのでしょうか? 機械的にはかることのできる時間が問題なのではありますまい。そうではなくて、人間の心のうちの時間、人間が人間らしく生きることを可能にする時間、そういう時間がわたしたちからだんだんと失われてきたようなのです。このとらえどころのない謎のような時間というものが、このふしぎなモモの物語の中心テーマなのです。 (P401『訳者のあとがき』)
モモミヒャエル・エンデ,大島かおりずっと気になっていたが、読めていなかった『モモ』。 ざっくりとした内容はNHK「100分で名著」を見て知っていた。 現在、ドイツ語学習者向け『モモ』を使ってドイツ語を勉強しており、この機会に読んでみようと思い選んだ。 序盤の100ページほどを読んだ時点で、「これって本当に児童書!?」と思った。 そして『モモ』が発表されたのは1973年だと知り、さらに驚いた。 ミヒャエル・エンデを予言者のように感じてしまうほど、現代を生きる私に刺さるものがあった。 文章やストーリーは子ども向けに書かれているが、これはぜひ大人に読んでもらいたい作品だ。 時間泥棒である「灰色の男たち」は、人々から時間を奪っていく。 街の人たちは無駄を嫌い、予定を詰め込み、いつも忙しくイライラしている。 子どもたちでさえ、遊ぶ面白さよりも「将来の役に立つかどうか」が全てになっている。 大切な人との会話、触れ合い、自分を慈しむ時間。 そういうものがどんどん剥ぎ落とされ、1秒の時間も無駄にしないことが良しとされ、時間に振り回されながら生きている人々。 その姿が、現代の我々と重なった。 「仕事に役立つことをしろ」 「無駄なことをするな」 「タイパを考えろ」 そんな言葉が溢れている私たちの日常に必要な物語だと思った。 特に印象的だったのは、「時間の花」だ。 自分自身の時間というものを、こんなにも美しく、儚く描くことができるのかと驚いた。 物語の最後には、『作者のみじかいあとがき』が載っている。 このあとがきを読むと、子どもたちに向けたミヒャエル・エンデのあたたかい眼差しを感じることができる。 ぜひ最後まで読んでほしい箇所だ。 日常を過ごしていく中で一度立ち止まり、自分にとっての時間とは何か、大切にしたいものは何かを考えたくなる作品だった。 . 時間をケチケチすることで、ほんとうはぜんぜんべつのなにかをケチケチしているということには、だれひとり気がついていないようでした。じぶんたちの生活が日ごとにまずしくなり、日ごとに画一的になり、日ごとに冷たくなっていることを、だれひとりみとめようとはしませんでした。 (P106) . 「時間がない」、「ひまがない」——こういうことばをわたしたちは毎日聞き、じぶんでも口にします。いそがしいおとなばかりではありません、子どもたちまでそうなのです。けれど、これほど足りなくなってしまった「時間」とは、いったいなになのでしょうか? 機械的にはかることのできる時間が問題なのではありますまい。そうではなくて、人間の心のうちの時間、人間が人間らしく生きることを可能にする時間、そういう時間がわたしたちからだんだんと失われてきたようなのです。このとらえどころのない謎のような時間というものが、このふしぎなモモの物語の中心テーマなのです。 (P401『訳者のあとがき』) - 2025年12月15日
 モモミヒャエル・エンデ,大島かおり読んでる
モモミヒャエル・エンデ,大島かおり読んでる - 2025年12月9日
 流刑地にてフランツ・カフカ,Franz Kafka,池内紀読み終わった短編小説ととても短い小品が収録されている。 その中から、主に短編小説について感想を述べる。 『判決』 こんなに短い話でこんなにも心がぐちゃぐちゃになることがあるのか!?と、その読み心地に驚いた。 少しずつ雲行きが怪しくなっていく展開にハラハラさせられた。 恐らく認知症である父親とのやり取りは、今の年齢だからこそ響くものがあった。 『流刑地にて』 あとがき「『流刑地にて』の読者のために」によると、この作品はカフカが生涯に一度だけ行なった自作朗読会で読んだ小説とのこと。 よりにもよってこの作品を朗読したなんて……!!と思わずにはいられなかった。 実際、聴衆の三人が失神し、会場から運び出されたらしい。 この作品は、「拷問で可能な限り苦しませて処刑する機械」について、将校によって話が進められていく形で展開していく。 処刑の話をしているシリアスなシーンなのに、なぜか滑稽に思えてならなかった。 どんな展開になるかドキドキしながら読んだ。 将校は自らの信念のために死を選んだのに、彼の顔には約束されていたはずの「浄化の表情」など現れず、その虚しさに胸が苦しくなった。 喫茶店のテーブルの下に埋められた墓も、虚しくてたまらなかった。 この流刑地は近い将来滅びるんだろうな、という予感が渦巻いていた。 『火夫』 主人公のカールは、火夫である男を助けることで依存し、縋っているように思えた。 そしてこの作品を読んで一番に思ったことは、「火夫の男が愛おしすぎる」ということだった。 火夫はドイツ人で、身体も態度も大きいと冒頭で描かれる。 そんな彼は、自身の不遇を訴えるために、息巻いて事務室に向かう。 しかしそこから、 ・調理場の女性を誘っても相手にされない ・出ていけと言われて「切々と苦しみを訴える恋人のような目つき」でカールを見つめる ・訴える機会を得たのに感情にのまれて全然うまく話せない ・カールに手を握られて、目をきらきらと光らせ、恍惚した顔つきになる と愛おしさが溢れる描写が続き、この火夫の今後に思いを馳せてしまった。 しかし火夫など最初から存在しなかったように思えてしまうラストには、胸が苦しくなった。 数が多い者、口がうまい者、権力がある者に、こういう人たちは消されてしまう。 カールの伯父だと言う男については、全てが芝居がかって見えて、胡散臭く感じた。 伯父というのは本当なのだろうか、と疑いたくなる人物だった。 . カフカの作品を久しぶりに読んだが、とても興味深くおもしろかった。 今回は書店で購入した白水uブックスで読んだのだが、紙が柔らかい新書サイズで読みやすかった。
流刑地にてフランツ・カフカ,Franz Kafka,池内紀読み終わった短編小説ととても短い小品が収録されている。 その中から、主に短編小説について感想を述べる。 『判決』 こんなに短い話でこんなにも心がぐちゃぐちゃになることがあるのか!?と、その読み心地に驚いた。 少しずつ雲行きが怪しくなっていく展開にハラハラさせられた。 恐らく認知症である父親とのやり取りは、今の年齢だからこそ響くものがあった。 『流刑地にて』 あとがき「『流刑地にて』の読者のために」によると、この作品はカフカが生涯に一度だけ行なった自作朗読会で読んだ小説とのこと。 よりにもよってこの作品を朗読したなんて……!!と思わずにはいられなかった。 実際、聴衆の三人が失神し、会場から運び出されたらしい。 この作品は、「拷問で可能な限り苦しませて処刑する機械」について、将校によって話が進められていく形で展開していく。 処刑の話をしているシリアスなシーンなのに、なぜか滑稽に思えてならなかった。 どんな展開になるかドキドキしながら読んだ。 将校は自らの信念のために死を選んだのに、彼の顔には約束されていたはずの「浄化の表情」など現れず、その虚しさに胸が苦しくなった。 喫茶店のテーブルの下に埋められた墓も、虚しくてたまらなかった。 この流刑地は近い将来滅びるんだろうな、という予感が渦巻いていた。 『火夫』 主人公のカールは、火夫である男を助けることで依存し、縋っているように思えた。 そしてこの作品を読んで一番に思ったことは、「火夫の男が愛おしすぎる」ということだった。 火夫はドイツ人で、身体も態度も大きいと冒頭で描かれる。 そんな彼は、自身の不遇を訴えるために、息巻いて事務室に向かう。 しかしそこから、 ・調理場の女性を誘っても相手にされない ・出ていけと言われて「切々と苦しみを訴える恋人のような目つき」でカールを見つめる ・訴える機会を得たのに感情にのまれて全然うまく話せない ・カールに手を握られて、目をきらきらと光らせ、恍惚した顔つきになる と愛おしさが溢れる描写が続き、この火夫の今後に思いを馳せてしまった。 しかし火夫など最初から存在しなかったように思えてしまうラストには、胸が苦しくなった。 数が多い者、口がうまい者、権力がある者に、こういう人たちは消されてしまう。 カールの伯父だと言う男については、全てが芝居がかって見えて、胡散臭く感じた。 伯父というのは本当なのだろうか、と疑いたくなる人物だった。 . カフカの作品を久しぶりに読んだが、とても興味深くおもしろかった。 今回は書店で購入した白水uブックスで読んだのだが、紙が柔らかい新書サイズで読みやすかった。 - 2025年11月20日
 読み終わった大河ドラマ「べらぼう」で、「愛した女性が亡くなり腐っていく様を目にしながらも、彼女の“美しい姿”を描き続ける喜多川歌麿」というシーンがあり、あまりにもつらくて最高だったのだが、そのシーンで九相図を思い出したので積読棚から引っ張り出してきた。 (歌麿がしていたことは九相図とは真逆だが) 現在では『呪術廻戦』で九相図を知った人も多いかもしれない。 私が初めて知ったのは、河鍋暁斎の展覧会だった。 幽霊・髑髏という流れで見て、かつ、暁斎が九歳の頃に川で拾った生首を写生したというエピソードを知っていたため、最初は暁斎の趣味かと思ってしまった。 後に仏教絵画だと知り、強く印象に残ったのを覚えている。 これまで私は、九相図とは男性出家者のための「性的煩悩(=女性)を退ける修行」に使われるものだと思っていた。 しかし九相図はそれだけではなく、近世初頭では女性が主体的に仏教へ関与する手段としても使われていたことが、この本を読んで分かった。 特に興味深かったのは、九相図が日本に伝わってきた頃のことだ。 九相図の各相を詠んだ詩「九相観詩」が日本に伝わったとき、出家者の悟りのための厳しい修行である「不浄観」から、在家者の共感を得やすい「無常」へと文脈が発展していた。 伝わったそのときから、文学的側面も色濃く結びついていたようだ。 そしてその後、朽ちていく死体を四季の移り変わりと重ねて詠んだ「九想詩」も生まれた。 この「無常観と四季」という組み合わせは、当時の日本人にウケるだろうな……というのが第一に感じたことだった。 九相の変化を四季の移り変わりになぞらえるという趣向は和歌にも取り入れられ、中・近世日本で制作された多くの九相図にも受け継がれているそうだ。 今回嬉しかったのは、河鍋暁斎の九相図について詳しく知ることができた点だ。 河鍋暁斎は私の推し絵師の一人であり、私が初めて九相図と出会ったきっかけでもある。 そんな彼の絵をカラーで見ることができ、また詳細な分析を読むことができて嬉しかった。 また河鍋暁斎の次に挙げられていた山口晃の「九相圖」は、私の中の九相図のイメージを大きく変えるものだった。 描かれているのは間違いなく九相図なのだが、死にゆく馬の胴体がバイクになっている。 やまと絵のような風景の中にバイクと融合した馬が存在している、そのチグハグさが面白かった。 一度生で見てみたい作品だ。 九相図は仏教絵画であるが、この本では文学的側面や説話にも目を向けており、たいへん面白く読むことができた。
読み終わった大河ドラマ「べらぼう」で、「愛した女性が亡くなり腐っていく様を目にしながらも、彼女の“美しい姿”を描き続ける喜多川歌麿」というシーンがあり、あまりにもつらくて最高だったのだが、そのシーンで九相図を思い出したので積読棚から引っ張り出してきた。 (歌麿がしていたことは九相図とは真逆だが) 現在では『呪術廻戦』で九相図を知った人も多いかもしれない。 私が初めて知ったのは、河鍋暁斎の展覧会だった。 幽霊・髑髏という流れで見て、かつ、暁斎が九歳の頃に川で拾った生首を写生したというエピソードを知っていたため、最初は暁斎の趣味かと思ってしまった。 後に仏教絵画だと知り、強く印象に残ったのを覚えている。 これまで私は、九相図とは男性出家者のための「性的煩悩(=女性)を退ける修行」に使われるものだと思っていた。 しかし九相図はそれだけではなく、近世初頭では女性が主体的に仏教へ関与する手段としても使われていたことが、この本を読んで分かった。 特に興味深かったのは、九相図が日本に伝わってきた頃のことだ。 九相図の各相を詠んだ詩「九相観詩」が日本に伝わったとき、出家者の悟りのための厳しい修行である「不浄観」から、在家者の共感を得やすい「無常」へと文脈が発展していた。 伝わったそのときから、文学的側面も色濃く結びついていたようだ。 そしてその後、朽ちていく死体を四季の移り変わりと重ねて詠んだ「九想詩」も生まれた。 この「無常観と四季」という組み合わせは、当時の日本人にウケるだろうな……というのが第一に感じたことだった。 九相の変化を四季の移り変わりになぞらえるという趣向は和歌にも取り入れられ、中・近世日本で制作された多くの九相図にも受け継がれているそうだ。 今回嬉しかったのは、河鍋暁斎の九相図について詳しく知ることができた点だ。 河鍋暁斎は私の推し絵師の一人であり、私が初めて九相図と出会ったきっかけでもある。 そんな彼の絵をカラーで見ることができ、また詳細な分析を読むことができて嬉しかった。 また河鍋暁斎の次に挙げられていた山口晃の「九相圖」は、私の中の九相図のイメージを大きく変えるものだった。 描かれているのは間違いなく九相図なのだが、死にゆく馬の胴体がバイクになっている。 やまと絵のような風景の中にバイクと融合した馬が存在している、そのチグハグさが面白かった。 一度生で見てみたい作品だ。 九相図は仏教絵画であるが、この本では文学的側面や説話にも目を向けており、たいへん面白く読むことができた。 - 2025年10月31日
 外国語独習法 (講談社現代新書)大山祐亮読み終わったよくSNSを拝見していて、ずっと読みたいと思っていた本。 独学で外国語を学んでいく際にどのように学習していけば良いか、ノウハウがたっぷり書かれており、たいへんためになった。 以下、ドイツ語学習に新たに取り入れたいことを挙げる。 ・暗記アプリを活用する。 ・単語を覚えるときは文やフレーズで書き取りを行う。 ・例文を複数個並べ、書き写しや音読を行って活用例に慣れる。 ・テキスト1周目は速く浅く、2周目は丁寧に、を心がける。 ・会話力を上げるために、作文力を鍛える。 ・文章をすばやく組み立ててアウトプットするために、例文をたくさん音読する。 ・「やさしい日本語」を参考に、言いたいことを言い換える練習をする。 ・非母語話者と会話練習をする。 以上の学習法はもちろんだが、私にとっては、学んでいく際の心構えのような部分もたいへん励みになった。 ・語学における失敗とは、途中で諦めてすべて放り出してしまうこと。究極的には、その一点に尽きます。途中でやめさえしなければ、いくら怠けようが語学力は進歩します。(P10) ・高いレベルに到達できなければ語学学習には意味がないというのも極端な考えです。上級レベルに到達しにくいからといって、年齢を重ねてから語学を始めても意味がないということにはなりません。外国語を極めるのではなく、その言語の学習を楽しむことや、コミュニケーションをとることを目標にするのであれば、何歳からでも遅くはありません。語学を始めるのに年齢制限などないのです。(P63) ・語学学習において、「語楽」の実現を妨げるような行為は悪です。語学に限らず、楽しんで勉強できていることに対して、「〇〇なんて勉強して役に立つの?」という質問をされることがあります。私自身も経験があります。これほどの水差し発言はありません。 草野球を楽しんでいる人に対して、「なんで趣味で野球なんかやってるの? なんでプロ野球を目指さないの?」と言う人はほとんどいないでしょう。語学も草野球と同じように、趣味として楽しむという選択肢があっても良いはずです。ところが、語学のような「実用的なスキル」と認識されているものでは、「やるからには必ず活用しなければならない」という発想に陥ってしまう人がいます。 〈略〉 語学には実用的な面があるし、それも大事なことです。しかし、実用性は語学のひとつの側面でしかありません。生まれも育ちも自分とは違う他人のことばに触れられる側面、自分の思考をことばにして紡げる側面、きれいな文字やきれいな本を鑑賞する芸術的な側面、自分の進歩を実感しやすい側面など、語学にはたくさんの魅力があります。語学はただの技能やスキルではないし、実用性は語学の本質ではないのです。 これから語学の世界に踏み込もうとする人には、そのすべての可能性を追求する権利があります。仮にスタート地点が仕事上の必要性であったとしても、学習が軌道に乗るにつれて楽しさを感じられるようになってくるかもしれません。仕事として英語、趣味として古代エジプト語を勉強するような人がいても良いじゃありませんか。面白いですよ、古代エジプト語も。 語学の可能性は無限大です。仕事に活かすのもよし、趣味として楽しむのもよし、仕事と趣味の両方にするのもよし。世界には80億人の人間がいるのですから、語学との付き合い方も80億通りあって良いはずです。(P210〜212) ・実際に仕事に使えるかはともかくとして、どんなことでも勉強してきてよかったと思う機会は必ずあります。自分の興味関心の赴くまま、好き勝手に勉強していきましょう。自分の人生は自分自身の手で飾り付けるものなのですから。(P215) 自分の好きなことを勉強したっていい。 継続さえできていたら大丈夫。 そう前向きな気持ちになれる言葉とたくさん出会い、とても励まされた。 これから先、ドイツ語を学んでいく中で立ち止まってしまうときが来たら、この本を読み返したいと思う。
外国語独習法 (講談社現代新書)大山祐亮読み終わったよくSNSを拝見していて、ずっと読みたいと思っていた本。 独学で外国語を学んでいく際にどのように学習していけば良いか、ノウハウがたっぷり書かれており、たいへんためになった。 以下、ドイツ語学習に新たに取り入れたいことを挙げる。 ・暗記アプリを活用する。 ・単語を覚えるときは文やフレーズで書き取りを行う。 ・例文を複数個並べ、書き写しや音読を行って活用例に慣れる。 ・テキスト1周目は速く浅く、2周目は丁寧に、を心がける。 ・会話力を上げるために、作文力を鍛える。 ・文章をすばやく組み立ててアウトプットするために、例文をたくさん音読する。 ・「やさしい日本語」を参考に、言いたいことを言い換える練習をする。 ・非母語話者と会話練習をする。 以上の学習法はもちろんだが、私にとっては、学んでいく際の心構えのような部分もたいへん励みになった。 ・語学における失敗とは、途中で諦めてすべて放り出してしまうこと。究極的には、その一点に尽きます。途中でやめさえしなければ、いくら怠けようが語学力は進歩します。(P10) ・高いレベルに到達できなければ語学学習には意味がないというのも極端な考えです。上級レベルに到達しにくいからといって、年齢を重ねてから語学を始めても意味がないということにはなりません。外国語を極めるのではなく、その言語の学習を楽しむことや、コミュニケーションをとることを目標にするのであれば、何歳からでも遅くはありません。語学を始めるのに年齢制限などないのです。(P63) ・語学学習において、「語楽」の実現を妨げるような行為は悪です。語学に限らず、楽しんで勉強できていることに対して、「〇〇なんて勉強して役に立つの?」という質問をされることがあります。私自身も経験があります。これほどの水差し発言はありません。 草野球を楽しんでいる人に対して、「なんで趣味で野球なんかやってるの? なんでプロ野球を目指さないの?」と言う人はほとんどいないでしょう。語学も草野球と同じように、趣味として楽しむという選択肢があっても良いはずです。ところが、語学のような「実用的なスキル」と認識されているものでは、「やるからには必ず活用しなければならない」という発想に陥ってしまう人がいます。 〈略〉 語学には実用的な面があるし、それも大事なことです。しかし、実用性は語学のひとつの側面でしかありません。生まれも育ちも自分とは違う他人のことばに触れられる側面、自分の思考をことばにして紡げる側面、きれいな文字やきれいな本を鑑賞する芸術的な側面、自分の進歩を実感しやすい側面など、語学にはたくさんの魅力があります。語学はただの技能やスキルではないし、実用性は語学の本質ではないのです。 これから語学の世界に踏み込もうとする人には、そのすべての可能性を追求する権利があります。仮にスタート地点が仕事上の必要性であったとしても、学習が軌道に乗るにつれて楽しさを感じられるようになってくるかもしれません。仕事として英語、趣味として古代エジプト語を勉強するような人がいても良いじゃありませんか。面白いですよ、古代エジプト語も。 語学の可能性は無限大です。仕事に活かすのもよし、趣味として楽しむのもよし、仕事と趣味の両方にするのもよし。世界には80億人の人間がいるのですから、語学との付き合い方も80億通りあって良いはずです。(P210〜212) ・実際に仕事に使えるかはともかくとして、どんなことでも勉強してきてよかったと思う機会は必ずあります。自分の興味関心の赴くまま、好き勝手に勉強していきましょう。自分の人生は自分自身の手で飾り付けるものなのですから。(P215) 自分の好きなことを勉強したっていい。 継続さえできていたら大丈夫。 そう前向きな気持ちになれる言葉とたくさん出会い、とても励まされた。 これから先、ドイツ語を学んでいく中で立ち止まってしまうときが来たら、この本を読み返したいと思う。 - 2025年9月25日
 李陵/山月記中島敦読み終わった衝動的に『山月記』が読みたくなって読んだ。 大まかな内容は知っていたが、ちゃんと読んだのは初めてだと思う。 虎になった李徴の語りが素晴らしく良かった。 私たちは誰もが虎になってしまう可能性を持っている。 自身を受け入れられず、暴れた感情に振り回され、支配されてしまったら、たちまち虎になってしまう。 とても現実味のある話だと思った。
李陵/山月記中島敦読み終わった衝動的に『山月記』が読みたくなって読んだ。 大まかな内容は知っていたが、ちゃんと読んだのは初めてだと思う。 虎になった李徴の語りが素晴らしく良かった。 私たちは誰もが虎になってしまう可能性を持っている。 自身を受け入れられず、暴れた感情に振り回され、支配されてしまったら、たちまち虎になってしまう。 とても現実味のある話だと思った。 - 2025年9月22日
- 2025年9月14日
- 2025年9月12日
 トラジェクトリー (文春e-book)グレゴリー・ケズナジャット読み終わった名古屋という土地、英会話教室、講師、という設定が私自身に馴染み深いもので、これまでのことを思い出しながら読んだ。 ブランドンとアポロ計画の宇宙飛行士たちとの対比が興味深かった。 確固たる目的地へと向かうために、住み慣れた場所(地球)から離れた人たち。 それに対して、中間地点にいるような気がするが、最終地点がなく宙ぶらりんなブランドン。 どこに行っても同じで、「自分」からは逃げきることはできない。 そんな終わりのない閉塞感をひしひしと感じた。 作中では、英会話教室の生徒・カワムラさんの提出物と思われる日記が挟まれる。 その日記は教室でのカワムラさんの態度とはかなりギャップがあり、彼の中の柔らかい部分、子どものように純粋な部分が表れているようだった。 私は言語に興味があるので、英語ネイティブの元同僚が言っていた以下の言葉が衝撃的だった。 (元同僚は出版関係の仕事をしている) . ——まあ、つまり、すべてが英語になっても、英語の中に日本語の一部を残すことができればいいなと思う。みんな日本語のことを忘れていっても、こんな言葉が英語の中で生き続けていたら、それはそれで素敵だなと思って。その意味では、やり甲斐のある仕事なんだ。 (P91,92) . このセリフを読んだとき、なんて傲慢で上から目線なんだと憤りを感じた。 また、英会話教室のスタッフ・ダイスケも、こう言う。 . やはりコストパフォーマンスも考慮に入れないといけないね。仮に日本語を勉強することにしたら、学習時間を控えめに設定しても、週二時間は要るでしょ。つまり年間で言うとおよそ百時間。授業の時間や移動の時間を入れれば、二百、三百時間じゃない。それは最低限でしょ? 本格的に勉強しようと思えばもっとかかるでしょう。時間の使い方は自由だけど、私ならやはりそんな時間があれば、アジアのこんなヘンテコな文字に使うよりももっと面白い使い方がいろいろあると思うなぁ。 (P65) ——あ、でも、教科書はここには持ち込まないほうがいいかも。このスペースはグローバルゾーンだからね。 (P80/「教科書」は日本語の教科書のことを指す) . ダイスケが求めているような「グローバルで活躍できる日本人」が増えて、グローバル化が進んでいっても、日本語がなくなることはないだろう(と私は願っている)。 母語というのは、自分自身である根っこを育てる力のようなものだと感じている。 言葉は人間を形作るものだ。 根を張った確固たる自分自身さえあれば、どこにいても、例え遠くに行ったとしても、宙ぶらりんにはならないのかもしれない。 そんなことを考えた。 . 表題作『トラジェクトリー』も『汽水』も、私自身の人生にとても近い作品だった。 他人事とは思えなかった。 そして「グローバル」という言葉について、何度も考えさせられた。 今の世界では、「“中心的な英語圏”に同化していくこと」が「グローバル」であると考えられていないだろうか。 少なくとも日本では、そういう傾向があるように思う。 私は幼少期から「西洋的なもの」に憧れ、語学の道を歩み、地元を出て、方言を隠しながら暮らしているが、未だ宙ぶらりんのままだ。 この本を読んで改めて、自分のルーツや居場所について考えたくなった。 . 子供の頃には方言が自ずと口をついて出た。方言であることすら意識はなかった。自分の言葉が正しくないこと、多くの人にとっては田舎の無知の証に聞こえることに気がついたのはその後だった。方言をやめる決心がついたわけではない。ただ対等に相手にされるためにはどのような言葉を話せばいいか、分かってきただけだ。地元の者同士なら方言で構わないけれど、どこでも通じるプロフェッショナルとして見做されるためには標準的な言葉を使うほかない。 少しずつイントネーションが変容した。言い回しがスタンダードなものに変わっていった。教育が身につくにつれて地方特有の言葉遣いが抜かれ、清澄とされる言葉だけが残った。 その英語はカウンターの上のロゴマークのように実用的で味気なく、なんだか物寂しい言葉だった。 (『汽水』P139,140)
トラジェクトリー (文春e-book)グレゴリー・ケズナジャット読み終わった名古屋という土地、英会話教室、講師、という設定が私自身に馴染み深いもので、これまでのことを思い出しながら読んだ。 ブランドンとアポロ計画の宇宙飛行士たちとの対比が興味深かった。 確固たる目的地へと向かうために、住み慣れた場所(地球)から離れた人たち。 それに対して、中間地点にいるような気がするが、最終地点がなく宙ぶらりんなブランドン。 どこに行っても同じで、「自分」からは逃げきることはできない。 そんな終わりのない閉塞感をひしひしと感じた。 作中では、英会話教室の生徒・カワムラさんの提出物と思われる日記が挟まれる。 その日記は教室でのカワムラさんの態度とはかなりギャップがあり、彼の中の柔らかい部分、子どものように純粋な部分が表れているようだった。 私は言語に興味があるので、英語ネイティブの元同僚が言っていた以下の言葉が衝撃的だった。 (元同僚は出版関係の仕事をしている) . ——まあ、つまり、すべてが英語になっても、英語の中に日本語の一部を残すことができればいいなと思う。みんな日本語のことを忘れていっても、こんな言葉が英語の中で生き続けていたら、それはそれで素敵だなと思って。その意味では、やり甲斐のある仕事なんだ。 (P91,92) . このセリフを読んだとき、なんて傲慢で上から目線なんだと憤りを感じた。 また、英会話教室のスタッフ・ダイスケも、こう言う。 . やはりコストパフォーマンスも考慮に入れないといけないね。仮に日本語を勉強することにしたら、学習時間を控えめに設定しても、週二時間は要るでしょ。つまり年間で言うとおよそ百時間。授業の時間や移動の時間を入れれば、二百、三百時間じゃない。それは最低限でしょ? 本格的に勉強しようと思えばもっとかかるでしょう。時間の使い方は自由だけど、私ならやはりそんな時間があれば、アジアのこんなヘンテコな文字に使うよりももっと面白い使い方がいろいろあると思うなぁ。 (P65) ——あ、でも、教科書はここには持ち込まないほうがいいかも。このスペースはグローバルゾーンだからね。 (P80/「教科書」は日本語の教科書のことを指す) . ダイスケが求めているような「グローバルで活躍できる日本人」が増えて、グローバル化が進んでいっても、日本語がなくなることはないだろう(と私は願っている)。 母語というのは、自分自身である根っこを育てる力のようなものだと感じている。 言葉は人間を形作るものだ。 根を張った確固たる自分自身さえあれば、どこにいても、例え遠くに行ったとしても、宙ぶらりんにはならないのかもしれない。 そんなことを考えた。 . 表題作『トラジェクトリー』も『汽水』も、私自身の人生にとても近い作品だった。 他人事とは思えなかった。 そして「グローバル」という言葉について、何度も考えさせられた。 今の世界では、「“中心的な英語圏”に同化していくこと」が「グローバル」であると考えられていないだろうか。 少なくとも日本では、そういう傾向があるように思う。 私は幼少期から「西洋的なもの」に憧れ、語学の道を歩み、地元を出て、方言を隠しながら暮らしているが、未だ宙ぶらりんのままだ。 この本を読んで改めて、自分のルーツや居場所について考えたくなった。 . 子供の頃には方言が自ずと口をついて出た。方言であることすら意識はなかった。自分の言葉が正しくないこと、多くの人にとっては田舎の無知の証に聞こえることに気がついたのはその後だった。方言をやめる決心がついたわけではない。ただ対等に相手にされるためにはどのような言葉を話せばいいか、分かってきただけだ。地元の者同士なら方言で構わないけれど、どこでも通じるプロフェッショナルとして見做されるためには標準的な言葉を使うほかない。 少しずつイントネーションが変容した。言い回しがスタンダードなものに変わっていった。教育が身につくにつれて地方特有の言葉遣いが抜かれ、清澄とされる言葉だけが残った。 その英語はカウンターの上のロゴマークのように実用的で味気なく、なんだか物寂しい言葉だった。 (『汽水』P139,140) - 2025年9月12日
 トラジェクトリー (文春e-book)グレゴリー・ケズナジャット読んでる
トラジェクトリー (文春e-book)グレゴリー・ケズナジャット読んでる - 2025年8月26日
 トラジェクトリー (文春e-book)グレゴリー・ケズナジャット読んでる
トラジェクトリー (文春e-book)グレゴリー・ケズナジャット読んでる - 2025年8月23日
 トラジェクトリー (文春e-book)グレゴリー・ケズナジャット読んでる
トラジェクトリー (文春e-book)グレゴリー・ケズナジャット読んでる - 2025年8月9日
- 2025年8月8日
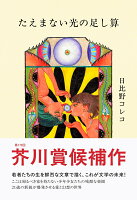 たえまない光の足し算日比野コレコ読み終わった衝撃的な作品だった。 薗やハグ、ひろめぐたち「とび商」は、「かいぶつ」と呼ばれる時計台のまわりで商売をしており、薗は異食、ひろめぐは軟派、ハグはフリーハグをしていた。 爆発を待つ時計台は薗たちの気持ちを表しているようで、気持ちがいつ爆発するか分からない危うさを感じた。 . 「痩せたらなにもかもが変わる!」 美容外科に飾られたそんな広告をきっかけに、薗はダイエットをして痩せ、異食をするようになった。 口にするものが「食べ物」であればあるほど食べられず、「食べ物ではないもの」であれば食べられる。 特に花の雄蕊と雌蕊を好んで食べる描写が強く印象に残っている。 そんな薗の行為は異様で考えられないものであったが、途中から登場する抱擁師・ハグにより、薗の異様さが私の中で薄れた。 . この小説を読む中で考えたことは、大きく分けて二つある。 一つは、世間からの性別の捉えられ方だ。 性行為に関して、世間から向けられる目が、性別(この小説では女性と男性)によってかなり異なり、イメージが固まってしまっていると感じた。 ハグ(女性)とひろめぐ(男性)の行為をSNSで目にした人たちは、ハグをか弱いもののように扱い、抱擁師としてのハグの仕事は破綻してしまう。 本当は、抱擁師であるハグの包容力で成り立っていたものなのに。 動画一つでハグの仕事が成り立たなくなってしまう流れの中で、頭のどこかで「やっぱりな」という諦めにも似た気持ちが浮かんだ。 女性を弱いもの、支配されるものだと捉えられてしまうのは、本当に悔しい。 そして、その人自身の光を性的魅力だと思われ、それが生涯拭い去れず、何をしても「そのせいだ」と思われてしまうのは、とても苦しい。 その人自身の光は変わらないはずなのに。 考えたことのもう一つは、過剰な包容力についてだ。 ハグとひろめぐの行為について、「抱擁師であるハグの包容力で成り立っていたもの」と書いたが、その包容力が恐ろしかった。 「包容力」という言葉からは温かく優しいイメージを抱くが、ハグのそれは果てしなく、それゆえに近寄りがたいような感じがした。 ハグは「みんなのひと」になりたかったし、そのためならどんな手段を使ってもいいと思っていた。 そのいきすぎた包容力は、薗の異食よりも怖く感じた。 . ハグの仕事が成り立たなくなる中で、薗の気持ちに変化が起きていたのが印象的だった。 これまで疑わず迷わず生きてきた薗が、初めて「方向転換」をすることを考える。 ハグとひろめぐが《痛くない出口》に向かったあと、「非生活者」だった薗が「人間(=生活者)」になるために動きだすラストは、ほんの少し希望があると思った。
たえまない光の足し算日比野コレコ読み終わった衝撃的な作品だった。 薗やハグ、ひろめぐたち「とび商」は、「かいぶつ」と呼ばれる時計台のまわりで商売をしており、薗は異食、ひろめぐは軟派、ハグはフリーハグをしていた。 爆発を待つ時計台は薗たちの気持ちを表しているようで、気持ちがいつ爆発するか分からない危うさを感じた。 . 「痩せたらなにもかもが変わる!」 美容外科に飾られたそんな広告をきっかけに、薗はダイエットをして痩せ、異食をするようになった。 口にするものが「食べ物」であればあるほど食べられず、「食べ物ではないもの」であれば食べられる。 特に花の雄蕊と雌蕊を好んで食べる描写が強く印象に残っている。 そんな薗の行為は異様で考えられないものであったが、途中から登場する抱擁師・ハグにより、薗の異様さが私の中で薄れた。 . この小説を読む中で考えたことは、大きく分けて二つある。 一つは、世間からの性別の捉えられ方だ。 性行為に関して、世間から向けられる目が、性別(この小説では女性と男性)によってかなり異なり、イメージが固まってしまっていると感じた。 ハグ(女性)とひろめぐ(男性)の行為をSNSで目にした人たちは、ハグをか弱いもののように扱い、抱擁師としてのハグの仕事は破綻してしまう。 本当は、抱擁師であるハグの包容力で成り立っていたものなのに。 動画一つでハグの仕事が成り立たなくなってしまう流れの中で、頭のどこかで「やっぱりな」という諦めにも似た気持ちが浮かんだ。 女性を弱いもの、支配されるものだと捉えられてしまうのは、本当に悔しい。 そして、その人自身の光を性的魅力だと思われ、それが生涯拭い去れず、何をしても「そのせいだ」と思われてしまうのは、とても苦しい。 その人自身の光は変わらないはずなのに。 考えたことのもう一つは、過剰な包容力についてだ。 ハグとひろめぐの行為について、「抱擁師であるハグの包容力で成り立っていたもの」と書いたが、その包容力が恐ろしかった。 「包容力」という言葉からは温かく優しいイメージを抱くが、ハグのそれは果てしなく、それゆえに近寄りがたいような感じがした。 ハグは「みんなのひと」になりたかったし、そのためならどんな手段を使ってもいいと思っていた。 そのいきすぎた包容力は、薗の異食よりも怖く感じた。 . ハグの仕事が成り立たなくなる中で、薗の気持ちに変化が起きていたのが印象的だった。 これまで疑わず迷わず生きてきた薗が、初めて「方向転換」をすることを考える。 ハグとひろめぐが《痛くない出口》に向かったあと、「非生活者」だった薗が「人間(=生活者)」になるために動きだすラストは、ほんの少し希望があると思った。 - 2025年8月8日
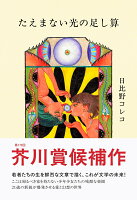 たえまない光の足し算日比野コレコ読んでる
たえまない光の足し算日比野コレコ読んでる - 2025年7月25日
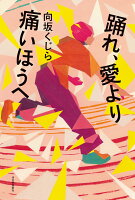 踊れ、愛より痛いほうへ向坂くじら読み終わった愛情がおぞましい、鬱陶しいと感じつつも、無意識にそれに縋ってしまっているように思えた。 抵抗していても、望んでいなくても、その愛情のもとに帰ってきてしまう。 抜け出すことができない。 アンノがテントで暮らしていることも、私にはそう見えた。 家を出ることにしたアンノは、両親に「わたしはもう、旅に出たんだと思ってください」と伝え、実家の庭にテントを設置して生活していた。 アンノ自身は親に頼らない生活をしているつもりかもしれない。 しかし実家の敷地内で暮らしていることは、アンノ自身が親から逃れられていない、自立できていないことを表しているようだった。 あーちゃん(元彼の祖母)とアンノの関係はとても興味深かった。 家族の愛情から切り離された(と思っている)二人は、友情を育んでいるように見えてそうではなく、ただこのときを一緒にやり過ごしているだけのような関係に見えた。 ともに過ごした時間は多かったかもしれないが、二人の間に愛情はなかったように思う。 アンノのバレエが忙しいしお金がないからと、アンノの母親は生まれるはずだった子どもを堕した。 その来るはずだった妹を、アンノがあーちゃんと弔う場面がとても好きだった。 遺影の代わりに自身の幼少期の写真を置いたアンノは、まるで昔の自分と決別しようとしているように見えた。 アンノの“頭が割れる”場面が、強く印象に残っている。 自分ではどうにもできないような感情が溢れ、激しく揺さぶられ、割れているから外のものが簡単に入ってきてしまう。 そのどうしようもない激情がよく表れていて好きだった。 . そのとき、足もとからふたりを見上げていたアンノの頭は、もともとそうなることが準備されていたみたいに、てっぺんからパカっと割れた。ひび割れからは脳がもりもりあふれだし、アンノは思った。ぜんぶ出ちゃう。そうしたらたいへんなことになる。だから、力のこもったお母さんの手を、それでも力いっぱいふりほどいて、あふれるままにしゃべった。 (P7)
踊れ、愛より痛いほうへ向坂くじら読み終わった愛情がおぞましい、鬱陶しいと感じつつも、無意識にそれに縋ってしまっているように思えた。 抵抗していても、望んでいなくても、その愛情のもとに帰ってきてしまう。 抜け出すことができない。 アンノがテントで暮らしていることも、私にはそう見えた。 家を出ることにしたアンノは、両親に「わたしはもう、旅に出たんだと思ってください」と伝え、実家の庭にテントを設置して生活していた。 アンノ自身は親に頼らない生活をしているつもりかもしれない。 しかし実家の敷地内で暮らしていることは、アンノ自身が親から逃れられていない、自立できていないことを表しているようだった。 あーちゃん(元彼の祖母)とアンノの関係はとても興味深かった。 家族の愛情から切り離された(と思っている)二人は、友情を育んでいるように見えてそうではなく、ただこのときを一緒にやり過ごしているだけのような関係に見えた。 ともに過ごした時間は多かったかもしれないが、二人の間に愛情はなかったように思う。 アンノのバレエが忙しいしお金がないからと、アンノの母親は生まれるはずだった子どもを堕した。 その来るはずだった妹を、アンノがあーちゃんと弔う場面がとても好きだった。 遺影の代わりに自身の幼少期の写真を置いたアンノは、まるで昔の自分と決別しようとしているように見えた。 アンノの“頭が割れる”場面が、強く印象に残っている。 自分ではどうにもできないような感情が溢れ、激しく揺さぶられ、割れているから外のものが簡単に入ってきてしまう。 そのどうしようもない激情がよく表れていて好きだった。 . そのとき、足もとからふたりを見上げていたアンノの頭は、もともとそうなることが準備されていたみたいに、てっぺんからパカっと割れた。ひび割れからは脳がもりもりあふれだし、アンノは思った。ぜんぶ出ちゃう。そうしたらたいへんなことになる。だから、力のこもったお母さんの手を、それでも力いっぱいふりほどいて、あふれるままにしゃべった。 (P7) - 2025年7月22日
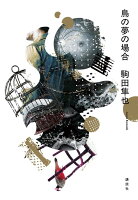 鳥の夢の場合駒田隼也読み終わった生と死、現実と非現実。 そういうものが曖昧に混ざり合っていくような感じがした。 文章の中で一人称と三人称が混ざる箇所があり、始めは読みづらかったが、次第にその人物との境目が分からなくなるような不思議な感覚になった。 離れて見ていたはずなのに、いつの間にか「わたし」になっていて、また「わたし」ではない自分になっている。 そんな感じがした。 私たちは、あるはずのものは必ずあると信じてしまっている。 疑うこともなく、当たり前にあるのだと立ち止まることもない。 しかし、この小説の中には「ないはずのものがあって、あるはずのものがない」。 でもそれは私たちが気づいていないだけで、この現実にもあるのかもしれない。 絶対にあるはずのボールが見つからないこと。 話した当人すら忘れてしまった言葉を覚えていること。 現実には存在していなかったけれど、確かに存在していた大切な時間のこと……。 そういう、特別ではない日常にも、ちぐはぐに曖昧になる瞬間、混じり合う瞬間はあるのだと思う。 普段受け流すように暮らしている日常を、ほんの少し立ち止まって見つめたくなるような作品だった。
鳥の夢の場合駒田隼也読み終わった生と死、現実と非現実。 そういうものが曖昧に混ざり合っていくような感じがした。 文章の中で一人称と三人称が混ざる箇所があり、始めは読みづらかったが、次第にその人物との境目が分からなくなるような不思議な感覚になった。 離れて見ていたはずなのに、いつの間にか「わたし」になっていて、また「わたし」ではない自分になっている。 そんな感じがした。 私たちは、あるはずのものは必ずあると信じてしまっている。 疑うこともなく、当たり前にあるのだと立ち止まることもない。 しかし、この小説の中には「ないはずのものがあって、あるはずのものがない」。 でもそれは私たちが気づいていないだけで、この現実にもあるのかもしれない。 絶対にあるはずのボールが見つからないこと。 話した当人すら忘れてしまった言葉を覚えていること。 現実には存在していなかったけれど、確かに存在していた大切な時間のこと……。 そういう、特別ではない日常にも、ちぐはぐに曖昧になる瞬間、混じり合う瞬間はあるのだと思う。 普段受け流すように暮らしている日常を、ほんの少し立ち止まって見つめたくなるような作品だった。 - 2025年7月21日
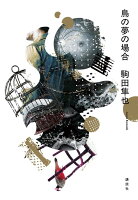 鳥の夢の場合駒田隼也読んでる
鳥の夢の場合駒田隼也読んでる - 2025年7月19日
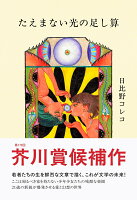 たえまない光の足し算日比野コレコ買った
たえまない光の足し算日比野コレコ買った - 2025年7月19日
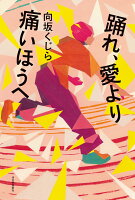 踊れ、愛より痛いほうへ向坂くじら買った
踊れ、愛より痛いほうへ向坂くじら買った
読み込み中...
