

K
@weitangshaobing
興味関心:フェミニズム、韓国、東アジア、ジェンダー、セクシュアリティ、外国語学習、海外ミステリー、メディア論、食文化、料理、旅
- 2025年12月6日
 ゴーイング・メインストリーム 過激主義が主流になる日ユリア・エブナー気になる
ゴーイング・メインストリーム 過激主義が主流になる日ユリア・エブナー気になる - 2025年12月6日
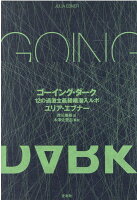 ゴーイング・ダークユリア・エブナー,西川美樹買った読んでる
ゴーイング・ダークユリア・エブナー,西川美樹買った読んでる - 2025年11月26日
 私たちに名刺がないだけで仕事してこなかったわけじゃないすんみ,京郷新聞ジェンダー企画チーム,京郷新聞ジェンダー企画班,尹怡景気になる
私たちに名刺がないだけで仕事してこなかったわけじゃないすんみ,京郷新聞ジェンダー企画チーム,京郷新聞ジェンダー企画班,尹怡景気になる - 2025年11月26日
 移動と階級伊藤将人気になる
移動と階級伊藤将人気になる - 2025年11月26日
 韓国インスタントラーメンの世界チ・ヨンジュン,中川里沙気になる
韓国インスタントラーメンの世界チ・ヨンジュン,中川里沙気になる - 2025年11月26日
 戦争みたいな味がするグレイス・M・チョー,石山徳子気になる
戦争みたいな味がするグレイス・M・チョー,石山徳子気になる - 2025年11月26日
 書かずにいられない味がある八田靖史,イ・サン(李相),イ・サン(李相)気になる
書かずにいられない味がある八田靖史,イ・サン(李相),イ・サン(李相)気になる - 2025年11月25日
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広買った読んでる
プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広買った読んでる - 2025年11月25日
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広気になる
プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広気になる - 2025年11月24日
 三体ワン・チャイ,光吉さくら,劉慈欣,大森望,立原透耶気になる
三体ワン・チャイ,光吉さくら,劉慈欣,大森望,立原透耶気になる - 2025年11月24日
 トゥモロー・アンド・トゥモロー・アンド・トゥモローガブリエル・ゼヴィン,池田真紀子読み終わった【ネタバレを避けて好きなところ引用】 この世はすべて不変と見えて実はそうではないのだと思った。子供じみた遊びが命を奪うかもしれない。友達が消えてしまうかもしれない。どれほど必死に自分を守ろうとしても、もう一つの結果になるおそれはつねに背中合わせだ。人は誰でもせいぜい人生の半分しか生きていない。ふとそんな風に思った。これまでの選択の積み重ねとしての人生がある。そしてもう一つ、捨てた選択肢が積み重なった人生がある。ときおり、そのもう一つの人生の存在が、いま現実に生きているほうの人生と同じくらいリアルに感じられることがある(p.221) 傷を舐めて癒やすことに執心していた。よく考えるとおかしな表現だ。だって、舐めたりしたら、傷はかえって悪化するのでは? 口のなかは黴菌だらけなのだから。しかし、人は自分の傷の味に耽溺しがちであることをセイディは知っている(p.340) このホテル、すごくかわいい。見る人全員を殺したくなっちゃう(p.428) 関係の一つの段階が終わりを迎えたとしても、そこからまた新たな関係が始まると信じることだ。愛とは定数であり、同時に変数でもあると知っておくことだ。(p.463) 「それ、狂気の定義じゃない? 〝狂気とは、同じ事を繰り返しながら、異なる結果を期待することである〟」(p.609)
トゥモロー・アンド・トゥモロー・アンド・トゥモローガブリエル・ゼヴィン,池田真紀子読み終わった【ネタバレを避けて好きなところ引用】 この世はすべて不変と見えて実はそうではないのだと思った。子供じみた遊びが命を奪うかもしれない。友達が消えてしまうかもしれない。どれほど必死に自分を守ろうとしても、もう一つの結果になるおそれはつねに背中合わせだ。人は誰でもせいぜい人生の半分しか生きていない。ふとそんな風に思った。これまでの選択の積み重ねとしての人生がある。そしてもう一つ、捨てた選択肢が積み重なった人生がある。ときおり、そのもう一つの人生の存在が、いま現実に生きているほうの人生と同じくらいリアルに感じられることがある(p.221) 傷を舐めて癒やすことに執心していた。よく考えるとおかしな表現だ。だって、舐めたりしたら、傷はかえって悪化するのでは? 口のなかは黴菌だらけなのだから。しかし、人は自分の傷の味に耽溺しがちであることをセイディは知っている(p.340) このホテル、すごくかわいい。見る人全員を殺したくなっちゃう(p.428) 関係の一つの段階が終わりを迎えたとしても、そこからまた新たな関係が始まると信じることだ。愛とは定数であり、同時に変数でもあると知っておくことだ。(p.463) 「それ、狂気の定義じゃない? 〝狂気とは、同じ事を繰り返しながら、異なる結果を期待することである〟」(p.609) - 2025年10月26日
 牛乳から世界がかわる小林国之気になる
牛乳から世界がかわる小林国之気になる - 2025年10月24日
 トゥモロー・アンド・トゥモロー・アンド・トゥモローガブリエル・ゼヴィン,池田真紀子買った読んでる
トゥモロー・アンド・トゥモロー・アンド・トゥモローガブリエル・ゼヴィン,池田真紀子買った読んでる - 2025年10月23日
 湯気を食べるくどうれいん読み終わった【好きなところ引用】 人生は円グラフだから、いやなことがあったらとにかくほかのことで頭の中を埋め尽くして、そのいやなことをさっさと灰色の細い「その他」にするほかないと思う。(p.70) 家で作るものがいちばんおいしい、と思ったことがある人にしか摑めない人生がある。大げさでなくそう思う。ゆとりがないときにこそ(たのむ)と菜箸を握るわたしたちに、どうかよい人生が訪れますように、と祈るような気持ちになる。 わたしの自炊は、趣味ではない。調律だ。人生に、自分で料理を作らなければ自分を保てない時間がたくさんあって、わたしは何度だってこの菜箸で、自分自身を調律していた。人生に余裕があるから自炊をたのしんでいるのではない。余裕がない人生のなかで、自分の人生に納得するためのその手段が自炊だった。(p.108) 自分の作ったものは自分の思っている味がして、おいしい。わたしはその興奮と安心に、何度でも救われている。(p.111) そういうとき、自分が何を食べたいのかもわからなくなってしまったりする。だめかも、と思ったらねぎとろ。そう決めてからずいぶん楽になった。「わたしはねぎとろが好きだから、いまねぎとろを食べるという選択をしてげんきになった」と思えることで、きちんと自分が自分のコントロール下にあることを確認できる。わたしが選んで、わたしが気に入っている、大丈夫、大丈夫。と。小さなことかもしれないけれど、参っているときはそういう小さな選択ですら人生を左右するような気もしてしまうのだ。(p.130)
湯気を食べるくどうれいん読み終わった【好きなところ引用】 人生は円グラフだから、いやなことがあったらとにかくほかのことで頭の中を埋め尽くして、そのいやなことをさっさと灰色の細い「その他」にするほかないと思う。(p.70) 家で作るものがいちばんおいしい、と思ったことがある人にしか摑めない人生がある。大げさでなくそう思う。ゆとりがないときにこそ(たのむ)と菜箸を握るわたしたちに、どうかよい人生が訪れますように、と祈るような気持ちになる。 わたしの自炊は、趣味ではない。調律だ。人生に、自分で料理を作らなければ自分を保てない時間がたくさんあって、わたしは何度だってこの菜箸で、自分自身を調律していた。人生に余裕があるから自炊をたのしんでいるのではない。余裕がない人生のなかで、自分の人生に納得するためのその手段が自炊だった。(p.108) 自分の作ったものは自分の思っている味がして、おいしい。わたしはその興奮と安心に、何度でも救われている。(p.111) そういうとき、自分が何を食べたいのかもわからなくなってしまったりする。だめかも、と思ったらねぎとろ。そう決めてからずいぶん楽になった。「わたしはねぎとろが好きだから、いまねぎとろを食べるという選択をしてげんきになった」と思えることで、きちんと自分が自分のコントロール下にあることを確認できる。わたしが選んで、わたしが気に入っている、大丈夫、大丈夫。と。小さなことかもしれないけれど、参っているときはそういう小さな選択ですら人生を左右するような気もしてしまうのだ。(p.130) - 2025年9月26日
 湯気を食べるくどうれいん買った
湯気を食べるくどうれいん買った - 2025年7月21日
 なぜか「なんとなく生きづらい」の正体メグ・アロール,野中香方子買った読んでる
なぜか「なんとなく生きづらい」の正体メグ・アロール,野中香方子買った読んでる - 2025年7月21日
 自分のために料理を作る山口祐加,星野概念読み終わった【好きなところ引用】 健康的な食事をしていると、自信が持てませんか? 今日仕事はダメダメだったけど、私の飯はうまい、というのはすごく大事です。(p.137) 気分が落ちているときには、だるくて動いていないのに地に足がついていないような、今を生きられていない感覚があると思います。さっきおっしゃったように、食べるときに食べているものの味をしっかり味わうとか、散歩するときには足で地面を踏みしめるといったことを通して、今ここが意識できるようになると、気分の安定は保ちやすくなると思います。マインドフルネスのような話です。(p.205) 目の前のものだけに集中できる時間を持つことが、現代の生活者には必要なのではないでしょうか。(p.211) 一人で食べることは「孤食」と呼ばれ、否定的な文脈で語られがちですが、実はすごく自由で豊かなことなのではないかと思います。「p.259)
自分のために料理を作る山口祐加,星野概念読み終わった【好きなところ引用】 健康的な食事をしていると、自信が持てませんか? 今日仕事はダメダメだったけど、私の飯はうまい、というのはすごく大事です。(p.137) 気分が落ちているときには、だるくて動いていないのに地に足がついていないような、今を生きられていない感覚があると思います。さっきおっしゃったように、食べるときに食べているものの味をしっかり味わうとか、散歩するときには足で地面を踏みしめるといったことを通して、今ここが意識できるようになると、気分の安定は保ちやすくなると思います。マインドフルネスのような話です。(p.205) 目の前のものだけに集中できる時間を持つことが、現代の生活者には必要なのではないでしょうか。(p.211) 一人で食べることは「孤食」と呼ばれ、否定的な文脈で語られがちですが、実はすごく自由で豊かなことなのではないかと思います。「p.259) - 2025年7月21日
 なぜか「なんとなく生きづらい」の正体メグ・アロール,野中香方子気になる
なぜか「なんとなく生きづらい」の正体メグ・アロール,野中香方子気になる - 2025年7月13日
 自分のために料理を作る山口祐加,星野概念買った読んでる
自分のために料理を作る山口祐加,星野概念買った読んでる - 2025年7月12日
 ヘルシンキ 生活の練習朴沙羅読み終わった【好きなところ引用】 誰かを「迷惑だ」と思うことで、もしかして私たちは、連帯して解決できるはずの事柄を見逃しているのかもしれない。それはもしかして、とても孤独なことではないだろうか。いろんな人たちと、そのときどきに、目的のために連帯したくないというなら、連帯するより誰かからの指示に従うことを選ぶなら、たしかに私たちの社会は、とても孤独で苦しく、生きづらい場所かも知れない。運動はみんなでやるものだ。社会はみんなで作ったり作り替えたりするものだ。普通の人々が、普通の会話を交わして、普通の結論に至る。そういうどこにも特別なことのないやりとりを繰り返して、普通の無数の人々が法律や制度やその運用のされ方や、それらの背景にある知識と規範を変えてきた。そういう普通の人々の集団の力を信じているから、私は社会学を面白いと思う。(p.202) 自分でない人間のものの見方や考え方、自分以外の人間たちが(大半が男だったり西洋人だったりするのは非常に腹立たしいが)これまで作り、調べ、話してきたことを知ることで、自分が生まれたときに与えられた条件からも、自分自身からも、自由になる。本を読むのは、今のくだらない自分を壊す手段の一つだ。(p.140)
ヘルシンキ 生活の練習朴沙羅読み終わった【好きなところ引用】 誰かを「迷惑だ」と思うことで、もしかして私たちは、連帯して解決できるはずの事柄を見逃しているのかもしれない。それはもしかして、とても孤独なことではないだろうか。いろんな人たちと、そのときどきに、目的のために連帯したくないというなら、連帯するより誰かからの指示に従うことを選ぶなら、たしかに私たちの社会は、とても孤独で苦しく、生きづらい場所かも知れない。運動はみんなでやるものだ。社会はみんなで作ったり作り替えたりするものだ。普通の人々が、普通の会話を交わして、普通の結論に至る。そういうどこにも特別なことのないやりとりを繰り返して、普通の無数の人々が法律や制度やその運用のされ方や、それらの背景にある知識と規範を変えてきた。そういう普通の人々の集団の力を信じているから、私は社会学を面白いと思う。(p.202) 自分でない人間のものの見方や考え方、自分以外の人間たちが(大半が男だったり西洋人だったりするのは非常に腹立たしいが)これまで作り、調べ、話してきたことを知ることで、自分が生まれたときに与えられた条件からも、自分自身からも、自由になる。本を読むのは、今のくだらない自分を壊す手段の一つだ。(p.140)
読み込み中...