-ゞ-
@1038sudf
- 2025年5月24日
- 2025年5月23日
 惑星カザンの桜林譲治惑星間を移動できるようになった人類は、惑星カザンに調査のための先遺隊を派遣する。しかし、先遺隊からの連絡が途絶え、彼らは消息不明となる。彼らは生きているのか?それを解明するため、主人公たち第二次調査隊は惑星カザンへと赴く・・・。 SFにおける異星人との邂逅では、だいたい衝突によって幕を開ける。しかしこの作品は、不穏なあらすじの割に大きな争いはなく、全体的に穏やかな雰囲気が漂っている。この手の物語では珍しい。 各章のタイトルが上手い。各章のラストを読んだ後、次章のタイトルを読んで展開を察したり、章を読んでからタイトルの意味が分かるなど、読んでいて面白かった。
惑星カザンの桜林譲治惑星間を移動できるようになった人類は、惑星カザンに調査のための先遺隊を派遣する。しかし、先遺隊からの連絡が途絶え、彼らは消息不明となる。彼らは生きているのか?それを解明するため、主人公たち第二次調査隊は惑星カザンへと赴く・・・。 SFにおける異星人との邂逅では、だいたい衝突によって幕を開ける。しかしこの作品は、不穏なあらすじの割に大きな争いはなく、全体的に穏やかな雰囲気が漂っている。この手の物語では珍しい。 各章のタイトルが上手い。各章のラストを読んだ後、次章のタイトルを読んで展開を察したり、章を読んでからタイトルの意味が分かるなど、読んでいて面白かった。 - 2025年5月19日
 無知学への招待塚原東吾,鶴田想人無知にはさまざまな種類がある! ヘンテコな言い分だが、この無知学という学問ではそれを真剣に研究する。 世の中には色んな無知があり、時にはあえて無知を装う事態もある。また、意図的に知識を遮断することで民衆を操作したりする。 この本を読んで、義務教育で性的な知識を教えないのは、有徳な無知(倫理的な観点からあえて知らせない、知らないようにすること)が原因なのではないかと思った。 無知の活用は日常のいたるところで行われているのだ。 我々がただ無知なだけで。
無知学への招待塚原東吾,鶴田想人無知にはさまざまな種類がある! ヘンテコな言い分だが、この無知学という学問ではそれを真剣に研究する。 世の中には色んな無知があり、時にはあえて無知を装う事態もある。また、意図的に知識を遮断することで民衆を操作したりする。 この本を読んで、義務教育で性的な知識を教えないのは、有徳な無知(倫理的な観点からあえて知らせない、知らないようにすること)が原因なのではないかと思った。 無知の活用は日常のいたるところで行われているのだ。 我々がただ無知なだけで。 - 2025年5月13日
 本屋、地元に生きる栗澤順一岩手の書店である「さわや書店」で働く著者が、本を外部に営業する外商部として奔走する——さわや書店を人々に利用してもらうため、著者はさまざまな試みを行う。 かつて本屋の仕事には外商というものがあり、本の営業マンともいうべき存在だった。 現代においては珍しい存在となり、外商の内実を知ることも難しい。 その中で、本書はその"珍しい仕事"の中身を知る貴重な手がかりとなるだろう。
本屋、地元に生きる栗澤順一岩手の書店である「さわや書店」で働く著者が、本を外部に営業する外商部として奔走する——さわや書店を人々に利用してもらうため、著者はさまざまな試みを行う。 かつて本屋の仕事には外商というものがあり、本の営業マンともいうべき存在だった。 現代においては珍しい存在となり、外商の内実を知ることも難しい。 その中で、本書はその"珍しい仕事"の中身を知る貴重な手がかりとなるだろう。 - 2025年5月7日
 目的への抵抗國分功一郎「暇と退屈の倫理学」で世間を席巻した國分功一郎が、その続編と位置付けた新書。 大学生、高校生に向けた講和を書籍化したもので、コロナ禍で起きたとある哲学者の炎上騒動、行政の権力優位など、分かりやすく解説してくれる。 ここから私の感想になるが、この本を読んでいて何度か「手段が目的化している」という言葉を想起した。 目的のための手段が、いつの間にか手段そのものに熱中している。「それは危険なことだぞ」と戒める意味合いで使われる。 たが、それは目的を絶対的に神聖視しているからこそ成り立つ。 もしも目的そのものに危険が孕んでいたとしたら、手段が目的と化すのは、手段が目的を食い止めていると言えるのではないか。 何かと肯定される目的という概念へ、本書は疑問を投げかける。一回は読んでみてほしい。
目的への抵抗國分功一郎「暇と退屈の倫理学」で世間を席巻した國分功一郎が、その続編と位置付けた新書。 大学生、高校生に向けた講和を書籍化したもので、コロナ禍で起きたとある哲学者の炎上騒動、行政の権力優位など、分かりやすく解説してくれる。 ここから私の感想になるが、この本を読んでいて何度か「手段が目的化している」という言葉を想起した。 目的のための手段が、いつの間にか手段そのものに熱中している。「それは危険なことだぞ」と戒める意味合いで使われる。 たが、それは目的を絶対的に神聖視しているからこそ成り立つ。 もしも目的そのものに危険が孕んでいたとしたら、手段が目的と化すのは、手段が目的を食い止めていると言えるのではないか。 何かと肯定される目的という概念へ、本書は疑問を投げかける。一回は読んでみてほしい。 - 2025年5月3日
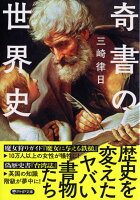 奇書の世界史三崎律日本書の構成はパンドラの箱と呼べるかもしれない。 本書では数奇な運命を辿った書物=奇書と定義し、さまざまな本を紹介する。その中には偽書もいくつか紹介されており、嘘を語ることの悪影響をいやでも知ることになる。 だが、最後に紹介される「月世界旅行(ジュール・ヴェルヌ)」では、夢物語という嘘によって現実が進歩するという事例が示される。 そして本項のラスト。 「人はよく「現実とフィクションの区別もつかないなんて」という皮肉を語ります。しかし私たちは、かつて空想にすぎないと一笑に付された物語のなかに生きているのです。 「世界」という歯車を誰よりも駆動させる者とは、誰よりも空想のなかに生きる者のことなのかもしれません。」 本で嘘を語るのは悪影響かもしれないと思わせつつ、最後に嘘から出た真が出てくる。この構成によって、内容は重たいながらも読後感を爽やかなものにしている。
奇書の世界史三崎律日本書の構成はパンドラの箱と呼べるかもしれない。 本書では数奇な運命を辿った書物=奇書と定義し、さまざまな本を紹介する。その中には偽書もいくつか紹介されており、嘘を語ることの悪影響をいやでも知ることになる。 だが、最後に紹介される「月世界旅行(ジュール・ヴェルヌ)」では、夢物語という嘘によって現実が進歩するという事例が示される。 そして本項のラスト。 「人はよく「現実とフィクションの区別もつかないなんて」という皮肉を語ります。しかし私たちは、かつて空想にすぎないと一笑に付された物語のなかに生きているのです。 「世界」という歯車を誰よりも駆動させる者とは、誰よりも空想のなかに生きる者のことなのかもしれません。」 本で嘘を語るのは悪影響かもしれないと思わせつつ、最後に嘘から出た真が出てくる。この構成によって、内容は重たいながらも読後感を爽やかなものにしている。 - 2025年5月2日
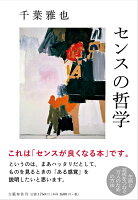 センスの哲学千葉雅也「センスとはなにか?」「センスが良いとはどういうことか?」を哲学の観点から考えた著者。その結果、「センスとはリズムである」という自身の"哲学"を見出す。 この本を読んで、温故知新という熟語について考えるようになった。 故を温め新しきを知るとは言うものの、故をどこまで温めるのかは人によって違う。極端な話、ずっと温め続けることだってできる。しかしそれでは新しさに向かうことができない。 まだ温まりきっていないとしても、どこかで切り上げて新しさに向かう妥協が、温故知新の秘訣なのかもしれない。
センスの哲学千葉雅也「センスとはなにか?」「センスが良いとはどういうことか?」を哲学の観点から考えた著者。その結果、「センスとはリズムである」という自身の"哲学"を見出す。 この本を読んで、温故知新という熟語について考えるようになった。 故を温め新しきを知るとは言うものの、故をどこまで温めるのかは人によって違う。極端な話、ずっと温め続けることだってできる。しかしそれでは新しさに向かうことができない。 まだ温まりきっていないとしても、どこかで切り上げて新しさに向かう妥協が、温故知新の秘訣なのかもしれない。 - 2025年4月28日
 世界史を大きく動かした植物稲垣栄洋マヤの伝説には、トウモロコシから人間が生まれたという話がある——人間と植物の関係は、捕食者と非捕食者という視点で見られがちだが、実は植物が人間に捕食"させている"のではないか?と思わされた。 植物は世界中に伝播しており、人間の食文化に深く根付いている。もはや人間は植物無しでは生きていけない。 はたして、人間は植物を管理しているのか・・・?我々が彼らに依存しているのではないか・・・? 本書のタイトルを見ると、「世界史を大きく動かした」とあるが、これは決して誇張ではないのである。
世界史を大きく動かした植物稲垣栄洋マヤの伝説には、トウモロコシから人間が生まれたという話がある——人間と植物の関係は、捕食者と非捕食者という視点で見られがちだが、実は植物が人間に捕食"させている"のではないか?と思わされた。 植物は世界中に伝播しており、人間の食文化に深く根付いている。もはや人間は植物無しでは生きていけない。 はたして、人間は植物を管理しているのか・・・?我々が彼らに依存しているのではないか・・・? 本書のタイトルを見ると、「世界史を大きく動かした」とあるが、これは決して誇張ではないのである。 - 2025年4月27日
- 2025年4月25日
 コンビニ人間 (文春文庫)村田沙耶香コンビニエンスストアのアルバイトを18年間続けている女性が、一人の男に出会ってアルバイトを辞める話。 こう書くとロマンチックである。 が、実際は違う。女性は世の慣習に共感できない変わり者だし、男もこじらせすぎて世間から疎まれている厄介者だ。ラブコメディかと思わせておいて、むしろ真逆を行く展開が待っていた。 世間と女性、世間と男、女性と男。彼らは最後まで分かりあえない。その非情さが徹底して描かれる。
コンビニ人間 (文春文庫)村田沙耶香コンビニエンスストアのアルバイトを18年間続けている女性が、一人の男に出会ってアルバイトを辞める話。 こう書くとロマンチックである。 が、実際は違う。女性は世の慣習に共感できない変わり者だし、男もこじらせすぎて世間から疎まれている厄介者だ。ラブコメディかと思わせておいて、むしろ真逆を行く展開が待っていた。 世間と女性、世間と男、女性と男。彼らは最後まで分かりあえない。その非情さが徹底して描かれる。 - 2025年4月21日
 絶望読書頭木弘樹大学生の頃に難病を患い、人生に絶望した著者。病室で文学に触れ、「絶望した時に読書をする」ことの意味を悟る。 小説をはじめ、娯楽は楽しむものとして存在している。しかし、心が鬱屈した時に楽しいものを見ると、より一層気分は沈んでしまう。 そうした娯楽を、本書は絶望した時の糧として活かすことを説く。 絶望読書というタイトルから手に取るのは敬遠されるかもしれないが、意外にも読み味は軽かった。
絶望読書頭木弘樹大学生の頃に難病を患い、人生に絶望した著者。病室で文学に触れ、「絶望した時に読書をする」ことの意味を悟る。 小説をはじめ、娯楽は楽しむものとして存在している。しかし、心が鬱屈した時に楽しいものを見ると、より一層気分は沈んでしまう。 そうした娯楽を、本書は絶望した時の糧として活かすことを説く。 絶望読書というタイトルから手に取るのは敬遠されるかもしれないが、意外にも読み味は軽かった。 - 2025年4月20日
- 2025年4月17日
 花と昆虫、不思議なだましあい発見記正者章子,田中肇読み終わった雄と雌を行き来する花、 ハナアブ類の序列、 いたちごっこの果てに実現した花と昆虫の共生・・・ 花と昆虫の駆け引きをかき集め、紹介した本。花生態学を中心とした専門的な内容だが、イラストが豊富で、花の仕組みを分かりやすく図解してくれる。 また、著者自身のエピソードが面白い。花を観察する様が不審者として捉えられたり、ルーペの倍率に関する話が出てきたりする。
花と昆虫、不思議なだましあい発見記正者章子,田中肇読み終わった雄と雌を行き来する花、 ハナアブ類の序列、 いたちごっこの果てに実現した花と昆虫の共生・・・ 花と昆虫の駆け引きをかき集め、紹介した本。花生態学を中心とした専門的な内容だが、イラストが豊富で、花の仕組みを分かりやすく図解してくれる。 また、著者自身のエピソードが面白い。花を観察する様が不審者として捉えられたり、ルーペの倍率に関する話が出てきたりする。 - 2025年4月15日
 草枕夏目漱石「純文学とは何か?」と人に聞かれたら、自分はまずこの本を差し出す。自分にとって草枕とは純文学そのものであり、草枕を読めば純文学とは何かが分かると思っている。 一人の画工が旅をして、旅先で女将やら坊さんと話をするというだけの平坦な物語に、漱石の文体と思想論が作品全体を彩っている。
草枕夏目漱石「純文学とは何か?」と人に聞かれたら、自分はまずこの本を差し出す。自分にとって草枕とは純文学そのものであり、草枕を読めば純文学とは何かが分かると思っている。 一人の画工が旅をして、旅先で女将やら坊さんと話をするというだけの平坦な物語に、漱石の文体と思想論が作品全体を彩っている。 - 2025年4月12日
 増補 海洋国家日本の戦後史宮城大蔵現在、日本と対立している国と言われて思い浮かぶのは韓国(と北朝鮮)や中国、ロシアであろうか(それでも文化的な交流はされている)。 しかし、戦後まもなくは東南アジアの国々とも緊張した関係にあった。現代になってその空気感が伝わっていないのは、先人たちの外交における尽力があってこそである。 本書では、日本の戦後まもない時代の外交について記されている。この国の歴史上もっとも外交に難があった時代、当時の日本人はどう立ち回ったのか?戦後日本とアジアの歴史について知りたい人はぜひ。
増補 海洋国家日本の戦後史宮城大蔵現在、日本と対立している国と言われて思い浮かぶのは韓国(と北朝鮮)や中国、ロシアであろうか(それでも文化的な交流はされている)。 しかし、戦後まもなくは東南アジアの国々とも緊張した関係にあった。現代になってその空気感が伝わっていないのは、先人たちの外交における尽力があってこそである。 本書では、日本の戦後まもない時代の外交について記されている。この国の歴史上もっとも外交に難があった時代、当時の日本人はどう立ち回ったのか?戦後日本とアジアの歴史について知りたい人はぜひ。 - 2025年4月4日
 傷を愛せるか 増補新版宮地尚子読み終わった
傷を愛せるか 増補新版宮地尚子読み終わった - 2025年3月7日
 黄金蝶を追って相川英輔「よく「あの人には才能がある」などというフレーズが褒め言葉として使われることがあるが、それは正しくない。実際には才能というものはいくつもの階層に分かれているのだ。」 本作の収録作の一つ『日曜日の翌日はいつも』の一文。才能の有無を問う文章はよく見かけるが、才能の質を問う文章には初めて会った。
黄金蝶を追って相川英輔「よく「あの人には才能がある」などというフレーズが褒め言葉として使われることがあるが、それは正しくない。実際には才能というものはいくつもの階層に分かれているのだ。」 本作の収録作の一つ『日曜日の翌日はいつも』の一文。才能の有無を問う文章はよく見かけるが、才能の質を問う文章には初めて会った。
読み込み中...



