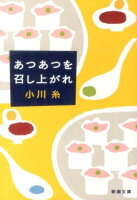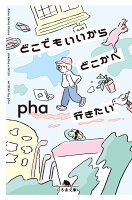あるふ
@alf0820
感想やメモを残していきます。
- 2025年10月1日
- 2025年9月7日
 学芸員しか知らない 美術館が楽しくなる話ちいさな美術館の学芸員読み終わった一つの展覧会ができるまでには想像していたより多くの工程があることが分かった。作品を借りに行く時、作品の護衛のために輸送業者だけでなく学芸員が同行しているのは驚きだった。 図録は今まであまり購入することはなかったけど、学芸員の方が展覧会のアーカイブとして苦労して制作されていると知って、今度美術館に行った時は是非手に入れたいと思った。 大規模な展覧会には新聞社が密接に関わっているらしい。実際に今行われている展覧会について調べてみると、主催の欄にいくつかの新聞社の名前が並んでいた。企画に新聞社の文化事業部が携わることもあるそう。 p133心が震えているということは、その作品があなたの常識や固定観念をコツコツと叩いてひびを入れている証拠です。 様々なアート作品に触れる度にそのひびは大きくなっていき、どこかのタイミングでパカッと割れるかもしれません。 p134すぐに応えの出ない、分からない状態をただのストレスととらえるのではなく、思考のストレッチと前向きに考えられるようになればしめたものです。
学芸員しか知らない 美術館が楽しくなる話ちいさな美術館の学芸員読み終わった一つの展覧会ができるまでには想像していたより多くの工程があることが分かった。作品を借りに行く時、作品の護衛のために輸送業者だけでなく学芸員が同行しているのは驚きだった。 図録は今まであまり購入することはなかったけど、学芸員の方が展覧会のアーカイブとして苦労して制作されていると知って、今度美術館に行った時は是非手に入れたいと思った。 大規模な展覧会には新聞社が密接に関わっているらしい。実際に今行われている展覧会について調べてみると、主催の欄にいくつかの新聞社の名前が並んでいた。企画に新聞社の文化事業部が携わることもあるそう。 p133心が震えているということは、その作品があなたの常識や固定観念をコツコツと叩いてひびを入れている証拠です。 様々なアート作品に触れる度にそのひびは大きくなっていき、どこかのタイミングでパカッと割れるかもしれません。 p134すぐに応えの出ない、分からない状態をただのストレスととらえるのではなく、思考のストレッチと前向きに考えられるようになればしめたものです。 - 2025年8月31日
 胃が合うふたり千早茜,新井見枝香読み終わった1ヶ月ほどかけて読了。表紙が可愛らしい。 2人の人生が綴られていて、そこに美味な食べ物が存在するのは意味があるのだと思った。 食べ物の表現法が個性的でとても美味しそう。特に甘露の薔薇と林檎のタンユェンの比喩表現がインパクトが強くて頭から離れない。「天女のおやつみたいに甘やかなかおりと、五つめの団子になって浸かりたいような温度が心地よかった。」 その他2人が行ったお店はどれも気になったので是非行ってみたい!沢山マップにピン留めした。 新井さんが自由すぎて面白かった。こんなに自由に生きてる人がいるんだと思うと心が軽くなった。 2人とも個性が強いのに胃が合う相手とこんな関係性でいられるのが素敵だなと思った。
胃が合うふたり千早茜,新井見枝香読み終わった1ヶ月ほどかけて読了。表紙が可愛らしい。 2人の人生が綴られていて、そこに美味な食べ物が存在するのは意味があるのだと思った。 食べ物の表現法が個性的でとても美味しそう。特に甘露の薔薇と林檎のタンユェンの比喩表現がインパクトが強くて頭から離れない。「天女のおやつみたいに甘やかなかおりと、五つめの団子になって浸かりたいような温度が心地よかった。」 その他2人が行ったお店はどれも気になったので是非行ってみたい!沢山マップにピン留めした。 新井さんが自由すぎて面白かった。こんなに自由に生きてる人がいるんだと思うと心が軽くなった。 2人とも個性が強いのに胃が合う相手とこんな関係性でいられるのが素敵だなと思った。 - 2025年8月21日
 どこからが病気なの?市原真読み終わった「病気は一つの要因からなる単純なものではなく無数の要因が絡み合ってなるものである」ということを前提として、病気に関する疑問に著者が回答していく。高校生向けの本ということで、例えが多く、噛み砕かれて解説されていて読みやすかった。 p54医療の世界には、診断名が決まらなくても行動指針が決まるならばまずはよし、という価値観が存在する p86医療を考える際に「時間軸」は極めて大事なモチーフである p187知性は恐怖を飼い慣らす手綱
どこからが病気なの?市原真読み終わった「病気は一つの要因からなる単純なものではなく無数の要因が絡み合ってなるものである」ということを前提として、病気に関する疑問に著者が回答していく。高校生向けの本ということで、例えが多く、噛み砕かれて解説されていて読みやすかった。 p54医療の世界には、診断名が決まらなくても行動指針が決まるならばまずはよし、という価値観が存在する p86医療を考える際に「時間軸」は極めて大事なモチーフである p187知性は恐怖を飼い慣らす手綱 - 2025年8月21日
- 2025年8月19日
 カフネ阿部暁子読み終わった差し伸べられた手によって登場人物達が救われていく物語。誰も悪くないのに上手くいかないところが人生をリアルに表しているなと思った。 後半はボロボロ泣いた。予想外の結末だった。 自分や周りの人のことを大事にしたいと思えた。
カフネ阿部暁子読み終わった差し伸べられた手によって登場人物達が救われていく物語。誰も悪くないのに上手くいかないところが人生をリアルに表しているなと思った。 後半はボロボロ泣いた。予想外の結末だった。 自分や周りの人のことを大事にしたいと思えた。 - 2025年8月16日
- 2025年8月15日
 本を読む人はうまくいく長倉顕太読み終わった今までは1冊を時間をかけてなるべく完璧に読み込むような読書をしていたが、「広く浅い読書はさまざまな分野の人々との会話に繋がる」と書かれていて、本の読み方を改めてみるのもありだと思った。 読む本に迷った時、ベストセラー作家が読んでいる本を読むという「本棚コピー読書法」は是非実践してみたい。 第6章の読書体質になる22のアクションプランでは、もう既に実践できているものもあったが、さらに新たな読書法を試してみたくなった。積ん読は悪いことではなく将来の自分への投資という考え方が素敵だなと思った。 「移動する人はうまくいく」も読みたくなった。
本を読む人はうまくいく長倉顕太読み終わった今までは1冊を時間をかけてなるべく完璧に読み込むような読書をしていたが、「広く浅い読書はさまざまな分野の人々との会話に繋がる」と書かれていて、本の読み方を改めてみるのもありだと思った。 読む本に迷った時、ベストセラー作家が読んでいる本を読むという「本棚コピー読書法」は是非実践してみたい。 第6章の読書体質になる22のアクションプランでは、もう既に実践できているものもあったが、さらに新たな読書法を試してみたくなった。積ん読は悪いことではなく将来の自分への投資という考え方が素敵だなと思った。 「移動する人はうまくいく」も読みたくなった。 - 2025年6月28日
 途中まで読んだ8章以降本格的に科学で難しくて途中で断念。 チーズは簡単に作れるものだと思っていたけど、完成までかなりの工程がある科学の結晶のような複雑な食べ物なのだと知った。これからは多少値が張っても我慢出来るかも…。 様々な種類のチーズがどのように作られているのか説明されていて、入れる菌の種類や熟成期間の長さを変えるだけで全く異なる性質のチーズが作られることに驚いた。穴あきチーズのエメンタールチーズは炭酸ガスを発生させる菌を入れているから穴がポコポコあいているらしい。他にも洞窟で熟成させるチーズがあったりと、本当に個性豊かでこれらの食べ物を「チーズ」という一括りにするのはもったいない気がしてきた。 乳を固めて固体にするのは人間がチーズを作る時だけではなく、子牛の胃の中でも行われていて子牛の第4胃では乳を固めて小腸を通過する時間を長くすることで消化吸収を高めているとのこと。チーズは動物に生来備わっているしくみを利用して作られた食べ物って思うと神聖さを感じてくる。 筋トレについて調べているとよくみかけるホエイはチーズを作る際の副産物だと知った。牛乳って偉大だ。
途中まで読んだ8章以降本格的に科学で難しくて途中で断念。 チーズは簡単に作れるものだと思っていたけど、完成までかなりの工程がある科学の結晶のような複雑な食べ物なのだと知った。これからは多少値が張っても我慢出来るかも…。 様々な種類のチーズがどのように作られているのか説明されていて、入れる菌の種類や熟成期間の長さを変えるだけで全く異なる性質のチーズが作られることに驚いた。穴あきチーズのエメンタールチーズは炭酸ガスを発生させる菌を入れているから穴がポコポコあいているらしい。他にも洞窟で熟成させるチーズがあったりと、本当に個性豊かでこれらの食べ物を「チーズ」という一括りにするのはもったいない気がしてきた。 乳を固めて固体にするのは人間がチーズを作る時だけではなく、子牛の胃の中でも行われていて子牛の第4胃では乳を固めて小腸を通過する時間を長くすることで消化吸収を高めているとのこと。チーズは動物に生来備わっているしくみを利用して作られた食べ物って思うと神聖さを感じてくる。 筋トレについて調べているとよくみかけるホエイはチーズを作る際の副産物だと知った。牛乳って偉大だ。 - 2025年6月11日
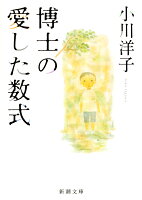 博士の愛した数式小川洋子読み終わった三人で過ごす時間は、それぞれがお互いを思いやり、温もりで溢れた尊いものであることがあることがよく伝わってきた。そんな時間がいつまでも続いてほしかったが、理想通りにはいかず小さな綻びが生じている様をタイガースの戦況と照らし合わすように表現されていて受け入れざるを得なかった。 博士の変化や、未亡人との関係性など明言はせず読み手の想像力を掻き立てる表現が多々用いられていて彼らの過ごす様子を間近で見守るような気持ちで読み進めた。 私も博士のおかげで数学の美しさを少し理解出来た気がするが、実際に博士から説明を受けた二人はよりダイレクトに美しさを目の当たりに出来たのだろうなと思うと羨ましい。 強い言葉や明確な言葉を用いずに遠回し遠回しに繊細に丁寧に本1冊を丸々使って表現されている三人の生活を、私が簡単な言葉で言い換えてしまったら全てが台無しになる気がして感想を上手く書くことが出来ない。でも間違いなく出会えて良かった1冊だった。
博士の愛した数式小川洋子読み終わった三人で過ごす時間は、それぞれがお互いを思いやり、温もりで溢れた尊いものであることがあることがよく伝わってきた。そんな時間がいつまでも続いてほしかったが、理想通りにはいかず小さな綻びが生じている様をタイガースの戦況と照らし合わすように表現されていて受け入れざるを得なかった。 博士の変化や、未亡人との関係性など明言はせず読み手の想像力を掻き立てる表現が多々用いられていて彼らの過ごす様子を間近で見守るような気持ちで読み進めた。 私も博士のおかげで数学の美しさを少し理解出来た気がするが、実際に博士から説明を受けた二人はよりダイレクトに美しさを目の当たりに出来たのだろうなと思うと羨ましい。 強い言葉や明確な言葉を用いずに遠回し遠回しに繊細に丁寧に本1冊を丸々使って表現されている三人の生活を、私が簡単な言葉で言い換えてしまったら全てが台無しになる気がして感想を上手く書くことが出来ない。でも間違いなく出会えて良かった1冊だった。 - 2025年6月9日
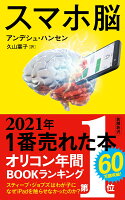 スマホ脳アンデシュ・ハンセン,久山葉子読み終わった一世代を・1つと例え、おびただしい量の・で埋め尽くされた見開きから始まり、私達が慣れきっている当たり前の世界は最後の・数個分であるという書き出しから始まる。私たちはそれらの・の連なりの最後のたった数個分で周囲の環境を著しく変化させてしまったのでそれに合わせた進化が出来ていない。主にそれが原因で心身に不具合が発生しているという内容。冒頭の説明のように分かりやすい例え話が多くスルスル読めた。私自身SNSの時間制限をして運動習慣をつけてから精神面の不安定さが改善されるのを確かに感じていた。それらが多くの実験結果を元に説明されていて納得することが出来た。 p74 「かもしれない」がドーパミンを増やす 「いいねがついたかも?見てみよう」は「ポーカーをもう1ゲームだけ、次こそは勝てるはず」と同じ p154 SNSは「私達の注目」を製品とし、広告主に転売している p248最大限にストレスレベルを下げ、集中力を高めたければ週に3回45分、出来れば息が切れて汗もかくまで運動するといい
スマホ脳アンデシュ・ハンセン,久山葉子読み終わった一世代を・1つと例え、おびただしい量の・で埋め尽くされた見開きから始まり、私達が慣れきっている当たり前の世界は最後の・数個分であるという書き出しから始まる。私たちはそれらの・の連なりの最後のたった数個分で周囲の環境を著しく変化させてしまったのでそれに合わせた進化が出来ていない。主にそれが原因で心身に不具合が発生しているという内容。冒頭の説明のように分かりやすい例え話が多くスルスル読めた。私自身SNSの時間制限をして運動習慣をつけてから精神面の不安定さが改善されるのを確かに感じていた。それらが多くの実験結果を元に説明されていて納得することが出来た。 p74 「かもしれない」がドーパミンを増やす 「いいねがついたかも?見てみよう」は「ポーカーをもう1ゲームだけ、次こそは勝てるはず」と同じ p154 SNSは「私達の注目」を製品とし、広告主に転売している p248最大限にストレスレベルを下げ、集中力を高めたければ週に3回45分、出来れば息が切れて汗もかくまで運動するといい - 2025年6月8日
- 2025年6月7日
- 2025年6月7日
- 2025年6月5日
 好きな食べ物がみつからない古賀及子読み終わった筆者と同じく好きな食べ物はなんですか?と聞かれて迷いなく答えられる自信はない。小学生の頃はイチゴ(可愛らしくて女の子らしい食べ物の代表格)と答えていたけど、今はアレルギーで食べられなくなったし改めて今自分の好きな食べ物はなんだろうと考えてみるとパッと答えが出てこない。私の好きな食べ物はなんだろうと考えながら読みすすめていくと、そうそうこれもあったなと好きな食べ物を思い出すことが出来て楽しかった。 自分の好きな〇〇を決めることで、他者とのコミュニケーションに繋がるだけでなく、自分自身のコミュニケーションにも繋がる(お!と思える瞬間が増え自分が活性化する)という話に納得した。私も著者に倣って、私の好きな食べ物をここで一度決めておく。私の好きな食べ物は塩パンということにしておく。これで街のパン屋を見かけた時にお!と思うことが出来るようになった。 食べ物の挿絵がかわいくて章末に辿り着く度ににやにやした。終盤のまさかの伏線回収が面白かった。
好きな食べ物がみつからない古賀及子読み終わった筆者と同じく好きな食べ物はなんですか?と聞かれて迷いなく答えられる自信はない。小学生の頃はイチゴ(可愛らしくて女の子らしい食べ物の代表格)と答えていたけど、今はアレルギーで食べられなくなったし改めて今自分の好きな食べ物はなんだろうと考えてみるとパッと答えが出てこない。私の好きな食べ物はなんだろうと考えながら読みすすめていくと、そうそうこれもあったなと好きな食べ物を思い出すことが出来て楽しかった。 自分の好きな〇〇を決めることで、他者とのコミュニケーションに繋がるだけでなく、自分自身のコミュニケーションにも繋がる(お!と思える瞬間が増え自分が活性化する)という話に納得した。私も著者に倣って、私の好きな食べ物をここで一度決めておく。私の好きな食べ物は塩パンということにしておく。これで街のパン屋を見かけた時にお!と思うことが出来るようになった。 食べ物の挿絵がかわいくて章末に辿り着く度ににやにやした。終盤のまさかの伏線回収が面白かった。 - 2025年6月1日
 木曜日にはココアを青山美智子読み終わった登場人物達の視点で描かれる12色の物語。何気ない言葉で救われてゆく登場人物達の物語に私の心も軽くなるような気持ちがした。半世紀ロマンスとラルフさんの一番良き日が特に好きだった。 物語は日本とシドニーを舞台としていて、オーストラリアという国に興味が湧いた。秋の桜、シドニーのジャカランダを見に行きたいと思った。 私も心落ち着く行きつけの喫茶店が欲しくなった。
木曜日にはココアを青山美智子読み終わった登場人物達の視点で描かれる12色の物語。何気ない言葉で救われてゆく登場人物達の物語に私の心も軽くなるような気持ちがした。半世紀ロマンスとラルフさんの一番良き日が特に好きだった。 物語は日本とシドニーを舞台としていて、オーストラリアという国に興味が湧いた。秋の桜、シドニーのジャカランダを見に行きたいと思った。 私も心落ち着く行きつけの喫茶店が欲しくなった。 - 2025年5月28日
- 2025年5月27日
 「好き」を言語化する技術三宅香帆読み終わったライブの後などすぐにSNSで他人の感想を漁ってしまう癖があるので、全体的にとても図星の内容が多かった。漁る前に自分の感想を書き留めておくことの大切さを知った。 話に興味を持ってもらえる導入例が納得出来たし勉強になった。 感想を書く前に他人の感想を見ない。 自分の感情を言語化する大切さ、 他人を気にせず自分の思うまま書いていいと自信をもらえた。 良かったところを細かく挙げていく、 共感、不快→自分との共通点 驚き、退屈→どこが新しい、ありきたりなのか 周りと違う意見を発信する時、「みんなの意見とは違うけど」の一文があると受け入れてもらいやすい。 長文を書く時は誰に何を伝えたいのかを考えて書く。 書き出し→サビ、自分語りは最初にやっておくべき、問いから始める 文章は後で修正することを前提にまず書き上げることが大切。
「好き」を言語化する技術三宅香帆読み終わったライブの後などすぐにSNSで他人の感想を漁ってしまう癖があるので、全体的にとても図星の内容が多かった。漁る前に自分の感想を書き留めておくことの大切さを知った。 話に興味を持ってもらえる導入例が納得出来たし勉強になった。 感想を書く前に他人の感想を見ない。 自分の感情を言語化する大切さ、 他人を気にせず自分の思うまま書いていいと自信をもらえた。 良かったところを細かく挙げていく、 共感、不快→自分との共通点 驚き、退屈→どこが新しい、ありきたりなのか 周りと違う意見を発信する時、「みんなの意見とは違うけど」の一文があると受け入れてもらいやすい。 長文を書く時は誰に何を伝えたいのかを考えて書く。 書き出し→サビ、自分語りは最初にやっておくべき、問いから始める 文章は後で修正することを前提にまず書き上げることが大切。 - 2025年5月20日
- 2025年5月18日
読み込み中...