こよなく
@coyonaku
読んだ本の中身を恐ろしいぐらい憶えてないので、記録をつけることにしました。
- 2025年11月23日
 消費者と日本経済の歴史満薗勇読み終わった自然淘汰的に便利で快適な方に流れた結果、今の自己責任かつ顧客満足を追求したお客様の時代なんでしょうけど、改めて消費者の権利と責任は自覚する必要があるなと。 外国人労働者の賃金未払のニュース見てから、あんなに好きだったシャトレーゼで買物するの未だに我慢してますんで、私も。
消費者と日本経済の歴史満薗勇読み終わった自然淘汰的に便利で快適な方に流れた結果、今の自己責任かつ顧客満足を追求したお客様の時代なんでしょうけど、改めて消費者の権利と責任は自覚する必要があるなと。 外国人労働者の賃金未払のニュース見てから、あんなに好きだったシャトレーゼで買物するの未だに我慢してますんで、私も。 - 2025年11月19日
 生き物の死にざま稲垣栄洋読み終わった生と死は表裏一体ですから。死にざまと題されてはいるけど、多様な種が遺伝子を残す為の千差万別の戦略が知れる、雑学本として楽しめた。 人間も他の生物も遺伝子を残すプログラミングされた物体に変わりなくて、他の生物との違いは、人間の方が多少は複雑な思考が出来ることだと考えてたんだけど、最後の死を悼むゾウの話を読むと、ゾウの方が死について深く考えたり理解してたりすんのかなぁと。
生き物の死にざま稲垣栄洋読み終わった生と死は表裏一体ですから。死にざまと題されてはいるけど、多様な種が遺伝子を残す為の千差万別の戦略が知れる、雑学本として楽しめた。 人間も他の生物も遺伝子を残すプログラミングされた物体に変わりなくて、他の生物との違いは、人間の方が多少は複雑な思考が出来ることだと考えてたんだけど、最後の死を悼むゾウの話を読むと、ゾウの方が死について深く考えたり理解してたりすんのかなぁと。 - 2025年11月18日
 芽むしり仔撃ち大江健三郎読み終わった理不尽や死の恐怖の存在感と、子供たちのみずみずしく溌剌と迸る情動。負と正、静と動の描写の気圧される。圧倒的な文章で読まされる時ってめちゃくちゃ嬉しい、文学に触れてるって気持ちになる。タイトル回収もゾッとした。理不尽や死ってそこに横たわってるだけで脅威。
芽むしり仔撃ち大江健三郎読み終わった理不尽や死の恐怖の存在感と、子供たちのみずみずしく溌剌と迸る情動。負と正、静と動の描写の気圧される。圧倒的な文章で読まされる時ってめちゃくちゃ嬉しい、文学に触れてるって気持ちになる。タイトル回収もゾッとした。理不尽や死ってそこに横たわってるだけで脅威。 - 2025年11月13日
 第四間氷期安部公房読み終わった山本研究所を訪れてからが超面白い。超SF。 偶然ドーキンスの進化の本を直近で読んでたから余計にくらった。長い時間をかけて自然選択的に進化しようと、意識的に改造して突然に進化しようと、未来を肯定するには現実は捨て去られる。 風を感じようとする水棲人の少年に感傷的になってしまう自分は、断絶した未来でも現実を温存したい側の人間だ。 先週の探偵ナイトスクープを見ていると、宿題の人権標語をAIに作ってもらい、あろうことか入選してしまった子供が出ていた。しかも同じようにAIに標語を作らせて入選した子が複数おり、誰も罪悪感を感じていなかった。これも未来の価値観なのか。
第四間氷期安部公房読み終わった山本研究所を訪れてからが超面白い。超SF。 偶然ドーキンスの進化の本を直近で読んでたから余計にくらった。長い時間をかけて自然選択的に進化しようと、意識的に改造して突然に進化しようと、未来を肯定するには現実は捨て去られる。 風を感じようとする水棲人の少年に感傷的になってしまう自分は、断絶した未来でも現実を温存したい側の人間だ。 先週の探偵ナイトスクープを見ていると、宿題の人権標語をAIに作ってもらい、あろうことか入選してしまった子供が出ていた。しかも同じようにAIに標語を作らせて入選した子が複数おり、誰も罪悪感を感じていなかった。これも未来の価値観なのか。 - 2025年11月11日
 進化とは何かリチャード・ドーキンス,吉成真由美読み終わったそりゃ「創造説」なんて信じてないし、人類には猿の祖先がいて、これからも進化していくもんだと前から思ってたけど、ムササビが50%の翼をもつ進化の途中過程だという視点は抜け落ちてたな。結局は他の生物に対しては完成形だと無意識に決めつけてたことに気付きました。私もまだまだですわ。 ダグラス・アダムスが『ギンガヒッチハイクガイド』朗読してるのは豪華すぎ。
進化とは何かリチャード・ドーキンス,吉成真由美読み終わったそりゃ「創造説」なんて信じてないし、人類には猿の祖先がいて、これからも進化していくもんだと前から思ってたけど、ムササビが50%の翼をもつ進化の途中過程だという視点は抜け落ちてたな。結局は他の生物に対しては完成形だと無意識に決めつけてたことに気付きました。私もまだまだですわ。 ダグラス・アダムスが『ギンガヒッチハイクガイド』朗読してるのは豪華すぎ。 - 2025年11月9日
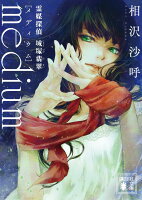 medium 霊媒探偵城塚翡翠相沢沙呼読み終わった流石にあからさま過ぎるしミスリードかなと疑ってはいたが、犯人探しの方に注意が向いて、種明かしで「あ〜そっちか〜」ってなった。これがマジシャンが小説で仕掛けるミスディレクション、奇術か〜。技術をしっかりくらった感じ。 エピローグは無い方が好きです。
medium 霊媒探偵城塚翡翠相沢沙呼読み終わった流石にあからさま過ぎるしミスリードかなと疑ってはいたが、犯人探しの方に注意が向いて、種明かしで「あ〜そっちか〜」ってなった。これがマジシャンが小説で仕掛けるミスディレクション、奇術か〜。技術をしっかりくらった感じ。 エピローグは無い方が好きです。 - 2025年11月6日
 壁 (新潮文庫)安部公房読み終わった空虚や疎外感、現実からの逃避が自分の心に収まりがいいが、寓話感の強い話が自分はあまり楽しめないとも気付いた。 都市的なモノである壁に安心(居場所)を覚えて成長する壁となるラストは諦めのようにも感じるし、救いのようにも思える。死んだ有機物から生きてる無機物へ。 昔『砂の女』を読んだ際は、なんて残酷な話なんだと思ったが、あれもポジティブな結末だったのか。
壁 (新潮文庫)安部公房読み終わった空虚や疎外感、現実からの逃避が自分の心に収まりがいいが、寓話感の強い話が自分はあまり楽しめないとも気付いた。 都市的なモノである壁に安心(居場所)を覚えて成長する壁となるラストは諦めのようにも感じるし、救いのようにも思える。死んだ有機物から生きてる無機物へ。 昔『砂の女』を読んだ際は、なんて残酷な話なんだと思ったが、あれもポジティブな結末だったのか。 - 2025年11月1日
 外交ドキュメント 歴史認識服部龍二読み終わった「本書の主たる目的は批評や提言ではなく、日本外交の視点から政策過程を分析することにある。諸外国との関係悪化だけでなく、修復の局面にも紙幅を割く。筆者が断を下すというよりも、読者のために材料を整理して提供したい。何度でも再燃しうる歴史問題を論じるうえで、そのことは基礎的な作業となるだろう。」 歴史問題における基礎的な日本側の政策過程を確認できたのは良かった、女性基金の事とか知らなかったし。ただ、中国と韓国側の視点が薄く、歴史認識の問題を理解するには物足りなく感じる。
外交ドキュメント 歴史認識服部龍二読み終わった「本書の主たる目的は批評や提言ではなく、日本外交の視点から政策過程を分析することにある。諸外国との関係悪化だけでなく、修復の局面にも紙幅を割く。筆者が断を下すというよりも、読者のために材料を整理して提供したい。何度でも再燃しうる歴史問題を論じるうえで、そのことは基礎的な作業となるだろう。」 歴史問題における基礎的な日本側の政策過程を確認できたのは良かった、女性基金の事とか知らなかったし。ただ、中国と韓国側の視点が薄く、歴史認識の問題を理解するには物足りなく感じる。 - 2025年10月29日
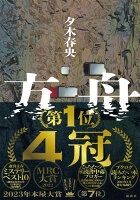 方舟夕木春央読み終わった作者の読ませたがってる通りに読んで見事に騙された!気持ちいい〜!!デスゲームで負けた側の気持ちになれる! 翔太郎が軽視した動機や無関心だったことにこそ意味があったのか〜おもしろ〜
方舟夕木春央読み終わった作者の読ませたがってる通りに読んで見事に騙された!気持ちいい〜!!デスゲームで負けた側の気持ちになれる! 翔太郎が軽視した動機や無関心だったことにこそ意味があったのか〜おもしろ〜 - 2025年10月26日
 うるさいこの音の全部高瀬隼子読み終わったヒリヒリする生焼けの痛みを味わいたくて、高瀬隼子さんの小説を読んでる。今作の主人公が作家であり、本が読まれることに感謝しつつも読者に抗議めいたのもあって、より一層ヒリヒリしました。 好き勝手にあれこれ言う周囲の声、相手に好かれようとする自分の声、そんな声に否定と反論を繰り返して答えもわからず悶々とする心の声が、うるさいこの音の全部。この音を消す方法が主人公にとっては物語を書いてる時なのかな。自分ならアルコールか。 周りにいい顔をしようとして都合を合わせていくうちに周りから生まれた知らない自分に侵食される恐怖。 後日談のタイトルが『明日、ここは静か』だから、全部黙らせて、書くことが出来るようになったのか、それとも明日への願いか。
うるさいこの音の全部高瀬隼子読み終わったヒリヒリする生焼けの痛みを味わいたくて、高瀬隼子さんの小説を読んでる。今作の主人公が作家であり、本が読まれることに感謝しつつも読者に抗議めいたのもあって、より一層ヒリヒリしました。 好き勝手にあれこれ言う周囲の声、相手に好かれようとする自分の声、そんな声に否定と反論を繰り返して答えもわからず悶々とする心の声が、うるさいこの音の全部。この音を消す方法が主人公にとっては物語を書いてる時なのかな。自分ならアルコールか。 周りにいい顔をしようとして都合を合わせていくうちに周りから生まれた知らない自分に侵食される恐怖。 後日談のタイトルが『明日、ここは静か』だから、全部黙らせて、書くことが出来るようになったのか、それとも明日への願いか。 - 2025年10月23日
 歴史とは何か 新版E.H.カー,近藤和彦読み終わった歴史関連の書籍を読んでると『歴史とは何か』からの引用をよく見かける。 本書は大学の講演を元にまとめられたものであり、皮肉とパンチラインに溢れた文書には心惹かれ、頻繁に引用されるも納得。カー自身も講演の中であらゆる名句を引用しまくってるので、意識的にやってたんじゃないかな。 第一講〜第四講までは、歴史の見方、歴史と現在の関わり方が記述されている。歴史とは過去の事実を並べるだけものでなく、現在から解釈を与えるもので、同時に現在の解釈も過去の事実によって影響を受ける相互作用ですよ。ただ解釈を与える歴史家も社会的影響を受けて解釈を与える個人ですよ。歴史を学ぶ時は歴史家の背景を学びましょう。そして偉人も社会の影響を受ける個人であり、歴史的事象は偉人1人が起こすものではなく、その時代の意思をもった個人の大衆の影響が大きいですよ。歴史と科学は近しくて、どちらも蓋然性が見えてくる一般化をしてますよ。みたいなことが書かれてて、まぁわかるなぁって感じ。 第五講からは歴史を通して現在、そして未来について書いてある。自然から脱却し自意識を持つことで歴史を知り、自意識による理性が自然や社会を制御する進歩であった。理性によって現在を疑うことで進歩は成し遂げられる。 世界的に右傾化している現在をカーなら皮肉的に嘆いてるかな、それでも世界は動く、と。
歴史とは何か 新版E.H.カー,近藤和彦読み終わった歴史関連の書籍を読んでると『歴史とは何か』からの引用をよく見かける。 本書は大学の講演を元にまとめられたものであり、皮肉とパンチラインに溢れた文書には心惹かれ、頻繁に引用されるも納得。カー自身も講演の中であらゆる名句を引用しまくってるので、意識的にやってたんじゃないかな。 第一講〜第四講までは、歴史の見方、歴史と現在の関わり方が記述されている。歴史とは過去の事実を並べるだけものでなく、現在から解釈を与えるもので、同時に現在の解釈も過去の事実によって影響を受ける相互作用ですよ。ただ解釈を与える歴史家も社会的影響を受けて解釈を与える個人ですよ。歴史を学ぶ時は歴史家の背景を学びましょう。そして偉人も社会の影響を受ける個人であり、歴史的事象は偉人1人が起こすものではなく、その時代の意思をもった個人の大衆の影響が大きいですよ。歴史と科学は近しくて、どちらも蓋然性が見えてくる一般化をしてますよ。みたいなことが書かれてて、まぁわかるなぁって感じ。 第五講からは歴史を通して現在、そして未来について書いてある。自然から脱却し自意識を持つことで歴史を知り、自意識による理性が自然や社会を制御する進歩であった。理性によって現在を疑うことで進歩は成し遂げられる。 世界的に右傾化している現在をカーなら皮肉的に嘆いてるかな、それでも世界は動く、と。 - 2025年10月16日
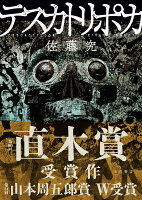 テスカトリポカ佐藤究読み終わったおもろすぎ。貪るように夢中で読んだ。 悪党の生い立ちから犯罪組織の結成、犯罪システムの構築、組織の崩壊までを描いた、超エンタメクライム小説。 弱者も善良な人も暴力も、資本主義に巻き込まれる資本主義の果てしなさが恐ろしい。 そんな資本主義すら覆うように根を張り原動力になってるのが信仰。資本主義と信仰が裏表の関係で、お互いの言い訳のように存在するけど、真の信仰に出会ったコシモはそんな負の関係から抜け出したようで心打たれる。
テスカトリポカ佐藤究読み終わったおもろすぎ。貪るように夢中で読んだ。 悪党の生い立ちから犯罪組織の結成、犯罪システムの構築、組織の崩壊までを描いた、超エンタメクライム小説。 弱者も善良な人も暴力も、資本主義に巻き込まれる資本主義の果てしなさが恐ろしい。 そんな資本主義すら覆うように根を張り原動力になってるのが信仰。資本主義と信仰が裏表の関係で、お互いの言い訳のように存在するけど、真の信仰に出会ったコシモはそんな負の関係から抜け出したようで心打たれる。 - 2025年10月9日
 アボカドの種俵万智読み終わったむっちゃ良かった。 歌集って初めて読むけど(筒井康隆のカラダ記念日は読んだことある)、連作になることでより実体が沸き立って、歌の暮らしの中に吸い込まれる感覚だった。 2020年から2023年まで詠まれた歌をまとめたもので、当然そこにはコロナや東京五輪が登場する。大きなニュースと同時に存在する市井の生活、空気が、こうやって記録されていくことに感動した。
アボカドの種俵万智読み終わったむっちゃ良かった。 歌集って初めて読むけど(筒井康隆のカラダ記念日は読んだことある)、連作になることでより実体が沸き立って、歌の暮らしの中に吸い込まれる感覚だった。 2020年から2023年まで詠まれた歌をまとめたもので、当然そこにはコロナや東京五輪が登場する。大きなニュースと同時に存在する市井の生活、空気が、こうやって記録されていくことに感動した。 - 2025年10月8日
 季刊日記 創刊号こだま,ネルノダイスキ,ドミニク・チェン,pha,伊藤亜和,初見健一,前田隆弘,北尾修一,古賀及子,こうの史代,品田遊,図Yカニナ,堀合俊博,大森時生,安達茉莉子,小沼理,尹雄大,山本浩貴,東直子,松浦弥太郎,林健太郎,柚木麻子,柿内正午,桜林直子,植本一子,武田砂鉄,浮,ピエール瀧,牧野伊三夫,猪瀬浩平,福尾匠,竹中万季,荘子it,葉山莉子,蓮沼執太,藤原辰史,蟹の親子,野村由芽,金川晋吾,鳥トマト気になる
季刊日記 創刊号こだま,ネルノダイスキ,ドミニク・チェン,pha,伊藤亜和,初見健一,前田隆弘,北尾修一,古賀及子,こうの史代,品田遊,図Yカニナ,堀合俊博,大森時生,安達茉莉子,小沼理,尹雄大,山本浩貴,東直子,松浦弥太郎,林健太郎,柚木麻子,柿内正午,桜林直子,植本一子,武田砂鉄,浮,ピエール瀧,牧野伊三夫,猪瀬浩平,福尾匠,竹中万季,荘子it,葉山莉子,蓮沼執太,藤原辰史,蟹の親子,野村由芽,金川晋吾,鳥トマト気になる - 2025年10月7日
 他人の顔安部公房読み終わった超おもしれー。 顔の効果とか拘束、自由、自我、欲望、他者、孤独、主人公の堂々巡りの思考、哲学、が長々と書かれてて、それ読んでるだけで面白いんだけど、妻の手紙がさらに面白い「尻尾をくわえた蛇のような長ったらしい告白を書いただけです」この一刀両断、そんな殺生な。 途中挟まった、仮面が大量生産された世界の空想話も、それだけでSF短編として充分面白い。まさに今ってSNSで誰もが覆面を手に入れた世界だ。 みんな人間関係は希薄で一方通行の会話をしてる。 「愛というものは、互いに仮面を剥がしっこすることで、そのためにも、愛する者のために、仮面をかぶる努力をしなければならないのだと。仮面がなければ、それを剥がすたのしみもないわけですからね。お分かりでしょうか、この意味が。」
他人の顔安部公房読み終わった超おもしれー。 顔の効果とか拘束、自由、自我、欲望、他者、孤独、主人公の堂々巡りの思考、哲学、が長々と書かれてて、それ読んでるだけで面白いんだけど、妻の手紙がさらに面白い「尻尾をくわえた蛇のような長ったらしい告白を書いただけです」この一刀両断、そんな殺生な。 途中挟まった、仮面が大量生産された世界の空想話も、それだけでSF短編として充分面白い。まさに今ってSNSで誰もが覆面を手に入れた世界だ。 みんな人間関係は希薄で一方通行の会話をしてる。 「愛というものは、互いに仮面を剥がしっこすることで、そのためにも、愛する者のために、仮面をかぶる努力をしなければならないのだと。仮面がなければ、それを剥がすたのしみもないわけですからね。お分かりでしょうか、この意味が。」 - 2025年10月1日
- 2025年9月27日
 一九八四年新訳版ジョージ・オーウェル,高橋和久読み終わった案外エンタメで、主人公は反乱勢力と合流して革命を目指したりすんのかなーと思ったけど全くそんな事無かった。ただ物語の圧が凄いからぐんぐん読めちゃう。 今後ことある毎に、あっ俺今〈二重思考〉してんなーとか考えちゃうだろうな。 トマスピンチョンの20ページ以上ある解説も満足度が高い。ここまで読み応えのある解説は初めてだ。
一九八四年新訳版ジョージ・オーウェル,高橋和久読み終わった案外エンタメで、主人公は反乱勢力と合流して革命を目指したりすんのかなーと思ったけど全くそんな事無かった。ただ物語の圧が凄いからぐんぐん読めちゃう。 今後ことある毎に、あっ俺今〈二重思考〉してんなーとか考えちゃうだろうな。 トマスピンチョンの20ページ以上ある解説も満足度が高い。ここまで読み応えのある解説は初めてだ。 - 2025年9月20日
 読み終わったページを捲る指が止まらなかった。 死刑制度と裁判員裁判があるこの国で、私たちは何を基準にして人を裁くのか、男性4人を射殺し一度は無期懲役判決を受けるも最高裁から差戻を経て死刑となった永山裁判を通じて考えることになる。 最高裁の差戻判決で語られた、所謂「永山判決」は他の事件でも考慮される一般的な要素であったのに、死刑にゴーサインを出せる根拠として記憶されていく。しかし著者は一人ひとりの被告人の内面に深く向き合い、被告人の過去、現在、未来を鑑みる必要があり、「人を処刑する画一的な基準はありえない」と結ぶ。 読み終わってすぐに死刑制度に対する現在の国民の賛否の割合を調べた。今も死刑賛成派が8割らしい。自分は可能性を奪ってはいけないのではないかって思うし、死刑存置であっても筆者が主張するように画一的な基準で裁くべきではないと思ってる、基準から零れたモノを掬って判断しなければならないのではないかと、それが人を人が裁くことなんじゃないかな。 p.306「最高検察庁は、このままでは被害者が一人だと死刑にできなくなるおそれがあると危惧を抱き、被害者が一人で、高裁で死刑が無期に減刑された事件を五件、連続で上告した。」 ってなんだこれ、検察はどうしても死刑にしたいのか。免罪事件もあったし、死人に口なしだもんね、と邪推が捗ります。
読み終わったページを捲る指が止まらなかった。 死刑制度と裁判員裁判があるこの国で、私たちは何を基準にして人を裁くのか、男性4人を射殺し一度は無期懲役判決を受けるも最高裁から差戻を経て死刑となった永山裁判を通じて考えることになる。 最高裁の差戻判決で語られた、所謂「永山判決」は他の事件でも考慮される一般的な要素であったのに、死刑にゴーサインを出せる根拠として記憶されていく。しかし著者は一人ひとりの被告人の内面に深く向き合い、被告人の過去、現在、未来を鑑みる必要があり、「人を処刑する画一的な基準はありえない」と結ぶ。 読み終わってすぐに死刑制度に対する現在の国民の賛否の割合を調べた。今も死刑賛成派が8割らしい。自分は可能性を奪ってはいけないのではないかって思うし、死刑存置であっても筆者が主張するように画一的な基準で裁くべきではないと思ってる、基準から零れたモノを掬って判断しなければならないのではないかと、それが人を人が裁くことなんじゃないかな。 p.306「最高検察庁は、このままでは被害者が一人だと死刑にできなくなるおそれがあると危惧を抱き、被害者が一人で、高裁で死刑が無期に減刑された事件を五件、連続で上告した。」 ってなんだこれ、検察はどうしても死刑にしたいのか。免罪事件もあったし、死人に口なしだもんね、と邪推が捗ります。 - 2025年9月19日
 日本SF傑作選1 筒井康隆 マグロマル/トラブル日下三蔵,筒井康隆読み終わった『わが善き狼』良かったなぁ。この短編そのものが懐かしさを覚える二重構造になって、泣きそうになった。 『おれに関する噂』まさに今のSNS。1カ月もしたら忘れる"なんでもない人"で騒いでバカバカしい。 『顔面崩壊』スプラッタとか苦手じゃない自分でもキツかった。 『東海道戦争』『カメロイド文部省』『最高級有機質肥料』『ベトナム観光公社』『郵政省』もかなり好きだった。傑作選の名に偽りなし。
日本SF傑作選1 筒井康隆 マグロマル/トラブル日下三蔵,筒井康隆読み終わった『わが善き狼』良かったなぁ。この短編そのものが懐かしさを覚える二重構造になって、泣きそうになった。 『おれに関する噂』まさに今のSNS。1カ月もしたら忘れる"なんでもない人"で騒いでバカバカしい。 『顔面崩壊』スプラッタとか苦手じゃない自分でもキツかった。 『東海道戦争』『カメロイド文部省』『最高級有機質肥料』『ベトナム観光公社』『郵政省』もかなり好きだった。傑作選の名に偽りなし。 - 2025年9月13日
読み込み中...

