

一世
@seedo81
【累計読書数5000冊以上】 デザイン戦略研究家・北九州市立大学MBA特任教授(アントレプレナーシップ・デザイン経営)・パブリックスピーカー。デザイナーとしては福岡デザインアワード/Pent Awards受賞。大学から約7年Portland・ORに住んで、帰国後25歳で起業。Xは主に本と料理と旅の話。
- 2025年3月29日
 ひらめきはカオスから生まれるオリ・ブラフマン/ジューダ・ポラック読み終わった読了。変革を起こそうとするならば、何かもを管理するよりも「意図的なカオス」を組み込むべきという話。「余白」「異分子」「セレンディピティ」という3つがそのキーワードとして挙げられ、それぞれの細かい解説が展開されるという構成になっています。 アイディア創発において「カオスの重要性」を語る本は以前にも幾つか読んだことがあります。けれども、この本がユニークなのは「組織論」という観点で書かれている点です(しかも事例として出てくるのは軍隊組織にどうやって「カオスの余白」を組み込むのかという実験です)。 つまりはカオスによって予想外のことが起きると、それは意図していなかった人物の採用を生み、そこから思いも寄らない発想や行動が生まれるという流れなのでしょう。いわゆる『ビジョナリー・カンパニー』シリーズで書かれるような「適切な人だけバスに乗せる」とは逆のアプローチと言えます。 著者本人の事例以外はわりと古く、しかもどこかで聞いたことがある有名なものばかりなので、そこはマイナスポイントかもしれません。とは言え、従来通り型の「組織論の本」に飽きている方には新鮮な視点をもらえる一冊と言えるでしょう。 あぁ・・でも、この本にある「日本の学生はアメリカよりも時間の余白があるから有能」って話は大きく間違っていると思います(苦笑) ● ひらめきはカオスから生まれる(オリ・ブラフマン/ジューダ・ボラック、2025年、ディスカヴァー・トゥエンティワン)
ひらめきはカオスから生まれるオリ・ブラフマン/ジューダ・ポラック読み終わった読了。変革を起こそうとするならば、何かもを管理するよりも「意図的なカオス」を組み込むべきという話。「余白」「異分子」「セレンディピティ」という3つがそのキーワードとして挙げられ、それぞれの細かい解説が展開されるという構成になっています。 アイディア創発において「カオスの重要性」を語る本は以前にも幾つか読んだことがあります。けれども、この本がユニークなのは「組織論」という観点で書かれている点です(しかも事例として出てくるのは軍隊組織にどうやって「カオスの余白」を組み込むのかという実験です)。 つまりはカオスによって予想外のことが起きると、それは意図していなかった人物の採用を生み、そこから思いも寄らない発想や行動が生まれるという流れなのでしょう。いわゆる『ビジョナリー・カンパニー』シリーズで書かれるような「適切な人だけバスに乗せる」とは逆のアプローチと言えます。 著者本人の事例以外はわりと古く、しかもどこかで聞いたことがある有名なものばかりなので、そこはマイナスポイントかもしれません。とは言え、従来通り型の「組織論の本」に飽きている方には新鮮な視点をもらえる一冊と言えるでしょう。 あぁ・・でも、この本にある「日本の学生はアメリカよりも時間の余白があるから有能」って話は大きく間違っていると思います(苦笑) ● ひらめきはカオスから生まれる(オリ・ブラフマン/ジューダ・ボラック、2025年、ディスカヴァー・トゥエンティワン)
- 2025年3月26日
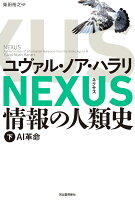 NEXUS 情報の人類史 下ユヴァル・ノア・ハラリ,柴田裕之読み終わった
NEXUS 情報の人類史 下ユヴァル・ノア・ハラリ,柴田裕之読み終わった - 2025年3月26日
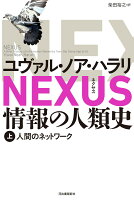 NEXUS 情報の人類史 上ユヴァル・ノア・ハラリ,柴田裕之読み終わった読了。ユヴァル・ノア・ハラリ氏の6年ぶりの著作。情報とは「人と人を繋ぐもの(NEXUS)」である、という前提を元に、最新のAI動向について警鐘を鳴らすような刺激的な内容でした。 上巻では歴史学者としての視点から、情報が国家形成にどのように影響を与えてきたか を掘り下げています。 例えば、古代エジプトの文書管理や中世ヨーロッパの教会ネットワークなど、情報がどのように国家や権力の形成を支えたか を具体例とともに解説しており、人類史を「情報史」として再解釈するアプローチが印象的でした。情報そのものが人類社会の形を決定づけてきたという観点は、ハラリ氏ならではの大胆な発想です。 下巻では、AIの進化とそれを使った各国の管理・監視体制の現状についての警告 が中心となっています。 特に、「AIがArtificial(人工)ではなくAlien(異なる)Intelligenceになりつつある」 という指摘には背筋が凍る思いがしました。AIが人間の意思を超えて独自に判断し、人類の社会構造に異質な影響を与えつつある現状を、冷徹に描き出しています。 この「異質な知性」が、人々の生活をより豊かにする可能性を秘めている一方で、その制御を失った場合には甚大なリスクが伴うというのは、現代社会が直面している最も重要なテーマの一つです。 特に印象に残ったのは、イランにおけるAIによるヒジャブ着用管理の実情 についての記述です。日本のメディアではほとんど取り上げられない話題ですが、政府がAIを使って市民の服装を監視し、宗教的規範を強制する現状 は、技術の利用がいかに容易に個人の自由を侵害するかを示しており、恐怖を覚えました。 「人間が宗教や貨幣を信じて社会を形成してきたように、AIが人のコミュニケーションに過度に関与し、管理する社会が到来しつつある」 というハラリ氏の警告が届くことなく、現実は加速度的に変わりつつあります。 これからの未来を考えるにあたって必読とも言える一冊だと思います(ハラリ氏の著作を読み慣れていない人にとってはやや難解な部分もあるかもしれませんが)。 ● NEXUS 情報の人類史 上: 人間のネットワーク/下: AI革命(ユヴァル・ノア・ハラリ、2025年、河出書房新社)
NEXUS 情報の人類史 上ユヴァル・ノア・ハラリ,柴田裕之読み終わった読了。ユヴァル・ノア・ハラリ氏の6年ぶりの著作。情報とは「人と人を繋ぐもの(NEXUS)」である、という前提を元に、最新のAI動向について警鐘を鳴らすような刺激的な内容でした。 上巻では歴史学者としての視点から、情報が国家形成にどのように影響を与えてきたか を掘り下げています。 例えば、古代エジプトの文書管理や中世ヨーロッパの教会ネットワークなど、情報がどのように国家や権力の形成を支えたか を具体例とともに解説しており、人類史を「情報史」として再解釈するアプローチが印象的でした。情報そのものが人類社会の形を決定づけてきたという観点は、ハラリ氏ならではの大胆な発想です。 下巻では、AIの進化とそれを使った各国の管理・監視体制の現状についての警告 が中心となっています。 特に、「AIがArtificial(人工)ではなくAlien(異なる)Intelligenceになりつつある」 という指摘には背筋が凍る思いがしました。AIが人間の意思を超えて独自に判断し、人類の社会構造に異質な影響を与えつつある現状を、冷徹に描き出しています。 この「異質な知性」が、人々の生活をより豊かにする可能性を秘めている一方で、その制御を失った場合には甚大なリスクが伴うというのは、現代社会が直面している最も重要なテーマの一つです。 特に印象に残ったのは、イランにおけるAIによるヒジャブ着用管理の実情 についての記述です。日本のメディアではほとんど取り上げられない話題ですが、政府がAIを使って市民の服装を監視し、宗教的規範を強制する現状 は、技術の利用がいかに容易に個人の自由を侵害するかを示しており、恐怖を覚えました。 「人間が宗教や貨幣を信じて社会を形成してきたように、AIが人のコミュニケーションに過度に関与し、管理する社会が到来しつつある」 というハラリ氏の警告が届くことなく、現実は加速度的に変わりつつあります。 これからの未来を考えるにあたって必読とも言える一冊だと思います(ハラリ氏の著作を読み慣れていない人にとってはやや難解な部分もあるかもしれませんが)。 ● NEXUS 情報の人類史 上: 人間のネットワーク/下: AI革命(ユヴァル・ノア・ハラリ、2025年、河出書房新社) - 2025年3月25日
 魂の経営古森重隆読み終わった読了。富士フイルムがデジタル化の波を受けて、異業種に大転換する際に会社を率いた古森氏による経営論。MBAでよく事例として取り扱うトピックですが、きちんと理解する機会はなかったので、本を取り寄せてみました。 文章の端々からやや「勝利者バイアス(成功したから本が書けている)」の匂いはしますが、研究投資とM&Aの大鉈をふるいながら会社を存続させた経営手法には迫力があります。 著者が旧満州からの5歳の時に命からがら帰国した経験があり、どこか「軍隊」のような厳しさが随所にあるため、2025年の風潮とは合ってない部分もありますし、読み手も選ぶ本ですが、今の日本にはない強さが溢れています。 ● 魂の経営(古森重隆、2013年、東洋経済新報社)
魂の経営古森重隆読み終わった読了。富士フイルムがデジタル化の波を受けて、異業種に大転換する際に会社を率いた古森氏による経営論。MBAでよく事例として取り扱うトピックですが、きちんと理解する機会はなかったので、本を取り寄せてみました。 文章の端々からやや「勝利者バイアス(成功したから本が書けている)」の匂いはしますが、研究投資とM&Aの大鉈をふるいながら会社を存続させた経営手法には迫力があります。 著者が旧満州からの5歳の時に命からがら帰国した経験があり、どこか「軍隊」のような厳しさが随所にあるため、2025年の風潮とは合ってない部分もありますし、読み手も選ぶ本ですが、今の日本にはない強さが溢れています。 ● 魂の経営(古森重隆、2013年、東洋経済新報社)
- 2025年3月24日
 企業文化をデザインする冨田憲二読み終わった読了。 「企業にとって企業風土(カルチャー)が新たな資産になりつつある。しかし、その価値は 見えにくく、即効性があるわけでもないため、明確に言語化されていない という課題がある。」 本書は、この問題に向き合い、企業文化をどのようにデザインし、経営資源として活用するか を探る一冊です。 著者の冨田憲二氏は、スマートニュースをはじめ、複数のベンチャー企業でHR(人事)を務めてきた経験を持つ。その実務経験をもとに、企業文化の構築と維持の具体的な方法論を提示しています。 また、企業文化の形成において 「体現者」と同じくらい「愛を叫ぶ人」が重要 という考え方にも共感しました。文化を築くのはトップやリーダー層だけでなく、それを積極的に支持し、社内外に伝播していく「文化の伝道者」の存在が欠かせない、という視点です。 本書ではかなりの比重が「ミッション・ビジョン・バリュー」で言うところの「バリューをいかに組織内に浸透させ、共有し、持続可能な形で育てていくか」 という点に焦点が当てられています。そのため、単なる理念策定ではなく、文化を実践レベルで機能させるための具体的な指針についてのヒントが得られるのがグッドポイントです。 企業カルチャーの構築論は抽象的になりがちですが、本書は その課題に対して実践的なガイダンスを提供している という点で面白い本でした。 ● 企業文化をデザインする(冨田憲二、2023年、日本実業出版社)
企業文化をデザインする冨田憲二読み終わった読了。 「企業にとって企業風土(カルチャー)が新たな資産になりつつある。しかし、その価値は 見えにくく、即効性があるわけでもないため、明確に言語化されていない という課題がある。」 本書は、この問題に向き合い、企業文化をどのようにデザインし、経営資源として活用するか を探る一冊です。 著者の冨田憲二氏は、スマートニュースをはじめ、複数のベンチャー企業でHR(人事)を務めてきた経験を持つ。その実務経験をもとに、企業文化の構築と維持の具体的な方法論を提示しています。 また、企業文化の形成において 「体現者」と同じくらい「愛を叫ぶ人」が重要 という考え方にも共感しました。文化を築くのはトップやリーダー層だけでなく、それを積極的に支持し、社内外に伝播していく「文化の伝道者」の存在が欠かせない、という視点です。 本書ではかなりの比重が「ミッション・ビジョン・バリュー」で言うところの「バリューをいかに組織内に浸透させ、共有し、持続可能な形で育てていくか」 という点に焦点が当てられています。そのため、単なる理念策定ではなく、文化を実践レベルで機能させるための具体的な指針についてのヒントが得られるのがグッドポイントです。 企業カルチャーの構築論は抽象的になりがちですが、本書は その課題に対して実践的なガイダンスを提供している という点で面白い本でした。 ● 企業文化をデザインする(冨田憲二、2023年、日本実業出版社)
- 2025年3月23日
 美食家の誕生橋本周子読み終わった読了。フランス革命前後に起きた、グルマン(美食家)の誕生についての本・・・と思って読み始めましたが、そうではなく著者グリモ・ド・ラ・レニエールについての内容、それも文学的な視点からの話なので、だいぶイメージと違いました。 一般的に「美食」と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、「どんなものを食べているか 言ってみたまえ。君がどんな人であるかを 言い当ててみせよう」 という名言で知られる 『美味礼讃』の著者ブリア・サヴァラン でしょう。 本書の中でも、グリモ・ド・ラ・レニエールとブリア・サヴァランを対比する形で話が進みますが、著者の関心は圧倒的にグリモ氏に傾いている ように感じました。 確かに、グリモ氏は料理本の著者というよりも、食を文学的に表現することの先駆者 であり、その功績は理解できます。しかし、その文体や表現には女性的なイメージが投影されており、個人的にはあまり好感が持てなかった ことが、この本に熱中できなかった理由かもしれません。 また、価格もそれなりの本なので、よほどフランス文学が好きな人、もしくはグリモ氏に特別な愛着がある人でない限り、購入はあまりお勧めできません。Amazonのレビューが 0件 なのも納得できるほど、かなりマニアックな内容です。 ● 美食家の誕生―グリモと〈食〉のフランス革命(橋本周子、2014年、名古屋大学出版会)
美食家の誕生橋本周子読み終わった読了。フランス革命前後に起きた、グルマン(美食家)の誕生についての本・・・と思って読み始めましたが、そうではなく著者グリモ・ド・ラ・レニエールについての内容、それも文学的な視点からの話なので、だいぶイメージと違いました。 一般的に「美食」と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、「どんなものを食べているか 言ってみたまえ。君がどんな人であるかを 言い当ててみせよう」 という名言で知られる 『美味礼讃』の著者ブリア・サヴァラン でしょう。 本書の中でも、グリモ・ド・ラ・レニエールとブリア・サヴァランを対比する形で話が進みますが、著者の関心は圧倒的にグリモ氏に傾いている ように感じました。 確かに、グリモ氏は料理本の著者というよりも、食を文学的に表現することの先駆者 であり、その功績は理解できます。しかし、その文体や表現には女性的なイメージが投影されており、個人的にはあまり好感が持てなかった ことが、この本に熱中できなかった理由かもしれません。 また、価格もそれなりの本なので、よほどフランス文学が好きな人、もしくはグリモ氏に特別な愛着がある人でない限り、購入はあまりお勧めできません。Amazonのレビューが 0件 なのも納得できるほど、かなりマニアックな内容です。 ● 美食家の誕生―グリモと〈食〉のフランス革命(橋本周子、2014年、名古屋大学出版会)
- 2025年3月23日
 瀬戸内レモン川久保篤志読み終わった読了。仕事の資料として、瀬戸内レモンの研究。5年前の出版ですが、あまり人気がなかった国産レモンがいかに瀬戸内地域でブランド化していったのか、現状の課題はどこなのかがまとめられたレポート。 お金がかかった企画だった記憶のある「おしい!広島」がブームのひとつの契機となっていることや、土産物でもJR・空港・ブランドショップ・カフェではどう売れ方が違うのかのリサーチなどが、特に興味深かったです。 元々アメリカ発の飲み物でフランスやイタリアのレモン産地でのレモン加工品とは流れが違う、なんて話にも納得。逆に、ハンバーガーとかは相性がいいのかも・・なんて思ってみたり。 あと、日本だとレモネードが砂糖が多すぎて人気ない・・という話でしたが、この本のリリースと同時くらいで、LEMONADE by Lemonicaが注目されることになるんですよね。 ● 瀬戸内レモン〜ブームの到来と六次産業化・島おこし〜(川久保篤志、2019年、溪水社)
瀬戸内レモン川久保篤志読み終わった読了。仕事の資料として、瀬戸内レモンの研究。5年前の出版ですが、あまり人気がなかった国産レモンがいかに瀬戸内地域でブランド化していったのか、現状の課題はどこなのかがまとめられたレポート。 お金がかかった企画だった記憶のある「おしい!広島」がブームのひとつの契機となっていることや、土産物でもJR・空港・ブランドショップ・カフェではどう売れ方が違うのかのリサーチなどが、特に興味深かったです。 元々アメリカ発の飲み物でフランスやイタリアのレモン産地でのレモン加工品とは流れが違う、なんて話にも納得。逆に、ハンバーガーとかは相性がいいのかも・・なんて思ってみたり。 あと、日本だとレモネードが砂糖が多すぎて人気ない・・という話でしたが、この本のリリースと同時くらいで、LEMONADE by Lemonicaが注目されることになるんですよね。 ● 瀬戸内レモン〜ブームの到来と六次産業化・島おこし〜(川久保篤志、2019年、溪水社)
- 2025年3月21日
 多元世界に向けたデザインアルトゥーロ・エスコバル,増井エドワード,森田敦郎,水内智英,水野大二郎,神崎隼人読了。持続可能な世界へのトランジションに向けて、「デザイン」の再定義/方向転換を図る人類学者アルトゥーロ・エスコバル氏の著書。 アプローチとしては、単なる「持続可能なデザイン」の議論にとどまらず、「デザインとは社会や文化、経済のあり方そのものを形づくるものだ」という視点から、社会全体の再構築を試みるものになっています。 著者のエスコバル氏がコロンビア生まれの人類学者ということもあり、西洋的な経済活動によって影響を受けるサウスアメリカの未来について「デザイン(トランジション・デザイン)」という言葉で、未来像を提言しているような内容となっています。 それはまるで、大航海時代に起きた南アメリカへの西洋の奪略行為を裏テーマ的に描いた映画『ブラックパンサー2』におけるワカンダとタロカンの歴史的背景を彷彿とさせるものがあります。 本書の最大の特徴は、デザイナーではない人類学者が「デザイン」という概念を用いて書いている点でしょう。 そのため、デザイン論にとどまらず、人類学、開発学、哲学、生態学、ラテンアメリカ研究、フェミニズム理論、仏教、音楽など、多種多様な視点が交錯する 展開となっています。このめまぐるしさが面白い反面、翻訳の影響もあるのか 日本語がやや回りくどく感じる 部分もあり、読み進めるには一定の集中力が必要でした。 とはいえ、本書は イタリアのデザイン思想家エツィオ・マンズィーニ の影響を強く受けながら、「デザインを単なるモノづくりの手法ではなく、社会構造を変革する手段として捉える」という重要な視点を提示しています。 本書で繰り返し登場するのが、「人がデザインをつくり、その作られたデザインの影響で、人が形づけられる」 という入れ子構造的な視点です。この考え方は、デザインとは単なる人間の創造物ではなく、それ自体が社会や文化、人間の行動を規定していく という洞察を示しています。 デザインを固定的なものではなく、相互依存的なプロセスとして捉える ことが、今後の社会変革において重要であるという著者からのメッセージを感じる良書でした。 ● 多元世界に向けたデザイン ラディカルな相互依存性、自治と自律、そして複数の世界をつくること(アルトゥーロ・エスコバル、2024年、BNN) 画像
多元世界に向けたデザインアルトゥーロ・エスコバル,増井エドワード,森田敦郎,水内智英,水野大二郎,神崎隼人読了。持続可能な世界へのトランジションに向けて、「デザイン」の再定義/方向転換を図る人類学者アルトゥーロ・エスコバル氏の著書。 アプローチとしては、単なる「持続可能なデザイン」の議論にとどまらず、「デザインとは社会や文化、経済のあり方そのものを形づくるものだ」という視点から、社会全体の再構築を試みるものになっています。 著者のエスコバル氏がコロンビア生まれの人類学者ということもあり、西洋的な経済活動によって影響を受けるサウスアメリカの未来について「デザイン(トランジション・デザイン)」という言葉で、未来像を提言しているような内容となっています。 それはまるで、大航海時代に起きた南アメリカへの西洋の奪略行為を裏テーマ的に描いた映画『ブラックパンサー2』におけるワカンダとタロカンの歴史的背景を彷彿とさせるものがあります。 本書の最大の特徴は、デザイナーではない人類学者が「デザイン」という概念を用いて書いている点でしょう。 そのため、デザイン論にとどまらず、人類学、開発学、哲学、生態学、ラテンアメリカ研究、フェミニズム理論、仏教、音楽など、多種多様な視点が交錯する 展開となっています。このめまぐるしさが面白い反面、翻訳の影響もあるのか 日本語がやや回りくどく感じる 部分もあり、読み進めるには一定の集中力が必要でした。 とはいえ、本書は イタリアのデザイン思想家エツィオ・マンズィーニ の影響を強く受けながら、「デザインを単なるモノづくりの手法ではなく、社会構造を変革する手段として捉える」という重要な視点を提示しています。 本書で繰り返し登場するのが、「人がデザインをつくり、その作られたデザインの影響で、人が形づけられる」 という入れ子構造的な視点です。この考え方は、デザインとは単なる人間の創造物ではなく、それ自体が社会や文化、人間の行動を規定していく という洞察を示しています。 デザインを固定的なものではなく、相互依存的なプロセスとして捉える ことが、今後の社会変革において重要であるという著者からのメッセージを感じる良書でした。 ● 多元世界に向けたデザイン ラディカルな相互依存性、自治と自律、そして複数の世界をつくること(アルトゥーロ・エスコバル、2024年、BNN) 画像 - 2025年3月20日
 クリエイティブ・マネジメント柴田雄一郎読み終わった読了。アート思考とデザイン思考、ロジカル思考を統合した「クリエイティブ・マネジメント」を提唱する研究者の柴田氏の本。 以前、オンデマンド的に出された『自分軸で生きてます』も大変面白い本だったので、一般流通での本が今回出版されることを楽しみにしていました(お気に入りのバンドがメジャーデビューしたような感じで)。 内容としては「アート思考・デザイン思考・ロジカル思考の融合」によっていかに新規事業を生むのか・・という話で、時々「自分の本を読んでるのかな?」と思うくらいに、発想とスキームが似ており、同じようなことを考える先駆者の方がいることを、僭越ながら大変心強く思いました。 特に「アート思考」はまだまだ国内では豊富な事例を交えた本が少ないので、著者の方の知見が詰まった素晴らしい教科書となっているこの本は貴重だと思います。 ● クリエイティブ・マネジメント(柴田雄一郎、フォレスト出版、フォレスト出版)
クリエイティブ・マネジメント柴田雄一郎読み終わった読了。アート思考とデザイン思考、ロジカル思考を統合した「クリエイティブ・マネジメント」を提唱する研究者の柴田氏の本。 以前、オンデマンド的に出された『自分軸で生きてます』も大変面白い本だったので、一般流通での本が今回出版されることを楽しみにしていました(お気に入りのバンドがメジャーデビューしたような感じで)。 内容としては「アート思考・デザイン思考・ロジカル思考の融合」によっていかに新規事業を生むのか・・という話で、時々「自分の本を読んでるのかな?」と思うくらいに、発想とスキームが似ており、同じようなことを考える先駆者の方がいることを、僭越ながら大変心強く思いました。 特に「アート思考」はまだまだ国内では豊富な事例を交えた本が少ないので、著者の方の知見が詰まった素晴らしい教科書となっているこの本は貴重だと思います。 ● クリエイティブ・マネジメント(柴田雄一郎、フォレスト出版、フォレスト出版)
- 2025年3月20日
 単純な脳、複雑な「私」池谷裕二読み終わった読了。「心」はいかにして生み出されるのか?この問いを脳科学の視点から探求するシリーズ3部作のうちの真ん中に位置する一冊。 他2作同様に著者の池谷裕二氏が、高校生と対話する形式で、意識や認識が「思い込み」や「脳の錯覚」に過ぎないことを論理的に解き明かしていきます。 「自分が感じている現実は、単なる脳のシミュレーションに過ぎないのではないか?」 という理屈をしっかりと池谷先生に解説されると、高校生の情操教育に何らかの影響を与えそうで、少し心配になります(苦笑) 生存率に直結する「痛み」という存在を解消するために「なぜそれが起きているのか」を考えられるだけの脳を得たことで、リカージョン(入れ子式・マトリョーシカ式)に様々なことについての謎を悩むようになった人類。 著者の見解によれば、脳科学的な視点からは、こうした思考は単なる妄想に過ぎない とのこと。もしそうならば、「じゃあ、そんなものか」と割り切ってしまえば、心理的ストレスが軽減される効果があるのか? それとも、むしろ余計に悩んでしまうのか? 読みながら考えさせられました。 2008年にマックス・プランク研究所の研究者がfMRIを利用して行なった脳研究で「人は運動実施の7秒前には脳が予測行動を開始している」と言う話があります。この本の中でも「5秒前の世界があったことをどう証明するのか」という「シミュレーション仮説」のような問いがあります。 そうやって悩むことさえ、もしかしたら脳の錯覚なのか・・とまさに思考のリカージョンが起きる内容。単なる脳の機能の話と思いきや、いつの間にか深遠な哲学的問いにまで導かれる、まさに思考の迷宮へと誘われる一冊でした。 ● 単純な脳、複雑な「私」(池谷裕二、2013年、講談社)
単純な脳、複雑な「私」池谷裕二読み終わった読了。「心」はいかにして生み出されるのか?この問いを脳科学の視点から探求するシリーズ3部作のうちの真ん中に位置する一冊。 他2作同様に著者の池谷裕二氏が、高校生と対話する形式で、意識や認識が「思い込み」や「脳の錯覚」に過ぎないことを論理的に解き明かしていきます。 「自分が感じている現実は、単なる脳のシミュレーションに過ぎないのではないか?」 という理屈をしっかりと池谷先生に解説されると、高校生の情操教育に何らかの影響を与えそうで、少し心配になります(苦笑) 生存率に直結する「痛み」という存在を解消するために「なぜそれが起きているのか」を考えられるだけの脳を得たことで、リカージョン(入れ子式・マトリョーシカ式)に様々なことについての謎を悩むようになった人類。 著者の見解によれば、脳科学的な視点からは、こうした思考は単なる妄想に過ぎない とのこと。もしそうならば、「じゃあ、そんなものか」と割り切ってしまえば、心理的ストレスが軽減される効果があるのか? それとも、むしろ余計に悩んでしまうのか? 読みながら考えさせられました。 2008年にマックス・プランク研究所の研究者がfMRIを利用して行なった脳研究で「人は運動実施の7秒前には脳が予測行動を開始している」と言う話があります。この本の中でも「5秒前の世界があったことをどう証明するのか」という「シミュレーション仮説」のような問いがあります。 そうやって悩むことさえ、もしかしたら脳の錯覚なのか・・とまさに思考のリカージョンが起きる内容。単なる脳の機能の話と思いきや、いつの間にか深遠な哲学的問いにまで導かれる、まさに思考の迷宮へと誘われる一冊でした。 ● 単純な脳、複雑な「私」(池谷裕二、2013年、講談社)
- 2025年3月17日
 「未来」を発明したサルアダム・ブリー,ジョナサン・レッドショウ,トーマス・スーデンドルフ,波多野理彩子読み終わった読了。サルが「未来を予測する能力=心のタイムトラベル」を身につけたことで、進化と発展がもたらされた——本書は、このテーマを 科学の観点から探る一冊 です。 進化人類学、認知心理学、神経科学、考古学、歴史学 など多様な分野を横断しながら、「人間はどのようにして未来を予測し、それによってどのように社会を築いてきたのか?」 を解き明かします。 著者は3名で、それぞれ異なる専門分野を背景に議論を展開しているため、話題が広範に広がる点も特徴的です。 ただし、紹介されるエピソードの多くは、どこかで読んだことがあるものが多く、それらを繋ぎ合わせた感は否めず・・自分としては新しい発見というよりは、既存の知見を整理し、未来予測というテーマのもとに編集した本のように思えました。 とはいえ、記憶と予測があることで「将来のために芽を摘む」という意識が生まれ、戦争や反逆が引き起こされる という視点には納得感があります。また、人類が長期的な視野を持つことによって、単なる生存戦略を超え、未来を見据えた選択を行うようになったことの影響は、ポジティブな側面だけでなく「仕返し」「子孫のことを考えた暴力」のような破壊的な行為にもつながるという指摘は興味深い視点でした。 「心のタイムマシン」に乗せられ、博物館の中を歩くように人類史を俯瞰できる読み物 という本という意味では、十分に楽しめる一冊でした。 ● 「未来」を発明したサル: 記憶と予測の人類史(トーマス・スーデンドルフ/ジョナサン・レッドショウ /アダム・ブリー、2024年、早川書房)
「未来」を発明したサルアダム・ブリー,ジョナサン・レッドショウ,トーマス・スーデンドルフ,波多野理彩子読み終わった読了。サルが「未来を予測する能力=心のタイムトラベル」を身につけたことで、進化と発展がもたらされた——本書は、このテーマを 科学の観点から探る一冊 です。 進化人類学、認知心理学、神経科学、考古学、歴史学 など多様な分野を横断しながら、「人間はどのようにして未来を予測し、それによってどのように社会を築いてきたのか?」 を解き明かします。 著者は3名で、それぞれ異なる専門分野を背景に議論を展開しているため、話題が広範に広がる点も特徴的です。 ただし、紹介されるエピソードの多くは、どこかで読んだことがあるものが多く、それらを繋ぎ合わせた感は否めず・・自分としては新しい発見というよりは、既存の知見を整理し、未来予測というテーマのもとに編集した本のように思えました。 とはいえ、記憶と予測があることで「将来のために芽を摘む」という意識が生まれ、戦争や反逆が引き起こされる という視点には納得感があります。また、人類が長期的な視野を持つことによって、単なる生存戦略を超え、未来を見据えた選択を行うようになったことの影響は、ポジティブな側面だけでなく「仕返し」「子孫のことを考えた暴力」のような破壊的な行為にもつながるという指摘は興味深い視点でした。 「心のタイムマシン」に乗せられ、博物館の中を歩くように人類史を俯瞰できる読み物 という本という意味では、十分に楽しめる一冊でした。 ● 「未来」を発明したサル: 記憶と予測の人類史(トーマス・スーデンドルフ/ジョナサン・レッドショウ /アダム・ブリー、2024年、早川書房)
- 2025年3月16日
 読了。企業が「好かれて応援される」ためには、人格のような「ブランド人格」が必要である:本書はこの概念を明確に定義し、ブランド人格をどのように構築し、維持していくのかを丁寧に解説 した一冊です。 著者の鬼木美和氏は、広告代理店 大広 のブランディングディレクターとして長年活躍されており、先日イベントで登壇されていたことがきっかけでこの本を知りました。 特に印象的だったのは、「ブランドとは社会から企業への期待値であり、それが高まると、企業の社会に対する提案権が強まる」 という考え方。ブランドを単なるマーケティングの延長ではなく、企業の社会的な立場や役割の文脈で捉える という視点は、これまであまり意識したことがなかったので、新たな学びがありました。 また、ブランド戦略の手法として 「バックキャスティング法」 についても触れられていましたが、これは私自身もブランド構築においてよく活用する手法なので、共感できるポイントが多かったです。「理想のブランド像から逆算して戦略を設計する」 という考え方は、持続可能なブランド構築に欠かせないアプローチだと再認識しました。 さらに、本書の後半には 「危機におけるブランド人格の管理」 という章があり、これが非常に興味深かったです。ブランドを「発展させる」だけでなく、企業が危機に直面した際にブランド人格をどのように守り、適切に対応していくのか という視点は、意外と語られることが少ないテーマだと思います。 30年以上のブランディング経験を持つ鬼木氏だからこそ書ける、実践的かつ体系的なブランド構築のガイドブック です。ブランド構築を始めたばかりの企業が どのようなポイントで悩み、どのように乗り越えていくのか がチャートマップのように整理されているため、実務に役立つ内容が詰まっています。 ● ファンを集められる会社だけが知っている「ブランド人格」(鬼木美和、2024年、時事通信社)
読了。企業が「好かれて応援される」ためには、人格のような「ブランド人格」が必要である:本書はこの概念を明確に定義し、ブランド人格をどのように構築し、維持していくのかを丁寧に解説 した一冊です。 著者の鬼木美和氏は、広告代理店 大広 のブランディングディレクターとして長年活躍されており、先日イベントで登壇されていたことがきっかけでこの本を知りました。 特に印象的だったのは、「ブランドとは社会から企業への期待値であり、それが高まると、企業の社会に対する提案権が強まる」 という考え方。ブランドを単なるマーケティングの延長ではなく、企業の社会的な立場や役割の文脈で捉える という視点は、これまであまり意識したことがなかったので、新たな学びがありました。 また、ブランド戦略の手法として 「バックキャスティング法」 についても触れられていましたが、これは私自身もブランド構築においてよく活用する手法なので、共感できるポイントが多かったです。「理想のブランド像から逆算して戦略を設計する」 という考え方は、持続可能なブランド構築に欠かせないアプローチだと再認識しました。 さらに、本書の後半には 「危機におけるブランド人格の管理」 という章があり、これが非常に興味深かったです。ブランドを「発展させる」だけでなく、企業が危機に直面した際にブランド人格をどのように守り、適切に対応していくのか という視点は、意外と語られることが少ないテーマだと思います。 30年以上のブランディング経験を持つ鬼木氏だからこそ書ける、実践的かつ体系的なブランド構築のガイドブック です。ブランド構築を始めたばかりの企業が どのようなポイントで悩み、どのように乗り越えていくのか がチャートマップのように整理されているため、実務に役立つ内容が詰まっています。 ● ファンを集められる会社だけが知っている「ブランド人格」(鬼木美和、2024年、時事通信社)
- 2025年3月16日
 VISUALIZE 60日本デザインセンター読み終わった読了。日本デザインセンターの創立60年記念冊子。 ブランドイメージや製品の魅力を理想的に表現するのみならず、 モノやコトに潜在する価値や、産み出されるサービスの本質、 新しい産業やそこに潜んでいる可能性を見極め分かりやすく可視化する力を「VISUALIZE」という新しい概念に集約し、編集された事例集です。 原研哉さんチームのデザイン、この凜とした佇まいと後ろに論理の背骨がしっかり取っている感じが好きです。 ● VISUALIZE 60(日本デザインセンター、2021年、誠文堂新光社)
VISUALIZE 60日本デザインセンター読み終わった読了。日本デザインセンターの創立60年記念冊子。 ブランドイメージや製品の魅力を理想的に表現するのみならず、 モノやコトに潜在する価値や、産み出されるサービスの本質、 新しい産業やそこに潜んでいる可能性を見極め分かりやすく可視化する力を「VISUALIZE」という新しい概念に集約し、編集された事例集です。 原研哉さんチームのデザイン、この凜とした佇まいと後ろに論理の背骨がしっかり取っている感じが好きです。 ● VISUALIZE 60(日本デザインセンター、2021年、誠文堂新光社)
- 2025年3月14日
 読了。「NewsPicksパブリッシング」創刊編集で、激務の結果として鬱を発症してしまった井上氏の著作。編集が今野良介氏だったので、告知みて買っちゃいました(編集者で選んで本買うのもだいぶマニアックかと思いますけど)。 テーマがテーマだけにちょっと重いかな・・と思いながらページをめくりはじめましたが、井上氏の言葉がしみこむように語りかけてきて、気がついたら一晩で読み終えてしまいました。 前半は自分語りで、中盤は様々な書籍を引用しながら「働くとは?」「経済とは?」「自分らしさとは?」のようなことが語られ、最後にNetflixの「LIGHTHOUSE」(星野源×若林正恭のトーク番組)を引用したエンディングへと向かうドキュメンタリーのような構成。特に、最後の「LIGHTHOUSE」からの件が、とてもリアルで・・社会や人と向き合う時の「目線とは?」みたいなことを考えさせられます。 そもそも自分はメンタルがあまり強くないし、集団行動と他者からの束縛が嫌いなので、大きな会社で働く未来から早々に離脱をしてしまいました。アメリカから戻ってきて東京に住むことも考えたけど、それも2週間くらいで「無理」となりました(苦笑) けれども、時々は組織の中でバリバリと働いている人たちをみて「自分もそっちの道を選んでいたらどうなっていたかな」なんて考える時もあり・・・だけど、この本を読む限りでは、きっと著者と同じような悩みを抱えていたことでしょう。それくらいリアルな言葉が並んでいる本でした。 あとは弱さを考えることが強さを考えることに繋がっていく論理の中で、ジョセフ・ヘンリック氏の名著『WEIRD』の引用があります。改めて、井上氏解釈で読んでいくと、これが日米のブランディングについての基礎理解と異なっているように見えてきました(そう考えたことはなかったけど)。 イケイケでキラキラな人生観に「ん?」と思う方には、ぜひ一読を・・可能ならば若いうちにお勧めしたい一冊です。引用されている本も良書ばかりですので、一種のブックガイドとして読むことも出来ますよ。 ● 強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考(井上慎平、2025年、ダイヤモンド社)
読了。「NewsPicksパブリッシング」創刊編集で、激務の結果として鬱を発症してしまった井上氏の著作。編集が今野良介氏だったので、告知みて買っちゃいました(編集者で選んで本買うのもだいぶマニアックかと思いますけど)。 テーマがテーマだけにちょっと重いかな・・と思いながらページをめくりはじめましたが、井上氏の言葉がしみこむように語りかけてきて、気がついたら一晩で読み終えてしまいました。 前半は自分語りで、中盤は様々な書籍を引用しながら「働くとは?」「経済とは?」「自分らしさとは?」のようなことが語られ、最後にNetflixの「LIGHTHOUSE」(星野源×若林正恭のトーク番組)を引用したエンディングへと向かうドキュメンタリーのような構成。特に、最後の「LIGHTHOUSE」からの件が、とてもリアルで・・社会や人と向き合う時の「目線とは?」みたいなことを考えさせられます。 そもそも自分はメンタルがあまり強くないし、集団行動と他者からの束縛が嫌いなので、大きな会社で働く未来から早々に離脱をしてしまいました。アメリカから戻ってきて東京に住むことも考えたけど、それも2週間くらいで「無理」となりました(苦笑) けれども、時々は組織の中でバリバリと働いている人たちをみて「自分もそっちの道を選んでいたらどうなっていたかな」なんて考える時もあり・・・だけど、この本を読む限りでは、きっと著者と同じような悩みを抱えていたことでしょう。それくらいリアルな言葉が並んでいる本でした。 あとは弱さを考えることが強さを考えることに繋がっていく論理の中で、ジョセフ・ヘンリック氏の名著『WEIRD』の引用があります。改めて、井上氏解釈で読んでいくと、これが日米のブランディングについての基礎理解と異なっているように見えてきました(そう考えたことはなかったけど)。 イケイケでキラキラな人生観に「ん?」と思う方には、ぜひ一読を・・可能ならば若いうちにお勧めしたい一冊です。引用されている本も良書ばかりですので、一種のブックガイドとして読むことも出来ますよ。 ● 強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考(井上慎平、2025年、ダイヤモンド社) - 2025年3月13日
 ディスカバリー・ドリブン戦略リタ・マグレイス,入山章栄,大浦千鶴子読み終わった読了。コロンビア大学ビジネススクール教授であり、ベストセラー作家でもあるリタ・マグレイスによる、「仮説思考計画戦略」についての一冊。 冒頭には、経営学者 クレイトン・クリステンセン教授 が友人として寄稿を寄せており、そういえば 『ジョブ理論』 の中でもマグレイス教授の理論が紹介されていたことを思い出しました。 主となるメッセージは、不安定な時代だからこそ、仮説と小さな実験を繰り返しながら戦略を構築すべき であり、その役割は経営トップではなく、チームにある(リーダーの役割はファシリテーション) というものです。 本の構成はユニークで、序盤は核心に触れず、事例紹介が続きます。そのため、監修を務めた 早稲田大学MBAの入山章栄教授 が「第5章から読んでみては?」と冒頭で推奨しているのも納得です(最初から読み始めると、途中で離脱してしまう読者もいるかもしれません)。 理論全体は、いわゆる 「イノベーション創発」 に近く、最近のトレンドでもある 「小さく動かす」「チームで動く」 というアプローチを正当化するものです。また、「ゴールをイメージする」ことの重要性 も強調されており、この点は デザイン思考 にも通じるものがあると感じました。 さらに、後半に登場する 「男女リーダーの間に本質的な差はない」 という議論が非常に興味深く、このテーマだけで新たな一冊が書けるのではないかと思いました。 ● ディスカバリー・ドリブン戦略: かつてないほど不確実な世界で「成長を最大化」する方法(リタ・マグレイス、2023年、東洋経済新報社)
ディスカバリー・ドリブン戦略リタ・マグレイス,入山章栄,大浦千鶴子読み終わった読了。コロンビア大学ビジネススクール教授であり、ベストセラー作家でもあるリタ・マグレイスによる、「仮説思考計画戦略」についての一冊。 冒頭には、経営学者 クレイトン・クリステンセン教授 が友人として寄稿を寄せており、そういえば 『ジョブ理論』 の中でもマグレイス教授の理論が紹介されていたことを思い出しました。 主となるメッセージは、不安定な時代だからこそ、仮説と小さな実験を繰り返しながら戦略を構築すべき であり、その役割は経営トップではなく、チームにある(リーダーの役割はファシリテーション) というものです。 本の構成はユニークで、序盤は核心に触れず、事例紹介が続きます。そのため、監修を務めた 早稲田大学MBAの入山章栄教授 が「第5章から読んでみては?」と冒頭で推奨しているのも納得です(最初から読み始めると、途中で離脱してしまう読者もいるかもしれません)。 理論全体は、いわゆる 「イノベーション創発」 に近く、最近のトレンドでもある 「小さく動かす」「チームで動く」 というアプローチを正当化するものです。また、「ゴールをイメージする」ことの重要性 も強調されており、この点は デザイン思考 にも通じるものがあると感じました。 さらに、後半に登場する 「男女リーダーの間に本質的な差はない」 という議論が非常に興味深く、このテーマだけで新たな一冊が書けるのではないかと思いました。 ● ディスカバリー・ドリブン戦略: かつてないほど不確実な世界で「成長を最大化」する方法(リタ・マグレイス、2023年、東洋経済新報社)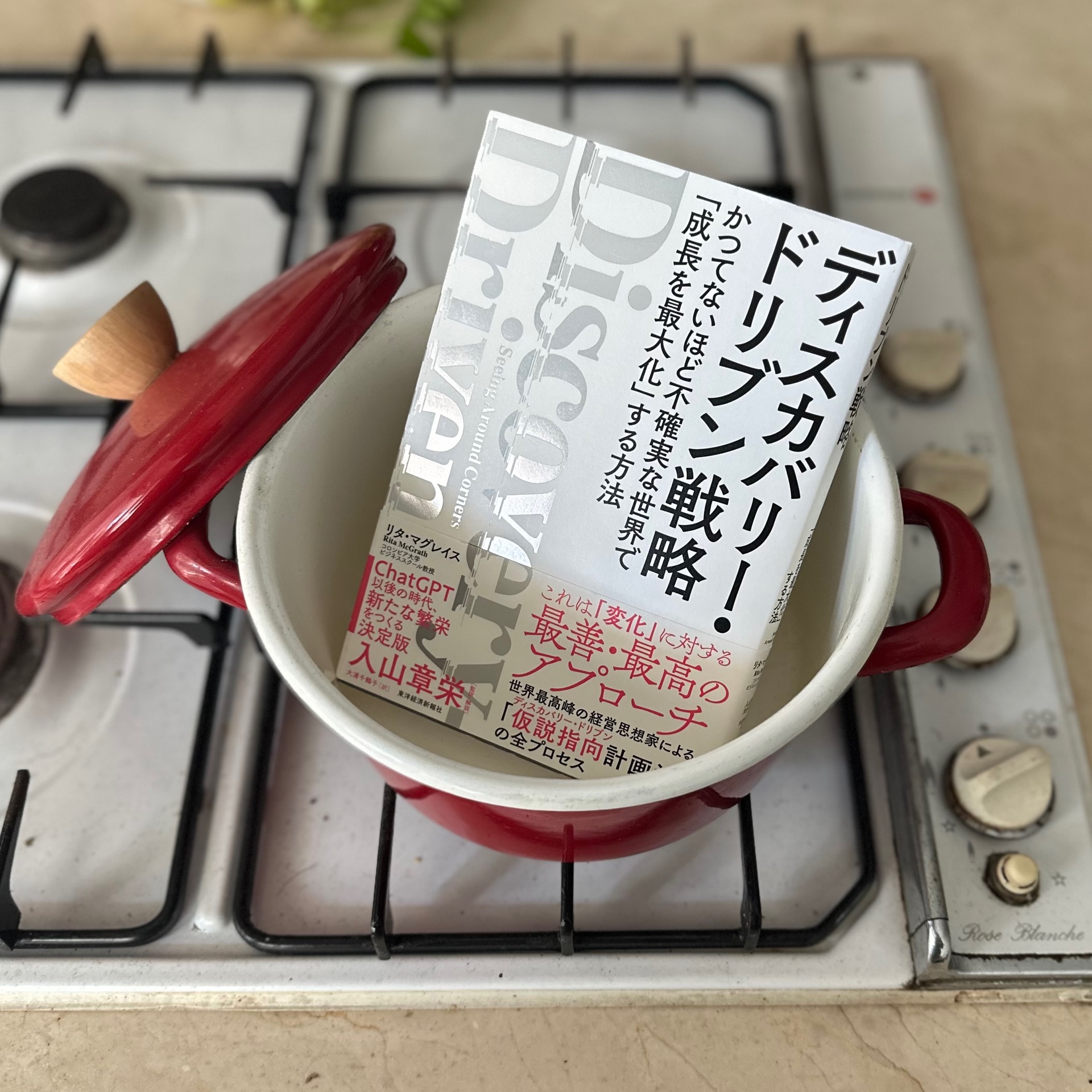
- 2025年3月11日
 読み終わった読了。「モダン」が誕生した19世紀から現在まで約200年のアートとデザインの動向を、表現法を軸に読み解く図説本。 豊富な資料がオールカラーで掲載され、そこには端的に時代背景から読み解く「なぜその表現が生まれたのか」が書かれています。 例えば「矢印や感嘆符はいつデザイン表現に取り入れられたのか?」「キリスト教におけるシンメトリー信仰の下にある西洋画とそれがない日本画の対比」をはじめ、段当たり前に見ているデザインやアート表現の裏にある歴史的・文化的背景に気づかされます。 そして、いつもながらですけど・・松田氏の本は想定が美しいので本としての価値が高いです。 本書のような 総覧的な視点から200年の表現を読み解くことで、自分が作るデザインがどの系譜に属し、どのような影響を受けているのかを知ることにつながるはず! 特に、これからグラフィックデザインを学ぶ学生にとっては、Pinterestなどで「仕上がったデザイン」ばかりを見るよりも、こうした表現の構造を理解する ほうが、実際の仕事に活かせる力 になるのではないかと思います。 ● アート&デザイン表現史 1800s-2000s(松田行正、2022年、左右社)
読み終わった読了。「モダン」が誕生した19世紀から現在まで約200年のアートとデザインの動向を、表現法を軸に読み解く図説本。 豊富な資料がオールカラーで掲載され、そこには端的に時代背景から読み解く「なぜその表現が生まれたのか」が書かれています。 例えば「矢印や感嘆符はいつデザイン表現に取り入れられたのか?」「キリスト教におけるシンメトリー信仰の下にある西洋画とそれがない日本画の対比」をはじめ、段当たり前に見ているデザインやアート表現の裏にある歴史的・文化的背景に気づかされます。 そして、いつもながらですけど・・松田氏の本は想定が美しいので本としての価値が高いです。 本書のような 総覧的な視点から200年の表現を読み解くことで、自分が作るデザインがどの系譜に属し、どのような影響を受けているのかを知ることにつながるはず! 特に、これからグラフィックデザインを学ぶ学生にとっては、Pinterestなどで「仕上がったデザイン」ばかりを見るよりも、こうした表現の構造を理解する ほうが、実際の仕事に活かせる力 になるのではないかと思います。 ● アート&デザイン表現史 1800s-2000s(松田行正、2022年、左右社)
- 2025年3月10日
 読み終わった読了。哲学の導入本として有名なこの本。「真理」「国家」「神」「存在」という4つのテーマを軸に、歴史的な流れに沿ってさまざまな哲学者の思想を解説しています。 内容は決して難解ではなく、ユーモアを交えながら「哲学者たちは何を、なぜ、どのように考えたのか」をキャラクター性を立たせて紹介してくれるので、哲学の入門書として非常にとっつきやすい構成になっています。 哲学の本論からは離れるけど、商業について「商人軽視は農業保護と権力保持の2軸で起きた」「資本主義があるから街の商売は最適化される」「新商品が出ないと困る人が増えるから無駄に出続ける」という著者の見解は、経済学という観点でかなり面白いと思いました(そもそも本のジャケットがバキ!) 読みながらジャンプ+に連載されていた『実在アンプラグド』(キルケゴールをはじめとする哲学者が現代に蘇りロックバンドを結成する)という漫画を思い出しました。ある意味で尖りすぎた思想家の考えは、ロックやパンクに通じるものなのかもしれません。 哲学に興味はあるけれど、どこから手をつければいいか迷っている人にとって、最初の一冊としてぴったりの本ではないでしょうか。 ● 史上最強の哲学入門(飲茶、2015年、河出書房新社)
読み終わった読了。哲学の導入本として有名なこの本。「真理」「国家」「神」「存在」という4つのテーマを軸に、歴史的な流れに沿ってさまざまな哲学者の思想を解説しています。 内容は決して難解ではなく、ユーモアを交えながら「哲学者たちは何を、なぜ、どのように考えたのか」をキャラクター性を立たせて紹介してくれるので、哲学の入門書として非常にとっつきやすい構成になっています。 哲学の本論からは離れるけど、商業について「商人軽視は農業保護と権力保持の2軸で起きた」「資本主義があるから街の商売は最適化される」「新商品が出ないと困る人が増えるから無駄に出続ける」という著者の見解は、経済学という観点でかなり面白いと思いました(そもそも本のジャケットがバキ!) 読みながらジャンプ+に連載されていた『実在アンプラグド』(キルケゴールをはじめとする哲学者が現代に蘇りロックバンドを結成する)という漫画を思い出しました。ある意味で尖りすぎた思想家の考えは、ロックやパンクに通じるものなのかもしれません。 哲学に興味はあるけれど、どこから手をつければいいか迷っている人にとって、最初の一冊としてぴったりの本ではないでしょうか。 ● 史上最強の哲学入門(飲茶、2015年、河出書房新社) - 2025年3月9日
 人はなぜ物を愛するのかアーロン・アフーヴィア,田沢恭子読了。消費者行動や「物への愛着」研究の第一人者、アーロン・アフーヴィア教授による、「なぜ人は物に愛着を持つのか?」を深掘りする一冊。人が物に対して抱く愛着の心理的メカニズムを探り、なぜ私たちは特定の物に強い思い入れを持つのかを科学的に解明されています。 人が物にハマるのは「擬人化(車を相棒と呼ぶ、ぬいぐるみに話しかける)」と「社会的結びつき(ファンが同じグッズを持つ、恋人とお揃いのアクセサリー)」にあるというのが主となる著者の主張で、そこは大変納得するものでした。 また、企業がいかにしてこの心理メカニズムを利用し、私たちの消費行動に影響を与えているのか という点も興味深いものでした。たしかに「ブランドのキャラ化」「ストーリーを用いた感情への訴えかけ」「パーソナライズ(自分好みへの改造)」されたアイテムへの愛着は強くなるというのは事実だと思います。 本書は単なる消費行動の分析ではなく、私たちが「何を大切にするのか」「どのように物と関係を築くのか」を振り返る契機 を与えてくれる一冊です。物への愛情が個人、家族、周囲の人と広がっていくことが「人と人を繋ぐこと:人の愛が繋がること」という結末はやや思考の飛躍があるようにも思えますが、著者の強い主張として心に残りました。 ● 人はなぜ物を愛するのか:「お気に入り」を生み出す心の仕組み(アーロン・アフーヴィア、2024年、白揚社)
人はなぜ物を愛するのかアーロン・アフーヴィア,田沢恭子読了。消費者行動や「物への愛着」研究の第一人者、アーロン・アフーヴィア教授による、「なぜ人は物に愛着を持つのか?」を深掘りする一冊。人が物に対して抱く愛着の心理的メカニズムを探り、なぜ私たちは特定の物に強い思い入れを持つのかを科学的に解明されています。 人が物にハマるのは「擬人化(車を相棒と呼ぶ、ぬいぐるみに話しかける)」と「社会的結びつき(ファンが同じグッズを持つ、恋人とお揃いのアクセサリー)」にあるというのが主となる著者の主張で、そこは大変納得するものでした。 また、企業がいかにしてこの心理メカニズムを利用し、私たちの消費行動に影響を与えているのか という点も興味深いものでした。たしかに「ブランドのキャラ化」「ストーリーを用いた感情への訴えかけ」「パーソナライズ(自分好みへの改造)」されたアイテムへの愛着は強くなるというのは事実だと思います。 本書は単なる消費行動の分析ではなく、私たちが「何を大切にするのか」「どのように物と関係を築くのか」を振り返る契機 を与えてくれる一冊です。物への愛情が個人、家族、周囲の人と広がっていくことが「人と人を繋ぐこと:人の愛が繋がること」という結末はやや思考の飛躍があるようにも思えますが、著者の強い主張として心に残りました。 ● 人はなぜ物を愛するのか:「お気に入り」を生み出す心の仕組み(アーロン・アフーヴィア、2024年、白揚社) - 2025年3月8日
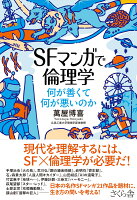 SFマンガで倫理学萬屋博喜読了。哲学の中でも、人間の行動や道徳、「人としてのあり方」について理論的に探る倫理学。そのテーマを 「SF漫画」を引き合いにしながら考える というユニークなアプローチを試みた一冊です。 漫画のストーリーや設定の裏にある倫理観を問い直すという方法は、難解になりがちな倫理学のテーマに入り込む「きっかけ」を提供するという点で興味深いものがあります。 実際に取り上げられている作品は、『火の鳥 生命編』『寄生獣』『BEASTARS』『人造人間キカイダー』『銀河鉄道999』『進撃の巨人』など、日本のSF漫画の中でも哲学的なテーマを持つ作品が選ばれています。 ただし、こうしたアプローチの特性上、漫画を知らない読者にとっては理解が難しくなりがちな部分もあります。また、倫理学の学問的な解説としても、漫画評論としても、どちらの側面においてもやや中途半端な印象を受ける部分は否めません。もう少し深い考察や分析が加わっていれば、より充実した内容になったかもしれません。 とはいえ、本書を通じて、日本の漫画が単なる娯楽ではなく、ひとつのアート表現であり、哲学的・倫理的なテーマを多く内包していることを改めて認識できる点は面白いと感じました。 ● SFマンガで倫理学 ―何が善くて何が悪いのか(萬屋博喜、2024年、さくら舎)
SFマンガで倫理学萬屋博喜読了。哲学の中でも、人間の行動や道徳、「人としてのあり方」について理論的に探る倫理学。そのテーマを 「SF漫画」を引き合いにしながら考える というユニークなアプローチを試みた一冊です。 漫画のストーリーや設定の裏にある倫理観を問い直すという方法は、難解になりがちな倫理学のテーマに入り込む「きっかけ」を提供するという点で興味深いものがあります。 実際に取り上げられている作品は、『火の鳥 生命編』『寄生獣』『BEASTARS』『人造人間キカイダー』『銀河鉄道999』『進撃の巨人』など、日本のSF漫画の中でも哲学的なテーマを持つ作品が選ばれています。 ただし、こうしたアプローチの特性上、漫画を知らない読者にとっては理解が難しくなりがちな部分もあります。また、倫理学の学問的な解説としても、漫画評論としても、どちらの側面においてもやや中途半端な印象を受ける部分は否めません。もう少し深い考察や分析が加わっていれば、より充実した内容になったかもしれません。 とはいえ、本書を通じて、日本の漫画が単なる娯楽ではなく、ひとつのアート表現であり、哲学的・倫理的なテーマを多く内包していることを改めて認識できる点は面白いと感じました。 ● SFマンガで倫理学 ―何が善くて何が悪いのか(萬屋博喜、2024年、さくら舎) - 2025年3月8日
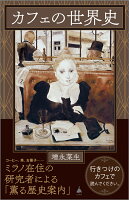 カフェの世界史増永菜生読み終わった読了。ミラノ在住で専門はルネサンス期イタリア史の研究家による著書。「カフェの世界史」とありますが、どちらかと言えば「カフェと世界史」という感じでしょうか。カフェメニューを入り口に近代のヨーロッパ史を学ぶような内容になっています。 いかにもカフェの話、というのは最終節に詰まっているので・・・ヨーロッパのカフェカルチャーについて興味がある人は、そこから読み始めた方がいいかもしれません(僕は世界史好きなので、わりと冒頭から一気に読んでしまいましたけど)。 「バレンタインを広めたのはモロゾフで、創業者はロシア革命から逃げる形で来日した」「コーヒー豆の消費拡大のためにコーヒーブレイク習慣を仕事場に意図的に広めたのはアメリカ」などの知らない話もありました。 まさにカフェでのんびりと読むのに良い本です。読んでいるとミラノに遊びにいった時の楽しい思い出が蘇ってきました。 ● カフェの世界史(増永菜生、2025年、SBクリエイティブ)
カフェの世界史増永菜生読み終わった読了。ミラノ在住で専門はルネサンス期イタリア史の研究家による著書。「カフェの世界史」とありますが、どちらかと言えば「カフェと世界史」という感じでしょうか。カフェメニューを入り口に近代のヨーロッパ史を学ぶような内容になっています。 いかにもカフェの話、というのは最終節に詰まっているので・・・ヨーロッパのカフェカルチャーについて興味がある人は、そこから読み始めた方がいいかもしれません(僕は世界史好きなので、わりと冒頭から一気に読んでしまいましたけど)。 「バレンタインを広めたのはモロゾフで、創業者はロシア革命から逃げる形で来日した」「コーヒー豆の消費拡大のためにコーヒーブレイク習慣を仕事場に意図的に広めたのはアメリカ」などの知らない話もありました。 まさにカフェでのんびりと読むのに良い本です。読んでいるとミラノに遊びにいった時の楽しい思い出が蘇ってきました。 ● カフェの世界史(増永菜生、2025年、SBクリエイティブ)
読み込み中...