

ユメ
@yumeticmode
紙の本と本屋さんを愛してやまない人間です。
吉田篤弘さん、辻村深月さん、三浦しをんさん、森見登美彦さん、今村翔吾さんが特に好きです。
- 2026年1月26日
 好日日記森下典子読み終わった感想『日日是好日』の著者である森下典子さんが、お茶の稽古を通じて感じる季節の移ろいについて綴った、二十四節気ごとに章立てされたエッセイ。心洗われるような文章をゆっくりと読み進めてゆく時間が、私に安らぎをもたらしてくれた。各章に、茶花や茶器、お茶菓子などを描いた著者自身によるフルカラーの挿画が収録されているのも目に嬉しい。 「立夏」の章で、私も敬愛する星野道夫さんの言葉が引用されていたことが印象に残っている。一年にいちどしか巡ってこない自然の美しさとの出会いを意識することで、ひとは自らの生の短さに自覚的になり、よりひたむきに生きられるようになるのかもしれない。四季よりもさらに濃やかな季節の変化に心を留めるゆとりを持ちたい、否、季節の変化を意識することによって精神的な余裕が生まれるのかもしれないと思った。 引用元である星野さんの『旅をする木』、そして森下さんの『日日是好日』を読み返したくなった。こうして、読んできた本と本が繋がってゆくことを感じられるのは嬉しいものだ。
好日日記森下典子読み終わった感想『日日是好日』の著者である森下典子さんが、お茶の稽古を通じて感じる季節の移ろいについて綴った、二十四節気ごとに章立てされたエッセイ。心洗われるような文章をゆっくりと読み進めてゆく時間が、私に安らぎをもたらしてくれた。各章に、茶花や茶器、お茶菓子などを描いた著者自身によるフルカラーの挿画が収録されているのも目に嬉しい。 「立夏」の章で、私も敬愛する星野道夫さんの言葉が引用されていたことが印象に残っている。一年にいちどしか巡ってこない自然の美しさとの出会いを意識することで、ひとは自らの生の短さに自覚的になり、よりひたむきに生きられるようになるのかもしれない。四季よりもさらに濃やかな季節の変化に心を留めるゆとりを持ちたい、否、季節の変化を意識することによって精神的な余裕が生まれるのかもしれないと思った。 引用元である星野さんの『旅をする木』、そして森下さんの『日日是好日』を読み返したくなった。こうして、読んできた本と本が繋がってゆくことを感じられるのは嬉しいものだ。 - 2026年1月26日
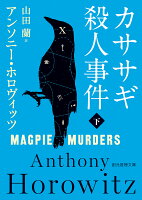 カササギ殺人事件<下>アンソニー・ホロヴィッツ,山田蘭読み終わった感想本屋大賞翻訳小説部門を受賞するなど、とても評判の高い作品だったので、読む前に期待値のハードルを上げていたつもりだったのだが、そこを易々と越えてくる面白さだった。すべての謎の真相が明かされた瞬間には深い満足感に包まれ、すぐに書店で続編を購入した。 下巻では作中作『カササギ殺人事件』だけでなく、その作者アラン・コンウェイと担当編集「わたし」の周りでも大きな事件が起こる。1950年代半ばの英国の小さな村サクスビー・オン・エイヴォンと、現代のロンドン、二重に進行してゆくフーダニットの虜になり、一心不乱にページを捲った。構成の見事さに感嘆の溜め息が漏れる。 「ミステリとは、真実をめぐる物語である——それ以上のものでもないし、それ以下のものでもない。確実なことなど何もないこの世界で、きっちりとすべてのiに点が打たれ、すべてのtに横棒が入っている本の最後のページにたどりつくのは、誰にとっても心の満たされる瞬間ではないだろうか」とは「わたし」の弁だが、本書を読むのはまさしくそうした心満たされる時間だった。
カササギ殺人事件<下>アンソニー・ホロヴィッツ,山田蘭読み終わった感想本屋大賞翻訳小説部門を受賞するなど、とても評判の高い作品だったので、読む前に期待値のハードルを上げていたつもりだったのだが、そこを易々と越えてくる面白さだった。すべての謎の真相が明かされた瞬間には深い満足感に包まれ、すぐに書店で続編を購入した。 下巻では作中作『カササギ殺人事件』だけでなく、その作者アラン・コンウェイと担当編集「わたし」の周りでも大きな事件が起こる。1950年代半ばの英国の小さな村サクスビー・オン・エイヴォンと、現代のロンドン、二重に進行してゆくフーダニットの虜になり、一心不乱にページを捲った。構成の見事さに感嘆の溜め息が漏れる。 「ミステリとは、真実をめぐる物語である——それ以上のものでもないし、それ以下のものでもない。確実なことなど何もないこの世界で、きっちりとすべてのiに点が打たれ、すべてのtに横棒が入っている本の最後のページにたどりつくのは、誰にとっても心の満たされる瞬間ではないだろうか」とは「わたし」の弁だが、本書を読むのはまさしくそうした心満たされる時間だった。 - 2026年1月24日
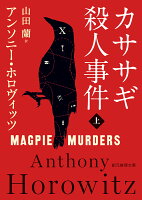 カササギ殺人事件<上>アンソニー・ホロヴィッツ,山田蘭読み終わった感想出版社で編集の仕事をしている「わたし」ことスーザン・ライランドが読者に語りかけてくる冒頭の文章——「ワインのボトル。ナチョ・チーズ味トルティーヤ・チップスの大袋と、ホット・サルサ・ディップの壜。手もとにはタバコをひと箱(はいはい、言いたいことはわかります)。窓に叩きつける雨。そして本。これって最高の組み合わせじゃない?」——に、いきなり心を掴まれた。 彼女が読んでいる原稿こそが、『カササギ殺人事件』というミステリ作品である。「わたし」の語りかけによって作中作『カササギ殺人事件』への期待は否が応にも高まり、実際、初めこそ数多い登場人物の名前を覚えるのに少々苦労したが、いつしか1950年代半ばの英国の小さな村で繰り広げられる物語にすっかり夢中になっていた。 閑静な村で相次いだ死。上巻は、名探偵アティカス・ピュントがひとり目を殺害した人物を断言したところで幕を閉じる。いったい何という終わり方だろう!下巻への期待は最高潮に高まる。『カササギ殺人事件』がわざわざ作中作という形式を取っていることにもきっと意味があるのだろうから、それが明かされるのも楽しみだ。
カササギ殺人事件<上>アンソニー・ホロヴィッツ,山田蘭読み終わった感想出版社で編集の仕事をしている「わたし」ことスーザン・ライランドが読者に語りかけてくる冒頭の文章——「ワインのボトル。ナチョ・チーズ味トルティーヤ・チップスの大袋と、ホット・サルサ・ディップの壜。手もとにはタバコをひと箱(はいはい、言いたいことはわかります)。窓に叩きつける雨。そして本。これって最高の組み合わせじゃない?」——に、いきなり心を掴まれた。 彼女が読んでいる原稿こそが、『カササギ殺人事件』というミステリ作品である。「わたし」の語りかけによって作中作『カササギ殺人事件』への期待は否が応にも高まり、実際、初めこそ数多い登場人物の名前を覚えるのに少々苦労したが、いつしか1950年代半ばの英国の小さな村で繰り広げられる物語にすっかり夢中になっていた。 閑静な村で相次いだ死。上巻は、名探偵アティカス・ピュントがひとり目を殺害した人物を断言したところで幕を閉じる。いったい何という終わり方だろう!下巻への期待は最高潮に高まる。『カササギ殺人事件』がわざわざ作中作という形式を取っていることにもきっと意味があるのだろうから、それが明かされるのも楽しみだ。 - 2026年1月22日
 さすらいの孤児ラスムスアストリッド・リンドグレーン読み終わった感想ヴェステルハーガ孤児の家を抜け出した少年ラスムスは、風来坊のオスカルと出会い、共に旅をするようになる。 ヴェステルハーガにいた頃のラスムスがいかに愛情というものに飢えていたのか、リンドグレーンのこまやかな筆致から切実に伝わってきて、胸が痛む。そんな彼が、陽気で歌と手風琴が上手く、自分のことを子どもだからと軽んじたりせず、それでいて大人としてきちんと庇護してくれるオスカルに出会ったら、それは慕わずにはいられないだろう。読者だって、オスカルのことを好きにならずにはいられないのだから(もちろん、ラスムスのことも)。 しかし、二人の旅路は、ピストル強盗事件に巻き込まれたことによって波瀾万丈なものとなる。数度にわたる犯人たちとの対峙は、いずれも息つかせぬ展開で、ハラハラドキドキしながら見守った。決して気が強い方ではないラスムスが、オスカルとの平穏な時間を守るために懸命に立ち向かう姿には胸が熱くなる。終盤、ラスムスがオスカルを追いかけていってからの大団円には、私も幸福な気持ちで満たされた。 旅路の途中の「夏の音」の描写が牧歌的な美しさを湛えていて、リンドグレーン作品の魅力をここでも感じた。
さすらいの孤児ラスムスアストリッド・リンドグレーン読み終わった感想ヴェステルハーガ孤児の家を抜け出した少年ラスムスは、風来坊のオスカルと出会い、共に旅をするようになる。 ヴェステルハーガにいた頃のラスムスがいかに愛情というものに飢えていたのか、リンドグレーンのこまやかな筆致から切実に伝わってきて、胸が痛む。そんな彼が、陽気で歌と手風琴が上手く、自分のことを子どもだからと軽んじたりせず、それでいて大人としてきちんと庇護してくれるオスカルに出会ったら、それは慕わずにはいられないだろう。読者だって、オスカルのことを好きにならずにはいられないのだから(もちろん、ラスムスのことも)。 しかし、二人の旅路は、ピストル強盗事件に巻き込まれたことによって波瀾万丈なものとなる。数度にわたる犯人たちとの対峙は、いずれも息つかせぬ展開で、ハラハラドキドキしながら見守った。決して気が強い方ではないラスムスが、オスカルとの平穏な時間を守るために懸命に立ち向かう姿には胸が熱くなる。終盤、ラスムスがオスカルを追いかけていってからの大団円には、私も幸福な気持ちで満たされた。 旅路の途中の「夏の音」の描写が牧歌的な美しさを湛えていて、リンドグレーン作品の魅力をここでも感じた。 - 2026年1月17日
 万感のおもい万城目学読み終わった感想変形本に角丸加工と様々な工夫が凝らされた装幀が目にする者を惹きつける。やはり夏葉社の本は佇まいが美しく、紙の本ならではの喜びがある。表紙に貼られた「エッセイ万歳」のシールにも思わず笑みが溢れ、この本を単行本で手に取ることができてよかったと思う(と言いつつ、最近刊行された文庫本には直木賞待ち会の模様を綴ったエッセイも新たに収録されているらしく、そちらも気になっている)。 ひと月ごとに「色」に焦点を当てたエッセイ「色へのおもい」が、瑞々しい情感で満たされていて心に沁みた。日々のあれこれに追われていると、決まった色しか視界に入ってこなくなってしまうことがあるが、私たちが生きる世界は無数の色に溢れている。いつも世界に対して心を開く余裕を持ち、日常がもたらしてくれる感動を忘れずにいたい。
万感のおもい万城目学読み終わった感想変形本に角丸加工と様々な工夫が凝らされた装幀が目にする者を惹きつける。やはり夏葉社の本は佇まいが美しく、紙の本ならではの喜びがある。表紙に貼られた「エッセイ万歳」のシールにも思わず笑みが溢れ、この本を単行本で手に取ることができてよかったと思う(と言いつつ、最近刊行された文庫本には直木賞待ち会の模様を綴ったエッセイも新たに収録されているらしく、そちらも気になっている)。 ひと月ごとに「色」に焦点を当てたエッセイ「色へのおもい」が、瑞々しい情感で満たされていて心に沁みた。日々のあれこれに追われていると、決まった色しか視界に入ってこなくなってしまうことがあるが、私たちが生きる世界は無数の色に溢れている。いつも世界に対して心を開く余裕を持ち、日常がもたらしてくれる感動を忘れずにいたい。 - 2026年1月16日
 赤いモレスキンの女アントワーヌ・ローラン,吉田洋之読み終わった感想私は文具が好きなので、『赤いモレスキンの女』というタイトルに惹かれずにはいられなかった。 パリの書店主であるローランは、ある日、ゴミ箱の上に捨てられていた女性のハンドバッグを拾う。そこに入っていたのは、赤いモレスキンの手帳と、サイン入りのパトリック・モディアノの本だった。ローランは、手帳に綴られた断片的な言葉から、急速に女性の内面に魅了されてゆく。手帳に記す文章には、その時々の心境が如実に表れるものだ。サイン本の為書きからロールというファーストネームだけ判明した女性がいったいどんな人物なのか、ローランが想像を掻き立てられるのも分かる気がする。しかも、彼女は自分と同じ本好きなのだから。ローランとロールは、本を通じて結びついているとも言える。それぞれの本棚の本の並べ方など、本にまつわる描写のディテールに心をくすぐられた。 ローランは、わずかな手がかりからロールを探し出そうとする。物語の展開自体に大きな驚きはないのだが、この大団円こそが望んでいたものなのだという素直な喜びを抱かせる力がある。クライマックスでの、「こんばんは、本を探しているんですが……」というひと言から始まるロールの台詞が、お洒落で好きだ。
赤いモレスキンの女アントワーヌ・ローラン,吉田洋之読み終わった感想私は文具が好きなので、『赤いモレスキンの女』というタイトルに惹かれずにはいられなかった。 パリの書店主であるローランは、ある日、ゴミ箱の上に捨てられていた女性のハンドバッグを拾う。そこに入っていたのは、赤いモレスキンの手帳と、サイン入りのパトリック・モディアノの本だった。ローランは、手帳に綴られた断片的な言葉から、急速に女性の内面に魅了されてゆく。手帳に記す文章には、その時々の心境が如実に表れるものだ。サイン本の為書きからロールというファーストネームだけ判明した女性がいったいどんな人物なのか、ローランが想像を掻き立てられるのも分かる気がする。しかも、彼女は自分と同じ本好きなのだから。ローランとロールは、本を通じて結びついているとも言える。それぞれの本棚の本の並べ方など、本にまつわる描写のディテールに心をくすぐられた。 ローランは、わずかな手がかりからロールを探し出そうとする。物語の展開自体に大きな驚きはないのだが、この大団円こそが望んでいたものなのだという素直な喜びを抱かせる力がある。クライマックスでの、「こんばんは、本を探しているんですが……」というひと言から始まるロールの台詞が、お洒落で好きだ。 - 2026年1月11日
 読み終わった感想心に残る一節以下、ネタバレを含む感想です。 最近、老いについて考えることが増えた。30代になった自分の肉体も精神も、確実に20代の頃とは変化している。そしてその変化は、今後も止まることはないだろう。そう思うと、時に悲観的になることもあるし、そうでなくとも、自分がどう歳を重ねてゆくべきなのかということについては惑うことばかりだ。 そんな折、信頼できる書き手の綴る物語の登場人物たちが時にもがきながらも人生を先へ進んでゆく様を見せてもらえると、心の拠り所を見つけたような気持ちになる。シリーズ開幕時はまだ少女だった幸がいつのまにか私の年齢を追い越して、本作では還暦を迎えていることに驚きもあるが、やはり彼女たちの人生模様を長く見守らせてもらえることは幸せに思う。 寄り添って生きることは前途多難な道でもあると言われていた幸と賢輔が睦まじく暮らしているのには胸が温まったし、二人がいくつになっても商いに対して知恵をこらして、五鈴屋の暖簾を次の百年へと受け継いでゆこうとする姿に尊敬の念を新たにした。幸の心境を描いた「血縁が無くとも、ひとはひとを思いやれるし、そのひとのために幾らでも精進を重ねられる」という言葉に、胸を掴まれる。 上巻で自らの老いについて悩んでいたお竹が、92歳になってなお幸の右腕として健在であるのにも活力をもらった。
読み終わった感想心に残る一節以下、ネタバレを含む感想です。 最近、老いについて考えることが増えた。30代になった自分の肉体も精神も、確実に20代の頃とは変化している。そしてその変化は、今後も止まることはないだろう。そう思うと、時に悲観的になることもあるし、そうでなくとも、自分がどう歳を重ねてゆくべきなのかということについては惑うことばかりだ。 そんな折、信頼できる書き手の綴る物語の登場人物たちが時にもがきながらも人生を先へ進んでゆく様を見せてもらえると、心の拠り所を見つけたような気持ちになる。シリーズ開幕時はまだ少女だった幸がいつのまにか私の年齢を追い越して、本作では還暦を迎えていることに驚きもあるが、やはり彼女たちの人生模様を長く見守らせてもらえることは幸せに思う。 寄り添って生きることは前途多難な道でもあると言われていた幸と賢輔が睦まじく暮らしているのには胸が温まったし、二人がいくつになっても商いに対して知恵をこらして、五鈴屋の暖簾を次の百年へと受け継いでゆこうとする姿に尊敬の念を新たにした。幸の心境を描いた「血縁が無くとも、ひとはひとを思いやれるし、そのひとのために幾らでも精進を重ねられる」という言葉に、胸を掴まれる。 上巻で自らの老いについて悩んでいたお竹が、92歳になってなお幸の右腕として健在であるのにも活力をもらった。 - 2026年1月10日
 読み終わった感想以下、ネタバレを含む感想です。 シリーズ本編で活躍した登場人物たちの過去と未来を描いた短編集。どの話もしみじみと心に沁みた。 惣次が井筒屋保晴として生きるに至った経緯が綴られた「風を抱く」には胸を突かれた。幸や菊栄のことを距離を置いて見守っていた惣次に、こんな温かな縁と悲しい別れがあったとは。風に揺れる小米花(雪柳)の素朴な美しさと、それを教えてくれたひととの思い出を胸に抱きながらこれからも逞しく生きてゆくのであろう惣次の姿が、切なく心に残る。 五鈴屋江戸本店で支配人を務める佐助の今昔の恋を記した「はた結び」。本編でも少し触れられていた過去の恋の行く末には胸が痛んだが、新たな恋が実ったことは本当によかった。他の奉公人たちに温かく見守られているのも、佐助の真面目な人柄があってこそだ。 老いに悩むお竹を主役に据えた「百代の過客」もとてもよかった。限りある一生をどう終えるのかということについて、私も色々と考えさせられる。自分の出来ることを全うする、与えられた生を力一杯生ききると決めたお竹の姿に、力強く励まされる思いがした。 そして、一途に幸を慕い続けてきた賢輔の想いの行方を描いた表題作「契り橋」。シリーズのタイトルである「金と銀」という言葉に物語が帰結する様がとても美しく、胸を打たれた。川面を彩る金波と銀波、そして二人が持つ手巾の月白、色の描写が綺麗なのも印象深い。
読み終わった感想以下、ネタバレを含む感想です。 シリーズ本編で活躍した登場人物たちの過去と未来を描いた短編集。どの話もしみじみと心に沁みた。 惣次が井筒屋保晴として生きるに至った経緯が綴られた「風を抱く」には胸を突かれた。幸や菊栄のことを距離を置いて見守っていた惣次に、こんな温かな縁と悲しい別れがあったとは。風に揺れる小米花(雪柳)の素朴な美しさと、それを教えてくれたひととの思い出を胸に抱きながらこれからも逞しく生きてゆくのであろう惣次の姿が、切なく心に残る。 五鈴屋江戸本店で支配人を務める佐助の今昔の恋を記した「はた結び」。本編でも少し触れられていた過去の恋の行く末には胸が痛んだが、新たな恋が実ったことは本当によかった。他の奉公人たちに温かく見守られているのも、佐助の真面目な人柄があってこそだ。 老いに悩むお竹を主役に据えた「百代の過客」もとてもよかった。限りある一生をどう終えるのかということについて、私も色々と考えさせられる。自分の出来ることを全うする、与えられた生を力一杯生ききると決めたお竹の姿に、力強く励まされる思いがした。 そして、一途に幸を慕い続けてきた賢輔の想いの行方を描いた表題作「契り橋」。シリーズのタイトルである「金と銀」という言葉に物語が帰結する様がとても美しく、胸を打たれた。川面を彩る金波と銀波、そして二人が持つ手巾の月白、色の描写が綺麗なのも印象深い。 - 2026年1月9日
 女王さまの休日古内一絵読み終わった感想ひさしぶりにシャールさんやさくら、ジャダたちと再会できたことが嬉しい。 今回、物語の舞台となるのは台湾だ。ヘチマと海老の小籠包やガチョウの油かけご飯、魯肉飯といった台湾グルメや、ピーナッツ豆花、仙草ゼリーといった薬膳スイーツがどれも美味しそうで、食欲をそそられる。とりわけ心惹かれたのは、とても爽やかな風味だという台湾珈琲だ。私はコーヒー党で、日頃様々な産地の豆を買うようにしているのだが、台湾産のコーヒーはまだ飲んだことがなく、すごく気になっている。 作中、「食べることは、生きることだ」という一文が出てくる。悩みを抱えていた登場人物たちが台湾の美味しい食事から活力を得てゆく姿を見ていると、その言葉がスッと胸に沁みてゆく。気分が塞ぎがちなときでも食べることは大切にしようと思わされるし、同時に、ただ美味しいものを食べればよいのではなく、自分の抱える問題に前向きに立ち向かおうとする心意気があってこそ食に癒されるのだとも肝に銘じておこうと思う。 かつて日本に統治されていた台湾の地で、物語は平和への祈りを込めて結ばれる。本書が刊行されてからのわずか数か月のあいだでも、世界情勢は激動してしまった。「それでも私たちは、この日常を、簡単にあきらめるわけにはいかない。自棄になったり、無気力になったり、声が大きいだけの流れに安易に取り込まれたりしてはいけない」という文章が、切々と胸に迫る。
女王さまの休日古内一絵読み終わった感想ひさしぶりにシャールさんやさくら、ジャダたちと再会できたことが嬉しい。 今回、物語の舞台となるのは台湾だ。ヘチマと海老の小籠包やガチョウの油かけご飯、魯肉飯といった台湾グルメや、ピーナッツ豆花、仙草ゼリーといった薬膳スイーツがどれも美味しそうで、食欲をそそられる。とりわけ心惹かれたのは、とても爽やかな風味だという台湾珈琲だ。私はコーヒー党で、日頃様々な産地の豆を買うようにしているのだが、台湾産のコーヒーはまだ飲んだことがなく、すごく気になっている。 作中、「食べることは、生きることだ」という一文が出てくる。悩みを抱えていた登場人物たちが台湾の美味しい食事から活力を得てゆく姿を見ていると、その言葉がスッと胸に沁みてゆく。気分が塞ぎがちなときでも食べることは大切にしようと思わされるし、同時に、ただ美味しいものを食べればよいのではなく、自分の抱える問題に前向きに立ち向かおうとする心意気があってこそ食に癒されるのだとも肝に銘じておこうと思う。 かつて日本に統治されていた台湾の地で、物語は平和への祈りを込めて結ばれる。本書が刊行されてからのわずか数か月のあいだでも、世界情勢は激動してしまった。「それでも私たちは、この日常を、簡単にあきらめるわけにはいかない。自棄になったり、無気力になったり、声が大きいだけの流れに安易に取り込まれたりしてはいけない」という文章が、切々と胸に迫る。 - 2026年1月8日
 読み終わった感想以下、ネタバレを含む感想です。 シリーズ完結巻。あらすじに「まさかの裏切り」という文言が入っていたので、いったい誰がどんな形で——とハラハラしながら読み進めた。かつての結の裏切りが今なお五鈴屋主従の心に影を落としているというのに、このうえまだ幸に試練が与えられるのか、と心苦しくもあった。いざ裏切りの全容が露見した際には私も幸や菊栄もろとも奈落に突き落とされたような心地がしたが、さすが髙田郁さんと言うべきか、一筋縄ではいかない、更なる驚きの展開が待ち受けている。結のことを考えるとなんとも複雑な気分になるが、音羽屋忠兵衛が報いを受けたこと、惣次が五鈴屋を害そうとしたわけではなかったことはよかった。 源流から始まったこの『あきない世傳 金と銀』の物語が大海に辿りつくとき、そこにはいったいどんな景色が広がっているのだろうと思っていたが、同じ浅草田原町で商いをする店々と手を取り合うという幸の知恵に、またしても感嘆させられた。揃いの王子茶の暖簾がはためく光景が、しみじみと胸を打つ。遅くなってしまったが、シリーズを最後まで見届けられて本当によかった。特別巻を読むのも楽しみだ。
読み終わった感想以下、ネタバレを含む感想です。 シリーズ完結巻。あらすじに「まさかの裏切り」という文言が入っていたので、いったい誰がどんな形で——とハラハラしながら読み進めた。かつての結の裏切りが今なお五鈴屋主従の心に影を落としているというのに、このうえまだ幸に試練が与えられるのか、と心苦しくもあった。いざ裏切りの全容が露見した際には私も幸や菊栄もろとも奈落に突き落とされたような心地がしたが、さすが髙田郁さんと言うべきか、一筋縄ではいかない、更なる驚きの展開が待ち受けている。結のことを考えるとなんとも複雑な気分になるが、音羽屋忠兵衛が報いを受けたこと、惣次が五鈴屋を害そうとしたわけではなかったことはよかった。 源流から始まったこの『あきない世傳 金と銀』の物語が大海に辿りつくとき、そこにはいったいどんな景色が広がっているのだろうと思っていたが、同じ浅草田原町で商いをする店々と手を取り合うという幸の知恵に、またしても感嘆させられた。揃いの王子茶の暖簾がはためく光景が、しみじみと胸を打つ。遅くなってしまったが、シリーズを最後まで見届けられて本当によかった。特別巻を読むのも楽しみだ。 - 2026年1月7日
 読み終わった感想シリーズ第4作の主人公となるのは、「シリウス」池袋店の店長であるいつき。本社が女性活躍を打ち出す前から店長を務めていた彼女は、昨今の「シリウス」の雰囲気に違和感を覚えていた。そんな中、偶然「キッチン常夜灯」に辿りついたいつきは、みもざやつぐみ、かなめと仕事の悩みを共有する関係になり、「シリウス」の改革案を次々と提案するようになってゆく。初めは複雑な気持ちを抱いていた歳下の女性社員たちと交流することで、前向きな気持ちが連鎖してゆく様が、読んでいて清々しい。私も仕事を頑張ろう、と励まされる思いがする。 また、いつきの父親が入院するくだりには色々と考えさせられた。親の老いはいつか必ず訪れる。そのとききちんと対応できるようにするためには、自分の生活基盤をしっかり固めておかなければ。 「キッチン常夜灯」の料理の数々は、今作も垂涎もの。中でもスズキのグラティネ、ジロール茸のオムレツ、牛タンのコンフィのサラダ、デザートガレット、栗のヴルーテ、そしてタイトルにもなっているオニオングラタンスープが気になって仕方がない。私も仕事帰りに「キッチン常夜灯」で夜をすごせたらな、と夢想してしまう。
読み終わった感想シリーズ第4作の主人公となるのは、「シリウス」池袋店の店長であるいつき。本社が女性活躍を打ち出す前から店長を務めていた彼女は、昨今の「シリウス」の雰囲気に違和感を覚えていた。そんな中、偶然「キッチン常夜灯」に辿りついたいつきは、みもざやつぐみ、かなめと仕事の悩みを共有する関係になり、「シリウス」の改革案を次々と提案するようになってゆく。初めは複雑な気持ちを抱いていた歳下の女性社員たちと交流することで、前向きな気持ちが連鎖してゆく様が、読んでいて清々しい。私も仕事を頑張ろう、と励まされる思いがする。 また、いつきの父親が入院するくだりには色々と考えさせられた。親の老いはいつか必ず訪れる。そのとききちんと対応できるようにするためには、自分の生活基盤をしっかり固めておかなければ。 「キッチン常夜灯」の料理の数々は、今作も垂涎もの。中でもスズキのグラティネ、ジロール茸のオムレツ、牛タンのコンフィのサラダ、デザートガレット、栗のヴルーテ、そしてタイトルにもなっているオニオングラタンスープが気になって仕方がない。私も仕事帰りに「キッチン常夜灯」で夜をすごせたらな、と夢想してしまう。 - 2026年1月4日
 パディントンの煙突掃除マイケル・ボンド読み終わった感想お隣のカリー氏の家の水道管を直そうとして、お風呂場をめちゃくちゃにしてしまったパディントン。バードさんはその事態のことを「不慮の熊害(ゆうがい)」と表現する。松岡享子さんの名訳が光っているのと、都合が悪いときだけ耳が遠くなるパディントンが可笑しくて、思わず声を立てて笑った。水道管に向かってブローランプを噴射するパディントン、それから別の章で煙突掃除をした結果またしても「熊害」を引き起こして煤まみれになったパディントンの挿絵が、すごく絶妙な表情で好きだ。 パディントンが天敵と言っても差し支えないカリー氏だが、普段は意地の悪い彼が、最終章で「おまえがいなくなると、さびしくなるな、クマ公」と言うのにはしんみりする。ペルーへ帰ったきりになってしまうと思われたパディントンが、ちゃんとまたウインザーガーデン三十二番地へ戻ってくるつもりなのだと分かったときには、私もホッと胸を撫で下ろした。ブラウンさん一家はパディントンのことを家族として大切に想っているが、パディントンにとっても同様なのだということに心が温まる。
パディントンの煙突掃除マイケル・ボンド読み終わった感想お隣のカリー氏の家の水道管を直そうとして、お風呂場をめちゃくちゃにしてしまったパディントン。バードさんはその事態のことを「不慮の熊害(ゆうがい)」と表現する。松岡享子さんの名訳が光っているのと、都合が悪いときだけ耳が遠くなるパディントンが可笑しくて、思わず声を立てて笑った。水道管に向かってブローランプを噴射するパディントン、それから別の章で煙突掃除をした結果またしても「熊害」を引き起こして煤まみれになったパディントンの挿絵が、すごく絶妙な表情で好きだ。 パディントンが天敵と言っても差し支えないカリー氏だが、普段は意地の悪い彼が、最終章で「おまえがいなくなると、さびしくなるな、クマ公」と言うのにはしんみりする。ペルーへ帰ったきりになってしまうと思われたパディントンが、ちゃんとまたウインザーガーデン三十二番地へ戻ってくるつもりなのだと分かったときには、私もホッと胸を撫で下ろした。ブラウンさん一家はパディントンのことを家族として大切に想っているが、パディントンにとっても同様なのだということに心が温まる。 - 2026年1月3日
 もうしばらくは早歩きくどうれいん読み終わった感想徒歩、自転車、自家用車、タクシー、新幹線、地下鉄、動く通路、たらい船——様々な形の「移動」を題材にしたエッセイ。くどうれいんさんのエッセイを読むときはいつもそうなのだが、にこにこと笑ったり、時にハッとさせられたりと、ページを捲りながら表情筋が忙しく動く。そんな読書の時間が、とても楽しい。 遠方へ旅に出るとき、最終日に日持ちのしない食べ物をお土産に買って帰るのは真似したいなと思った。私は食べ物のお土産というと土産物店でその土地の銘菓を買いがちなのだが、それだけではなく、くどうさんのように百貨店やスーパーなどでその土地ならではの生鮮食品を買うのも楽しそうだ。旅のお土産としてカレールーをテイクアウトしたっていいんだ、と目から鱗だった。表紙のイラストはなぜサボテンなのだろう?とちょっと不思議だったのだが、その謎も解けてスッキリ。 書店回りの前に食パン二斤とケーキ三つを買って、担当編集さんに「まじですか?」と笑われるくどうさん。私は、そんなくどうさんの気持ちのいい食べっぷりが好きである。
もうしばらくは早歩きくどうれいん読み終わった感想徒歩、自転車、自家用車、タクシー、新幹線、地下鉄、動く通路、たらい船——様々な形の「移動」を題材にしたエッセイ。くどうれいんさんのエッセイを読むときはいつもそうなのだが、にこにこと笑ったり、時にハッとさせられたりと、ページを捲りながら表情筋が忙しく動く。そんな読書の時間が、とても楽しい。 遠方へ旅に出るとき、最終日に日持ちのしない食べ物をお土産に買って帰るのは真似したいなと思った。私は食べ物のお土産というと土産物店でその土地の銘菓を買いがちなのだが、それだけではなく、くどうさんのように百貨店やスーパーなどでその土地ならではの生鮮食品を買うのも楽しそうだ。旅のお土産としてカレールーをテイクアウトしたっていいんだ、と目から鱗だった。表紙のイラストはなぜサボテンなのだろう?とちょっと不思議だったのだが、その謎も解けてスッキリ。 書店回りの前に食パン二斤とケーキ三つを買って、担当編集さんに「まじですか?」と笑われるくどうさん。私は、そんなくどうさんの気持ちのいい食べっぷりが好きである。 - 2026年1月3日
 祝祭と予感恩田陸読み終わった感想『蜜蜂と遠雷』のスピンオフ。本編に登場したキャラクターたちの過去と未来が、色彩豊かに切り取られている。 芳ヶ江国際ピアノコンクール2次予選の課題曲「春と修羅」の作曲家・菱沼忠明と、その教え子・小山内健次の交流を描いた「袈裟と鞦韆」がとりわけ印象に残っている。この短編を読んでから2次予選での明石・マサル・塵・亜夜の演奏を振り返ると、音楽を通じてひとの心の中にある風景が受け継がれてゆくことに遥かな思いになった。宮沢賢治が耕した畑——小山内健次の生まれ故郷であり、菱沼忠明が訪れたホップ畑——そして高島明石が心の拠り所とし、風間塵が彼の演奏から感じ取った桑畑。時を越え、少しずつ形を変えながら「生活者の音楽」が続いていることが感慨深く、やはり音楽は素晴らしいと思わされる。 ヴィオラに転向した奏が運命の楽器と出会うまでを描いた「鈴蘭と階段」もよかった。音楽に造詣の深い誰からも「これはあなたの楽器だ」と認められる一台と出会えるなんて、奇跡のようなことだと思う。
祝祭と予感恩田陸読み終わった感想『蜜蜂と遠雷』のスピンオフ。本編に登場したキャラクターたちの過去と未来が、色彩豊かに切り取られている。 芳ヶ江国際ピアノコンクール2次予選の課題曲「春と修羅」の作曲家・菱沼忠明と、その教え子・小山内健次の交流を描いた「袈裟と鞦韆」がとりわけ印象に残っている。この短編を読んでから2次予選での明石・マサル・塵・亜夜の演奏を振り返ると、音楽を通じてひとの心の中にある風景が受け継がれてゆくことに遥かな思いになった。宮沢賢治が耕した畑——小山内健次の生まれ故郷であり、菱沼忠明が訪れたホップ畑——そして高島明石が心の拠り所とし、風間塵が彼の演奏から感じ取った桑畑。時を越え、少しずつ形を変えながら「生活者の音楽」が続いていることが感慨深く、やはり音楽は素晴らしいと思わされる。 ヴィオラに転向した奏が運命の楽器と出会うまでを描いた「鈴蘭と階段」もよかった。音楽に造詣の深い誰からも「これはあなたの楽器だ」と認められる一台と出会えるなんて、奇跡のようなことだと思う。 - 2026年1月2日
 蜜蜂と遠雷恩田陸読み終わった感想再読『spring』を再読したら、こちらも無性に読み返したくなり、今年最初の一冊に選んだ。 クラシック音楽の曲想を、豊かな自然の情景や壮大な人間ドラマになぞらえた文章表現がとても美しく、初読時と変わらず恍惚としながら読んだ。 本書を読んでいると、自分が音楽をやっていたときの思い出や、演奏してきた旋律、そして音楽に対して抱いた感情の数々が次々と呼び起こされる。それらは決して綺麗なものばかりではなく、時に読み進めるのが苦しくもなる。だが、物語が終盤に差しかかってくると、圧倒的な実感を伴って「音楽って素晴らしい」と思わせてくれるのだ。風間塵という少年の存在が、初めこそ「災厄」ではないかと危惧されながらも、やがて他のコンテスタント・審査員・聴衆に音楽の喜びという「ギフト」をもたらしたのと同様に、この物語も読者の心に「ギフト」として作用する。 オーケストラの中に身を置きながら「音楽とはなぜこんなにも美しいのだろう」と泣きたくなった瞬間のことを思い出した。音楽は時代も国境も越え、奏でる者、そして聴く者の心を掴む。音楽に触れることは、とても刹那的でありながら、同時に永遠性を獲得することでもあるのだ。
蜜蜂と遠雷恩田陸読み終わった感想再読『spring』を再読したら、こちらも無性に読み返したくなり、今年最初の一冊に選んだ。 クラシック音楽の曲想を、豊かな自然の情景や壮大な人間ドラマになぞらえた文章表現がとても美しく、初読時と変わらず恍惚としながら読んだ。 本書を読んでいると、自分が音楽をやっていたときの思い出や、演奏してきた旋律、そして音楽に対して抱いた感情の数々が次々と呼び起こされる。それらは決して綺麗なものばかりではなく、時に読み進めるのが苦しくもなる。だが、物語が終盤に差しかかってくると、圧倒的な実感を伴って「音楽って素晴らしい」と思わせてくれるのだ。風間塵という少年の存在が、初めこそ「災厄」ではないかと危惧されながらも、やがて他のコンテスタント・審査員・聴衆に音楽の喜びという「ギフト」をもたらしたのと同様に、この物語も読者の心に「ギフト」として作用する。 オーケストラの中に身を置きながら「音楽とはなぜこんなにも美しいのだろう」と泣きたくなった瞬間のことを思い出した。音楽は時代も国境も越え、奏でる者、そして聴く者の心を掴む。音楽に触れることは、とても刹那的でありながら、同時に永遠性を獲得することでもあるのだ。 - 2025年12月30日
 プー横丁にたった家A.A.ミルン,石井桃子読み終わった感想再読はねっかえりのトラーが木から降りられなくなった話や、プーたちが橋の上から棒投げをして遊ぶ話、強風でフクロの家が吹き倒されてしまった話など、ひとつひとつのエピソードには確かに昔楽しく読んでいた記憶がある。 それなのに、なぜか最終話「クリストファー・ロビンとプーが、魔法の丘に出かけ、ふたりは、いまもそこにおります」に関してだけはすっぽりと記憶が抜け落ちており、こんな終わり方だったのかと衝撃を受けた。あるいは、幼少期の私には、まだこの最終話の切なさが理解できなかったのかもしれない。学校に通い始めたクリストファー・ロビンの世界から徐々にプーたちと遊ぶ時間が失われてゆくのは、とてもリアルな子どもの在り方だが、そこをふわりと魔法でくるんで描いているのが、作者A.A.ミルンの優しさなのかもしれないと思った。
プー横丁にたった家A.A.ミルン,石井桃子読み終わった感想再読はねっかえりのトラーが木から降りられなくなった話や、プーたちが橋の上から棒投げをして遊ぶ話、強風でフクロの家が吹き倒されてしまった話など、ひとつひとつのエピソードには確かに昔楽しく読んでいた記憶がある。 それなのに、なぜか最終話「クリストファー・ロビンとプーが、魔法の丘に出かけ、ふたりは、いまもそこにおります」に関してだけはすっぽりと記憶が抜け落ちており、こんな終わり方だったのかと衝撃を受けた。あるいは、幼少期の私には、まだこの最終話の切なさが理解できなかったのかもしれない。学校に通い始めたクリストファー・ロビンの世界から徐々にプーたちと遊ぶ時間が失われてゆくのは、とてもリアルな子どもの在り方だが、そこをふわりと魔法でくるんで描いているのが、作者A.A.ミルンの優しさなのかもしれないと思った。 - 2025年12月29日
 ドリトル先生アフリカゆきヒュー・ロフティング,井伏鱒二読み終わった感想再読ドリトル先生は純粋に生物の生態に関心があり、また、自分の家で暮らす動物たちのことを家族のように大切に思っていて、彼らの関係は対等である。動物たちはドリトル先生のことを深く尊敬しているが、決して一方的に庇護されているわけではなく、すぐれた医者であるものの生活力を欠いた先生のことを手助けして暮らしている。この絶妙なバランスこそが、本書を楽しく読める所以かもしれないと思った。 アヒルのダブダブ、犬のジップ、ブタのガブガブ、オウムのポリネシア、フクロのトートー、サルのチーチーをはじめとする動物たちは皆個性的で、彼らのことを好きにならずにはいられない。動物好きとおひとよしが高じて(そこもまた愛すべきところではある)すぐに生活苦に陥るドリトル先生だが、しっかり者のダブダブとポリネシアがついているおかげでハラハラしすぎずに見守ることができる。 病気のサルを治しにやってきたアフリカでジョリギンキの王様に追われたドリトル先生一行を、サルたちが橋を架けて助けたあと、チーチーが「えらい探検家や白いひげの博物学者が、何人も、ながい間、密林にかくれて、サルのこの芸当を見ようとしました。けれども、わたくしたちは、まだひとりの白人にも、これを見せたことがありません。有名なサルの橋をごらんになったのは、先生、あなたが最初です」と伝えたのにはぐっときた。動物たちは、ちゃんと真心を持った人間を見分けるのだ。
ドリトル先生アフリカゆきヒュー・ロフティング,井伏鱒二読み終わった感想再読ドリトル先生は純粋に生物の生態に関心があり、また、自分の家で暮らす動物たちのことを家族のように大切に思っていて、彼らの関係は対等である。動物たちはドリトル先生のことを深く尊敬しているが、決して一方的に庇護されているわけではなく、すぐれた医者であるものの生活力を欠いた先生のことを手助けして暮らしている。この絶妙なバランスこそが、本書を楽しく読める所以かもしれないと思った。 アヒルのダブダブ、犬のジップ、ブタのガブガブ、オウムのポリネシア、フクロのトートー、サルのチーチーをはじめとする動物たちは皆個性的で、彼らのことを好きにならずにはいられない。動物好きとおひとよしが高じて(そこもまた愛すべきところではある)すぐに生活苦に陥るドリトル先生だが、しっかり者のダブダブとポリネシアがついているおかげでハラハラしすぎずに見守ることができる。 病気のサルを治しにやってきたアフリカでジョリギンキの王様に追われたドリトル先生一行を、サルたちが橋を架けて助けたあと、チーチーが「えらい探検家や白いひげの博物学者が、何人も、ながい間、密林にかくれて、サルのこの芸当を見ようとしました。けれども、わたくしたちは、まだひとりの白人にも、これを見せたことがありません。有名なサルの橋をごらんになったのは、先生、あなたが最初です」と伝えたのにはぐっときた。動物たちは、ちゃんと真心を持った人間を見分けるのだ。 - 2025年12月28日
 虚弱に生きる絶対に終電を逃さない女読み終わった感想今、虚弱体質と向き合いながら生きる様を赤裸々に綴ったこのエッセイが広く読まれ、読者が自身の虚弱についてSNSやブログなどで発信するムーブメントが広がっていることに、とても勇気付けられている。現状の社会は健康で体力のあるひとに合わせて設計されているが、そうではないひともたくさんいるのだと周知されることによって、もっと誰もが生きやすい社会へと変わってゆく一端になってくれないだろうかと期待しているからだ。 著者の虚弱ぶりは読む前に想像していたのを遥かに上回っており、私のことを同列に並べて語るのは憚られる。それでも、「体力がないことは時間がないこと」という著者の言葉には深く共感してしまう。私が抱えている心身の不調の中でも、特に悩まされてきたのは入眠困難と過眠なので、本書のこれらについての記述には共感し通しだった。 著者が凄いのは、その時間がない中で健康になるための自炊や運動の時間を捻出していることだ。私は自身の虚弱についてほとんど諦めかけていたのだが、本書と出会ったことで、たとえ健康にはなれずとも、少しでも虚弱が軽減されるよう努めたいと思った。 また、著者は現行の社会保障が不十分であることを指摘している。著者のようなひとが生きやすくなるよう、公助がもっと充実することを切に願う。誰にでも健康を失う可能性はあるのだから、セーフティーネットがきちんと用意されていることが、誰にとっても安心して暮らせる社会に繋がると思うのだ。
虚弱に生きる絶対に終電を逃さない女読み終わった感想今、虚弱体質と向き合いながら生きる様を赤裸々に綴ったこのエッセイが広く読まれ、読者が自身の虚弱についてSNSやブログなどで発信するムーブメントが広がっていることに、とても勇気付けられている。現状の社会は健康で体力のあるひとに合わせて設計されているが、そうではないひともたくさんいるのだと周知されることによって、もっと誰もが生きやすい社会へと変わってゆく一端になってくれないだろうかと期待しているからだ。 著者の虚弱ぶりは読む前に想像していたのを遥かに上回っており、私のことを同列に並べて語るのは憚られる。それでも、「体力がないことは時間がないこと」という著者の言葉には深く共感してしまう。私が抱えている心身の不調の中でも、特に悩まされてきたのは入眠困難と過眠なので、本書のこれらについての記述には共感し通しだった。 著者が凄いのは、その時間がない中で健康になるための自炊や運動の時間を捻出していることだ。私は自身の虚弱についてほとんど諦めかけていたのだが、本書と出会ったことで、たとえ健康にはなれずとも、少しでも虚弱が軽減されるよう努めたいと思った。 また、著者は現行の社会保障が不十分であることを指摘している。著者のようなひとが生きやすくなるよう、公助がもっと充実することを切に願う。誰にでも健康を失う可能性はあるのだから、セーフティーネットがきちんと用意されていることが、誰にとっても安心して暮らせる社会に繋がると思うのだ。 - 2025年12月27日
 読み終わった感想『spring』の舞台裏や未来が綴られたスピンオフ短編集。前作と比べると、春を中心としたバレエダンサーたちの人間性によりスポットが当てられている。もちろん、バレエの描写も圧巻。 フランツの引退公演と春との別れを描いた短編「石の花」がとりわけ印象に残っている。生まれによって生き方を定められたフランツの背負う重荷、春との愛憎入り混じったバレエの神を奪い合う関係性と、終わりの見えている間柄であるという悲哀、そうしたものが「石の花」というプログラムにぎゅっと詰めこまれていた。 『spring』の「春の祭典」にも思ったが、恩田さんの、古典作品に春たちの物語を乗せてゆく力(とでも言えばよいのだろうか)は本当に凄い。ややもすれば単なる引用になりかねないが、本書においては古典と春たちの生き様がぴたりと調和し、いっそう響きを増している。春が振り付けた「桜の森の満開の下」も、坂口安吾の小説とラフマニノフの「鐘」を組み合わせてバレエにするなんて、いったいどうしたらひらめくのだろう、と圧倒される。 春たちがすごしたいくつもの季節——それはいずれも刹那的だからこそ美しい——を垣間見ることができて、よかった。
読み終わった感想『spring』の舞台裏や未来が綴られたスピンオフ短編集。前作と比べると、春を中心としたバレエダンサーたちの人間性によりスポットが当てられている。もちろん、バレエの描写も圧巻。 フランツの引退公演と春との別れを描いた短編「石の花」がとりわけ印象に残っている。生まれによって生き方を定められたフランツの背負う重荷、春との愛憎入り混じったバレエの神を奪い合う関係性と、終わりの見えている間柄であるという悲哀、そうしたものが「石の花」というプログラムにぎゅっと詰めこまれていた。 『spring』の「春の祭典」にも思ったが、恩田さんの、古典作品に春たちの物語を乗せてゆく力(とでも言えばよいのだろうか)は本当に凄い。ややもすれば単なる引用になりかねないが、本書においては古典と春たちの生き様がぴたりと調和し、いっそう響きを増している。春が振り付けた「桜の森の満開の下」も、坂口安吾の小説とラフマニノフの「鐘」を組み合わせてバレエにするなんて、いったいどうしたらひらめくのだろう、と圧倒される。 春たちがすごしたいくつもの季節——それはいずれも刹那的だからこそ美しい——を垣間見ることができて、よかった。 - 2025年12月26日
 spring恩田陸読み終わった感想再読スピンオフ『spring another season』が刊行されたのに合わせて再読。 私はかつて学生オーケストラに所属していたことがあるため、バレエという題材につい音楽という側面から注目してしまうのだが、恩田陸さんの文章には読んでいると本当に音が鳴り出すような凄味がある。どうして言葉を用いてこんなにも見事に音楽というものを表現できるのか、感嘆するばかりだ。この物語の世界に浸っているあいだ中、数々のバレエ音楽の美しい旋律が脳内で渦巻いていた。 また、七瀬が「この古典文学にこの音楽を合わせてバレエにしたらどうか」という妄想をひたすら羅列するくだりでは、いったいどうしたらこんなアイデアが浮かぶのだろうと、恩田さんの上辺だけでない教養に圧倒される。 本書のクライマックスである「春の祭典」も、あの不協和音が打ち鳴らされる中で生贄を捧げるというバレエに、日本の学校の窮屈さ・息苦しさ・異質な存在に対する排他性を投影するという発想が圧巻だ。初読時は無我夢中でひたすらページを捲っていたのだが、今回は春の踊りに涙ぐみそうになった。 本書のタイトル『spring』は、もちろん主人公である萬春の名前に由来するのだろうが、彼の創りあげる舞台を観て読者の心に幾多の感情が芽吹く様にも相応しいと思った。
spring恩田陸読み終わった感想再読スピンオフ『spring another season』が刊行されたのに合わせて再読。 私はかつて学生オーケストラに所属していたことがあるため、バレエという題材につい音楽という側面から注目してしまうのだが、恩田陸さんの文章には読んでいると本当に音が鳴り出すような凄味がある。どうして言葉を用いてこんなにも見事に音楽というものを表現できるのか、感嘆するばかりだ。この物語の世界に浸っているあいだ中、数々のバレエ音楽の美しい旋律が脳内で渦巻いていた。 また、七瀬が「この古典文学にこの音楽を合わせてバレエにしたらどうか」という妄想をひたすら羅列するくだりでは、いったいどうしたらこんなアイデアが浮かぶのだろうと、恩田さんの上辺だけでない教養に圧倒される。 本書のクライマックスである「春の祭典」も、あの不協和音が打ち鳴らされる中で生贄を捧げるというバレエに、日本の学校の窮屈さ・息苦しさ・異質な存在に対する排他性を投影するという発想が圧巻だ。初読時は無我夢中でひたすらページを捲っていたのだが、今回は春の踊りに涙ぐみそうになった。 本書のタイトル『spring』は、もちろん主人公である萬春の名前に由来するのだろうが、彼の創りあげる舞台を観て読者の心に幾多の感情が芽吹く様にも相応しいと思った。
読み込み中...