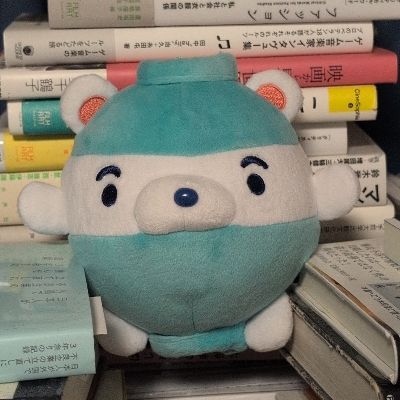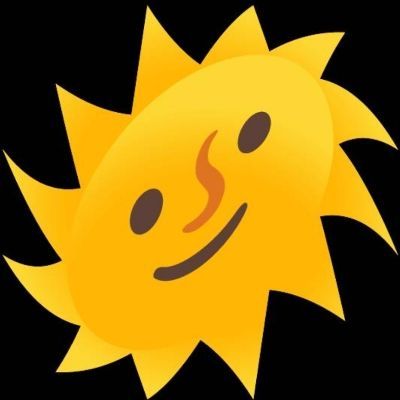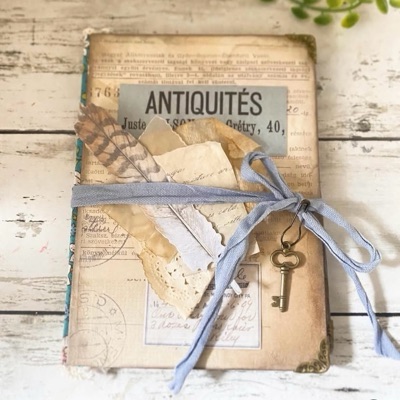君たちの記念碑はどこにある?

47件の記録
 みゆ@ant12bb212026年1月18日読んでる@ 自宅第6章音楽という記憶装置 ローレンス・スコット『ナイト・カリプソ』はハンセン病患者隔離施設のある島を舞台にしてあるらしい。読んでみたいと思ったら、日本語訳はないみたい。 うーん、気になる。
みゆ@ant12bb212026年1月18日読んでる@ 自宅第6章音楽という記憶装置 ローレンス・スコット『ナイト・カリプソ』はハンセン病患者隔離施設のある島を舞台にしてあるらしい。読んでみたいと思ったら、日本語訳はないみたい。 うーん、気になる。
 みゆ@ant12bb212026年1月18日読み終わった@ 自宅全部を理解して読めたとは正直言えないけど、自分の世界がまた少し広がった気がする。 第9章 革命は男の顔をしているか――カリブ海の女性の記憶 女性についても触れられていたのが良かった。
みゆ@ant12bb212026年1月18日読み終わった@ 自宅全部を理解して読めたとは正直言えないけど、自分の世界がまた少し広がった気がする。 第9章 革命は男の顔をしているか――カリブ海の女性の記憶 女性についても触れられていたのが良かった。

 むぐらばな@mugurabana-252025年7月31日読み始めた読んでる@ 電車「私が諸島である」につづく、とても興味深い本。わたしは、国に属することにより利益を得、植民地支配に手を貸してしまっている自覚はあるものの、先住民族の方々が「もともと」持っている物語を掬い取ることができないでいる。……しかし、キマラーによれば、盗用や模倣ではなく、自分たち自身(共同体)がみずから「作り出す」関係性(物語)こそが自然との契約たりうる、という。 だから、だろうか? 植民支配を受けながら自分たちの「ことば」を(物語を)みつけ、先に編みはじめていたカリブ海の人びとに、わたしは学びたい。 ……手前勝手なのはわかっているが。
むぐらばな@mugurabana-252025年7月31日読み始めた読んでる@ 電車「私が諸島である」につづく、とても興味深い本。わたしは、国に属することにより利益を得、植民地支配に手を貸してしまっている自覚はあるものの、先住民族の方々が「もともと」持っている物語を掬い取ることができないでいる。……しかし、キマラーによれば、盗用や模倣ではなく、自分たち自身(共同体)がみずから「作り出す」関係性(物語)こそが自然との契約たりうる、という。 だから、だろうか? 植民支配を受けながら自分たちの「ことば」を(物語を)みつけ、先に編みはじめていたカリブ海の人びとに、わたしは学びたい。 ……手前勝手なのはわかっているが。

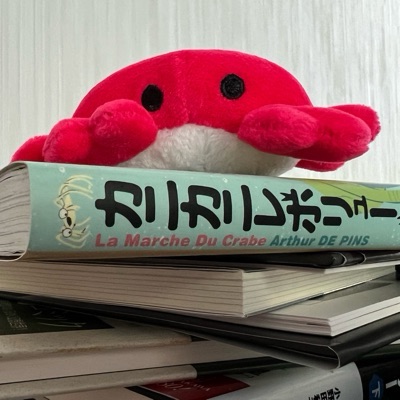
 なかちきか@susie_may41412025年7月26日気になる買った@ 丸善 メトロ・エム後楽園店本屋ルヌガンガさん推薦 『私が諸島である』から読みたかったけれど、立ち寄った書店にはこちらのみ在庫。 この本も、フランツ・ファノンに呼ばれてたどり着いた一冊なんだな、と、第1章でいきなり『地に呪わせたる者』に再会して気づく。
なかちきか@susie_may41412025年7月26日気になる買った@ 丸善 メトロ・エム後楽園店本屋ルヌガンガさん推薦 『私が諸島である』から読みたかったけれど、立ち寄った書店にはこちらのみ在庫。 この本も、フランツ・ファノンに呼ばれてたどり着いた一冊なんだな、と、第1章でいきなり『地に呪わせたる者』に再会して気づく。
 つたゐ@tutai_k2025年7月19日読み終わった昨日病院の待ち時間などで読了。 中村達さんの前著『私が諸島である』を読んで、すごくよくて、二冊目の本が出るのを楽しみに待っていたので、一章一章大切に読んだ。 文字/書物として残っていく歴史、その「歴史の正統性を定める存在」について、深く考えることになったし、特に興味深かったのは「フラクタル・ファミリーズ」の章。「家族」という結束を「一単位」としてある程度要素が決まっている状態で算出される価値観がいまの私が生活している環境では隆盛を誇っているが、それとは全く異なる「フラクタルな関係性」という「家族」をカリブ海の人々が名乗る、というところに胸が熱くなった。 『私が諸島である』でもっと読みたい!と思っていた女性たちのこととかも、丁寧に賞立てて書かれていて嬉しかった! 中村さんの研究をこれからも追い続けていきたいなー。
つたゐ@tutai_k2025年7月19日読み終わった昨日病院の待ち時間などで読了。 中村達さんの前著『私が諸島である』を読んで、すごくよくて、二冊目の本が出るのを楽しみに待っていたので、一章一章大切に読んだ。 文字/書物として残っていく歴史、その「歴史の正統性を定める存在」について、深く考えることになったし、特に興味深かったのは「フラクタル・ファミリーズ」の章。「家族」という結束を「一単位」としてある程度要素が決まっている状態で算出される価値観がいまの私が生活している環境では隆盛を誇っているが、それとは全く異なる「フラクタルな関係性」という「家族」をカリブ海の人々が名乗る、というところに胸が熱くなった。 『私が諸島である』でもっと読みたい!と思っていた女性たちのこととかも、丁寧に賞立てて書かれていて嬉しかった! 中村さんの研究をこれからも追い続けていきたいなー。



 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年7月10日読み終わった本書において書かれていることは即効性のあるものではなく、明確に遅効性を特徴とする。しかし、記憶や歴史が長い時間をかけて積み重なり強固な存在になるのと同様に、長い時間をかけて実践していくもの、その結果としてあらわれ出てくるのをじっくりと待つものは、ちょっとやそっとで打ち倒され存在そのものをなかったことにされてしまうような脆弱なものにはならない。何度でも想像/創造され、参照されるものとしての記憶や歴史を、いかにして残していくか。絶望を瞬間的な点として捉えることができるのならば、過去から未来へと延々と続く線として(断続的な点の集まりとして)希望を見いだすことができるかもしれない。長生きしたいね。肉体としても、記憶としても。中村さんの言葉を借りるなら、「地憶(geomemory)」になるだろうか。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年7月10日読み終わった本書において書かれていることは即効性のあるものではなく、明確に遅効性を特徴とする。しかし、記憶や歴史が長い時間をかけて積み重なり強固な存在になるのと同様に、長い時間をかけて実践していくもの、その結果としてあらわれ出てくるのをじっくりと待つものは、ちょっとやそっとで打ち倒され存在そのものをなかったことにされてしまうような脆弱なものにはならない。何度でも想像/創造され、参照されるものとしての記憶や歴史を、いかにして残していくか。絶望を瞬間的な点として捉えることができるのならば、過去から未来へと延々と続く線として(断続的な点の集まりとして)希望を見いだすことができるかもしれない。長生きしたいね。肉体としても、記憶としても。中村さんの言葉を借りるなら、「地憶(geomemory)」になるだろうか。









 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年7月9日まだ読んでる歴史が「実際にあったこと」として、つまり史実として正しいことのみで構成されてしまうのではなく、そのような文献的なもののみならず人々の記憶のなかにのみ残っているようなものによっても構成されるべきなのだ、というカリブ海思想は、不思議なことに現在進行形で脅威となっている排外主義への抵抗手段にもなりうるのかもしれない。 記憶の継承こそが歴史の要点なのだと語る西洋の学者は、しかしその「家族」を核家族だったり血の繋がりのあるものとしてしか想定しない。一方で、奴隷制などによって分断されたカリブ海の人々の「血統」は、伝統的な家族観の枠組みを超えて存在している。血が繋がっているかどうか、同一民族であるかどうか、そんなことは関係なく紡がれていく生活、生活の積み重ねである歴史は、「単一」であることに縋った関係性よりも強靭なものとなる。 難しいのは、単一的で伝統的な家族観だったりを求めている者らは、実際に強靭である関係性を求めているわけではなく、単にそのイデオロギー的なものに酔いしれているだけなのだろう、ということだったりする。だから「こっちのほうがつよいよ!」と言ってもなびかない。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年7月9日まだ読んでる歴史が「実際にあったこと」として、つまり史実として正しいことのみで構成されてしまうのではなく、そのような文献的なもののみならず人々の記憶のなかにのみ残っているようなものによっても構成されるべきなのだ、というカリブ海思想は、不思議なことに現在進行形で脅威となっている排外主義への抵抗手段にもなりうるのかもしれない。 記憶の継承こそが歴史の要点なのだと語る西洋の学者は、しかしその「家族」を核家族だったり血の繋がりのあるものとしてしか想定しない。一方で、奴隷制などによって分断されたカリブ海の人々の「血統」は、伝統的な家族観の枠組みを超えて存在している。血が繋がっているかどうか、同一民族であるかどうか、そんなことは関係なく紡がれていく生活、生活の積み重ねである歴史は、「単一」であることに縋った関係性よりも強靭なものとなる。 難しいのは、単一的で伝統的な家族観だったりを求めている者らは、実際に強靭である関係性を求めているわけではなく、単にそのイデオロギー的なものに酔いしれているだけなのだろう、ということだったりする。だから「こっちのほうがつよいよ!」と言ってもなびかない。









 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月27日まだ読んでる生まれるということは何かを新しく始めるということではなく、他者の苦しみを分かち合うということであり、つまり深淵に呑み込まれた人々の記憶を共有するということだ。だからこそ〈関係〉――分かち合いのエネルギー――は、彼らの記憶を現在の私たちが甦らせ、彼らと共にあることを、可能にするのである。(p.78) 逆に考えると、他者の苦しみを分かち合うという営みから(無意識に)逃れようとするのもまた人間であり、マイノリティやあれやこれやの苦境に押し込められている者たちの声を聴こうとしない大多数の人間=マジョリティがいることもまた、納得できる。できてしまう。苦しいのは嫌だ。それは端的に言って重荷だ。背負いたくないのは当然とも言える。ではどうすべきか。重荷ではなく、たのしいものであると感じてもらうほかない。じゃあどうすれば、というのはわからない。少なくとも、万能解はない。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月27日まだ読んでる生まれるということは何かを新しく始めるということではなく、他者の苦しみを分かち合うということであり、つまり深淵に呑み込まれた人々の記憶を共有するということだ。だからこそ〈関係〉――分かち合いのエネルギー――は、彼らの記憶を現在の私たちが甦らせ、彼らと共にあることを、可能にするのである。(p.78) 逆に考えると、他者の苦しみを分かち合うという営みから(無意識に)逃れようとするのもまた人間であり、マイノリティやあれやこれやの苦境に押し込められている者たちの声を聴こうとしない大多数の人間=マジョリティがいることもまた、納得できる。できてしまう。苦しいのは嫌だ。それは端的に言って重荷だ。背負いたくないのは当然とも言える。ではどうすべきか。重荷ではなく、たのしいものであると感じてもらうほかない。じゃあどうすれば、というのはわからない。少なくとも、万能解はない。









 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月25日読み始めた前著『私が諸島である』の感覚を忘れないうちに読み始める。やらねばならない仕事を放り出して読んでしまうほどおもしろいから困る。とりあえず1章まででストップ。ぜんぶ読んでから仕事したらいいじゃん、どうせ気になって集中できないんだし、と何者かが囁いている。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月25日読み始めた前著『私が諸島である』の感覚を忘れないうちに読み始める。やらねばならない仕事を放り出して読んでしまうほどおもしろいから困る。とりあえず1章まででストップ。ぜんぶ読んでから仕事したらいいじゃん、どうせ気になって集中できないんだし、と何者かが囁いている。