

かのうさん
@readskanokanon
かのうさんです。
1ヶ月に10冊くらいの本を読んだり読まなかったり。
色々な本を読みます。
- 2026年2月24日
 観る技術、読む技術、書く技術。北村匡平読み終わった読む技術、書く技術は教えてくれる本はたくさんあったけど、それに加え、観る技術まで教えてくれる本はなかったな。 P82 現代社会はあらゆることが「情報」と化して、必要か不必要か、役に立つか立たないか、という物差しで捉えがち 私たちの内部にある感性を育てるためには深読することが大切。 深読と同じように映像も深く観る。 そのための方法が書いてありました。 その観る技術、読む技術を持って書いてみようかなと思います。 巻末付録に観る技術を養う映画リストを載せていただいているので、これを参考にまずは映画を観てみてメタ視点を鍛えられたらと思います。
観る技術、読む技術、書く技術。北村匡平読み終わった読む技術、書く技術は教えてくれる本はたくさんあったけど、それに加え、観る技術まで教えてくれる本はなかったな。 P82 現代社会はあらゆることが「情報」と化して、必要か不必要か、役に立つか立たないか、という物差しで捉えがち 私たちの内部にある感性を育てるためには深読することが大切。 深読と同じように映像も深く観る。 そのための方法が書いてありました。 その観る技術、読む技術を持って書いてみようかなと思います。 巻末付録に観る技術を養う映画リストを載せていただいているので、これを参考にまずは映画を観てみてメタ視点を鍛えられたらと思います。 - 2026年2月23日
 ふつうの人が小説家として生活していくには津村記久子読み終わった誰かの書いたものを読む時、著者は一体どんな人なのか知った上で、興味深く著書を読むことがある。 津村記久子さん。 名前は存じていますが、どんな文章を書く人なのか全く存じ上げませんでした。 (申し訳ないです。これから読みます) ただ、夏葉社の島田さんがロングインタビューされているこの作家さんは、島田さんが好きな人なんだろうなという意識があったので、島田さんの考え方が好きな私は読んでみることにしました。 うわぁ。好き。津村さんの考え方好き! って、思いました。 年齢も私よりちょっと上くらいの津村さんの経験されたこと、私にも覚えがあって境遇的にもどこか似ている。 だから「ふつうの人」なのかもしれないけれど、鋭い観察眼と物事への深堀力(?)が徹底されていて、そこが凄いなと。 いちいち鋭いこと仰っていてドキドキしながら読みました。 特にP173の「自分の人生をコントロールすることに意識的だった人ってのは、いま大丈夫」 あとP179の最後のあたり。 本当にどこでこうなったんだろうな。 そして、今10代の娘ともうすぐ10代の息子を持つ母として、彼女らが夢中になれる何かを見つけられたらいいなと思うと共に、それを邪魔しない大人でありたいなと思うのでした。 あと、これ。環境はやっぱり大事。 本、読もう。家族で。そのためには、私がSNSばかりやらないのが一番大切だと思う。
ふつうの人が小説家として生活していくには津村記久子読み終わった誰かの書いたものを読む時、著者は一体どんな人なのか知った上で、興味深く著書を読むことがある。 津村記久子さん。 名前は存じていますが、どんな文章を書く人なのか全く存じ上げませんでした。 (申し訳ないです。これから読みます) ただ、夏葉社の島田さんがロングインタビューされているこの作家さんは、島田さんが好きな人なんだろうなという意識があったので、島田さんの考え方が好きな私は読んでみることにしました。 うわぁ。好き。津村さんの考え方好き! って、思いました。 年齢も私よりちょっと上くらいの津村さんの経験されたこと、私にも覚えがあって境遇的にもどこか似ている。 だから「ふつうの人」なのかもしれないけれど、鋭い観察眼と物事への深堀力(?)が徹底されていて、そこが凄いなと。 いちいち鋭いこと仰っていてドキドキしながら読みました。 特にP173の「自分の人生をコントロールすることに意識的だった人ってのは、いま大丈夫」 あとP179の最後のあたり。 本当にどこでこうなったんだろうな。 そして、今10代の娘ともうすぐ10代の息子を持つ母として、彼女らが夢中になれる何かを見つけられたらいいなと思うと共に、それを邪魔しない大人でありたいなと思うのでした。 あと、これ。環境はやっぱり大事。 本、読もう。家族で。そのためには、私がSNSばかりやらないのが一番大切だと思う。 - 2026年2月21日
 告白町田康読み終わったなんていう、、、。 はぁー。惨い。 河内十人斬りの背景があまりに悲しい。 何とかならなかったのか。 熊太郎がやられたことを考えると、最早やむなしと思ってしまう自分もいる。 その人が犯罪者になるのは環境のせい、、とは一概には言えないが、それでもいくらだって熊太郎に優しくできたはずではなかったか。 どうしてこうも、皆が皆自分の利益のことしか考えないんだろう。悲しくなる。 ちょっと、自分も熊太郎が恨んだ人間のようになっていないか反省しながら読んだ。 小説の中の一般の人たち(熊太郎に関係ない人たち)も私のように熊太郎を応援する人がたくさんいたようである。 最後の方に 今の世であれば熊太郎がやったことは人々の最も憎むべきところであったろうと書いてある。 だけど、それは食う心配がなくなったからで、消して慈悲深くなったわけではない。 ただ、「人間というものはまず自分の生存、それを何よりも優先し、それが満たされて初めて他のことを思いやることができるのである。」P615L7 と書いてある。 人を思いやれるというのは、自分が満たされて初めて湧き上がる感情なのだ。 今の世の中、どうなのかな? 自分は他人のことを思いやれているのかどうか、自問自答したい。
告白町田康読み終わったなんていう、、、。 はぁー。惨い。 河内十人斬りの背景があまりに悲しい。 何とかならなかったのか。 熊太郎がやられたことを考えると、最早やむなしと思ってしまう自分もいる。 その人が犯罪者になるのは環境のせい、、とは一概には言えないが、それでもいくらだって熊太郎に優しくできたはずではなかったか。 どうしてこうも、皆が皆自分の利益のことしか考えないんだろう。悲しくなる。 ちょっと、自分も熊太郎が恨んだ人間のようになっていないか反省しながら読んだ。 小説の中の一般の人たち(熊太郎に関係ない人たち)も私のように熊太郎を応援する人がたくさんいたようである。 最後の方に 今の世であれば熊太郎がやったことは人々の最も憎むべきところであったろうと書いてある。 だけど、それは食う心配がなくなったからで、消して慈悲深くなったわけではない。 ただ、「人間というものはまず自分の生存、それを何よりも優先し、それが満たされて初めて他のことを思いやることができるのである。」P615L7 と書いてある。 人を思いやれるというのは、自分が満たされて初めて湧き上がる感情なのだ。 今の世の中、どうなのかな? 自分は他人のことを思いやれているのかどうか、自問自答したい。 - 2026年2月14日
 文字禍しきみ,中島敦読み終わった難しい。 文字を読みすぎると、その文字に囚われて物事の本質を見失うという内容の話に思えたんだけど、熟読しないとわからない。 これは、中島敦は何を言いたかったのかな? 頭が良すぎてよくわからない。 山月記といい、この話といい(ってか中島敦はこの2冊しか知らないが)、いわゆる高学歴で頭ばっかりで動いている人の事をバカにしていたのかな。中島敦は。 現在、本を読む人は少なくなってきた感じがするけれど、皆、SNSが好きで文字ばかり追いかけているイメージがある。 文章は読まないけど、文字読んでるよーって。 そうなると、人間は崩壊する? んんー。現在のこの危機を予言した文章なのか? よくわかりません。
文字禍しきみ,中島敦読み終わった難しい。 文字を読みすぎると、その文字に囚われて物事の本質を見失うという内容の話に思えたんだけど、熟読しないとわからない。 これは、中島敦は何を言いたかったのかな? 頭が良すぎてよくわからない。 山月記といい、この話といい(ってか中島敦はこの2冊しか知らないが)、いわゆる高学歴で頭ばっかりで動いている人の事をバカにしていたのかな。中島敦は。 現在、本を読む人は少なくなってきた感じがするけれど、皆、SNSが好きで文字ばかり追いかけているイメージがある。 文章は読まないけど、文字読んでるよーって。 そうなると、人間は崩壊する? んんー。現在のこの危機を予言した文章なのか? よくわかりません。 - 2026年2月14日
 山月記中島敦,ねこ助読み終わった乙女の本棚と書いてある通り、乙女が本棚に忍ばせるシリーズとしていいなと思う。 絵が素敵だ。 この山月記。 全部日本語だった。 所々、漢文が潜んでいるかと思った。 特に李徴の内面を書いたところなど。 何度読んでも、李徴が自分になるやもしれぬと思うし、高校の時もそう思ったな。 しっかし、中島敦、すごい文を書く。
山月記中島敦,ねこ助読み終わった乙女の本棚と書いてある通り、乙女が本棚に忍ばせるシリーズとしていいなと思う。 絵が素敵だ。 この山月記。 全部日本語だった。 所々、漢文が潜んでいるかと思った。 特に李徴の内面を書いたところなど。 何度読んでも、李徴が自分になるやもしれぬと思うし、高校の時もそう思ったな。 しっかし、中島敦、すごい文を書く。 - 2026年2月12日
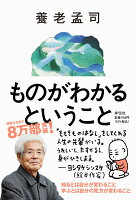 ものがわかるということ養老孟司読み終わった個性個性って言うけれど、心に個性があると思ってるから労力を使うはめになるっていうのは、確かになぁと思った。 個性ってのはそんな一筋縄じゃわからないよということ。師匠と何十年と同じことをやってようやく見えてくるということ。 身体表現の完成した形、つまり型を極めた先に個性がある。 個性とは文武両道の武のこと。 なるほど。 つまり、いかに私が今頭だけで生きているのかということがわかる。
ものがわかるということ養老孟司読み終わった個性個性って言うけれど、心に個性があると思ってるから労力を使うはめになるっていうのは、確かになぁと思った。 個性ってのはそんな一筋縄じゃわからないよということ。師匠と何十年と同じことをやってようやく見えてくるということ。 身体表現の完成した形、つまり型を極めた先に個性がある。 個性とは文武両道の武のこと。 なるほど。 つまり、いかに私が今頭だけで生きているのかということがわかる。 - 2026年2月11日
 草の花福永武彦読み終わった『草の花 (新潮文庫)』福永 武彦 池澤夏樹さんのお父上だと知って、読んでみたいと思った。 なんと、儚く綺麗で内省的な愛の物語だろう。 ここまで強烈なのに、こんなに清潔な愛とは。 文庫版の月のように美しい小説だった。 藤木と汐見との友情は、不思議なものだった。 こんなにも恋愛感情にも似た友情というものは実際あるものなのか。 そして、やっぱり汐見は死にたかったのかが最大の疑問。 潔癖。潔癖すぎて苦しい。ああ、もっと汚れててもいいのにと思う。汐見はさぞかし生きにくかっただろう。 汐見は物凄く博識だったんだろう。 だからこそ、色んなことに矛盾を感じてジタバタしていたんだろうなと思う。 うー。ジワジワくるお話だったなと思う。 同時に福永武彦の作品をもっと読みたくなった。 同時期の三島由紀夫の文章もそれは綺麗で、読み応えがあるが、あちらは明るいのに対して、こちらは陰鬱な美しさがあって、私はこちらの方が趣味に合った。
草の花福永武彦読み終わった『草の花 (新潮文庫)』福永 武彦 池澤夏樹さんのお父上だと知って、読んでみたいと思った。 なんと、儚く綺麗で内省的な愛の物語だろう。 ここまで強烈なのに、こんなに清潔な愛とは。 文庫版の月のように美しい小説だった。 藤木と汐見との友情は、不思議なものだった。 こんなにも恋愛感情にも似た友情というものは実際あるものなのか。 そして、やっぱり汐見は死にたかったのかが最大の疑問。 潔癖。潔癖すぎて苦しい。ああ、もっと汚れててもいいのにと思う。汐見はさぞかし生きにくかっただろう。 汐見は物凄く博識だったんだろう。 だからこそ、色んなことに矛盾を感じてジタバタしていたんだろうなと思う。 うー。ジワジワくるお話だったなと思う。 同時に福永武彦の作品をもっと読みたくなった。 同時期の三島由紀夫の文章もそれは綺麗で、読み応えがあるが、あちらは明るいのに対して、こちらは陰鬱な美しさがあって、私はこちらの方が趣味に合った。 - 2026年2月8日
 1945年に生まれて尾崎真理子,池澤夏樹読み終わったこの間の高橋源一郎さんの飛ぶ教室(ラジオ)でゲストだった池澤夏樹さん。 実はあまり存じ上げず。 無教養で申し訳ないです。 ただ、ラジオからの話し方で私、絶対この人好きだ!から手に取ってみた本。 読んで良かった。 やはり、生き方がかっこいい。 いちいち言葉が深い。 他の本も読んでみたいと思う。 特に今日、この選挙の時期に絶対読んで自分なりに色々と考えることができたと思う。 日本について。世界について。 池澤さんの周りの方に好きな作家さんが多いのに、なぜ今頃知ったんだろう。 本当に不思議。 この世をより良く生きるために、考えながら池澤夏樹さんの本を一冊ずつ読んでみようと思う。 特に最後の方で、今のリベラルは政治に無関心だって言葉が非常に痛かった。 文学全集にも興味ある。
1945年に生まれて尾崎真理子,池澤夏樹読み終わったこの間の高橋源一郎さんの飛ぶ教室(ラジオ)でゲストだった池澤夏樹さん。 実はあまり存じ上げず。 無教養で申し訳ないです。 ただ、ラジオからの話し方で私、絶対この人好きだ!から手に取ってみた本。 読んで良かった。 やはり、生き方がかっこいい。 いちいち言葉が深い。 他の本も読んでみたいと思う。 特に今日、この選挙の時期に絶対読んで自分なりに色々と考えることができたと思う。 日本について。世界について。 池澤さんの周りの方に好きな作家さんが多いのに、なぜ今頃知ったんだろう。 本当に不思議。 この世をより良く生きるために、考えながら池澤夏樹さんの本を一冊ずつ読んでみようと思う。 特に最後の方で、今のリベラルは政治に無関心だって言葉が非常に痛かった。 文学全集にも興味ある。 - 2026年2月8日
 1945年に生まれて尾崎真理子,池澤夏樹読んでる
1945年に生まれて尾崎真理子,池澤夏樹読んでる - 2026年2月6日
- 2026年2月6日
- 2026年2月3日
 ラウリ・クースクを探して宮内悠介読み終わったソビエト連邦の崩壊の時代、エストニアに住んでいたラウリという少年とその友人たちの物語。 ラウリという人物が実際にいたような。 まさか、これがフィクションなんて。 ソビエトの話。すごく小さい時に毎日テレビに出てきたゴルバチョフとかエリツィンとかのその辺りの話。 普通の人間の普通の人生。 だけれども、皆それぞれ経験しているし、何かを感じ、何かを持っている。 あえて、そこは言わず平気なフリして生きていて、そこに誤解もあるのかもしれないけれど、ただ淡々と生きている。 あなたはあなただよ 立場とか、考え方だとか色々あるかもしれないけれど、そこを込みでどんな人間であれ、あなたは大切だよ。 そう言われているような素敵な話だった。 昨日の正義は今日の敵? だったかな? そんな言葉が何度も出てきた。 それと、やはりその人の表面的な見えてるだけのことでその人を判断してはいけなのではないか。 その人の中核のその人本来のものは変わらずあり続けるんだから、立場がどうだとか、〇〇という考え方を持っている、またはそうなったからと言って、攻撃したり、悪く思ったりするほど浅いことはないのかもしれない。 中高生に読んでもらいたいな。
ラウリ・クースクを探して宮内悠介読み終わったソビエト連邦の崩壊の時代、エストニアに住んでいたラウリという少年とその友人たちの物語。 ラウリという人物が実際にいたような。 まさか、これがフィクションなんて。 ソビエトの話。すごく小さい時に毎日テレビに出てきたゴルバチョフとかエリツィンとかのその辺りの話。 普通の人間の普通の人生。 だけれども、皆それぞれ経験しているし、何かを感じ、何かを持っている。 あえて、そこは言わず平気なフリして生きていて、そこに誤解もあるのかもしれないけれど、ただ淡々と生きている。 あなたはあなただよ 立場とか、考え方だとか色々あるかもしれないけれど、そこを込みでどんな人間であれ、あなたは大切だよ。 そう言われているような素敵な話だった。 昨日の正義は今日の敵? だったかな? そんな言葉が何度も出てきた。 それと、やはりその人の表面的な見えてるだけのことでその人を判断してはいけなのではないか。 その人の中核のその人本来のものは変わらずあり続けるんだから、立場がどうだとか、〇〇という考え方を持っている、またはそうなったからと言って、攻撃したり、悪く思ったりするほど浅いことはないのかもしれない。 中高生に読んでもらいたいな。 - 2026年2月1日
 塩一トンの読書須賀敦子読み終わった須賀敦子の読書記録。 静かで深い文章 本についての情報に接する機会はあきれるほどめぐまれていて、私たちはいつの間にかその本のことはもう既に知っていると思い込み、その本を「じっさいに読んだ」経験とすり替えて、知識を手っ取り早く入手したことにして、誤魔化していないか? というような事が序盤書いてあってハッとした。 1トンの塩の例えは、姑さんのその人を知るには共に1トンの塩を舐めなければわからないから来ているらしいが、何とも今の世の中、暮らし方に通じる耳の痛い話だ。
塩一トンの読書須賀敦子読み終わった須賀敦子の読書記録。 静かで深い文章 本についての情報に接する機会はあきれるほどめぐまれていて、私たちはいつの間にかその本のことはもう既に知っていると思い込み、その本を「じっさいに読んだ」経験とすり替えて、知識を手っ取り早く入手したことにして、誤魔化していないか? というような事が序盤書いてあってハッとした。 1トンの塩の例えは、姑さんのその人を知るには共に1トンの塩を舐めなければわからないから来ているらしいが、何とも今の世の中、暮らし方に通じる耳の痛い話だ。 - 2026年1月29日
 ラウリ・クースクを探して宮内悠介読んでる
ラウリ・クースクを探して宮内悠介読んでる - 2026年1月28日
 観る技術、読む技術、書く技術。北村匡平気になる
観る技術、読む技術、書く技術。北村匡平気になる - 2026年1月28日
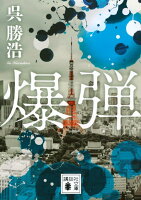 爆弾呉勝浩読み終わった『爆弾』呉 勝浩 映画の予告のスズキタゴサク=佐藤二朗さんだけ見て、映画はいまだ見られず、原作を先に読んだ。 スズキタゴサク、猟奇的な爆弾魔、得体の知れない気持ち悪さがある。だが、どこか憎めない哀愁のようなものを感じる。のは、先に映画予告の佐藤二朗さんの演技を見ていたからか? 全て読んでみて、1度や2度の失敗でその人を判断してしまう、現代社会の闇というか、弱さを感じた。 類家の天才的な取調べが冴え渡ってかっこよかった。 けれど、これから先応援したくなるのは等々力かな。 自分の中の闇。誰もが持っているものだろうと思う。 大切なのはそれを意識しながら、それでも誠実にこの世を生きていくということか。 「これはこうだ」「これをこうする」ってルールを自分の中で決めないと、きっとこの世は脆いんだろうという怖さを感じた本だった。
爆弾呉勝浩読み終わった『爆弾』呉 勝浩 映画の予告のスズキタゴサク=佐藤二朗さんだけ見て、映画はいまだ見られず、原作を先に読んだ。 スズキタゴサク、猟奇的な爆弾魔、得体の知れない気持ち悪さがある。だが、どこか憎めない哀愁のようなものを感じる。のは、先に映画予告の佐藤二朗さんの演技を見ていたからか? 全て読んでみて、1度や2度の失敗でその人を判断してしまう、現代社会の闇というか、弱さを感じた。 類家の天才的な取調べが冴え渡ってかっこよかった。 けれど、これから先応援したくなるのは等々力かな。 自分の中の闇。誰もが持っているものだろうと思う。 大切なのはそれを意識しながら、それでも誠実にこの世を生きていくということか。 「これはこうだ」「これをこうする」ってルールを自分の中で決めないと、きっとこの世は脆いんだろうという怖さを感じた本だった。 - 2026年1月19日
 批判的日常美学について難波優輝気になる
批判的日常美学について難波優輝気になる - 2026年1月19日
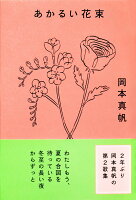 あかるい花束岡本真帆読み終わった生活の中にある別れやちょっとした痛みも含め、それらをすくい上げながら丁寧に明るく放つ、そんな短歌集。 266首。 初読みだけど、すごく好きだな、この方の歌。 川と山の歌が好き。
あかるい花束岡本真帆読み終わった生活の中にある別れやちょっとした痛みも含め、それらをすくい上げながら丁寧に明るく放つ、そんな短歌集。 266首。 初読みだけど、すごく好きだな、この方の歌。 川と山の歌が好き。 - 2026年1月17日
- 2026年1月16日
 本が読めない33歳が国語の教科書を読むかまど,みくのしん読み終わった『本が読めない33歳が国語の教科書を読む~やまなし・少年の日の思い出・山月記・枕草子』かまど,みくのしん あー、今回すごく面白かった。 みくのしんさんの感性、特に自然を感じる感覚ってのはものすごいものがある。 この人、自然と共に生きた人なんだろうな。 と思ってみたら、東京出身?自然経験が沢山あった人なんだろうか? 私はかろうじてみくのしんさんの感覚がわかるんだが、私が「かろうじて」ということは果たして今の子たちは彼のような感覚がわかるのか?と思った。 そういう経験をさせてあげられてるのか?と。 まだまだ足りないと思う。 生きていくためにはみくのしんさんのようなこういう感覚が1番大切だと思うのよ。 やっぱり、私も人間的な感性を取り戻すために子どもたちと一緒に自然的な感性を大切にする行動したいわ。 山月記、少年の日の思い出、枕草子は学校でやったな。 やまなしは記憶にない。 山月記は鮮明に覚えている。 私もトラかもしれないと思った記憶が。 少年の日の思い出は、エーミールにものすごい同情した記憶が。 枕草子は先生の書いた板書きがみくのしんさんの書いたそれと同じで、この3つを誰に教わったか先生の記憶も蘇った。 国語好きになるかならないかって、本当に先生次第だな。 こんなこと言っちゃあ怒られそうだけど、現文の授業、超つまんなかったよ、あの生徒のことを小馬鹿にする先生のせいで。 山月記をその先生が朗々と読んでいたの思い出して、この人は李徴のことを馬鹿にするタイプの人間だろうなって思ったのを思い出した。 すみません。今では思い出してもそこまで悪い先生とは思わない。 親友が進路のことで、けちょんけちょんに言われたので相当腹たっていました。 皆が皆、生徒の感性を認めてくれるかまどさんのような先生だったらいいね。 学校の授業嫌いな子が少なくなると思う。
本が読めない33歳が国語の教科書を読むかまど,みくのしん読み終わった『本が読めない33歳が国語の教科書を読む~やまなし・少年の日の思い出・山月記・枕草子』かまど,みくのしん あー、今回すごく面白かった。 みくのしんさんの感性、特に自然を感じる感覚ってのはものすごいものがある。 この人、自然と共に生きた人なんだろうな。 と思ってみたら、東京出身?自然経験が沢山あった人なんだろうか? 私はかろうじてみくのしんさんの感覚がわかるんだが、私が「かろうじて」ということは果たして今の子たちは彼のような感覚がわかるのか?と思った。 そういう経験をさせてあげられてるのか?と。 まだまだ足りないと思う。 生きていくためにはみくのしんさんのようなこういう感覚が1番大切だと思うのよ。 やっぱり、私も人間的な感性を取り戻すために子どもたちと一緒に自然的な感性を大切にする行動したいわ。 山月記、少年の日の思い出、枕草子は学校でやったな。 やまなしは記憶にない。 山月記は鮮明に覚えている。 私もトラかもしれないと思った記憶が。 少年の日の思い出は、エーミールにものすごい同情した記憶が。 枕草子は先生の書いた板書きがみくのしんさんの書いたそれと同じで、この3つを誰に教わったか先生の記憶も蘇った。 国語好きになるかならないかって、本当に先生次第だな。 こんなこと言っちゃあ怒られそうだけど、現文の授業、超つまんなかったよ、あの生徒のことを小馬鹿にする先生のせいで。 山月記をその先生が朗々と読んでいたの思い出して、この人は李徴のことを馬鹿にするタイプの人間だろうなって思ったのを思い出した。 すみません。今では思い出してもそこまで悪い先生とは思わない。 親友が進路のことで、けちょんけちょんに言われたので相当腹たっていました。 皆が皆、生徒の感性を認めてくれるかまどさんのような先生だったらいいね。 学校の授業嫌いな子が少なくなると思う。
読み込み中...


