
碧衣
@aoi-honmimi
- 2026年2月23日
 ドラゴンフライアーシュラ・K.ル=グウィン,アーシュラ・K.ル=グウィン,清水真砂子読み終わった世界の秩序が崩れた遥か昔、魔法使いたちは私利私欲のために権力者に仕え、己の力を見せつけるために魔法を使う。それを危惧した者たちによる魔法使いのための学院の設立に至るまでの流れ。 ある島の名士の一人息子で魔法の才能を持ち、愛する人がいる若者が選び取る道。 大賢人なき知恵の場はもはや知恵の場ではなくなり、今では己の力を競い合う場となり果て、死を拒絶する者の残骸が場を支配しよう画策する。そこに訪れる変容の炎は魔法の世界に破滅をもたらすのか──。 外部を受け入れることによる軋轢、男女の分断、歴史の積み重ねにより固定された価値観、人々はそれを疑いすらしない。それは魔法使いも同じ。だけど、その価値観に亀裂が入り出した。新しい時代がやって来る。
ドラゴンフライアーシュラ・K.ル=グウィン,アーシュラ・K.ル=グウィン,清水真砂子読み終わった世界の秩序が崩れた遥か昔、魔法使いたちは私利私欲のために権力者に仕え、己の力を見せつけるために魔法を使う。それを危惧した者たちによる魔法使いのための学院の設立に至るまでの流れ。 ある島の名士の一人息子で魔法の才能を持ち、愛する人がいる若者が選び取る道。 大賢人なき知恵の場はもはや知恵の場ではなくなり、今では己の力を競い合う場となり果て、死を拒絶する者の残骸が場を支配しよう画策する。そこに訪れる変容の炎は魔法の世界に破滅をもたらすのか──。 外部を受け入れることによる軋轢、男女の分断、歴史の積み重ねにより固定された価値観、人々はそれを疑いすらしない。それは魔法使いも同じ。だけど、その価値観に亀裂が入り出した。新しい時代がやって来る。 - 2026年2月12日
 帰還マーガレット・チョドス=アーヴィン,アーシュラ・K.ル=グウィン,アーシュラ・K.ル=グウィン,Ursula K.Le Guin,清水真砂子読み終わった世界に異変が起きている最中、大賢人ゲドの故郷の島で農夫の妻が傷ついた少女を拾い彼女にテルーという名を与える。 世界を旅する男たち、一処に留まる女たち。 この世界に女のまじない師はいても女の魔法使いはいない。 閉ざされた闇の世界から抜け出して、家庭を持つ“普通の”人間となったテナーの視点、彼女が内側で燻ぶらせ続けているものはこれまで作者が感じてきたものなのだろうかと思われる。 故郷に戻って来たゲドは世界の均衡を守るために魔法を失い、以前の親しみをも失っていた。 長く不在だった王が玉座について世界は変わり出している。 根本が揺るがされようとしている。それは魔法も例外ではない。
帰還マーガレット・チョドス=アーヴィン,アーシュラ・K.ル=グウィン,アーシュラ・K.ル=グウィン,Ursula K.Le Guin,清水真砂子読み終わった世界に異変が起きている最中、大賢人ゲドの故郷の島で農夫の妻が傷ついた少女を拾い彼女にテルーという名を与える。 世界を旅する男たち、一処に留まる女たち。 この世界に女のまじない師はいても女の魔法使いはいない。 閉ざされた闇の世界から抜け出して、家庭を持つ“普通の”人間となったテナーの視点、彼女が内側で燻ぶらせ続けているものはこれまで作者が感じてきたものなのだろうかと思われる。 故郷に戻って来たゲドは世界の均衡を守るために魔法を失い、以前の親しみをも失っていた。 長く不在だった王が玉座について世界は変わり出している。 根本が揺るがされようとしている。それは魔法も例外ではない。 - 2026年2月9日
 さいはての島へゲイル・ギャラティ,アーシュラ・K.ル=グウィン,アーシュラ・K.ル=グウィン,Ursula K.Le Guin,清水真砂子読み終わった平和と統治を司る腕環が王の塔に戻り、十数年は平和だった世界に異変が起き出している。その報せを寄越した王子と共に大賢人となったゲドは世界の変調の原因を探す旅に出る。 800年空白の玉座、魔法をかけなくなったまじない師、死んだように生きる人々、島の腐敗と薬物汚染、魔法の根幹、そして魔法と人々の信頼を揺るがす事態は何者かが均衡を狂わそうとしているとゲドは考える。 人々が持つ本能的な死への恐怖。それをどう捉えるか。ただただ恐れ、思考を放棄するのか、または恐れそのものを受け入れ限りある生を全うするか、それとも死を征服し亡者の王となるのか。この物語をどう捉えればいいのか正直、分からない。アースシーの世界を介して私達のいる現実世界になにかを訴えているのだろうか。
さいはての島へゲイル・ギャラティ,アーシュラ・K.ル=グウィン,アーシュラ・K.ル=グウィン,Ursula K.Le Guin,清水真砂子読み終わった平和と統治を司る腕環が王の塔に戻り、十数年は平和だった世界に異変が起き出している。その報せを寄越した王子と共に大賢人となったゲドは世界の変調の原因を探す旅に出る。 800年空白の玉座、魔法をかけなくなったまじない師、死んだように生きる人々、島の腐敗と薬物汚染、魔法の根幹、そして魔法と人々の信頼を揺るがす事態は何者かが均衡を狂わそうとしているとゲドは考える。 人々が持つ本能的な死への恐怖。それをどう捉えるか。ただただ恐れ、思考を放棄するのか、または恐れそのものを受け入れ限りある生を全うするか、それとも死を征服し亡者の王となるのか。この物語をどう捉えればいいのか正直、分からない。アースシーの世界を介して私達のいる現実世界になにかを訴えているのだろうか。 - 2026年2月7日
 こわれた腕環アーシュラ・K.ル=グウィン,清水真砂子読み終わった暗闇に仕える少女は外海からやって来た魔法使いと出会う。その出会いは少女の生きる道の選択を迫るものとなり、深い葛藤の末、少女が選ぶ道は───。 帝国に属する島のひとつアチュアンの墓地の大巫女が死に、彼女の生まれ変わりとして選ばれた少女は「喰らわれし者」を意味する名を付けられ、やがて過去も真の名前も忘れ去り、“名なき者たち”に仕える器としての年月を過ごすようになっていく。 そんな大巫女のみが入れる墓地の地下迷宮の宝物庫に眠る古のまじない師・エレス・アクべの腕環の片割れ。統治と平和のしるしが刻まれた腕環の文字を復元するため魔法使いゲドは禁忌の地下迷宮に潜入する。 前巻でもそうだったが、この世界の魔法は最強でも万能でもない。“名なき者たち”の力が強い地下迷宮でゲドは半ば死にかけて、少女の助力がなければ助からなかった。そんな少女にゲドは「自由」という可能性をもたらす。かりそめの安寧を手放し、重荷を背負って歩む自由。広がる世界と未知なるものに対する不安と恐怖、そして犯した罪への呵責…そんな思いを抱える少女をゲドが送り届けようとする場所は少女には最良の場だと思った。沈黙が許されたあの場所で少女の心はどう変化していくのか。
こわれた腕環アーシュラ・K.ル=グウィン,清水真砂子読み終わった暗闇に仕える少女は外海からやって来た魔法使いと出会う。その出会いは少女の生きる道の選択を迫るものとなり、深い葛藤の末、少女が選ぶ道は───。 帝国に属する島のひとつアチュアンの墓地の大巫女が死に、彼女の生まれ変わりとして選ばれた少女は「喰らわれし者」を意味する名を付けられ、やがて過去も真の名前も忘れ去り、“名なき者たち”に仕える器としての年月を過ごすようになっていく。 そんな大巫女のみが入れる墓地の地下迷宮の宝物庫に眠る古のまじない師・エレス・アクべの腕環の片割れ。統治と平和のしるしが刻まれた腕環の文字を復元するため魔法使いゲドは禁忌の地下迷宮に潜入する。 前巻でもそうだったが、この世界の魔法は最強でも万能でもない。“名なき者たち”の力が強い地下迷宮でゲドは半ば死にかけて、少女の助力がなければ助からなかった。そんな少女にゲドは「自由」という可能性をもたらす。かりそめの安寧を手放し、重荷を背負って歩む自由。広がる世界と未知なるものに対する不安と恐怖、そして犯した罪への呵責…そんな思いを抱える少女をゲドが送り届けようとする場所は少女には最良の場だと思った。沈黙が許されたあの場所で少女の心はどう変化していくのか。 - 2026年2月4日
 影との戦いルース・ロビンス,アーシュラ・K.ル=グウィン,アーシュラ・K.ル=グウィン,Ursula K.Le Guin,清水真砂子読み終わったジブリ映画の『ゲド戦記』がしょっちゅう駄作扱いされているのが気になったので(個人的に悪印象はあまりない)原作小説に着手してみた。 ジブリでは主人公を導くイケオジのハイタカ(ゲド)の少年〜青年期、潜在的に魔法の能力に優れ、血の気の多い彼は自身の師匠や賢人たちの教えに内心で反発し、いけ好かない相手に自身の能力を知らしめたいという欲求から禁じ手に手を出してしまう。そこからゲドは孤独な旅に身を置くことになる。 作中の地図を見るだけでも世界観の作り込みが感じられ、SF作家でもある著者だからか魔法の話にも科学的な要素が含まれている。読む前にこの作品の重厚さを若干、侮っていたことを反省した。 戦うべく〈影〉を自身の身に受け止めたゲドのこの先の旅を見届けたくなる。
影との戦いルース・ロビンス,アーシュラ・K.ル=グウィン,アーシュラ・K.ル=グウィン,Ursula K.Le Guin,清水真砂子読み終わったジブリ映画の『ゲド戦記』がしょっちゅう駄作扱いされているのが気になったので(個人的に悪印象はあまりない)原作小説に着手してみた。 ジブリでは主人公を導くイケオジのハイタカ(ゲド)の少年〜青年期、潜在的に魔法の能力に優れ、血の気の多い彼は自身の師匠や賢人たちの教えに内心で反発し、いけ好かない相手に自身の能力を知らしめたいという欲求から禁じ手に手を出してしまう。そこからゲドは孤独な旅に身を置くことになる。 作中の地図を見るだけでも世界観の作り込みが感じられ、SF作家でもある著者だからか魔法の話にも科学的な要素が含まれている。読む前にこの作品の重厚さを若干、侮っていたことを反省した。 戦うべく〈影〉を自身の身に受け止めたゲドのこの先の旅を見届けたくなる。 - 2026年2月1日
 夜明けの縁をさ迷う人々小川洋子読み終わったかつて読んだある人が語る華やかで肉欲に満ちた残酷な物語たちは人々からは虚言や妄言として扱われ、見向きもされない。だけど彼女たちの中でそれは紛れもない彼女たちの物語なのだろう。 二作目の「教授宅の留守番」の怒涛の贈り物地獄と最後の「再試合」の永遠に終わらない甲子園の決勝戦の吐き気がしそうなほどうんざりする感じが似ている。 関節カスタネットのために文字通り自らを捧げようとする涙売り、神様から苦しまずに死ぬことを許されない生き物サンバカツギ、家が入居者を選ぶ不動産屋…奇妙で残酷な話の中に、生きている人々の裏側に引っ越してきた人々がどんな理由でその人の裏側に入ったかを知ると内側から感動が広がる「パラソルチョコレート」のような話を入れてくるのはずるいと思わずにいられない。
夜明けの縁をさ迷う人々小川洋子読み終わったかつて読んだある人が語る華やかで肉欲に満ちた残酷な物語たちは人々からは虚言や妄言として扱われ、見向きもされない。だけど彼女たちの中でそれは紛れもない彼女たちの物語なのだろう。 二作目の「教授宅の留守番」の怒涛の贈り物地獄と最後の「再試合」の永遠に終わらない甲子園の決勝戦の吐き気がしそうなほどうんざりする感じが似ている。 関節カスタネットのために文字通り自らを捧げようとする涙売り、神様から苦しまずに死ぬことを許されない生き物サンバカツギ、家が入居者を選ぶ不動産屋…奇妙で残酷な話の中に、生きている人々の裏側に引っ越してきた人々がどんな理由でその人の裏側に入ったかを知ると内側から感動が広がる「パラソルチョコレート」のような話を入れてくるのはずるいと思わずにいられない。 - 2026年1月28日
 シュガータイム小川洋子(小説家)読み終わったかつて読んだ真剣にものを食べている時の人間は、かわいそうな存在だと思ってた。 そんな私が今では食欲に捕らわれている。 披露宴会場に取り残されたアイスクリーム・ロイヤルに群がる宴会係、成長しない弟、肉体関係を持たない恋人… 以前、読んだ時はなんとも思わなかったけど小川洋子作品の登場人物はひとりで行動する人々ばかりだから、事故に遭った主人公の恋人と一緒にいたとされる女性の正体を友人と突き止めに行くという展開は珍しく感じた。 もう三度目にもなるので主人公の恋人の手紙には彼は自分に酔ってるなくらいの微かな感情しかなかったけど、その代わりに主人公と弟の生活にヒステリックに入り込んで来る彼らの母親の存在が不快だった。母親の気持ちも分からなくはないけど彼女の心配なんて彼らはとっくに通り過ぎてやっている。
シュガータイム小川洋子(小説家)読み終わったかつて読んだ真剣にものを食べている時の人間は、かわいそうな存在だと思ってた。 そんな私が今では食欲に捕らわれている。 披露宴会場に取り残されたアイスクリーム・ロイヤルに群がる宴会係、成長しない弟、肉体関係を持たない恋人… 以前、読んだ時はなんとも思わなかったけど小川洋子作品の登場人物はひとりで行動する人々ばかりだから、事故に遭った主人公の恋人と一緒にいたとされる女性の正体を友人と突き止めに行くという展開は珍しく感じた。 もう三度目にもなるので主人公の恋人の手紙には彼は自分に酔ってるなくらいの微かな感情しかなかったけど、その代わりに主人公と弟の生活にヒステリックに入り込んで来る彼らの母親の存在が不快だった。母親の気持ちも分からなくはないけど彼女の心配なんて彼らはとっくに通り過ぎてやっている。 - 2026年1月23日
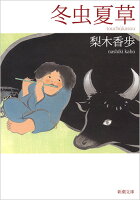 冬虫夏草梨木香歩読み終わったかつて読んだ友人の家の家守をする文士・綿貫征四郎は二月も家に帰って来ない飼い犬のゴローを探すのに加え、鈴鹿の山奥にあるとされるイワナの夫婦が営む宿屋を目指し旅に出る。 急速に近代化が進む世の中に対して、綿貫の周囲には毘沙門の祭りに参加するムジナや説法を施すタヌキが存在し、鈴鹿の山には河童、さらには竜神の存在が示唆されている。そして多くの植物たちの存在がある。 綿貫は自身は憂鬱を長い間、引き受けられない性質を物書きとしての短所と語る場面がある。確かにそれは弱点になるかもしれない。けれど、旅の道中に起きた見ず知らずの人の不幸を彼は本気で同情し寄り添える。良い意味で線引が出来るのは人としては強みではないだろうかと思う。大成はせずとも細く長くは生きていけそうな気がする。
冬虫夏草梨木香歩読み終わったかつて読んだ友人の家の家守をする文士・綿貫征四郎は二月も家に帰って来ない飼い犬のゴローを探すのに加え、鈴鹿の山奥にあるとされるイワナの夫婦が営む宿屋を目指し旅に出る。 急速に近代化が進む世の中に対して、綿貫の周囲には毘沙門の祭りに参加するムジナや説法を施すタヌキが存在し、鈴鹿の山には河童、さらには竜神の存在が示唆されている。そして多くの植物たちの存在がある。 綿貫は自身は憂鬱を長い間、引き受けられない性質を物書きとしての短所と語る場面がある。確かにそれは弱点になるかもしれない。けれど、旅の道中に起きた見ず知らずの人の不幸を彼は本気で同情し寄り添える。良い意味で線引が出来るのは人としては強みではないだろうかと思う。大成はせずとも細く長くは生きていけそうな気がする。 - 2026年1月8日
 ブラフマンの埋葬小川洋子読み終わったかつて読んだ水かきのある短い手足、胴の1.2倍ある尻尾、ボタンのような鼻。 地上ではやんちゃだが水の中では音もなく泳ぎ、時折、思慮深い目をする。ブラフマンはまさに謎そのものだ。 芸術家に仕事場を提供する〈創作家の家〉を管理する僕と森からやって来たブラフマンとの短い日々。 初見に読んだ時は気付かなかったけど、僕が好意を寄せる雑貨屋の娘との関係は早い段階から相容れないものだなと感じた。そもそも彼女には列車に乗って彼女に会いに来る恋人がいる訳だし、彼女からしたら僕の存在は店のお得意様でその上、車の運転を教えてくれる良くて友人止まりな関係に過ぎないのだろう。その彼女の踏み越えられたくない領域を僕は踏んでしまったことで悲劇は起きたという解説にはなるほどと思った。 じゃあ、彼の命は犠牲になるためだけに存在したのだろうか。 そうだとしたらあまりにも虚しすぎる。
ブラフマンの埋葬小川洋子読み終わったかつて読んだ水かきのある短い手足、胴の1.2倍ある尻尾、ボタンのような鼻。 地上ではやんちゃだが水の中では音もなく泳ぎ、時折、思慮深い目をする。ブラフマンはまさに謎そのものだ。 芸術家に仕事場を提供する〈創作家の家〉を管理する僕と森からやって来たブラフマンとの短い日々。 初見に読んだ時は気付かなかったけど、僕が好意を寄せる雑貨屋の娘との関係は早い段階から相容れないものだなと感じた。そもそも彼女には列車に乗って彼女に会いに来る恋人がいる訳だし、彼女からしたら僕の存在は店のお得意様でその上、車の運転を教えてくれる良くて友人止まりな関係に過ぎないのだろう。その彼女の踏み越えられたくない領域を僕は踏んでしまったことで悲劇は起きたという解説にはなるほどと思った。 じゃあ、彼の命は犠牲になるためだけに存在したのだろうか。 そうだとしたらあまりにも虚しすぎる。 - 2026年1月5日
 まぶた小川洋子読み終わったかつて読んだ飛行機で隣同士になった老婆の思い出と突然の死。それが男が眠るのが難しい飛行機の中で眠りへと導いてくれる物語だ──。 みすぼらしい見た目に似合わないピンクのマニキュアをした野菜売りの老婆が野菜と共に置いていった名前の分からない中国野菜の種はやがて生長し、夜に光を放つ…これってこんなに奇妙な話だったっけ?短編集は覚えている話とほとんど忘れている話に差があっておもしろい。 「バックストローク」の背泳ぎの選手だった弟と彼のためにすべてを捧げる母親。そして放置される夫と他のきょうだいという構図は『凍りついた香り』と類似していることから何かロールモデルがあるのだろうかと気になった。 表題作は語り手の15歳の少女と逢瀬を重ねる中年男性N。少女と二人きりの時はロマンチックな雰囲気を醸し出せるNがその外側に出ると情けなさと滑稽さが露呈して、それにこちらが共感性羞恥を感じて居た堪れない気持ちになる。
まぶた小川洋子読み終わったかつて読んだ飛行機で隣同士になった老婆の思い出と突然の死。それが男が眠るのが難しい飛行機の中で眠りへと導いてくれる物語だ──。 みすぼらしい見た目に似合わないピンクのマニキュアをした野菜売りの老婆が野菜と共に置いていった名前の分からない中国野菜の種はやがて生長し、夜に光を放つ…これってこんなに奇妙な話だったっけ?短編集は覚えている話とほとんど忘れている話に差があっておもしろい。 「バックストローク」の背泳ぎの選手だった弟と彼のためにすべてを捧げる母親。そして放置される夫と他のきょうだいという構図は『凍りついた香り』と類似していることから何かロールモデルがあるのだろうかと気になった。 表題作は語り手の15歳の少女と逢瀬を重ねる中年男性N。少女と二人きりの時はロマンチックな雰囲気を醸し出せるNがその外側に出ると情けなさと滑稽さが露呈して、それにこちらが共感性羞恥を感じて居た堪れない気持ちになる。 - 2026年1月1日
 海小川洋子読み終わったかつて読んだ恋人の実家への挨拶、体の大きな「小さな弟」だけが奏でられる鳴鱗琴。最初に読んだ頃はただ穏やかな話だと思っていたけど、読み返すとあちらこちらに不穏な気配が紛れ込んでいることに気づく。しかし、それに気づいたからと言って何かが変化することがないのを私は知っている。 二作目の「風薫るウィーンの旅六日間」のシュールさに変な笑いが出そうになりながらも厳粛な気持ちになり、「バタフライ和文タイプ事務所」の活字管理人は今の時代ならどこにいるのだろうと考えたりする。 「ひよこトラック」の言葉を話さない少女と孤独な老齢なホテルのドアマンとの言葉のないやり取りや、「ガイド」の少年と思い出に題名を付ける題名屋の老人との交流。一見、穏やかで微笑ましくも見えるこれらの物語の中にも毒は紛れ込んでいるのだろうか。
海小川洋子読み終わったかつて読んだ恋人の実家への挨拶、体の大きな「小さな弟」だけが奏でられる鳴鱗琴。最初に読んだ頃はただ穏やかな話だと思っていたけど、読み返すとあちらこちらに不穏な気配が紛れ込んでいることに気づく。しかし、それに気づいたからと言って何かが変化することがないのを私は知っている。 二作目の「風薫るウィーンの旅六日間」のシュールさに変な笑いが出そうになりながらも厳粛な気持ちになり、「バタフライ和文タイプ事務所」の活字管理人は今の時代ならどこにいるのだろうと考えたりする。 「ひよこトラック」の言葉を話さない少女と孤独な老齢なホテルのドアマンとの言葉のないやり取りや、「ガイド」の少年と思い出に題名を付ける題名屋の老人との交流。一見、穏やかで微笑ましくも見えるこれらの物語の中にも毒は紛れ込んでいるのだろうか。 - 2025年12月24日
 若草物語ルイザ・メイ・オルコット,Louisa May Alcott,T・チューダー,Tasha Tudor,矢川澄子読み終わった従軍牧師として戦地に赴いている夫に代わり家を守る夫人と4人の娘たち。友人の不運を救うため財産を失い貧しい生活を送りながらも楽しく過ごすマーチ家と隣人のお金持ちローレンス氏の孫のローリーとの愉快な日々。 その中で性格が異なる姉妹が抱える問題。その解決には露骨なキリスト教的な教訓も交えてて正直、反射的な拒否感もあったけど、日々いい子でいることを目指す彼女たちの成長には必要な出来事たちであったのだろうと一応納得はする。 キャラクター的には作者の投影である次女のジョーに注目が行きがちだけど、個人的に好きなのは三女のエリザベス(ベス)だ。活発なジョーとは対照的に恥ずかしがりやで家族以外とは交流を持とうとはしないけど、傷ついた人や物を放っておけずその時には勇気を出して相手と向き合い、当たり前のように献身的になれる。孫娘を亡くしたローレンス氏を最初は怖がっていたけどピアノを介して友人関係にまでなれたのには思わず涙ぐみそうになった。それくらい彼女に入れ込んでしまった。
若草物語ルイザ・メイ・オルコット,Louisa May Alcott,T・チューダー,Tasha Tudor,矢川澄子読み終わった従軍牧師として戦地に赴いている夫に代わり家を守る夫人と4人の娘たち。友人の不運を救うため財産を失い貧しい生活を送りながらも楽しく過ごすマーチ家と隣人のお金持ちローレンス氏の孫のローリーとの愉快な日々。 その中で性格が異なる姉妹が抱える問題。その解決には露骨なキリスト教的な教訓も交えてて正直、反射的な拒否感もあったけど、日々いい子でいることを目指す彼女たちの成長には必要な出来事たちであったのだろうと一応納得はする。 キャラクター的には作者の投影である次女のジョーに注目が行きがちだけど、個人的に好きなのは三女のエリザベス(ベス)だ。活発なジョーとは対照的に恥ずかしがりやで家族以外とは交流を持とうとはしないけど、傷ついた人や物を放っておけずその時には勇気を出して相手と向き合い、当たり前のように献身的になれる。孫娘を亡くしたローレンス氏を最初は怖がっていたけどピアノを介して友人関係にまでなれたのには思わず涙ぐみそうになった。それくらい彼女に入れ込んでしまった。 - 2025年12月20日
 日本の10大カルト島田裕巳読み終わった霊感商法、所在を明かさない勧誘、独自の教義… いわゆるカルトと呼ばれる宗教に対するこういったイメージ。しかし、元を辿るとキリスト教もイスラム教も仏教もかつてはカルトだった。 子供の頃にオウム真理教をテレビで見て漠然とした気味の悪さを感じていて、後にカルト宗教に漂う胡散臭さに入信する人の気がしれないと思っていたが、カルトまたは新宗教と呼ばれる集団は高度経済成長がはじまった時代に地方からやって来たばかりの人間たちの新たな人間関係のネットワークの場として、バブル時代は金余りの風潮や性をめぐる堕落に付いてこられず精神性を深める生き方や純潔を強調した教団に居場所を求める人が少なからざるいたことを知る。 そうなるとカルト宗教がなくならないことが分かる。 ただ信仰している分には問題がないが、信仰の自由を盾にして行われる高額献金や子供への虐待ともとれる行為、そして社会に対する攻撃が問題なのだから我々ができることは注視するくらいだろうか。
日本の10大カルト島田裕巳読み終わった霊感商法、所在を明かさない勧誘、独自の教義… いわゆるカルトと呼ばれる宗教に対するこういったイメージ。しかし、元を辿るとキリスト教もイスラム教も仏教もかつてはカルトだった。 子供の頃にオウム真理教をテレビで見て漠然とした気味の悪さを感じていて、後にカルト宗教に漂う胡散臭さに入信する人の気がしれないと思っていたが、カルトまたは新宗教と呼ばれる集団は高度経済成長がはじまった時代に地方からやって来たばかりの人間たちの新たな人間関係のネットワークの場として、バブル時代は金余りの風潮や性をめぐる堕落に付いてこられず精神性を深める生き方や純潔を強調した教団に居場所を求める人が少なからざるいたことを知る。 そうなるとカルト宗教がなくならないことが分かる。 ただ信仰している分には問題がないが、信仰の自由を盾にして行われる高額献金や子供への虐待ともとれる行為、そして社会に対する攻撃が問題なのだから我々ができることは注視するくらいだろうか。 - 2025年12月17日
 沸騰大陸三浦英之読み終わった人口が爆発し、人間の生と性、暴力と欲望が激しく入り乱れるアフリカの姿を見てきた著者。 アラブの春の後のエジプトで民主主義を求めて立ち上がろうとする国民の身体に実弾を撃ち込む自国の軍隊、化学兵器を使い多くの子供を殺害するアサド政権、誘拐した少女たちの体に爆弾を巻き付け遠隔操作で爆発させるテロを起こすボコ・ハラム、経済が大きく発展したウガンダで無垢な子供を生贄に捧げる「資源の呪い」に捕われた人々、ケニアとソマリアのテロと報復の応酬──。 彼の地では人の命があまりにも軽く、そして不公平に不平等に扱われる。その現状に読んでる側も激しい憤りを感じたのだから直接現場で見聞きしてきた著者の思いは相当だろう。その嘆きと葛藤が本書で窺われる。 欧州に翻弄されてきた歴史、自国の政治の汚職、貧困、格差、疫病、感染症、戦争、テロ、レイプ、自然破壊。著者の本を読むと人間の愚かさがダイレクトに伝わって来て嫌悪感で頭が沸騰しそうになる。 では、自分に何が出来るか。この現実に目を背けないことくらいしか今は思いつかない。
沸騰大陸三浦英之読み終わった人口が爆発し、人間の生と性、暴力と欲望が激しく入り乱れるアフリカの姿を見てきた著者。 アラブの春の後のエジプトで民主主義を求めて立ち上がろうとする国民の身体に実弾を撃ち込む自国の軍隊、化学兵器を使い多くの子供を殺害するアサド政権、誘拐した少女たちの体に爆弾を巻き付け遠隔操作で爆発させるテロを起こすボコ・ハラム、経済が大きく発展したウガンダで無垢な子供を生贄に捧げる「資源の呪い」に捕われた人々、ケニアとソマリアのテロと報復の応酬──。 彼の地では人の命があまりにも軽く、そして不公平に不平等に扱われる。その現状に読んでる側も激しい憤りを感じたのだから直接現場で見聞きしてきた著者の思いは相当だろう。その嘆きと葛藤が本書で窺われる。 欧州に翻弄されてきた歴史、自国の政治の汚職、貧困、格差、疫病、感染症、戦争、テロ、レイプ、自然破壊。著者の本を読むと人間の愚かさがダイレクトに伝わって来て嫌悪感で頭が沸騰しそうになる。 では、自分に何が出来るか。この現実に目を背けないことくらいしか今は思いつかない。 - 2025年12月15日
 わたしたちが孤児だったころカズオ・イシグロ,入江真佐子読み終わった上海で暮らしていた十歳の頃に両親が失踪し、後年はイギリスの社交界でも名を知られる探偵となったクリストファー・バンクスは再び上海の地に足を踏み入れる。 貿易会社に勤めていた父と反アヘン運動に熱心だった美しい母。 母が抱えていたであろう自己矛盾、母の理想と父の重圧、日本人の友人との日々。子供であったが故に知らされなかったこと。 個人的にバンクスがしょっちゅう腹を立てる描写が印象に残る。 自身ではどうにもできない現実に彼は腹を立てている。それは大人になっても変わらない。 辿ってきたスリリングで緊迫した冒険の本来の姿は滑稽と思えるくらいにありきたりで残酷なほど醜悪だった。その事実にバンクスは打ちのめされただろう。自分が生きてこられたのは愛する人を穢し、辱めた者の施しの上で成り立っていたのだから。 愛する人に恩を返すことはもはや叶わなず、共に生きるべき人は自ら手放してしまった。だけど、まだ希望はある。幼くも気高い心を持つ孤児の少女との再び築き上げていく“家族”としての未来が。
わたしたちが孤児だったころカズオ・イシグロ,入江真佐子読み終わった上海で暮らしていた十歳の頃に両親が失踪し、後年はイギリスの社交界でも名を知られる探偵となったクリストファー・バンクスは再び上海の地に足を踏み入れる。 貿易会社に勤めていた父と反アヘン運動に熱心だった美しい母。 母が抱えていたであろう自己矛盾、母の理想と父の重圧、日本人の友人との日々。子供であったが故に知らされなかったこと。 個人的にバンクスがしょっちゅう腹を立てる描写が印象に残る。 自身ではどうにもできない現実に彼は腹を立てている。それは大人になっても変わらない。 辿ってきたスリリングで緊迫した冒険の本来の姿は滑稽と思えるくらいにありきたりで残酷なほど醜悪だった。その事実にバンクスは打ちのめされただろう。自分が生きてこられたのは愛する人を穢し、辱めた者の施しの上で成り立っていたのだから。 愛する人に恩を返すことはもはや叶わなず、共に生きるべき人は自ら手放してしまった。だけど、まだ希望はある。幼くも気高い心を持つ孤児の少女との再び築き上げていく“家族”としての未来が。 - 2025年12月11日
 恐怖の構造 (幻冬舎新書)平山夢明読み終わったなぜ、怖いと感じる場所や状況を避けるのに、怖いとされるエンタメを楽しむのか──。 人形やピエロといった“人間の形をした人間ではないもの”に感じる恐怖や、宗教や歴史的なバックボーンが関係している国によっての恐怖の違い、恐怖よりも実は厄介な不安についての考察、そしてホラー作家の著者ならではのホラー小説論が展開される。 著者と対談した精神科医の春日武彦氏は不安や恐怖が解消される気持ちよさは快感となるため人はホラーを楽しむとする一方、後味が悪い話は珍味だと書いているが大抵のホラー作品はそうではなかろうか?そうしたらホラーそのものが珍味ということになりそうだ。 今までは受け身でホラー小説を読んできて、最近は怖さを感じにくくなってきたと思っていたので自分がホラーで怖がっているのか、サスペンスかスリラーで怖がっているのかや、怖さのツボを確認するという視点を持つのは面白い試みだと思えた。 ちなみに本書で怖かったのは著者が過ごしてきたやたらと怒鳴ったり叫んだり殴ってくる大人が多かったというどんな世紀末だと言いたくなる街だ。これはスリラーにあたるらしい。
恐怖の構造 (幻冬舎新書)平山夢明読み終わったなぜ、怖いと感じる場所や状況を避けるのに、怖いとされるエンタメを楽しむのか──。 人形やピエロといった“人間の形をした人間ではないもの”に感じる恐怖や、宗教や歴史的なバックボーンが関係している国によっての恐怖の違い、恐怖よりも実は厄介な不安についての考察、そしてホラー作家の著者ならではのホラー小説論が展開される。 著者と対談した精神科医の春日武彦氏は不安や恐怖が解消される気持ちよさは快感となるため人はホラーを楽しむとする一方、後味が悪い話は珍味だと書いているが大抵のホラー作品はそうではなかろうか?そうしたらホラーそのものが珍味ということになりそうだ。 今までは受け身でホラー小説を読んできて、最近は怖さを感じにくくなってきたと思っていたので自分がホラーで怖がっているのか、サスペンスかスリラーで怖がっているのかや、怖さのツボを確認するという視点を持つのは面白い試みだと思えた。 ちなみに本書で怖かったのは著者が過ごしてきたやたらと怒鳴ったり叫んだり殴ってくる大人が多かったというどんな世紀末だと言いたくなる街だ。これはスリラーにあたるらしい。 - 2025年12月10日
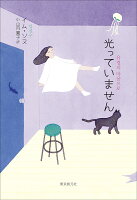 光っていませんイム・ソヌ,小山内園子読み終わったある日突然現れた分身を名乗る幽霊、人間をクラゲにする変種のクラゲの出現、家の床に根が生えた男に冬眠の手伝いを頼む男、突然死したわたしに訪れた死後のアフターサービス… 就職難、ジェンダーギャップ、苦しい妊活事情など韓国社会のままならない現実をやり過ごすために次第に惰性になり、うやむやにしてきた本心をイレギュラーな出来事をきっかけに解放していく。 どの話も心許なさはあるがこのまま停滞を続けるよりはいいのかとも思える結果だけど、最後の「カーテンコール、延長線、ファイナルステージ」は生きる喜びを感じられたのが死んだ後というのはどこか物悲しく感じてしまう。
光っていませんイム・ソヌ,小山内園子読み終わったある日突然現れた分身を名乗る幽霊、人間をクラゲにする変種のクラゲの出現、家の床に根が生えた男に冬眠の手伝いを頼む男、突然死したわたしに訪れた死後のアフターサービス… 就職難、ジェンダーギャップ、苦しい妊活事情など韓国社会のままならない現実をやり過ごすために次第に惰性になり、うやむやにしてきた本心をイレギュラーな出来事をきっかけに解放していく。 どの話も心許なさはあるがこのまま停滞を続けるよりはいいのかとも思える結果だけど、最後の「カーテンコール、延長線、ファイナルステージ」は生きる喜びを感じられたのが死んだ後というのはどこか物悲しく感じてしまう。 - 2025年12月8日
 わたしを離さないでカズオ・イシグロ,土屋政雄読み終わったわたしたちが長い年月を過ごしたあの場所で教わったことと教わらなかったこと。やがて自分たちに否応なく訪れる運命にどう向き合っていくのか。 介護人のキャシーはかつて過ごした全寮制の学び舎・ヘールシャムでの日々を振り返る。創造性を重要視し、定期的に生徒たちの作品の展示即売会が催された。 校内で起こる友人同士の細やかなマウンティング、からかいやイジメ、思春期特有の謎のブーム、そして性的な事柄への興味と一見すれば普通の学生生活の要素が如実に描かれているが、後に彼らが知っていく自身の生い立ちとその後に辿る残酷な運命。 そんな彼らを出荷される前の家畜のようだと思ってしまった自分に心底ゾッとした。 読み終わった今でも彼らがこの運命から逃れる術はなかったのだろうかと考える。憤りを持ちながらもあまりにもあっさりとその運命を受け入れている彼らの姿が悲しくうつる。
わたしを離さないでカズオ・イシグロ,土屋政雄読み終わったわたしたちが長い年月を過ごしたあの場所で教わったことと教わらなかったこと。やがて自分たちに否応なく訪れる運命にどう向き合っていくのか。 介護人のキャシーはかつて過ごした全寮制の学び舎・ヘールシャムでの日々を振り返る。創造性を重要視し、定期的に生徒たちの作品の展示即売会が催された。 校内で起こる友人同士の細やかなマウンティング、からかいやイジメ、思春期特有の謎のブーム、そして性的な事柄への興味と一見すれば普通の学生生活の要素が如実に描かれているが、後に彼らが知っていく自身の生い立ちとその後に辿る残酷な運命。 そんな彼らを出荷される前の家畜のようだと思ってしまった自分に心底ゾッとした。 読み終わった今でも彼らがこの運命から逃れる術はなかったのだろうかと考える。憤りを持ちながらもあまりにもあっさりとその運命を受け入れている彼らの姿が悲しくうつる。 - 2025年12月4日
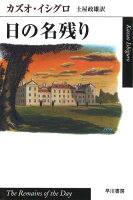 日の名残りカズオ・イシグロ,土屋政雄読み終わった過ぎ去った日々に何を選び、何を選ばなかったのか。 もしも、選ばなかった方の道を選んでいたら何か変わったのだろうか──。 イギリス・ヨークシャーのダーリントン・ホールで長年、執事として仕えてきたスティーブンス。偉大な執事とは何かを常に考え続ける職業意識の高い、良く言うと生真面目で悪く言うと堅物で優柔が効かない人物。 彼の新たな雇主の勧めと彼自身のある目的のための自動車旅行に出た先々で見るイギリスの田舎の風景とそこに暮らす人々との触れ合いの最中に思い出される尊敬するダーリントン卿と栄華を極めたダーリントン・ホールでの日々、そして元女中頭との邂逅の中で彼が見て見ぬふりをしてきたこと。 ダーリントン卿の過ち、ミス・ケントンとの関係への分岐点はあったと思うけどスティーブンスがスティーブンスでいる限りは変わらないような気がする。それは彼がどこまでも執事のままだから。
日の名残りカズオ・イシグロ,土屋政雄読み終わった過ぎ去った日々に何を選び、何を選ばなかったのか。 もしも、選ばなかった方の道を選んでいたら何か変わったのだろうか──。 イギリス・ヨークシャーのダーリントン・ホールで長年、執事として仕えてきたスティーブンス。偉大な執事とは何かを常に考え続ける職業意識の高い、良く言うと生真面目で悪く言うと堅物で優柔が効かない人物。 彼の新たな雇主の勧めと彼自身のある目的のための自動車旅行に出た先々で見るイギリスの田舎の風景とそこに暮らす人々との触れ合いの最中に思い出される尊敬するダーリントン卿と栄華を極めたダーリントン・ホールでの日々、そして元女中頭との邂逅の中で彼が見て見ぬふりをしてきたこと。 ダーリントン卿の過ち、ミス・ケントンとの関係への分岐点はあったと思うけどスティーブンスがスティーブンスでいる限りは変わらないような気がする。それは彼がどこまでも執事のままだから。 - 2025年11月30日
 聖なるズー濱野ちひろ読み終わった動物性愛は獣姦と何が違うのか、種族の違う者同士が心を通わせ、愛し合うことは可能なのだろうか。 そもそも、同じ種族であるヒト同士は本当に心を通わせ合っているのだろうか──。 長い間、性暴力の被害に遭って来た中で恋人としての愛情とそれに絡まる性愛の意味が分からなくった著者が動物性愛について調査するために赴いたドイツで世界唯一の動物性愛者の団体に所属する動物性愛者(通称ズー)との交流を始める。 ズーたちは何よりもパートナーである動物との対等性を何よりも大切にし、言葉を持たない彼ら彼女らとの中で生じ、発見されるやり取り(=パーソナリティ)に魅了される。 そして、パートナーである動物を愛玩動物として「子供視」するのではなく、性的欲望を持つ成熟した存在として丸ごと受け止める。 ズーの中には生まれながらのズーと、後にズーになっていく人がいる。 生まれながらのズーは読んでいると何かの手違いで人間に生まれて来てしまった動物のような哀愁を感じ、後にズーになる人の自身のセクシャリティを決めるという考えは私にとっては目からウロコだった。 そんなズーたちの世間の風当たりは強く、動物性愛は精神疾患のひとつとして捉えられている。 最後まで読んでみても私にはズーと動物が心を通わせられてるかについては半身半疑だった。 それは言葉を持たない動物たちの本心はこちらには分からないからだけど、同じ言葉を使うヒト同士でもその人の本心が理解出来たとは言い難い。それはむしろ言葉がある故なのかもしれない。言葉はいくらでも取り繕えてしまうから。 そして私自身が誰かと心を通わせられたという実感がないのもあるのだと思う。著者と同じように純粋に動物を愛するズーたちに対しての羨望があるのかもしれない。
聖なるズー濱野ちひろ読み終わった動物性愛は獣姦と何が違うのか、種族の違う者同士が心を通わせ、愛し合うことは可能なのだろうか。 そもそも、同じ種族であるヒト同士は本当に心を通わせ合っているのだろうか──。 長い間、性暴力の被害に遭って来た中で恋人としての愛情とそれに絡まる性愛の意味が分からなくった著者が動物性愛について調査するために赴いたドイツで世界唯一の動物性愛者の団体に所属する動物性愛者(通称ズー)との交流を始める。 ズーたちは何よりもパートナーである動物との対等性を何よりも大切にし、言葉を持たない彼ら彼女らとの中で生じ、発見されるやり取り(=パーソナリティ)に魅了される。 そして、パートナーである動物を愛玩動物として「子供視」するのではなく、性的欲望を持つ成熟した存在として丸ごと受け止める。 ズーの中には生まれながらのズーと、後にズーになっていく人がいる。 生まれながらのズーは読んでいると何かの手違いで人間に生まれて来てしまった動物のような哀愁を感じ、後にズーになる人の自身のセクシャリティを決めるという考えは私にとっては目からウロコだった。 そんなズーたちの世間の風当たりは強く、動物性愛は精神疾患のひとつとして捉えられている。 最後まで読んでみても私にはズーと動物が心を通わせられてるかについては半身半疑だった。 それは言葉を持たない動物たちの本心はこちらには分からないからだけど、同じ言葉を使うヒト同士でもその人の本心が理解出来たとは言い難い。それはむしろ言葉がある故なのかもしれない。言葉はいくらでも取り繕えてしまうから。 そして私自身が誰かと心を通わせられたという実感がないのもあるのだと思う。著者と同じように純粋に動物を愛するズーたちに対しての羨望があるのかもしれない。
読み込み中...