

ヒナタ
@hinata625141
- 2026年1月31日
 マルチの子西尾潤読み終わった側から見れば何もかもがおかしいのにずぶずぶと自ら嵌りこんでいく。 あとがきで自分もマルチにハマって借金を作った経験のある著者が、マルチにハマりやすい人の特徴として挙げているのが、自分に満足できてない人、勉強熱心な人、自己評価の低い人。そんなの全く当てはまらない人のほうが少ないんじゃないかと思って怖くなる。 『愚か者』シリーズもそうだったのだけど西尾さんの作品は、反社会的な世界が他人事には思えない。おばあちゃん子で、親バレを恐れ、承認欲求の強い真瑠子は、私だったのかも知れないのだから。 終盤の怒涛の展開も救いのあるラストもとても良かった。
マルチの子西尾潤読み終わった側から見れば何もかもがおかしいのにずぶずぶと自ら嵌りこんでいく。 あとがきで自分もマルチにハマって借金を作った経験のある著者が、マルチにハマりやすい人の特徴として挙げているのが、自分に満足できてない人、勉強熱心な人、自己評価の低い人。そんなの全く当てはまらない人のほうが少ないんじゃないかと思って怖くなる。 『愚か者』シリーズもそうだったのだけど西尾さんの作品は、反社会的な世界が他人事には思えない。おばあちゃん子で、親バレを恐れ、承認欲求の強い真瑠子は、私だったのかも知れないのだから。 終盤の怒涛の展開も救いのあるラストもとても良かった。 - 2026年1月29日
- 2026年1月27日
 愚か者の身分西尾潤読み終わった映画が本当に最高だったので慌てて原作を読んだ。原作は連作短編集で映画では端折られたエピソードもあるのだけど大まかな流れはもちろん同じなので映画の裏側をのぞいているような楽しさがある。 とはいえ、原作自体がめちゃめちゃ面白い。 彼らのやっていることは社会的に許されることではないけれど、彼らもまた怯えながら必死に生き延びようとしている。彼らを知れば知るほど同じ人間だと思う。決して他人事ではない。だからこそ一筋の光のあるラストに救われる。 全編通してスリルのある展開で一気に読まされるのだけど、読み終わって思い返すと心に残るのは静かなエモーショナルな場面というのも素敵だなと思った。 西尾さんの作品追いかけよう〜!
愚か者の身分西尾潤読み終わった映画が本当に最高だったので慌てて原作を読んだ。原作は連作短編集で映画では端折られたエピソードもあるのだけど大まかな流れはもちろん同じなので映画の裏側をのぞいているような楽しさがある。 とはいえ、原作自体がめちゃめちゃ面白い。 彼らのやっていることは社会的に許されることではないけれど、彼らもまた怯えながら必死に生き延びようとしている。彼らを知れば知るほど同じ人間だと思う。決して他人事ではない。だからこそ一筋の光のあるラストに救われる。 全編通してスリルのある展開で一気に読まされるのだけど、読み終わって思い返すと心に残るのは静かなエモーショナルな場面というのも素敵だなと思った。 西尾さんの作品追いかけよう〜! - 2026年1月26日
- 2026年1月26日
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子読み終わった
プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子読み終わった - 2026年1月23日
 絶望はしてません斎藤美奈子『日本の同時代小説』を読み返したついでに最新作も読んだ。本書も本の紹介がベースながら政治への切り口が鋭くて笑ってる場合ではないのだがくすくす笑いながらあっという間に読めてしまう。絶望はしたくないな。笑っていたい。 エンタメ作品、おもにドラマについてのコラムもある。斉藤さんは朝ドラや大河において主人公の生き方が史実よりマイルドに描かれることがあまりお気に召さないようだけど(私もです…)、『虎に翼』はめずらしく評伝よりもドラマの方が面白いと太鼓判を押されてて、ですよね!!!と思った👍
絶望はしてません斎藤美奈子『日本の同時代小説』を読み返したついでに最新作も読んだ。本書も本の紹介がベースながら政治への切り口が鋭くて笑ってる場合ではないのだがくすくす笑いながらあっという間に読めてしまう。絶望はしたくないな。笑っていたい。 エンタメ作品、おもにドラマについてのコラムもある。斉藤さんは朝ドラや大河において主人公の生き方が史実よりマイルドに描かれることがあまりお気に召さないようだけど(私もです…)、『虎に翼』はめずらしく評伝よりもドラマの方が面白いと太鼓判を押されてて、ですよね!!!と思った👍 - 2026年1月23日
 日本の同時代小説 (岩波新書)斎藤美奈子読み終わった再読本。 1960年代から2010年代まで10年ごとに区切り、その当時売れてた小説を基点に社会や政治を論じた一冊。さすが斉藤美奈子さんだなぁ。ノートにまとめたいと思いつつまだやれてません。
日本の同時代小説 (岩波新書)斎藤美奈子読み終わった再読本。 1960年代から2010年代まで10年ごとに区切り、その当時売れてた小説を基点に社会や政治を論じた一冊。さすが斉藤美奈子さんだなぁ。ノートにまとめたいと思いつつまだやれてません。 - 2026年1月23日
 明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語田中ひかる読み終わった以前読んだ『明治のナイチンゲール 大関和物語』と同じく、田中ひかるさんのご著書です。本書はタイトルにある高橋瑞さんを中心としながらも、女性で初めて公認医師となった荻野吟子さん、二番目に公認女医となった生澤久野さん、東京女医学校を設立した吉岡彌生さんなど、明治の世に医学の世界に飛び込んだ女性たちの物語です。 女性で初めて医師になった吟子さんは美人で潔癖な女性というパブリックイメージだったそうですが、日本で三番目の公認女医になった本書の主人公、高橋瑞さんは道なき道を根性で突き進むバンカラっぷりがまるで正反対でむちゃくちゃ面白いです! 五分刈りに二重マント、まるで「男隠居」と陰口を言われるも、貧者からは金を取らない「義」の医師であり続けた高橋瑞、あまりにかっこよすぎて朝ドラにしてほしすぎる〜!! 三日も四日も大学の門の前で立ち尽くし学長に直談判して女子初の入学許可を取り付けたとか、この時代に官費でなく私費(借金)で、しかも当てもなくドイツ語も喋れないのにドイツ留学するとか(そもそも当時ドイツの大学は女子の入学を認めてなかったのに聴講を許される)、エピソードがいちいち強烈で面白すぎるんですが、自分のやりたいことを無理でもなんでもやり通す力、それ自体が才能だなぁとしみじみ思います。 それにしても高橋瑞さん、実家とは縁を切ってるし、お金もツテもないから常に貧乏で、そうでなくても女が一人で生きていくにはあまりにしんどい明治の世を生き抜いたどころか、医者になってドイツまで行ってるの、あまりにパワフル。ファンです。 本書を読んでいると、まだ男女平等なんてほど遠かった時代に男性占有の学問の世界に入っていく女子学生らに浴びせられる嫌がらせに胸が痛みます。『虎に翼』で寅ちゃんたちが同じように男子学生らに嫌がらせを受けていたのを思い出してイ〜〜〜!となっちゃいますね。 当時、女医が増えることを批判する「女医亡国論」が専門誌を賑わせたりもしたそうです。 端緒は、瑞の留学直前に『東京医事新誌』に掲載された「S・F」という人物による「本邦の女医」という記事である。「S・F」は、「女子に医学を研究せしむるや否やは重大の社会問題」であるとし、女医の「問題点」を三点挙げた。 〈まず、妊娠出産によって診療ができなくなる期間、患者をどうするのか。次に、そもそも女は「解剖および生理上」医学を修める資質があるのか。そして「下宿屋の二階に男子生徒と寝食を共にする」ことで生じる「艶聞」についてである。〉 「妊娠出産によって診療ができなくなる期間、患者をどうするのか」ってそれ2018年に発覚した医学部不正入試問題のときも似たようなこと言ってる人いましたよね……進歩ね〜〜とガックリしてしまいます。 瑞さんは我は我の道をゆくタイプなのでこういう社会問題に口は出さず、ただ自分の背中を見せながら後進には金を出して援助するタイプだったようですが、「女医亡国論」に堂々と誌上で反論する本多詮子さん(日本で四番目の公認女医)や、地元で地域医療をコツコツと続けて地元民からの信頼を得た生澤久野さん、女子のための初めての医学校を設立した吉岡彌生さんら、道なき道を切り開いた女性たちが未来の女医たちのためにそれぞれのやり方で闘う姿も本書には描かれています。 「雨垂れ石を穿つ」という言葉は寅ちゃんを絶望させた言葉でもありますが、やっぱりこうして先人のひとりひとりがこうして闘ってくれたかからこそ、女性医師が当たり前にいる今があるんだな〜と胸が熱くなります。と同時に、『虎に翼』を見たからこそ、医者になりたくてもなれなかった女性たちもたくさんいただろうな……と思って切なくもなりました。名前の残らなかった人たちの悔しさもまた、時代を推し進める原動力になったはず。 というわけで本書、『虎に翼』が好きだった人にもぜひぜひおすすめです!!
明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語田中ひかる読み終わった以前読んだ『明治のナイチンゲール 大関和物語』と同じく、田中ひかるさんのご著書です。本書はタイトルにある高橋瑞さんを中心としながらも、女性で初めて公認医師となった荻野吟子さん、二番目に公認女医となった生澤久野さん、東京女医学校を設立した吉岡彌生さんなど、明治の世に医学の世界に飛び込んだ女性たちの物語です。 女性で初めて医師になった吟子さんは美人で潔癖な女性というパブリックイメージだったそうですが、日本で三番目の公認女医になった本書の主人公、高橋瑞さんは道なき道を根性で突き進むバンカラっぷりがまるで正反対でむちゃくちゃ面白いです! 五分刈りに二重マント、まるで「男隠居」と陰口を言われるも、貧者からは金を取らない「義」の医師であり続けた高橋瑞、あまりにかっこよすぎて朝ドラにしてほしすぎる〜!! 三日も四日も大学の門の前で立ち尽くし学長に直談判して女子初の入学許可を取り付けたとか、この時代に官費でなく私費(借金)で、しかも当てもなくドイツ語も喋れないのにドイツ留学するとか(そもそも当時ドイツの大学は女子の入学を認めてなかったのに聴講を許される)、エピソードがいちいち強烈で面白すぎるんですが、自分のやりたいことを無理でもなんでもやり通す力、それ自体が才能だなぁとしみじみ思います。 それにしても高橋瑞さん、実家とは縁を切ってるし、お金もツテもないから常に貧乏で、そうでなくても女が一人で生きていくにはあまりにしんどい明治の世を生き抜いたどころか、医者になってドイツまで行ってるの、あまりにパワフル。ファンです。 本書を読んでいると、まだ男女平等なんてほど遠かった時代に男性占有の学問の世界に入っていく女子学生らに浴びせられる嫌がらせに胸が痛みます。『虎に翼』で寅ちゃんたちが同じように男子学生らに嫌がらせを受けていたのを思い出してイ〜〜〜!となっちゃいますね。 当時、女医が増えることを批判する「女医亡国論」が専門誌を賑わせたりもしたそうです。 端緒は、瑞の留学直前に『東京医事新誌』に掲載された「S・F」という人物による「本邦の女医」という記事である。「S・F」は、「女子に医学を研究せしむるや否やは重大の社会問題」であるとし、女医の「問題点」を三点挙げた。 〈まず、妊娠出産によって診療ができなくなる期間、患者をどうするのか。次に、そもそも女は「解剖および生理上」医学を修める資質があるのか。そして「下宿屋の二階に男子生徒と寝食を共にする」ことで生じる「艶聞」についてである。〉 「妊娠出産によって診療ができなくなる期間、患者をどうするのか」ってそれ2018年に発覚した医学部不正入試問題のときも似たようなこと言ってる人いましたよね……進歩ね〜〜とガックリしてしまいます。 瑞さんは我は我の道をゆくタイプなのでこういう社会問題に口は出さず、ただ自分の背中を見せながら後進には金を出して援助するタイプだったようですが、「女医亡国論」に堂々と誌上で反論する本多詮子さん(日本で四番目の公認女医)や、地元で地域医療をコツコツと続けて地元民からの信頼を得た生澤久野さん、女子のための初めての医学校を設立した吉岡彌生さんら、道なき道を切り開いた女性たちが未来の女医たちのためにそれぞれのやり方で闘う姿も本書には描かれています。 「雨垂れ石を穿つ」という言葉は寅ちゃんを絶望させた言葉でもありますが、やっぱりこうして先人のひとりひとりがこうして闘ってくれたかからこそ、女性医師が当たり前にいる今があるんだな〜と胸が熱くなります。と同時に、『虎に翼』を見たからこそ、医者になりたくてもなれなかった女性たちもたくさんいただろうな……と思って切なくもなりました。名前の残らなかった人たちの悔しさもまた、時代を推し進める原動力になったはず。 というわけで本書、『虎に翼』が好きだった人にもぜひぜひおすすめです!! - 2026年1月23日
 八月の銀の雪伊与原新読み終わったどの短編も良かったけど、最後に収録された短編「十万年の生物」がすごかった。 報告書の改竄を要求されたことがきっかけで長年働いてきた原発を辞めた人と、戦時中に風船爆弾の開発に携わった気象台の技師の息子、海辺の空に舞い上がる凧をきっかけに言葉を交わすことになった二人の物語がめちゃめちゃ「今」だなと思った。 伊与原先生の作品どれも面白いんだけど、戦争や災害における科学者のリグレットが描かれるとき、とくにアツいなと思う。
八月の銀の雪伊与原新読み終わったどの短編も良かったけど、最後に収録された短編「十万年の生物」がすごかった。 報告書の改竄を要求されたことがきっかけで長年働いてきた原発を辞めた人と、戦時中に風船爆弾の開発に携わった気象台の技師の息子、海辺の空に舞い上がる凧をきっかけに言葉を交わすことになった二人の物語がめちゃめちゃ「今」だなと思った。 伊与原先生の作品どれも面白いんだけど、戦争や災害における科学者のリグレットが描かれるとき、とくにアツいなと思う。 - 2026年1月22日
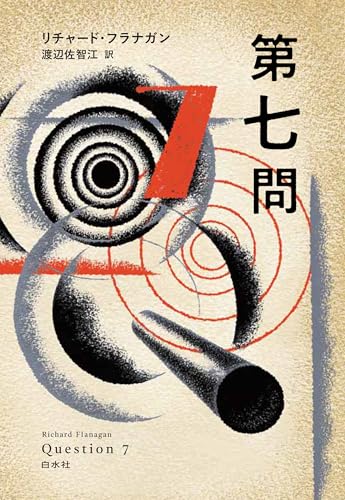 第七問リチャード・フラナガン,渡辺佐智江読み終わった〈その日の広島に残されているものは、問いだけである。〉 なぜわたしたちは戦争をするのか。なぜわたしたちは互いに対して暴虐な行為をするのだろうか。 原子爆弾の開発の歴史、捕虜として日本で強制労働させられながら生き延びた父の物語、凄惨な侵略を受けたタスマニアというルーツ、本物の死を覚悟した瞬間、その記憶。 〈それが決して答えの出ない問いであっても、わたしたちはその問いを問いつづけなければならない。〉 問いつづけること。 たぶん答えは記憶と言葉の中にある。だから私たちには歴史も物語も必要なんだと思った。 世界の足場が危うくなる今、この本を読めて良かったと思う。切実に。
第七問リチャード・フラナガン,渡辺佐智江読み終わった〈その日の広島に残されているものは、問いだけである。〉 なぜわたしたちは戦争をするのか。なぜわたしたちは互いに対して暴虐な行為をするのだろうか。 原子爆弾の開発の歴史、捕虜として日本で強制労働させられながら生き延びた父の物語、凄惨な侵略を受けたタスマニアというルーツ、本物の死を覚悟した瞬間、その記憶。 〈それが決して答えの出ない問いであっても、わたしたちはその問いを問いつづけなければならない。〉 問いつづけること。 たぶん答えは記憶と言葉の中にある。だから私たちには歴史も物語も必要なんだと思った。 世界の足場が危うくなる今、この本を読めて良かったと思う。切実に。 - 2026年1月1日
 悪人吉田修一読み終わった平戸の灯台に行ったので不意に読み返したくなった。ちょうど実家にあったし。多分刊行当時(2007年)に読んでそれ以来だと思う。 メインの登場人物だけじゃなく数多くの関係者の視点が次々と重なるドキュメンタリーチックな展開に序盤からぐっと引き込まれる。地方を舞台にしたピカレスクノベルとしてはクラシックレベルに強度の高い作品だなと改めて読んで思った。 〈祐一の車は、唐津市内を抜けて、呼子へ向かう道を走っていた。背後に流れる景色は変わっていくのだが、いくら走っても道の先にはゴールがない。国道が終われば県道に繋がり、県道を抜ければ市道や町道が伸びている。光代はダッシュボードに置かれた道路地図を手に取った。適当なページを捲ると、全面に色とりどりの道が記載されている。オレンジ色の国道、緑色の県道、青い地方 道路に、白い路地。まるでここに書かれた無数の道路が、自分と祐一が乗るこの車をがんじがらめにしている網のように思えた。仕事をさぼって好きな人とドライブしているだけなのに、逃げても逃げても道は追いかけてくる。走っても走っても道はどこかへ繋がっている。〉 この小説を読むと地方の閉塞感を強く感じるのだけど、〈閉塞感〉という言葉には閉じ込められるようなイメージがある。だけど実際に車を走らせれば、その道に終わりがないこと、出口がないことに軽く絶望を感じてしまう気持ちが体感としてよくわかる。ここすごくいい言語化だなと思った。 今読むと恋愛至上主義な時代だな…とも感じるし、追い立てられて恋愛に救われようとする終盤も今ならどうだろうも考えたりもするのだけど、それでも逃避行からのラストまでの二人の切実さやロマンチックさは時代を問わず良いスパイスだなと思ったりもした。 女性の描写だけが過剰に美化されることも露悪化されることもなく、目を背けたいような愚かさは男女関係なく描かれていたのも今読むとかなりフラットだなと思う。 〈祐一は車で何度か走ったことのある佐賀の風景を思い描いた。長崎と違い、気が抜けてしまうほど平坦な土地で、どこまでも単調な街道が伸びている。前にも後ろにも山はない。急な坂道もなければ、石畳の路地もない。真新しいアスファルト道路がただ真っすぐに伸びている。 道の両側には本屋やパチンコ屋やファーストフードの大型店が並んでいる。どの店舗にも大きな駐車場があり、たくさん車は停まっているのに、なぜかその風景の中に人だけがいない。〉 このもめっちゃわかるーーー!!!と思いながら読んだ。ロードノベルとしての再現度の高さもこの作品の魅力のひとつ。 普遍性というのも小説の価値の一つだけど、一方でそこに住んでる人間にしかわからないような空気や情報を物語に閉じ込めるのもまた小説の価値だなと思った。 ひさびさの再読、面白かった。また10年後くらいに読み返して自分がどう感じるか知りたいな。
悪人吉田修一読み終わった平戸の灯台に行ったので不意に読み返したくなった。ちょうど実家にあったし。多分刊行当時(2007年)に読んでそれ以来だと思う。 メインの登場人物だけじゃなく数多くの関係者の視点が次々と重なるドキュメンタリーチックな展開に序盤からぐっと引き込まれる。地方を舞台にしたピカレスクノベルとしてはクラシックレベルに強度の高い作品だなと改めて読んで思った。 〈祐一の車は、唐津市内を抜けて、呼子へ向かう道を走っていた。背後に流れる景色は変わっていくのだが、いくら走っても道の先にはゴールがない。国道が終われば県道に繋がり、県道を抜ければ市道や町道が伸びている。光代はダッシュボードに置かれた道路地図を手に取った。適当なページを捲ると、全面に色とりどりの道が記載されている。オレンジ色の国道、緑色の県道、青い地方 道路に、白い路地。まるでここに書かれた無数の道路が、自分と祐一が乗るこの車をがんじがらめにしている網のように思えた。仕事をさぼって好きな人とドライブしているだけなのに、逃げても逃げても道は追いかけてくる。走っても走っても道はどこかへ繋がっている。〉 この小説を読むと地方の閉塞感を強く感じるのだけど、〈閉塞感〉という言葉には閉じ込められるようなイメージがある。だけど実際に車を走らせれば、その道に終わりがないこと、出口がないことに軽く絶望を感じてしまう気持ちが体感としてよくわかる。ここすごくいい言語化だなと思った。 今読むと恋愛至上主義な時代だな…とも感じるし、追い立てられて恋愛に救われようとする終盤も今ならどうだろうも考えたりもするのだけど、それでも逃避行からのラストまでの二人の切実さやロマンチックさは時代を問わず良いスパイスだなと思ったりもした。 女性の描写だけが過剰に美化されることも露悪化されることもなく、目を背けたいような愚かさは男女関係なく描かれていたのも今読むとかなりフラットだなと思う。 〈祐一は車で何度か走ったことのある佐賀の風景を思い描いた。長崎と違い、気が抜けてしまうほど平坦な土地で、どこまでも単調な街道が伸びている。前にも後ろにも山はない。急な坂道もなければ、石畳の路地もない。真新しいアスファルト道路がただ真っすぐに伸びている。 道の両側には本屋やパチンコ屋やファーストフードの大型店が並んでいる。どの店舗にも大きな駐車場があり、たくさん車は停まっているのに、なぜかその風景の中に人だけがいない。〉 このもめっちゃわかるーーー!!!と思いながら読んだ。ロードノベルとしての再現度の高さもこの作品の魅力のひとつ。 普遍性というのも小説の価値の一つだけど、一方でそこに住んでる人間にしかわからないような空気や情報を物語に閉じ込めるのもまた小説の価値だなと思った。 ひさびさの再読、面白かった。また10年後くらいに読み返して自分がどう感じるか知りたいな。 - 2025年12月30日
 わたしもナグネだから伊東順子読み終わった激動の母国を離れ海外で生きることを選んだ、もしくはそうせざるを得なかった韓国人たちへのインタビューを母体としたエッセイ。インタビュイーたちの波瀾万丈な人生に惹かれると同時に、それを語らせた伊東さんもすごいなと思う。 対馬に四三事件の被害者の遺体がたくさん流れ着いていたという話は初めて知った。 〈一九八〇年代、世界中で強権政治に反対する運動が起きていた。その中で韓国や台湾のように民主化を実現させた国もあれば、ミャンマーや中国のように民主化の夢が踏みにじられた国もあった。弾圧から逃れた人たちの一部は日本に、また民主化後の韓国にもやってきた。 第二次世界大戦後、アジアで曲がりなりにも民主主義的な制度を許されたのは日本だけだった。たとえ米占領軍から与えられたものだとしても、それが不完全な民主主義だったとしても(そもそも民主主義に完成形はなく、いつだって途上にある)、私たちには言論と表現の自由があった。そこに韓国も加わった。 今、アジアの民主主義にとって日韓の役割はとても重要だと思う。そうだ、私たちはアジアの民主主義のベースキャンプを作ろう。キムさんとそんな話をした。〉 これを読んで、日本の民主主義は日本に住む人だけのものではないんだな、と目が覚めるような気がした。日本はアジアの他国に対しては侵略したという負の歴史があるけれど、戦後は自分の政府も他の国も軍事政権の批判することのできる言論の自由を手に入れたし、軍事政権下で弾圧され国外に脱出せざるをえなかった韓国や中国やミャンマーの人びとを受け止めてきた歴史がある。そういうことを積み重ねてきたことには自信を持っていいはずだし、そういう歴史がもっとフューチャーされたらいいんじゃないかなと思った。
わたしもナグネだから伊東順子読み終わった激動の母国を離れ海外で生きることを選んだ、もしくはそうせざるを得なかった韓国人たちへのインタビューを母体としたエッセイ。インタビュイーたちの波瀾万丈な人生に惹かれると同時に、それを語らせた伊東さんもすごいなと思う。 対馬に四三事件の被害者の遺体がたくさん流れ着いていたという話は初めて知った。 〈一九八〇年代、世界中で強権政治に反対する運動が起きていた。その中で韓国や台湾のように民主化を実現させた国もあれば、ミャンマーや中国のように民主化の夢が踏みにじられた国もあった。弾圧から逃れた人たちの一部は日本に、また民主化後の韓国にもやってきた。 第二次世界大戦後、アジアで曲がりなりにも民主主義的な制度を許されたのは日本だけだった。たとえ米占領軍から与えられたものだとしても、それが不完全な民主主義だったとしても(そもそも民主主義に完成形はなく、いつだって途上にある)、私たちには言論と表現の自由があった。そこに韓国も加わった。 今、アジアの民主主義にとって日韓の役割はとても重要だと思う。そうだ、私たちはアジアの民主主義のベースキャンプを作ろう。キムさんとそんな話をした。〉 これを読んで、日本の民主主義は日本に住む人だけのものではないんだな、と目が覚めるような気がした。日本はアジアの他国に対しては侵略したという負の歴史があるけれど、戦後は自分の政府も他の国も軍事政権の批判することのできる言論の自由を手に入れたし、軍事政権下で弾圧され国外に脱出せざるをえなかった韓国や中国やミャンマーの人びとを受け止めてきた歴史がある。そういうことを積み重ねてきたことには自信を持っていいはずだし、そういう歴史がもっとフューチャーされたらいいんじゃないかなと思った。 - 2025年12月26日
 現代思想2025年11月臨時増刊号 特集=ラフカディオ・ハーン/小泉八雲三浦佑之,小泉凡,岩田重則,平藤喜久子,東雅夫,福嶋亮大読んでるばけばけと重ね合わせながら読んでる。 資本主義、キリスト教、西洋文明という〈大きなもの〉に背を向け、周縁の地を旅し、周縁の文化を愛し、最後は日本に骨を埋めた。 こんな生き方、なかなかできることではない。自分の考えや思想を強く信じていたんだと思う。
現代思想2025年11月臨時増刊号 特集=ラフカディオ・ハーン/小泉八雲三浦佑之,小泉凡,岩田重則,平藤喜久子,東雅夫,福嶋亮大読んでるばけばけと重ね合わせながら読んでる。 資本主義、キリスト教、西洋文明という〈大きなもの〉に背を向け、周縁の地を旅し、周縁の文化を愛し、最後は日本に骨を埋めた。 こんな生き方、なかなかできることではない。自分の考えや思想を強く信じていたんだと思う。 - 2025年12月24日
 エトセトラ VOL.14福田和子,高井ゆと里読んでる北原恵さんによる「防空壕の女―― ジェンダー/植民地主義から見る 戦争画 の視点 」 戦争画はいろいろあっても「空襲」を描いたものが少ないのは何故か、というこちらの論考がとても興味深かった。 〈上空の爆撃機から地上を見下ろす視点で描いた戦争画は、一般に「前線」の絵にカテゴライズされる。一方、市民の暮らす空間は「銃後」とされる。だが、空襲時には、前線を飛ぶ爆撃機の下の地上は戦場である。つまり空襲は、市民の暮らす「銃後」と「前線」の境界を揺るがす出来事であり、表象なのである。 地上からの防空が機能せず、一方的に被害を受けるだけの空襲の図像は、日本軍や国家が完敗した「敗北の象徴」だと言えないか。被害者としての「空襲」を描いた日本の美術作品が少なく感じられるのは、もしかしたら、「女子供を守る」という戦争の大義が崩れかねない男性性や軍隊・国家のアイデンティティに関係がないだろうか。そして、「銃後=女」「前線=「男」にジェンダー化した二分法は、民間人の空襲被害者への補償がなされないことを自然化しているのではないか。〉 空襲は「敗北の象徴」。『火垂るの墓』で市民目線の空襲を徹底的に描いた高畑勲の特異性に気付かされる。
エトセトラ VOL.14福田和子,高井ゆと里読んでる北原恵さんによる「防空壕の女―― ジェンダー/植民地主義から見る 戦争画 の視点 」 戦争画はいろいろあっても「空襲」を描いたものが少ないのは何故か、というこちらの論考がとても興味深かった。 〈上空の爆撃機から地上を見下ろす視点で描いた戦争画は、一般に「前線」の絵にカテゴライズされる。一方、市民の暮らす空間は「銃後」とされる。だが、空襲時には、前線を飛ぶ爆撃機の下の地上は戦場である。つまり空襲は、市民の暮らす「銃後」と「前線」の境界を揺るがす出来事であり、表象なのである。 地上からの防空が機能せず、一方的に被害を受けるだけの空襲の図像は、日本軍や国家が完敗した「敗北の象徴」だと言えないか。被害者としての「空襲」を描いた日本の美術作品が少なく感じられるのは、もしかしたら、「女子供を守る」という戦争の大義が崩れかねない男性性や軍隊・国家のアイデンティティに関係がないだろうか。そして、「銃後=女」「前線=「男」にジェンダー化した二分法は、民間人の空襲被害者への補償がなされないことを自然化しているのではないか。〉 空襲は「敗北の象徴」。『火垂るの墓』で市民目線の空襲を徹底的に描いた高畑勲の特異性に気付かされる。 - 2025年12月20日
 わたしが初めて買った韓国の小説はハン・ガンの『菜食主義者』だった。〈新しい韓国の文学〉と名付けられた、やわらかくて白い表紙のシリーズの一冊目をどういう経緯で買ったのか、自分でもよく覚えていない。だけどすぐに読まず積んだまま、2016年のハン・ガンのブッカー賞受賞のニュースを聞いて慌てて読んだのを覚えている。その『菜食主義者』こそこの本の著者・金承福さんのつくった出版社クオンが一番初めに出した本だった。 クオンの本ではないけど同じ2016年、日本では『82年生まれ、キム・ジヨン』(斎藤真理子さんの訳)が出て日本でも女性の間で大きな共感を呼んだ。 それからもうすぐ10年になる。どれだけたくさんの韓国の小説を読んできただろう。二つの国の文学と文学者たちを結んでくれた金さんたちの情熱あってのことだなぁとしみじみ感謝したくなった。 神保町にあるクオンの本屋チェッコリ、実はまだ行ったことないので来年はぜひ行ってみたい。 〈一九七〇年に光州で生まれ八歳まで暮らしたハン・ガンは、「何があっても人間であり続けるということは何なのだろうか」と自問自答しながら小説を書いてきたと、ノーベル文学賞受賞記念講演で語った。 これは私自身もずっと前から自分自身に投げかけてきた問いでもある。人間であり続けるとは何だろうか。ただ人間であり続けるのではなく、「何があっても」という切実な前提がついた質問。人間であり続けるということは、結局、その問いかけ一つを手放さないことなのかもしれない。〉
わたしが初めて買った韓国の小説はハン・ガンの『菜食主義者』だった。〈新しい韓国の文学〉と名付けられた、やわらかくて白い表紙のシリーズの一冊目をどういう経緯で買ったのか、自分でもよく覚えていない。だけどすぐに読まず積んだまま、2016年のハン・ガンのブッカー賞受賞のニュースを聞いて慌てて読んだのを覚えている。その『菜食主義者』こそこの本の著者・金承福さんのつくった出版社クオンが一番初めに出した本だった。 クオンの本ではないけど同じ2016年、日本では『82年生まれ、キム・ジヨン』(斎藤真理子さんの訳)が出て日本でも女性の間で大きな共感を呼んだ。 それからもうすぐ10年になる。どれだけたくさんの韓国の小説を読んできただろう。二つの国の文学と文学者たちを結んでくれた金さんたちの情熱あってのことだなぁとしみじみ感謝したくなった。 神保町にあるクオンの本屋チェッコリ、実はまだ行ったことないので来年はぜひ行ってみたい。 〈一九七〇年に光州で生まれ八歳まで暮らしたハン・ガンは、「何があっても人間であり続けるということは何なのだろうか」と自問自答しながら小説を書いてきたと、ノーベル文学賞受賞記念講演で語った。 これは私自身もずっと前から自分自身に投げかけてきた問いでもある。人間であり続けるとは何だろうか。ただ人間であり続けるのではなく、「何があっても」という切実な前提がついた質問。人間であり続けるということは、結局、その問いかけ一つを手放さないことなのかもしれない。〉 - 2025年12月18日
 言葉のトランジットグレゴリー・ケズナジャット読み終わった先日読んだ『トラジェクトリー』の著者のエッセイ。中東のルーツを持ち、アメリカで生まれ育ち、日本に長らく暮らしながら、インターネットのある時代もない時代も旅をしてきたグレゴリーさんの思考に浸る。 グレゴリーさんがオーストラリアのバースである女性作家の作品を見た時のこと。 〈作品に添えられた、ヒル自身の説明文によると、これらの絵に描かれているのは、一九五〇年代にオーストラリアで行われた強制的同化の政策だそうだ。先住民のコミュニティーは核家族ごとに分けられて国家が用意した住宅で、白人の指導者の下、新しい生活習慣を教え込まれたという。ヒル自身もその制度を経験させられたのだ。 ヒルの絵を見ながら、僕が到着したときから抱いていた違和感が、より明確になってくる。この土地まで広がり、その他の言葉と文化を容赦なく追い出す英語の脅威を感じずにいられない。 皮肉なのは、いうまでもなく僕が生まれた故郷にも似たような歴史があるということだ。先住民との対立は別に隠された歴史ではない。過酷な未開の地へ果敢に臨んだ開拓者なんていうイメージは、国民的な伝説となっている。日本語で「欧米」と「西洋」という言葉が違和感もなくほぼ同義的に使われているくらい、北米大陸におけるヨーロッパの植民地主義は残酷で徹底的なものだった。二十世紀に入った時点で、僕の故郷には強制的に同化させるほどの先住民はもはやいなかった。 馴染みの言葉と文化がバースにもあるということに対して僕が違和感を覚えるなら、先 に故郷の歴史から考えるのがいいだろう。〉 こういう視点にハッとさせられる。
言葉のトランジットグレゴリー・ケズナジャット読み終わった先日読んだ『トラジェクトリー』の著者のエッセイ。中東のルーツを持ち、アメリカで生まれ育ち、日本に長らく暮らしながら、インターネットのある時代もない時代も旅をしてきたグレゴリーさんの思考に浸る。 グレゴリーさんがオーストラリアのバースである女性作家の作品を見た時のこと。 〈作品に添えられた、ヒル自身の説明文によると、これらの絵に描かれているのは、一九五〇年代にオーストラリアで行われた強制的同化の政策だそうだ。先住民のコミュニティーは核家族ごとに分けられて国家が用意した住宅で、白人の指導者の下、新しい生活習慣を教え込まれたという。ヒル自身もその制度を経験させられたのだ。 ヒルの絵を見ながら、僕が到着したときから抱いていた違和感が、より明確になってくる。この土地まで広がり、その他の言葉と文化を容赦なく追い出す英語の脅威を感じずにいられない。 皮肉なのは、いうまでもなく僕が生まれた故郷にも似たような歴史があるということだ。先住民との対立は別に隠された歴史ではない。過酷な未開の地へ果敢に臨んだ開拓者なんていうイメージは、国民的な伝説となっている。日本語で「欧米」と「西洋」という言葉が違和感もなくほぼ同義的に使われているくらい、北米大陸におけるヨーロッパの植民地主義は残酷で徹底的なものだった。二十世紀に入った時点で、僕の故郷には強制的に同化させるほどの先住民はもはやいなかった。 馴染みの言葉と文化がバースにもあるということに対して僕が違和感を覚えるなら、先 に故郷の歴史から考えるのがいいだろう。〉 こういう視点にハッとさせられる。 - 2025年12月17日
 「なむ」の来歴斎藤真理子読み終わった翻訳家・斎藤真理子さんのエッセイ。韓国、沖縄、そして東京。さまざまな土地に根を下ろしながら言葉や文学を通して社会を見る斎藤さんの文章、とても素敵。 〈読むたびに尽きない発見がある。そして随所に戦争の匂いが漂う。「これが正しい事だと云って/戦争が起ったこれが正しい事だと云って/終戦になった」(「その眸」)と振り返るのは住友銀行の深山杏子さん。この詩集には従軍、抑留、戦災、引揚げの記憶と共に、朝鮮戦争の勃発と日本の再軍備という現実が書かれている。隣の戦争で日本経済が潤っていくのを、多くの人が窓口でひたひたと感じていたはずだ。詩でなければできないやり方で、歴史の中の個人が浮き彫りになっている。この国はどこをぐるりと一周して今に至ったのかと、七十年前の本を読みながら考える。〉 〈何てつまんないんだろう! でも、気がきいてなくても、「イイネ」がつかなくても、自分にとって違和感のない語彙を積み重ねて地道に考えていかないと、これからの時代、自分がもたない。〉
「なむ」の来歴斎藤真理子読み終わった翻訳家・斎藤真理子さんのエッセイ。韓国、沖縄、そして東京。さまざまな土地に根を下ろしながら言葉や文学を通して社会を見る斎藤さんの文章、とても素敵。 〈読むたびに尽きない発見がある。そして随所に戦争の匂いが漂う。「これが正しい事だと云って/戦争が起ったこれが正しい事だと云って/終戦になった」(「その眸」)と振り返るのは住友銀行の深山杏子さん。この詩集には従軍、抑留、戦災、引揚げの記憶と共に、朝鮮戦争の勃発と日本の再軍備という現実が書かれている。隣の戦争で日本経済が潤っていくのを、多くの人が窓口でひたひたと感じていたはずだ。詩でなければできないやり方で、歴史の中の個人が浮き彫りになっている。この国はどこをぐるりと一周して今に至ったのかと、七十年前の本を読みながら考える。〉 〈何てつまんないんだろう! でも、気がきいてなくても、「イイネ」がつかなくても、自分にとって違和感のない語彙を積み重ねて地道に考えていかないと、これからの時代、自分がもたない。〉 - 2025年12月10日
 明治のナイチンゲール 大関和物語田中ひかる読み終わった時期朝ドラの原案と聞いて読んでみたのだけど、出自だけ見ると大関和さんは明治に没落した武家の娘という、ばけばけのモデルの小泉節さんと同じ境遇だった。大和さんは嫁に行ったけど苦労して離婚し、まだシングルマザーという言葉がない時代にシングルマザーになる。 明治は女に人権のない時代だが、アメリカから来た宣教師や女性の教育者たちによって日本にもフェミニズムの風が吹く。大和さんはキリスト教や英語、看護など海外から学びながら、それが難しい時代に「女の自立」を実現していたことがまぶしい。 朝ドラの民としては廃娼運動やクリスチャンである大和さんの一面がどう描かれるのか楽しみ。
明治のナイチンゲール 大関和物語田中ひかる読み終わった時期朝ドラの原案と聞いて読んでみたのだけど、出自だけ見ると大関和さんは明治に没落した武家の娘という、ばけばけのモデルの小泉節さんと同じ境遇だった。大和さんは嫁に行ったけど苦労して離婚し、まだシングルマザーという言葉がない時代にシングルマザーになる。 明治は女に人権のない時代だが、アメリカから来た宣教師や女性の教育者たちによって日本にもフェミニズムの風が吹く。大和さんはキリスト教や英語、看護など海外から学びながら、それが難しい時代に「女の自立」を実現していたことがまぶしい。 朝ドラの民としては廃娼運動やクリスチャンである大和さんの一面がどう描かれるのか楽しみ。 - 2025年11月30日
 フクロウ准教授の午睡伊与原新読み終わった
フクロウ准教授の午睡伊与原新読み終わった - 2025年11月28日
 シミズくんとヤマウチくん われら非実在の恋人たち山内尚,清水えす子
シミズくんとヤマウチくん われら非実在の恋人たち山内尚,清水えす子
読み込み中...

