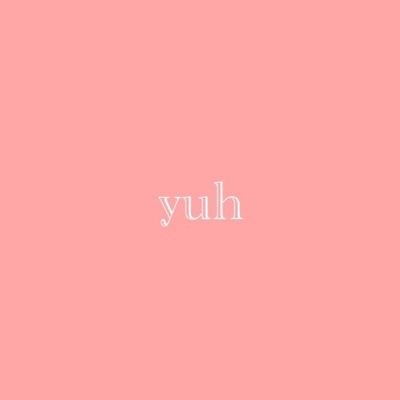
さくらゆう
@skryuh_
- 2026年2月16日
 猫がいれば、そこが我が家ヤマザキ・マリ読んだ良い本でした。 『テルマエロマエ』の作者さんだと知らずに手に取りましたが、地球規模で大移動して生活していて、幼少期から大人になってもどこで暮らしている時も動物や植物など命を尊んでいて、生き方や考え方がとても尊敬できるなと思いました。 『テルマエロマエ』読んでみたくなりました。 猫はかわいい。
猫がいれば、そこが我が家ヤマザキ・マリ読んだ良い本でした。 『テルマエロマエ』の作者さんだと知らずに手に取りましたが、地球規模で大移動して生活していて、幼少期から大人になってもどこで暮らしている時も動物や植物など命を尊んでいて、生き方や考え方がとても尊敬できるなと思いました。 『テルマエロマエ』読んでみたくなりました。 猫はかわいい。 - 2026年2月14日
 贈り物の本安達茉莉子,有松遼一,浅生鴨,牟田都子,青山ゆみこ,青木奈緒読んだ『娑婆は桜』 祖父が頭と手指の体操のためにノートに日記を認めて残した言葉 祖父の記憶や思考が失われはじめた頃、日記には「娑婆は桜」という言葉が増える。他には何度も書かれた自宅の住所。そして孫の誕生日。 「一日でも長く、共にいきてゆけるよう、ガンバッてみようと思っている」 そして、次のページにはまた「娑婆は桜」。 「死ぬまでにあと何回桜を見れるだろうか」という言葉を昨年何かのつぶやきで拝見して以来、このことを考えるようになった。 きっとこのおじいさんも桜を深く味わっていたのかもしれないし、記憶の中の桜を思い起こしていたのかもしれない。 自分が残していく人たちを思い、「一日でも長く、共に」と思う気持ちは、どれほどのものかと、涙が止まらない。 命は儚い。
贈り物の本安達茉莉子,有松遼一,浅生鴨,牟田都子,青山ゆみこ,青木奈緒読んだ『娑婆は桜』 祖父が頭と手指の体操のためにノートに日記を認めて残した言葉 祖父の記憶や思考が失われはじめた頃、日記には「娑婆は桜」という言葉が増える。他には何度も書かれた自宅の住所。そして孫の誕生日。 「一日でも長く、共にいきてゆけるよう、ガンバッてみようと思っている」 そして、次のページにはまた「娑婆は桜」。 「死ぬまでにあと何回桜を見れるだろうか」という言葉を昨年何かのつぶやきで拝見して以来、このことを考えるようになった。 きっとこのおじいさんも桜を深く味わっていたのかもしれないし、記憶の中の桜を思い起こしていたのかもしれない。 自分が残していく人たちを思い、「一日でも長く、共に」と思う気持ちは、どれほどのものかと、涙が止まらない。 命は儚い。 - 2026年2月8日
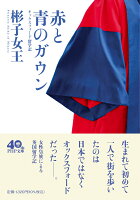 赤と青のガウン彬子女王彬子女王の英国留学記でした。 少し前(といっても数ヶ月、もしくは数年かもしれない)にXでこの本のことを知り、興味を持って積ん読にしていたものをようやく読みました。 一般人の留学では、普通はないだろうなという出来事(故エリザベス女王とのマンツーマンのお茶会など)も拝見できたり、一般人が普通に生きているだけでは体験できない事柄をこうやって文章にしてもらえるのはありがたいことだなぁと思いました。 彬子女王は英国での日本美術について研究されていたんですね。 昨年、原田マハさんの『たゆたえども沈ます』でゴッホやその周りの方々が日本美術に興味関心を持っていく時代の様子を読んだり、ちいさな美術館の学芸員さんの『学芸員が教える日本美術が楽しくなる話』を読んだりして、日本美術への関心が高まっているところでしたので、益々面白く読ませていただきました。 各章題に四字熟語を使用されているところも勉強になりますね。
赤と青のガウン彬子女王彬子女王の英国留学記でした。 少し前(といっても数ヶ月、もしくは数年かもしれない)にXでこの本のことを知り、興味を持って積ん読にしていたものをようやく読みました。 一般人の留学では、普通はないだろうなという出来事(故エリザベス女王とのマンツーマンのお茶会など)も拝見できたり、一般人が普通に生きているだけでは体験できない事柄をこうやって文章にしてもらえるのはありがたいことだなぁと思いました。 彬子女王は英国での日本美術について研究されていたんですね。 昨年、原田マハさんの『たゆたえども沈ます』でゴッホやその周りの方々が日本美術に興味関心を持っていく時代の様子を読んだり、ちいさな美術館の学芸員さんの『学芸員が教える日本美術が楽しくなる話』を読んだりして、日本美術への関心が高まっているところでしたので、益々面白く読ませていただきました。 各章題に四字熟語を使用されているところも勉強になりますね。 - 2026年2月7日
- 2026年2月7日
 彼女たちの場合は江國香織好きな作家好きな装丁読んだ「かわいい子には旅をさせよ」 それがよく分かるような物語でした。 実際には大人が旅をさせたわけではなく、子どもたちが勝手に旅に出て行ったのですが。 学校で勉強するだけでは知ることができないことを、17歳と14歳の少女たちはたくさん経験して学んだ。 「従姉に誘拐された」とばかり主張する父親に、「あの子たちは2人で旅に出たのよ」と言い返す母親の言葉をとても好ましく思いました。 17歳と14歳の少女2人のアメリカ東西横断旅物語。
彼女たちの場合は江國香織好きな作家好きな装丁読んだ「かわいい子には旅をさせよ」 それがよく分かるような物語でした。 実際には大人が旅をさせたわけではなく、子どもたちが勝手に旅に出て行ったのですが。 学校で勉強するだけでは知ることができないことを、17歳と14歳の少女たちはたくさん経験して学んだ。 「従姉に誘拐された」とばかり主張する父親に、「あの子たちは2人で旅に出たのよ」と言い返す母親の言葉をとても好ましく思いました。 17歳と14歳の少女2人のアメリカ東西横断旅物語。 - 2026年1月31日
 本と歩く人カルステン・ヘン,川東雅樹読んだ街に灯りをともすような本。最後の最後に穏やかで優しい気持ちになれる。みんなそれぞれに問題を抱えていて、それを解決するのは本だったり、本を届けてくれる人だったり、本を通して繋がれた人たちだったり。 「物語はハッピーエンドじゃないとね」 というように温かな終わりでした。 洋書特有の言い回しや会話劇も魅力。
本と歩く人カルステン・ヘン,川東雅樹読んだ街に灯りをともすような本。最後の最後に穏やかで優しい気持ちになれる。みんなそれぞれに問題を抱えていて、それを解決するのは本だったり、本を届けてくれる人だったり、本を通して繋がれた人たちだったり。 「物語はハッピーエンドじゃないとね」 というように温かな終わりでした。 洋書特有の言い回しや会話劇も魅力。 - 2026年1月24日
 ぼくは勉強ができない山田詠美読んだ時代を感じさせない本だなと思いました。 独特なリズムの読み心地。 こういう読み心地は初めてでした。 ぬるぬるっと入り込む感じ。 「読む」よりも「視る」というような感じ。 性にあけすけ、だけどいやらしいわけではない。 純情さもあり、「生物の性」に誠実なためのあけすけ感。 父親はおらず、母と祖父と暮らす、「人好き」のするお調子者の高校生男子が主人公。 学校の成績は悪いけれど、物事の捉え方が達観していたりして、固定観念で決め付けて絡んでくる人たちをバッサリ切る話術に聞き入ってしまいます。 主人公の周りにいる、豊富な登場人物たちが、いろんな物事を勃発させて、その都度いろんなことを考える。母と祖父の曲者感や、三世代親子の会話がテンポが良く愛あるユーモアに満ちていて好きでした。 「ぼくは勉強ができない」 「あなたの高尚な悩み」 「雑音の順位」 「健全な精神」 「○をつけよ」 「時差ぼけ回復」 「賢者の皮むき」 「ぼくは勉強ができる」 「番外編・眠れる分度器」 短編それぞれのタイトルからも主人公の皮肉な感じが垣間見れて「イイネ」。 人間には余白が必要で、余白があるから魅力的になる。 そんな感じを教えてくれます。
ぼくは勉強ができない山田詠美読んだ時代を感じさせない本だなと思いました。 独特なリズムの読み心地。 こういう読み心地は初めてでした。 ぬるぬるっと入り込む感じ。 「読む」よりも「視る」というような感じ。 性にあけすけ、だけどいやらしいわけではない。 純情さもあり、「生物の性」に誠実なためのあけすけ感。 父親はおらず、母と祖父と暮らす、「人好き」のするお調子者の高校生男子が主人公。 学校の成績は悪いけれど、物事の捉え方が達観していたりして、固定観念で決め付けて絡んでくる人たちをバッサリ切る話術に聞き入ってしまいます。 主人公の周りにいる、豊富な登場人物たちが、いろんな物事を勃発させて、その都度いろんなことを考える。母と祖父の曲者感や、三世代親子の会話がテンポが良く愛あるユーモアに満ちていて好きでした。 「ぼくは勉強ができない」 「あなたの高尚な悩み」 「雑音の順位」 「健全な精神」 「○をつけよ」 「時差ぼけ回復」 「賢者の皮むき」 「ぼくは勉強ができる」 「番外編・眠れる分度器」 短編それぞれのタイトルからも主人公の皮肉な感じが垣間見れて「イイネ」。 人間には余白が必要で、余白があるから魅力的になる。 そんな感じを教えてくれます。 - 2026年1月14日
 未来への地図: 新しい一歩を踏み出すあなたにロバートA.ミンツァー,星野道夫読んだ著者は日本人なのに、なぜ訳者がついているかというと、こちらの本は右から開くと日本語の本、左から開くと英語の本という仕様になっております。 そして、右から開くと1ページ目には、息を呑むほど美しい、カリブーが列を成し水辺を歩く写真がありました。水面に反射した空の青、眩しいほどの水光、猛々しい立派な角を携えたカリブーたち。 次のページは見開きで、首元まで水に浸かるくらいの深い川を渡るカリブーの群れの写真。カリブーの周りに飛び散る水飛沫が、ものすごい躍動感を感じさせます。カリブーが一歩一歩水底を蹴り、前進する様子が浮かぶようです。 すごい…と息を呑まずにはいられません。 そこから数ページ、野性の動物たちの写真が続き、そして星野道夫さんの語りが始まります。どうやら、中学校で講演会をした時の内容を文字起こししたような文章でした。 星野道夫さんがどのようにして探検家であり写真家でありエッセイストとして生きるようになったのか、その始まりから、語られていました。 noteに続きの感想あります https://note.com/skryuh_/n/nb9049635f2c6
未来への地図: 新しい一歩を踏み出すあなたにロバートA.ミンツァー,星野道夫読んだ著者は日本人なのに、なぜ訳者がついているかというと、こちらの本は右から開くと日本語の本、左から開くと英語の本という仕様になっております。 そして、右から開くと1ページ目には、息を呑むほど美しい、カリブーが列を成し水辺を歩く写真がありました。水面に反射した空の青、眩しいほどの水光、猛々しい立派な角を携えたカリブーたち。 次のページは見開きで、首元まで水に浸かるくらいの深い川を渡るカリブーの群れの写真。カリブーの周りに飛び散る水飛沫が、ものすごい躍動感を感じさせます。カリブーが一歩一歩水底を蹴り、前進する様子が浮かぶようです。 すごい…と息を呑まずにはいられません。 そこから数ページ、野性の動物たちの写真が続き、そして星野道夫さんの語りが始まります。どうやら、中学校で講演会をした時の内容を文字起こししたような文章でした。 星野道夫さんがどのようにして探検家であり写真家でありエッセイストとして生きるようになったのか、その始まりから、語られていました。 noteに続きの感想あります https://note.com/skryuh_/n/nb9049635f2c6 - 2026年1月10日
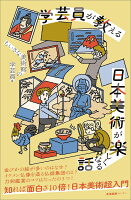 学芸員が教える 日本美術が楽しくなる話ちいさな美術館の学芸員読んだ前作は「学芸員」という仕事についてと、「学芸員」から見た美術館や展覧会の楽しみ方を教えてもらえる本でした。 今作はもっと突っ込んで、タイトルの通り日本美術に特化した本です。 仏様の種類の違いと仏像の見分け方とか、日本美術の画家の派閥とか、葛飾北斎はなぜ人気になったのかとか、平面作品も立体作品も照明の当たり具合で見え方がかわるとか、こういうところを見ると面白いよとか、日本美術初心者の楽しみ方を教えてもらえます。あと日本美術の有名画家たちは以外と高齢になってから絵に専念した方が多く、今で言う定年後とか70.80歳くらいからその道を歩み始めていることにはとても活力をもらいますね。
学芸員が教える 日本美術が楽しくなる話ちいさな美術館の学芸員読んだ前作は「学芸員」という仕事についてと、「学芸員」から見た美術館や展覧会の楽しみ方を教えてもらえる本でした。 今作はもっと突っ込んで、タイトルの通り日本美術に特化した本です。 仏様の種類の違いと仏像の見分け方とか、日本美術の画家の派閥とか、葛飾北斎はなぜ人気になったのかとか、平面作品も立体作品も照明の当たり具合で見え方がかわるとか、こういうところを見ると面白いよとか、日本美術初心者の楽しみ方を教えてもらえます。あと日本美術の有名画家たちは以外と高齢になってから絵に専念した方が多く、今で言う定年後とか70.80歳くらいからその道を歩み始めていることにはとても活力をもらいますね。 - 2026年1月10日
- 2026年1月1日
 薔薇の木 枇杷の木 檸檬の木江國香織読んだ久しぶりに江國香織さんの文章を感じたくて、積読から救い出しました。文章の波に流され揺蕩うような江國さんの文章は心地良いです。まぶたに日の光を当てたくなりました。元日のお日様を浴びたらご利益あるでしょうか。 不倫が蔓延している世界なので、あまり積極的にはおすすめできませんが、それでも江國さんの文章は好きだと思ってしまいます。 「旦那好みの妻」の型に嵌め込まれている女性、仕事もできて家のことも完璧にこなし旦那にも「綺麗だ」と褒められるけれど満たされない女性、なぜ旦那と結婚したのかわからなくなっている女性、感情ではなく計画的に人生を進めている女性、姉の元カレの既婚者男性に想いを寄せ続けている女性、結婚したけれど1番好きな人は他にいる女性、身の程を弁えた不倫に徹している女性、身の程を弁えず引っ掻き回す女性、恋愛から遠ざかり一人を満喫している女性 いろんな女性たちとそこに関わる男性たちの恋愛事情。
薔薇の木 枇杷の木 檸檬の木江國香織読んだ久しぶりに江國香織さんの文章を感じたくて、積読から救い出しました。文章の波に流され揺蕩うような江國さんの文章は心地良いです。まぶたに日の光を当てたくなりました。元日のお日様を浴びたらご利益あるでしょうか。 不倫が蔓延している世界なので、あまり積極的にはおすすめできませんが、それでも江國さんの文章は好きだと思ってしまいます。 「旦那好みの妻」の型に嵌め込まれている女性、仕事もできて家のことも完璧にこなし旦那にも「綺麗だ」と褒められるけれど満たされない女性、なぜ旦那と結婚したのかわからなくなっている女性、感情ではなく計画的に人生を進めている女性、姉の元カレの既婚者男性に想いを寄せ続けている女性、結婚したけれど1番好きな人は他にいる女性、身の程を弁えた不倫に徹している女性、身の程を弁えず引っ掻き回す女性、恋愛から遠ざかり一人を満喫している女性 いろんな女性たちとそこに関わる男性たちの恋愛事情。 - 2025年12月13日
 皇后の碧阿部智里好きな作家好きな装丁読んだ阿部さんの描かれる風景描写、世界構造、そこに住まう生物たちは色鮮やかで美しくて好きです。 火・水・風・土の四大元素がモチーフの世界構成。 土の世界で生まれ育った主人公が、故郷を火の種族に襲われ、住む場所を追いやられたのち、風の種族の王様に拾われ育てられた。そこから6年、主人公は自分の境遇に不満を抱くこともなく王に仕えてきたけれど、更に生活が一変することに。ひとりで戦わなければいけない状況で、主人公は知らずに自立を強いられていく。 何を見て、何を考え、何を決めて、動くのか。 自分の頭で考えることは、自身の尊厳を守ること。 単なる皇帝と妃や寵姫の女同士の戦いとか、そういう宮廷話ではないです。 事の顛末は、こうだったらいいなと思いながら読み進めた通りでした。ミスリードはところどころあるけれど、明らかなので、本筋は掴みやすいかと思います。 「烏に単は似合わない」で受けた衝撃(ダメージ)と似たものはなかったです。 八咫烏シリーズも大好きなのですが、一作目を読み終えたあとはしばらく塞いでしまいましたからね。 でもあの世界に魅せられて次の巻も読み、どハマりしていったのですが。 今シリーズも続きが楽しみです。 (シリーズものですよね?)
皇后の碧阿部智里好きな作家好きな装丁読んだ阿部さんの描かれる風景描写、世界構造、そこに住まう生物たちは色鮮やかで美しくて好きです。 火・水・風・土の四大元素がモチーフの世界構成。 土の世界で生まれ育った主人公が、故郷を火の種族に襲われ、住む場所を追いやられたのち、風の種族の王様に拾われ育てられた。そこから6年、主人公は自分の境遇に不満を抱くこともなく王に仕えてきたけれど、更に生活が一変することに。ひとりで戦わなければいけない状況で、主人公は知らずに自立を強いられていく。 何を見て、何を考え、何を決めて、動くのか。 自分の頭で考えることは、自身の尊厳を守ること。 単なる皇帝と妃や寵姫の女同士の戦いとか、そういう宮廷話ではないです。 事の顛末は、こうだったらいいなと思いながら読み進めた通りでした。ミスリードはところどころあるけれど、明らかなので、本筋は掴みやすいかと思います。 「烏に単は似合わない」で受けた衝撃(ダメージ)と似たものはなかったです。 八咫烏シリーズも大好きなのですが、一作目を読み終えたあとはしばらく塞いでしまいましたからね。 でもあの世界に魅せられて次の巻も読み、どハマりしていったのですが。 今シリーズも続きが楽しみです。 (シリーズものですよね?) - 2025年12月8日
 学芸員しか知らない 美術館が楽しくなる話ちいさな美術館の学芸員読んだこちらの本に書かれているのは、「学芸員」という人が、「どんな仕事をしているのか」ということ。 ・展覧会がどうやって作られているのか ・学芸員は普段何をしているのか ・鑑賞マナーについて学芸員の視点からの考え ・学芸員と共に、美術館を支えている他の職業 という内容構成で、「学芸員」のお仕事が紹介されています。 第1章の『一つの展覧会ができるまで』を読んでいると、今まで観てきた展覧会の裏事情も想像したりして、それを数千円で楽しませていただけるのだから恵まれているなぁと感じますね。 「始めに作品ありき」そこから、その作品の作家さんにフォーカスするのか、その作品が生まれた時代にフォーカスするのか、その作品のジャンルにフォーカスするのか、を考えるそうです。それだけ聞いても、「なるほど、視点が違えば一つの作品からも全く違う展覧会が生まれるだろうなぁ」と分かりますよね。また、この展覧会の「『始めの作品』はどれだったんだろう」と考えながら鑑賞するのも面白そうだなと、裏事情を知ったからできる楽しみ方もありそうですね。 noteに詳細感想書いてます。
学芸員しか知らない 美術館が楽しくなる話ちいさな美術館の学芸員読んだこちらの本に書かれているのは、「学芸員」という人が、「どんな仕事をしているのか」ということ。 ・展覧会がどうやって作られているのか ・学芸員は普段何をしているのか ・鑑賞マナーについて学芸員の視点からの考え ・学芸員と共に、美術館を支えている他の職業 という内容構成で、「学芸員」のお仕事が紹介されています。 第1章の『一つの展覧会ができるまで』を読んでいると、今まで観てきた展覧会の裏事情も想像したりして、それを数千円で楽しませていただけるのだから恵まれているなぁと感じますね。 「始めに作品ありき」そこから、その作品の作家さんにフォーカスするのか、その作品が生まれた時代にフォーカスするのか、その作品のジャンルにフォーカスするのか、を考えるそうです。それだけ聞いても、「なるほど、視点が違えば一つの作品からも全く違う展覧会が生まれるだろうなぁ」と分かりますよね。また、この展覧会の「『始めの作品』はどれだったんだろう」と考えながら鑑賞するのも面白そうだなと、裏事情を知ったからできる楽しみ方もありそうですね。 noteに詳細感想書いてます。 - 2025年11月24日
 読んだ「わからない」ことを「わからない」ままにしておくと一生「わからないまま」だから、少しずつわかろうとしているところなのですが、そのヒントになるかなーと思って手に取った本です。 【芸術を「わからない人」など存在しない】 と言い切ってくれます。 美術館へ行き慣れていない方、美術品を見慣れていない方向けの書き出しから、少しずつレベルアップしていく内容構成となってました。 それぞれ自分なりの楽しみ方を見つけたらいいよ ってことですが、楽しみ方の見つけ方のヒントをたくさんくれる本です。 冬の足音近づいてきて秋も終わっちゃいそうですが、最後に「芸術の秋」楽しみませんか。 noteにもう少し詳細な感想書きました。
読んだ「わからない」ことを「わからない」ままにしておくと一生「わからないまま」だから、少しずつわかろうとしているところなのですが、そのヒントになるかなーと思って手に取った本です。 【芸術を「わからない人」など存在しない】 と言い切ってくれます。 美術館へ行き慣れていない方、美術品を見慣れていない方向けの書き出しから、少しずつレベルアップしていく内容構成となってました。 それぞれ自分なりの楽しみ方を見つけたらいいよ ってことですが、楽しみ方の見つけ方のヒントをたくさんくれる本です。 冬の足音近づいてきて秋も終わっちゃいそうですが、最後に「芸術の秋」楽しみませんか。 noteにもう少し詳細な感想書きました。 - 2025年11月18日
 ぼくが生きてる、ふたつの世界五十嵐大おすすめお気に入り読んだ耳が聴こえない、ろうの両親のもとに生まれた、健聴者の子どもを描いた作品です。「聴こえる世界」と「聴こえない世界」。それが、タイトルの「ふたつの世界」です。 家族のことを「上手く愛せない」ことに葛藤する彼を、常に大きな愛で抱擁し続ける母の視線や言動や感情、それらが全て彼を突き刺すように、こちらにも突き刺さります。 noteにもう少し詳細な感想書いてます。 https://note.com/skryuh_/n/n5f24c1d65e75
ぼくが生きてる、ふたつの世界五十嵐大おすすめお気に入り読んだ耳が聴こえない、ろうの両親のもとに生まれた、健聴者の子どもを描いた作品です。「聴こえる世界」と「聴こえない世界」。それが、タイトルの「ふたつの世界」です。 家族のことを「上手く愛せない」ことに葛藤する彼を、常に大きな愛で抱擁し続ける母の視線や言動や感情、それらが全て彼を突き刺すように、こちらにも突き刺さります。 noteにもう少し詳細な感想書いてます。 https://note.com/skryuh_/n/n5f24c1d65e75 - 2025年10月23日
- 2025年10月15日
 クリームイエローの海と春キャベツのある家せやま南天読んだ大手商社で働いていた永井津麦ながい つむぎは身体を壊したことで退職し、現在は家事代行の派遣社員として働いている。これまで特別問題もなくスムーズに家事代行として働いてきた津麦だが、新たに担当することとなった織野家おりのけは今までの経験では太刀打ちできないほどに、生活が破綻している(津麦にはそう見える)家だった。 この家で自分にできることとは? 生活とは? 自分はこれまで何をしてきた? 織野家で働くことで、自分を見つめ直し、人には人の生活があることを学び直し、「生活」というものがどういうものか、「家事」というものがどういうものか、自分にとっての「家事」とはどういうものか、を見つけていく。 生活について、生きることについて、何をして生きるかなど、「家事」を通して見せてもらえる作品でした。 もうちょっと詳しくnoteに感想書きました↓ https://note.com/skryuh_/n/n3fea7b61a4bd?sub_rt=share_b
クリームイエローの海と春キャベツのある家せやま南天読んだ大手商社で働いていた永井津麦ながい つむぎは身体を壊したことで退職し、現在は家事代行の派遣社員として働いている。これまで特別問題もなくスムーズに家事代行として働いてきた津麦だが、新たに担当することとなった織野家おりのけは今までの経験では太刀打ちできないほどに、生活が破綻している(津麦にはそう見える)家だった。 この家で自分にできることとは? 生活とは? 自分はこれまで何をしてきた? 織野家で働くことで、自分を見つめ直し、人には人の生活があることを学び直し、「生活」というものがどういうものか、「家事」というものがどういうものか、自分にとっての「家事」とはどういうものか、を見つけていく。 生活について、生きることについて、何をして生きるかなど、「家事」を通して見せてもらえる作品でした。 もうちょっと詳しくnoteに感想書きました↓ https://note.com/skryuh_/n/n3fea7b61a4bd?sub_rt=share_b - 2025年9月20日
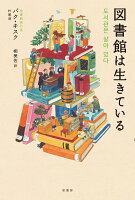 図書館は生きているパク・キスク,柳美佐おすすめ読んだ「自分にとって当然の権利が誰かにとってそうではないなんてことがあってはいけない」 など、社会のこと、福祉のこと、人種や宗教、性別などのことにも触れながら、公共の施設の在り方についてたくさん語られていて、学ぶことが多かった。 旅先や他の地域の図書館に行くことも好きなのだけれど、筆者も旅先で必ず図書館に訪れているそうで、おすすめの世界の図書館一覧も掲載されている。見所満載の図書館情報は面白い。シャーロックホームズ愛好家がパトロンとなっているコナンドイルコレクションを所蔵しているなど、コアな図書館もあるらしい。楽器を借りれたり、楽器製作室がある図書館もあるらしい。羨ましい。 図書館の運営難は世界共通らしい。微々たる力しか持たないけれど、1番の支援は図書館を利用すること。子供の頃から気がつけば図書館な足が向いているような人間なので、図書館になくなられては困る。これからも図書館利用を続けるし、こういった図書館利用を推奨する書籍も広まってほしい。 「図書館を定期的に訪れる利用者は、書店にもよく行く人たち」 こちらにも大いに共感します。
図書館は生きているパク・キスク,柳美佐おすすめ読んだ「自分にとって当然の権利が誰かにとってそうではないなんてことがあってはいけない」 など、社会のこと、福祉のこと、人種や宗教、性別などのことにも触れながら、公共の施設の在り方についてたくさん語られていて、学ぶことが多かった。 旅先や他の地域の図書館に行くことも好きなのだけれど、筆者も旅先で必ず図書館に訪れているそうで、おすすめの世界の図書館一覧も掲載されている。見所満載の図書館情報は面白い。シャーロックホームズ愛好家がパトロンとなっているコナンドイルコレクションを所蔵しているなど、コアな図書館もあるらしい。楽器を借りれたり、楽器製作室がある図書館もあるらしい。羨ましい。 図書館の運営難は世界共通らしい。微々たる力しか持たないけれど、1番の支援は図書館を利用すること。子供の頃から気がつけば図書館な足が向いているような人間なので、図書館になくなられては困る。これからも図書館利用を続けるし、こういった図書館利用を推奨する書籍も広まってほしい。 「図書館を定期的に訪れる利用者は、書店にもよく行く人たち」 こちらにも大いに共感します。 - 2025年9月17日
 星の花濱野京子読んだ
星の花濱野京子読んだ - 2025年9月12日
 アルジャーノンに花束を新版ダニエル・キイス,小尾芙佐読んだ「どういう終わりを迎えるのか」と、ひたすらに心理学書や哲学書のような文章を読み進めました。終わりが「温かなもの」で良かった。「人間とは」とか「愛情とは」とか「善意とは」「寛容とは」「利口とは」など倫理道徳の様々ことを問い掛けられ続けているような読書体験でした。 タイトルの「アルジャーノン」とは、作中に登場するネズミのみではなく、これまで生きた(生きている)実験に使用された命たち全てを含んでいるように思いました。
アルジャーノンに花束を新版ダニエル・キイス,小尾芙佐読んだ「どういう終わりを迎えるのか」と、ひたすらに心理学書や哲学書のような文章を読み進めました。終わりが「温かなもの」で良かった。「人間とは」とか「愛情とは」とか「善意とは」「寛容とは」「利口とは」など倫理道徳の様々ことを問い掛けられ続けているような読書体験でした。 タイトルの「アルジャーノン」とは、作中に登場するネズミのみではなく、これまで生きた(生きている)実験に使用された命たち全てを含んでいるように思いました。
読み込み中...


