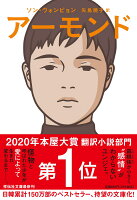うえの
@uen0
- 2026年2月17日
![フィフティ・ピープル[新版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8596/9784750518596_1_5.jpg?_ex=200x200) フィフティ・ピープル[新版]チョン・セラン,斎藤真理子読み終わった新版を改めて読んだ。 一生好き。 とても読みやすいんですが、その随所に現れる価値観や倫理観が私を救う。 ブックサンタでここ2年ほどこの本を選んでます。 #チョンセラン #フィフティピープル #韓国文学 ------好きなことば------ ねぇ、五十年後にはみんな死んでると思うより、三十年後ぐらい経ったらみんな孤児になってると思う方が怖くない? 家族ぐらい、一線を越えて自分の偏見を押し付けてくる人間たちもいない。 僕は、あなたみたいな歳のとり方はしないつもりです。それがいちばん恐ろしいです。 俺、脱退するアイドルの気持ち、わかるな。同じ会社に七年とか八年勤めて辞めるなんていくらでもあるのに、批判されるようなことじゃないと思うな。 自分のやりたいことが、今の社会では無用扱いされていると知ってはいるが、確固たる意志をもってこの専攻を選び、自分たちの後から来る人の選択の自由を保証するために、冷たい地面に座っている。 土台の大切さを気にもしない人たちが大学を統廃合している。 必要なんだよ。ああいう人たちが増えれば増えるほど、それとは違う人が必要になるんだよ。ラッパ手が必要なの。目をそらさない人が必要なの。目をそらさないこと。そのためにここを、選んだでしょ。 前に好きだった歌を大人になってからばかにする人って、何か、偉そう。いい歌だからずーっと歌われてるんじゃないの? 見渡す限りでたらめなのだから、子どもに別の方向を示してやることもできないのだ。 これが福祉なんだなあ。体験してみるまではわからなかった。 娘のことを考えなくてはならない。もしも将来、チャンボクや妻が認知症や他の病気にかかったら、この子一人で何ができるだろう。二人がいっぺんに病気になったら、耐えられるだろうか。そのときも国が助けてくれるだろうか。世の中はそういう方向に進んでいるだろうか。景気も悪いし、人口も減っていくのに、そんなことができるだろうか。 「九十五パーセントの女性が、公開してないってよ。何年か後に訊いてみたんだって。そしたら、自分の決定を後悔してる人は五パーセントしかいなかったって」 「どこで見たの?」 「インターネット」 「いい統計だね、それ」 「いい統計でしょ」 「けど、私がその五パーセントだったらどうしよう?」 「そうねえ」 「それ、どうやったらわかるのかなあ」 「わかるとしても、何年か経たないと」 「わかったら、おしえてあげるからね」 「うん」 たぶん、教えてくれないだろう。スギョンも忘れるだろうし、訊かないだろう。何年後か、お互いの目の中に、今夜のことを連想させるものを見つけたとしても、見えなかったふりをするだろう。何でもないことは何でもないことらしく、忘れなくては。 在所者の健康に国が責任を持つということ。極悪非道な殺人者であっても刑務所内で病んだり、死んだりするのを放っておかないということは、どこかドンヨルを安心させるものがあった。人目が届かないところでもシステムが機能しており、少なくともぎりぎりの線では人権が実態を持っているという点で。 世界を見る視点が似ていた。ハニョンはそんなところがあった。野蛮から文明へと脱出してきた人だけが持っている、基本的人権への強烈な指向性みたいなもの。青くさい表現かもしれないけど。 「何で地獄の穴(ヘル・ピット)なんですか?」 ずっと知りたかったが訊けなかったことを、イサクが訊いた。 「人生は地獄みたいで、楽しいのは少人数のよき友とうまいものを食べるときだけってことを、忘れないようにです」 耳に優しい話し方をなさるおじいさまだわ、とスンファは微笑んだ。古い古い傷を、その言葉は塗り薬のように覆ってくれた。それをスンファは一言も信じなかったし、同意もしなかったけれど、ありがたいと思った。 無意識に持って出てきたおそろいの指輪が、握りしめた手の中で踊った。 ある作品の創り手とその消費者は世界じゅうに散らばっているが、それは特別に結ばれた関係で、肌合いの似通った人々である 「もともとそうだなんて、ありえます?死ぬのが当たり前の職業なんて、なくさなきゃ。造船所で働きたければ死ぬ覚悟をすべきだなんて。工場でも病院でも人を全とっかえしてるんですよ」 ヒョンジェはなぜか真顔で言った。 「最近の若い奴は弱っちいな…」 「ミキサーにかけられたくないからって、弱いわけじゃありませんよ」 「それより……いつも負けてばっかりいるみたいで、辛いんです」 すべてがなぜこんなにもでたらめなのか、めちゃくちゃだらけなのか。このぬかるみの中で変化を起こそうと試みても、何てしょっちゅう、挫折させられることだろう。努力はかなわず、限界にぶつかり、失望させられ、のろのろ、のろのろと改善がなされてはまた後退するのに耐えながら、どうやったらくたびれ果てずにいられるだろう。ヒョンジェは気持ちを吐露し、そして尋ねた。話をかいつまむことは難しかった。 「私にアドバイスを求めているんじゃないでしょう?」 望んではいけないのだろうか。ヒョンジェはかすかに笑った。 「若い人たちは勘違いをしているよ。老人は答えを持っていると思ってるんだね。そんなことはないんだよ。私はただの年寄りです」 「他の方たちはそうでも、先生は違うと思うんです」 「君はほめ上手だね。私はアドバイスが嫌いだけど、ソ先生が望んでいるようだから言いましょう。ほんとは、アドバイスがいちばん嫌なんだよ、そんな資格は私にはないし。ただね、…私たちの仕事は、石を遠くに投げることだと考えてみましょうよ。とにもかくも、力いっぱい遠くへ。みんな、錯覚しているんですよ。誰もが同じ位置から投げていて、人の能力は似たり寄ったりだから石が遠くに行かないって。でも実は、同じ位置から投げているんじゃないんです。時代というもの、世代というものがあるからですよ。ソ先生はスタートラインから投げているわけではないんだよ。私の世代や、そして私たちの中間の世代が投げた石が落ちた地点で、それを拾って投げているんです。わかりますか?」 「リレーみたいなものだということですね?」 「それですよ。今でもすばらしい学生だね、君は。もちろん、そのことはしばしば忘れられます。ときどき、ろくでもない連中が現れて、反対方向に石を投げることもありますよ。でも、ちょっとでも遠くへ投げて、ちょっとでも長いスパンで見ていく機会が運よくソ先生に与えられたら——例えば四十年ぐらい後、私ぐらいの年になって振り返ったら、石は遠くまで来ているでしょう。そして、その石が落ちたやぶを次の人たちが探して、また、それを投げるんです。ソ先生では届かなかった距離までね」
フィフティ・ピープル[新版]チョン・セラン,斎藤真理子読み終わった新版を改めて読んだ。 一生好き。 とても読みやすいんですが、その随所に現れる価値観や倫理観が私を救う。 ブックサンタでここ2年ほどこの本を選んでます。 #チョンセラン #フィフティピープル #韓国文学 ------好きなことば------ ねぇ、五十年後にはみんな死んでると思うより、三十年後ぐらい経ったらみんな孤児になってると思う方が怖くない? 家族ぐらい、一線を越えて自分の偏見を押し付けてくる人間たちもいない。 僕は、あなたみたいな歳のとり方はしないつもりです。それがいちばん恐ろしいです。 俺、脱退するアイドルの気持ち、わかるな。同じ会社に七年とか八年勤めて辞めるなんていくらでもあるのに、批判されるようなことじゃないと思うな。 自分のやりたいことが、今の社会では無用扱いされていると知ってはいるが、確固たる意志をもってこの専攻を選び、自分たちの後から来る人の選択の自由を保証するために、冷たい地面に座っている。 土台の大切さを気にもしない人たちが大学を統廃合している。 必要なんだよ。ああいう人たちが増えれば増えるほど、それとは違う人が必要になるんだよ。ラッパ手が必要なの。目をそらさない人が必要なの。目をそらさないこと。そのためにここを、選んだでしょ。 前に好きだった歌を大人になってからばかにする人って、何か、偉そう。いい歌だからずーっと歌われてるんじゃないの? 見渡す限りでたらめなのだから、子どもに別の方向を示してやることもできないのだ。 これが福祉なんだなあ。体験してみるまではわからなかった。 娘のことを考えなくてはならない。もしも将来、チャンボクや妻が認知症や他の病気にかかったら、この子一人で何ができるだろう。二人がいっぺんに病気になったら、耐えられるだろうか。そのときも国が助けてくれるだろうか。世の中はそういう方向に進んでいるだろうか。景気も悪いし、人口も減っていくのに、そんなことができるだろうか。 「九十五パーセントの女性が、公開してないってよ。何年か後に訊いてみたんだって。そしたら、自分の決定を後悔してる人は五パーセントしかいなかったって」 「どこで見たの?」 「インターネット」 「いい統計だね、それ」 「いい統計でしょ」 「けど、私がその五パーセントだったらどうしよう?」 「そうねえ」 「それ、どうやったらわかるのかなあ」 「わかるとしても、何年か経たないと」 「わかったら、おしえてあげるからね」 「うん」 たぶん、教えてくれないだろう。スギョンも忘れるだろうし、訊かないだろう。何年後か、お互いの目の中に、今夜のことを連想させるものを見つけたとしても、見えなかったふりをするだろう。何でもないことは何でもないことらしく、忘れなくては。 在所者の健康に国が責任を持つということ。極悪非道な殺人者であっても刑務所内で病んだり、死んだりするのを放っておかないということは、どこかドンヨルを安心させるものがあった。人目が届かないところでもシステムが機能しており、少なくともぎりぎりの線では人権が実態を持っているという点で。 世界を見る視点が似ていた。ハニョンはそんなところがあった。野蛮から文明へと脱出してきた人だけが持っている、基本的人権への強烈な指向性みたいなもの。青くさい表現かもしれないけど。 「何で地獄の穴(ヘル・ピット)なんですか?」 ずっと知りたかったが訊けなかったことを、イサクが訊いた。 「人生は地獄みたいで、楽しいのは少人数のよき友とうまいものを食べるときだけってことを、忘れないようにです」 耳に優しい話し方をなさるおじいさまだわ、とスンファは微笑んだ。古い古い傷を、その言葉は塗り薬のように覆ってくれた。それをスンファは一言も信じなかったし、同意もしなかったけれど、ありがたいと思った。 無意識に持って出てきたおそろいの指輪が、握りしめた手の中で踊った。 ある作品の創り手とその消費者は世界じゅうに散らばっているが、それは特別に結ばれた関係で、肌合いの似通った人々である 「もともとそうだなんて、ありえます?死ぬのが当たり前の職業なんて、なくさなきゃ。造船所で働きたければ死ぬ覚悟をすべきだなんて。工場でも病院でも人を全とっかえしてるんですよ」 ヒョンジェはなぜか真顔で言った。 「最近の若い奴は弱っちいな…」 「ミキサーにかけられたくないからって、弱いわけじゃありませんよ」 「それより……いつも負けてばっかりいるみたいで、辛いんです」 すべてがなぜこんなにもでたらめなのか、めちゃくちゃだらけなのか。このぬかるみの中で変化を起こそうと試みても、何てしょっちゅう、挫折させられることだろう。努力はかなわず、限界にぶつかり、失望させられ、のろのろ、のろのろと改善がなされてはまた後退するのに耐えながら、どうやったらくたびれ果てずにいられるだろう。ヒョンジェは気持ちを吐露し、そして尋ねた。話をかいつまむことは難しかった。 「私にアドバイスを求めているんじゃないでしょう?」 望んではいけないのだろうか。ヒョンジェはかすかに笑った。 「若い人たちは勘違いをしているよ。老人は答えを持っていると思ってるんだね。そんなことはないんだよ。私はただの年寄りです」 「他の方たちはそうでも、先生は違うと思うんです」 「君はほめ上手だね。私はアドバイスが嫌いだけど、ソ先生が望んでいるようだから言いましょう。ほんとは、アドバイスがいちばん嫌なんだよ、そんな資格は私にはないし。ただね、…私たちの仕事は、石を遠くに投げることだと考えてみましょうよ。とにもかくも、力いっぱい遠くへ。みんな、錯覚しているんですよ。誰もが同じ位置から投げていて、人の能力は似たり寄ったりだから石が遠くに行かないって。でも実は、同じ位置から投げているんじゃないんです。時代というもの、世代というものがあるからですよ。ソ先生はスタートラインから投げているわけではないんだよ。私の世代や、そして私たちの中間の世代が投げた石が落ちた地点で、それを拾って投げているんです。わかりますか?」 「リレーみたいなものだということですね?」 「それですよ。今でもすばらしい学生だね、君は。もちろん、そのことはしばしば忘れられます。ときどき、ろくでもない連中が現れて、反対方向に石を投げることもありますよ。でも、ちょっとでも遠くへ投げて、ちょっとでも長いスパンで見ていく機会が運よくソ先生に与えられたら——例えば四十年ぐらい後、私ぐらいの年になって振り返ったら、石は遠くまで来ているでしょう。そして、その石が落ちたやぶを次の人たちが探して、また、それを投げるんです。ソ先生では届かなかった距離までね」 - 2026年2月2日
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子読み終わったアツい友情。愛おしい。 シリアスなSFだと思ってたら、シニカルな掛け合いが魅力的な友情スポ根物語。 Audibleの読み手の方の読み分けがすごく良かった。
プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子読み終わったアツい友情。愛おしい。 シリアスなSFだと思ってたら、シニカルな掛け合いが魅力的な友情スポ根物語。 Audibleの読み手の方の読み分けがすごく良かった。 - 2026年2月2日
- 2025年12月25日
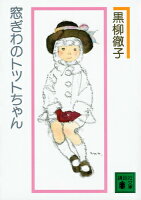 窓ぎわのトットちゃん 新組版黒柳徹子読み終わった去年?にアニメーションの映画を見てから、ちゃんと原作読まなきゃなと心に決めて買った一冊。 子供たちが生きていきやすい世界を優先できる生き方をしていきたいものだな。もっと、ゆとりをもって生きていける時間が必要な気がした。そういうところに、豊かさは宿っているような気がする。
窓ぎわのトットちゃん 新組版黒柳徹子読み終わった去年?にアニメーションの映画を見てから、ちゃんと原作読まなきゃなと心に決めて買った一冊。 子供たちが生きていきやすい世界を優先できる生き方をしていきたいものだな。もっと、ゆとりをもって生きていける時間が必要な気がした。そういうところに、豊かさは宿っているような気がする。 - 2025年12月20日
 ギリシャ語の時間ハン・ガン,斎藤真理子読み終わった回復する人間につながる物語だな、と感じた。 印象に残った言葉------ 私を許してくれますか。 許せないとしたら、私が許しを乞うていることを憶えていてくれますか。 世界は幻で、生きるのは夢だ。と、だしぬけにつぶやいてみた。 だが、血は流れ、涙は湧いてくるのに。
ギリシャ語の時間ハン・ガン,斎藤真理子読み終わった回復する人間につながる物語だな、と感じた。 印象に残った言葉------ 私を許してくれますか。 許せないとしたら、私が許しを乞うていることを憶えていてくれますか。 世界は幻で、生きるのは夢だ。と、だしぬけにつぶやいてみた。 だが、血は流れ、涙は湧いてくるのに。 - 2025年12月14日
 アンダー、サンダー、テンダーチョン・セラン,吉川凪読み終わった子どもの頃は、今の人間関係がどう変容するかなんて想像できやしなかった。変容することを知ってしまったからこそ感じる、その時代の豊かさと親しみのある閉塞感。 映像を見たわけではないのに、映像を流す場面でなぜか涙が出た。そういう風に日常の記録を後から見返すと、きっととてつもなく居心地が悪くて、そして愛おしいのだろう。 印象に残った言葉--------- 長生きして、嫌いな人たちがみんな没落するのを見てから死にたい みんな私に、ちょっとは我を折れというけど、そんな人たちとは話が通じない。我を殺したら誰も守ってくれないってことくらい、わかるわ 「君にはわからないよ」 何がわからないのか聞くべきだったのに、その時はそのままでもよかった。なせわかってくれないのかと責めているのではなく、微妙に優しい断定だったから、私は私が知らないことがいつかわかるだろうと思い、一緒に座席にもたれて眠る甘い時間が続くだろうと信じていた。 ぞっとするような事件を起こした子供たちはたいてい、自分自身がぞっとするような世界に閉じこめられているということを、誰もその子たちをそこから救い出すことも、さらには正視することもしなかっただろうというとを知っているから。 大切なものは絶えず失われ、愛した人たちが次々と死んでいなくなってしまうのに、それを耐えられるように設計されていない ニュースが伝える死傷者の中に自分の名前がないことだけでも幸運だと考える潔さの上に、私たちの友情は続いている 少ない金が最大限効果的に使われることを願うから、子供に寄付してるんだよ 悪化する環境を、いい人たちが耐えている。辞めないで闘う人たちのおかげで、それでも何とかこの程度には維持できてるんだけど、闘うことすらできない会社のほうが多いのよ
アンダー、サンダー、テンダーチョン・セラン,吉川凪読み終わった子どもの頃は、今の人間関係がどう変容するかなんて想像できやしなかった。変容することを知ってしまったからこそ感じる、その時代の豊かさと親しみのある閉塞感。 映像を見たわけではないのに、映像を流す場面でなぜか涙が出た。そういう風に日常の記録を後から見返すと、きっととてつもなく居心地が悪くて、そして愛おしいのだろう。 印象に残った言葉--------- 長生きして、嫌いな人たちがみんな没落するのを見てから死にたい みんな私に、ちょっとは我を折れというけど、そんな人たちとは話が通じない。我を殺したら誰も守ってくれないってことくらい、わかるわ 「君にはわからないよ」 何がわからないのか聞くべきだったのに、その時はそのままでもよかった。なせわかってくれないのかと責めているのではなく、微妙に優しい断定だったから、私は私が知らないことがいつかわかるだろうと思い、一緒に座席にもたれて眠る甘い時間が続くだろうと信じていた。 ぞっとするような事件を起こした子供たちはたいてい、自分自身がぞっとするような世界に閉じこめられているということを、誰もその子たちをそこから救い出すことも、さらには正視することもしなかっただろうというとを知っているから。 大切なものは絶えず失われ、愛した人たちが次々と死んでいなくなってしまうのに、それを耐えられるように設計されていない ニュースが伝える死傷者の中に自分の名前がないことだけでも幸運だと考える潔さの上に、私たちの友情は続いている 少ない金が最大限効果的に使われることを願うから、子供に寄付してるんだよ 悪化する環境を、いい人たちが耐えている。辞めないで闘う人たちのおかげで、それでも何とかこの程度には維持できてるんだけど、闘うことすらできない会社のほうが多いのよ - 2025年12月6日
 沈みかけの船より、愛をこめて 幻夢コレクション中田永一,乙一,安達寛高,山白朝子読み終わったタイトルの美しさもそうだけど、タイトルから想起される物語とは全然違って、そういう意味かとなる感じが「メアリースーを殺して」の時を思い出した。 鬼の話が好きだったな
沈みかけの船より、愛をこめて 幻夢コレクション中田永一,乙一,安達寛高,山白朝子読み終わったタイトルの美しさもそうだけど、タイトルから想起される物語とは全然違って、そういう意味かとなる感じが「メアリースーを殺して」の時を思い出した。 鬼の話が好きだったな - 2025年12月2日
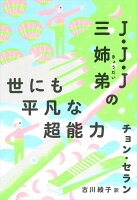 J・J・J三姉弟の世にも平凡な超能力チョン・セラン,古川綾子読み終わったサラッと読めるけれど、書き記されるちょっとした価値観や物事の見え方にあたたかさと優しさと倫理観が現れる。そこが好きなんだよな。 著者は「なんでもない偶然、どうってことない超能力、平凡で小さな親切、たびたび出会う思いやりについての物語が書きたかった」と。まさにそんな物語。
J・J・J三姉弟の世にも平凡な超能力チョン・セラン,古川綾子読み終わったサラッと読めるけれど、書き記されるちょっとした価値観や物事の見え方にあたたかさと優しさと倫理観が現れる。そこが好きなんだよな。 著者は「なんでもない偶然、どうってことない超能力、平凡で小さな親切、たびたび出会う思いやりについての物語が書きたかった」と。まさにそんな物語。 - 2025年11月27日
 侍女の物語マーガレット・アトウッド読み終わったこんな世界が来て欲しくないと切に祈りながらも、極右政権が台頭している現状の政権を見ていると、一歩間違えるとこうなりかねない片鱗が見え隠れしてただただ怖い。
侍女の物語マーガレット・アトウッド読み終わったこんな世界が来て欲しくないと切に祈りながらも、極右政権が台頭している現状の政権を見ていると、一歩間違えるとこうなりかねない片鱗が見え隠れしてただただ怖い。 - 2025年11月7日
 ヘルマフロディテの体温小島てるみ読みたい
ヘルマフロディテの体温小島てるみ読みたい - 2025年10月20日
 一心同体だった山内マリコ読み終わった私たちも分断させられていたのかもしれない。 この続いていく円は、平面ではなく、螺旋のように上へと繋がって、あのガラスを破ると信じたい。下ではなく、上へと進んでいると信じてやまない。 印象に残った言葉------ 北島に救われた女の子がいるってことを思い出して。 二人でいれば無敵だった。 憧れていた無敵の女の子たちは、もう道しるべにはなってくれない。 美人。 その言葉は、もはやあなたを喜ばせはしない。きれいな牛だぜと言われてるみたい。 人生は、友達と一緒に進めないんだ。 性被害に遭わないように空手を習わせたい。恋愛至上主義の罠に嵌まらないようにシスターフッドの物語を読ませたい。女の子の人生には危険が多すぎて、その罠を回避させるために、なにをしてあげられるのかを考え出すと、不安で眠れなくなる。涙がでる。 ミソジニーは女性にしたら、自己嫌悪に転化する。自分のことが嫌いで嫌いで、自傷までする女の子たちに救いになるのは、優しい彼氏じゃなくて、自分との和解なの。自分の中に埋まった「男の視線」をやっつけること。女じゃなくて、人になること。
一心同体だった山内マリコ読み終わった私たちも分断させられていたのかもしれない。 この続いていく円は、平面ではなく、螺旋のように上へと繋がって、あのガラスを破ると信じたい。下ではなく、上へと進んでいると信じてやまない。 印象に残った言葉------ 北島に救われた女の子がいるってことを思い出して。 二人でいれば無敵だった。 憧れていた無敵の女の子たちは、もう道しるべにはなってくれない。 美人。 その言葉は、もはやあなたを喜ばせはしない。きれいな牛だぜと言われてるみたい。 人生は、友達と一緒に進めないんだ。 性被害に遭わないように空手を習わせたい。恋愛至上主義の罠に嵌まらないようにシスターフッドの物語を読ませたい。女の子の人生には危険が多すぎて、その罠を回避させるために、なにをしてあげられるのかを考え出すと、不安で眠れなくなる。涙がでる。 ミソジニーは女性にしたら、自己嫌悪に転化する。自分のことが嫌いで嫌いで、自傷までする女の子たちに救いになるのは、優しい彼氏じゃなくて、自分との和解なの。自分の中に埋まった「男の視線」をやっつけること。女じゃなくて、人になること。 - 2025年9月28日
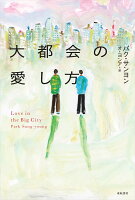 大都会の愛し方オ・ヨンア,パク・サンヨン読み終わった
大都会の愛し方オ・ヨンア,パク・サンヨン読み終わった - 2025年9月20日
 ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい大前粟生読み終わった自分の加害性や弱さを抱え込みながら、優しくありたい、優しい世界であってほしいと祈りつづけるような物語。 映画がすごく好きで、いつか原作も読もうと思ってたんですが、忘れており。近所の個人経営の本屋さんで見つけて買いました。映画も小説もどちらも良い作品です。 印象に残った言葉------------- 軽薄さや無関心と間違えられてしまうようなやさしさ。 恋愛や男女の話があまりされない。そういう話、楽しいけど、疲れてしまうから。消費したり消費されたりしているって、自覚してしまうときがあるから。 でも、安心できるところの方がめずらしいじゃん。世のなか。 打たれ弱くて、いいじゃん。打たれ弱いの、悪いことじゃないのに。撃たれ弱いひとを打つ方が悪いんじゃん。 こうやって白城のなかで、ひどいことが自然法則みたいになってるのがつらい。 ごめん ラインを送ろうとして、でもごめんとかいって楽になるのは自分じゃないかと七森は思った。ごめんということばを送って、こっちこそごめん、を引き出す?それで白城も楽になる?その想定をする傲慢さによけいしんどくなった。考え過ぎだ、と自分でわかっているけれど、いまは沈みたい。 僕も最低で、この最低を抱えて生きていくことに酔えたらどんなに楽だろ。注意、したい。怒れるようになりたい。でも、こわいんだ、僕はただ、他のひとたちにも、自分の言動でひとが傷ついているかもしれないって気づいてほしい。気づいて、そこからはみんな仲良く、健康に生きてくれたらいいのにな。いまの僕みたいに、しんどくなってほしくない。 嫌なことをいってくるやつはもっと嫌なやつであってくれ どんなことばも、社会から発せられたものだ。 やさしすぎるんだよ、と白城は思う。傷ついていく七森と麦戸ちゃんたちを、やさしさから自由にしたい白城は、ぬいぐるみとしゃべらない。 お互いひとりでいるような感じでだれかといたいとき たかが結婚で私のこと変えられると思うな 心に鎧を装着して身構えてください 彼女は他サークルや社会で起こっているセクシャルハラスメントに気づいていないのではなく、きちんと「ひどいこと」と認識した上で、自分の視界から外している。たとえ自分自身が被害にあっていても、「子供みたい」な七森や麦戸と異なり、つらいと言わないし、認めない。加害者にならないよう努めている七森に対し、被害者でいたくない白城は対照的だ。ジェンダー問題に限らず、声を上げても無駄だと達観したり強者の理屈を内面化したりして、被害者や立場の弱い者がどうにか現実に順応することは、悲しいことにそんなに珍しいことではない。これは今まで、多くのフィクションが金や性に汚い大人と純粋な子どもの闘いを描いてきた弊害でもあると、私は思う。成熟することは、理不尽であること、そしてそれに従うことを指すようになってしまったからだ。 血のつながった家族であっても他者とみなし、そして他者を操作できない存在として認め、放って置けないけどそっと見守っている。相手の世界を侵害せずに関係し合うことの例を見せてくれる。 「ふつうにひどい」現実の中で身を躱しながら暮らしていて、痛いとか苦しいとか、助けを求める言葉すら忘れてしまいそうな白城をやさしくない人間にデフォルメして描写することもできるのに、彼女の世界を侵害せずに解きほぐして書かれている。大前さんの書く厚い包帯のような物語の数々が、七森や麦戸に共感するひとはもちろん、白城のようなひとにも届いて、その放っておかれた傷をもふんわりと覆えばいい。
ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい大前粟生読み終わった自分の加害性や弱さを抱え込みながら、優しくありたい、優しい世界であってほしいと祈りつづけるような物語。 映画がすごく好きで、いつか原作も読もうと思ってたんですが、忘れており。近所の個人経営の本屋さんで見つけて買いました。映画も小説もどちらも良い作品です。 印象に残った言葉------------- 軽薄さや無関心と間違えられてしまうようなやさしさ。 恋愛や男女の話があまりされない。そういう話、楽しいけど、疲れてしまうから。消費したり消費されたりしているって、自覚してしまうときがあるから。 でも、安心できるところの方がめずらしいじゃん。世のなか。 打たれ弱くて、いいじゃん。打たれ弱いの、悪いことじゃないのに。撃たれ弱いひとを打つ方が悪いんじゃん。 こうやって白城のなかで、ひどいことが自然法則みたいになってるのがつらい。 ごめん ラインを送ろうとして、でもごめんとかいって楽になるのは自分じゃないかと七森は思った。ごめんということばを送って、こっちこそごめん、を引き出す?それで白城も楽になる?その想定をする傲慢さによけいしんどくなった。考え過ぎだ、と自分でわかっているけれど、いまは沈みたい。 僕も最低で、この最低を抱えて生きていくことに酔えたらどんなに楽だろ。注意、したい。怒れるようになりたい。でも、こわいんだ、僕はただ、他のひとたちにも、自分の言動でひとが傷ついているかもしれないって気づいてほしい。気づいて、そこからはみんな仲良く、健康に生きてくれたらいいのにな。いまの僕みたいに、しんどくなってほしくない。 嫌なことをいってくるやつはもっと嫌なやつであってくれ どんなことばも、社会から発せられたものだ。 やさしすぎるんだよ、と白城は思う。傷ついていく七森と麦戸ちゃんたちを、やさしさから自由にしたい白城は、ぬいぐるみとしゃべらない。 お互いひとりでいるような感じでだれかといたいとき たかが結婚で私のこと変えられると思うな 心に鎧を装着して身構えてください 彼女は他サークルや社会で起こっているセクシャルハラスメントに気づいていないのではなく、きちんと「ひどいこと」と認識した上で、自分の視界から外している。たとえ自分自身が被害にあっていても、「子供みたい」な七森や麦戸と異なり、つらいと言わないし、認めない。加害者にならないよう努めている七森に対し、被害者でいたくない白城は対照的だ。ジェンダー問題に限らず、声を上げても無駄だと達観したり強者の理屈を内面化したりして、被害者や立場の弱い者がどうにか現実に順応することは、悲しいことにそんなに珍しいことではない。これは今まで、多くのフィクションが金や性に汚い大人と純粋な子どもの闘いを描いてきた弊害でもあると、私は思う。成熟することは、理不尽であること、そしてそれに従うことを指すようになってしまったからだ。 血のつながった家族であっても他者とみなし、そして他者を操作できない存在として認め、放って置けないけどそっと見守っている。相手の世界を侵害せずに関係し合うことの例を見せてくれる。 「ふつうにひどい」現実の中で身を躱しながら暮らしていて、痛いとか苦しいとか、助けを求める言葉すら忘れてしまいそうな白城をやさしくない人間にデフォルメして描写することもできるのに、彼女の世界を侵害せずに解きほぐして書かれている。大前さんの書く厚い包帯のような物語の数々が、七森や麦戸に共感するひとはもちろん、白城のようなひとにも届いて、その放っておかれた傷をもふんわりと覆えばいい。 - 2025年8月31日
 涙の箱きむふな,ハン・ガン読み終わった「男の子なんだから泣くんじゃない」「大人なんだから泣くんじゃない」そんな言葉が漂うこの世に、優しく穏やかな一石を投じる。そんな物語をなんじゃないかと思う。 装画・挿絵がとても美しい。junaidaさんのイラスト。 童話というジャンルを買ったのはいつぶりだろう。 作者のことば 「時おり、予想外の瞬間に、私たちを救うために訪れてくれる涙に感謝する」
涙の箱きむふな,ハン・ガン読み終わった「男の子なんだから泣くんじゃない」「大人なんだから泣くんじゃない」そんな言葉が漂うこの世に、優しく穏やかな一石を投じる。そんな物語をなんじゃないかと思う。 装画・挿絵がとても美しい。junaidaさんのイラスト。 童話というジャンルを買ったのはいつぶりだろう。 作者のことば 「時おり、予想外の瞬間に、私たちを救うために訪れてくれる涙に感謝する」 - 2025年8月31日
 彼女の名前はすんみ,チョ・ナムジュ,小山内園子読み終わった「誰かの母」「誰かの妻」「女子高生」「給食のおばちゃん」「誰かの娘」ではなく、ひとりひとりを描き、彼女たちが上げた声を繋いでゆく物語。 印象に残った言葉--------- 黙ってやり過ごす二番目の人にはなりたくはなかった。三番目、四番目、五番目の被害者を作るつもりは、ない。 ただ、おもしろくてやりがいのある仕事にそれ相応の報酬が与えられたら、どんなにいいだろうかと思う。 私だってそうだったんだよ。あたしたちの頃はもっと酷かったんだから。そんなことを言う先輩にはなるまいと、心に誓った。でもそれだけでは足りない。言ってはならないことを言わない人で終わらず、言うべきことを言える人にならなければ。自分が今日のみ込んだ言葉、自分しか言ってあげられない言葉について、考えている。 あんたが愛嬌ふりまいてもふりまかなくても関係ない。あんたはいつだって、あたしのウォンだから。愛嬌なんか、くそくらえってんだ。 でも、いざこんな目に遭ってみると、お金がないってことはちょっと残念ですまされる話じゃない。命を脅かされることなんだね。 三十年後、ひょっとしたらそれより早く訪れるかもしれない自分の最後の瞬間を想像する。おそらくそばに家族はいないだろうし、私はその時も後悔していないだろう。まだ熱の残る私の骨箱を抱いてこの道を歩くであろう誰かが、しっかりしていて礼儀正しい、こういうことになれた人であってほしいと思う。 結婚して。いいことの方が多いから。ただ、結婚しても誰かの妻、誰かの嫁、誰かの母になろうってがんばらないで、自分のままでいて 空気を読まないでいられるのだって権力だよ 女性の仕事を臨時的な職や補助的な仕事だけに限定しないための闘い。 「最近の小学生はなんでも知ってるのよ。昨日の配食の時に、明日からストライキですよね。ストライキって何のためにやるんですか?と言われてびっくりしちゃった」 「で、何で答えたの?」 「あとであなたたちが、おばさんみたいに生きて欲しくないからだよって」 「お母さんみたいに生きたら、何がだめなのさ」 スビンは平然とごはんをたいらげ、弁当を作ってもらったお礼と忘れなかったけど、エレベータに乗るとがまんしていた涙が込み上げた。お母さんは、自分の人生をどんな人生だと思ってるのよ。 自分がどう暮らし、どんな態度をとり、どんな価値観を持つかは、周りの人を、組織を、もっといえば社会を、変えていくのだから。責任を果たす大人になりたい。 韓国には「卵で岩を打つ」ということわざがあります。卵を投げつけたからといって岩を穿つことができないように、絶対不可能で無謀なことをいう言葉です。これに対して「卵で岩は割れなくても汚すことはできる」というジョークも生まれました。誰が言い始めたのかわからないこの言葉が、私はとても好きです。役に立たない巨大な岩が私たちの前進を妨げているとき、そうか、と足を止めたり、引き返したりしたくありません。ここにそぐわない岩の塊が道を塞いでいるよと声を上げたいのです。一緒に悩んでみたいのです。 もしかしたら、ここにある物語は巨大で堅固な岩に投げつけられて割れた、無数の卵の痕跡かもしれません。そして私は、今日も卵を投げつけています。いつかこの岩は割れるはずだと、みんなで動かして無くせるはずだと信じながら。向こうにどんな道が続いているのだろうと、胸をときめかせながら。 訳者あとがき 社会の不条理に声を上げることは、現実を変えたいと宣言することである。変化を見届けようとすることである。 声を上げることそのものより、声を上げ続けることのほうがはるかに困難なのだ。
彼女の名前はすんみ,チョ・ナムジュ,小山内園子読み終わった「誰かの母」「誰かの妻」「女子高生」「給食のおばちゃん」「誰かの娘」ではなく、ひとりひとりを描き、彼女たちが上げた声を繋いでゆく物語。 印象に残った言葉--------- 黙ってやり過ごす二番目の人にはなりたくはなかった。三番目、四番目、五番目の被害者を作るつもりは、ない。 ただ、おもしろくてやりがいのある仕事にそれ相応の報酬が与えられたら、どんなにいいだろうかと思う。 私だってそうだったんだよ。あたしたちの頃はもっと酷かったんだから。そんなことを言う先輩にはなるまいと、心に誓った。でもそれだけでは足りない。言ってはならないことを言わない人で終わらず、言うべきことを言える人にならなければ。自分が今日のみ込んだ言葉、自分しか言ってあげられない言葉について、考えている。 あんたが愛嬌ふりまいてもふりまかなくても関係ない。あんたはいつだって、あたしのウォンだから。愛嬌なんか、くそくらえってんだ。 でも、いざこんな目に遭ってみると、お金がないってことはちょっと残念ですまされる話じゃない。命を脅かされることなんだね。 三十年後、ひょっとしたらそれより早く訪れるかもしれない自分の最後の瞬間を想像する。おそらくそばに家族はいないだろうし、私はその時も後悔していないだろう。まだ熱の残る私の骨箱を抱いてこの道を歩くであろう誰かが、しっかりしていて礼儀正しい、こういうことになれた人であってほしいと思う。 結婚して。いいことの方が多いから。ただ、結婚しても誰かの妻、誰かの嫁、誰かの母になろうってがんばらないで、自分のままでいて 空気を読まないでいられるのだって権力だよ 女性の仕事を臨時的な職や補助的な仕事だけに限定しないための闘い。 「最近の小学生はなんでも知ってるのよ。昨日の配食の時に、明日からストライキですよね。ストライキって何のためにやるんですか?と言われてびっくりしちゃった」 「で、何で答えたの?」 「あとであなたたちが、おばさんみたいに生きて欲しくないからだよって」 「お母さんみたいに生きたら、何がだめなのさ」 スビンは平然とごはんをたいらげ、弁当を作ってもらったお礼と忘れなかったけど、エレベータに乗るとがまんしていた涙が込み上げた。お母さんは、自分の人生をどんな人生だと思ってるのよ。 自分がどう暮らし、どんな態度をとり、どんな価値観を持つかは、周りの人を、組織を、もっといえば社会を、変えていくのだから。責任を果たす大人になりたい。 韓国には「卵で岩を打つ」ということわざがあります。卵を投げつけたからといって岩を穿つことができないように、絶対不可能で無謀なことをいう言葉です。これに対して「卵で岩は割れなくても汚すことはできる」というジョークも生まれました。誰が言い始めたのかわからないこの言葉が、私はとても好きです。役に立たない巨大な岩が私たちの前進を妨げているとき、そうか、と足を止めたり、引き返したりしたくありません。ここにそぐわない岩の塊が道を塞いでいるよと声を上げたいのです。一緒に悩んでみたいのです。 もしかしたら、ここにある物語は巨大で堅固な岩に投げつけられて割れた、無数の卵の痕跡かもしれません。そして私は、今日も卵を投げつけています。いつかこの岩は割れるはずだと、みんなで動かして無くせるはずだと信じながら。向こうにどんな道が続いているのだろうと、胸をときめかせながら。 訳者あとがき 社会の不条理に声を上げることは、現実を変えたいと宣言することである。変化を見届けようとすることである。 声を上げることそのものより、声を上げ続けることのほうがはるかに困難なのだ。 - 2025年8月15日
 そっと 静かにハン・ガン,古川綾子読み終わった曲が分かったら、聴きながらその言語が聴き取れたら、もっと素敵な読書体験になるんだろうなぁと思った。 印象に残った言葉--------- そっと静かに 称賛はパワーになると言うけれど、度が過ぎるとかえって勇気を削ぐことにもなると、そのときはじめて知った。 よく知らないという渇き 私が自分の魂を売り渡したとき あなたは買い戻してくれて 私を支えてくれた これはこそらく、一糸乱れず、かっこよく、速く進む行進とは異なるのだと思う。よろめきながら、ふらつきながら、倒れそうで倒れない、それでもなんとか顔を上げて進む「歩み」なのなと思う。行進というよりは、行進しようとする姿勢とでもいうのだろうか。 もっと良くなるはずだという思いだけが 人生と道を変えるはず 淡々って、あんなにも大きな力なんだ。 生きてゆける道を取り戻すこと 愛する時間は多くない 「子育て中だからって残り物ばかり食べたり、疲れてるのに窮屈な格好で寝たりしてはいけませんよ。引け目を感じることなく食べて、手足を伸ばして寝なさい。妻を見ていて思いました。そうやって生きてきた結果、痛かったり具合の悪かったりするところがどれほど多いことか…。一度きりの人生じゃないですか」 私たちの胸にも白い雪が降るときがあるでしょう その雪が溶けるまで一緒に歩いてみましょう 見てください 私は踊っています 燃え立つ車椅子で なんの魔術も秘法もありません ただ、いかなるものも私を完全に破壊できなかっただけ 傷ついても損なわれない人たち。いかなるものにも破壊されない「最後の私」を感じさせる人たち。 痛みよりは光として残る思い出。 そんな思い出があなたにもあるだろうか。百通りの気遣う言葉よりも胸が締め付けられる、黙って手を差し出す握手みたいな思い出が。 エイブルビー (誰か私の手を握ってください) もう、立ち上がって歩く時間 (もう、私の手を握って行きましょう) 誰か私の手を握ってください、という言葉を声にして出して言うのは難しい。だから断崖絶壁の上でも、手を伸ばせなくなってしまう人がいる。
そっと 静かにハン・ガン,古川綾子読み終わった曲が分かったら、聴きながらその言語が聴き取れたら、もっと素敵な読書体験になるんだろうなぁと思った。 印象に残った言葉--------- そっと静かに 称賛はパワーになると言うけれど、度が過ぎるとかえって勇気を削ぐことにもなると、そのときはじめて知った。 よく知らないという渇き 私が自分の魂を売り渡したとき あなたは買い戻してくれて 私を支えてくれた これはこそらく、一糸乱れず、かっこよく、速く進む行進とは異なるのだと思う。よろめきながら、ふらつきながら、倒れそうで倒れない、それでもなんとか顔を上げて進む「歩み」なのなと思う。行進というよりは、行進しようとする姿勢とでもいうのだろうか。 もっと良くなるはずだという思いだけが 人生と道を変えるはず 淡々って、あんなにも大きな力なんだ。 生きてゆける道を取り戻すこと 愛する時間は多くない 「子育て中だからって残り物ばかり食べたり、疲れてるのに窮屈な格好で寝たりしてはいけませんよ。引け目を感じることなく食べて、手足を伸ばして寝なさい。妻を見ていて思いました。そうやって生きてきた結果、痛かったり具合の悪かったりするところがどれほど多いことか…。一度きりの人生じゃないですか」 私たちの胸にも白い雪が降るときがあるでしょう その雪が溶けるまで一緒に歩いてみましょう 見てください 私は踊っています 燃え立つ車椅子で なんの魔術も秘法もありません ただ、いかなるものも私を完全に破壊できなかっただけ 傷ついても損なわれない人たち。いかなるものにも破壊されない「最後の私」を感じさせる人たち。 痛みよりは光として残る思い出。 そんな思い出があなたにもあるだろうか。百通りの気遣う言葉よりも胸が締め付けられる、黙って手を差し出す握手みたいな思い出が。 エイブルビー (誰か私の手を握ってください) もう、立ち上がって歩く時間 (もう、私の手を握って行きましょう) 誰か私の手を握ってください、という言葉を声にして出して言うのは難しい。だから断崖絶壁の上でも、手を伸ばせなくなってしまう人がいる。 - 2025年8月3日
 八重歯が見たいすんみ,チョン・セラン読み終わった訳者あとがきに、著者が物語の最後をどう改編したかが記されてるんですが、そこをそういうふうに変えてくれるチョン・セランさん一生好きだわ〜となった。 その性別であるが故に被る暴力や被害や偏見をたしかに描きながら、重さだけでなく軽やかに駆け抜けてゆくような希望とユーモアが胸にのこる。 印象に残った言葉--------- システムがシステム維持のためにしか回ってないことを知ってからは、耐えられなかったですね。放っておけばますますひどくなるのは自明なことでしたし。 役に立つ生命体じゃないかもしれないけど、それなりにおもしろくはあるよなぁ そんなものになる必要ないと思うけど。誰かの何にもなる必要ないよ。 必ず幸せになるべきだとも思わないで。それは一時的な状態でしかないんだって。みんなその一時的な状態を手にしようとしてもがいてるのよ 確かに、失礼極まりない奴らに公正だなんて、クソくらえです 人類は二十万年も進化しながらも、明らかな悪の部分をどうして取り除くことができなかったのだろう。この陳腐な話からどのようにして抜け出すことができるかについて書く人間として、何度も噛み締めるべき問いだった。 著者あとがき 会ったことのない誰かの口の中で、ポッピングシャワーのようにパチパチと弾けたいという気持ちは、ずっと変わっていません。軽さを恐れなかった時にこそ得ることができる重さを推し量りながら、へこたれずに書き続けていきます。 訳者あとがき いろいろなところで非常ベルを見かけた。トイレで盗撮についての注意喚起とともに設置されたものや、ズバリ「女性安心ベル」と名付けられたものもあった。その非常ベルを見るたびに、安心する一方、なぜか複雑な気持ちにもなった。私たちの周りには、のんなにもたくさんの危険が潜んでいるのか、と。
八重歯が見たいすんみ,チョン・セラン読み終わった訳者あとがきに、著者が物語の最後をどう改編したかが記されてるんですが、そこをそういうふうに変えてくれるチョン・セランさん一生好きだわ〜となった。 その性別であるが故に被る暴力や被害や偏見をたしかに描きながら、重さだけでなく軽やかに駆け抜けてゆくような希望とユーモアが胸にのこる。 印象に残った言葉--------- システムがシステム維持のためにしか回ってないことを知ってからは、耐えられなかったですね。放っておけばますますひどくなるのは自明なことでしたし。 役に立つ生命体じゃないかもしれないけど、それなりにおもしろくはあるよなぁ そんなものになる必要ないと思うけど。誰かの何にもなる必要ないよ。 必ず幸せになるべきだとも思わないで。それは一時的な状態でしかないんだって。みんなその一時的な状態を手にしようとしてもがいてるのよ 確かに、失礼極まりない奴らに公正だなんて、クソくらえです 人類は二十万年も進化しながらも、明らかな悪の部分をどうして取り除くことができなかったのだろう。この陳腐な話からどのようにして抜け出すことができるかについて書く人間として、何度も噛み締めるべき問いだった。 著者あとがき 会ったことのない誰かの口の中で、ポッピングシャワーのようにパチパチと弾けたいという気持ちは、ずっと変わっていません。軽さを恐れなかった時にこそ得ることができる重さを推し量りながら、へこたれずに書き続けていきます。 訳者あとがき いろいろなところで非常ベルを見かけた。トイレで盗撮についての注意喚起とともに設置されたものや、ズバリ「女性安心ベル」と名付けられたものもあった。その非常ベルを見るたびに、安心する一方、なぜか複雑な気持ちにもなった。私たちの周りには、のんなにもたくさんの危険が潜んでいるのか、と。 - 2025年7月25日
 交渉力橋下徹読み終わった上司に勧められて読んだ。著者とは政治的思想は合わないので、そこの観点では疑問に思う部分は多々あったが、交渉にだけ割り切って読んだという感じ。読みやすい一冊だと思う。 「政治家は道徳家ではない」とあったが、直近の選挙を見るに、最低限の倫理観はやっぱ必要だと思う。交渉力という面では不要なのかもしれんが、政治家の仕事は交渉だけじゃなかろう。 そんで、交渉という側面では日韓の歴史を踏まえる必要はないとかいう言葉もあったが、そんな態度を続けてしまっているからこそ、近年の排外主義や歴史修正主義的なヤカラが幅を利かせてしまってるんじゃないか。 交渉という目先よりも、もっと重んじることの方がほんとはある。そういう部分を頭の片隅に置きながら、学び取れるところだけ学びとる読み方が良さそう。
交渉力橋下徹読み終わった上司に勧められて読んだ。著者とは政治的思想は合わないので、そこの観点では疑問に思う部分は多々あったが、交渉にだけ割り切って読んだという感じ。読みやすい一冊だと思う。 「政治家は道徳家ではない」とあったが、直近の選挙を見るに、最低限の倫理観はやっぱ必要だと思う。交渉力という面では不要なのかもしれんが、政治家の仕事は交渉だけじゃなかろう。 そんで、交渉という側面では日韓の歴史を踏まえる必要はないとかいう言葉もあったが、そんな態度を続けてしまっているからこそ、近年の排外主義や歴史修正主義的なヤカラが幅を利かせてしまってるんじゃないか。 交渉という目先よりも、もっと重んじることの方がほんとはある。そういう部分を頭の片隅に置きながら、学び取れるところだけ学びとる読み方が良さそう。 - 2025年7月8日
 回復する人間ハン・ガン,斎藤真理子読み終わった急に傷つくことはあっても、急に回復することはないのかもしれない。光の加減で少し煌めく細い糸を少しずつ手繰り寄せていくような、そんな回復。 全てを手繰り寄せたとて、壊れる以前の自分に戻るわけではない。 それを分かりながらも、手繰り寄せていくような歩み。 そして夢がどの物語にも現れる。 印象に残った言葉---------- 回復する人間 彼女はまるで散歩に出てきた人みたいにゆぬくりと、壊れやすい沈黙を保護しているかのような慎重な足取りで階段を上っていた。 どんな人間関係にもありうる誤解と幻想が、彼女と私のあいだにもあった。 姉さんの罪なんて、いもしない怪物みたいなものなのに。そんなものに薄い布をかぶせて、後生大事に抱いて生きるのはやめて。ぐっすり眠ってよ。もう悪夢を見ないで。誰の非難も信じないで。 だけどそのうち一つだって、私は口にすることができなかった。 彼女が帰ってこない。この文章を消して私は待つ。全力で待つ。あたりがほの青く明るくなる前に、彼女が回復した、と最初の一行を私は書く。 これらのすべての痛覚はあまりにも弱々しいと、何度も両目をまばたきしながらあなたは思う。今、自分が経験しているどんなことからも、私を回復させないでほしいと、この冷たい土がもっと冷え、顔も体もかちこちに凍りつくようにしてくれと、お願いだからここから二度と体を起こせないようにしてくれと、あなたは誰に向けたものでもない祈りの言葉を口の中でつぶやきつづける。 こんな日の夜の散歩でいちばん大事なのは視線に耐えるということだ。偏見と嫌悪、軽蔑と恐怖の視線、ときに露骨でときに慇懃なそれらの視線を感知しながら黙って前へと進む。 離れ小島に二人きりで漂着したように、私たちはしだいに互いを窒息させるようになった。そうして、二度と渡れない川を作っていった。互いへの配慮、相手のためになりたいという気持ち、友情、仲間意識などは川の向こうに残された。 痛みがあってこそ回復がある。 韓国の小説を読んでいると往々にして、本を閉じても登場人物が何処かで生きつづけているような気がすることがある ページを閉じても終わらない、読者と一緒に生きていく女性たち。
回復する人間ハン・ガン,斎藤真理子読み終わった急に傷つくことはあっても、急に回復することはないのかもしれない。光の加減で少し煌めく細い糸を少しずつ手繰り寄せていくような、そんな回復。 全てを手繰り寄せたとて、壊れる以前の自分に戻るわけではない。 それを分かりながらも、手繰り寄せていくような歩み。 そして夢がどの物語にも現れる。 印象に残った言葉---------- 回復する人間 彼女はまるで散歩に出てきた人みたいにゆぬくりと、壊れやすい沈黙を保護しているかのような慎重な足取りで階段を上っていた。 どんな人間関係にもありうる誤解と幻想が、彼女と私のあいだにもあった。 姉さんの罪なんて、いもしない怪物みたいなものなのに。そんなものに薄い布をかぶせて、後生大事に抱いて生きるのはやめて。ぐっすり眠ってよ。もう悪夢を見ないで。誰の非難も信じないで。 だけどそのうち一つだって、私は口にすることができなかった。 彼女が帰ってこない。この文章を消して私は待つ。全力で待つ。あたりがほの青く明るくなる前に、彼女が回復した、と最初の一行を私は書く。 これらのすべての痛覚はあまりにも弱々しいと、何度も両目をまばたきしながらあなたは思う。今、自分が経験しているどんなことからも、私を回復させないでほしいと、この冷たい土がもっと冷え、顔も体もかちこちに凍りつくようにしてくれと、お願いだからここから二度と体を起こせないようにしてくれと、あなたは誰に向けたものでもない祈りの言葉を口の中でつぶやきつづける。 こんな日の夜の散歩でいちばん大事なのは視線に耐えるということだ。偏見と嫌悪、軽蔑と恐怖の視線、ときに露骨でときに慇懃なそれらの視線を感知しながら黙って前へと進む。 離れ小島に二人きりで漂着したように、私たちはしだいに互いを窒息させるようになった。そうして、二度と渡れない川を作っていった。互いへの配慮、相手のためになりたいという気持ち、友情、仲間意識などは川の向こうに残された。 痛みがあってこそ回復がある。 韓国の小説を読んでいると往々にして、本を閉じても登場人物が何処かで生きつづけているような気がすることがある ページを閉じても終わらない、読者と一緒に生きていく女性たち。 - 2025年7月3日
読み込み中...