糸太
@itota-tboyt5
- 2026年2月15日
 精選日本随筆選集 歓喜宮崎智之読み終わった随筆が流行っているという。ほかにも、近ごろは日記もよく目にするようになった。一人称で日々を描くのが、というより、それを読みたいと思う人が増えているということだろう。 こうやって名随筆を集めてもらったおかげで、鈍い私もようやく気がつく。なるほど、面白い。とくにジャンルにこだわって読書してこなかったけれど、意識して手に取ってみてもいいのかもしれない。とくに薄田泣菫。いつかまた出会えますように。 宮崎さんの作品も、随筆だとは意識してなかったけれど、たしかに印象に残ってるもんなあ。この一人称の日常というのが、いまの私にもフィットしていたということを、図らずもうまく流行りに乗れていたという意味で、こそばゆくもちょっと誇らしい。
精選日本随筆選集 歓喜宮崎智之読み終わった随筆が流行っているという。ほかにも、近ごろは日記もよく目にするようになった。一人称で日々を描くのが、というより、それを読みたいと思う人が増えているということだろう。 こうやって名随筆を集めてもらったおかげで、鈍い私もようやく気がつく。なるほど、面白い。とくにジャンルにこだわって読書してこなかったけれど、意識して手に取ってみてもいいのかもしれない。とくに薄田泣菫。いつかまた出会えますように。 宮崎さんの作品も、随筆だとは意識してなかったけれど、たしかに印象に残ってるもんなあ。この一人称の日常というのが、いまの私にもフィットしていたということを、図らずもうまく流行りに乗れていたという意味で、こそばゆくもちょっと誇らしい。 - 2026年2月15日
 タタール人の砂漠ブッツァーティ,ディーノ・ブッツァーティ,脇功読み終わった思い当たる節がありすぎる。でもその共感はけっして、こんなコトあるよなあ、といった体験に基づくものではない。 主人公ドローゴの置かれているのは、現実ではちょっと考えにくいシチュエーションである。なのに、あまりに自然に共感してしまうのは、ドローゴがこの環境下で選んでしまう、後ろ向きな決断の一つひとつが、自分もたしかにそんな風にしちゃうかも、と素直に思えてしまうからだ。 理屈では説明できない不可思議な心の動き。誰とも分かち合ったことがないのに、見事に言い当ててくる。これが、とくに大きな展開もないストーリーを通じてなのだから、ただただ驚く。 でも、時の遁走が止まった後の心象は、まだ私の感覚には遠いものだった。いつか分かるのかな。きっと分かるんだろうな。そんな予感を抱いてしまうほどに、私にとっては説得力を持つ小説だった。
タタール人の砂漠ブッツァーティ,ディーノ・ブッツァーティ,脇功読み終わった思い当たる節がありすぎる。でもその共感はけっして、こんなコトあるよなあ、といった体験に基づくものではない。 主人公ドローゴの置かれているのは、現実ではちょっと考えにくいシチュエーションである。なのに、あまりに自然に共感してしまうのは、ドローゴがこの環境下で選んでしまう、後ろ向きな決断の一つひとつが、自分もたしかにそんな風にしちゃうかも、と素直に思えてしまうからだ。 理屈では説明できない不可思議な心の動き。誰とも分かち合ったことがないのに、見事に言い当ててくる。これが、とくに大きな展開もないストーリーを通じてなのだから、ただただ驚く。 でも、時の遁走が止まった後の心象は、まだ私の感覚には遠いものだった。いつか分かるのかな。きっと分かるんだろうな。そんな予感を抱いてしまうほどに、私にとっては説得力を持つ小説だった。 - 2026年2月15日
 わたしもナグネだから伊東順子読み終わった韓国の人々の生きざまを介することで、見知った近現代史がより立体的に立ち上がってくる感覚がした。日本人として学校で学んだ知識だけでは、いかに世界を捉えるのに不充分かを思い知らされる。 北朝鮮、ロシア、中国、そして米国。隣国であるだけに取りまく環境は日本と似ているが、それぞれの国との関わり具合は随分と違う。もちろん地理的要因もあるだろう。でも決定的に異なるのは、やむを得ず移動せざるを得なかった人々の数なのかもしれない。そんな同胞の存在が、国境という前提を無意識に拡張していく。 コロナへの対応の違いにも、はっとさせられる。水際対策を加速させた我が国に対して、韓国は「国境を閉じることはしなかった。日本以上に厳しい監視と行動規制をしながらも、人々の移動は止めない。それが韓国政府のポリシーであり、背景には「誇りある七〇〇万人海外同胞」の存在がある」と、伊東さんは指摘している。 そしてこの感覚は、いま現在と地続きなのだ。登場する人物たちの魅力的な語りに、私自身の足元を照らし出してもらえた気がしている。
わたしもナグネだから伊東順子読み終わった韓国の人々の生きざまを介することで、見知った近現代史がより立体的に立ち上がってくる感覚がした。日本人として学校で学んだ知識だけでは、いかに世界を捉えるのに不充分かを思い知らされる。 北朝鮮、ロシア、中国、そして米国。隣国であるだけに取りまく環境は日本と似ているが、それぞれの国との関わり具合は随分と違う。もちろん地理的要因もあるだろう。でも決定的に異なるのは、やむを得ず移動せざるを得なかった人々の数なのかもしれない。そんな同胞の存在が、国境という前提を無意識に拡張していく。 コロナへの対応の違いにも、はっとさせられる。水際対策を加速させた我が国に対して、韓国は「国境を閉じることはしなかった。日本以上に厳しい監視と行動規制をしながらも、人々の移動は止めない。それが韓国政府のポリシーであり、背景には「誇りある七〇〇万人海外同胞」の存在がある」と、伊東さんは指摘している。 そしてこの感覚は、いま現在と地続きなのだ。登場する人物たちの魅力的な語りに、私自身の足元を照らし出してもらえた気がしている。 - 2026年2月3日
 斜め論松本卓也読み終わった何か問題が生じたとき、その原因を探り当てて除去する。また動き出してみて上手くいかなかったら、違う原因を探し出して除去。そしてまたすぐ動く。繰り返せば必ず未来は開ける。怖がるな、スピードを落とすな、動き続けろ…。 べつに医療やケアの現場の話ではないけれども、一般的にそんな価値観ってある気がする。 でも、原因に対処する動きはなにも一つだけってわけでもない。仲間と話し合ったりしながらいろいろと試してるうちに、ひょんなことから問題そのものが雲散霧消し、なのにまた新たに問題が見つかって、顔を見合わせ笑っちゃうこともあるんじゃなかろうか。 この本を読みながら、そんなことを考えていた。そしてこうも思った。でもやっぱり、どっちかだけじゃなくてバランスなんだよな。 水平、垂直、そして斜め。空間的に捉えれば、ほかの場面でも面白く捉え直すことができるかもしれない。そのための参考になる考え方が、この本からは多く得られた気がしている。 たとえばオープンダイアローグの中で、弱毒化した垂直的関係を導入するための「リフレクティング」という工夫、さらに補論Ⅱのアディクションアプローチとハームリダクションの関係などは、とても興味深かった。
斜め論松本卓也読み終わった何か問題が生じたとき、その原因を探り当てて除去する。また動き出してみて上手くいかなかったら、違う原因を探し出して除去。そしてまたすぐ動く。繰り返せば必ず未来は開ける。怖がるな、スピードを落とすな、動き続けろ…。 べつに医療やケアの現場の話ではないけれども、一般的にそんな価値観ってある気がする。 でも、原因に対処する動きはなにも一つだけってわけでもない。仲間と話し合ったりしながらいろいろと試してるうちに、ひょんなことから問題そのものが雲散霧消し、なのにまた新たに問題が見つかって、顔を見合わせ笑っちゃうこともあるんじゃなかろうか。 この本を読みながら、そんなことを考えていた。そしてこうも思った。でもやっぱり、どっちかだけじゃなくてバランスなんだよな。 水平、垂直、そして斜め。空間的に捉えれば、ほかの場面でも面白く捉え直すことができるかもしれない。そのための参考になる考え方が、この本からは多く得られた気がしている。 たとえばオープンダイアローグの中で、弱毒化した垂直的関係を導入するための「リフレクティング」という工夫、さらに補論Ⅱのアディクションアプローチとハームリダクションの関係などは、とても興味深かった。 - 2026年2月2日
 シリアの家族小松由佳読み終わった戦場は思ったよりも日常で、日常は思ったより戦場である。戦禍を描く作品に触れるとき、よくこんなことを思う。考えれば当たり前のこと。どんな環境に置かれても生活は続くのだから。戦場から遠く離れた場所に暮らしているとつい忘れがちなこの当たり前を、小松さんの文章は手触り感のある現実として思い出させてくれる。 アサド政権下の緊迫した空気感を味わった直後に、「おいおい、ラードワーン(小松さんのパートナー)」と頭を抱えたくなる家族の騒動が起こったり。どちらも切羽詰まった問題であり、いや、そもそも分けて考えられるものでもなく、一人の人間が直面しているたった一つの日常であることを教えてくれる。 もちろんシリアの貴重な記録であることは間違いない。ただ心に残るのは人間のことなのだ。前作の『人間の土地へ』というタイトルがまさに、今作にもずっと響き続けている。
シリアの家族小松由佳読み終わった戦場は思ったよりも日常で、日常は思ったより戦場である。戦禍を描く作品に触れるとき、よくこんなことを思う。考えれば当たり前のこと。どんな環境に置かれても生活は続くのだから。戦場から遠く離れた場所に暮らしているとつい忘れがちなこの当たり前を、小松さんの文章は手触り感のある現実として思い出させてくれる。 アサド政権下の緊迫した空気感を味わった直後に、「おいおい、ラードワーン(小松さんのパートナー)」と頭を抱えたくなる家族の騒動が起こったり。どちらも切羽詰まった問題であり、いや、そもそも分けて考えられるものでもなく、一人の人間が直面しているたった一つの日常であることを教えてくれる。 もちろんシリアの貴重な記録であることは間違いない。ただ心に残るのは人間のことなのだ。前作の『人間の土地へ』というタイトルがまさに、今作にもずっと響き続けている。 - 2026年1月26日
 つぎの民話松井至読み終わった「言葉が嫌いだった」という人が書いたとはとても思えない。まるで詩のように、頭を経由することなく直接心を動かされる。不思議に思いながらも、いや、もしかしたら逆かもしれないと思い直す。つまり、嫌いだからこそ、こんな風に書けるのかもしれない。 『うたうかなた』という章は、障がい者の集うアトリエが舞台だ。ここには複数の職員が働いているがマニュアルはない。利用者ごとに異なる特性の把握も「ひとりの人間に向き合うことに変わりはないので意味を感じなくなって止めました」と、代表の男性は当たり前のように語る。そんな場のあり方を見て松井さんは、「いつも言葉が持つ分別の能力とは反対を向いて、むしろ分け隔てられてきたものの境をなくして初期化することを試みていた」のではと感じる。 私には、この世界への向き合い方が松井さんの文章と重なって見えた。 言葉が覆い隠してしまう世界がある。饒舌になればなるほど、あるという確かな事実すら忘れてしまう。 それは映像も同じだ。カメラはどうしたって恣意的に世界を切り取ってしまう。そんな道具を携えて、松井さんは悩みつつキャリアを重ねてきたのだろう。だからこそ、カメラをペンに持ち替えても、世界へと触れようとする作法や佇まいは変わらない。 たとえば多様性という概念がある。いろんな人の個性を尊重しようとする態度が大切であることは間違いない。 でも、そもそもが多様なのである。それを画一的に向かわせてきたのが、言葉であり映像なのだということを思ったりした。つまり、自分と相手を分けて考えて、お互いの立場を尊重するという態度がすでに、世界の在り方に即してないのではないか、という直感に出会ったりして、案外慄いたりする。 映像作品へのリンクもある。 こんなにも本が面白いんだ。本業である仕事にはさらに興味津々である。
つぎの民話松井至読み終わった「言葉が嫌いだった」という人が書いたとはとても思えない。まるで詩のように、頭を経由することなく直接心を動かされる。不思議に思いながらも、いや、もしかしたら逆かもしれないと思い直す。つまり、嫌いだからこそ、こんな風に書けるのかもしれない。 『うたうかなた』という章は、障がい者の集うアトリエが舞台だ。ここには複数の職員が働いているがマニュアルはない。利用者ごとに異なる特性の把握も「ひとりの人間に向き合うことに変わりはないので意味を感じなくなって止めました」と、代表の男性は当たり前のように語る。そんな場のあり方を見て松井さんは、「いつも言葉が持つ分別の能力とは反対を向いて、むしろ分け隔てられてきたものの境をなくして初期化することを試みていた」のではと感じる。 私には、この世界への向き合い方が松井さんの文章と重なって見えた。 言葉が覆い隠してしまう世界がある。饒舌になればなるほど、あるという確かな事実すら忘れてしまう。 それは映像も同じだ。カメラはどうしたって恣意的に世界を切り取ってしまう。そんな道具を携えて、松井さんは悩みつつキャリアを重ねてきたのだろう。だからこそ、カメラをペンに持ち替えても、世界へと触れようとする作法や佇まいは変わらない。 たとえば多様性という概念がある。いろんな人の個性を尊重しようとする態度が大切であることは間違いない。 でも、そもそもが多様なのである。それを画一的に向かわせてきたのが、言葉であり映像なのだということを思ったりした。つまり、自分と相手を分けて考えて、お互いの立場を尊重するという態度がすでに、世界の在り方に即してないのではないか、という直感に出会ったりして、案外慄いたりする。 映像作品へのリンクもある。 こんなにも本が面白いんだ。本業である仕事にはさらに興味津々である。 - 2026年1月19日
 大正教養主義の成立と末路松井健人読み終わった何の疑いも持っていなかった。「教養」は善いもので、あるに越したことはない、のではなかったっけ。 価値観が揺さぶれる。とても心地よい。読書に求めるものがまさにこれ。そんな思いを抱き、手当たり次第に本を求めたいと感じた自分に、思わず苦笑してしまう。なにも東西の古典を漁ろうってわけじゃないが、同じ穴のムジナと言えなくもないような…。
大正教養主義の成立と末路松井健人読み終わった何の疑いも持っていなかった。「教養」は善いもので、あるに越したことはない、のではなかったっけ。 価値観が揺さぶれる。とても心地よい。読書に求めるものがまさにこれ。そんな思いを抱き、手当たり次第に本を求めたいと感じた自分に、思わず苦笑してしまう。なにも東西の古典を漁ろうってわけじゃないが、同じ穴のムジナと言えなくもないような…。 - 2026年1月19日
 オルタナティブ民俗学島村恭則,畑中章宏読み終わったたしかに「民俗学」って、何を対象にしているのか、知っているようで知らずに過ごしてきた。たとえば「民藝」とは、扱う範囲がどう違うのか。無理に線引きする必要もないのかもしれないが、その眼差すところの違いは非常に興味深かった。 また、民俗学を取り巻く現在の世界的な流れも、私が抱いているイメージとはズレがあった。なるほど「オルタナティブ」である。機会があれば、島村さんの本もぜひ手に取ってみようと思う。
オルタナティブ民俗学島村恭則,畑中章宏読み終わったたしかに「民俗学」って、何を対象にしているのか、知っているようで知らずに過ごしてきた。たとえば「民藝」とは、扱う範囲がどう違うのか。無理に線引きする必要もないのかもしれないが、その眼差すところの違いは非常に興味深かった。 また、民俗学を取り巻く現在の世界的な流れも、私が抱いているイメージとはズレがあった。なるほど「オルタナティブ」である。機会があれば、島村さんの本もぜひ手に取ってみようと思う。 - 2026年1月12日
 生きるための表現手引き渡邉康太郎読み終わった私にも「つたない」ながらも続けている趣味がいくつかある。これらを表現活動と呼ぶのはおこがましいが、渡邉さんはそんな気持ちを肯定して、それこそが大事なんだと背中を押してくれる。 大切なのは「変化」だという。目指すのは「上達」だけじゃなくていい。「下手」でもがいているからこそ、自分だけに見つけられることもあるのかもしれない。 「ひとりの人が自分の心身で感じ取った、言葉になりえない感触には、独特の意味が宿ります」 ここをもっと面白がれたら、「成長」という評価軸から逃れられそうだ。できないはずがない。だってその昔、面白そうという衝動にしたがってやり始めたんだから。 渡邉さんの授業って楽しいだろうなあ。いつか「ひとりだけの展覧会」も試してみようと思う。
生きるための表現手引き渡邉康太郎読み終わった私にも「つたない」ながらも続けている趣味がいくつかある。これらを表現活動と呼ぶのはおこがましいが、渡邉さんはそんな気持ちを肯定して、それこそが大事なんだと背中を押してくれる。 大切なのは「変化」だという。目指すのは「上達」だけじゃなくていい。「下手」でもがいているからこそ、自分だけに見つけられることもあるのかもしれない。 「ひとりの人が自分の心身で感じ取った、言葉になりえない感触には、独特の意味が宿ります」 ここをもっと面白がれたら、「成長」という評価軸から逃れられそうだ。できないはずがない。だってその昔、面白そうという衝動にしたがってやり始めたんだから。 渡邉さんの授業って楽しいだろうなあ。いつか「ひとりだけの展覧会」も試してみようと思う。 - 2026年1月12日
 天人五衰三島由紀夫読み終わったこれまで時代を越えて連綿と続いてきた「宿命」づけられた「純粋」。もっとも相容れないのが「自意識」でありそうなものだが、第四巻ではむしろ、登場人物たちがその自意識にとらわれていく様が描かれているように見える。 たとえば本多は、自意識とそれを超えた世界との狭間で、自分と性質がよく似た透に「夢」を見ようとした。しかし、この壮大な実験の中にも自意識は知らぬ間に忍び寄ってくる。 肉体を通してではなく、ただ「見る」ことはできるのだろうか。死という方法のほかに。 本多は自らの肉体の滅びを前にして、理知を介さずに世界に触れるための気づきを得ていく。 「死を内側から生きるという、この世の少数の者にしか許されていない感覚上の修練を本多はおのずから会得していた。(中略)この世をひとたび終末の側から眺めれば、すべては確定し、一本の糸に引きしぼられ、終りへ向って足並をそろえて進んでいた。(中略)理智はなお動いていたが氷結していた。美はすべて幻のようになった」 この境地に及んで、本多はラストシーンへと導かれていく。これこそ本多の運命だったとも言えるのかもしれない。 そこで衝撃的な言葉と出くわす。これまで紡いできた物語を一気にひっくり返すほどの、凄まじい一言に。 でも、読み終えて思う。妙な納得感があるのだ。とんでもないことを言われたのに、同時に、そりゃそうなるのかもなあと腑に落ちるような。 さて三島由紀夫である。この物語を読んで、市ヶ谷での最期について、すこし印象が変わった。憂国などという言葉以上の世界観が広がる。この入口を感じられただけでも、今回の読書は貴重な体験だったなあ。
天人五衰三島由紀夫読み終わったこれまで時代を越えて連綿と続いてきた「宿命」づけられた「純粋」。もっとも相容れないのが「自意識」でありそうなものだが、第四巻ではむしろ、登場人物たちがその自意識にとらわれていく様が描かれているように見える。 たとえば本多は、自意識とそれを超えた世界との狭間で、自分と性質がよく似た透に「夢」を見ようとした。しかし、この壮大な実験の中にも自意識は知らぬ間に忍び寄ってくる。 肉体を通してではなく、ただ「見る」ことはできるのだろうか。死という方法のほかに。 本多は自らの肉体の滅びを前にして、理知を介さずに世界に触れるための気づきを得ていく。 「死を内側から生きるという、この世の少数の者にしか許されていない感覚上の修練を本多はおのずから会得していた。(中略)この世をひとたび終末の側から眺めれば、すべては確定し、一本の糸に引きしぼられ、終りへ向って足並をそろえて進んでいた。(中略)理智はなお動いていたが氷結していた。美はすべて幻のようになった」 この境地に及んで、本多はラストシーンへと導かれていく。これこそ本多の運命だったとも言えるのかもしれない。 そこで衝撃的な言葉と出くわす。これまで紡いできた物語を一気にひっくり返すほどの、凄まじい一言に。 でも、読み終えて思う。妙な納得感があるのだ。とんでもないことを言われたのに、同時に、そりゃそうなるのかもなあと腑に落ちるような。 さて三島由紀夫である。この物語を読んで、市ヶ谷での最期について、すこし印象が変わった。憂国などという言葉以上の世界観が広がる。この入口を感じられただけでも、今回の読書は貴重な体験だったなあ。 - 2026年1月3日
 暁の寺三島由紀夫読み終わった転生はしたのか。そもそも転生する主体とは何なのか。いや、むしろこれを感じ取っている本多の世界の方が、あまりに不確かで疑わしいのではないか。 幼い月光姫は日本人の生まれ変わりを訴える。しかし脇腹に黒子は見えない。この不在が本多の心の底と共鳴する。 「救われるという資質の久如。人が思わず手をさしのべて、自分も大切にしている或る輝やかしい価値の救済を企てずにはいられぬような、そういう危機を感じさせたことがなかった。(それこそは魅惑というものではないか。)遺憾ながら、彼は魅惑に失けた自立的な人間だったのである」 この自覚が屈折した恋心に変わる。不可能を前提とする「純粋」への、矛盾を孕む希求と重ね合わせながら。 そして、この欲望の成就する世界が、インドで体験した世界の在り方とも響き合う。アートマンとブラフマンに融け合う世界。阿頼耶識に触れては消滅していく世界。月光姫は言う。 「小さいころの私は、鏡のような子供で、人の心のなかにあるものを全部映すことができて、それを口に出して言っていたのではないか、思うのです。あなたが何か考える、するとそれがみんな私の心に映る、そんな具合だった」 黒子が見えるか見えないかも、そうなのかもしれない。世界をどう見たいのか。いま生きている世界もこんな理知や意志の入り込む隙もない不確かさの上にしかない…でも、本当にそうだろうか。 世界とは隔絶した存在もまたある。象徴的に描かれているのが、富士山と月光姫であるように思った。結局、本多の預かり知らぬところで月光姫は死んだ。しかも20歳で。 第四巻では転生がどう成されるのか。矜持をも失ってしまった日本人の群衆が、これでもかというくらい醜く描かれるような予感もする。 いよいよ最後か。どきどきしながら読み進めたいと思う。
暁の寺三島由紀夫読み終わった転生はしたのか。そもそも転生する主体とは何なのか。いや、むしろこれを感じ取っている本多の世界の方が、あまりに不確かで疑わしいのではないか。 幼い月光姫は日本人の生まれ変わりを訴える。しかし脇腹に黒子は見えない。この不在が本多の心の底と共鳴する。 「救われるという資質の久如。人が思わず手をさしのべて、自分も大切にしている或る輝やかしい価値の救済を企てずにはいられぬような、そういう危機を感じさせたことがなかった。(それこそは魅惑というものではないか。)遺憾ながら、彼は魅惑に失けた自立的な人間だったのである」 この自覚が屈折した恋心に変わる。不可能を前提とする「純粋」への、矛盾を孕む希求と重ね合わせながら。 そして、この欲望の成就する世界が、インドで体験した世界の在り方とも響き合う。アートマンとブラフマンに融け合う世界。阿頼耶識に触れては消滅していく世界。月光姫は言う。 「小さいころの私は、鏡のような子供で、人の心のなかにあるものを全部映すことができて、それを口に出して言っていたのではないか、思うのです。あなたが何か考える、するとそれがみんな私の心に映る、そんな具合だった」 黒子が見えるか見えないかも、そうなのかもしれない。世界をどう見たいのか。いま生きている世界もこんな理知や意志の入り込む隙もない不確かさの上にしかない…でも、本当にそうだろうか。 世界とは隔絶した存在もまたある。象徴的に描かれているのが、富士山と月光姫であるように思った。結局、本多の預かり知らぬところで月光姫は死んだ。しかも20歳で。 第四巻では転生がどう成されるのか。矜持をも失ってしまった日本人の群衆が、これでもかというくらい醜く描かれるような予感もする。 いよいよ最後か。どきどきしながら読み進めたいと思う。 - 2025年12月26日
 奔馬三島由紀夫読み終わった若者の内にある「純粋」は美しく、これ以上なく強く人を惹きつける。 でも、いざ誰かと分かち合おうとすると、簡単に穢されてしまう。瞬く間に強さは失われ、世の中に均されてしまう。 だから「純粋」をそのままの姿で捉えるには、本人からの働きかけが為されるより前に、周りにいる人間が自らのうちに見出してやる必要がある。 勲の同志たちもしかり。だから決起へと向かう際には、リーダーの掛け声よりも人智を超えた神の言葉が必要だった。 でも「宇気比」はおりてこず、結果的に心の「純粋」には蓋がされ、各々が持っていた悪か蒐められて「裏切り」を招くことになった。 いや、むしろ血盟こそが悪の本質なのでは、と勲は疑う。血盟とは「もう少しで真理に手を届かせようとしては死によって挫折して、又あらためて羊水の中の眠りからはじめなければならぬ、あの賽の河原のような人類的営為に対する、晴れやかな侮蔑だったのだ」 であれば、「純粋」は世の中にどう存在しうるのだろうか。 松枝清顕は死んだ。そして飯沼勲に転生し、「純粋」は本多の心の中に見出された。ここまではいいのだ。他人さえ巻き込まなければ。 さて、物語の次なる舞台はどこだろう。20年後と考えれば、サンフランシスコ平和条約あたり。そして第四巻は高度成長期になろうか。 そう単純に、転生ストーリーが続くとも限らないか。 面白すぎる。はやく第三巻に進もう。
奔馬三島由紀夫読み終わった若者の内にある「純粋」は美しく、これ以上なく強く人を惹きつける。 でも、いざ誰かと分かち合おうとすると、簡単に穢されてしまう。瞬く間に強さは失われ、世の中に均されてしまう。 だから「純粋」をそのままの姿で捉えるには、本人からの働きかけが為されるより前に、周りにいる人間が自らのうちに見出してやる必要がある。 勲の同志たちもしかり。だから決起へと向かう際には、リーダーの掛け声よりも人智を超えた神の言葉が必要だった。 でも「宇気比」はおりてこず、結果的に心の「純粋」には蓋がされ、各々が持っていた悪か蒐められて「裏切り」を招くことになった。 いや、むしろ血盟こそが悪の本質なのでは、と勲は疑う。血盟とは「もう少しで真理に手を届かせようとしては死によって挫折して、又あらためて羊水の中の眠りからはじめなければならぬ、あの賽の河原のような人類的営為に対する、晴れやかな侮蔑だったのだ」 であれば、「純粋」は世の中にどう存在しうるのだろうか。 松枝清顕は死んだ。そして飯沼勲に転生し、「純粋」は本多の心の中に見出された。ここまではいいのだ。他人さえ巻き込まなければ。 さて、物語の次なる舞台はどこだろう。20年後と考えれば、サンフランシスコ平和条約あたり。そして第四巻は高度成長期になろうか。 そう単純に、転生ストーリーが続くとも限らないか。 面白すぎる。はやく第三巻に進もう。 - 2025年12月13日
 春の雪三島由紀夫読み終わった今年は三島由紀夫生誕百年らしい。年末になって気がついて、これもなんかのタイミングだと手に取った。 遺作ということもあり、どうしても割腹自殺と結びつけて文章を追ってしまう。もちろん真意など知るべくもないが、それでも物語を通じて描き出される世界は美しくありながら雄弁である。 「個性のことを考えているんだ」 たとえば清顕の友人である本多の語りには、明治が過去になりつつある時代ならではの苦悩が滲む。 歴史の大きな流れに比べたら、個人などないに等しいほど小さい。とは言え、小さくとも自分の成し遂げたことが、未来に社会を変える一助になるかもしれない。でも、もう生きてはいない自分にとって、そこには何の意味があるだろう。 「それが歴史というものだ、と人は言うだろう」 頭ではわかる。けれども本多は、自分が意志の人間であることをやめられないと嘆く。そして、自分には理解できない佇まいでこの時代と向き合う清顕に、寄り添っていくことを決める。 「海と陸とのこれほど壮大な境界に身を置く思いは、あたかも一つの時代から一つの時代へ移る、巨きな歴史的瞬間に立会っているような気がするではないか。そして本多と清頭が生きている現代も、一つの潮の退き際、一つの波打際、一つの境界に他ならなかった」 タイトルを思い起こさせる。どこまでも広く深い海は、どんな比喩をも溶け込ませてしまう。 それにしても、不勉強ながらあらすじも知らずに読み始めたものだから、最後の一文には結構な衝撃を受けた。 嘘だろ。 どうすんのよ、これから。 はやく第二巻を求めなくては。
春の雪三島由紀夫読み終わった今年は三島由紀夫生誕百年らしい。年末になって気がついて、これもなんかのタイミングだと手に取った。 遺作ということもあり、どうしても割腹自殺と結びつけて文章を追ってしまう。もちろん真意など知るべくもないが、それでも物語を通じて描き出される世界は美しくありながら雄弁である。 「個性のことを考えているんだ」 たとえば清顕の友人である本多の語りには、明治が過去になりつつある時代ならではの苦悩が滲む。 歴史の大きな流れに比べたら、個人などないに等しいほど小さい。とは言え、小さくとも自分の成し遂げたことが、未来に社会を変える一助になるかもしれない。でも、もう生きてはいない自分にとって、そこには何の意味があるだろう。 「それが歴史というものだ、と人は言うだろう」 頭ではわかる。けれども本多は、自分が意志の人間であることをやめられないと嘆く。そして、自分には理解できない佇まいでこの時代と向き合う清顕に、寄り添っていくことを決める。 「海と陸とのこれほど壮大な境界に身を置く思いは、あたかも一つの時代から一つの時代へ移る、巨きな歴史的瞬間に立会っているような気がするではないか。そして本多と清頭が生きている現代も、一つの潮の退き際、一つの波打際、一つの境界に他ならなかった」 タイトルを思い起こさせる。どこまでも広く深い海は、どんな比喩をも溶け込ませてしまう。 それにしても、不勉強ながらあらすじも知らずに読み始めたものだから、最後の一文には結構な衝撃を受けた。 嘘だろ。 どうすんのよ、これから。 はやく第二巻を求めなくては。 - 2025年12月1日
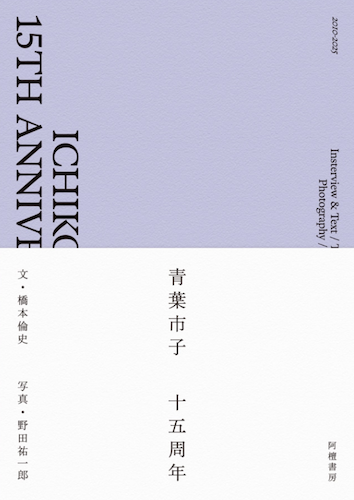 ICHIKO AOBA 15th Anniversary Book橋本倫史,野田祐一郎読み終わった近ごろ音楽はもっぱら仕事をしながらのストリーミング再生である。私が選ぶのは最初の一曲だけ。あとは次から次へと好きそうな曲を勝手に流してくれるが、ときおり強く惹きつけられて仕事の手がとまることがある。青葉市子さんの音楽とは、こうして出会った。 本書では、15年の音楽活動を振り返りつつ、青葉さんが音楽とどう向き合ってきたかを、ほんの少しだけ垣間見ることができる。その時そのときの自分と真摯に向き合って、必死に産み落としてきた音楽なんだなという印象を強く持った。 これは作品制作だけではなく、演奏についても同じ。弾いた弦の響きはその時のものでしかないから、空気にかき消えてしまうまでの全責任を負う、みたいな覚悟さえ感じた。 ストリーミングで聞き流している場合じゃないな。生で聴ける機会も狙いつつ、とりあえずファーストアルバムから、時系列をたどって聴いてみようと思う。
ICHIKO AOBA 15th Anniversary Book橋本倫史,野田祐一郎読み終わった近ごろ音楽はもっぱら仕事をしながらのストリーミング再生である。私が選ぶのは最初の一曲だけ。あとは次から次へと好きそうな曲を勝手に流してくれるが、ときおり強く惹きつけられて仕事の手がとまることがある。青葉市子さんの音楽とは、こうして出会った。 本書では、15年の音楽活動を振り返りつつ、青葉さんが音楽とどう向き合ってきたかを、ほんの少しだけ垣間見ることができる。その時そのときの自分と真摯に向き合って、必死に産み落としてきた音楽なんだなという印象を強く持った。 これは作品制作だけではなく、演奏についても同じ。弾いた弦の響きはその時のものでしかないから、空気にかき消えてしまうまでの全責任を負う、みたいな覚悟さえ感じた。 ストリーミングで聞き流している場合じゃないな。生で聴ける機会も狙いつつ、とりあえずファーストアルバムから、時系列をたどって聴いてみようと思う。 - 2025年12月1日
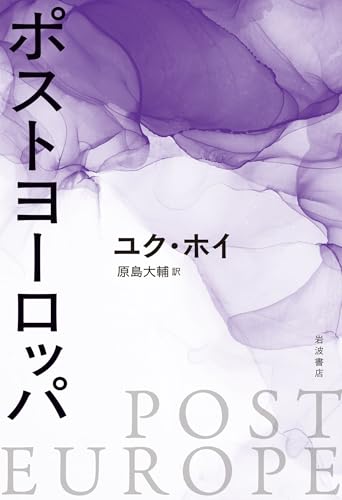 ポストヨーロッパユク・ホイ読み終わった生まれ落ちたのが、すっかりアメリカ化された日本である私にとって、思考の個体化はいかにしてなされうるのだろうか。 難解な内容に読み進めるのも骨が折れたが、それでも綱渡りのように理解された内容を寄せ集めていくと、それはそれで恐ろしいことが書かれているようにも思えた。 つまり、言葉(もしくは「舌」)を超えて思考せよ、と言われている気がする。そこにこそ、個体化への希望が残されている、と。 もしかして全く的外れなのかもしれない。けれども、私の中ではぎりぎり繋がっている。 100年単位の未来を見据えたときに、ポストヨーロッパ的な思考が求められるのは間違いないのだろう。この前提に立ったうえで、足がかりにできるヒントが、この本には存分に詰まっていることは感じるのだが、いかんせん難しい…。
ポストヨーロッパユク・ホイ読み終わった生まれ落ちたのが、すっかりアメリカ化された日本である私にとって、思考の個体化はいかにしてなされうるのだろうか。 難解な内容に読み進めるのも骨が折れたが、それでも綱渡りのように理解された内容を寄せ集めていくと、それはそれで恐ろしいことが書かれているようにも思えた。 つまり、言葉(もしくは「舌」)を超えて思考せよ、と言われている気がする。そこにこそ、個体化への希望が残されている、と。 もしかして全く的外れなのかもしれない。けれども、私の中ではぎりぎり繋がっている。 100年単位の未来を見据えたときに、ポストヨーロッパ的な思考が求められるのは間違いないのだろう。この前提に立ったうえで、足がかりにできるヒントが、この本には存分に詰まっていることは感じるのだが、いかんせん難しい…。 - 2025年11月30日
 ポピュリズム大陸 南米外山尚之読み終わった日本にいると自然とニュースは欧米もしくはアジアに偏る。これが地球の裏側にある南米となれば、どうしたって縁遠い。 だからだろう。大きな出来事があっても、大雑把な理解だけで済ませてしまう。 そんな時、たとえば「お祭り好きな南米の気質」みたいなのは、私にとって物事を単純化するのにとても都合がよくて、つまり「考え方のデフォルトが違うのだからこんな事が起きるのだ」などと、ほとんど何も分かろうとしていない態度で納得してしまうことが多い。 この本を読んで、そんな「南米気質」の根っこにある前提を学び直すことができた。まずは植民地支配に端を発する格差社会がある。日々の生活がままならない中に差し込む希望の光にも、読書前よりも深い解像度をもって想像を広げられた。 すると不思議なことに、歩んできた歴史が全く異なる日本の中にも、たびたび同じような風景が見つかる気がしてきた。もちろん違う。けれども民主主義を使いこなすうえで、南米諸国から学ぶべき点は数多くある。 外山さんの言葉を借りるなら、「政治を動かしているのは、(中略)顔の見えない属性ではなく、人々の熱意」である。地球の反対側だろうが、その真理は変わることはない。
ポピュリズム大陸 南米外山尚之読み終わった日本にいると自然とニュースは欧米もしくはアジアに偏る。これが地球の裏側にある南米となれば、どうしたって縁遠い。 だからだろう。大きな出来事があっても、大雑把な理解だけで済ませてしまう。 そんな時、たとえば「お祭り好きな南米の気質」みたいなのは、私にとって物事を単純化するのにとても都合がよくて、つまり「考え方のデフォルトが違うのだからこんな事が起きるのだ」などと、ほとんど何も分かろうとしていない態度で納得してしまうことが多い。 この本を読んで、そんな「南米気質」の根っこにある前提を学び直すことができた。まずは植民地支配に端を発する格差社会がある。日々の生活がままならない中に差し込む希望の光にも、読書前よりも深い解像度をもって想像を広げられた。 すると不思議なことに、歩んできた歴史が全く異なる日本の中にも、たびたび同じような風景が見つかる気がしてきた。もちろん違う。けれども民主主義を使いこなすうえで、南米諸国から学ぶべき点は数多くある。 外山さんの言葉を借りるなら、「政治を動かしているのは、(中略)顔の見えない属性ではなく、人々の熱意」である。地球の反対側だろうが、その真理は変わることはない。 - 2025年11月17日
 歴史修正ミュージアム小森真樹読み終わった私にとってミュージアムは美術品を鑑賞しにいく場所でしかなかった。展示されているのは世にも貴重な芸術品で、だからこそ敷居が高く、足を向けるのには多少の緊張が伴った。 でもそれは違う、と本書は教えてくれる。 そもそもコレクションは恣意的な視線を通じて行われたものであるし、展示にはその時代の空気による編集を加えたものにしかならない。そして、そのような「歴史修正」は絶えず更新され続けており、私のようなアートに気後れするような人々の手にも、ひろく委ねられている。 もちろん無視しようとすればできるけれど、その態度はけっして、未来の社会に好ましい結果を導きはしないだろう。 色眼鏡をはずしてみる。案外、ミュージアムの側からは、手を伸ばしてくれているのかも。
歴史修正ミュージアム小森真樹読み終わった私にとってミュージアムは美術品を鑑賞しにいく場所でしかなかった。展示されているのは世にも貴重な芸術品で、だからこそ敷居が高く、足を向けるのには多少の緊張が伴った。 でもそれは違う、と本書は教えてくれる。 そもそもコレクションは恣意的な視線を通じて行われたものであるし、展示にはその時代の空気による編集を加えたものにしかならない。そして、そのような「歴史修正」は絶えず更新され続けており、私のようなアートに気後れするような人々の手にも、ひろく委ねられている。 もちろん無視しようとすればできるけれど、その態度はけっして、未来の社会に好ましい結果を導きはしないだろう。 色眼鏡をはずしてみる。案外、ミュージアムの側からは、手を伸ばしてくれているのかも。 - 2025年11月10日
 柳宗悦 無地の美学佐々風太読み終わった柳宗悦の美について語られるとき、浄土真宗の「他力」がよく取り上げられる。たとえば、自らのはからいを超えた他力に委ねた造形にこそ美は宿る、といった具合に。 そのたびに、じゃあその造形を美しいと感じる心からは、はからいをどう排除できるのか、というのがいつも疑問だった。 本書の第四章では、「見る」-「見られる」の構造として、これと似た問題に触れられている。自分の中の疑問が氷解したわけではないが、考えるヒントをたくさんもらえた気がしている。 さらに、もっと対等に美と付き合いたいなと普段から思っている私にとって、第五章から終章にかけては、すこしの希望も感じられた。 「私たちは、知らず知らずのうちに無地の美をーあるいは無地的なる言動をー生んでいる可能性があるということを、柳の無地論は示唆する」なんて、とても心強く響いた。
柳宗悦 無地の美学佐々風太読み終わった柳宗悦の美について語られるとき、浄土真宗の「他力」がよく取り上げられる。たとえば、自らのはからいを超えた他力に委ねた造形にこそ美は宿る、といった具合に。 そのたびに、じゃあその造形を美しいと感じる心からは、はからいをどう排除できるのか、というのがいつも疑問だった。 本書の第四章では、「見る」-「見られる」の構造として、これと似た問題に触れられている。自分の中の疑問が氷解したわけではないが、考えるヒントをたくさんもらえた気がしている。 さらに、もっと対等に美と付き合いたいなと普段から思っている私にとって、第五章から終章にかけては、すこしの希望も感じられた。 「私たちは、知らず知らずのうちに無地の美をーあるいは無地的なる言動をー生んでいる可能性があるということを、柳の無地論は示唆する」なんて、とても心強く響いた。 - 2025年11月10日
 読み終わった土地の凹凸はどうしてこんなにも心を湧き立たせるのだろう。足の裏からダイレクトに伝わる刺激が、目の前に広がる景色を後退させ、その土地のもう一つの姿を浮かび上がらせてくれる。 この本が見せてくれるのは、そんな遠い昔でもない「武蔵野」である。何世代か遡るだけなのに、とんだ異世界が広がっている。でもその場所は、不思議と居心地がよかった。 本文中には武蔵野を描いた文学作品が多く紹介される。さまざまな角度からの描写に触れるたび、その景色を知っているような気さえしてくる。 このあり得ない既視感のなかに、なぜか居心地のよさが潜んでいる。 光の歴史だけではなく、闇があってもなお。 人間が自然とのあわいに生きてきた記憶は、案外、いろんな所に転がっているのかもしれない。 祖父母のちょっとした仕草や神社の大木の根元に生える雑草とか、または、いま踏みしめている土地の凹凸にも。
読み終わった土地の凹凸はどうしてこんなにも心を湧き立たせるのだろう。足の裏からダイレクトに伝わる刺激が、目の前に広がる景色を後退させ、その土地のもう一つの姿を浮かび上がらせてくれる。 この本が見せてくれるのは、そんな遠い昔でもない「武蔵野」である。何世代か遡るだけなのに、とんだ異世界が広がっている。でもその場所は、不思議と居心地がよかった。 本文中には武蔵野を描いた文学作品が多く紹介される。さまざまな角度からの描写に触れるたび、その景色を知っているような気さえしてくる。 このあり得ない既視感のなかに、なぜか居心地のよさが潜んでいる。 光の歴史だけではなく、闇があってもなお。 人間が自然とのあわいに生きてきた記憶は、案外、いろんな所に転がっているのかもしれない。 祖父母のちょっとした仕草や神社の大木の根元に生える雑草とか、または、いま踏みしめている土地の凹凸にも。 - 2025年10月29日
 生類の思想藤原辰史読み終わった生類から描きだされる世界に頷きつつも、この視点に立ったとき、実際にどう行動していけるかを、考えながら読み進めた。結局私には分からずじまいだったが、最後の章に朧げながらの道標があるように思えた。 たとえば「すでにその効力を失いつつある「人権宣言」をつくりなおすことはできないだろうか」とある。そして、作りなおすための始点は「お互いの微生物を食べ合うこと、リスクを顧みず意識的に微生物を共有しようとすることへの執念だけ」と言い切る。 フランス革命から200余年、理想に近づこうと人類は歩みを進めてきた。三歩進んで二歩下がりながらも、たえず次の一歩を踏み出してきた力は執念とも言えるだろう。 いま、ここで一度、立ち止まること。 人とは何かを改めて捉えなおし、その上で人としての在り方を世界に謳いあげること。 百年単位の未来へ。 大きな課題が突きつけられている。
生類の思想藤原辰史読み終わった生類から描きだされる世界に頷きつつも、この視点に立ったとき、実際にどう行動していけるかを、考えながら読み進めた。結局私には分からずじまいだったが、最後の章に朧げながらの道標があるように思えた。 たとえば「すでにその効力を失いつつある「人権宣言」をつくりなおすことはできないだろうか」とある。そして、作りなおすための始点は「お互いの微生物を食べ合うこと、リスクを顧みず意識的に微生物を共有しようとすることへの執念だけ」と言い切る。 フランス革命から200余年、理想に近づこうと人類は歩みを進めてきた。三歩進んで二歩下がりながらも、たえず次の一歩を踏み出してきた力は執念とも言えるだろう。 いま、ここで一度、立ち止まること。 人とは何かを改めて捉えなおし、その上で人としての在り方を世界に謳いあげること。 百年単位の未来へ。 大きな課題が突きつけられている。
読み込み中...