

くん
@kun
福岡在住の本好きです。読書会にもちょこちょこ参加。ミステリー、SF、純文、エッセイ、なんでも読みます。
- 2026年1月3日
 読み終わったリアル脱出ゲーム×ミステリーという斬新な組み合わせが気になり読んでみた。 リアル脱出ゲームを共通の趣味としている大学生コンビの2人。 専攻も性格も違い、少しデコボコしているけれど、側から見ているとお互いの苦手な部分を補い合っているように見える。 そんな2人がたまたま参加することになったリアル脱出ゲーム。 実際に出てくるパズルや図版が読んでいる読者にも体験しているような気分にさせる。 少しホラー要素も含みつつ、楽しい謎解きは一変して殺人事件となり、そこから犯人に翻弄されながらも推理が進んでいく。 ミスリードなどにひっかかって犯人が分からなかったけど、動機は早い段階で読み解けた。 トリックは解けば簡単なものだけど、リアル脱出ゲーム好きにはたまらないミステリーだと思う。 主人公2人の推理、シリーズものとしても読んでみたい。
読み終わったリアル脱出ゲーム×ミステリーという斬新な組み合わせが気になり読んでみた。 リアル脱出ゲームを共通の趣味としている大学生コンビの2人。 専攻も性格も違い、少しデコボコしているけれど、側から見ているとお互いの苦手な部分を補い合っているように見える。 そんな2人がたまたま参加することになったリアル脱出ゲーム。 実際に出てくるパズルや図版が読んでいる読者にも体験しているような気分にさせる。 少しホラー要素も含みつつ、楽しい謎解きは一変して殺人事件となり、そこから犯人に翻弄されながらも推理が進んでいく。 ミスリードなどにひっかかって犯人が分からなかったけど、動機は早い段階で読み解けた。 トリックは解けば簡単なものだけど、リアル脱出ゲーム好きにはたまらないミステリーだと思う。 主人公2人の推理、シリーズものとしても読んでみたい。 - 2025年12月7日
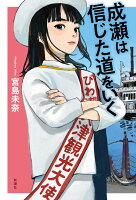 成瀬は信じた道をいく宮島未奈読み終わった成瀬シリーズ第二弾は高校生から大学生へと成長していく成瀬と成瀬のまわりの人たちとのお話。 成瀬は相変わらずだけど、大学生になるのかーと感慨深かった。 今回も連作短編で、登場人物はリングするけれど、五話それぞれ独立した話になっていて読みやすく、そしてどの作品も面白かった。 五話通して成瀬と島崎の関係の変化が一番メインで描かれていたけど、成瀬のお父さんが可愛らしい性格だった。 心配性だけどおっとり優しいお父さんと、泰然とした娘の対比がおもしろかった。 次はいよいよ最終巻。 楽しみにしていたけれど、名残惜しい。
成瀬は信じた道をいく宮島未奈読み終わった成瀬シリーズ第二弾は高校生から大学生へと成長していく成瀬と成瀬のまわりの人たちとのお話。 成瀬は相変わらずだけど、大学生になるのかーと感慨深かった。 今回も連作短編で、登場人物はリングするけれど、五話それぞれ独立した話になっていて読みやすく、そしてどの作品も面白かった。 五話通して成瀬と島崎の関係の変化が一番メインで描かれていたけど、成瀬のお父さんが可愛らしい性格だった。 心配性だけどおっとり優しいお父さんと、泰然とした娘の対比がおもしろかった。 次はいよいよ最終巻。 楽しみにしていたけれど、名残惜しい。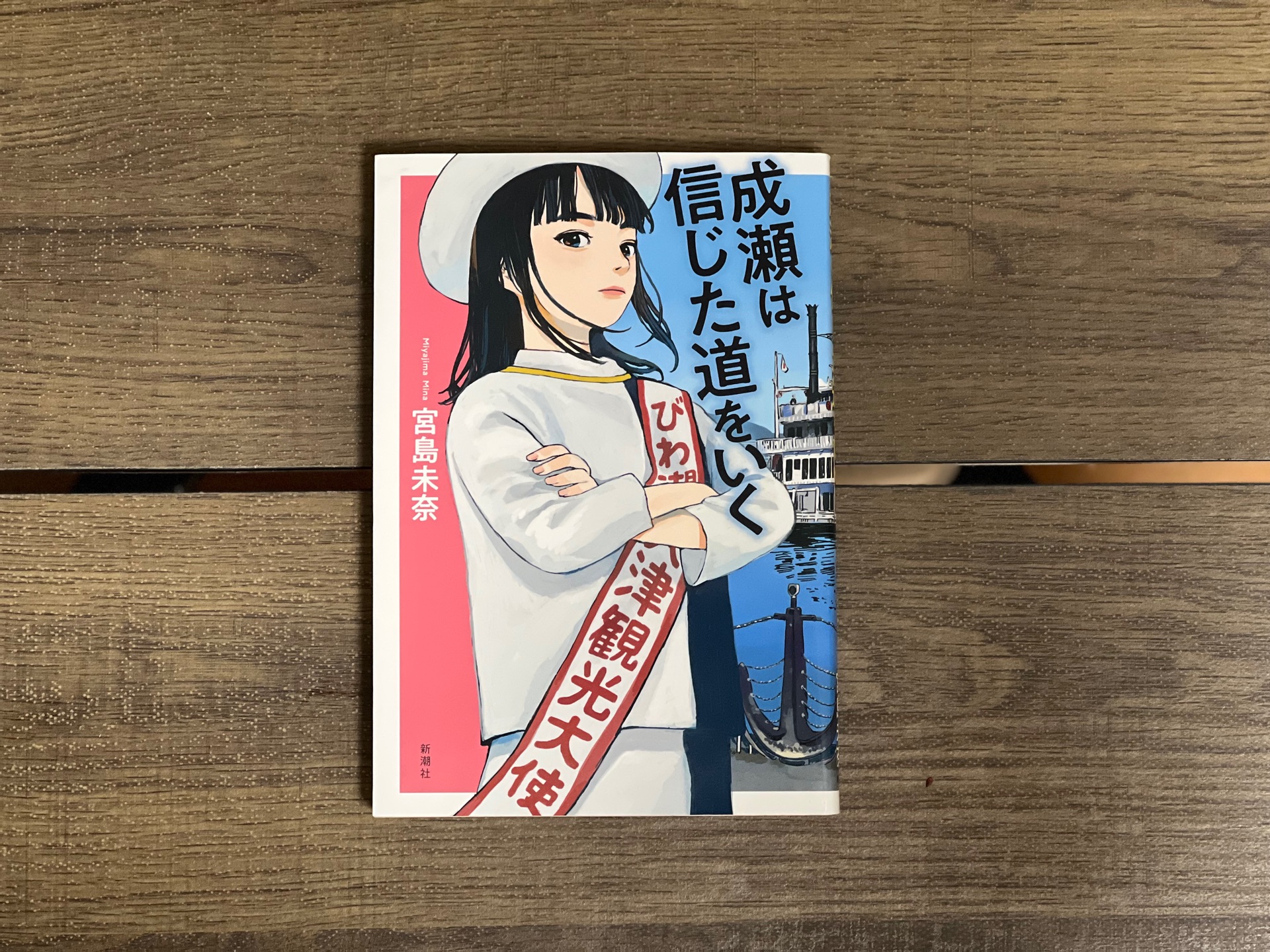
- 2025年11月9日
 謎の香りはパン屋から土屋うさぎ読み終わった第23回『このミステリーがすごい!』大賞受賞作ということ、パン屋さんが舞台というのでパン好きなら読まねば!と思っていたら文喫にあったので読み始めたら読み終わってしまった。 5種類のパンをテーマに5つの章に分かれたお話と謎だったので、テンポよくするすると読み進められた。 読んでるとパンが食べたくなる。 そして、最後に明かされる2つの真相。 伏線に気付かず…で、ちょっと悔しい。 ヒントは散りばめられていたのに。 美味しくて、あったかい気持ちになるお話ばかりで、最後のカレーパンのお話は少しグッときてしまった。 本を閉じて、パンを早速買って帰りたい。
謎の香りはパン屋から土屋うさぎ読み終わった第23回『このミステリーがすごい!』大賞受賞作ということ、パン屋さんが舞台というのでパン好きなら読まねば!と思っていたら文喫にあったので読み始めたら読み終わってしまった。 5種類のパンをテーマに5つの章に分かれたお話と謎だったので、テンポよくするすると読み進められた。 読んでるとパンが食べたくなる。 そして、最後に明かされる2つの真相。 伏線に気付かず…で、ちょっと悔しい。 ヒントは散りばめられていたのに。 美味しくて、あったかい気持ちになるお話ばかりで、最後のカレーパンのお話は少しグッときてしまった。 本を閉じて、パンを早速買って帰りたい。 - 2025年10月20日
 ヤクザときどきピアノ 増補版鈴木智彦読み終わった「ずっとピアノが弾きたかった。」 そんなまえがきの一文からスタートした、ヤクザライターの鈴木智彦さんが52歳にして通い始めたピアノ初心者によるピアノ教室レッスンのドキュメンタリー。 ヤクザライターというだけに、独特の言い回しが多く、本を開いて30分後、笑いが止まらず本を閉じた。 外で読むのが危険すぎて、自宅にて一気読みした。 遅筆である鈴木さんが5年も取材に費やした「サカナとヤクザ」が校了し、ライターズ・ハイの状態でABBAの「ダンシング・クイーン」を聞いて涙を流し、猛烈に感情を揺さぶられ、 「ピアノでこの曲を弾きたい」 という思いからスタートしたピアノ教室探しでも、ヤクザライターの変なクセが出たり、随所で笑ってしまった。 そんな中で出会った『レイコ先生』がとても素敵な方だった。 「練習すれば、弾けない曲などありません」 というレイコ先生の一太刀で、鈴木さんの「ダンシング・クイーン」を弾くための日々が始まる。 レイコ先生が伝える音楽の楽しさ、弾きたいという気持ちを大切にしたレッスンは、読んでいて清々しかった。 どこまでも表現がヤクザ寄りで、歴代の音楽家を極道の系譜で語って説明されて、ますます理解できずに笑ったり、随所に世間とのズレを見せるところが、この本の魅力かもしれない。 自分の持てる語彙を懸命に使い、ピアノの楽しさ、音楽の素晴らしさ、大人になって音楽を始めるという体験を語ろうとするその姿が随所に散りばめられ、読んでいるだけで音楽の素晴らしさ、楽しさ、そして鈴木さんの音楽に向き合う真摯な姿が伝わってきた。 最終目標である発表会の結末は…ぜひ読んでみて欲しい。 発表会は2019年12月に開催され、YouTubeにも上がっている。 文庫は増補版ということで、発表会後、コロナ禍を経て鈴木さんはピアノを続けているのか、そこまでも追加されている。
ヤクザときどきピアノ 増補版鈴木智彦読み終わった「ずっとピアノが弾きたかった。」 そんなまえがきの一文からスタートした、ヤクザライターの鈴木智彦さんが52歳にして通い始めたピアノ初心者によるピアノ教室レッスンのドキュメンタリー。 ヤクザライターというだけに、独特の言い回しが多く、本を開いて30分後、笑いが止まらず本を閉じた。 外で読むのが危険すぎて、自宅にて一気読みした。 遅筆である鈴木さんが5年も取材に費やした「サカナとヤクザ」が校了し、ライターズ・ハイの状態でABBAの「ダンシング・クイーン」を聞いて涙を流し、猛烈に感情を揺さぶられ、 「ピアノでこの曲を弾きたい」 という思いからスタートしたピアノ教室探しでも、ヤクザライターの変なクセが出たり、随所で笑ってしまった。 そんな中で出会った『レイコ先生』がとても素敵な方だった。 「練習すれば、弾けない曲などありません」 というレイコ先生の一太刀で、鈴木さんの「ダンシング・クイーン」を弾くための日々が始まる。 レイコ先生が伝える音楽の楽しさ、弾きたいという気持ちを大切にしたレッスンは、読んでいて清々しかった。 どこまでも表現がヤクザ寄りで、歴代の音楽家を極道の系譜で語って説明されて、ますます理解できずに笑ったり、随所に世間とのズレを見せるところが、この本の魅力かもしれない。 自分の持てる語彙を懸命に使い、ピアノの楽しさ、音楽の素晴らしさ、大人になって音楽を始めるという体験を語ろうとするその姿が随所に散りばめられ、読んでいるだけで音楽の素晴らしさ、楽しさ、そして鈴木さんの音楽に向き合う真摯な姿が伝わってきた。 最終目標である発表会の結末は…ぜひ読んでみて欲しい。 発表会は2019年12月に開催され、YouTubeにも上がっている。 文庫は増補版ということで、発表会後、コロナ禍を経て鈴木さんはピアノを続けているのか、そこまでも追加されている。 - 2025年10月15日
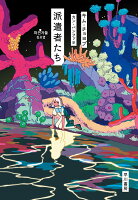 派遣者たちカン・バンファ,キム・チョヨプ読み終わった住処を奪われた人類と氾濫体との戦いを巡るディストピアかと思い読み始めると、冒頭から三分の一くらいまでは地下都市ラブバワでのテリンの日々を淡々と描いていたのに、中盤から突然、個について、意識や自我の存在について問いかけ始める。 「自我とは?」 「個体とは?」 「死とは?」 「われわれとは?」 「わたしたちとは?」 「きみが本当にひとつの存在なのか」 人間と外側との境界線が崩れることで、人間と非人間との共生の難しさ、変化と困難がテーマとして浮き彫りになってくる。 本来の自分を全く失うことなく、異質な他者との共存は難しい。自身の存在や生存を脅かす危険性がある他者を、主人公のテリンは苦悩の果てに信じ、受け入れ、変化する。 テリンとイゼフが望む2人共通の夢と未来は、そこに憎しみも加えられて到達した結末はとても美しかった。 コロナを経たからこそ描くことができた、他者との共生と個の存在について描いた作品でした。 また何年かしたら再読してその時の自分がどう感じるのかを味わってみたい。
派遣者たちカン・バンファ,キム・チョヨプ読み終わった住処を奪われた人類と氾濫体との戦いを巡るディストピアかと思い読み始めると、冒頭から三分の一くらいまでは地下都市ラブバワでのテリンの日々を淡々と描いていたのに、中盤から突然、個について、意識や自我の存在について問いかけ始める。 「自我とは?」 「個体とは?」 「死とは?」 「われわれとは?」 「わたしたちとは?」 「きみが本当にひとつの存在なのか」 人間と外側との境界線が崩れることで、人間と非人間との共生の難しさ、変化と困難がテーマとして浮き彫りになってくる。 本来の自分を全く失うことなく、異質な他者との共存は難しい。自身の存在や生存を脅かす危険性がある他者を、主人公のテリンは苦悩の果てに信じ、受け入れ、変化する。 テリンとイゼフが望む2人共通の夢と未来は、そこに憎しみも加えられて到達した結末はとても美しかった。 コロナを経たからこそ描くことができた、他者との共生と個の存在について描いた作品でした。 また何年かしたら再読してその時の自分がどう感じるのかを味わってみたい。 - 2025年10月5日
 立ち読みの歴史小林昌樹読み終わった三宅香帆さんがPage Turnersで紹介していて気になって図書館で借りてみたら面白かった! メモを取りたいところが多すぎて、メモばかりとっていたらなかなか読み進められずやっと読み終わった。 立ち読みの歴史を語る時、リテラシーとしての識字率が前提になる。 読み書きができなければそもそも本を読めない。 都市部で読み書きできる人が増えて来て、ようやく立ち読みの歴史を紐解く調査がスタート。 立ち読みするためには開架式になったタイミング(江戸時代は閉架式で座売りだった)、開架式になるには平置きからタテ置きするために和本(和装本)から洋本(洋装本)となり、さらに背表紙がつかなければならい…など、江戸から明治、大正にかけてどのタイミングで立ち読みがスタートするのか、近代読書史・書籍流通史、出版社や書店の社史まで使って紐解くところがすごかった。 江戸時代の本の種類や、そもそも雑誌は本屋で売られていなかったという歴史など、現代には残っておらず、本の流通の大きな変化は知らないことばかりだった。 大火や震災、戦争によって消えてしまった様々な歴史や事実を作者が様々な文献や資料、図版から掘り起こしていくのに大変苦労していたところも本文中に正直に書かれていた。 調査の過程は国立国会図書館で15年にわたるレファレンス業務の経験が活かされていた。 巻末の図版出典や、もっと読書史を読みたい読者への推薦図書リストなどを見るとよく分かる。 読書史の推薦図書もかなり読んでみたい本ばかりでした。 丹念な調査から掘り起こした立ち読みの歴史、そして立ち読みがどう変化していこうとしているのか、ぜひ読んでみてほしい。
立ち読みの歴史小林昌樹読み終わった三宅香帆さんがPage Turnersで紹介していて気になって図書館で借りてみたら面白かった! メモを取りたいところが多すぎて、メモばかりとっていたらなかなか読み進められずやっと読み終わった。 立ち読みの歴史を語る時、リテラシーとしての識字率が前提になる。 読み書きができなければそもそも本を読めない。 都市部で読み書きできる人が増えて来て、ようやく立ち読みの歴史を紐解く調査がスタート。 立ち読みするためには開架式になったタイミング(江戸時代は閉架式で座売りだった)、開架式になるには平置きからタテ置きするために和本(和装本)から洋本(洋装本)となり、さらに背表紙がつかなければならい…など、江戸から明治、大正にかけてどのタイミングで立ち読みがスタートするのか、近代読書史・書籍流通史、出版社や書店の社史まで使って紐解くところがすごかった。 江戸時代の本の種類や、そもそも雑誌は本屋で売られていなかったという歴史など、現代には残っておらず、本の流通の大きな変化は知らないことばかりだった。 大火や震災、戦争によって消えてしまった様々な歴史や事実を作者が様々な文献や資料、図版から掘り起こしていくのに大変苦労していたところも本文中に正直に書かれていた。 調査の過程は国立国会図書館で15年にわたるレファレンス業務の経験が活かされていた。 巻末の図版出典や、もっと読書史を読みたい読者への推薦図書リストなどを見るとよく分かる。 読書史の推薦図書もかなり読んでみたい本ばかりでした。 丹念な調査から掘り起こした立ち読みの歴史、そして立ち読みがどう変化していこうとしているのか、ぜひ読んでみてほしい。 - 2025年9月30日
 GOAT meets(01)イ・ラン,乗代雄介,小田雅久仁,朝吹真理子,金原ひとみ読み終わった買った「GOAT」の姉妹誌として7月に誕生した「GOAT meets」。 読者が作家たちと出会い、また作家自身が新たなテーマと出会う場、というコンセプトの文芸誌。 小説、エッセイ、ノンフィクション、詩、短歌、イラスト、写真、現代アートと幅広く取り扱われていて、文芸誌の本としての分厚さよりも中身の濃さに圧倒されて少しずつ読んだ。 国境、言語、性別、障害、戦争、時、世界、病…。 様々な違いや分断を越えて、行きたい場所へ行く、会いたい人に会いに行く、やりたいことを達成する。 表紙裏に書かれた、 「ともに新たな世界と出会いにいきましょう。新たな人を見にいきましょう。」 その自戒の念もこもったメッセージをテーマに創作されたたくさんの作品はどれも新鮮で衝撃的だった。 韓国の作家や作品、韓国と日本の関係性と未来についての作品も多く、韓国作家の作品が気になり始めているタイミングだったので読むことでかなり読みたい作品が増えてしまった。 GOATは読書バリアフリーにも取り組んでいて、紙の本と同時に電子書籍を同時配信し、さらに視覚障害・肢体不自由などの理由で必要としてる方へテキストデータの提供も行なっていたり、日本点字図書館の協力でテキストDAISY版の提供も行なっている。 テキストデータの提供、DAISY版への提供の難しさについては、滝口悠生さんの「テキストデータについて試行と提案」に詳しく書かれていた。印刷に関わっている身としては印刷後の国立国会図書館以外への提供については知らないことばかりだったので勉強になった。 出版社や著者への提言は、制度や仕組みをすぎに変えられない現実問題と、今読みたい必要としている読者に向けて、今すぐに取り組めることとして良いなと思った。 ポッドキャストと連動した対談「そろそろ本屋大賞についてマジメに語ろうか」は誌面で読む前にポッドキャストで聞いていたので楽しみながらしっかり読むことができた。 本屋大賞も創設されて20年を越え、創設当初の目的や、芥川賞・直木賞との関係性は気になっていたところで面白い対談だった。 今後、オーディオブック化も進めていくとのことなので、耳でも目でも楽しめる作りは、これからの読書バリアフリーへの推進へと繋がっていくのかな。その道のりを期待したい。
GOAT meets(01)イ・ラン,乗代雄介,小田雅久仁,朝吹真理子,金原ひとみ読み終わった買った「GOAT」の姉妹誌として7月に誕生した「GOAT meets」。 読者が作家たちと出会い、また作家自身が新たなテーマと出会う場、というコンセプトの文芸誌。 小説、エッセイ、ノンフィクション、詩、短歌、イラスト、写真、現代アートと幅広く取り扱われていて、文芸誌の本としての分厚さよりも中身の濃さに圧倒されて少しずつ読んだ。 国境、言語、性別、障害、戦争、時、世界、病…。 様々な違いや分断を越えて、行きたい場所へ行く、会いたい人に会いに行く、やりたいことを達成する。 表紙裏に書かれた、 「ともに新たな世界と出会いにいきましょう。新たな人を見にいきましょう。」 その自戒の念もこもったメッセージをテーマに創作されたたくさんの作品はどれも新鮮で衝撃的だった。 韓国の作家や作品、韓国と日本の関係性と未来についての作品も多く、韓国作家の作品が気になり始めているタイミングだったので読むことでかなり読みたい作品が増えてしまった。 GOATは読書バリアフリーにも取り組んでいて、紙の本と同時に電子書籍を同時配信し、さらに視覚障害・肢体不自由などの理由で必要としてる方へテキストデータの提供も行なっていたり、日本点字図書館の協力でテキストDAISY版の提供も行なっている。 テキストデータの提供、DAISY版への提供の難しさについては、滝口悠生さんの「テキストデータについて試行と提案」に詳しく書かれていた。印刷に関わっている身としては印刷後の国立国会図書館以外への提供については知らないことばかりだったので勉強になった。 出版社や著者への提言は、制度や仕組みをすぎに変えられない現実問題と、今読みたい必要としている読者に向けて、今すぐに取り組めることとして良いなと思った。 ポッドキャストと連動した対談「そろそろ本屋大賞についてマジメに語ろうか」は誌面で読む前にポッドキャストで聞いていたので楽しみながらしっかり読むことができた。 本屋大賞も創設されて20年を越え、創設当初の目的や、芥川賞・直木賞との関係性は気になっていたところで面白い対談だった。 今後、オーディオブック化も進めていくとのことなので、耳でも目でも楽しめる作りは、これからの読書バリアフリーへの推進へと繋がっていくのかな。その道のりを期待したい。 - 2025年9月22日
 ジェリーフィッシュは凍らない市川憂人読み終わったパラレルワールドの1980年代を舞台に、現実とは異なる発展を遂げた科学技術で誕生した小型飛行船「ジェリーフィッシュ」を惨劇の現場としたクローズド・サークル。犯人の独白、当時のジェリーフィッシュ内の物語、捜査する警察側の視点、3つの視点から描かれた、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」への挑戦作。 最初の殺人が起こった後のジェリーフィッシュ内の会話から、何となく犯人は分かったけれど、果たして全員死んだのか、それとも犯人だけ生き残ったのか分からず、さらにトリックも分からなかった。 中盤でなんとなくトリックが明示され、エピローグ直前で犯人は確定するけれど、犯人の動機が分からなかった。 エピローグで明かされた真実と動機。 犯人が最後にどうなったのか。 気になる終わり方だった。 読み終えて、もう一度最初から読み返し、作者に騙されていた事が悔しかった。 続編の「ブルーローズは眠らない」も早く読んでみたい。
ジェリーフィッシュは凍らない市川憂人読み終わったパラレルワールドの1980年代を舞台に、現実とは異なる発展を遂げた科学技術で誕生した小型飛行船「ジェリーフィッシュ」を惨劇の現場としたクローズド・サークル。犯人の独白、当時のジェリーフィッシュ内の物語、捜査する警察側の視点、3つの視点から描かれた、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」への挑戦作。 最初の殺人が起こった後のジェリーフィッシュ内の会話から、何となく犯人は分かったけれど、果たして全員死んだのか、それとも犯人だけ生き残ったのか分からず、さらにトリックも分からなかった。 中盤でなんとなくトリックが明示され、エピローグ直前で犯人は確定するけれど、犯人の動機が分からなかった。 エピローグで明かされた真実と動機。 犯人が最後にどうなったのか。 気になる終わり方だった。 読み終えて、もう一度最初から読み返し、作者に騙されていた事が悔しかった。 続編の「ブルーローズは眠らない」も早く読んでみたい。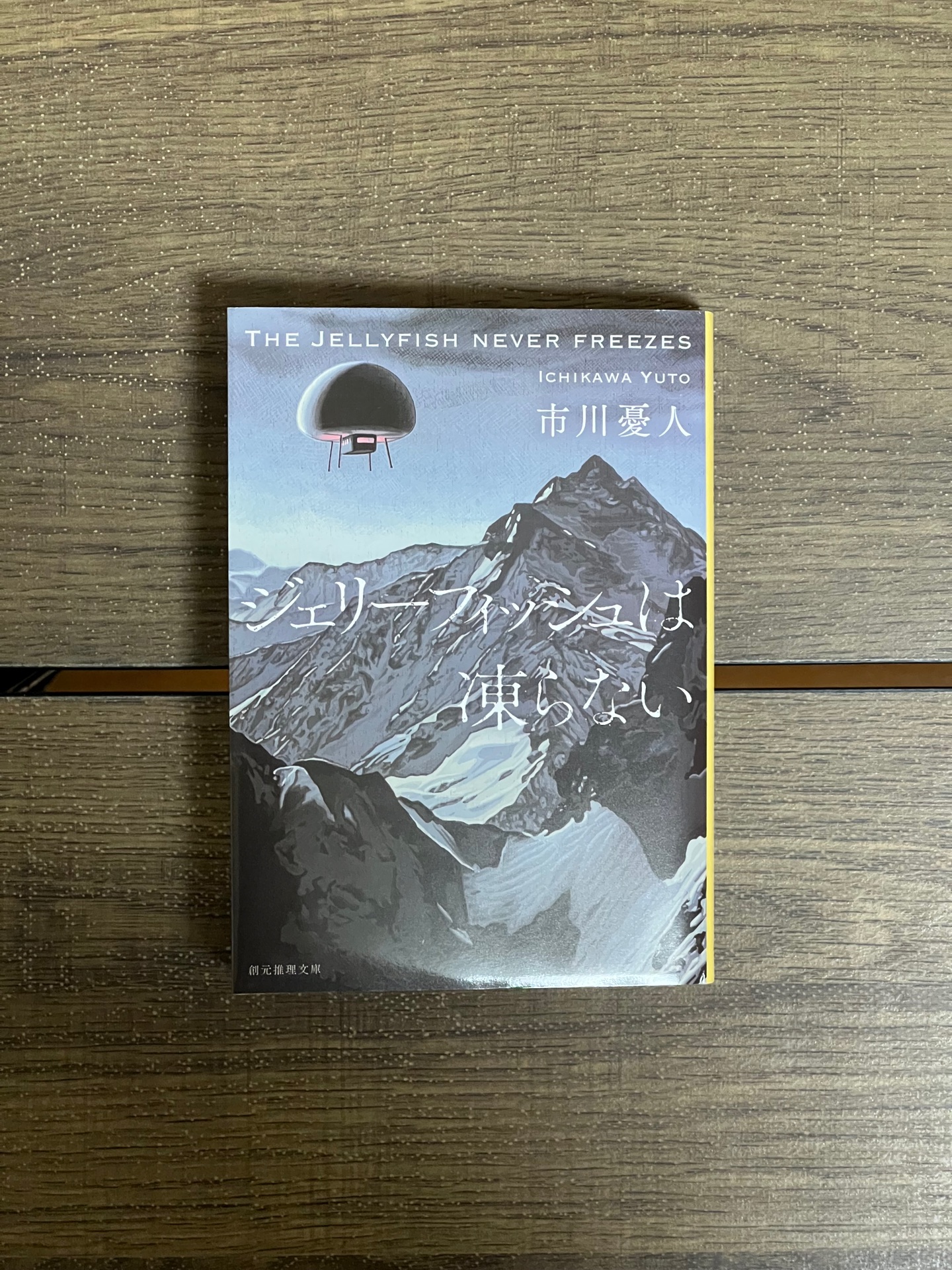
- 2025年9月20日
 読み終わった小学生以来かも?というくらい久しぶりに読んだ「なんて素敵にジャパネスク」。 氷室冴子さんの作品がオレンジ文庫で復刊始まって懐かしくなり、初めて読んだ氷室冴子作品というのとで、図書館で借りた。 新装版だけど発行年は1999年。 コバルト文庫なので中高生向けのライトノベルで、舞台は平安時代。 だけどそこは現代的に一部置き換えて、話し言葉も現代なので昔読んだ時も読みやすかった。 当時としてはあり得ない設定だけど、お転婆で行動的な瑠璃姫と、幼なじみ高彬をメインとした恋愛と結婚と陰謀のお話。 結婚しようとするタイミングで事件が起き、なかなか結婚できない二人の、ドタバタストーリー。 元気な瑠璃姫に久々に再会して、懐かしかった。 新装版あとがきで氷室さん自身も、 「シリーズ物を書いていると、主人公がいつも同じ失敗をしているのはバカみたいに思えてくるし、人間としても成長して欲しい『欲』みたいなものが出てしてしまいます。」 と語っていて、大人になってしまって続きを書かなくなってしまった…という事が書かれていて、少しずつコバルト文庫から卒業していった気持ちにも似ていた。 十数年ぶりにゲラを読み直し、原稿を書いていたときの感覚を思い出し、 「再会できて、ほんとうに嬉しい。物語というのはありがたい、会おうとすれば、いつでも再会できるから、と当たり前のことにも気づきました。」 そんな思いを語っていて、昔読んだ本を読み返すのも良いなーと改めて感じた。 新装版のあとがき、読めて良かった。 コバルト文庫から2018年に復刻版が出ているけれど、図書館にあったので借りてみたけれど、かなり年季が入っているし、水濡れで傷んでいるため本を開くたびにハウスダストアレルギーの身としてはツラかった…。
読み終わった小学生以来かも?というくらい久しぶりに読んだ「なんて素敵にジャパネスク」。 氷室冴子さんの作品がオレンジ文庫で復刊始まって懐かしくなり、初めて読んだ氷室冴子作品というのとで、図書館で借りた。 新装版だけど発行年は1999年。 コバルト文庫なので中高生向けのライトノベルで、舞台は平安時代。 だけどそこは現代的に一部置き換えて、話し言葉も現代なので昔読んだ時も読みやすかった。 当時としてはあり得ない設定だけど、お転婆で行動的な瑠璃姫と、幼なじみ高彬をメインとした恋愛と結婚と陰謀のお話。 結婚しようとするタイミングで事件が起き、なかなか結婚できない二人の、ドタバタストーリー。 元気な瑠璃姫に久々に再会して、懐かしかった。 新装版あとがきで氷室さん自身も、 「シリーズ物を書いていると、主人公がいつも同じ失敗をしているのはバカみたいに思えてくるし、人間としても成長して欲しい『欲』みたいなものが出てしてしまいます。」 と語っていて、大人になってしまって続きを書かなくなってしまった…という事が書かれていて、少しずつコバルト文庫から卒業していった気持ちにも似ていた。 十数年ぶりにゲラを読み直し、原稿を書いていたときの感覚を思い出し、 「再会できて、ほんとうに嬉しい。物語というのはありがたい、会おうとすれば、いつでも再会できるから、と当たり前のことにも気づきました。」 そんな思いを語っていて、昔読んだ本を読み返すのも良いなーと改めて感じた。 新装版のあとがき、読めて良かった。 コバルト文庫から2018年に復刻版が出ているけれど、図書館にあったので借りてみたけれど、かなり年季が入っているし、水濡れで傷んでいるため本を開くたびにハウスダストアレルギーの身としてはツラかった…。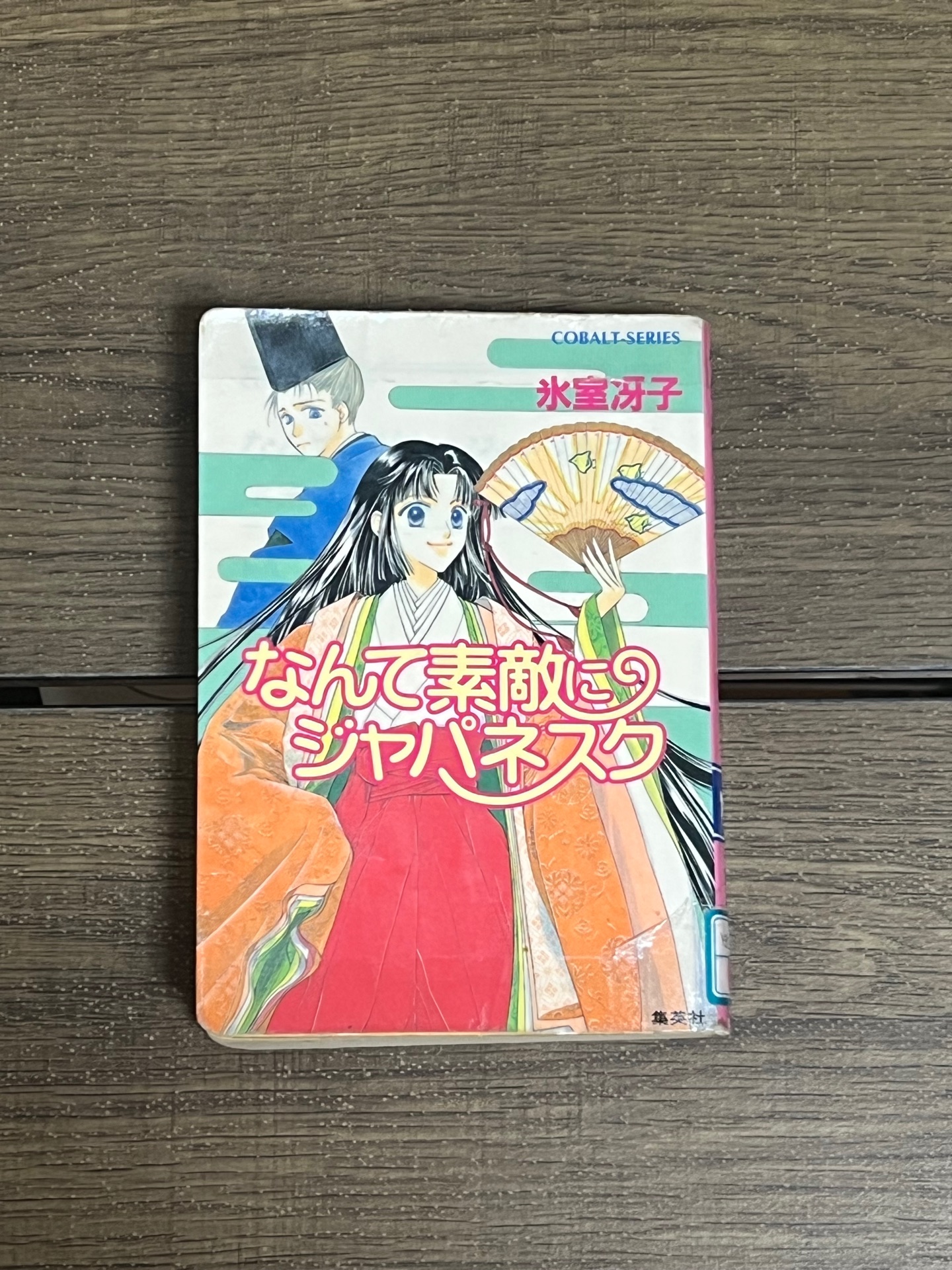
- 2025年9月15日
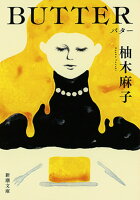 BUTTER柚木麻子読み終わった買った実際にあった事件を翻案にした作品。 出版から時間が経っていたけれど、海外で様々な賞を取り、話題が再燃していたので読んでみた。 読んでみたら面白くて、読み終わるのがもったいなくてなかなか読み終えることができなかった。 フェミニストとマーガリンを嫌悪するカジマナこと梶井真奈子に翻弄される週刊誌記者の町田里佳。 次第にカジマナを友達のように感じ始める里佳と、見た目も中身も変化する彼女に周囲の人間も翻弄され、巻き込まれていく。 作品内では、登場する人物たちの外見が細かく表現される。 梶井に翻弄され変化していく過程すらも細かく正確に表現される。 それは、すべての中心にいる梶井真奈子の外見も。巨峰のようだと度々表現される目、しみのないもちもちと内側から輝く白い肌、ぷっくりとした濃いピンクのおちょぼ口、つやつやと光る髪。 「ちびくろ・さんぼ」の虎のように、梶井を中心に、事件に関わる人々はぐるぐると回転するように翻弄されていく。虎がバターになってしまうように、彼らの結末がどうなっていくのか最後まで気になって目が離せなかった。 里佳と里佳に関わる人たちの結末は、梶井が求めても手に入れられないものだったのかな、と感じた。 変化していく外見と、それに対して変化していく人々の態度なども、この作品を通して描かれているテーマでもあったのかもしれない。 もう一つの大きなテーマが食べ物。 バターを食べる時、落ちる感じがするという梶井真奈子。 「そう。ふわりと、舞い上がるのではなく、落ちる。エレベーターですっと一階下に落ちる感じ。舌先から身体が深く沈んでいくの」 バターたっぷりのこってりとした食べ物が梶井から紹介されていく。 梶井から教えられた食べ物を食べる里佳の美味しく味わう描写に、食欲が刺激されてしまった。 バター醤油ご飯、たらこパスタ、ウエストのバタークリームのクリスマスケーキ、ガーリックバターライス、塩バターラーメン…。 バター醤油ご飯と塩バターラーメンは我慢できずに食べてしまった。
BUTTER柚木麻子読み終わった買った実際にあった事件を翻案にした作品。 出版から時間が経っていたけれど、海外で様々な賞を取り、話題が再燃していたので読んでみた。 読んでみたら面白くて、読み終わるのがもったいなくてなかなか読み終えることができなかった。 フェミニストとマーガリンを嫌悪するカジマナこと梶井真奈子に翻弄される週刊誌記者の町田里佳。 次第にカジマナを友達のように感じ始める里佳と、見た目も中身も変化する彼女に周囲の人間も翻弄され、巻き込まれていく。 作品内では、登場する人物たちの外見が細かく表現される。 梶井に翻弄され変化していく過程すらも細かく正確に表現される。 それは、すべての中心にいる梶井真奈子の外見も。巨峰のようだと度々表現される目、しみのないもちもちと内側から輝く白い肌、ぷっくりとした濃いピンクのおちょぼ口、つやつやと光る髪。 「ちびくろ・さんぼ」の虎のように、梶井を中心に、事件に関わる人々はぐるぐると回転するように翻弄されていく。虎がバターになってしまうように、彼らの結末がどうなっていくのか最後まで気になって目が離せなかった。 里佳と里佳に関わる人たちの結末は、梶井が求めても手に入れられないものだったのかな、と感じた。 変化していく外見と、それに対して変化していく人々の態度なども、この作品を通して描かれているテーマでもあったのかもしれない。 もう一つの大きなテーマが食べ物。 バターを食べる時、落ちる感じがするという梶井真奈子。 「そう。ふわりと、舞い上がるのではなく、落ちる。エレベーターですっと一階下に落ちる感じ。舌先から身体が深く沈んでいくの」 バターたっぷりのこってりとした食べ物が梶井から紹介されていく。 梶井から教えられた食べ物を食べる里佳の美味しく味わう描写に、食欲が刺激されてしまった。 バター醤油ご飯、たらこパスタ、ウエストのバタークリームのクリスマスケーキ、ガーリックバターライス、塩バターラーメン…。 バター醤油ご飯と塩バターラーメンは我慢できずに食べてしまった。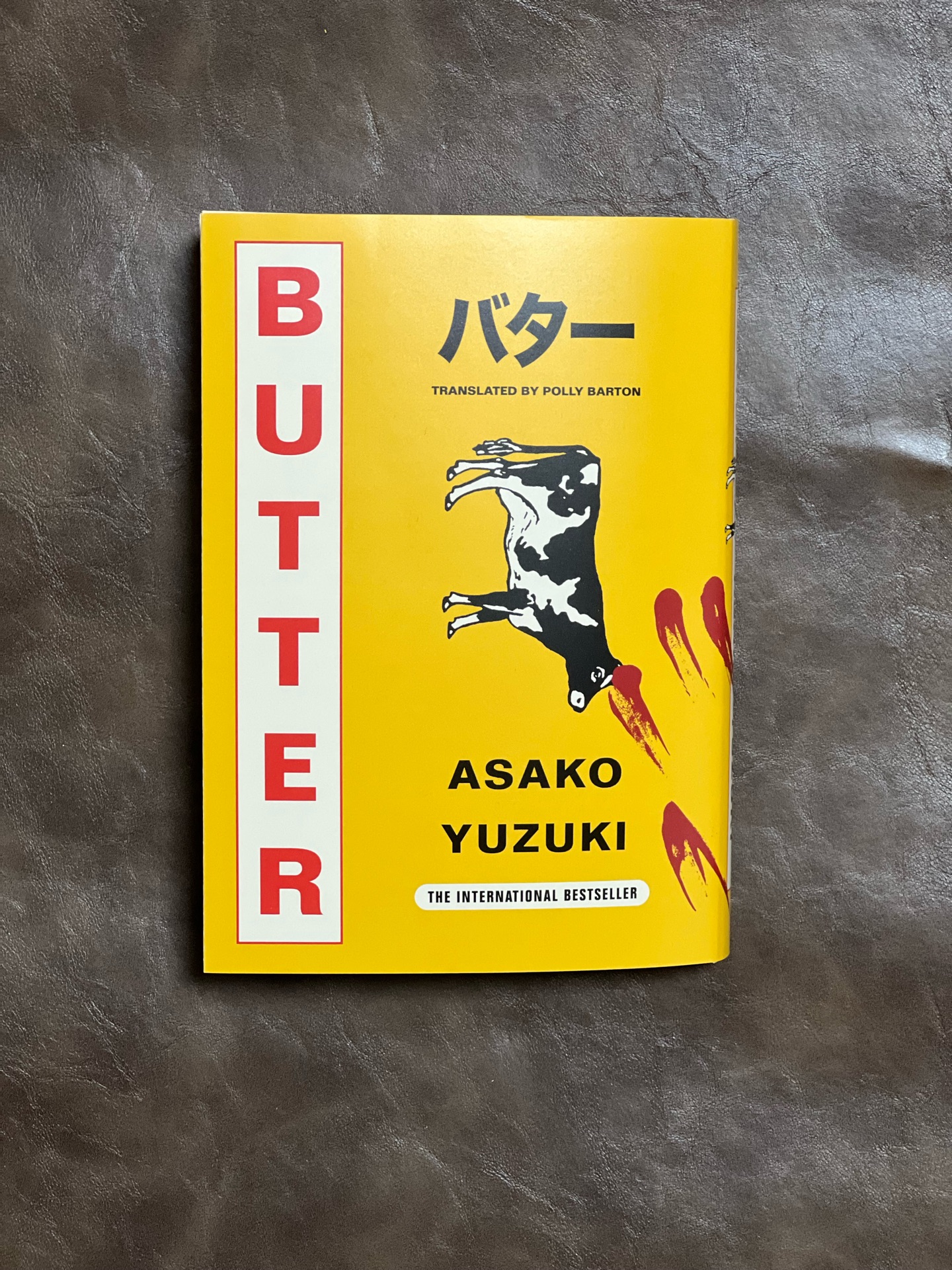
- 2025年9月4日
 スワイプ厳禁 変死した大学生のスマホ知念実希人読み終わった左ページに文章、右ページにスマホ画面、見開きで展開されるモキュメンタリー・ホラー。 あっという間に読み終わったけど、ドンデン返しに一瞬着いていけなくて再読してしまった。 最後のドンデン返しの所まで、しっかり騙されてしまっていた。 ドンデン返し好きにはオススメです。 変わった判型で、中も凝った作りをしてるのに税込499円という頑張りを賞賛したい。 9月18日に発売される続編必ず読まねば。
スワイプ厳禁 変死した大学生のスマホ知念実希人読み終わった左ページに文章、右ページにスマホ画面、見開きで展開されるモキュメンタリー・ホラー。 あっという間に読み終わったけど、ドンデン返しに一瞬着いていけなくて再読してしまった。 最後のドンデン返しの所まで、しっかり騙されてしまっていた。 ドンデン返し好きにはオススメです。 変わった判型で、中も凝った作りをしてるのに税込499円という頑張りを賞賛したい。 9月18日に発売される続編必ず読まねば。 - 2025年9月3日
 方舟夕木春央読み終わった地下に閉じ込められ、全員死ぬかもしれない危機的状況の中、なぜ殺人は起こったのか。 犯人は誰なのか。 疑心暗鬼になり精神を消耗する人、理不尽な状況に感情を爆発させる人…。 閉じ込められ、追い詰められた人たちの心理描写と、タイムリミットが迫る中犯人を追い詰めていく謎解きに目が離せず、ページを捲る手を止められなかった。 全ての謎が解き明かされた時、真実がひっくり返される。 これは、何度も読み返して伏線を振り返りたくなる作品でした。 ちょっと気持ちが落ち着くまで夕木さんの次の「十戒」は読めなさそうです。
方舟夕木春央読み終わった地下に閉じ込められ、全員死ぬかもしれない危機的状況の中、なぜ殺人は起こったのか。 犯人は誰なのか。 疑心暗鬼になり精神を消耗する人、理不尽な状況に感情を爆発させる人…。 閉じ込められ、追い詰められた人たちの心理描写と、タイムリミットが迫る中犯人を追い詰めていく謎解きに目が離せず、ページを捲る手を止められなかった。 全ての謎が解き明かされた時、真実がひっくり返される。 これは、何度も読み返して伏線を振り返りたくなる作品でした。 ちょっと気持ちが落ち着くまで夕木さんの次の「十戒」は読めなさそうです。 - 2025年9月1日
 白魔の檻山口未桜読み終わった今回も展開と真相が気になって一気読みしてしまった。 「禁忌の子」の続編「白魔の檻」の主人公は、前作の冒頭に一瞬だけ登場した研修医の春田。 前作のテーマが生殖医療、今作は過疎地医療の現実。 へき地での医療は、現場で戦う医師や看護師などの医療従事者たちのやり甲斐だけでギリギリ成り立っているが、すでに限界を迎えている。 その限界からの悲劇と、東日本大震災、阪神淡路大震災が事件と複雑に絡み合い、事件の真相が解かれた時、哀しいやるせ無さと、それでも医療従事者は目の前に患者がいれば体が勝手に動いてしまうという現実が重かった。 前作は少し遠い世界の話に感じられた部分があったけど、今作はすぐ近くにある残酷な現実だった。 迫り来る硫化水素によって、へき地の病院は自然の密室となり、閉じ込められた病院内で起こる密室殺人のトリックは、目に見えるヒントから真相を解くことはできなくても、別の視点から見る事で簡単に突破できるトリックだった。 登場人物たちはそれぞれ誰にも言えない、誰にも理解でき無い苦しみや葛藤があり、どれも重かった。 城崎先生の「生きていてほしかったんだ」という言葉にも、彼の優しさと苦しみがこめられているようだった。
白魔の檻山口未桜読み終わった今回も展開と真相が気になって一気読みしてしまった。 「禁忌の子」の続編「白魔の檻」の主人公は、前作の冒頭に一瞬だけ登場した研修医の春田。 前作のテーマが生殖医療、今作は過疎地医療の現実。 へき地での医療は、現場で戦う医師や看護師などの医療従事者たちのやり甲斐だけでギリギリ成り立っているが、すでに限界を迎えている。 その限界からの悲劇と、東日本大震災、阪神淡路大震災が事件と複雑に絡み合い、事件の真相が解かれた時、哀しいやるせ無さと、それでも医療従事者は目の前に患者がいれば体が勝手に動いてしまうという現実が重かった。 前作は少し遠い世界の話に感じられた部分があったけど、今作はすぐ近くにある残酷な現実だった。 迫り来る硫化水素によって、へき地の病院は自然の密室となり、閉じ込められた病院内で起こる密室殺人のトリックは、目に見えるヒントから真相を解くことはできなくても、別の視点から見る事で簡単に突破できるトリックだった。 登場人物たちはそれぞれ誰にも言えない、誰にも理解でき無い苦しみや葛藤があり、どれも重かった。 城崎先生の「生きていてほしかったんだ」という言葉にも、彼の優しさと苦しみがこめられているようだった。 - 2025年8月31日
 禁忌の子山口未桜読み終わった救急医の武田の元に搬送された彼に瓜二つの溺死体。 顔、骨格、身体的な特徴、全てがあまりに同じ。 疑問と不安を抱いた武田は同僚の城崎の助けを借り、正体不明の溺死体の調査を始める。 作者が現役医師で、投稿作で、デビュー作。 それだけでも発売当時かなり話題になり、書店から一気に消えたと盛り上がっていたタイミングでたまたま立ち寄った紀伊国屋書店で見つけたので買って積んだままにしていた。 続編の「白魔の檻」が8月29日発売。 しかも予約しちゃってるので続編読むために読まねばとようやく開いたらページを捲る手を止められず、一気に読み終わった。 なぜ2人は瓜二つなのか。 もしかして2人は生き別れた双子? 武田に瓜二つの溺死体の正体は? なぜ死んだのか? 初っ端から謎が怒涛のように押し寄せて、手がかりもなくお手上げだったけど、話が進むうちにさらに謎は深まり、第二の事件も…。 最後まで読んだ時、ようやくタイトルの意味を理解してスッキリした。 伏線全部回収したけど、密室のトリックだけが物足りなかったところ。 続編の「白魔の檻」に期待したい。
禁忌の子山口未桜読み終わった救急医の武田の元に搬送された彼に瓜二つの溺死体。 顔、骨格、身体的な特徴、全てがあまりに同じ。 疑問と不安を抱いた武田は同僚の城崎の助けを借り、正体不明の溺死体の調査を始める。 作者が現役医師で、投稿作で、デビュー作。 それだけでも発売当時かなり話題になり、書店から一気に消えたと盛り上がっていたタイミングでたまたま立ち寄った紀伊国屋書店で見つけたので買って積んだままにしていた。 続編の「白魔の檻」が8月29日発売。 しかも予約しちゃってるので続編読むために読まねばとようやく開いたらページを捲る手を止められず、一気に読み終わった。 なぜ2人は瓜二つなのか。 もしかして2人は生き別れた双子? 武田に瓜二つの溺死体の正体は? なぜ死んだのか? 初っ端から謎が怒涛のように押し寄せて、手がかりもなくお手上げだったけど、話が進むうちにさらに謎は深まり、第二の事件も…。 最後まで読んだ時、ようやくタイトルの意味を理解してスッキリした。 伏線全部回収したけど、密室のトリックだけが物足りなかったところ。 続編の「白魔の檻」に期待したい。 - 2025年8月28日
 日記の練習くどうれいん読み終わった買った兼業作家から専業作家へと歩み始めたタイミングからスタートした「NHK出版本がひらく」というウェブマガジンでの日記の連載を書籍化した作品。 日記の練習と日記の本番という2つの要素で構成されている。 10代の頃から日記を書き続けているくどうさん。 それなのに、日記は「続けるもの」ではなく、続く日記なんて面白くない。毎日欠かさず書こうと思ったことは一度もない…そんな日記の紹介にびっくりした。 くどうさんにとって日記は「日々の記録」ではなく、「日々を記録しようと思った自分の記録」で、できる日とできない日の緩急が自分らしく、ノートがなくても、ブログがなくても、日記は死ぬまで勝手に書くものだと思っている…という考えに日記に対して気負った思いで取り組んでいたのかもと考えを改めた。 「書くと生活はおもしろくなるということをひとりでも多くの人にわかってほしい」というのをきっかけに始まったこの日記の連載は、日記に挫折した人に向けて、日記との新しい向き合い方を教えてくれる。 「日記の練習」という日記の断片が、エッセイのような物語のような、ひと月を振り返った長めの日記の「日記の本番」へと姿を変えていくのも楽しんで欲しい。 この本を読んで、読み始めて日記を再開したけれど、あとがきを読むとちょっと思うところがあった。 それは本文をちゃんと読んでから読んでみて欲しい。
日記の練習くどうれいん読み終わった買った兼業作家から専業作家へと歩み始めたタイミングからスタートした「NHK出版本がひらく」というウェブマガジンでの日記の連載を書籍化した作品。 日記の練習と日記の本番という2つの要素で構成されている。 10代の頃から日記を書き続けているくどうさん。 それなのに、日記は「続けるもの」ではなく、続く日記なんて面白くない。毎日欠かさず書こうと思ったことは一度もない…そんな日記の紹介にびっくりした。 くどうさんにとって日記は「日々の記録」ではなく、「日々を記録しようと思った自分の記録」で、できる日とできない日の緩急が自分らしく、ノートがなくても、ブログがなくても、日記は死ぬまで勝手に書くものだと思っている…という考えに日記に対して気負った思いで取り組んでいたのかもと考えを改めた。 「書くと生活はおもしろくなるということをひとりでも多くの人にわかってほしい」というのをきっかけに始まったこの日記の連載は、日記に挫折した人に向けて、日記との新しい向き合い方を教えてくれる。 「日記の練習」という日記の断片が、エッセイのような物語のような、ひと月を振り返った長めの日記の「日記の本番」へと姿を変えていくのも楽しんで欲しい。 この本を読んで、読み始めて日記を再開したけれど、あとがきを読むとちょっと思うところがあった。 それは本文をちゃんと読んでから読んでみて欲しい。 - 2025年8月16日
 読み終わった@ 自宅本を読みたくて会社を辞めたという三宅香帆さんの読書論。 かなり話題になったし、実際2024年1番売れた新書だし、新書大賞も受賞されていたので気になっていたけど読むきっかけがなく、最近三宅香帆さんのYouTubeチャンネルを見て読んでみたくなりようやく手に取った。 働いていると本が読めない、疲れてスマホばかり見てしまう、そんな声がたくさん寄せられ、「そもそも本も読めない余裕のない社会はおかしい」と訴えるまえがきから始まり、映画『花束みたいな恋をした』を下敷きに読書史と労働史へと大風呂敷を広げた展開は、よくよく読み進めてみれば、なぜ本を読む事が出来ないのかを、読めなくなってしまった人へ実感させるための仕掛けだった。(ネタバレになるので言及はしないので読んでみてください) 明治・大正から始まり、現代に至るまでの道のりを辿り、作者が1番訴えたかった提言と結論は最終章の3行にこめられている。 もちろん、働きながら本を読むコツについても、あとがきでしっかりと書かれているので、これから本を読めるようになりたいという人たちへの一助にもなる。 ちなみに私はまったく同じ方法やってました。 働きながら本を読める方にも読者人を増やす布教のために読むのをオススメします。
読み終わった@ 自宅本を読みたくて会社を辞めたという三宅香帆さんの読書論。 かなり話題になったし、実際2024年1番売れた新書だし、新書大賞も受賞されていたので気になっていたけど読むきっかけがなく、最近三宅香帆さんのYouTubeチャンネルを見て読んでみたくなりようやく手に取った。 働いていると本が読めない、疲れてスマホばかり見てしまう、そんな声がたくさん寄せられ、「そもそも本も読めない余裕のない社会はおかしい」と訴えるまえがきから始まり、映画『花束みたいな恋をした』を下敷きに読書史と労働史へと大風呂敷を広げた展開は、よくよく読み進めてみれば、なぜ本を読む事が出来ないのかを、読めなくなってしまった人へ実感させるための仕掛けだった。(ネタバレになるので言及はしないので読んでみてください) 明治・大正から始まり、現代に至るまでの道のりを辿り、作者が1番訴えたかった提言と結論は最終章の3行にこめられている。 もちろん、働きながら本を読むコツについても、あとがきでしっかりと書かれているので、これから本を読めるようになりたいという人たちへの一助にもなる。 ちなみに私はまったく同じ方法やってました。 働きながら本を読める方にも読者人を増やす布教のために読むのをオススメします。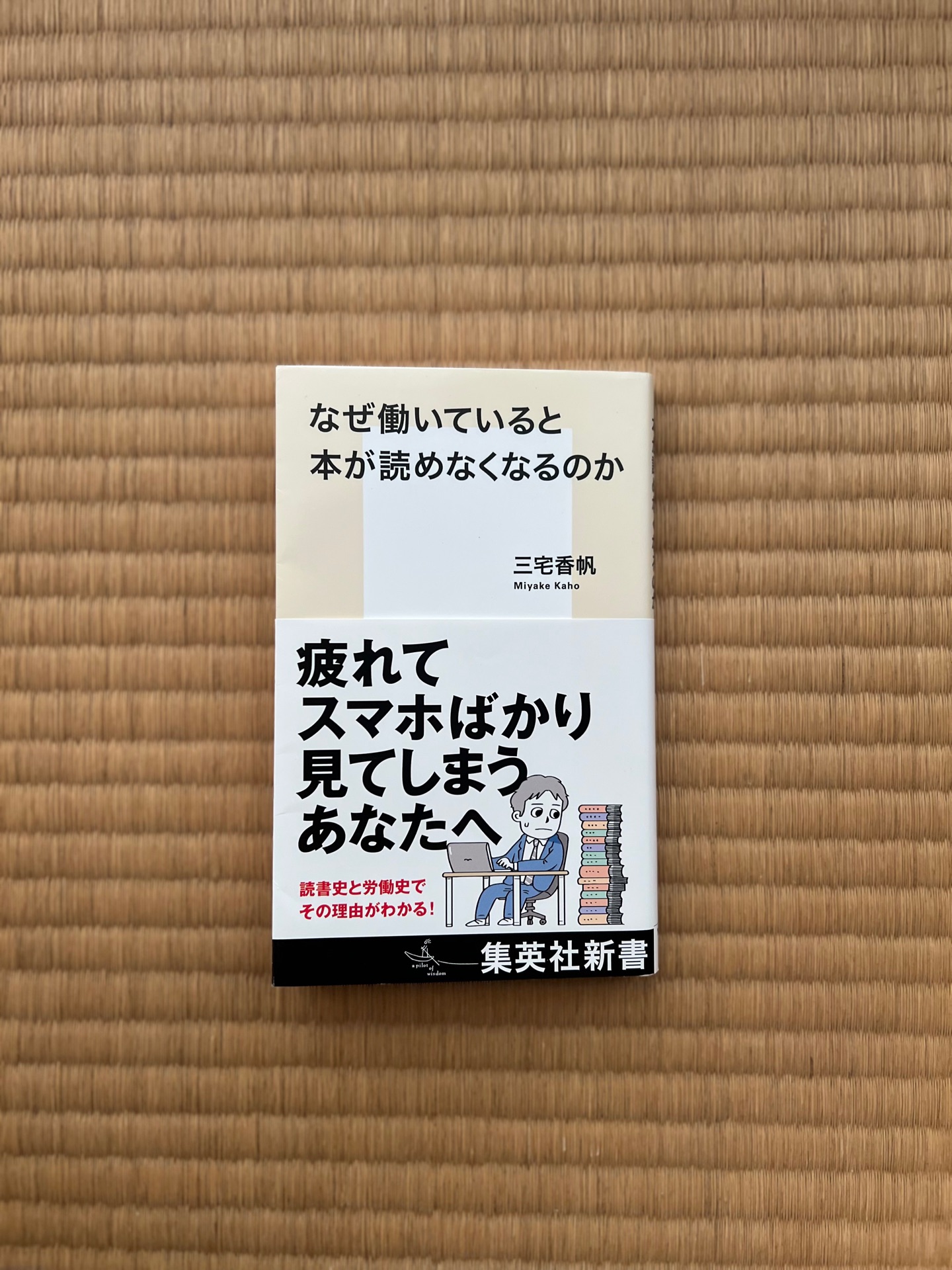
- 2025年4月29日
- 2025年4月15日
 本なら売るほど 1児島青読み終わった読みたくて書店を探し回ったけど、どこも在庫切れで見つからず、増刷のタイミングでようやく購入したマンガ。 マンガで売り切れってなかなかないのでは。 読書好きだからこそ、本を愛しているからこそ、不良在庫の死刑執行に心痛める店主。 そんな彼の心を救うのも、やはり本がもたらす出会い。 「心ない人に買われるくらいなら心ある人に捨てられたい」 複雑な本読みの心理の言葉にグッときた第一話。 本を通して出会う本読みたちの人生や想いが、すごく良かった。 4月15日に発売される第二巻を買い逃さないために予約済み。 次はどんな物語が待っているのか楽しみ。 表紙カバーをはずしたデザインがとっても素敵なのでぜひ電子ではなく紙で読んで欲しい。
本なら売るほど 1児島青読み終わった読みたくて書店を探し回ったけど、どこも在庫切れで見つからず、増刷のタイミングでようやく購入したマンガ。 マンガで売り切れってなかなかないのでは。 読書好きだからこそ、本を愛しているからこそ、不良在庫の死刑執行に心痛める店主。 そんな彼の心を救うのも、やはり本がもたらす出会い。 「心ない人に買われるくらいなら心ある人に捨てられたい」 複雑な本読みの心理の言葉にグッときた第一話。 本を通して出会う本読みたちの人生や想いが、すごく良かった。 4月15日に発売される第二巻を買い逃さないために予約済み。 次はどんな物語が待っているのか楽しみ。 表紙カバーをはずしたデザインがとっても素敵なのでぜひ電子ではなく紙で読んで欲しい。 - 2025年4月14日
 本なら売るほど 2児島青読み終わった1巻の入手に苦労したのでしっかり予約しておいたので発売日に手元に届いた。 辞典の話は捨てる人、拾う人、どちらの視点もありそうでおもしろかった。 一見のような客が、どこかで少しずつ繋がって、別の物語を語り出したり、まったく関係がなさそうな別の舞台で本との深い繋がりが出てきたり、今回も本を読む人なら深く味わえるお話ばかりで、すごく良かった。 3巻も楽しみ。
本なら売るほど 2児島青読み終わった1巻の入手に苦労したのでしっかり予約しておいたので発売日に手元に届いた。 辞典の話は捨てる人、拾う人、どちらの視点もありそうでおもしろかった。 一見のような客が、どこかで少しずつ繋がって、別の物語を語り出したり、まったく関係がなさそうな別の舞台で本との深い繋がりが出てきたり、今回も本を読む人なら深く味わえるお話ばかりで、すごく良かった。 3巻も楽しみ。 - 2025年3月28日
 お砂糖ひとさじで松田青子気になる
お砂糖ひとさじで松田青子気になる
読み込み中...
