
saeko
@saekyh
2025.07以降に読んだものと思ったことの記録
- 2026年2月22日
- 2026年2月21日
 学芸員しか知らない 美術館が楽しくなる話ちいさな美術館の学芸員学芸員の友だちの話を思い浮かべながら読んだ。 展示会の企画から実現までの仕事の流れの話を読んで、めちゃくちゃ要件定義とプロジェクトマネジメントしてる…!となった。 テーマ先行ではなく、展示できる作品ありきで展示会のコンセプトが決まる、というのがすごく現実的で印象に残った。 一期一会の美術館の展示、もっと味わって楽しもう…。 美術は生活において無駄なものかもしれないけど、無駄があってこそ人生は豊かになるんだ、という気持ちが伝わってきてよかった。
学芸員しか知らない 美術館が楽しくなる話ちいさな美術館の学芸員学芸員の友だちの話を思い浮かべながら読んだ。 展示会の企画から実現までの仕事の流れの話を読んで、めちゃくちゃ要件定義とプロジェクトマネジメントしてる…!となった。 テーマ先行ではなく、展示できる作品ありきで展示会のコンセプトが決まる、というのがすごく現実的で印象に残った。 一期一会の美術館の展示、もっと味わって楽しもう…。 美術は生活において無駄なものかもしれないけど、無駄があってこそ人生は豊かになるんだ、という気持ちが伝わってきてよかった。 - 2026年2月16日
- 2026年2月14日
 はじめての戦争と平和鶴岡路人読みやすくて一気に読んだ。 憲法の改訂、防衛費の増大、非核三原則の見直しと、自民党は戦争に向かうつもりか。選挙期間中に多く聞かれた批判であるし、自分自身もそう思っていた。 もちろん戦争が起こるべきではないのは当然だけれど、当為と存在は別、つまり起こるべきではないけど実際は起こってしまうと考えたときに、どのように抑止すべきなのか、は一筋縄ではいかない問いだ。 国際政治と安全保障は、ものすごく多面的で、どの角度から見るかによって正解が異なる。 たとえば軍備拡大はよくないというけれど、軍事力を甘く見られて攻め込まれてもいいの? 核兵器はよくないけれど、持っていること自体が核兵器の行使の抑止になるとしたら? 国際情勢は刻一刻と変わるので、過去のセオリーがいまも通用するとは限らない。 しかも政治は結果論で評価されるので、事前の妥当性の評価がとても難しい。 単純化した理想論ではなく現実的な目線で、戦争を起こさないためにはどうするべきかを考えるための枠組みを教えてくれる本だった。
はじめての戦争と平和鶴岡路人読みやすくて一気に読んだ。 憲法の改訂、防衛費の増大、非核三原則の見直しと、自民党は戦争に向かうつもりか。選挙期間中に多く聞かれた批判であるし、自分自身もそう思っていた。 もちろん戦争が起こるべきではないのは当然だけれど、当為と存在は別、つまり起こるべきではないけど実際は起こってしまうと考えたときに、どのように抑止すべきなのか、は一筋縄ではいかない問いだ。 国際政治と安全保障は、ものすごく多面的で、どの角度から見るかによって正解が異なる。 たとえば軍備拡大はよくないというけれど、軍事力を甘く見られて攻め込まれてもいいの? 核兵器はよくないけれど、持っていること自体が核兵器の行使の抑止になるとしたら? 国際情勢は刻一刻と変わるので、過去のセオリーがいまも通用するとは限らない。 しかも政治は結果論で評価されるので、事前の妥当性の評価がとても難しい。 単純化した理想論ではなく現実的な目線で、戦争を起こさないためにはどうするべきかを考えるための枠組みを教えてくれる本だった。 - 2026年2月12日
 「なぜ1+1=2なのか?」からはじめる非常識な数学教室ユージニア・チェン,熊谷玲美筋金入りの数学嫌いで、テストは万年赤点、高校生のときに数学の問題を解くのが嫌で嫌で、ドリルのページを握りつぶした記憶が鮮明に残っている。そんなわたしが常にひっかかっていたのが「なんでそうなるのか?」「なんでこんなことをするのか?」という前提で、これが理解できないゆえ自分は数学が苦手なのだと思っていたが、この本では「数学が苦手な人と数学者の考え方は同じだ」というのだから嬉しい驚きだ。 たしかに、「1+1=2になるのはなぜか?」「4+2=2+4といえるのはなぜか?」などは、当たり前のように見えて深遠な問いのような感じがする。そして抽象数学においては、答えは常に一つではなくて、前提によって変わる。つまり、「なぜXなのか?」ではなく「Xになるのはどのような場合か?」という問い立てが妥当というのはなるほど、と思った。 数字や図形などの抽象度の高い情報にはやはりあまり興味が持てなくて、結構読み飛ばしてしまったけど、数字によって情報を抽象化(=一般化)することで、世界をもっと高解像度で理解できるようになる、という考え方はおもしろかった。 作者が本当に数学が好きだという想いが伝わってくるのがとてもいい。
「なぜ1+1=2なのか?」からはじめる非常識な数学教室ユージニア・チェン,熊谷玲美筋金入りの数学嫌いで、テストは万年赤点、高校生のときに数学の問題を解くのが嫌で嫌で、ドリルのページを握りつぶした記憶が鮮明に残っている。そんなわたしが常にひっかかっていたのが「なんでそうなるのか?」「なんでこんなことをするのか?」という前提で、これが理解できないゆえ自分は数学が苦手なのだと思っていたが、この本では「数学が苦手な人と数学者の考え方は同じだ」というのだから嬉しい驚きだ。 たしかに、「1+1=2になるのはなぜか?」「4+2=2+4といえるのはなぜか?」などは、当たり前のように見えて深遠な問いのような感じがする。そして抽象数学においては、答えは常に一つではなくて、前提によって変わる。つまり、「なぜXなのか?」ではなく「Xになるのはどのような場合か?」という問い立てが妥当というのはなるほど、と思った。 数字や図形などの抽象度の高い情報にはやはりあまり興味が持てなくて、結構読み飛ばしてしまったけど、数字によって情報を抽象化(=一般化)することで、世界をもっと高解像度で理解できるようになる、という考え方はおもしろかった。 作者が本当に数学が好きだという想いが伝わってくるのがとてもいい。 - 2026年2月4日
 KISSA BY KISSA 路上と喫茶ー僕が日本を歩いて旅する理由クレイグ・モド,今井栄一東京から京都をつなぐ中山道を徒歩で踏破したアメリカ人作家クレイグ・モドによる、旅の道中で出会った喫茶店の記録。 翻訳文とはにわかに信じがたい豊かな語り口で、時を止めたまま少しずつ失われゆく日本の喫茶店(とピザトースト)の姿を描く。 どこか寂しさと静謐さを湛えながらもセンチメンタリズムに陥いることのないフラットな眼差しに、自分は目の前にある社会の姿と向き合えているだろうかと考えさせられる。 ただ好き、おいしい、興味深い、という気持ちだけでなく、彼の生い立ちや人生観に深く紐づいた物語を読んで、出会いの意味と無意味さに想いを馳せた。
KISSA BY KISSA 路上と喫茶ー僕が日本を歩いて旅する理由クレイグ・モド,今井栄一東京から京都をつなぐ中山道を徒歩で踏破したアメリカ人作家クレイグ・モドによる、旅の道中で出会った喫茶店の記録。 翻訳文とはにわかに信じがたい豊かな語り口で、時を止めたまま少しずつ失われゆく日本の喫茶店(とピザトースト)の姿を描く。 どこか寂しさと静謐さを湛えながらもセンチメンタリズムに陥いることのないフラットな眼差しに、自分は目の前にある社会の姿と向き合えているだろうかと考えさせられる。 ただ好き、おいしい、興味深い、という気持ちだけでなく、彼の生い立ちや人生観に深く紐づいた物語を読んで、出会いの意味と無意味さに想いを馳せた。 - 2026年1月31日
 ショッピン・イン・アオモリ能町みね子合間に挟まれるチョコレートコラムに心惹かれた。青森市の珈琲クレオパトラのチョコレートシフォンケーキ、佇まいが上品で美しい!弘前にあるというみらぼおのチョコレートパンケーキ、きっと甘さが濃厚で美味しいんだろうなあ…食べてみたい! 青森名物からちょっとした日用品までいろいろなアイテムが取り上げられているけども、やっぱり食べ物に関する話がいちばんわくわくする。
ショッピン・イン・アオモリ能町みね子合間に挟まれるチョコレートコラムに心惹かれた。青森市の珈琲クレオパトラのチョコレートシフォンケーキ、佇まいが上品で美しい!弘前にあるというみらぼおのチョコレートパンケーキ、きっと甘さが濃厚で美味しいんだろうなあ…食べてみたい! 青森名物からちょっとした日用品までいろいろなアイテムが取り上げられているけども、やっぱり食べ物に関する話がいちばんわくわくする。 - 2026年1月27日
 センスの哲学千葉雅也センスといえば、いろんなものを学んで、構造を抽象化して、自分も再現できるように…みたいなロジカルな話になるかと思ったら、もっと自由で発散的な話で、少し驚いた。 センスを「不在」と「存在」のリズムと捉えて、自由に構成してみる。人間は安定性を求めながらも、不安定に享楽を感じるものだし、無秩序に見えるリズムにも、なんらかの物語を感じようとするものだという。 本当にそれでセンスのあるものが作れるのかなあ、なんか意図とか大事なんじゃないのか、という気はするが、意味とか目的から抜け出して、単一のメッセージで括らずに、細かい出来事に心を動かされながら、物事の複雑性に目を向けられるようになるというのは、大切なことだと思う。
センスの哲学千葉雅也センスといえば、いろんなものを学んで、構造を抽象化して、自分も再現できるように…みたいなロジカルな話になるかと思ったら、もっと自由で発散的な話で、少し驚いた。 センスを「不在」と「存在」のリズムと捉えて、自由に構成してみる。人間は安定性を求めながらも、不安定に享楽を感じるものだし、無秩序に見えるリズムにも、なんらかの物語を感じようとするものだという。 本当にそれでセンスのあるものが作れるのかなあ、なんか意図とか大事なんじゃないのか、という気はするが、意味とか目的から抜け出して、単一のメッセージで括らずに、細かい出来事に心を動かされながら、物事の複雑性に目を向けられるようになるというのは、大切なことだと思う。 - 2026年1月23日
 世界の食卓から社会が見える岡根谷実里テーブルに並んだ食べ物はすべて社会と紐づいている、ということは感覚的にはわかりつつも、あまりふみこんで調べたことがなかったのでおもしろかった! 様々な国の食事情とその背景にある社会情勢について、詳しく調べられていて、おいしそうな食べ物にそそられつつも勉強になる。そしてそれぞれの国の家庭に実際に足を運んでいる岡根谷さんの行動力がすごい。 ヨーグルトはブルガリアの名産というわけではなくて、社会主義経済において国民に分配するのに最適化された栄養食という話とか、日本の野菜が水っぽくて味が薄いと言われるのは、女性の社会進出に伴う時短料理の需要に応えるためとか、まさかそんなことと結びついていたのか!という目から鱗の発見がたくさんあった。
世界の食卓から社会が見える岡根谷実里テーブルに並んだ食べ物はすべて社会と紐づいている、ということは感覚的にはわかりつつも、あまりふみこんで調べたことがなかったのでおもしろかった! 様々な国の食事情とその背景にある社会情勢について、詳しく調べられていて、おいしそうな食べ物にそそられつつも勉強になる。そしてそれぞれの国の家庭に実際に足を運んでいる岡根谷さんの行動力がすごい。 ヨーグルトはブルガリアの名産というわけではなくて、社会主義経済において国民に分配するのに最適化された栄養食という話とか、日本の野菜が水っぽくて味が薄いと言われるのは、女性の社会進出に伴う時短料理の需要に応えるためとか、まさかそんなことと結びついていたのか!という目から鱗の発見がたくさんあった。 - 2026年1月17日
 目的への抵抗國分功一郎「暇と退屈の倫理学」がおもしろかったので。 こちらは高校生向けの講義の書き起こしなので、文章が平易で読みやすい。 感染症の流行を理由に、政府が国民の移動の自由を制限することは許されるのか。政府は合目的的に存在するものなのか。 当たり前だと思っている出来事に対して疑問を投げかけ、会話を重ねていくことの大切さを説いている。 本書のタイトルにもなっている、目的に捉われないことの重要さは共感できる。本書では、目的のない行為は存在しないが、行為が目的を超える範囲で人間は自由であるという。たとえば、売上を向上させるという目的で仕事が発生しても、目的に捉われずにその仕事を楽しめるとき、人は自由であるということだろうか。 これは「暇と退屈の倫理学」でも書かれていた「目の前のことを楽しむ」ということに共通しているのだろうと思った。 一方で、遊びとしての社会活動や政治、というのも書かれていたが、社会活動が目的を超えたら ー たとえば、自分たちを抑圧している何かを解消したいという目的を超えて、参加者がその活動そのものに楽しみを見出すことになったとき ー 参加者にとっては自由を感じる楽しい経験になるかもしらないけれども、方向性を誤ると暴走してしまったりすることにつながらないのかなあと思った。 ただふむふむと納得させられるだけでなく、批判的にも考えさせられる一冊だった。
目的への抵抗國分功一郎「暇と退屈の倫理学」がおもしろかったので。 こちらは高校生向けの講義の書き起こしなので、文章が平易で読みやすい。 感染症の流行を理由に、政府が国民の移動の自由を制限することは許されるのか。政府は合目的的に存在するものなのか。 当たり前だと思っている出来事に対して疑問を投げかけ、会話を重ねていくことの大切さを説いている。 本書のタイトルにもなっている、目的に捉われないことの重要さは共感できる。本書では、目的のない行為は存在しないが、行為が目的を超える範囲で人間は自由であるという。たとえば、売上を向上させるという目的で仕事が発生しても、目的に捉われずにその仕事を楽しめるとき、人は自由であるということだろうか。 これは「暇と退屈の倫理学」でも書かれていた「目の前のことを楽しむ」ということに共通しているのだろうと思った。 一方で、遊びとしての社会活動や政治、というのも書かれていたが、社会活動が目的を超えたら ー たとえば、自分たちを抑圧している何かを解消したいという目的を超えて、参加者がその活動そのものに楽しみを見出すことになったとき ー 参加者にとっては自由を感じる楽しい経験になるかもしらないけれども、方向性を誤ると暴走してしまったりすることにつながらないのかなあと思った。 ただふむふむと納得させられるだけでなく、批判的にも考えさせられる一冊だった。 - 2026年1月15日
 純粋哲学の世界高村友也ちょっと開いた「専門用語を用いず平易な日常言語で語られる」という文句のわりには語り口が小難しく、読みづらいと感じてしまった。 また入門書を銘打ってはいるが、歴史や理論についてではなく、あくまで筆者の問題意識や考えに則って話が進んでいくので、どちらかというとエッセイに近いなという印象を受けた。 逆にいえば、哲学の用語などの紹介ではなく、「哲学的に思考することの入門書」という切り口は新鮮だなとは思った。
純粋哲学の世界高村友也ちょっと開いた「専門用語を用いず平易な日常言語で語られる」という文句のわりには語り口が小難しく、読みづらいと感じてしまった。 また入門書を銘打ってはいるが、歴史や理論についてではなく、あくまで筆者の問題意識や考えに則って話が進んでいくので、どちらかというとエッセイに近いなという印象を受けた。 逆にいえば、哲学の用語などの紹介ではなく、「哲学的に思考することの入門書」という切り口は新鮮だなとは思った。 - 2026年1月12日
 暇と退屈の倫理学國分功一郎世間に数多ある「東大・京大でもっとも読まれた本」の代表作。 かなり前から本屋に並んでおり、友人も薦めていたので認知はしていたのだが、その重厚なタイトルに引け目を感じて、なかなか手が伸びなかった。 しかし、最近哲学に関する本を読むようになってハードルが下がってきたのと、なにより「自分はなんのために生きているんだ」「これからどうやって生きていったらいいんだろう」と考えることが増えたことをきっかけに、発売後15年経ってもいまだ平積みされているこの本を手に取ってみた。 環境には恵まれている。住む場所があり、家庭があり、友人があり、ほどよく仕事をして、ほどよく余暇を過ごす。そんな生活をする中で、「自分はこのままでいいのだろうか」と焦りを感じるようになった。 幼い頃からの夢が叶えられていないような気がする。テレビを観れば、努力を重ねてひとかどの者になった人たちが特集されている。自分もやりたいことをやって、何事かを成すべきではないのか。でも、それって一体なんなんだ、どうやったらいいんだ…。 こんな思考のスパイラルに陥っている自分の状態をまさに言い表した一冊だった。 豊かな社会では、暇ができる。その暇の中で、人間は退屈している。そこで人間は暇を悪とみなし、退屈をまぎらわすための何かを探している。それは例えば、人から与えられるものを消費することであったり、仕事をしたりすることである。 消費は、自分の欲望ではなく、他者から与えられた欲望を内面化しようとする行為なので、永遠に満たされない。 仕事は、なんらかの信条に隷属的で、それ以外の物事に対して盲目的なので、人は「自分はこれをやっていればいいのだ」と楽になる。しかし、その仕事の遂行の中で、自分の期待通りに事が運ばないと、また退屈する。そしてまた隷属の対象を見つける…。 こうして人間は生きている限り退屈のループから逃れられない。 この考え方にはっとさせられた。学生時代は「将来の夢=仕事」と単純化して人生を捉えていた。しかし実際は、生活もあるし、趣味もあるし、さまざまな要素がある。そのさまざまな要素を行き来する中で、わたしはなんとなく退屈していて、隷属する対象を求めて「なにか打ち込める仕事を」と考えていたのだ。 國分氏はこの考え方を批判する。それは人生の多様な要素を排除しており、その純粋さゆえに、極度の愛国心やテロリズムなどにも通ずる、破壊に繋がりうるからである。 では私たちはどう生きていったらいいのか?氏の提言は主に2つ。人生を「楽しむ」ことと「考える」ことである。 楽しむことは、瞬間的な享楽を消費することではなくて、目の前のことにしっかりと時間をかけて、知識も身につけて向き合うことである。その対象は食でも、芸術でも、なんでもよい。退屈を仕事で凌ごうとする欲求に抗って、自分が楽しいと感じることを噛み締める贅沢な時間を過ごすのだ。 その次に、楽しんで終わりではなく、考えることだ。氏は、ある物事を楽しんでいれば、自然と考えることに繋がると主張する。たとえば、この味わいはどうやったら生まれるのだろう?とか、この芸術家はなにに影響を受けているのだろう?というように。 刹那的な情報をいったりきたりするのではなくて、自分が「楽しい」と感じることを「考える」暇をつくることが、退屈とうまく付き合っていく生き方なのではないか、という考え方だ。 この本が出版されたのは15年前ではあるけれども、まったく色褪せない主張だと感じた。 わたしたちの生活の一部になってしまったSNSを介して、欲望を惹起するような情報が30秒、15秒という短時間で大量に流れ込んでくる。その情報の洪水の中で、様々なことに少しずつ羨望の眼差しを向け、欲望を再生産しながら、自分が何が欲しいのかわからなくなる。その欲求不満の捌け口として、邪念を振り捨てて取り組めるような信仰の対象を求め、仕事を通して自己実現しようとする…。 この他者が作り出す情報によりいつまでも満たされない退屈に歯止めをかけるために、自分自身の楽しみにしっかりと心を傾けることが大切なのだ。 経済的利潤を最大化するために加速していく資本主義の磁場に対して、この本の主張はその歯止めになるような力強いものではなく、社会の仕組みの構築というよりは個人の意識の中に止まる淡く儚いものであるとも感じる。しかしまずは自分個人の取り組みとしてその実践を始めて、人生への不満感が満たされるのか、自己変容が起きるのかどうかを試してみたい。 いままさに読んでよかった本だと思った。
暇と退屈の倫理学國分功一郎世間に数多ある「東大・京大でもっとも読まれた本」の代表作。 かなり前から本屋に並んでおり、友人も薦めていたので認知はしていたのだが、その重厚なタイトルに引け目を感じて、なかなか手が伸びなかった。 しかし、最近哲学に関する本を読むようになってハードルが下がってきたのと、なにより「自分はなんのために生きているんだ」「これからどうやって生きていったらいいんだろう」と考えることが増えたことをきっかけに、発売後15年経ってもいまだ平積みされているこの本を手に取ってみた。 環境には恵まれている。住む場所があり、家庭があり、友人があり、ほどよく仕事をして、ほどよく余暇を過ごす。そんな生活をする中で、「自分はこのままでいいのだろうか」と焦りを感じるようになった。 幼い頃からの夢が叶えられていないような気がする。テレビを観れば、努力を重ねてひとかどの者になった人たちが特集されている。自分もやりたいことをやって、何事かを成すべきではないのか。でも、それって一体なんなんだ、どうやったらいいんだ…。 こんな思考のスパイラルに陥っている自分の状態をまさに言い表した一冊だった。 豊かな社会では、暇ができる。その暇の中で、人間は退屈している。そこで人間は暇を悪とみなし、退屈をまぎらわすための何かを探している。それは例えば、人から与えられるものを消費することであったり、仕事をしたりすることである。 消費は、自分の欲望ではなく、他者から与えられた欲望を内面化しようとする行為なので、永遠に満たされない。 仕事は、なんらかの信条に隷属的で、それ以外の物事に対して盲目的なので、人は「自分はこれをやっていればいいのだ」と楽になる。しかし、その仕事の遂行の中で、自分の期待通りに事が運ばないと、また退屈する。そしてまた隷属の対象を見つける…。 こうして人間は生きている限り退屈のループから逃れられない。 この考え方にはっとさせられた。学生時代は「将来の夢=仕事」と単純化して人生を捉えていた。しかし実際は、生活もあるし、趣味もあるし、さまざまな要素がある。そのさまざまな要素を行き来する中で、わたしはなんとなく退屈していて、隷属する対象を求めて「なにか打ち込める仕事を」と考えていたのだ。 國分氏はこの考え方を批判する。それは人生の多様な要素を排除しており、その純粋さゆえに、極度の愛国心やテロリズムなどにも通ずる、破壊に繋がりうるからである。 では私たちはどう生きていったらいいのか?氏の提言は主に2つ。人生を「楽しむ」ことと「考える」ことである。 楽しむことは、瞬間的な享楽を消費することではなくて、目の前のことにしっかりと時間をかけて、知識も身につけて向き合うことである。その対象は食でも、芸術でも、なんでもよい。退屈を仕事で凌ごうとする欲求に抗って、自分が楽しいと感じることを噛み締める贅沢な時間を過ごすのだ。 その次に、楽しんで終わりではなく、考えることだ。氏は、ある物事を楽しんでいれば、自然と考えることに繋がると主張する。たとえば、この味わいはどうやったら生まれるのだろう?とか、この芸術家はなにに影響を受けているのだろう?というように。 刹那的な情報をいったりきたりするのではなくて、自分が「楽しい」と感じることを「考える」暇をつくることが、退屈とうまく付き合っていく生き方なのではないか、という考え方だ。 この本が出版されたのは15年前ではあるけれども、まったく色褪せない主張だと感じた。 わたしたちの生活の一部になってしまったSNSを介して、欲望を惹起するような情報が30秒、15秒という短時間で大量に流れ込んでくる。その情報の洪水の中で、様々なことに少しずつ羨望の眼差しを向け、欲望を再生産しながら、自分が何が欲しいのかわからなくなる。その欲求不満の捌け口として、邪念を振り捨てて取り組めるような信仰の対象を求め、仕事を通して自己実現しようとする…。 この他者が作り出す情報によりいつまでも満たされない退屈に歯止めをかけるために、自分自身の楽しみにしっかりと心を傾けることが大切なのだ。 経済的利潤を最大化するために加速していく資本主義の磁場に対して、この本の主張はその歯止めになるような力強いものではなく、社会の仕組みの構築というよりは個人の意識の中に止まる淡く儚いものであるとも感じる。しかしまずは自分個人の取り組みとしてその実践を始めて、人生への不満感が満たされるのか、自己変容が起きるのかどうかを試してみたい。 いままさに読んでよかった本だと思った。 - 2026年1月2日
 斜め論松本卓也統合失調症の発症と治癒における病理学的モデルが主題になっているが、この理論は精神病以外の一般的なテーマにもあてはめられるように感じた。 世界に向き合い、了解しようとする態度として、目標を達成しようと上を目指したり、真相を掘り下げて理解しようとする「垂直性」が支配的だが、類似性のある他者と境遇を分かち合う「水平性」の重要性と、どちらかに偏ることなく水平性を前提として垂直性を弱毒化して取り入れる手法を提案する(=斜め横断性)。 またそれだけでなく、垂直性/水平性に対置される「死ぬための思想」と「生き延びるための思想」も印象的だった。なにか一つの決定的な出来事を重要視するのではなく、その先も続いていくものに目を向けることの大切さが、自分の今後の人生の意思決定においてじわじわと沁みてくるのではないかと思った。
斜め論松本卓也統合失調症の発症と治癒における病理学的モデルが主題になっているが、この理論は精神病以外の一般的なテーマにもあてはめられるように感じた。 世界に向き合い、了解しようとする態度として、目標を達成しようと上を目指したり、真相を掘り下げて理解しようとする「垂直性」が支配的だが、類似性のある他者と境遇を分かち合う「水平性」の重要性と、どちらかに偏ることなく水平性を前提として垂直性を弱毒化して取り入れる手法を提案する(=斜め横断性)。 またそれだけでなく、垂直性/水平性に対置される「死ぬための思想」と「生き延びるための思想」も印象的だった。なにか一つの決定的な出来事を重要視するのではなく、その先も続いていくものに目を向けることの大切さが、自分の今後の人生の意思決定においてじわじわと沁みてくるのではないかと思った。 - 2025年12月23日
 静かな働き方シモーヌ・ストルゾフ,大熊希美労働に生活を侵食されることに警鐘を鳴らす本はいろいろあるけれど、この本では事例紹介だけではなく、労働がやりがいや自己実現と繋げて語られるようになった歴史的背景に言及している点がおもしろかった。 古代ギリシアから労働は避けるべきものとされていたが、贖宥状の販売に反対したプロテスタントが労働を尊ぶ文化を生み出し、それが利益を生み出すことを正とする資本主義の理念と合致した。現代になると、経済成長によってCEOの収益は何倍にもなったが、社員には充分に還元されず、金銭のかわりにやりがいやモチベーションを対価とするようになっていく…というのが記憶にある大掴みな話。 やはり本を読んでいるといいのは、いままで自分が所与のものと思っていたことが、その時代の思想を反映して生まれたもので、絶対的なものではないということに気づけることだ。内面化していた価値観を相対的に捉えることができるようになる。 この本では、ワークライフバランスをとるうえでの特効薬を提示してくれるわけではない。 ただ、やりたいことを仕事にすることや、仕事で自己実現をすることが唯一の正解ではない、と説いたうえで、自分にとっての成功とはなにか、社会の期待に応えるのではなく自分自身で決めることが大切だと教えてくれる。 どんなに搾取的な競争社会を憂えたところで、いますぐにその構造が変わるわけではない。それをふまえたうえで、ある程度は適合しつつも、自分の人生を手放さないようにせよ、という極めて現実的なアドバイスだと感じた。
静かな働き方シモーヌ・ストルゾフ,大熊希美労働に生活を侵食されることに警鐘を鳴らす本はいろいろあるけれど、この本では事例紹介だけではなく、労働がやりがいや自己実現と繋げて語られるようになった歴史的背景に言及している点がおもしろかった。 古代ギリシアから労働は避けるべきものとされていたが、贖宥状の販売に反対したプロテスタントが労働を尊ぶ文化を生み出し、それが利益を生み出すことを正とする資本主義の理念と合致した。現代になると、経済成長によってCEOの収益は何倍にもなったが、社員には充分に還元されず、金銭のかわりにやりがいやモチベーションを対価とするようになっていく…というのが記憶にある大掴みな話。 やはり本を読んでいるといいのは、いままで自分が所与のものと思っていたことが、その時代の思想を反映して生まれたもので、絶対的なものではないということに気づけることだ。内面化していた価値観を相対的に捉えることができるようになる。 この本では、ワークライフバランスをとるうえでの特効薬を提示してくれるわけではない。 ただ、やりたいことを仕事にすることや、仕事で自己実現をすることが唯一の正解ではない、と説いたうえで、自分にとっての成功とはなにか、社会の期待に応えるのではなく自分自身で決めることが大切だと教えてくれる。 どんなに搾取的な競争社会を憂えたところで、いますぐにその構造が変わるわけではない。それをふまえたうえで、ある程度は適合しつつも、自分の人生を手放さないようにせよ、という極めて現実的なアドバイスだと感じた。 - 2025年12月20日
 食べたくなる本三浦哲哉料理本批評ってはじめて読んだ。 批評というと、いろんな人の意見や主張をばっさばっさと切り捨てつつ己の論を構築していく、みたいなちょっと上から目線なような印象があったのだが、この本はちがった。 食や料理家に対する尊敬の念を感じるし、王道なものにも常軌を逸したものも素直に受け止めたり、驚いたり、影響されたりしてみせる、筆者の斜に構えてなさというか懐の深さがすごくいいなと思った。 これまでに様々な人が様々な立場から考えて、研究してきたもの。受け継がれる味、消えていく味。という、脈々とつづく人と食の歴史に思いを馳せ、一食一食を大切にしたいと思った。
食べたくなる本三浦哲哉料理本批評ってはじめて読んだ。 批評というと、いろんな人の意見や主張をばっさばっさと切り捨てつつ己の論を構築していく、みたいなちょっと上から目線なような印象があったのだが、この本はちがった。 食や料理家に対する尊敬の念を感じるし、王道なものにも常軌を逸したものも素直に受け止めたり、驚いたり、影響されたりしてみせる、筆者の斜に構えてなさというか懐の深さがすごくいいなと思った。 これまでに様々な人が様々な立場から考えて、研究してきたもの。受け継がれる味、消えていく味。という、脈々とつづく人と食の歴史に思いを馳せ、一食一食を大切にしたいと思った。 - 2025年12月16日
 さみしくてごめん永井玲衣ちょっと開いた永井さんは学校の先輩だ。 昔、自分の幼さゆえに迷惑をかけ、「あなたはいろいろな人を失望させました」というメールを受け取ったことがある。それ以来交流はない。 前後の記憶もあいまいなほど過去の出来事だが、人から「失望した」と言われたのは人生でいまのところそれが唯一の体験だ。 その衝撃と申し訳なさと恥辱の気持ちが淡くただたしかに深層に残っており、屈折した罪悪感で永井さんの著作にはなかなか手が伸びなかった。 またそれとは別に、知人がひとかどの者になっていると自分が何者でもないコンプレックスが刺激されるようで微妙な気持ちがあり、距離を置いていたのだが、母に無理やり借りさせられた(?)ため少し読んだ。 世界に対する解像度が高い人なのだなと思う。わたしはそんなに細やかに具に世界を見て面白がったり訝しんだり驚いたりできない。きっとわたしだけでなく多くの人ができないから、彼女はひとかどの者になったのだろう。これを感性と呼ぶのだろうか? 永井さんはたしか学生の頃からブログを書いていて、それがとにかく面白かった。そのユニークな着眼や発想は、所与のものもあるだろうが、昔から積み重ねてきた言葉にして出力するという行為が、洗練されていま実を成しているということなのだろう。 それを素直に、すごいと思い、また何者でもない自分にいたたまれなくなって、本を閉じた。
さみしくてごめん永井玲衣ちょっと開いた永井さんは学校の先輩だ。 昔、自分の幼さゆえに迷惑をかけ、「あなたはいろいろな人を失望させました」というメールを受け取ったことがある。それ以来交流はない。 前後の記憶もあいまいなほど過去の出来事だが、人から「失望した」と言われたのは人生でいまのところそれが唯一の体験だ。 その衝撃と申し訳なさと恥辱の気持ちが淡くただたしかに深層に残っており、屈折した罪悪感で永井さんの著作にはなかなか手が伸びなかった。 またそれとは別に、知人がひとかどの者になっていると自分が何者でもないコンプレックスが刺激されるようで微妙な気持ちがあり、距離を置いていたのだが、母に無理やり借りさせられた(?)ため少し読んだ。 世界に対する解像度が高い人なのだなと思う。わたしはそんなに細やかに具に世界を見て面白がったり訝しんだり驚いたりできない。きっとわたしだけでなく多くの人ができないから、彼女はひとかどの者になったのだろう。これを感性と呼ぶのだろうか? 永井さんはたしか学生の頃からブログを書いていて、それがとにかく面白かった。そのユニークな着眼や発想は、所与のものもあるだろうが、昔から積み重ねてきた言葉にして出力するという行為が、洗練されていま実を成しているということなのだろう。 それを素直に、すごいと思い、また何者でもない自分にいたたまれなくなって、本を閉じた。 - 2025年12月15日
 虚空へ谷川俊太郎先日、祖母を見送った。 言葉にできない気持ちでいっぱいで、驚きなのか、哀しみなのか、喪失感なのか。心の準備はできていたからか、思ったより穏やかに受け止められているなと思う時もあれば、不意に涙が流れる瞬間もある。 人が旅立つ瞬間を共にするのは初めてで、あまりにも生と死が地続きで、その境の曖昧さを思い頭がぼうっとしてしまう。こんな時だからこそ思索できることがあるはずだと思い、自分にしては珍しく詩集に手を取った。 十四行の言葉少なな詩。普段好んで読んでいる学術書たちとは対照的なひろい余白。それなのに情報がひろがっていく。まるで森の中でゆっくりと深呼吸をしているかのような、言葉を通して自分の心の内奥に思いを馳せられるような探究の時間。こういう時のために、人には詩が必要なんだなあと思った。 今読んでよかった。今じゃなきゃ読めなかった。
虚空へ谷川俊太郎先日、祖母を見送った。 言葉にできない気持ちでいっぱいで、驚きなのか、哀しみなのか、喪失感なのか。心の準備はできていたからか、思ったより穏やかに受け止められているなと思う時もあれば、不意に涙が流れる瞬間もある。 人が旅立つ瞬間を共にするのは初めてで、あまりにも生と死が地続きで、その境の曖昧さを思い頭がぼうっとしてしまう。こんな時だからこそ思索できることがあるはずだと思い、自分にしては珍しく詩集に手を取った。 十四行の言葉少なな詩。普段好んで読んでいる学術書たちとは対照的なひろい余白。それなのに情報がひろがっていく。まるで森の中でゆっくりと深呼吸をしているかのような、言葉を通して自分の心の内奥に思いを馳せられるような探究の時間。こういう時のために、人には詩が必要なんだなあと思った。 今読んでよかった。今じゃなきゃ読めなかった。 - 2025年12月14日
 男女賃金格差の経済学大湾秀雄タイトル的に硬派な学術書なのかなという印象を受けており、経済学の門外漢である自分が読めるのか?と思いつつ読み始めたが、とても明晰な文体で驚くほどすいすいと読み進めることができた。 日本における男女の賃金格差の実態とその解決策について、経済学の視点から統計を用いて定量的なデータで解明している。学生の頃、経済学ってモデルを示すだけで実際とは全然違うじゃん!とひねくれていたが、モデル化によって複雑な事象が明確になり理解しやすくなるのだなあと今さらながら実感した。統計ってすごいぜ。 ゲーム理論で考えると、企業が男女を公平に扱い、家庭でも家事を男女平等に分担するともっとも効率的なナッシュ均衡が実現する。にも関わらず、日本の男女賃金格差はOECD諸国の中だとワースト2位である。それを招く原因とはなにか?最たるものはジェンダーバイアスである。「女性はすぐに仕事を辞めるので育成にリソースを割かなくて良い」「女性に大変な仕事をさせるとよくないので手堅い仕事を回そう」などと統計的差別や代表性バイアスからくる意識的・無意識的な女性に対する差別的な扱いにより、女性はキャリアアップをすることが困難な状況になっている。 仮に成長意欲が高い女性がいたとしても、差別的な処遇を受ける状況下では、成長の限界を感じて結果的に辞めてしまう。このときバイアスが自己成就的であるという。 また長時間労働をすることで評価される長時間プライムも、出産や育児を担う女性にとってネガティブに作用する。 差別の解消には、まず組織における格差の実態を明らかにすることが必要だ。単純な平均賃金の男女比較では実態と乖離することがあるので、回帰分析を用いて、経験や子供の有無が同じ属性の男女で比較する必要がある。組織内での格差を可視化できたら、是正するための取り組みを。女性対象の育成研修を行ったり、管理職に引き上げようとする取り組みと同時に、労働スタイルの柔軟性の確保により、育児と両立しやすい働き方を実現することが必要だ。 そして改善されたかどうかの証明のために、KPIに基づく自己点検が必要となる。というのが大筋だった。 非常に冷静かつ建設的な提言だと感じたし、チャイルドペナルティやマミートラックが自分ごとであるいち女性としては、ぜひこの施策の実現に期待したいと感じた。読んでよかった一冊!
男女賃金格差の経済学大湾秀雄タイトル的に硬派な学術書なのかなという印象を受けており、経済学の門外漢である自分が読めるのか?と思いつつ読み始めたが、とても明晰な文体で驚くほどすいすいと読み進めることができた。 日本における男女の賃金格差の実態とその解決策について、経済学の視点から統計を用いて定量的なデータで解明している。学生の頃、経済学ってモデルを示すだけで実際とは全然違うじゃん!とひねくれていたが、モデル化によって複雑な事象が明確になり理解しやすくなるのだなあと今さらながら実感した。統計ってすごいぜ。 ゲーム理論で考えると、企業が男女を公平に扱い、家庭でも家事を男女平等に分担するともっとも効率的なナッシュ均衡が実現する。にも関わらず、日本の男女賃金格差はOECD諸国の中だとワースト2位である。それを招く原因とはなにか?最たるものはジェンダーバイアスである。「女性はすぐに仕事を辞めるので育成にリソースを割かなくて良い」「女性に大変な仕事をさせるとよくないので手堅い仕事を回そう」などと統計的差別や代表性バイアスからくる意識的・無意識的な女性に対する差別的な扱いにより、女性はキャリアアップをすることが困難な状況になっている。 仮に成長意欲が高い女性がいたとしても、差別的な処遇を受ける状況下では、成長の限界を感じて結果的に辞めてしまう。このときバイアスが自己成就的であるという。 また長時間労働をすることで評価される長時間プライムも、出産や育児を担う女性にとってネガティブに作用する。 差別の解消には、まず組織における格差の実態を明らかにすることが必要だ。単純な平均賃金の男女比較では実態と乖離することがあるので、回帰分析を用いて、経験や子供の有無が同じ属性の男女で比較する必要がある。組織内での格差を可視化できたら、是正するための取り組みを。女性対象の育成研修を行ったり、管理職に引き上げようとする取り組みと同時に、労働スタイルの柔軟性の確保により、育児と両立しやすい働き方を実現することが必要だ。 そして改善されたかどうかの証明のために、KPIに基づく自己点検が必要となる。というのが大筋だった。 非常に冷静かつ建設的な提言だと感じたし、チャイルドペナルティやマミートラックが自分ごとであるいち女性としては、ぜひこの施策の実現に期待したいと感じた。読んでよかった一冊! - 2025年12月9日
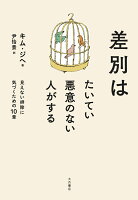 差別はたいてい悪意のない人がするキム・ジヘ,尹怡景読みながら、自分も差別の対象にされているかもしれないという憤りと、自分も差別をしているかもしれないという焦りを行き来する、緊張感のある一冊だった。 「差別」という言葉を聞くと、なんとなく自分とは縁遠いことに感じてしまいがちだった。日本に暮らしていると、自分が明確に差別されているという経験をすることはあまりないので、「白人からの黒人への差別」というような海外の事例をイメージしていたからだ。 しかし本書を読んでいると、差別はもっと身近なところにあり、多層的かつ複雑な構造をしているがゆえに、社会に浸透して取り除くことは難しいものだということに気づく。 作中の例に挙げられていたもので印象的だったのは、韓国内で女性は男性に差別されているけれど、韓国に流れ着いたイエメン難民に対して、韓国の女性は犯罪を恐れる、滞在を拒否するといった特権を行使することができるという例だった。 人間は単純な二分法ではわけられず、たとえば黒人の異性愛者でイスラム教だったら?白人の同性愛者でトランスジェンダーだったら?と様々な立場があり、文脈によって差別する側にも、被差別者にもなりうる。 そして差別の構造は再生産される。自分が被差別者の立場に置かれると、特権的待遇を受けられないがゆえに、差別している側に比肩するほどの能力を身につけることが難しく、「被差別者は劣っているのだ」というレッテルを強化してしまう。 差別をめぐる現代のさまざまな言説にも言及している。女性の登用率を増やすことは、男性に対する差別なのか?どんな人にも、他人を嫌う自由がある?デモによって公共機関に影響を与えるのは迷惑?など、身の回りで聞いたことがあるようなモヤっとする問題についても、差別論の研究者の視点から明晰な捉え方を示唆してくれる。 差別をしないように努力しようで終わりではなくて、差別撤廃法の制定が必要であるるという、制度による解決策を提案しているところも現実的でよかった。
差別はたいてい悪意のない人がするキム・ジヘ,尹怡景読みながら、自分も差別の対象にされているかもしれないという憤りと、自分も差別をしているかもしれないという焦りを行き来する、緊張感のある一冊だった。 「差別」という言葉を聞くと、なんとなく自分とは縁遠いことに感じてしまいがちだった。日本に暮らしていると、自分が明確に差別されているという経験をすることはあまりないので、「白人からの黒人への差別」というような海外の事例をイメージしていたからだ。 しかし本書を読んでいると、差別はもっと身近なところにあり、多層的かつ複雑な構造をしているがゆえに、社会に浸透して取り除くことは難しいものだということに気づく。 作中の例に挙げられていたもので印象的だったのは、韓国内で女性は男性に差別されているけれど、韓国に流れ着いたイエメン難民に対して、韓国の女性は犯罪を恐れる、滞在を拒否するといった特権を行使することができるという例だった。 人間は単純な二分法ではわけられず、たとえば黒人の異性愛者でイスラム教だったら?白人の同性愛者でトランスジェンダーだったら?と様々な立場があり、文脈によって差別する側にも、被差別者にもなりうる。 そして差別の構造は再生産される。自分が被差別者の立場に置かれると、特権的待遇を受けられないがゆえに、差別している側に比肩するほどの能力を身につけることが難しく、「被差別者は劣っているのだ」というレッテルを強化してしまう。 差別をめぐる現代のさまざまな言説にも言及している。女性の登用率を増やすことは、男性に対する差別なのか?どんな人にも、他人を嫌う自由がある?デモによって公共機関に影響を与えるのは迷惑?など、身の回りで聞いたことがあるようなモヤっとする問題についても、差別論の研究者の視点から明晰な捉え方を示唆してくれる。 差別をしないように努力しようで終わりではなくて、差別撤廃法の制定が必要であるるという、制度による解決策を提案しているところも現実的でよかった。 - 2025年12月5日
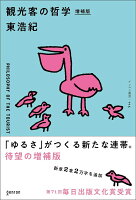 観光客の哲学 増補版東浩紀「訂正可能性の哲学」と同様、わからないのに面白くぐいぐい読み進められる読書体験だった。 内容は難解で、理解できたとは言えないのでメタ的な感想しか出てこないのだが、氏の物事を構造的に捉え、ある事象の本質を異質なもののアナロジーとすることで解釈を多様に深化させていく、卓越した思考力と独創性に舌を巻くばかり。 今度こそはしっかり理解しようと1行1行気合を入れて読んでいても、その自在な発想力と広範な知識からくる仔細な記述にあっという間にふり落とされてしまう。でも、ほんの少しキーワードくらいは頭に残せたのでよかったと思う。 本書の主な主張は、AかBか、右派か左派か、ナショナリズムかグローバリズムかといった二極化した価値観がはびこる世界において、「AでありながらBでもある」というようないずれかに属しない自由なオルタナティブの提案である。そのコミュニティのウチでもソトでもなく、ただ無責任に楽しんで去っていく観光客のような在り方を肯定することで、世界をより高解像度で捉えられる、ということだろうか? 政治的には対立しながら経済的には関係性を続けていたり、反体制を謳いながら愛国心を持つというような、一見相反する価値観は共存するのだと気づくと、自分のミクロな社会生活に置き換えても葛藤が解消されて少し楽に生きられるかもという気持ちにはなった。
観光客の哲学 増補版東浩紀「訂正可能性の哲学」と同様、わからないのに面白くぐいぐい読み進められる読書体験だった。 内容は難解で、理解できたとは言えないのでメタ的な感想しか出てこないのだが、氏の物事を構造的に捉え、ある事象の本質を異質なもののアナロジーとすることで解釈を多様に深化させていく、卓越した思考力と独創性に舌を巻くばかり。 今度こそはしっかり理解しようと1行1行気合を入れて読んでいても、その自在な発想力と広範な知識からくる仔細な記述にあっという間にふり落とされてしまう。でも、ほんの少しキーワードくらいは頭に残せたのでよかったと思う。 本書の主な主張は、AかBか、右派か左派か、ナショナリズムかグローバリズムかといった二極化した価値観がはびこる世界において、「AでありながらBでもある」というようないずれかに属しない自由なオルタナティブの提案である。そのコミュニティのウチでもソトでもなく、ただ無責任に楽しんで去っていく観光客のような在り方を肯定することで、世界をより高解像度で捉えられる、ということだろうか? 政治的には対立しながら経済的には関係性を続けていたり、反体制を謳いながら愛国心を持つというような、一見相反する価値観は共存するのだと気づくと、自分のミクロな社会生活に置き換えても葛藤が解消されて少し楽に生きられるかもという気持ちにはなった。
読み込み中...

