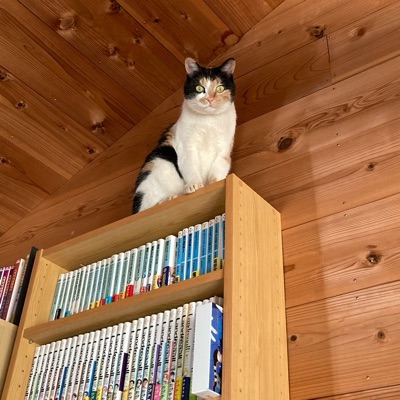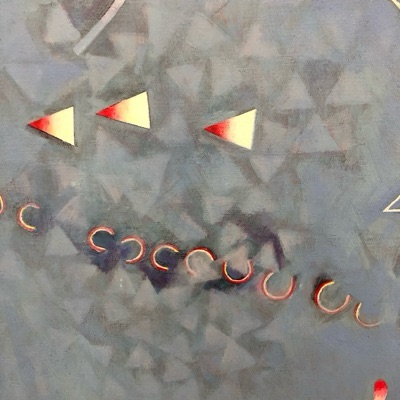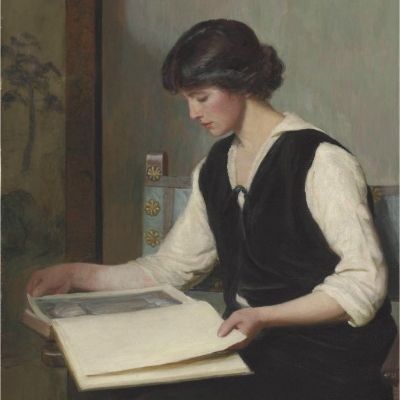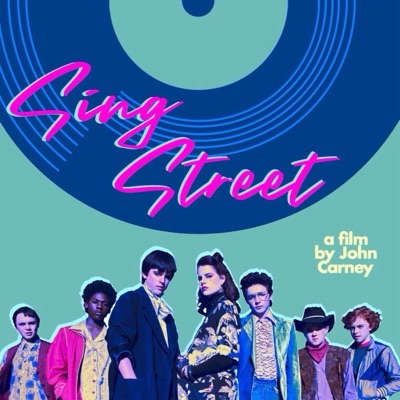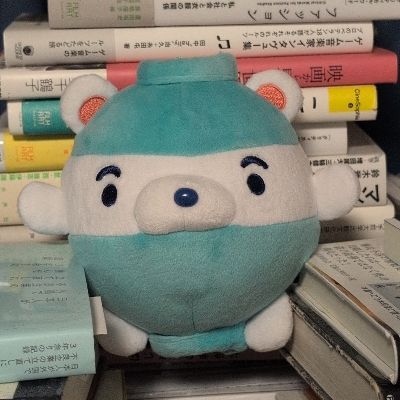無数の言語、無数の世界

60件の記録
 ほげっこー@hoagecko2025年12月13日読みたい言語は話者の環境を反映する。 となれば、言語と認知はどこまで違うのか。 このテーマ・疑問は私も以前から気になっていたところだ。 わかりやすい例でいうと、食べ物となる動植物の部位については地域の環境によってそれを指す言葉の密度は様々だ。 そのような違いを語ると謳うのが本書だ。これは読みたい。
ほげっこー@hoagecko2025年12月13日読みたい言語は話者の環境を反映する。 となれば、言語と認知はどこまで違うのか。 このテーマ・疑問は私も以前から気になっていたところだ。 わかりやすい例でいうと、食べ物となる動植物の部位については地域の環境によってそれを指す言葉の密度は様々だ。 そのような違いを語ると謳うのが本書だ。これは読みたい。
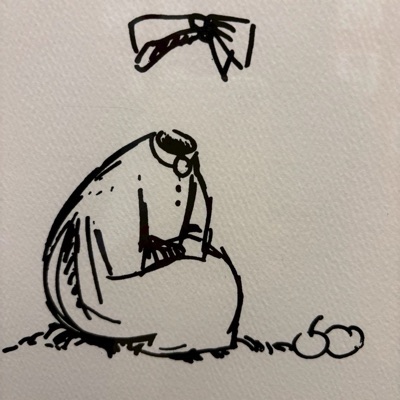
 花蝶@hana-choh2025年12月13日気になる読みたい当たり前のように周りに存在する物、時間、匂いなど形に表せないような物を言語学者の方々が表現している一冊だと感じました。 読むと物の見方が変わりそうです。 世界観の視野が広がり楽しくなりそうです。 私にとってすごく興味深い作品です。
花蝶@hana-choh2025年12月13日気になる読みたい当たり前のように周りに存在する物、時間、匂いなど形に表せないような物を言語学者の方々が表現している一冊だと感じました。 読むと物の見方が変わりそうです。 世界観の視野が広がり楽しくなりそうです。 私にとってすごく興味深い作品です。




 jaguchi@jaguchi872025年12月9日買ったその日の本の購入予算を完全にオーバーしていたけど、勢いで買ってしまった。でも読みたかった本だからいいよね。 ※追記 「買った」タグをつけて投稿したら自分の「気になる」欄から消えててびっくりした。そんな賢い機能があるなんて。
jaguchi@jaguchi872025年12月9日買ったその日の本の購入予算を完全にオーバーしていたけど、勢いで買ってしまった。でも読みたかった本だからいいよね。 ※追記 「買った」タグをつけて投稿したら自分の「気になる」欄から消えててびっくりした。そんな賢い機能があるなんて。

 jaguchi@jaguchi872025年11月25日読みたいとても気になっている本。「ピダハン」のダニエル・エヴェレットの息子さんなんだね。「ピダハン」も気になりつつまだ手にできていない。どちらを先に買おうかな。
jaguchi@jaguchi872025年11月25日読みたいとても気になっている本。「ピダハン」のダニエル・エヴェレットの息子さんなんだね。「ピダハン」も気になりつつまだ手にできていない。どちらを先に買おうかな。


 ふるえ@furu_furu2025年11月4日読んでる時間を言葉で捉えるためには人間の認知機能として空間と結びつける必要があるのではないか、みたいに読んでいたら、どこかの言語では空間と時間に関係がないと今の所見られる表現しているらしくて、振り出しに戻った感がある。けれど、それは言語によって概念の捉え方が違うことでもあって、言葉(や文化)によって自分がとらえる世界はある程度依存しているのかもしれないなと思って、電車を出る。
ふるえ@furu_furu2025年11月4日読んでる時間を言葉で捉えるためには人間の認知機能として空間と結びつける必要があるのではないか、みたいに読んでいたら、どこかの言語では空間と時間に関係がないと今の所見られる表現しているらしくて、振り出しに戻った感がある。けれど、それは言語によって概念の捉え方が違うことでもあって、言葉(や文化)によって自分がとらえる世界はある程度依存しているのかもしれないなと思って、電車を出る。

 saeko@saekyh2025年11月2日さまざまな言語の社会・文化的背景について紹介してくれるエッセイ的な本かと思って読んでみたら、さまざまな研究の事例が紹介されるわりと硬派な学術書で、読むのがちょっと大変だった! でも言語は社会と紐づいて発展するという認知言語学の考え方に基づいて、いろいろな事例が紹介されていて興味深かった。 章ごとのテーマが時間・空間・色などの身近なものだったり、冒頭で紹介される筆者の経験談(マンハッタンの街角で眺めた雪や、飛行機から見えるマイアミの海の色をどんな言葉で表したらいいだろう?など)が美しくてよかった。 「言語はそれを話す人々の生き方や世界の感じ方と密接に結びついており、言語が失われるということはそうしたオルタナティブな経験の可能性が失われるということでもある。」
saeko@saekyh2025年11月2日さまざまな言語の社会・文化的背景について紹介してくれるエッセイ的な本かと思って読んでみたら、さまざまな研究の事例が紹介されるわりと硬派な学術書で、読むのがちょっと大変だった! でも言語は社会と紐づいて発展するという認知言語学の考え方に基づいて、いろいろな事例が紹介されていて興味深かった。 章ごとのテーマが時間・空間・色などの身近なものだったり、冒頭で紹介される筆者の経験談(マンハッタンの街角で眺めた雪や、飛行機から見えるマイアミの海の色をどんな言葉で表したらいいだろう?など)が美しくてよかった。 「言語はそれを話す人々の生き方や世界の感じ方と密接に結びついており、言語が失われるということはそうしたオルタナティブな経験の可能性が失われるということでもある。」

 ふるえ@furu_furu2025年10月29日ふと思い出した仕事帰りの電車の中で開こうと思ったけれど眠たくて読めそうにないので諦めて、でもこれまで読んできた内容を思い出す。遠くの、聞いたこともない言語の人たちが表現する詩や、音楽や、絵とかを見てみたいと思う。自分たちとは違う表現方法を持って世界を知覚している人たちの作品はどういうものになるのか気になる。
ふるえ@furu_furu2025年10月29日ふと思い出した仕事帰りの電車の中で開こうと思ったけれど眠たくて読めそうにないので諦めて、でもこれまで読んできた内容を思い出す。遠くの、聞いたこともない言語の人たちが表現する詩や、音楽や、絵とかを見てみたいと思う。自分たちとは違う表現方法を持って世界を知覚している人たちの作品はどういうものになるのか気になる。



 ふるえ@furu_furu2025年10月28日読んでる未来は前方、過去は後方だったり、左から右に流れるとか、そういう時間に対する空間の認識が言語体系によって異なる。過去は前方にある(過ぎ去ったものなので見えるという考え方なのだろうか)、未来は上方向に、過去は下方向にあるといったように、どのような環境で暮らすかによって異なる感覚を持つようになるのかもしれない。 めちゃくちゃ面白く読み進めて、でも全然ページが進んでいなくてまだまだ読めるなとなり嬉しくなる。
ふるえ@furu_furu2025年10月28日読んでる未来は前方、過去は後方だったり、左から右に流れるとか、そういう時間に対する空間の認識が言語体系によって異なる。過去は前方にある(過ぎ去ったものなので見えるという考え方なのだろうか)、未来は上方向に、過去は下方向にあるといったように、どのような環境で暮らすかによって異なる感覚を持つようになるのかもしれない。 めちゃくちゃ面白く読み進めて、でも全然ページが進んでいなくてまだまだ読めるなとなり嬉しくなる。


 ふるえ@furu_furu2025年10月27日読んでる言葉が認識したものを表現するものだとするなら、言語によって認知しているものが異なっているのか気になる。 読み進めながら、よくこういう言語みたいなものが定着しているなと思う。
ふるえ@furu_furu2025年10月27日読んでる言葉が認識したものを表現するものだとするなら、言語によって認知しているものが異なっているのか気になる。 読み進めながら、よくこういう言語みたいなものが定着しているなと思う。


 ふるえ@furu_furu2025年10月25日買った@ 有隣堂 グラングリーン大阪店タイトルと紹介文に惹かれて買う。 家まで待てずに帰りの電車の中で読んで、「はじめに」の段階でもう面白い。言葉は認知科学としても確かに考えられるよなと思って、目の前にあるもの、今いる環境をどう知覚するのかによって言語が変わっていくというのはとても面白い。地球と全く同じ自然環境の星があったとして、同じような、あるいは似たような言語が生まれたりするんだろうか。これから読み進めるのが楽しみ。
ふるえ@furu_furu2025年10月25日買った@ 有隣堂 グラングリーン大阪店タイトルと紹介文に惹かれて買う。 家まで待てずに帰りの電車の中で読んで、「はじめに」の段階でもう面白い。言葉は認知科学としても確かに考えられるよなと思って、目の前にあるもの、今いる環境をどう知覚するのかによって言語が変わっていくというのはとても面白い。地球と全く同じ自然環境の星があったとして、同じような、あるいは似たような言語が生まれたりするんだろうか。これから読み進めるのが楽しみ。
 はるのひ@harunohinouta2025年10月10日気になる読みたい見かけた面白そう。 高校生の時に初めて読んだ言語学の本は鈴木孝夫さんの「日本語と外国語」。言葉は世界を認識する手段であると同時にその認識結果の証拠でもある、ということを日本語と外国語(の文化)における認識の違いを比較しながら考察されていて、世界の見え方が広がるような読書体験で本当に面白かった。 「日本語と外国語」では西欧語との比較だけだったから、それよりさらに広い範囲の言語に触れられていそうな本書でどんなことが語られているのか読んでみたい。
はるのひ@harunohinouta2025年10月10日気になる読みたい見かけた面白そう。 高校生の時に初めて読んだ言語学の本は鈴木孝夫さんの「日本語と外国語」。言葉は世界を認識する手段であると同時にその認識結果の証拠でもある、ということを日本語と外国語(の文化)における認識の違いを比較しながら考察されていて、世界の見え方が広がるような読書体験で本当に面白かった。 「日本語と外国語」では西欧語との比較だけだったから、それよりさらに広い範囲の言語に触れられていそうな本書でどんなことが語られているのか読んでみたい。