

紫嶋
@09sjm
読書備忘録
文芸から新書から学術書まで、幅広く読みます
- 2026年2月24日
 女二人のニューギニア有吉佐和子借りてきた読み始めた
女二人のニューギニア有吉佐和子借りてきた読み始めた - 2026年2月22日
 皇后の碧阿部智里借りてきた読み始めた
皇后の碧阿部智里借りてきた読み始めた - 2026年2月21日
 借りてきた読み終わった「ゆる民俗学ラジオ」にて紹介されていたのを聴き、内容に非常に興味が湧いたため読んでみた。 ダム建設により閉村した山村「三面村」における人々の暮らしを、フィールドワークとして実際に現地に住み込んだ著者がまとめあげた記録。 単なる表面的、物理的な調査に留まらず、村人との交流を通して山で暮らす人々の世界観や精神性にまで深く踏み込んだ内容となっている。 三面に限らず、かつて日本の各地に存在したであろう山での暮らしのあり方、日本人と山(自然)との向き合い方をそこから透かし見ることができる気がした。 調査研究の記録というと堅苦しいイメージもあるが、この本は良い意味でどこかエッセイのようでもあり、四季に移ろう山の情景の描写や、村民の方言混じりの素直な言葉からは、文学的な味わいすら感じられる。 それらを記録に留めようとした著者の感性の豊かさのなせる技か。それとも、そうした情緒に訴えかけるものを、山は強く放っているのかもしれない。 また、この本は山の暮らしの記録であると同時に、「ダム開発により失われることが確定した村の最後の記録」でもある。 失われたのは三面村という地図上の名前だけでなく、そこで暮らしてきた人々の何百年にもわたる営みや文化、知恵、技術、精神でもあるのだと、この本を通してその重みを思い知らされた。 一度失われれば二度と取り戻すことはできないもの。時代の流れとはいえ、失われたものはあまりに大きすぎるように思う。 本書の終盤、閉村を受けて村人が語った言葉が、胸に刺さった。
借りてきた読み終わった「ゆる民俗学ラジオ」にて紹介されていたのを聴き、内容に非常に興味が湧いたため読んでみた。 ダム建設により閉村した山村「三面村」における人々の暮らしを、フィールドワークとして実際に現地に住み込んだ著者がまとめあげた記録。 単なる表面的、物理的な調査に留まらず、村人との交流を通して山で暮らす人々の世界観や精神性にまで深く踏み込んだ内容となっている。 三面に限らず、かつて日本の各地に存在したであろう山での暮らしのあり方、日本人と山(自然)との向き合い方をそこから透かし見ることができる気がした。 調査研究の記録というと堅苦しいイメージもあるが、この本は良い意味でどこかエッセイのようでもあり、四季に移ろう山の情景の描写や、村民の方言混じりの素直な言葉からは、文学的な味わいすら感じられる。 それらを記録に留めようとした著者の感性の豊かさのなせる技か。それとも、そうした情緒に訴えかけるものを、山は強く放っているのかもしれない。 また、この本は山の暮らしの記録であると同時に、「ダム開発により失われることが確定した村の最後の記録」でもある。 失われたのは三面村という地図上の名前だけでなく、そこで暮らしてきた人々の何百年にもわたる営みや文化、知恵、技術、精神でもあるのだと、この本を通してその重みを思い知らされた。 一度失われれば二度と取り戻すことはできないもの。時代の流れとはいえ、失われたものはあまりに大きすぎるように思う。 本書の終盤、閉村を受けて村人が語った言葉が、胸に刺さった。 - 2026年2月20日
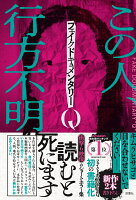 フェイクドキュメンタリーQフェイクドキュメンタリーQ借りてきた読み終わったYouTubeでフェイクドキュメンタリー(モキュメンタリー)ホラーの動画を投稿している『Q』の書籍版。動画の方をよく観ていたため、本の方も読んでみた。 書籍の方もフェイクドキュメンタリーのテイストを崩しておらず、なおかつ主軸はあくまで動画であるというスタンスなので、すでに動画を見知っている人も、書籍で初めて知ったという人も、どちらも楽しめるのではないかと思う。 また書籍版には「動画の投稿後、新たに判明した情報」や「視聴者から寄せられた情報」という形で追記が多数掲載されているので、動画と併せて読む価値ありかと思う。 このチャンネルに限らず、フェイクドキュメンタリーホラーというジャンルもすっかり定着した今日この頃だが、出来に関しては玉石混交ではあると思う。 フェイクであるという前提を大きく言い放ちながらもチープにならず、観る者が思わずゾッとしてしまう、人間の本能的な恐怖を刺激するような良質なホラーが、これからも生み出されることに期待したい。
フェイクドキュメンタリーQフェイクドキュメンタリーQ借りてきた読み終わったYouTubeでフェイクドキュメンタリー(モキュメンタリー)ホラーの動画を投稿している『Q』の書籍版。動画の方をよく観ていたため、本の方も読んでみた。 書籍の方もフェイクドキュメンタリーのテイストを崩しておらず、なおかつ主軸はあくまで動画であるというスタンスなので、すでに動画を見知っている人も、書籍で初めて知ったという人も、どちらも楽しめるのではないかと思う。 また書籍版には「動画の投稿後、新たに判明した情報」や「視聴者から寄せられた情報」という形で追記が多数掲載されているので、動画と併せて読む価値ありかと思う。 このチャンネルに限らず、フェイクドキュメンタリーホラーというジャンルもすっかり定着した今日この頃だが、出来に関しては玉石混交ではあると思う。 フェイクであるという前提を大きく言い放ちながらもチープにならず、観る者が思わずゾッとしてしまう、人間の本能的な恐怖を刺激するような良質なホラーが、これからも生み出されることに期待したい。 - 2026年2月11日
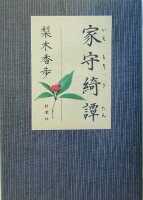 家守綺譚梨木香歩借りてきた読み終わった時は明治時代、冴えない文筆家として細々と暮らす青年を主人公に、彼が暮らす家や庭、近隣の土地を舞台として綴られる静かな物語。お利口で可愛い犬もいる。 各話、ひそやかにクローズアップされる植物があり、その描写に四季の移ろいの鮮やかさや風情をしみじみと感じさせられる。花の色、光の温度、風の香り、水の音…それらにじっと意識を傾ける時間を現代人はほとんど忘れかけているが、この本の中には未だそうした時間がゆっくりと流れている。 また「綺譚」の名の通り、主人公の日々の傍らでは、不可思議な出来事や人外的存在がちらりちらりと見え隠れしているが、それらも不思議と当たり前の、自然なこととして見えてくる。 ひとつには、わざとらしくない絶妙な塩梅でそれらを書き表す筆者の巧さがあるだろう。そしてまた、明治時代という設定や、妖しい物事を現実の延長で捉えて疑わない作中の人々の姿勢が、読者までもを呑み込んで「この時代ならあったかもしれないな」なんて気分にさせられる。 日常と隣り合わせに描かれる幻想が温かく、美しく、大変お気に入りの一冊になった。 なお、作中に「先年、エルトゥールル号遭難事件があった」という記述があるため、この物語は1890年以降の設定であることがわかる。 また、様々に登場する地名や地形などから、主人公が暮らすのは現在の京都市山科区であることも見えてくる。 この小説もまた、一味違った「京都小説」なのである。 琵琶湖や湖から疏水の存在も重要な役割を果たす本作、実在する土地に想いを馳せながら読むのもまた一興だろう。
家守綺譚梨木香歩借りてきた読み終わった時は明治時代、冴えない文筆家として細々と暮らす青年を主人公に、彼が暮らす家や庭、近隣の土地を舞台として綴られる静かな物語。お利口で可愛い犬もいる。 各話、ひそやかにクローズアップされる植物があり、その描写に四季の移ろいの鮮やかさや風情をしみじみと感じさせられる。花の色、光の温度、風の香り、水の音…それらにじっと意識を傾ける時間を現代人はほとんど忘れかけているが、この本の中には未だそうした時間がゆっくりと流れている。 また「綺譚」の名の通り、主人公の日々の傍らでは、不可思議な出来事や人外的存在がちらりちらりと見え隠れしているが、それらも不思議と当たり前の、自然なこととして見えてくる。 ひとつには、わざとらしくない絶妙な塩梅でそれらを書き表す筆者の巧さがあるだろう。そしてまた、明治時代という設定や、妖しい物事を現実の延長で捉えて疑わない作中の人々の姿勢が、読者までもを呑み込んで「この時代ならあったかもしれないな」なんて気分にさせられる。 日常と隣り合わせに描かれる幻想が温かく、美しく、大変お気に入りの一冊になった。 なお、作中に「先年、エルトゥールル号遭難事件があった」という記述があるため、この物語は1890年以降の設定であることがわかる。 また、様々に登場する地名や地形などから、主人公が暮らすのは現在の京都市山科区であることも見えてくる。 この小説もまた、一味違った「京都小説」なのである。 琵琶湖や湖から疏水の存在も重要な役割を果たす本作、実在する土地に想いを馳せながら読むのもまた一興だろう。 - 2026年2月6日
 山に生きる人びと宮本常一借りてきた読み始めた
山に生きる人びと宮本常一借りてきた読み始めた - 2026年2月5日
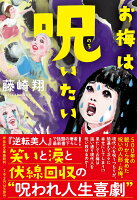 お梅は呪いたい藤崎翔借りてきた読み終わった「塞翁が馬」「禍を転じて福となす」という言葉があるが、この小説の物語もまさにその通り。呪いの人形・お梅の悪意と害意によるアクションが、巡り巡って周囲の人間をどんどんと幸せにしてしまう、笑いあり感動ありのドタバタヒューマンコメディ……といったところだろうか。 何がどう転んでいくのか、毎話ピタゴラスイッチに似たワクワク感がある。各話ごと独立しながらも、前の話に登場した人物が別の話にも関わってくるなど、クスリとできる仕掛けもある。 人形のお梅自身は決して改心することはなく、どこまでも純度100パーセントの悪意で、呪いの人形としての本懐を遂げようと努力(?)しているのが良い。結果的に人間を幸せにしてしまい、毎回ひとり悔しそうにしているところに愛嬌も感じてしまう。これからもお梅にはどこまでも邪悪な呪い人形でいてもらいたい笑 作中には時事ネタや作者のメタ的なツッコミなどもあり、それをユーモラスと捉えるかサムいと捉えるかは少々人によって分かれるところか。良くも悪くも、今この時代にリアルタイムで楽しむ用のエンタメ小説だろう。
お梅は呪いたい藤崎翔借りてきた読み終わった「塞翁が馬」「禍を転じて福となす」という言葉があるが、この小説の物語もまさにその通り。呪いの人形・お梅の悪意と害意によるアクションが、巡り巡って周囲の人間をどんどんと幸せにしてしまう、笑いあり感動ありのドタバタヒューマンコメディ……といったところだろうか。 何がどう転んでいくのか、毎話ピタゴラスイッチに似たワクワク感がある。各話ごと独立しながらも、前の話に登場した人物が別の話にも関わってくるなど、クスリとできる仕掛けもある。 人形のお梅自身は決して改心することはなく、どこまでも純度100パーセントの悪意で、呪いの人形としての本懐を遂げようと努力(?)しているのが良い。結果的に人間を幸せにしてしまい、毎回ひとり悔しそうにしているところに愛嬌も感じてしまう。これからもお梅にはどこまでも邪悪な呪い人形でいてもらいたい笑 作中には時事ネタや作者のメタ的なツッコミなどもあり、それをユーモラスと捉えるかサムいと捉えるかは少々人によって分かれるところか。良くも悪くも、今この時代にリアルタイムで楽しむ用のエンタメ小説だろう。 - 2026年2月1日
 観応の擾乱亀田俊和借りてきた読み終わった室町幕府黎明期、足利尊氏と直義の兄弟同士が争った内紛「観応の擾乱」について、そのきっかけ、経緯、経過、顛末までを細かく解説した、非常に読み応えのある新書。 短い期間で優劣が劇的に入れ替わり、勢力の分布や敵味方の構成も絶えず変動する内乱が、わかりやすくまとめられている。 日本史に疎く、武将の名前もろくに覚えられないような私でも混乱することなく、むしろ歴史の面白さに引き込まれて、手に汗握るような気持ちで読み切れたことに感謝である。 また、擾乱期の戦のみならず、並行して幕府で誰がどのような政治を行なっていたかについても書かれているため、結果として室町幕府の初期の頃の組織や政治のあり方についても理解が深まった。 表面的には兄弟の争いとされる「観応の擾乱」だが、詳細を追えば追うほど、社会情勢や取り巻きらの思惑が複雑に絡み合う状況が見えてきて、兄弟当人らは本当はどうしたかったのだろうか……と一抹のやるせなさが残る。 結果的に勝者となったのは兄の足利尊氏だが、彼が「何をしたのか」は伝わっていても、「何を考えていたのか」は明確には見えてこない。歴史とはそういうものだというのを差し引いても、尊氏という人物はどうにもわかりにくいな、と感じる。 彼に焦点を当てた学術書などを、もう少し読んでみたいという気持ちになった。 本書は「観応の擾乱」について知りたいという方には大変おすすめできる一冊だが、一方で足利兄弟、とりわけ尊氏をどのように評価するかについては、少々筆者の私情というか、尊氏に肩入れする形での感情論・精神論的記載がわずかに入り混じっている点には注意が必要と思う。 もっとも、そもそもの前提として足利尊氏を朝廷(天皇)に対する逆賊とみなしたり、室町幕府を低く評価したりするような風潮が戦前戦中に生まれていることもあり、それに対する反論の意もこもっているのだろう。
観応の擾乱亀田俊和借りてきた読み終わった室町幕府黎明期、足利尊氏と直義の兄弟同士が争った内紛「観応の擾乱」について、そのきっかけ、経緯、経過、顛末までを細かく解説した、非常に読み応えのある新書。 短い期間で優劣が劇的に入れ替わり、勢力の分布や敵味方の構成も絶えず変動する内乱が、わかりやすくまとめられている。 日本史に疎く、武将の名前もろくに覚えられないような私でも混乱することなく、むしろ歴史の面白さに引き込まれて、手に汗握るような気持ちで読み切れたことに感謝である。 また、擾乱期の戦のみならず、並行して幕府で誰がどのような政治を行なっていたかについても書かれているため、結果として室町幕府の初期の頃の組織や政治のあり方についても理解が深まった。 表面的には兄弟の争いとされる「観応の擾乱」だが、詳細を追えば追うほど、社会情勢や取り巻きらの思惑が複雑に絡み合う状況が見えてきて、兄弟当人らは本当はどうしたかったのだろうか……と一抹のやるせなさが残る。 結果的に勝者となったのは兄の足利尊氏だが、彼が「何をしたのか」は伝わっていても、「何を考えていたのか」は明確には見えてこない。歴史とはそういうものだというのを差し引いても、尊氏という人物はどうにもわかりにくいな、と感じる。 彼に焦点を当てた学術書などを、もう少し読んでみたいという気持ちになった。 本書は「観応の擾乱」について知りたいという方には大変おすすめできる一冊だが、一方で足利兄弟、とりわけ尊氏をどのように評価するかについては、少々筆者の私情というか、尊氏に肩入れする形での感情論・精神論的記載がわずかに入り混じっている点には注意が必要と思う。 もっとも、そもそもの前提として足利尊氏を朝廷(天皇)に対する逆賊とみなしたり、室町幕府を低く評価したりするような風潮が戦前戦中に生まれていることもあり、それに対する反論の意もこもっているのだろう。 - 2026年1月22日
 潰える 最恐の書き下ろしアンソロジー一穂ミチ,原浩,小野不由美,澤村伊智,鈴木光司,阿泉来堂借りてきた読み始めた以前読んだ同シリーズのアンソロジー『堕ちる』よりも、全体的にホラーとしても小説としても質の高い一冊だと感じた(私個人の好みの問題もあるだろうが)。 平成のホラーに親しんできた身としては、かの伝説的な作品『リング』に連なる物語を、作者の裏話的なテイストの小説として読めたことは、懐かしさも相まってニヤリとしてしまう嬉しさがあった。 また小野不由美先生の短編は、実質「営繕かるかや」シリーズのひとつである。あのシリーズが好きな人は、この話だけでもぜひ読んで欲しい。 全体を読んでいると、現代のホラーにおいては「お化けが怖い」というだけでは足りない(あるいはお化け自体はもはやオマケでしかない)のだろうなと感じる。 それよりも、今まで信じていた常識や日常が、一気に崩れて反転するその概念的な現象こそが「怖い」とされているのではないか。 狂人と思っていた人物こそが真実を知るキーパーソンで、逆に信頼できると思っていた人物が実はとうに狂ってしまっていたり。 あるいは自分は正常なつもりでいても、周りからは壊れているとみなされて相手にされず孤立したり。 そういう認識のズレが、最大瞬間風速的に起こる展開に、今の人々は恐怖を抱くのかもしれない。 (創作物としては、そういうどんでん返しオチばかり続くと少し飽きてしまうのが難点ではあるが……)
潰える 最恐の書き下ろしアンソロジー一穂ミチ,原浩,小野不由美,澤村伊智,鈴木光司,阿泉来堂借りてきた読み始めた以前読んだ同シリーズのアンソロジー『堕ちる』よりも、全体的にホラーとしても小説としても質の高い一冊だと感じた(私個人の好みの問題もあるだろうが)。 平成のホラーに親しんできた身としては、かの伝説的な作品『リング』に連なる物語を、作者の裏話的なテイストの小説として読めたことは、懐かしさも相まってニヤリとしてしまう嬉しさがあった。 また小野不由美先生の短編は、実質「営繕かるかや」シリーズのひとつである。あのシリーズが好きな人は、この話だけでもぜひ読んで欲しい。 全体を読んでいると、現代のホラーにおいては「お化けが怖い」というだけでは足りない(あるいはお化け自体はもはやオマケでしかない)のだろうなと感じる。 それよりも、今まで信じていた常識や日常が、一気に崩れて反転するその概念的な現象こそが「怖い」とされているのではないか。 狂人と思っていた人物こそが真実を知るキーパーソンで、逆に信頼できると思っていた人物が実はとうに狂ってしまっていたり。 あるいは自分は正常なつもりでいても、周りからは壊れているとみなされて相手にされず孤立したり。 そういう認識のズレが、最大瞬間風速的に起こる展開に、今の人々は恐怖を抱くのかもしれない。 (創作物としては、そういうどんでん返しオチばかり続くと少し飽きてしまうのが難点ではあるが……) - 2026年1月5日
 借りてきた読み終わった一言で言うならば、非常に評価に悩む本である。 この本は、イギリスの書誌学者ウィリアム・ブレイズによる『書物の敵』を、庄司氏が日本語訳した上で適宜加除補正したものとなる。 1880年に初版が出版されたブレイズの『書物の敵』を、50年後の1930年という極めて早い段階で訳し、日本国内で読める形にしたという点は評価に値する。 それから長らく、日本語で読める『書物の敵』といえば庄司氏のこの本のみであったという点も、一定の価値と認めることはできよう。 しかし、上記の通りこの本は純粋な和訳ではなく、「適宜加除補正」がなされているという点に注意が必要である。 そしてまた、この「適宜加除補正」の仕方がとにかく酷い。 ブレイズが書いた元の文章の和訳が続いていたかと思うと、シームレスに庄司氏の主観混じりの補足や主張が挟み込まれたり、ブレイズが記した文章を端折り、代わりに日本における事例を書き加えたりと、やりたい放題だ。 そのせいで、一体どこからどこまでが真にブレイズが記した『書物の敵』の内容なのか、一見しただけでは分からなくなってしまっている。 加除補正を行なった理由として庄司氏は、50年の歳月が経過して現状からズレが生じていたり不足があったりすることを挙げているが、せめて純粋な和訳を載せた後、各章末に補足として私見なり自論なりを載せればよかったのに……と思わずにいられない。 こうした、ともすれば編者の驕りともとれる改変のせいで、結果としてこの本自体の価値も薄れてしまっている。 幸いなことに、現代では八坂書房から出版された完全かつ純粋な日本語訳の『書物の敵』が存在している。 ブレイズの『書物の敵』に興味を持った人は、ぜひそちらをお読みいただきたい。
借りてきた読み終わった一言で言うならば、非常に評価に悩む本である。 この本は、イギリスの書誌学者ウィリアム・ブレイズによる『書物の敵』を、庄司氏が日本語訳した上で適宜加除補正したものとなる。 1880年に初版が出版されたブレイズの『書物の敵』を、50年後の1930年という極めて早い段階で訳し、日本国内で読める形にしたという点は評価に値する。 それから長らく、日本語で読める『書物の敵』といえば庄司氏のこの本のみであったという点も、一定の価値と認めることはできよう。 しかし、上記の通りこの本は純粋な和訳ではなく、「適宜加除補正」がなされているという点に注意が必要である。 そしてまた、この「適宜加除補正」の仕方がとにかく酷い。 ブレイズが書いた元の文章の和訳が続いていたかと思うと、シームレスに庄司氏の主観混じりの補足や主張が挟み込まれたり、ブレイズが記した文章を端折り、代わりに日本における事例を書き加えたりと、やりたい放題だ。 そのせいで、一体どこからどこまでが真にブレイズが記した『書物の敵』の内容なのか、一見しただけでは分からなくなってしまっている。 加除補正を行なった理由として庄司氏は、50年の歳月が経過して現状からズレが生じていたり不足があったりすることを挙げているが、せめて純粋な和訳を載せた後、各章末に補足として私見なり自論なりを載せればよかったのに……と思わずにいられない。 こうした、ともすれば編者の驕りともとれる改変のせいで、結果としてこの本自体の価値も薄れてしまっている。 幸いなことに、現代では八坂書房から出版された完全かつ純粋な日本語訳の『書物の敵』が存在している。 ブレイズの『書物の敵』に興味を持った人は、ぜひそちらをお読みいただきたい。 - 2026年1月3日
 書物の敵ウィリアム・ブレイズ,William Blades,高宮利行,高橋勇借りてきた読み終わった元となるのは19世紀イギリスの書誌学者、ウィリアム・ブレイズが啓蒙も兼ねて記した書。その完全かつ純粋な日本語訳は、この本が初めてかつ唯一となる。 「書誌学」という学問の存在を、私はこの本を読むと同時に初めて知った。物(ガワ)としての書物の有り様や取り扱われ方を研究分析する学問…というところだろうか。古の巻物や羊皮紙に記された写本から、現代の印刷技術で大量生産された本に至るまで、全てが研究対象になり得る。 古い書物であればあるほど、現物が失われていたり不完全であったり、原本がなく不確かな写しやさまざまな記録から情報を集めるしかないことは想像に易い。 この『書物の敵』はタイトル通り、古来から絶えず書物の敵となり続けてきたさまざまな要素を、火や水、埃や虫、人の手による破壊など章ごとにまとめ上げている。 そこには、書誌学に向き合ってきたブレイズ本人の経験や想いも多分に含まれているのだろう。きっと自身の研究を進める中で、抗えない天災で失われた書物を思って悔しさを味わったり、無知や軽率さからくる人災で損なわれた書物を知って憤まんやる方ない思いを抱えたりしたのだろうな…と文章の端々から滲み出る彼の嘆きや怒りから推察される。 21世紀の今においても、火や水は常に書物の敵であり続けているし、ブレイズが本を記した当時と比べれば幾分かマシになっているとはいえ、本を雑に取り扱う人や本の価値を顧みない人によって、今なお書物は損なわれ続けている。 読書家、特に紙の本を好んでいる人がこの『書物の敵』を読んだなら、きっと書かれている内容やブレイズの想いに共感できると思う。 そしてまた、彼の時代にはなかった、現代ならではの書物の敵についても思いを馳せたくなる。読書人口の減少、デジタル化の推進、図書館や大学など文化施設の予算も減らされるこの時代において、紙の書物は果たして適切に守られ残されていくのだろうか。 本文の最後に添えられている、ブレイズの後書き文がまた良い味を出している。ここに込められた「書物愛・読書愛」は、時代を越えて通ずるように思う。
書物の敵ウィリアム・ブレイズ,William Blades,高宮利行,高橋勇借りてきた読み終わった元となるのは19世紀イギリスの書誌学者、ウィリアム・ブレイズが啓蒙も兼ねて記した書。その完全かつ純粋な日本語訳は、この本が初めてかつ唯一となる。 「書誌学」という学問の存在を、私はこの本を読むと同時に初めて知った。物(ガワ)としての書物の有り様や取り扱われ方を研究分析する学問…というところだろうか。古の巻物や羊皮紙に記された写本から、現代の印刷技術で大量生産された本に至るまで、全てが研究対象になり得る。 古い書物であればあるほど、現物が失われていたり不完全であったり、原本がなく不確かな写しやさまざまな記録から情報を集めるしかないことは想像に易い。 この『書物の敵』はタイトル通り、古来から絶えず書物の敵となり続けてきたさまざまな要素を、火や水、埃や虫、人の手による破壊など章ごとにまとめ上げている。 そこには、書誌学に向き合ってきたブレイズ本人の経験や想いも多分に含まれているのだろう。きっと自身の研究を進める中で、抗えない天災で失われた書物を思って悔しさを味わったり、無知や軽率さからくる人災で損なわれた書物を知って憤まんやる方ない思いを抱えたりしたのだろうな…と文章の端々から滲み出る彼の嘆きや怒りから推察される。 21世紀の今においても、火や水は常に書物の敵であり続けているし、ブレイズが本を記した当時と比べれば幾分かマシになっているとはいえ、本を雑に取り扱う人や本の価値を顧みない人によって、今なお書物は損なわれ続けている。 読書家、特に紙の本を好んでいる人がこの『書物の敵』を読んだなら、きっと書かれている内容やブレイズの想いに共感できると思う。 そしてまた、彼の時代にはなかった、現代ならではの書物の敵についても思いを馳せたくなる。読書人口の減少、デジタル化の推進、図書館や大学など文化施設の予算も減らされるこの時代において、紙の書物は果たして適切に守られ残されていくのだろうか。 本文の最後に添えられている、ブレイズの後書き文がまた良い味を出している。ここに込められた「書物愛・読書愛」は、時代を越えて通ずるように思う。 - 2025年12月14日
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広借りてきた読み終わった良いところで上巻が終わっていたので、続きが気になりすぎて読み始めた下巻。最後の最後まで気の抜けない展開にハラハラワクワクしながら読破した。 以降、ネタバレ含むので注意。 前情報なしで読み始めた時に想像していた内容とは良い意味で異なっていた本作。一言で表すならばSFバディ物とでもいう話だった。 そのバディの相手が、人間でも地球産のアンドロイドでもなく、遠い星の異星人であることがとにかく面白く、彼の存在が終始癒しであった。当然言葉も何もかも通じない二人が、意思疎通できるようになっていくまでの流れはかなりの見所だと思う。 また、そんなバディの二人が「共闘」して挑む対象も、宇宙に生息する微生物や、それらがもたらす深刻な環境問題であり、銃火器で戦争をするのとは異なる方向性での深刻で気の抜けない「戦い」の様子から目が離せない。 各々の星や種族の滅亡がかかった重大なミッションでありながらも、どこかユーモラスな空気が漂い続けているのは、彼らが二人とも純粋でひたむきな知的好奇心の持ち主だったからだと思う。 知らないことに対する「知りたい」という気持ちは、相互理解においてもあらゆる進化においても、また問題解決においても極めて重要な鍵になるのかもしれないな…と感じた。 映画化も進行しているとのことで、成功したら良いなと願っている。
プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広借りてきた読み終わった良いところで上巻が終わっていたので、続きが気になりすぎて読み始めた下巻。最後の最後まで気の抜けない展開にハラハラワクワクしながら読破した。 以降、ネタバレ含むので注意。 前情報なしで読み始めた時に想像していた内容とは良い意味で異なっていた本作。一言で表すならばSFバディ物とでもいう話だった。 そのバディの相手が、人間でも地球産のアンドロイドでもなく、遠い星の異星人であることがとにかく面白く、彼の存在が終始癒しであった。当然言葉も何もかも通じない二人が、意思疎通できるようになっていくまでの流れはかなりの見所だと思う。 また、そんなバディの二人が「共闘」して挑む対象も、宇宙に生息する微生物や、それらがもたらす深刻な環境問題であり、銃火器で戦争をするのとは異なる方向性での深刻で気の抜けない「戦い」の様子から目が離せない。 各々の星や種族の滅亡がかかった重大なミッションでありながらも、どこかユーモラスな空気が漂い続けているのは、彼らが二人とも純粋でひたむきな知的好奇心の持ち主だったからだと思う。 知らないことに対する「知りたい」という気持ちは、相互理解においてもあらゆる進化においても、また問題解決においても極めて重要な鍵になるのかもしれないな…と感じた。 映画化も進行しているとのことで、成功したら良いなと願っている。 - 2025年12月4日
 日本怪談集 取り憑く霊種村季弘借りてきた読み終わった動植物や物、人体に関する霊や怪異の物語を集めたアンソロジー。どれもひと時代前に生み出された話なだけあり、古き良き怪談の香りがする。 幽霊そのもののあからさまな恐ろしさよりも、何かが起こるかもしれない、何かがいるかもしれない、あるいはもう裏では何かが起こっているかもという不安を煽る雰囲気ホラーは日本の十八番であり、この本でもそんな元祖ジャパニーズホラー的空気を味わうことができた。 江戸川乱歩の『人間椅子』を怪談扱いすることの是非については要審議だと思うが…今で言う「人怖(ヒトコワ)」のはしりとして捉えればありなのかもしれない笑
日本怪談集 取り憑く霊種村季弘借りてきた読み終わった動植物や物、人体に関する霊や怪異の物語を集めたアンソロジー。どれもひと時代前に生み出された話なだけあり、古き良き怪談の香りがする。 幽霊そのもののあからさまな恐ろしさよりも、何かが起こるかもしれない、何かがいるかもしれない、あるいはもう裏では何かが起こっているかもという不安を煽る雰囲気ホラーは日本の十八番であり、この本でもそんな元祖ジャパニーズホラー的空気を味わうことができた。 江戸川乱歩の『人間椅子』を怪談扱いすることの是非については要審議だと思うが…今で言う「人怖(ヒトコワ)」のはしりとして捉えればありなのかもしれない笑 - 2025年11月10日
- 2025年11月7日
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広借りてきた読み終わった「一切の前情報なく読んで!できれば映画化でネタバレを踏む確率が上がる前に!!」というような声を多く見かけたため、ならば今のうちに…と読み始めた作品。 同様の読書家が沢山いると思うので笑、ここでもネタバレなしの感想に留めておくが、重厚に練り込まれたSFでありつつも、科学や宇宙に疎い人間が読んでもちゃんと「なるほど」と心地よく理解できるよう描写されていて、バランスの取れた苦にならない理系小説といった感じだった。 話の展開上、作品の世界観や主人公の置かれている状況などが見えてくるまでに少し時間がかかるため、それまでは正直じれったさというか…退屈さもあったのだが、話が見えてくると共に面白さのエンジンがかかり始め、200ページあたりからぐっと掴まれる感覚があった。予想外の展開も多々あり、そう来たかと。 気づけばワクワクしながら上巻を読み終えた。 これを書いている現時点ではまだ下巻は読めておらず、ここから先どうなるのー!?とそわそわしているが、引き続きネタバレを踏まないよう気をつけながら、物語を最後まで見届けたいと思う。
プロジェクト・ヘイル・メアリー 上アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広借りてきた読み終わった「一切の前情報なく読んで!できれば映画化でネタバレを踏む確率が上がる前に!!」というような声を多く見かけたため、ならば今のうちに…と読み始めた作品。 同様の読書家が沢山いると思うので笑、ここでもネタバレなしの感想に留めておくが、重厚に練り込まれたSFでありつつも、科学や宇宙に疎い人間が読んでもちゃんと「なるほど」と心地よく理解できるよう描写されていて、バランスの取れた苦にならない理系小説といった感じだった。 話の展開上、作品の世界観や主人公の置かれている状況などが見えてくるまでに少し時間がかかるため、それまでは正直じれったさというか…退屈さもあったのだが、話が見えてくると共に面白さのエンジンがかかり始め、200ページあたりからぐっと掴まれる感覚があった。予想外の展開も多々あり、そう来たかと。 気づけばワクワクしながら上巻を読み終えた。 これを書いている現時点ではまだ下巻は読めておらず、ここから先どうなるのー!?とそわそわしているが、引き続きネタバレを踏まないよう気をつけながら、物語を最後まで見届けたいと思う。 - 2025年11月1日
 都市 江戸に生きる吉田伸之借りてきた読み終わった近世以降、日本最大の都市であった江戸について、城下町やその内訳である町方・寺社・宿場といった空間としての仕組み、そしてそこに暮らす人々の商いや生活の成り立ち方などについて丁寧に論述している新書。 特筆すべきは、筆者自身も強いこだわりを持っている視点…幕府や武家といった支配層の上からの視点ではなく、ある意味では非支配層ともいうべき民衆の側から見た、下からの視点で都市の有り様を分析していることである。それにより、生活空間としての江戸のあり方が、とても生き生きと血の通ったものとして立ち現れてくる。 本文は憶測に頼ることなく、様々な史料や数字を土台に書き上げられている一方で、「おわりに」の章に記された筆者の想いの丈の温かさに心打たれた。一部を引用する。 >江戸を生きた民衆たちは、(中略)けっして「名も無き民衆」ではない。一人ひとりが、権力者や偉人・英雄たちと同じように、生を受けて以来、かけがえのない名前を持ち、その後の人生を歩んだ実在した人びとなのである。 こう考える筆者だからこそ、民衆の視点に立つことを徹底しているのだろうと納得した。
都市 江戸に生きる吉田伸之借りてきた読み終わった近世以降、日本最大の都市であった江戸について、城下町やその内訳である町方・寺社・宿場といった空間としての仕組み、そしてそこに暮らす人々の商いや生活の成り立ち方などについて丁寧に論述している新書。 特筆すべきは、筆者自身も強いこだわりを持っている視点…幕府や武家といった支配層の上からの視点ではなく、ある意味では非支配層ともいうべき民衆の側から見た、下からの視点で都市の有り様を分析していることである。それにより、生活空間としての江戸のあり方が、とても生き生きと血の通ったものとして立ち現れてくる。 本文は憶測に頼ることなく、様々な史料や数字を土台に書き上げられている一方で、「おわりに」の章に記された筆者の想いの丈の温かさに心打たれた。一部を引用する。 >江戸を生きた民衆たちは、(中略)けっして「名も無き民衆」ではない。一人ひとりが、権力者や偉人・英雄たちと同じように、生を受けて以来、かけがえのない名前を持ち、その後の人生を歩んだ実在した人びとなのである。 こう考える筆者だからこそ、民衆の視点に立つことを徹底しているのだろうと納得した。 - 2025年11月1日
 江戸人の教養塩村耕借りてきた読み終わった主に江戸時代に書かれたり読まれたりしていた様々な古書を読み解き、当時の人々の思想や価値観、日常の暮らしの様子などを解説する一冊。 元々が新聞の連載であったこともあり、コラム形式でさっくり読める内容になっている。ちょうど見開きで一項目ずつ、平易かつユーモラスな文調で読みやすい。 古書と一言で表してもその種類は豊富で、学者の手記もあれば一般人の日記や手紙、さらには店の納品書なども含まれる。 いずれも当時の様子を伝える大切な資料であり、(一部は写ししか残っていないものはありつつも)こうして紙と文字による情報が残り続けていることは凄いこと。 江戸時代の識字率や、様々なことを書き残すという習慣、そして出版の隆盛なども大きく影響しているのだと思う。 そう考えると、たとえ当時の人にとっては何気ないメモ書きであったとしても、重みが増すのを感じるのであった。
江戸人の教養塩村耕借りてきた読み終わった主に江戸時代に書かれたり読まれたりしていた様々な古書を読み解き、当時の人々の思想や価値観、日常の暮らしの様子などを解説する一冊。 元々が新聞の連載であったこともあり、コラム形式でさっくり読める内容になっている。ちょうど見開きで一項目ずつ、平易かつユーモラスな文調で読みやすい。 古書と一言で表してもその種類は豊富で、学者の手記もあれば一般人の日記や手紙、さらには店の納品書なども含まれる。 いずれも当時の様子を伝える大切な資料であり、(一部は写ししか残っていないものはありつつも)こうして紙と文字による情報が残り続けていることは凄いこと。 江戸時代の識字率や、様々なことを書き残すという習慣、そして出版の隆盛なども大きく影響しているのだと思う。 そう考えると、たとえ当時の人にとっては何気ないメモ書きであったとしても、重みが増すのを感じるのであった。 - 2025年10月24日
 読み終わった買った先日山陰地方を経由して旅行する機会があり、ならばその道中に読もうと選んだのがこの一冊だった。 尾崎翠は明治生まれ、鳥取県出身の女性作家。若くして文才を開花させ、さまざまな作品を残している。残念ながら、自身の体調などの事情で次第に執筆量は減り、晩年は再び筆をとることなかったが、一部からは高く評価された作家である。 そんな彼女の内なる思考や世界観、理想とした文学の精神性のカケラたちが、作品の隅々にまで散りばめられている。 作風はどこかふわふわと漂うようで、内省的で、時にシュールでもある印象を受けた。文体については明治大正という時代性もあるだろうが、それを差し引いても詩的で掴みどころがなく、少し難解さも含んでいる。 例えるなら、薄暗い屋根裏で一人詩作に耽るような雰囲気。輪郭が曖昧な朧月や、空気の潤んだ朝靄のような……そういった明度や彩度、湿度を持った作品群だった。 決して暗鬱としているわけではないが、溌剌さには少し欠けた、表面上は物静かだが頭の中では絶えず騒がしいくらいに思考を巡らせているタイプの。 実際、そんな人物が彼女の作品には数多登場する。特にそういった、少し考えすぎて風変わりであったり繊細さを秘めているような少女が登場する時、それはもしかすると筆者自身がモデルになっているのではないかと思う。 同様に、作品にたびたび漂う湿度ある空気や、晴空より曇り空が似合いそうな情景も、筆者が生まれ育った鳥取の自然・天候の影響があるのかもしれない。 代表作である『第七官界彷徨』は確かに恋愛の哲学めいていて、登場人物のキャラも濃く面白かった。 個人的にはそのほか『歩行』『花束』『無風帯から』あたりが好き。 唯一、この本に関しての難点を挙げるならば、巻末に筆者の年譜がある一方で、作品の掲載順は発表順にはなっていない。 そのため作風の変遷や文章の精神性の深まりを追おうとするには少し不向きであることが、個人的には残念だった。
読み終わった買った先日山陰地方を経由して旅行する機会があり、ならばその道中に読もうと選んだのがこの一冊だった。 尾崎翠は明治生まれ、鳥取県出身の女性作家。若くして文才を開花させ、さまざまな作品を残している。残念ながら、自身の体調などの事情で次第に執筆量は減り、晩年は再び筆をとることなかったが、一部からは高く評価された作家である。 そんな彼女の内なる思考や世界観、理想とした文学の精神性のカケラたちが、作品の隅々にまで散りばめられている。 作風はどこかふわふわと漂うようで、内省的で、時にシュールでもある印象を受けた。文体については明治大正という時代性もあるだろうが、それを差し引いても詩的で掴みどころがなく、少し難解さも含んでいる。 例えるなら、薄暗い屋根裏で一人詩作に耽るような雰囲気。輪郭が曖昧な朧月や、空気の潤んだ朝靄のような……そういった明度や彩度、湿度を持った作品群だった。 決して暗鬱としているわけではないが、溌剌さには少し欠けた、表面上は物静かだが頭の中では絶えず騒がしいくらいに思考を巡らせているタイプの。 実際、そんな人物が彼女の作品には数多登場する。特にそういった、少し考えすぎて風変わりであったり繊細さを秘めているような少女が登場する時、それはもしかすると筆者自身がモデルになっているのではないかと思う。 同様に、作品にたびたび漂う湿度ある空気や、晴空より曇り空が似合いそうな情景も、筆者が生まれ育った鳥取の自然・天候の影響があるのかもしれない。 代表作である『第七官界彷徨』は確かに恋愛の哲学めいていて、登場人物のキャラも濃く面白かった。 個人的にはそのほか『歩行』『花束』『無風帯から』あたりが好き。 唯一、この本に関しての難点を挙げるならば、巻末に筆者の年譜がある一方で、作品の掲載順は発表順にはなっていない。 そのため作風の変遷や文章の精神性の深まりを追おうとするには少し不向きであることが、個人的には残念だった。 - 2025年9月26日
 キッチン常夜灯(1)長月天音読み終わった買った働くということから逃れられない現代人は、時に忙しさや疲労から日々の食事をおざなりにしがちだが、温かく美味しい食事で自らを労ることは、何よりの生活の基盤であるということを思い出させてくれる小説だった。 作中では、ままならない人間関係や仕事の悩み、大切な人との別れなど、人生におけるシビアな局面も沢山描かれている。だからこそ、真心を込めた美味しい料理でもてなしてくれるシェフたちの存在や、眠れぬ夜や孤独な心の居場所となってくれる店のありがたさがじんわりと胸に沁みてくる。 登場する料理はどれも実に美味しそうで、けれどその描写に終始したグルメ小説ではない点も良かった。あくまでメインは、料理を食べる人・作る人たちであって、そうした人々の温かく時に不器用な交流を描いたヒューマンドラマである。 仕事から帰ってきた夜、眠る前にベッドで一話ずつ読み進めたくなるような…そんな一冊だった。ただし、お腹が空くことは必須なのでご注意を!
キッチン常夜灯(1)長月天音読み終わった買った働くということから逃れられない現代人は、時に忙しさや疲労から日々の食事をおざなりにしがちだが、温かく美味しい食事で自らを労ることは、何よりの生活の基盤であるということを思い出させてくれる小説だった。 作中では、ままならない人間関係や仕事の悩み、大切な人との別れなど、人生におけるシビアな局面も沢山描かれている。だからこそ、真心を込めた美味しい料理でもてなしてくれるシェフたちの存在や、眠れぬ夜や孤独な心の居場所となってくれる店のありがたさがじんわりと胸に沁みてくる。 登場する料理はどれも実に美味しそうで、けれどその描写に終始したグルメ小説ではない点も良かった。あくまでメインは、料理を食べる人・作る人たちであって、そうした人々の温かく時に不器用な交流を描いたヒューマンドラマである。 仕事から帰ってきた夜、眠る前にベッドで一話ずつ読み進めたくなるような…そんな一冊だった。ただし、お腹が空くことは必須なのでご注意を! - 2025年9月13日
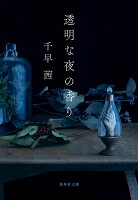 透明な夜の香り千早茜借りてきた読み終わったテーマとなる「香り」というものが持つパワー、魅力、奥深さを120%活かし尽くした物語だったと思う。 嗜好品としての香水やアロマに限定することなく、また調香師のお仕事系小説にとどまることなく、人間の人生・記憶・生活に否応なしに(良くも悪くも)寄り添い染み付く「香り」を主軸に展開していく物語は、とても読み応えがあった。 料理や生活用品に活用される健全で実用的な香りから、事件や嘘と結びつく後ろ向きな香りまで、作中ではさまざまな香りの描写が登場し、その都度文字の向こう側に漂う香りを想像という嗅覚で感じ取ろうと意識が働く。そんな読書体験もなかなかないため新鮮だった。 思えば香りとは、単にそれ自体のにおいというだけでなく、そこから連想される何かや個人の記憶にも深く結びついていて、その情報量は侮れないのだなと気付かされる。 登場人物たちのキャラ付けのバランスも非常に良かった。誰もが未熟と達観を抱えながら、自分の過去や感情と向き合っていると感じられる。ありがちな恋愛展開にもならず、この物語の彼らだからこその関係性にゆったりと着地したような読後感が心地よかった。
透明な夜の香り千早茜借りてきた読み終わったテーマとなる「香り」というものが持つパワー、魅力、奥深さを120%活かし尽くした物語だったと思う。 嗜好品としての香水やアロマに限定することなく、また調香師のお仕事系小説にとどまることなく、人間の人生・記憶・生活に否応なしに(良くも悪くも)寄り添い染み付く「香り」を主軸に展開していく物語は、とても読み応えがあった。 料理や生活用品に活用される健全で実用的な香りから、事件や嘘と結びつく後ろ向きな香りまで、作中ではさまざまな香りの描写が登場し、その都度文字の向こう側に漂う香りを想像という嗅覚で感じ取ろうと意識が働く。そんな読書体験もなかなかないため新鮮だった。 思えば香りとは、単にそれ自体のにおいというだけでなく、そこから連想される何かや個人の記憶にも深く結びついていて、その情報量は侮れないのだなと気付かされる。 登場人物たちのキャラ付けのバランスも非常に良かった。誰もが未熟と達観を抱えながら、自分の過去や感情と向き合っていると感じられる。ありがちな恋愛展開にもならず、この物語の彼らだからこその関係性にゆったりと着地したような読後感が心地よかった。
読み込み中...
