
blue-red
@blue-red
お金と本棚が無いときは、所持している本を読み直してやり過ごしてます(´・ω・`) → 本棚ふやしたのでしばらくは安心して新しい本買える(*´ω`*)
- 2026年2月6日
 ポトスライムの舟津村記久子読み終わった単行本芥川賞純文学って、「特別な何者かにならなければならない」という現代人にかけられた呪いへのアンチテーゼなんだな。その手の刺激を含意しない形で、しかし妙に人を惹きつける、そんな物語をつむぐ実践的な試みなんだな。 芥川賞受賞作を最近かたっぱしから読んでて感じつつあったのだけど、本作「ポトスライムの舟」はそれを確信させるすばらしい完成度でした。
ポトスライムの舟津村記久子読み終わった単行本芥川賞純文学って、「特別な何者かにならなければならない」という現代人にかけられた呪いへのアンチテーゼなんだな。その手の刺激を含意しない形で、しかし妙に人を惹きつける、そんな物語をつむぐ実践的な試みなんだな。 芥川賞受賞作を最近かたっぱしから読んでて感じつつあったのだけど、本作「ポトスライムの舟」はそれを確信させるすばらしい完成度でした。 - 2026年1月23日
 トラジェクトリーグレゴリー・ケズナジャット読み終わった単行本ダイスケが言う。「グローバルマインド」を持って「グローバルに活躍していく日本人」をサポートするのが英会話学校の任務だと。しかし、ブランドンのように大きな決心や特別な訓練もなく勧誘に乗って他国から移り住み、その日その日を変わり映えなく働く英会話学校の講師は、その「グローバル」的なるものをもう実現してしまっているのではないか? ちょっとした需要とビザなどの政策・制度がうまくかみ合えば、国を跨いだ働き方も意外とあっさり実現してしまう。 もっとも、その生活は、テッシュ配りをしたり、面倒な生徒の相手したり、同僚と愚痴ったり、とても地味だ。巷で喧伝される「グローバル」は、キラキラしてスタイリッシュでワクワクに満ちた何かを我々にイメージさせるが、それとは程遠い。けれども、こっちこそが実地で、世の中の「グローバル」の大多数はこんな感じだ。 人付き合いも、同僚や昔の友人と飲みに行ったり、母国の家族とオンライン通話したりするぐらい。「グローバル」という言葉が連想させる煌びやかな広がりはない。仲間である同僚とは二軒目まで飲みあかすが、面倒くさい生徒のカワムラさんとは二軒目には行かない。そこに他意はない。普通のことだ。 けれども、思いもよらず軌道はニアミスし、興味も無かったアポロ計画の詳細に付き合わされたり、文化的・地理的・年代的に生まれも育ちも異なるおじさんの人生の一片を深く知ることもある。「グローバル」が虚栄を超えて意味を持つならば、そんなニアミスにあるのだと思う
トラジェクトリーグレゴリー・ケズナジャット読み終わった単行本ダイスケが言う。「グローバルマインド」を持って「グローバルに活躍していく日本人」をサポートするのが英会話学校の任務だと。しかし、ブランドンのように大きな決心や特別な訓練もなく勧誘に乗って他国から移り住み、その日その日を変わり映えなく働く英会話学校の講師は、その「グローバル」的なるものをもう実現してしまっているのではないか? ちょっとした需要とビザなどの政策・制度がうまくかみ合えば、国を跨いだ働き方も意外とあっさり実現してしまう。 もっとも、その生活は、テッシュ配りをしたり、面倒な生徒の相手したり、同僚と愚痴ったり、とても地味だ。巷で喧伝される「グローバル」は、キラキラしてスタイリッシュでワクワクに満ちた何かを我々にイメージさせるが、それとは程遠い。けれども、こっちこそが実地で、世の中の「グローバル」の大多数はこんな感じだ。 人付き合いも、同僚や昔の友人と飲みに行ったり、母国の家族とオンライン通話したりするぐらい。「グローバル」という言葉が連想させる煌びやかな広がりはない。仲間である同僚とは二軒目まで飲みあかすが、面倒くさい生徒のカワムラさんとは二軒目には行かない。そこに他意はない。普通のことだ。 けれども、思いもよらず軌道はニアミスし、興味も無かったアポロ計画の詳細に付き合わされたり、文化的・地理的・年代的に生まれも育ちも異なるおじさんの人生の一片を深く知ることもある。「グローバル」が虚栄を超えて意味を持つならば、そんなニアミスにあるのだと思う - 2026年1月11日
 推し、燃ゆ宇佐見りん読み終わった単行本芥川賞読書後、どうにもずっとモヤモヤしていた。小説の推し活(主人公の推しに抱く気持ち)の描写は素晴らしい。とても瑞々しく、主人公の背景もあってか神聖性すらを帯びている。 しかし、何でこんなに主人公にいくつもの苦境や苦痛を与えるんだ? 納得できない。少し読み直してみたが、やはり読んでてつらい。 いや、小説の設定に「何でこうなんだ!? 納得できない! おかしい!」とか言っている奴のほうがおかしいことくらいオレにも分かっている。設定が現実的ではないとか言いたいわけではない。「こんな状況ありえないよ」なんて言う気はない。むしろ逆だ。 もはや何故納得できないのか、自分でもよくわかなくなってきた。ただ一つ言いたいのは、受診してついたという「ふたつほど(の)診断名」を描き切って欲しかった。せめて、主人公に与えられる苦境や苦痛の主原因に、名前ぐらい与えて欲しかった。
推し、燃ゆ宇佐見りん読み終わった単行本芥川賞読書後、どうにもずっとモヤモヤしていた。小説の推し活(主人公の推しに抱く気持ち)の描写は素晴らしい。とても瑞々しく、主人公の背景もあってか神聖性すらを帯びている。 しかし、何でこんなに主人公にいくつもの苦境や苦痛を与えるんだ? 納得できない。少し読み直してみたが、やはり読んでてつらい。 いや、小説の設定に「何でこうなんだ!? 納得できない! おかしい!」とか言っている奴のほうがおかしいことくらいオレにも分かっている。設定が現実的ではないとか言いたいわけではない。「こんな状況ありえないよ」なんて言う気はない。むしろ逆だ。 もはや何故納得できないのか、自分でもよくわかなくなってきた。ただ一つ言いたいのは、受診してついたという「ふたつほど(の)診断名」を描き切って欲しかった。せめて、主人公に与えられる苦境や苦痛の主原因に、名前ぐらい与えて欲しかった。 - 2025年12月20日
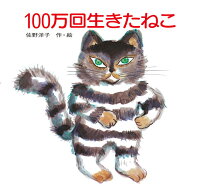 100万回生きたねこ佐野洋子再読した絵本とらねこの物語は、人の人生そのものだな。 悪い人・良い人・普通の人のさまざまな親元へ、選べることなく生まれ落ち、寵愛を受けるがその有り難みなんか知ったこっちゃなく、いつしか親元から離れ、独りとなり、他者と出会い、他者との付き合い方を知り、他者を愛することを覚え、愛する人と死別し、そしていつか自分も死に、この世から去る。 自分の人生が始まってしまったら、好きでも嫌いでも、もうリセットボタンはない。固有の一つの生をまっとうする必要がある。逆説的に、固有の生を引き受けないうちは100万回でも生まれ直したつもりになれる。物語はそんな寓話かもしれない。
100万回生きたねこ佐野洋子再読した絵本とらねこの物語は、人の人生そのものだな。 悪い人・良い人・普通の人のさまざまな親元へ、選べることなく生まれ落ち、寵愛を受けるがその有り難みなんか知ったこっちゃなく、いつしか親元から離れ、独りとなり、他者と出会い、他者との付き合い方を知り、他者を愛することを覚え、愛する人と死別し、そしていつか自分も死に、この世から去る。 自分の人生が始まってしまったら、好きでも嫌いでも、もうリセットボタンはない。固有の一つの生をまっとうする必要がある。逆説的に、固有の生を引き受けないうちは100万回でも生まれ直したつもりになれる。物語はそんな寓話かもしれない。 - 2025年12月14日
 土の中の子供中村文則読み終わった単行本芥川賞主人公が物を落とし始めたときは「あーあヤバい小説に当たってしまった」と思ったが、なるほどそのような生まれと育ちの背景があるのか。 全体を通し、癖になる暗さに満ちている。暗い森を深く奥へ進んでいくような。ページをめくる動機は、単なる怖いもの見たさなのか、その奥で人の心の捉えきれない豊かさを見れる予感がするせいか。 むろん後者は幻想で、著者・中村文則の圧倒的な心理描写のせいで熱に当てられただけだ。あるのは、決してロマンチックなものではなく、単なる破滅願望と強迫観念と憤怒と生存本能の支離滅裂な混濁だ。突発的な感情のうねりだ。よくある話だ。心理カウンセリングにでも行ってスマートに解決しよう。たとえ主人公の身の上や出来事を遠い世界のように感じられたとしても、誰もこれとは無縁ではいられない。埋めたつもりでも土の中から何度も滲み出てくるのだから。
土の中の子供中村文則読み終わった単行本芥川賞主人公が物を落とし始めたときは「あーあヤバい小説に当たってしまった」と思ったが、なるほどそのような生まれと育ちの背景があるのか。 全体を通し、癖になる暗さに満ちている。暗い森を深く奥へ進んでいくような。ページをめくる動機は、単なる怖いもの見たさなのか、その奥で人の心の捉えきれない豊かさを見れる予感がするせいか。 むろん後者は幻想で、著者・中村文則の圧倒的な心理描写のせいで熱に当てられただけだ。あるのは、決してロマンチックなものではなく、単なる破滅願望と強迫観念と憤怒と生存本能の支離滅裂な混濁だ。突発的な感情のうねりだ。よくある話だ。心理カウンセリングにでも行ってスマートに解決しよう。たとえ主人公の身の上や出来事を遠い世界のように感じられたとしても、誰もこれとは無縁ではいられない。埋めたつもりでも土の中から何度も滲み出てくるのだから。 - 2025年12月12日
 コマネチのためにすんみ,チョ・ナムジュ読み終わった表紙のイラストが素晴らしいのだが、日本版オリジナルなのだろうか。キラキラしたベタベタした「可愛らしさ」や「女の子」から離れた等身大のそれを表象しているようだ。 物語もまた、等身大の女の子の成長を描いている。いや、等身大というには、劣悪な環境や失敗が少々多めかもしれない。けれども、根本的な部分で、コマニや家族に悲壮感は感じられない。どうにも自分には、この絶妙な淡々とした前向きさのようなものが、この小説の魅力のように思える。 小説の序説や著者のあとがきにて、これ以上ないほど的確にこの小説の要旨はまとまっている。著者チョ・ナムジュは「失敗のあとを生き続ける人々の物語」だという。本編中には、“大人になるということは、失敗したあとの人生を生き続けるということなのかもしれない”という金言もある。 あえてこれに蛇足を付け加えるならば、「失敗」するためには、小さなことでもいいので自分なりの「挑戦」や「冒険」を行う必要があるということを言っておこう。コマネチのようにオリンピックに出ることも金メダルを取ることもなかったとしても、あれだけ熱中し、色々あって小学4年生で離れた体操競技も、まあ悪くはないよね。
コマネチのためにすんみ,チョ・ナムジュ読み終わった表紙のイラストが素晴らしいのだが、日本版オリジナルなのだろうか。キラキラしたベタベタした「可愛らしさ」や「女の子」から離れた等身大のそれを表象しているようだ。 物語もまた、等身大の女の子の成長を描いている。いや、等身大というには、劣悪な環境や失敗が少々多めかもしれない。けれども、根本的な部分で、コマニや家族に悲壮感は感じられない。どうにも自分には、この絶妙な淡々とした前向きさのようなものが、この小説の魅力のように思える。 小説の序説や著者のあとがきにて、これ以上ないほど的確にこの小説の要旨はまとまっている。著者チョ・ナムジュは「失敗のあとを生き続ける人々の物語」だという。本編中には、“大人になるということは、失敗したあとの人生を生き続けるということなのかもしれない”という金言もある。 あえてこれに蛇足を付け加えるならば、「失敗」するためには、小さなことでもいいので自分なりの「挑戦」や「冒険」を行う必要があるということを言っておこう。コマネチのようにオリンピックに出ることも金メダルを取ることもなかったとしても、あれだけ熱中し、色々あって小学4年生で離れた体操競技も、まあ悪くはないよね。 - 2025年11月30日
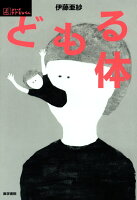 どもる体伊藤亜紗ケアをひらく読み終わった職場に吃音の人がいるので理解を深めるために読む。だからといって別に自分が特別な何かができるわけではないけどね!! できることはないかもしれんが、すべきでないことはあるのでそれを心得ておこう。人文・当事者研究編
どもる体伊藤亜紗ケアをひらく読み終わった職場に吃音の人がいるので理解を深めるために読む。だからといって別に自分が特別な何かができるわけではないけどね!! できることはないかもしれんが、すべきでないことはあるのでそれを心得ておこう。人文・当事者研究編 - 2025年11月30日
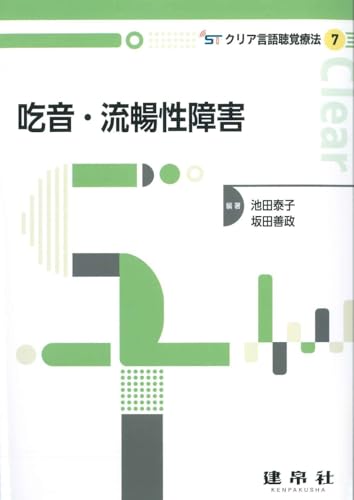 吃音・流暢性障害坂田善政,池田泰子読み終わった職場に吃音の人がいるので理解を深めるために読む。だからといって別に自分が特別な何かができるわけではないけどね!! できることはないかもしれんが、すべきでないことはあるのでそれを心得ておこう。臨床・教科書編
吃音・流暢性障害坂田善政,池田泰子読み終わった職場に吃音の人がいるので理解を深めるために読む。だからといって別に自分が特別な何かができるわけではないけどね!! できることはないかもしれんが、すべきでないことはあるのでそれを心得ておこう。臨床・教科書編 - 2025年11月16日
 それがやさしさじゃ困る植本一子,鳥羽和久読み終わった子どもが「つくる」ことについて触れた収録論文が特に良かった。 確かに自分も、幼少・小学ぐらいまでショボいけれども何か作ってやろうとしていたが、思春期ぐらいから作ること・出来たものを正に「気恥ずかしく」なっていき、純粋に作れなくなった。 けれども、年を取り、「つくる」ことに向き合っている。一周して昔の自分に再会したようだ。
それがやさしさじゃ困る植本一子,鳥羽和久読み終わった子どもが「つくる」ことについて触れた収録論文が特に良かった。 確かに自分も、幼少・小学ぐらいまでショボいけれども何か作ってやろうとしていたが、思春期ぐらいから作ること・出来たものを正に「気恥ずかしく」なっていき、純粋に作れなくなった。 けれども、年を取り、「つくる」ことに向き合っている。一周して昔の自分に再会したようだ。 - 2025年11月9日
 工場日記シモーヌ・ヴェイユ,佐藤紀子,冨原眞弓読み終わった工場に縁ある人間なので、シモーヌ・ヴェイユの思想も著作も解説書も読んだことないが興味わいて手に取ってみた。 読んでいてまず驚いたのは、一年弱の短い期間なのにかなり色んな機械工作作業を行なっていることだった。ヴェイユが携わるのは機械部品製作で、使用する工作機械や行われる作業は、大型プレス機、小型プレス機、フライス盤、歪取り、リベット打ち、穴あけ、溶鉱炉、焼なまし、型抜き、ねじ切りなどなど。製作する部品は絶縁材、座金、缶、コンデンサ用箔、圧着端子、シャント、ネジ、受け座などなど。1日当たりの製作数は数百から二、三千。しかも日によって製作部品がコロコロ変わる。人文的には興味持たれない部分なんだろうけど、当時のディープな機械系工場模様に唸らされる。 さらに、支払い金額や仕損じといったさらなるディテール、職場の人物たちとのやり取りや印象などなど。日記の後半はそれらに基づく思索が増えていく。「何でも見てやろう」ならぬ「何でも記録してやろう」「何でも思索の糧にしてやろう」という気迫がすごい。 本書の紹介文を覗くと、過酷な日々に心身が消耗していく悲壮な記録として紹介されるのが一般的なようだ。それは確かにそうで、嘆きにも似たヴェイユの肉体的・精神的な苦痛の描写は、本書全体に重くのしかかっている。しかしかつての生徒向けの手紙という体裁ではあるが、安直な革命信仰を一蹴するかのように、ヴェイユは次のように自身の経験を肯定する。 「なぜなら、いまこそようやく、この経験に含まれる利益をすべて引きだせる状態にたどりついたからです。とりわけ、抽象の世界を抜け出し、実存をそなえた人間たちのただなかにいるという感覚をいだいています。善い人も悪い人もいますが、いずれも本物の善さと悪さです。」p.242-243
工場日記シモーヌ・ヴェイユ,佐藤紀子,冨原眞弓読み終わった工場に縁ある人間なので、シモーヌ・ヴェイユの思想も著作も解説書も読んだことないが興味わいて手に取ってみた。 読んでいてまず驚いたのは、一年弱の短い期間なのにかなり色んな機械工作作業を行なっていることだった。ヴェイユが携わるのは機械部品製作で、使用する工作機械や行われる作業は、大型プレス機、小型プレス機、フライス盤、歪取り、リベット打ち、穴あけ、溶鉱炉、焼なまし、型抜き、ねじ切りなどなど。製作する部品は絶縁材、座金、缶、コンデンサ用箔、圧着端子、シャント、ネジ、受け座などなど。1日当たりの製作数は数百から二、三千。しかも日によって製作部品がコロコロ変わる。人文的には興味持たれない部分なんだろうけど、当時のディープな機械系工場模様に唸らされる。 さらに、支払い金額や仕損じといったさらなるディテール、職場の人物たちとのやり取りや印象などなど。日記の後半はそれらに基づく思索が増えていく。「何でも見てやろう」ならぬ「何でも記録してやろう」「何でも思索の糧にしてやろう」という気迫がすごい。 本書の紹介文を覗くと、過酷な日々に心身が消耗していく悲壮な記録として紹介されるのが一般的なようだ。それは確かにそうで、嘆きにも似たヴェイユの肉体的・精神的な苦痛の描写は、本書全体に重くのしかかっている。しかしかつての生徒向けの手紙という体裁ではあるが、安直な革命信仰を一蹴するかのように、ヴェイユは次のように自身の経験を肯定する。 「なぜなら、いまこそようやく、この経験に含まれる利益をすべて引きだせる状態にたどりついたからです。とりわけ、抽象の世界を抜け出し、実存をそなえた人間たちのただなかにいるという感覚をいだいています。善い人も悪い人もいますが、いずれも本物の善さと悪さです。」p.242-243 - 2025年11月5日
 新プロパガンダ論西田亮介,辻田真佐憲再読したプロパガンダというくくりで見る2018年から2020年ごろまで政治ネタ批評対談といった本。ただ、いかんせん現在の政治とメディアの状況が、この頃から一歩も二歩も変わってしまってるので、本書は若干賞味期限切れしてしまった感は否めない。自分の場合は、意図的に現在との違いを探りたくて再読したのだが。 儲かるから或いは推しだからという理由で自発的に作られた政治系切り抜き動画がたくさん出回るさまが象徴するように、本書からわずか5年の間に、「プロパガンダ」というような政治側が一方的に仕掛ける時代ではなくなったのが現在だ。むろん政党・政治家サイドからの「マーケティング」は真っ当なものも道理を外れたものも含めて今も続いているわけで、それらの受け止め方の一材料を供する本ではある。
新プロパガンダ論西田亮介,辻田真佐憲再読したプロパガンダというくくりで見る2018年から2020年ごろまで政治ネタ批評対談といった本。ただ、いかんせん現在の政治とメディアの状況が、この頃から一歩も二歩も変わってしまってるので、本書は若干賞味期限切れしてしまった感は否めない。自分の場合は、意図的に現在との違いを探りたくて再読したのだが。 儲かるから或いは推しだからという理由で自発的に作られた政治系切り抜き動画がたくさん出回るさまが象徴するように、本書からわずか5年の間に、「プロパガンダ」というような政治側が一方的に仕掛ける時代ではなくなったのが現在だ。むろん政党・政治家サイドからの「マーケティング」は真っ当なものも道理を外れたものも含めて今も続いているわけで、それらの受け止め方の一材料を供する本ではある。 - 2025年10月26日
 探究(1)柄谷行人再読した哲学・思想講談社学術文庫ウィトゲンシュタインの言語ゲームを核にして、「他者」とは何かを探る本。色んな哲学者・思想家の言説を紐付けながら思考を広げていくさまには舌を巻く。「話す-聞く」の立場から「教える-学ぶ」の立場で言語に接することで「他者」が現れるという視点は面白い。 言語ゲームの規則を共有する者の集まりが共同体であり、共同体と共同体の間、すなわち言語ゲームの規則を共有しない者との接触で「他者」が現れるというの全くその通りだろう。だが、別に共同体を離れるような仰々しいことをしなくても、言語ゲームの規則のすれ違いは誰とでも常に起きるので、そこに敏感でいることが「独我論」から離れる秘訣だと思うな。少なくとも日常レベルでは。 ウィトゲンシュタインと並んでマルクスの資本(の中の貨幣論)も議論のウエイトを占めるが、これもものすごく雑に平たくまとめると、商品や商売のおかげで「他者」と出会えるよねという結論になるな。うーむ、自由市場経済万歳。 しっかし、ドストエフスキーの小説で出てくる、あのねっちこい陰キャラ感全開の予防線張りまくり長回しセリフたちにこんな高尚な意味があったとは!? バフチンのポリフォニー理論は知っていたつもりだったが思わず本当かよとツッコミまずにいられない。
探究(1)柄谷行人再読した哲学・思想講談社学術文庫ウィトゲンシュタインの言語ゲームを核にして、「他者」とは何かを探る本。色んな哲学者・思想家の言説を紐付けながら思考を広げていくさまには舌を巻く。「話す-聞く」の立場から「教える-学ぶ」の立場で言語に接することで「他者」が現れるという視点は面白い。 言語ゲームの規則を共有する者の集まりが共同体であり、共同体と共同体の間、すなわち言語ゲームの規則を共有しない者との接触で「他者」が現れるというの全くその通りだろう。だが、別に共同体を離れるような仰々しいことをしなくても、言語ゲームの規則のすれ違いは誰とでも常に起きるので、そこに敏感でいることが「独我論」から離れる秘訣だと思うな。少なくとも日常レベルでは。 ウィトゲンシュタインと並んでマルクスの資本(の中の貨幣論)も議論のウエイトを占めるが、これもものすごく雑に平たくまとめると、商品や商売のおかげで「他者」と出会えるよねという結論になるな。うーむ、自由市場経済万歳。 しっかし、ドストエフスキーの小説で出てくる、あのねっちこい陰キャラ感全開の予防線張りまくり長回しセリフたちにこんな高尚な意味があったとは!? バフチンのポリフォニー理論は知っていたつもりだったが思わず本当かよとツッコミまずにいられない。 - 2025年10月19日
 臨床のフリコラージュ斎藤環,東畑開人読み終わった精神分析臨床心理学内容を一言でいえば2人の心理臨床・精神医学オタクトークなんだが、門外漢にも充分おもしろい。私見だが、こういう対談本は中身以外に前書きと後書きの重要度が大きい。前書きと後書きで対談を串刺しにして、書籍としての一体感を一気に高めるわけだが、本書もご多分に漏れず前書き・後書きがとても良きなり
臨床のフリコラージュ斎藤環,東畑開人読み終わった精神分析臨床心理学内容を一言でいえば2人の心理臨床・精神医学オタクトークなんだが、門外漢にも充分おもしろい。私見だが、こういう対談本は中身以外に前書きと後書きの重要度が大きい。前書きと後書きで対談を串刺しにして、書籍としての一体感を一気に高めるわけだが、本書もご多分に漏れず前書き・後書きがとても良きなり - 2025年10月19日
 きことわ朝吹真理子読み終わった単行本小説芥川賞登場人物・ストーリー・舞台設定・セリフ・心情描写に、何の奇抜さもケレン味も驚きも衝撃もスキャンダラスさも無い。分かりやすい悲劇も喜劇も無い。幼少期に交友のあった女性二人が25年後に縁あって再会し、二日間ほどある家屋の片付けを行って終わり。 しかし、そういった奇抜さがあろうがなかろうが25年の間に生活は積み重ねられ人生は進んでいく。出産・育児があったり、家族の早世があったり。そこへ感情と記憶が付着し、心の中に晴れない何かが溜まっていく。小説は、そういった機微を丁寧に記述する。 これだけ地味な小説なのに、最後まで自分が楽しんで読めたことにおどろく。若い頃だったら絶対無理だったであろうと考えると、年を取ることもまあ悪くはないかなと思えてくる。小説の締めくくりもこれまた地味なわけだが、何だか整理がついたような、とても前向きなラストに思えてくるから不思議だ。
きことわ朝吹真理子読み終わった単行本小説芥川賞登場人物・ストーリー・舞台設定・セリフ・心情描写に、何の奇抜さもケレン味も驚きも衝撃もスキャンダラスさも無い。分かりやすい悲劇も喜劇も無い。幼少期に交友のあった女性二人が25年後に縁あって再会し、二日間ほどある家屋の片付けを行って終わり。 しかし、そういった奇抜さがあろうがなかろうが25年の間に生活は積み重ねられ人生は進んでいく。出産・育児があったり、家族の早世があったり。そこへ感情と記憶が付着し、心の中に晴れない何かが溜まっていく。小説は、そういった機微を丁寧に記述する。 これだけ地味な小説なのに、最後まで自分が楽しんで読めたことにおどろく。若い頃だったら絶対無理だったであろうと考えると、年を取ることもまあ悪くはないかなと思えてくる。小説の締めくくりもこれまた地味なわけだが、何だか整理がついたような、とても前向きなラストに思えてくるから不思議だ。 - 2025年10月19日
 ハンチバック市川沙央読み終わった単行本小説芥川賞読後に反芻していると、東畑開人による心理臨床が「心を可能にする仕事」と「心を自由にする仕事」へ分類される話を思い出した(「臨床のフリコラージュ」など)。大雑把に言えば、前者は環境調整を行い、安全や余裕を確保する。後者は当人の中で反復されること、深層的な心の問題を扱う。 小説には、社会の中で括弧付きの「普通」に収まらない人が「心を可能」にしようと苦闘するさまを中心に描くタイプがあり、同じく芥川賞受賞した「コンビニ人間」などはこちらか。 「ハンチバック」では、「心を可能にする」こと(身体障害者の環境の問題)についても語られるが、それ自体は主人公の思弁や個有名の引用として触れられるに留められる(しかし、その語りは強烈なパンチ力を放つが)。物語そのものは、むしろ、環境を寄与のものした上で「心を自由にする」スリリングな試みを中心に進んで行く。語りの視点を使い分けながらそれぞれをハイブリッドに収めることで、本作は幅広い読み手を引きつける作品強度を持っている。
ハンチバック市川沙央読み終わった単行本小説芥川賞読後に反芻していると、東畑開人による心理臨床が「心を可能にする仕事」と「心を自由にする仕事」へ分類される話を思い出した(「臨床のフリコラージュ」など)。大雑把に言えば、前者は環境調整を行い、安全や余裕を確保する。後者は当人の中で反復されること、深層的な心の問題を扱う。 小説には、社会の中で括弧付きの「普通」に収まらない人が「心を可能」にしようと苦闘するさまを中心に描くタイプがあり、同じく芥川賞受賞した「コンビニ人間」などはこちらか。 「ハンチバック」では、「心を可能にする」こと(身体障害者の環境の問題)についても語られるが、それ自体は主人公の思弁や個有名の引用として触れられるに留められる(しかし、その語りは強烈なパンチ力を放つが)。物語そのものは、むしろ、環境を寄与のものした上で「心を自由にする」スリリングな試みを中心に進んで行く。語りの視点を使い分けながらそれぞれをハイブリッドに収めることで、本作は幅広い読み手を引きつける作品強度を持っている。 - 2025年10月11日
 ブラックボックス砂川文次読み終わった単行本小説芥川賞現代小説には様々な形で社会からはみ出す人たちが描かれ、我々の常識にさざなみを起こす。しかし、その人物がときおり感情を抑えきれずもはや正当防衛といえないレベルで暴力を振るう人物だったらどう受け止めるべきか。ダイバーシティとは社会的排除とは包摂とは、さてはて。 そんな倫理的な談議はさておき、終着点は明白だ。逮捕されて刑務所にぶち込まれる。それでお終い。そんな物語。 しかしこれは小説だ。そこには彼の人生と心が書き表わされる。読者を「それでお終い」にさせない場所まで連れて行く。 “自分が物を直すとき、直した後に感じた高揚感は所有欲とか見栄とかいうのではなくて、これならどこまでも行ける気がする、そういう直感をもたらしてくれるからだった、と今になって思う" その感覚なら、よく分かるぜ!
ブラックボックス砂川文次読み終わった単行本小説芥川賞現代小説には様々な形で社会からはみ出す人たちが描かれ、我々の常識にさざなみを起こす。しかし、その人物がときおり感情を抑えきれずもはや正当防衛といえないレベルで暴力を振るう人物だったらどう受け止めるべきか。ダイバーシティとは社会的排除とは包摂とは、さてはて。 そんな倫理的な談議はさておき、終着点は明白だ。逮捕されて刑務所にぶち込まれる。それでお終い。そんな物語。 しかしこれは小説だ。そこには彼の人生と心が書き表わされる。読者を「それでお終い」にさせない場所まで連れて行く。 “自分が物を直すとき、直した後に感じた高揚感は所有欲とか見栄とかいうのではなくて、これならどこまでも行ける気がする、そういう直感をもたらしてくれるからだった、と今になって思う" その感覚なら、よく分かるぜ! - 2025年10月11日
 コンビニ人間村田沙耶香読み終わった単行本小説芥川賞明け透けのない思考と次の瞬間には何か突拍子もない行動をしそうな主人公、脇を固めるある種わかりやすくキャラ立ちした登場人物たち。とくに白羽が活躍し出して以降は文字通りページをめくる手が止まらずに読み切ってしまった。おもしろーい 小説が問いかける社会的問題と向き合うも良し、ハラハラドキドキエンタメ小説として楽しむも良し。前者の点においても鋭利に私たちを刺す。個を個として受け止めず「ムラのオスとメス」の仲間にしたがる社会。優れた小説とは多面的に楽しめるのだなー コンビニでしか世界の一部になれないという一見悲壮な設定とは裏腹に、主人公の働きっぷりとコンビニの描写は生き生きとしていて読んでいて楽しい。コンビニ労働のいわゆる「お仕事小説」としても秀逸に機能している。 しかしまあ自分がコンビニ店長なら、最強人材である古倉さんには感謝感激雨あられでしょ
コンビニ人間村田沙耶香読み終わった単行本小説芥川賞明け透けのない思考と次の瞬間には何か突拍子もない行動をしそうな主人公、脇を固めるある種わかりやすくキャラ立ちした登場人物たち。とくに白羽が活躍し出して以降は文字通りページをめくる手が止まらずに読み切ってしまった。おもしろーい 小説が問いかける社会的問題と向き合うも良し、ハラハラドキドキエンタメ小説として楽しむも良し。前者の点においても鋭利に私たちを刺す。個を個として受け止めず「ムラのオスとメス」の仲間にしたがる社会。優れた小説とは多面的に楽しめるのだなー コンビニでしか世界の一部になれないという一見悲壮な設定とは裏腹に、主人公の働きっぷりとコンビニの描写は生き生きとしていて読んでいて楽しい。コンビニ労働のいわゆる「お仕事小説」としても秀逸に機能している。 しかしまあ自分がコンビニ店長なら、最強人材である古倉さんには感謝感激雨あられでしょ - 2025年10月11日
 東京都同情塔九段理江読み終わった単行本小説芥川賞芥川賞受賞作に言うのも失礼な話だけど、グルーヴ(本書の言葉でいえば「フロー」)の効いた読み易い上手い文章で、グイグイと読まされてしまった。バベルの塔や言葉の壁がモチーフなのに、小説そのものはとても読みやすいというアンビバレンス。著者の他の作品も読んでみたい 場面や状況の展開そのものはミニマムで、ほとんど登場人物の思考や会話で占められる。何やら社会性や政治性を誘起する設定の小説だが、良くも悪くもテーマの重さは感じさせない。宣伝されてない本書のもう一つのテーマは建築・建築家の持つ欲望についてだと思うが、個人的はそちらの方にアクチュアリティを感じ、今後も気になりそうな概念だ。 些細な点だが指摘しておくと、登場人物に死去をもたらすために精神的な異常者を物語ご都合的にその場限りで用いるのは好きじゃないな、とサラ・マキナのように頭の中の検閲が
東京都同情塔九段理江読み終わった単行本小説芥川賞芥川賞受賞作に言うのも失礼な話だけど、グルーヴ(本書の言葉でいえば「フロー」)の効いた読み易い上手い文章で、グイグイと読まされてしまった。バベルの塔や言葉の壁がモチーフなのに、小説そのものはとても読みやすいというアンビバレンス。著者の他の作品も読んでみたい 場面や状況の展開そのものはミニマムで、ほとんど登場人物の思考や会話で占められる。何やら社会性や政治性を誘起する設定の小説だが、良くも悪くもテーマの重さは感じさせない。宣伝されてない本書のもう一つのテーマは建築・建築家の持つ欲望についてだと思うが、個人的はそちらの方にアクチュアリティを感じ、今後も気になりそうな概念だ。 些細な点だが指摘しておくと、登場人物に死去をもたらすために精神的な異常者を物語ご都合的にその場限りで用いるのは好きじゃないな、とサラ・マキナのように頭の中の検閲が - 2025年9月8日
 イルカと否定神学斎藤環ケアをひらく読み終わった哲学・思想精神分析これは……良い!!! 何やら固そうな書名と地味な装丁で敬遠されないかと勝手に心配してしまう(ToT) 後書きにも書かれているようにできる限り読みやすさに配慮され、登場する用語には要約説明もつけられており、入門書感覚でも読み始められる(はず)。 オープンダイヤローグによる精神病回復効果の基礎を解明するという動機から書かれた本だから、そんな専門っぽいマニアックな問いに興味持たれないのかもしれないけど、ここで論考される「対話の謎」解き明かしは、もっと日常的、一般的、普遍的なレベルでも大いに示唆を与えてくれると、オレは思うんだけどなあー。 以下、自分的超解釈メモ: 言葉(対話)で相手の考え(コンテクスト)を変化させると言えばめちゃくちゃ普通っぽいんだけど、本書はさらに思索を深め、言語が本質的に持つ否定神学的構造(唯一の実体というものを持たない空虚)、そこから生まれる逆説化がコンテクストの揺さぶりを起こすという仮説が熱い。 これは下手すると悪い方向の結果も生み得るわけだが、そのためオープンダイヤローグはポリフォニーと余白が重要。非誘導的な余白が学習Ⅲを活性化させる。あとは個々人が持つレジリエンスを信じる。そんな感じか。
イルカと否定神学斎藤環ケアをひらく読み終わった哲学・思想精神分析これは……良い!!! 何やら固そうな書名と地味な装丁で敬遠されないかと勝手に心配してしまう(ToT) 後書きにも書かれているようにできる限り読みやすさに配慮され、登場する用語には要約説明もつけられており、入門書感覚でも読み始められる(はず)。 オープンダイヤローグによる精神病回復効果の基礎を解明するという動機から書かれた本だから、そんな専門っぽいマニアックな問いに興味持たれないのかもしれないけど、ここで論考される「対話の謎」解き明かしは、もっと日常的、一般的、普遍的なレベルでも大いに示唆を与えてくれると、オレは思うんだけどなあー。 以下、自分的超解釈メモ: 言葉(対話)で相手の考え(コンテクスト)を変化させると言えばめちゃくちゃ普通っぽいんだけど、本書はさらに思索を深め、言語が本質的に持つ否定神学的構造(唯一の実体というものを持たない空虚)、そこから生まれる逆説化がコンテクストの揺さぶりを起こすという仮説が熱い。 これは下手すると悪い方向の結果も生み得るわけだが、そのためオープンダイヤローグはポリフォニーと余白が重要。非誘導的な余白が学習Ⅲを活性化させる。あとは個々人が持つレジリエンスを信じる。そんな感じか。 - 2025年9月7日
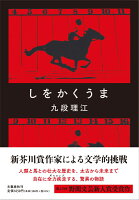 しをかくうま九段理江読み終わった単行本小説ちょっと悪い言い方をすれば、読後の感覚はどう受け止めればいいかよく分からず座りが悪い。即物的だが良い言い方をすれば、読後もたくさんの伏線・ダブルミーニング・メタファーを咀嚼して味わえる小説。 登場人物たちの会話と行動はなんとも浮世離れしており、一般的な意味での共感は誘わない。最後の自分の脳で創作することに拘る未来人が、もっとも現代人的で共感しやすいのが皮肉的だ。作者の本意ではないかもしれないが、昨今の「考察」系のテーブルに載せることもできそうだなと思った。 座りの悪いままにしておくのも良いが、自分なりの解釈を本棚に戻す前に書き残そう。 「しをかくうま」とは「詩を欠く馬」。言葉は詩であり、名前は詩であるのに、作中で名前が呼ばれないままの主人公は「詩を欠く馬」であり、馬=詩=言葉を追い求める続ける。TRANSSNART(主人公の子孫か)もまた言葉を追い求め、雨の中で立ちすくむ。この物語は、言葉を自分のものとする欲望から、不治の病のように逃れられない者たちの焦燥の物語。
しをかくうま九段理江読み終わった単行本小説ちょっと悪い言い方をすれば、読後の感覚はどう受け止めればいいかよく分からず座りが悪い。即物的だが良い言い方をすれば、読後もたくさんの伏線・ダブルミーニング・メタファーを咀嚼して味わえる小説。 登場人物たちの会話と行動はなんとも浮世離れしており、一般的な意味での共感は誘わない。最後の自分の脳で創作することに拘る未来人が、もっとも現代人的で共感しやすいのが皮肉的だ。作者の本意ではないかもしれないが、昨今の「考察」系のテーブルに載せることもできそうだなと思った。 座りの悪いままにしておくのも良いが、自分なりの解釈を本棚に戻す前に書き残そう。 「しをかくうま」とは「詩を欠く馬」。言葉は詩であり、名前は詩であるのに、作中で名前が呼ばれないままの主人公は「詩を欠く馬」であり、馬=詩=言葉を追い求める続ける。TRANSSNART(主人公の子孫か)もまた言葉を追い求め、雨の中で立ちすくむ。この物語は、言葉を自分のものとする欲望から、不治の病のように逃れられない者たちの焦燥の物語。
読み込み中...