

みつ
@m-tk
気になった本を、読める時に読む。
心について考えたい。
ほんとうはもっとゆっくり生きていきたい。
- 2026年2月23日
 なぜ人と組織は変われないのかロバート・キーガン,リサ・ラスコウ・レイヒー,池村千秋借りてきた読んでる
なぜ人と組織は変われないのかロバート・キーガン,リサ・ラスコウ・レイヒー,池村千秋借りてきた読んでる - 2026年2月8日
 大学でどう学ぶか濱中淳子借りてきた読んでる── 「学校歴のせいにしてはいけないし、いい大学を出たからといって、学習を忘れれば、教育の効果は縮小する。学歴や学校歴だけに囚われず、教育の機会を真摯に活用し、学生の本分を忘れない努力が、将来のキャリアを豊かにする」──本章の最後に、「学び習慣仮説」を提唱した矢野さんの言葉をいまいちど引いておきたいと思います。
大学でどう学ぶか濱中淳子借りてきた読んでる── 「学校歴のせいにしてはいけないし、いい大学を出たからといって、学習を忘れれば、教育の効果は縮小する。学歴や学校歴だけに囚われず、教育の機会を真摯に活用し、学生の本分を忘れない努力が、将来のキャリアを豊かにする」──本章の最後に、「学び習慣仮説」を提唱した矢野さんの言葉をいまいちど引いておきたいと思います。 - 2026年2月1日
 文系?理系?志村史夫借りてきた読んでる── 一人の人間が「理科系」に属するか、「文科系」に属するかなどというのは、本来、学校の学科の試験の"良し悪し"なんかで決められるものではないのです。さらに、学校の試験などを通じて評価し得る人間の能力や資質は、ほんの少しの限られたものにすぎないのです。それなのに、日本の社会では現実的に、学校の試験の成績次第で、一人の人間の「優劣」や「適性」、そして「文科系」か「理科系」かのレッテルが貼られてしまう傾向があることを否めないのはまことに遺憾です。
文系?理系?志村史夫借りてきた読んでる── 一人の人間が「理科系」に属するか、「文科系」に属するかなどというのは、本来、学校の学科の試験の"良し悪し"なんかで決められるものではないのです。さらに、学校の試験などを通じて評価し得る人間の能力や資質は、ほんの少しの限られたものにすぎないのです。それなのに、日本の社会では現実的に、学校の試験の成績次第で、一人の人間の「優劣」や「適性」、そして「文科系」か「理科系」かのレッテルが貼られてしまう傾向があることを否めないのはまことに遺憾です。 - 2026年1月27日
 人生にコンセプトを澤田智洋借りてきた読んでる──中高生でも、「実は夢がない」という人は意外と多いはずです。とくに学校では頻繁に夢を尋ねられるため、夢がないことで罪悪感を覚えたり、「友だちは弁護士になるという夢に向かって頑張っているのに、自分はそもそも大学に行きたいのかもわからない・・・・・・」と自己否定につながることもよくあります。でもそれは、夢を持っている人の存在が強く際立っているだけであり、持っていない人だって大勢いるのです。まずはこのことを知ってください。
人生にコンセプトを澤田智洋借りてきた読んでる──中高生でも、「実は夢がない」という人は意外と多いはずです。とくに学校では頻繁に夢を尋ねられるため、夢がないことで罪悪感を覚えたり、「友だちは弁護士になるという夢に向かって頑張っているのに、自分はそもそも大学に行きたいのかもわからない・・・・・・」と自己否定につながることもよくあります。でもそれは、夢を持っている人の存在が強く際立っているだけであり、持っていない人だって大勢いるのです。まずはこのことを知ってください。 - 2026年1月23日
 悩みとつきあおう串崎真志借りてきたかつて読んだ── 不思議です。本を読むことで、なにか安心を得ていたところがありました。そういう高校生も、少ないながらいることでしょう。 この本は、そんな「かつての自分」に贈るメッセージでもあります。岩波ジュニア新書にこんな本があったらいいなあと、ずっと思っていたのです。
悩みとつきあおう串崎真志借りてきたかつて読んだ── 不思議です。本を読むことで、なにか安心を得ていたところがありました。そういう高校生も、少ないながらいることでしょう。 この本は、そんな「かつての自分」に贈るメッセージでもあります。岩波ジュニア新書にこんな本があったらいいなあと、ずっと思っていたのです。 - 2026年1月18日
 会社で働く松井大助借りてきた読み終わった── こうした会社員の物語を届けたかったのは、多くの人にとって、実はいちばんよくわからない職業ではないか、と感じているからです。「スポーツ選手やお医者さん、お花屋さんのしていることはなんとなくわかるけれど、会社員って何をしているんだろう」と。世界に何億何千万人といる、その会社員のかっこいい一面を紹介したいと思いました。
会社で働く松井大助借りてきた読み終わった── こうした会社員の物語を届けたかったのは、多くの人にとって、実はいちばんよくわからない職業ではないか、と感じているからです。「スポーツ選手やお医者さん、お花屋さんのしていることはなんとなくわかるけれど、会社員って何をしているんだろう」と。世界に何億何千万人といる、その会社員のかっこいい一面を紹介したいと思いました。 - 2026年1月15日
 自分にやさしくする生き方伊藤絵美借りてきた読んでる── ストレッサーやストレス反応には、一つ一つ、きっちりと観察の目を向け、気づいてあげることにしましょう。あるものを「なかったこと」にするのではなく、「あるもの」として、あるがままに気づきを向けるほうが、自分にやさしくすることに直接つながります。
自分にやさしくする生き方伊藤絵美借りてきた読んでる── ストレッサーやストレス反応には、一つ一つ、きっちりと観察の目を向け、気づいてあげることにしましょう。あるものを「なかったこと」にするのではなく、「あるもの」として、あるがままに気づきを向けるほうが、自分にやさしくすることに直接つながります。 - 2026年1月8日
 後悔を活かす心理学上市秀雄借りてきた読んでる── 私たちにとって重要なことは、後悔しないようにすることだけではない。「後悔したときに適切に対処し、後悔を乗り越え、自分を高めていくための努力をすること」も必要なのである。
後悔を活かす心理学上市秀雄借りてきた読んでる── 私たちにとって重要なことは、後悔しないようにすることだけではない。「後悔したときに適切に対処し、後悔を乗り越え、自分を高めていくための努力をすること」も必要なのである。 - 2026年1月8日
 本・子ども・大人ポール・アザール,Paul Hazard,横山正矢,矢崎源九郎借りてきた読んでる
本・子ども・大人ポール・アザール,Paul Hazard,横山正矢,矢崎源九郎借りてきた読んでる - 2026年1月4日
 傷のあわい宮地尚子買った読んでる── 出会った人々の「物語化」を試みているが、そのことへの躊躇も正直なところ感じている。物語にすることでそれぞれの人を単純化してしまっていないか、私の解釈を押し付けてはいないかが気になる。ただ、結末は時間に開かれている。人生には結末などない。結末のように見えても、そこからも人生は続く。死というものがあるが、その後でさえも物語は紡がれていく。
傷のあわい宮地尚子買った読んでる── 出会った人々の「物語化」を試みているが、そのことへの躊躇も正直なところ感じている。物語にすることでそれぞれの人を単純化してしまっていないか、私の解釈を押し付けてはいないかが気になる。ただ、結末は時間に開かれている。人生には結末などない。結末のように見えても、そこからも人生は続く。死というものがあるが、その後でさえも物語は紡がれていく。 - 2025年12月30日
 心に折り合いをつけて うまいことやる習慣中村恒子,奥田弘美買った読んでる── もっと根本的なことを言えば、生活をするため人は働くんです。それは、大昔から変わりません。 自分を食べさせていくため、家族を食べさせていくために働く。それが仕事のいちばんの目的です。 (中略) だから、お金のために働くっていうのは、何も恥ずかしいことやない。あたりまえのこと。とっても立派なことやと思います。
心に折り合いをつけて うまいことやる習慣中村恒子,奥田弘美買った読んでる── もっと根本的なことを言えば、生活をするため人は働くんです。それは、大昔から変わりません。 自分を食べさせていくため、家族を食べさせていくために働く。それが仕事のいちばんの目的です。 (中略) だから、お金のために働くっていうのは、何も恥ずかしいことやない。あたりまえのこと。とっても立派なことやと思います。 - 2025年12月30日
 ことばのかたちおーなり由子ブックサンタ読みたい
ことばのかたちおーなり由子ブックサンタ読みたい - 2025年12月30日
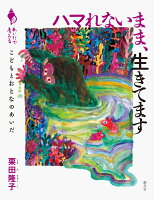 ハマれないまま、生きてます栗田隆子借りてきた読み終わった── 自分の思いを言葉で伝えられなかった悲しさ。「言葉がない」というのはまさに「子ども」であるゆえだ。自分の思いを押し殺さず、十全に伝えるには、「子ども」の私が持っている言葉はあまりに少なく、また表面的なものでしかなかった。あたりまえのそのことが私にはとてもつらかった。自分のことを言葉で伝えられない絶望や悲しさについて語りたい。
ハマれないまま、生きてます栗田隆子借りてきた読み終わった── 自分の思いを言葉で伝えられなかった悲しさ。「言葉がない」というのはまさに「子ども」であるゆえだ。自分の思いを押し殺さず、十全に伝えるには、「子ども」の私が持っている言葉はあまりに少なく、また表面的なものでしかなかった。あたりまえのそのことが私にはとてもつらかった。自分のことを言葉で伝えられない絶望や悲しさについて語りたい。 - 2025年12月30日
 苦しい時は電話して坂口恭平借りてきた読んでる── 死にたいと思うことは何も悪いことではありません。僕の経験から言うなら、誰にでも起こりうることであり、生きている中でいたって普通のことです。むしろ、それがない人を探すほうが難しいくらいです。ですが、対話がされなすぎて、ないことになっているだけです。 必要なのは、対話ができる場所をつくること。目に見えるところにつくってもなかなか集まりにくいのが現状です。目に見えない場所。でも確実にある場所。いつでもつながる場所。対話が繰り広げられる場所。そういう場所をつくりたいと思って「いのっち の電話」をはじめました。 だから、簡単にやめるわけにはいかないのです。
苦しい時は電話して坂口恭平借りてきた読んでる── 死にたいと思うことは何も悪いことではありません。僕の経験から言うなら、誰にでも起こりうることであり、生きている中でいたって普通のことです。むしろ、それがない人を探すほうが難しいくらいです。ですが、対話がされなすぎて、ないことになっているだけです。 必要なのは、対話ができる場所をつくること。目に見えるところにつくってもなかなか集まりにくいのが現状です。目に見えない場所。でも確実にある場所。いつでもつながる場所。対話が繰り広げられる場所。そういう場所をつくりたいと思って「いのっち の電話」をはじめました。 だから、簡単にやめるわけにはいかないのです。 - 2025年12月30日
 自殺者を減らす!波名城翔借りてきた読み終わった── 彼らは、自殺に追い込んだやつを成敗に行って欲しいんです。会社へ乗り込み、学校のいじめだったら学校に乗り込む。あの人たちはそうして欲しいんです。いわゆる、環境調整をして欲しいんですね。 これらを抱えて生きていくのはつらいよね。それを取り除かなあかんでしょ。取り除いてあげなあかん。取り除いてくれる社会的な構造になっていますか!?!?どこ行ったら取り除いてくれるんですか!?この答えを、彼らは聞きたいんです。
自殺者を減らす!波名城翔借りてきた読み終わった── 彼らは、自殺に追い込んだやつを成敗に行って欲しいんです。会社へ乗り込み、学校のいじめだったら学校に乗り込む。あの人たちはそうして欲しいんです。いわゆる、環境調整をして欲しいんですね。 これらを抱えて生きていくのはつらいよね。それを取り除かなあかんでしょ。取り除いてあげなあかん。取り除いてくれる社会的な構造になっていますか!?!?どこ行ったら取り除いてくれるんですか!?この答えを、彼らは聞きたいんです。 - 2025年12月30日
 あなただけの人生をどう生きるか渡辺和子借りてきた読み終わった── 「大学の四年間を振り返って」というレポートに、「自分にとって入学当初の大学の自由というものは、苦しみでもあった」という述懐がありました。進学、受験、勉強に追われた高校時代に夢にまで見た自由かも知れません。けれどもその自由は、また苦しみでもあります。なぜなら、自由な時間の使い方に対しては、それを使う人が全責任を負わなければならないからです。
あなただけの人生をどう生きるか渡辺和子借りてきた読み終わった── 「大学の四年間を振り返って」というレポートに、「自分にとって入学当初の大学の自由というものは、苦しみでもあった」という述懐がありました。進学、受験、勉強に追われた高校時代に夢にまで見た自由かも知れません。けれどもその自由は、また苦しみでもあります。なぜなら、自由な時間の使い方に対しては、それを使う人が全責任を負わなければならないからです。 - 2025年9月7日
 かかわり方のまなび方西村佳哲借りてきた読んでる── 「人の力をどう引き出すか?」という問いをあらためて見直してみると、意識が「人」より「引き出す」ほうに偏っていたことに気づく。もし仮にかかわられる側だったとして、自分のことをよく見ようともしないで「引き出し」にかかってくる人間がいたら、どんな気分だろう。僕は嫌です。エネルギーを解放したいし、本領も発揮したい。だから上手く引き出してくれる人は魅力的だけど、勝手にはされたくないし、相手の都合で引き出されるなんてもってのほかだ。
かかわり方のまなび方西村佳哲借りてきた読んでる── 「人の力をどう引き出すか?」という問いをあらためて見直してみると、意識が「人」より「引き出す」ほうに偏っていたことに気づく。もし仮にかかわられる側だったとして、自分のことをよく見ようともしないで「引き出し」にかかってくる人間がいたら、どんな気分だろう。僕は嫌です。エネルギーを解放したいし、本領も発揮したい。だから上手く引き出してくれる人は魅力的だけど、勝手にはされたくないし、相手の都合で引き出されるなんてもってのほかだ。 - 2025年8月31日
- 2025年8月6日
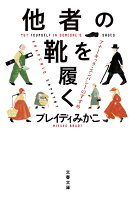 他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめブレイディみかこ買った読んでる一万円選書── 彼女が獄中で書いためざしの歌が示しているのは、自分の靴が脱げなければ他者の靴は履けないということだ。そして逆説的に、自分の靴に頓着しない人は自主自律の人だということでもある。
他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめブレイディみかこ買った読んでる一万円選書── 彼女が獄中で書いためざしの歌が示しているのは、自分の靴が脱げなければ他者の靴は履けないということだ。そして逆説的に、自分の靴に頓着しない人は自主自律の人だということでもある。 - 2025年8月6日
 〈自分らしさ〉って何だろう?榎本博明借りてきた読み終わった── 早くスッキリしたいと思うかもしれない。でも、今の自分に納得がいかないからといって、自分を否定する必要はない。 自己の二重性を思い出してみよう。「見られている自分」に対して納得のいかない「見ている自分」がいるわけだ。その「見ている自分」は、適当に流されている自分にも不満を持たなかった以前の自分と比べて、はるかに向上心に満ちた自分と言えるだろう。そんな自分は、けっして否定すべきものではない。むしろ肯定し、応援すべきなのではないだろうか。
〈自分らしさ〉って何だろう?榎本博明借りてきた読み終わった── 早くスッキリしたいと思うかもしれない。でも、今の自分に納得がいかないからといって、自分を否定する必要はない。 自己の二重性を思い出してみよう。「見られている自分」に対して納得のいかない「見ている自分」がいるわけだ。その「見ている自分」は、適当に流されている自分にも不満を持たなかった以前の自分と比べて、はるかに向上心に満ちた自分と言えるだろう。そんな自分は、けっして否定すべきものではない。むしろ肯定し、応援すべきなのではないだろうか。
読み込み中...
