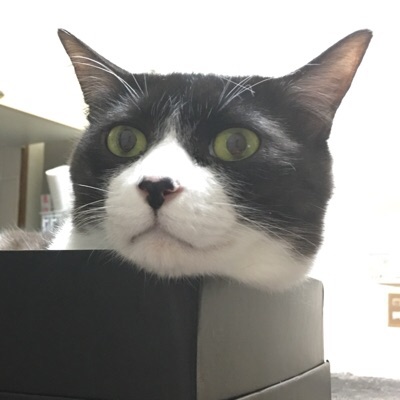「透明」になんかされるものか --鷲田清一エッセイ集

94件の記録
 saiki@lighthouse_2025年12月30日買った12/20荻窪Titleにて購入。20代の頃からゆっくりとマイペースに読んでいる数少ない著者のひとり。積読もいくつかあるけど、本屋さんで「本買うぞ!」な時に何かしら1冊買いがち。
saiki@lighthouse_2025年12月30日買った12/20荻窪Titleにて購入。20代の頃からゆっくりとマイペースに読んでいる数少ない著者のひとり。積読もいくつかあるけど、本屋さんで「本買うぞ!」な時に何かしら1冊買いがち。
 もち@noro_302025年11月24日読み終わった"理解しあえるはずだという前提に立つと、 ひとは理解しあえなかったときについ 共存できたかもしれない場所を 閉じてしまう" 久しぶりに読む鷲田清一さん。 いつの間にか考えること 感じることをやめたものたちを 拾い上げて見つめる大事な時間。
もち@noro_302025年11月24日読み終わった"理解しあえるはずだという前提に立つと、 ひとは理解しあえなかったときについ 共存できたかもしれない場所を 閉じてしまう" 久しぶりに読む鷲田清一さん。 いつの間にか考えること 感じることをやめたものたちを 拾い上げて見つめる大事な時間。

 きん@paraboots2025年11月8日気になる他者との細やかな対話の必要性を、今朝の朝刊内で鷲田先生は語っていた。僕たちは言語という同じく等しいプラットフォームを持っているようで、実は同じものを見ていない、最近よく考えていることを先生も指摘されていて少し安堵のようなものを感じた。物事はそんなに単純ではないなあと日々感じている。
きん@paraboots2025年11月8日気になる他者との細やかな対話の必要性を、今朝の朝刊内で鷲田先生は語っていた。僕たちは言語という同じく等しいプラットフォームを持っているようで、実は同じものを見ていない、最近よく考えていることを先生も指摘されていて少し安堵のようなものを感じた。物事はそんなに単純ではないなあと日々感じている。







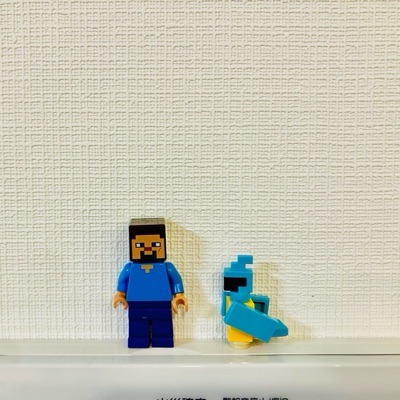 さおり@prn9909082025年10月11日読み終わった静かで優しい眼差しがじわじわと沁みてきて、最近のいろいろなことで、薄らと荒んでしまっている心をそっとあやしてくれているようなそんな心地になる言葉が連ねられていた.決して激しくはない落ち着いた平易な言葉が並べられていて、それでいて読んでいくうちにぽっと火が灯ったようなあたたかいものが体のなかに宿ったような気持ちになれた.この本の帯にある言葉も本当に良くてめちゃくちゃグッとくるんだけど「腸(はらわた)から滲みでてくる言葉」というところの「人の思いは言葉の腸をとおして滲みでてくるもの、ときにはそれを破いて吹きでてくるもの」という文章に心を掴まれた.そういうふうな言葉を拾っていきたいし、自分もそういう言葉を使いたいなと思う.
さおり@prn9909082025年10月11日読み終わった静かで優しい眼差しがじわじわと沁みてきて、最近のいろいろなことで、薄らと荒んでしまっている心をそっとあやしてくれているようなそんな心地になる言葉が連ねられていた.決して激しくはない落ち着いた平易な言葉が並べられていて、それでいて読んでいくうちにぽっと火が灯ったようなあたたかいものが体のなかに宿ったような気持ちになれた.この本の帯にある言葉も本当に良くてめちゃくちゃグッとくるんだけど「腸(はらわた)から滲みでてくる言葉」というところの「人の思いは言葉の腸をとおして滲みでてくるもの、ときにはそれを破いて吹きでてくるもの」という文章に心を掴まれた.そういうふうな言葉を拾っていきたいし、自分もそういう言葉を使いたいなと思う.

 annamsmonde@annamsmonde2025年10月11日読み終わった「ふつうの本なら九割方わからないと買って損をしたとおもうものだが、哲学の本に限っては、一割か二割しかわからなくてもつくづく得をしたとおもう。そして見得のようなそのフレーズを呪文のように丸暗記してしまう。ヘンといえばヘンなのだが、それまでもやもやしていたものがこのフレーズによって結晶作用を起こしてしまうような快感があるからかもしれない。」 ここ!好きでした。 哲学者の人でさえそうなんだ😳と、哲学の本を読む勇気がもらえましたし、結晶作用の快感というのがすごく納得できて嬉しかったです。 手に取ったタイミングで苦戦したので、2週間ねかせて再度ちびちび読み進めたら楽しく読めた! 本との呼吸が合った体感が嬉しい꒰՞o̴̶̷̤ᾥo̴̶̷̤՞꒱
annamsmonde@annamsmonde2025年10月11日読み終わった「ふつうの本なら九割方わからないと買って損をしたとおもうものだが、哲学の本に限っては、一割か二割しかわからなくてもつくづく得をしたとおもう。そして見得のようなそのフレーズを呪文のように丸暗記してしまう。ヘンといえばヘンなのだが、それまでもやもやしていたものがこのフレーズによって結晶作用を起こしてしまうような快感があるからかもしれない。」 ここ!好きでした。 哲学者の人でさえそうなんだ😳と、哲学の本を読む勇気がもらえましたし、結晶作用の快感というのがすごく納得できて嬉しかったです。 手に取ったタイミングで苦戦したので、2週間ねかせて再度ちびちび読み進めたら楽しく読めた! 本との呼吸が合った体感が嬉しい꒰՞o̴̶̷̤ᾥo̴̶̷̤՞꒱

 ハム@unia2025年8月4日読み終わった今の若い人たちは〜みたいな言説って自分も言ってしまうけど同じ時代を生きているようで見えているものがまるで違うのだからアプローチだって違って当然なことを忘れがち。 歴史の脈拍を追うことは難しい。 鷲田さんクラスの人でもそうなのだから。 歴史を振り返ればそのムーブはおかしいとか、その流れは必然なのになぜ気付かなかったのかとか言えるけど、リアルタイムでそれらを把握することの難しさを人はスルーしてしまう。 昨今の流れは「大きな否定」ではなく「小さな肯定」の積み重ねと鷲田さんは言う。 世代論ではないが、上の世代の「大きな否定」とは違う「小さな肯定」というムーブを認識しづらい上の世代の人にとっては、若い人のやっていることが奇怪に見えて仕方がないんだろうと思う。 「多様性」という言葉はアパルトヘイトの言い換えにすぎないのではないか。 強い言葉だけど、いわゆる知識人の本には等しくこの言説が飛び交う気がする。 安易な「多様性」ほど恐ろしいものはない。
ハム@unia2025年8月4日読み終わった今の若い人たちは〜みたいな言説って自分も言ってしまうけど同じ時代を生きているようで見えているものがまるで違うのだからアプローチだって違って当然なことを忘れがち。 歴史の脈拍を追うことは難しい。 鷲田さんクラスの人でもそうなのだから。 歴史を振り返ればそのムーブはおかしいとか、その流れは必然なのになぜ気付かなかったのかとか言えるけど、リアルタイムでそれらを把握することの難しさを人はスルーしてしまう。 昨今の流れは「大きな否定」ではなく「小さな肯定」の積み重ねと鷲田さんは言う。 世代論ではないが、上の世代の「大きな否定」とは違う「小さな肯定」というムーブを認識しづらい上の世代の人にとっては、若い人のやっていることが奇怪に見えて仕方がないんだろうと思う。 「多様性」という言葉はアパルトヘイトの言い換えにすぎないのではないか。 強い言葉だけど、いわゆる知識人の本には等しくこの言説が飛び交う気がする。 安易な「多様性」ほど恐ろしいものはない。




 極光@aurora_20192025年7月20日読み終わった「いろんな人と巡りあうとき、「誰」と向き合っているかが大切なのに、往々にしてどういう属性の「人」かしか視野に入れていないように見える。」という一文が刺さった。多様性を謳いながら、実際は自分と価値観の合う人としか関わらないようにして、静かに分断が進んでいく社会に警鐘を鳴らしているかのようだった。
極光@aurora_20192025年7月20日読み終わった「いろんな人と巡りあうとき、「誰」と向き合っているかが大切なのに、往々にしてどういう属性の「人」かしか視野に入れていないように見える。」という一文が刺さった。多様性を謳いながら、実際は自分と価値観の合う人としか関わらないようにして、静かに分断が進んでいく社会に警鐘を鳴らしているかのようだった。
 Rie@rie_books2025年6月16日気になる読みたい大好きな鷲田清一先生のエッセイとは、気になる。「聴くことの力」「死なないでいる理由」「大事なものは目に見えにくい」はどれも付箋がいっぱい付いた。
Rie@rie_books2025年6月16日気になる読みたい大好きな鷲田清一先生のエッセイとは、気になる。「聴くことの力」「死なないでいる理由」「大事なものは目に見えにくい」はどれも付箋がいっぱい付いた。



 朝日出版社@asahipress2025年6月9日出版社より過去に起きたことにはどういった蓄積、連なりがあったのか、 いま起きていることはこの先にどうつながっていくのか? 戦禍のウクライナから来日した詩人のことば、「透明化されている人々」に言及し話題を呼んだ投稿など、 いま私たちが直面する問題について、鷲田さんの言葉でひも解く一冊です。 ぜひめくってみてください。
朝日出版社@asahipress2025年6月9日出版社より過去に起きたことにはどういった蓄積、連なりがあったのか、 いま起きていることはこの先にどうつながっていくのか? 戦禍のウクライナから来日した詩人のことば、「透明化されている人々」に言及し話題を呼んだ投稿など、 いま私たちが直面する問題について、鷲田さんの言葉でひも解く一冊です。 ぜひめくってみてください。









 ✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年6月7日読んでる"(略)問題提起は、この社会のあり方が辛い、苦しい、不平等で悔しいという人たちからしかなされない。そういう人たちの異議申し立てがなかったら、今日いわれる性差別やパワーハラスメントも問題として浮上してはこなかったのだ。 ホロコースト生還者、エリ・ヴィーゼルの言葉を引けば、「愛の反対は憎しみではない。無関心だ」。関心(インタレスト)を持ちあうというこの相互のリスペクトがあってはじめて民主主義は機能する。"
✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年6月7日読んでる"(略)問題提起は、この社会のあり方が辛い、苦しい、不平等で悔しいという人たちからしかなされない。そういう人たちの異議申し立てがなかったら、今日いわれる性差別やパワーハラスメントも問題として浮上してはこなかったのだ。 ホロコースト生還者、エリ・ヴィーゼルの言葉を引けば、「愛の反対は憎しみではない。無関心だ」。関心(インタレスト)を持ちあうというこの相互のリスペクトがあってはじめて民主主義は機能する。"