

ハム
@unia
読んでいて特に印象に残った語りたい作品をピックアップ。
- 2025年10月27日
 この国の同調圧力山崎雅弘読み終わったなぜ日本人が同調圧力に弱いのかという問いはかなり気になったのだけど、その起源を辿る本ではなかった。 戦時中のエピソードが多く、同調圧力による負の側面を押し出しているけどそれは現在から考えるからそう言えるだけなのでは?とも少し思ってしまう。 当時は人道的、人権といった概念も今とは比較にならないものだし、特攻や集団自決が同調圧力ってそうなんだけど他の選択肢が考えられないからなぁ。 もちろん著者の意図が戦争の判断の断罪とかじゃなくて同調圧力という思想のインフラが及ぼす影響への警鐘だからこそインパクトのあるエピソードを出しているのだろうけど。 同調圧力に弱い起源については、日本語の文脈依存の性質、主語を特定させない語り、曖昧な表現の多用みたいな言語的なところに根ざしているんじゃないかと仮説をたててみた。 宗教観、自然観とかもありそうだけど、このあたりは日本語との兼ね合いで双方に影響を与えていそうな気がする。
この国の同調圧力山崎雅弘読み終わったなぜ日本人が同調圧力に弱いのかという問いはかなり気になったのだけど、その起源を辿る本ではなかった。 戦時中のエピソードが多く、同調圧力による負の側面を押し出しているけどそれは現在から考えるからそう言えるだけなのでは?とも少し思ってしまう。 当時は人道的、人権といった概念も今とは比較にならないものだし、特攻や集団自決が同調圧力ってそうなんだけど他の選択肢が考えられないからなぁ。 もちろん著者の意図が戦争の判断の断罪とかじゃなくて同調圧力という思想のインフラが及ぼす影響への警鐘だからこそインパクトのあるエピソードを出しているのだろうけど。 同調圧力に弱い起源については、日本語の文脈依存の性質、主語を特定させない語り、曖昧な表現の多用みたいな言語的なところに根ざしているんじゃないかと仮説をたててみた。 宗教観、自然観とかもありそうだけど、このあたりは日本語との兼ね合いで双方に影響を与えていそうな気がする。 - 2025年10月24日
- 2025年10月23日
 「ルフィ」の子どもたち週刊SPA!編集部特殊詐欺取材班読み終わった「ルフィ」すら駒のひとつって犯罪組織の闇の深さがなんとも。そんなのドラマの中だけの世界であってほしい。 単に社会システムの歯車にたまたま噛み合わなかったがために闇バイトの世界に足を踏み入れてしまったみたいな構図もみえる。 もちろん犯罪はダメなんだけど、「親ガチャの哲学」での議論のように社会的包摂性の在り方が問われている気がする。 情弱ビジネスなんかもイタチごっこで取り締まりも難しいだろうし、インパクトは大きいのに一筋縄にはいかない難しい問題だと思う。
「ルフィ」の子どもたち週刊SPA!編集部特殊詐欺取材班読み終わった「ルフィ」すら駒のひとつって犯罪組織の闇の深さがなんとも。そんなのドラマの中だけの世界であってほしい。 単に社会システムの歯車にたまたま噛み合わなかったがために闇バイトの世界に足を踏み入れてしまったみたいな構図もみえる。 もちろん犯罪はダメなんだけど、「親ガチャの哲学」での議論のように社会的包摂性の在り方が問われている気がする。 情弱ビジネスなんかもイタチごっこで取り締まりも難しいだろうし、インパクトは大きいのに一筋縄にはいかない難しい問題だと思う。 - 2025年10月20日
 MONKEY vol. 37 特集 猿の英単語スイッチ・パブリッシング,柴田元幸読み終わった翻訳の特集も英単語ひとつひとつを深掘りしててかなりおもしろかったんだけど、それよりも前回なかなかの衝撃だったオーイン・マクナミーの短編が今回も読めて、それに対する評論がまた良かった。 オーイン・マクナミーに漂う悲哀の始原を探る論考はデカルトやレヴィ=ストロースから神経科学者や音楽家までを貫くダイナミックさ。 ここまでのものを論じることはないにしてもオーイン・マクナミーには強い印象をもったし、悲哀という感じすごくわかる。日本語で読めるものがあまりないというのはちょっと残念。
MONKEY vol. 37 特集 猿の英単語スイッチ・パブリッシング,柴田元幸読み終わった翻訳の特集も英単語ひとつひとつを深掘りしててかなりおもしろかったんだけど、それよりも前回なかなかの衝撃だったオーイン・マクナミーの短編が今回も読めて、それに対する評論がまた良かった。 オーイン・マクナミーに漂う悲哀の始原を探る論考はデカルトやレヴィ=ストロースから神経科学者や音楽家までを貫くダイナミックさ。 ここまでのものを論じることはないにしてもオーイン・マクナミーには強い印象をもったし、悲哀という感じすごくわかる。日本語で読めるものがあまりないというのはちょっと残念。 - 2025年10月18日
- 2025年10月16日
 書かずにいられない味がある八田靖史,イ・サン(李相),イ・サン(李相)読み終わった韓国ドラマ「暴君のシェフ」がおもしろかったので食に関するものが読みたいと思っていたら絶妙なタイミングでいい本が出てた。 韓国の食に関する小説やエッセイなど、読んでて食欲をそそる話がいっぱい。 小説もエッセイも時代を反映したものが多くてあまり馴染みない文化に触れることができてよかった。 出前や飲食店で働くルポが特に当時の人間模様とかも垣間見れておもしろかった。 時代もあって食べることと生きることが密接なことが文学を通しても伝わってくる。 あー、ユッケジャン麺とか食べたくなる。
書かずにいられない味がある八田靖史,イ・サン(李相),イ・サン(李相)読み終わった韓国ドラマ「暴君のシェフ」がおもしろかったので食に関するものが読みたいと思っていたら絶妙なタイミングでいい本が出てた。 韓国の食に関する小説やエッセイなど、読んでて食欲をそそる話がいっぱい。 小説もエッセイも時代を反映したものが多くてあまり馴染みない文化に触れることができてよかった。 出前や飲食店で働くルポが特に当時の人間模様とかも垣間見れておもしろかった。 時代もあって食べることと生きることが密接なことが文学を通しても伝わってくる。 あー、ユッケジャン麺とか食べたくなる。 - 2025年10月14日
 知里幸惠 アイヌ神謡集中川裕読み終わった「ユーカラおとめ」を読んだ流れで。 アイヌが共にした自然、文化、言語を残したいという想いが詰まった知里幸恵の命を賭した作品。 環境問題うんぬんと御託を並べるよりこうした自然への畏敬の念を疎かにしないアイヌのような文化的メンタリティを学ぶことのほうがよほど大事なんじゃないかと思う。 ウサギが鹿くらい大きかったのに小さくなった話、可愛さと怖さが混じった話としてわかりやすいから印象に残ったけどいろんな神話に様々なメッセージを込めて語り継ぐ口承文学って文化の保存の観点からするとかなりハードル高いんだろうなと思う。 マイノリティとして追いやられていたらなおさら。 知里幸恵の熱量が込められたものがこうしてきちんと残って良かったと思う。
知里幸惠 アイヌ神謡集中川裕読み終わった「ユーカラおとめ」を読んだ流れで。 アイヌが共にした自然、文化、言語を残したいという想いが詰まった知里幸恵の命を賭した作品。 環境問題うんぬんと御託を並べるよりこうした自然への畏敬の念を疎かにしないアイヌのような文化的メンタリティを学ぶことのほうがよほど大事なんじゃないかと思う。 ウサギが鹿くらい大きかったのに小さくなった話、可愛さと怖さが混じった話としてわかりやすいから印象に残ったけどいろんな神話に様々なメッセージを込めて語り継ぐ口承文学って文化の保存の観点からするとかなりハードル高いんだろうなと思う。 マイノリティとして追いやられていたらなおさら。 知里幸恵の熱量が込められたものがこうしてきちんと残って良かったと思う。 - 2025年10月10日
 ユーカラおとめ泉ゆたか読み終わった金田一京助がかなり嫌なやつに描かれていた。 時代的なこともあるけど本人にはさほど悪気がないのがまたなんとも… 女性に対して、アイヌに対して、今の時代ではアウトな態度がどこまで本当かはわからないけど当時の認識としてあのようことが多くあったことは事実だし、それが知里幸恵にとってモチベーションにも負担にもなっていたのかなと思う。 時代のひと言で済まされてしまいがちだけど、もう少しうまいやり方があったのではないかと思ってしまう。 知里幸恵という人の生涯があまりにも軽んじられているように思えてしかたかない。 彼女が命をかけて成しえたものが語り継がれて評価されているのがせめてもの救い。 普段マジョリティに属していたり、日本みたいな「誇り」という概念に控えめな国にいるからこそ彼女のような自分を犠牲にしてまでアイヌを守ろうとする意志に強い印象を覚え、心を動かされるのかなと思いました。
ユーカラおとめ泉ゆたか読み終わった金田一京助がかなり嫌なやつに描かれていた。 時代的なこともあるけど本人にはさほど悪気がないのがまたなんとも… 女性に対して、アイヌに対して、今の時代ではアウトな態度がどこまで本当かはわからないけど当時の認識としてあのようことが多くあったことは事実だし、それが知里幸恵にとってモチベーションにも負担にもなっていたのかなと思う。 時代のひと言で済まされてしまいがちだけど、もう少しうまいやり方があったのではないかと思ってしまう。 知里幸恵という人の生涯があまりにも軽んじられているように思えてしかたかない。 彼女が命をかけて成しえたものが語り継がれて評価されているのがせめてもの救い。 普段マジョリティに属していたり、日本みたいな「誇り」という概念に控えめな国にいるからこそ彼女のような自分を犠牲にしてまでアイヌを守ろうとする意志に強い印象を覚え、心を動かされるのかなと思いました。 - 2025年10月8日
 大谷翔平の社会学内野宗治読み終わった大谷翔平のことというより大谷翔平から透けて見える社会についての本で、けっこう社会学してておもしろかった。 日本という国が閉鎖的なことが改めて浮き彫りになった。 バースの記録阻止、バレンティン差し置いての村上宗隆の記録賛辞とか昔から今に至るまで変わらない部分があるのは残念。 野茂英雄がドジャース入団の経緯、きちんと知らなかった。売国奴とまで言われての掌返し、日本っぽいな。 田澤ルールなんてのもあったな。 日本の政治や経済が停滞しているほどスポーツに向かう力が強まり優秀な選手が出てくるなんていう指摘もおもしろい。 NPBや日本のメディアの問題点を大谷翔平を通して語ることでスッキリ理解できた。 良くも悪くも稀代のアイコンとして大谷翔平を消費している日本の闇が垣間見えた。
大谷翔平の社会学内野宗治読み終わった大谷翔平のことというより大谷翔平から透けて見える社会についての本で、けっこう社会学してておもしろかった。 日本という国が閉鎖的なことが改めて浮き彫りになった。 バースの記録阻止、バレンティン差し置いての村上宗隆の記録賛辞とか昔から今に至るまで変わらない部分があるのは残念。 野茂英雄がドジャース入団の経緯、きちんと知らなかった。売国奴とまで言われての掌返し、日本っぽいな。 田澤ルールなんてのもあったな。 日本の政治や経済が停滞しているほどスポーツに向かう力が強まり優秀な選手が出てくるなんていう指摘もおもしろい。 NPBや日本のメディアの問題点を大谷翔平を通して語ることでスッキリ理解できた。 良くも悪くも稀代のアイコンとして大谷翔平を消費している日本の闇が垣間見えた。 - 2025年10月3日
 性と芸術会田誠読み終わったキャンセルカルチャーに見舞われた会田誠が自身の作品について解説しているのだけど、芸術家が言葉で表現しなきゃならないというなんて野暮な社会なのだろう。 でも芸術への向き合い方って義務教育でもあまり踏み込まないし、積極的に学んでいかないと理解しにくい側面があるから感性だけで芸術家の表現を受け止めきれないのはけっこうな頻度で起きてしまっている気がする。 〈私は芸術というものは「一つのメッセージを伝える容器」という役割をなるべく拒絶すべきだと考えている。〉 〈芸術はそういった一般的な言語・思考の空間と同じ次元にあるべきではない。それでは「わざわざ芸術をやる意味」がなくなってしまう。 私は芸術は究極的には何も主張しないと思っている。芸術はナンセンスを、意味の絶対零度を目指す。〉 この本を読むと彼の作品の意図や彼自身が思うところの芸術の意味をしっかり体現していることがよくわかるし、読んだうえで作品を見ると確かな納得感もあって、会田誠の芸術家としての評価も頷けると思う。 でも芸術にふだんあまり馴染みのない人が彼の「犬」を見たら、特にフェミニストたちが怒るのもわからんでもないけど、不一致や不和を生むという視点を見落としてるから話が平行線なんだろう。 議論も織り込み済みな芸術を提示しているのだけど、万人が納得するのは無理ということがまた芸術が存在する下地でもある気がする。 ニーチェ、ランシエール、松岡正剛、永井玲衣、など最近に読んだ人たちの思想との親和性があって思考が深まる読書でした。
性と芸術会田誠読み終わったキャンセルカルチャーに見舞われた会田誠が自身の作品について解説しているのだけど、芸術家が言葉で表現しなきゃならないというなんて野暮な社会なのだろう。 でも芸術への向き合い方って義務教育でもあまり踏み込まないし、積極的に学んでいかないと理解しにくい側面があるから感性だけで芸術家の表現を受け止めきれないのはけっこうな頻度で起きてしまっている気がする。 〈私は芸術というものは「一つのメッセージを伝える容器」という役割をなるべく拒絶すべきだと考えている。〉 〈芸術はそういった一般的な言語・思考の空間と同じ次元にあるべきではない。それでは「わざわざ芸術をやる意味」がなくなってしまう。 私は芸術は究極的には何も主張しないと思っている。芸術はナンセンスを、意味の絶対零度を目指す。〉 この本を読むと彼の作品の意図や彼自身が思うところの芸術の意味をしっかり体現していることがよくわかるし、読んだうえで作品を見ると確かな納得感もあって、会田誠の芸術家としての評価も頷けると思う。 でも芸術にふだんあまり馴染みのない人が彼の「犬」を見たら、特にフェミニストたちが怒るのもわからんでもないけど、不一致や不和を生むという視点を見落としてるから話が平行線なんだろう。 議論も織り込み済みな芸術を提示しているのだけど、万人が納得するのは無理ということがまた芸術が存在する下地でもある気がする。 ニーチェ、ランシエール、松岡正剛、永井玲衣、など最近に読んだ人たちの思想との親和性があって思考が深まる読書でした。 - 2025年9月26日
 熊になったわたし 人類学者、シベリアで世界の狭間に生きるナスターシャ・マルタン,大石侑香,高野優読み終わった人間主体で物事を考えすぎるのは文明化した時代にはなかなか避けられないからこそこういった人類学ベースの知見が大事なのだと思う。 熊と人が混じっているとか、つながっているとか正直なところよくわからないんだけれど、著者自身もそれらをわからないまま悩み、模索し、人類学的な方法論で向き合っていく過程は読み物としてもおもしろい。 自分のなかに熊が同居する人はなかなかいないだろうけど、個人のアイデンティティは程度の差こそあれさまざまなものが混じることで作られていくことを考えると、自分であっても自分という人間についてはわからないことのほうが多いのかも。 フィールドワークしている文化に根ざした価値観の反映があれど熊に噛まれたことをトラウマにせず向き合う著者の胆力には驚く。 いろいろ揺さぶってくれた。
熊になったわたし 人類学者、シベリアで世界の狭間に生きるナスターシャ・マルタン,大石侑香,高野優読み終わった人間主体で物事を考えすぎるのは文明化した時代にはなかなか避けられないからこそこういった人類学ベースの知見が大事なのだと思う。 熊と人が混じっているとか、つながっているとか正直なところよくわからないんだけれど、著者自身もそれらをわからないまま悩み、模索し、人類学的な方法論で向き合っていく過程は読み物としてもおもしろい。 自分のなかに熊が同居する人はなかなかいないだろうけど、個人のアイデンティティは程度の差こそあれさまざまなものが混じることで作られていくことを考えると、自分であっても自分という人間についてはわからないことのほうが多いのかも。 フィールドワークしている文化に根ざした価値観の反映があれど熊に噛まれたことをトラウマにせず向き合う著者の胆力には驚く。 いろいろ揺さぶってくれた。 - 2025年9月24日
 月魄の楽響 -Fêtes galantes-: ヴェルレーヌ詩集ポール・ヴェルレーヌ,祇遠偲世読み終わったヴェルレーヌの詩を初めて読んだ。 まず翻訳をした方の技量がすごい。 あとがきにも書かれていたように、全体を崩すことなく一語を崩すことができないのが詩であって、まさに翻訳をする過程で再創造を成し遂げている。 原著はどう表現されているのか気になるほどの描写と表現に呑み込まれた。 美しい旋律のクラシックを聴いているかのように、幻想的な世界に浸れる芸術的な詩だった。 叙情性、神秘性、厳かさ、美しさが調和していて、「初恋」が特に印象的だった。 高き底靴(ヒール)に裳裾(もすも)をたなびかせ 坂なす路欄をめぐりて歩く影ひとつ 時に涼風葉を揺らし 木漏れる光と梳けこむ 白き脚 -誰もが享受する憧憬(せかい)に心は奪われる 時として木陰のベンチと腰掛けて 植梢を眺める瞳の美しさ 嫉妬の矢となり飛び交う あげは蝶 ブラウスの襟をほどいてはららぐ その瞬間 純白の胸売にて眠る在りし日の 記憶よ明滅 (いかずち)よみがえる 砂金ときらめく暮秋のかえで 落ち葉なす時間にふたり寄りそうて 夢は泡影 夜月と浮んで腕をとり -いとも恥ずかし気に- 互いの名前を奏でてささやいた 幸悦たる言葉に満ちた 思い出よ
月魄の楽響 -Fêtes galantes-: ヴェルレーヌ詩集ポール・ヴェルレーヌ,祇遠偲世読み終わったヴェルレーヌの詩を初めて読んだ。 まず翻訳をした方の技量がすごい。 あとがきにも書かれていたように、全体を崩すことなく一語を崩すことができないのが詩であって、まさに翻訳をする過程で再創造を成し遂げている。 原著はどう表現されているのか気になるほどの描写と表現に呑み込まれた。 美しい旋律のクラシックを聴いているかのように、幻想的な世界に浸れる芸術的な詩だった。 叙情性、神秘性、厳かさ、美しさが調和していて、「初恋」が特に印象的だった。 高き底靴(ヒール)に裳裾(もすも)をたなびかせ 坂なす路欄をめぐりて歩く影ひとつ 時に涼風葉を揺らし 木漏れる光と梳けこむ 白き脚 -誰もが享受する憧憬(せかい)に心は奪われる 時として木陰のベンチと腰掛けて 植梢を眺める瞳の美しさ 嫉妬の矢となり飛び交う あげは蝶 ブラウスの襟をほどいてはららぐ その瞬間 純白の胸売にて眠る在りし日の 記憶よ明滅 (いかずち)よみがえる 砂金ときらめく暮秋のかえで 落ち葉なす時間にふたり寄りそうて 夢は泡影 夜月と浮んで腕をとり -いとも恥ずかし気に- 互いの名前を奏でてささやいた 幸悦たる言葉に満ちた 思い出よ - 2025年9月19日
 マザーツリースザンヌ・シマード,三木直子読み終わった森や自然といった生態系が人のように複雑なネットワークでつながっているというのは漠然と知ってはいても、それが発見されて周りに理解してもらうための道のりにこれほどまでの苦労があったとは思わなかった。 ひとつの研究に対する想い、苦しみなどのすごい熱量をエッセンスだけ読めるというのはなんという贅沢なことかと思う。 自伝的な語りの中にかなり専門性の高い話も織り込まれて読み応えがすごい。小難しい話も多くてけっこう体力もっていかれるけど深い森を進んでいくような感覚と共に自然の癒やしを感じる。 人間は自然の一部であり、生かされている存在であるということを強く意識すべき。森や自然への畏敬の念を、マイナスイオンを感じられるような作品だった。
マザーツリースザンヌ・シマード,三木直子読み終わった森や自然といった生態系が人のように複雑なネットワークでつながっているというのは漠然と知ってはいても、それが発見されて周りに理解してもらうための道のりにこれほどまでの苦労があったとは思わなかった。 ひとつの研究に対する想い、苦しみなどのすごい熱量をエッセンスだけ読めるというのはなんという贅沢なことかと思う。 自伝的な語りの中にかなり専門性の高い話も織り込まれて読み応えがすごい。小難しい話も多くてけっこう体力もっていかれるけど深い森を進んでいくような感覚と共に自然の癒やしを感じる。 人間は自然の一部であり、生かされている存在であるということを強く意識すべき。森や自然への畏敬の念を、マイナスイオンを感じられるような作品だった。 - 2025年9月18日
 アリ語で寝言を言いました村上貴弘読み終わったアリの世界が働き方や社会の在り方を考えるうえで人間の世界の縮図となりうるのおもしろい。 多様性が大事なのはその通りなのだけど、ブラックな環境で生き抜いた種もあれば、ぼーっとほどほどの環境を取る種もあって、そのどちらも正解とされる。 さらには血縁度マックスで多様性の戦略をとらないでも長く繁栄している種もある。 アリの生態には種の存続、繁栄において学ぶべき点が多いことがよくわかる。 進化の過程において、フリーライドするような一見すると悪になるものが複雑化、多様化の鍵だったりする。 なんでもかんでも正義は正しく悪は駆逐でもないとするのもおもしろい点。 人間は本当に覇権を取っているのかという前提を大きく揺さぶる。 利用されているのは誰なのか。 アリの世界を面白おかしく見ながらここまで深い思索に耽ることができるとは思わなかった。 ゴリラからアリへの読書の旅、おもしろかった。
アリ語で寝言を言いました村上貴弘読み終わったアリの世界が働き方や社会の在り方を考えるうえで人間の世界の縮図となりうるのおもしろい。 多様性が大事なのはその通りなのだけど、ブラックな環境で生き抜いた種もあれば、ぼーっとほどほどの環境を取る種もあって、そのどちらも正解とされる。 さらには血縁度マックスで多様性の戦略をとらないでも長く繁栄している種もある。 アリの生態には種の存続、繁栄において学ぶべき点が多いことがよくわかる。 進化の過程において、フリーライドするような一見すると悪になるものが複雑化、多様化の鍵だったりする。 なんでもかんでも正義は正しく悪は駆逐でもないとするのもおもしろい点。 人間は本当に覇権を取っているのかという前提を大きく揺さぶる。 利用されているのは誰なのか。 アリの世界を面白おかしく見ながらここまで深い思索に耽ることができるとは思わなかった。 ゴリラからアリへの読書の旅、おもしろかった。 - 2025年9月17日
 ゴリラからの警告山極寿一読み終わったゴリラの視点を通して人間社会のおかしな点を知る試み。 人間は人間の世界だけを見ているためにそれが当たり前になっている。人間は元々どうだったのか、今ある社会は当たり前なのかという視点を持つことを怠る。 まさかゴリラにその気づきを与えられるとは。 祖先を同じとするゴリラの社会を通して浮かび上がる人間の特性やゴリラとの違いを認識することが今の世界を改めて俯瞰して眺める一助となるのがおもしろい。 他の何かを持ってきて比べるというアプローチから自分を自分たらしめているものを知る。 あらゆることに対してこのような視点を持つことの必要性が感じられた。
ゴリラからの警告山極寿一読み終わったゴリラの視点を通して人間社会のおかしな点を知る試み。 人間は人間の世界だけを見ているためにそれが当たり前になっている。人間は元々どうだったのか、今ある社会は当たり前なのかという視点を持つことを怠る。 まさかゴリラにその気づきを与えられるとは。 祖先を同じとするゴリラの社会を通して浮かび上がる人間の特性やゴリラとの違いを認識することが今の世界を改めて俯瞰して眺める一助となるのがおもしろい。 他の何かを持ってきて比べるというアプローチから自分を自分たらしめているものを知る。 あらゆることに対してこのような視点を持つことの必要性が感じられた。 - 2025年9月16日
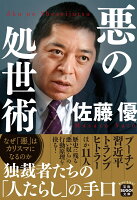 悪の処世術佐藤優読み終わった悪とは何なのか。 立場によって変わるものをどう捉えていけばいいのかわからなくなる。 プーチンも習近平も金正恩も保身がゼロではないとはいえ国を思っての政治をしている。 でも日本から見ればありえないふるまいに見えてしまう。 アルバニアの独裁者エンベル・ホッジャについては知らなかったけどここにも彼なりの強い正義があることがわかる。 自由と平等はトレードオフと言うけれど、「自由だけど食えない」と「自由はないけど飢えることはない」はどちらがいいのか。 もちろん単純な二元論ではないのだけれど、一概にこちらとは言えない。 ヒトラーのくだりもけっこう今のこの時代とリンクする部分も多いし、いわゆる独裁者とされる人たちから見えてくること、考えるヒントになることが多いことがよくわかる。
悪の処世術佐藤優読み終わった悪とは何なのか。 立場によって変わるものをどう捉えていけばいいのかわからなくなる。 プーチンも習近平も金正恩も保身がゼロではないとはいえ国を思っての政治をしている。 でも日本から見ればありえないふるまいに見えてしまう。 アルバニアの独裁者エンベル・ホッジャについては知らなかったけどここにも彼なりの強い正義があることがわかる。 自由と平等はトレードオフと言うけれど、「自由だけど食えない」と「自由はないけど飢えることはない」はどちらがいいのか。 もちろん単純な二元論ではないのだけれど、一概にこちらとは言えない。 ヒトラーのくだりもけっこう今のこの時代とリンクする部分も多いし、いわゆる独裁者とされる人たちから見えてくること、考えるヒントになることが多いことがよくわかる。 - 2025年9月12日
 世界のほうがおもしろすぎた松岡正剛読み終わったインタビュー形式での語りなので自著や対談のような知の応酬がないためいつもよりは超ハイコンテクスト味が少なくて話がすっと入ってくる。 「雑誌の記事として椎名林檎を取り上げるんじゃなくて、メディアが椎名林檎化するにはどうするかを考える」 松岡正剛さんの言う編集という概念を考えるうえでこの例えは参考になる。 松岡さんって度々と椎名林檎について言及してるイメージがあるけどかなり好きなんだろうな。 なんとなくその気持ちはわかる。 寺田寅彦を読んでいて松岡正剛をイメージしたけど、この本で寺田寅彦からの影響について言ってる箇所があって、俳諧精神と割れ目の科学だと。 これは松岡正剛さんを知るうえでかなり腑に落ちた。 松岡正剛という存在について、考えてきたことについてわからないなりに解像度は上がった気がする。 これだけすごい松岡正剛という存在もいまいち世間的には知られてなかったり正体がはっきりしないという感じがなんともカッコいい。 編集工学、目の付け所、考え方などいろんなことのヒントが多く、学ぶべきことが詰まった素晴らしい一冊。 インタビュアーの話の引き出し方も上手いからこそなんだと思う。 めちゃくちゃ良かった。
世界のほうがおもしろすぎた松岡正剛読み終わったインタビュー形式での語りなので自著や対談のような知の応酬がないためいつもよりは超ハイコンテクスト味が少なくて話がすっと入ってくる。 「雑誌の記事として椎名林檎を取り上げるんじゃなくて、メディアが椎名林檎化するにはどうするかを考える」 松岡正剛さんの言う編集という概念を考えるうえでこの例えは参考になる。 松岡さんって度々と椎名林檎について言及してるイメージがあるけどかなり好きなんだろうな。 なんとなくその気持ちはわかる。 寺田寅彦を読んでいて松岡正剛をイメージしたけど、この本で寺田寅彦からの影響について言ってる箇所があって、俳諧精神と割れ目の科学だと。 これは松岡正剛さんを知るうえでかなり腑に落ちた。 松岡正剛という存在について、考えてきたことについてわからないなりに解像度は上がった気がする。 これだけすごい松岡正剛という存在もいまいち世間的には知られてなかったり正体がはっきりしないという感じがなんともカッコいい。 編集工学、目の付け所、考え方などいろんなことのヒントが多く、学ぶべきことが詰まった素晴らしい一冊。 インタビュアーの話の引き出し方も上手いからこそなんだと思う。 めちゃくちゃ良かった。 - 2025年9月7日
 宗教と暴力 激動する世界と宗教 (角川学芸出版単行本)佐藤優,松岡正剛,池上彰,石川明人,高岡豊読み終わった松岡正剛さんと佐藤優さんのポジショントークを許さない鋭い切り込みに若い二人が戦々恐々としている様子が目に浮かぶ。 池上さんは安定の対応力、池上さんがいなかったら空気張り詰めきってしんどそう。 宗教と暴力というテーマがここまで裏表くるくると視点の転回があるとは。 暴力がどこに根差すものなのかは議論の立ち位置で変わるため定義も定めにくい。 宗教が普遍主義か否かのくだりも一筋縄にはいかない視点の提示は勉強になる。 松岡正剛さんが雑多な視点から話を振る最後のパネルディスカッションを見てると、専門性を持って語ることは重要なんだけど一面的な印象になりがちなのがよくわかる。 だからこそ若い専門家ふたりにキラーパスを出す松岡正剛さんの凄さが際立つけど、愛あるものとわかっても怖いだろうなあ。
宗教と暴力 激動する世界と宗教 (角川学芸出版単行本)佐藤優,松岡正剛,池上彰,石川明人,高岡豊読み終わった松岡正剛さんと佐藤優さんのポジショントークを許さない鋭い切り込みに若い二人が戦々恐々としている様子が目に浮かぶ。 池上さんは安定の対応力、池上さんがいなかったら空気張り詰めきってしんどそう。 宗教と暴力というテーマがここまで裏表くるくると視点の転回があるとは。 暴力がどこに根差すものなのかは議論の立ち位置で変わるため定義も定めにくい。 宗教が普遍主義か否かのくだりも一筋縄にはいかない視点の提示は勉強になる。 松岡正剛さんが雑多な視点から話を振る最後のパネルディスカッションを見てると、専門性を持って語ることは重要なんだけど一面的な印象になりがちなのがよくわかる。 だからこそ若い専門家ふたりにキラーパスを出す松岡正剛さんの凄さが際立つけど、愛あるものとわかっても怖いだろうなあ。 - 2025年9月6日
 ピタゴラスと豆寺田寅彦読み終わった風邪を半分ひいていると風邪をこじらせないみたいな話から類推して「いつも非常時の一歩手前の心持を持続するのが本当の非常時を招致しないための護符になるという奇論にも真実があるかも」と捉えたり、「弱いものの負け惜しみの中にも半面の真がある」と捉えたり、 こうしたスタンスは大事だよなと思ったところにマスクをする人しない人、免疫に差が出る出ないみたい話がさらに出てきて驚いた。 似たようなことをずっと人は議論してんだなと。 昭和9年から現代に至ってもまだはっきりしないことはもちろんあるだろうけど、 寺田寅彦の時代を経ても色褪せない語りと目の付け所のキレキレ具合がすごい。
ピタゴラスと豆寺田寅彦読み終わった風邪を半分ひいていると風邪をこじらせないみたいな話から類推して「いつも非常時の一歩手前の心持を持続するのが本当の非常時を招致しないための護符になるという奇論にも真実があるかも」と捉えたり、「弱いものの負け惜しみの中にも半面の真がある」と捉えたり、 こうしたスタンスは大事だよなと思ったところにマスクをする人しない人、免疫に差が出る出ないみたい話がさらに出てきて驚いた。 似たようなことをずっと人は議論してんだなと。 昭和9年から現代に至ってもまだはっきりしないことはもちろんあるだろうけど、 寺田寅彦の時代を経ても色褪せない語りと目の付け所のキレキレ具合がすごい。 - 2025年9月5日
 科学と文学寺田寅彦読み終わった科学と文学が根っこのところではつながっているのは同意。でも日本ってなぜか文系理系っていう妙な分け方をしてる稀有な国だからか両者をうまく動かしてる人材が少ない気がする。 寺田寅彦、中谷宇吉郎、湯川秀樹なんかは科学と文学のハイブリッドだし、近年でも松岡正剛、平野啓一郎、落合陽一あたりがぱっと浮かぶ。 確かに両輪をうまく稼働してて思考の深みがえぐい。 文学過多な人にとっては科学って専門性が強く見えるうえに文学自体が人文の領域に閉じ込められがちだからかな。 そう考えるとSFなんかは良い架け橋なのか。娯楽としてでも科学的思考へのアクセスは日本には急務な気がする。 伊藤計劃、ユヴァル・ノア・ハラリあたりは考証もすごいし文学から科学のルートのお手本になるかな。 現代こそ文理なんて分けてないで学ばなきゃだけど、当時からこの思想を持つ寺田寅彦ってやっぱりすごいなと思う。
科学と文学寺田寅彦読み終わった科学と文学が根っこのところではつながっているのは同意。でも日本ってなぜか文系理系っていう妙な分け方をしてる稀有な国だからか両者をうまく動かしてる人材が少ない気がする。 寺田寅彦、中谷宇吉郎、湯川秀樹なんかは科学と文学のハイブリッドだし、近年でも松岡正剛、平野啓一郎、落合陽一あたりがぱっと浮かぶ。 確かに両輪をうまく稼働してて思考の深みがえぐい。 文学過多な人にとっては科学って専門性が強く見えるうえに文学自体が人文の領域に閉じ込められがちだからかな。 そう考えるとSFなんかは良い架け橋なのか。娯楽としてでも科学的思考へのアクセスは日本には急務な気がする。 伊藤計劃、ユヴァル・ノア・ハラリあたりは考証もすごいし文学から科学のルートのお手本になるかな。 現代こそ文理なんて分けてないで学ばなきゃだけど、当時からこの思想を持つ寺田寅彦ってやっぱりすごいなと思う。
読み込み中...

