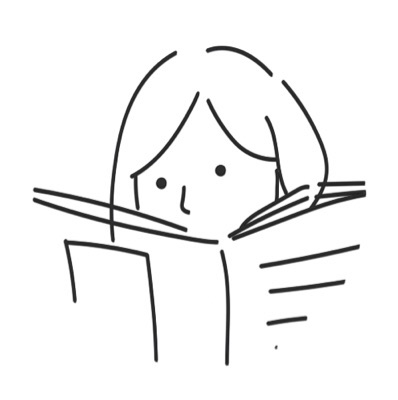無意味なんかじゃない自分 ハンセン病作家・北條民雄を読む

59件の記録
 日向コイケ@hygkik2026年1月2日読んでる《困難な状況に陥った人が必死になって自分を鼓舞したり、「自分という存在は無意味なんかじゃないのだ」と叫ぼうとする時、つい同じような境遇の人たちより目立とうとしてしまったり、誰かに対して意地悪になってしまったり、時には攻撃的になってしまったりすることがあるのではないか、と。》
日向コイケ@hygkik2026年1月2日読んでる《困難な状況に陥った人が必死になって自分を鼓舞したり、「自分という存在は無意味なんかじゃないのだ」と叫ぼうとする時、つい同じような境遇の人たちより目立とうとしてしまったり、誰かに対して意地悪になってしまったり、時には攻撃的になってしまったりすることがあるのではないか、と。》- むこうやま@65yama_kana2025年12月11日読み終わった荒井裕樹さんのサントリー学芸賞受賞作。 ハンセン病にたいする厳然とした差別の様相をきっちり伝えながら、それでも北条民雄という人物をこんな憎めない感じで描けちゃうのは、相当な現場感覚があるからこそできることだよなぁと本当に尊敬する(逆に当事者たちの声を聞いてきた人にしかやってほしくないことではある)。 ゴールデンバットのエピソード含め、患者さんたちから聞き取ったことを分析の核として落とし込んでいくところが見事というか、そこが個人的にとても好きだった。こんなやり方を選択できる真摯さが荒井さんだなぁとしみじみ思う。

 花木コヘレト@qohelet2025年11月7日読み終わった図書館本ハンセン病本書において、筆者の荒井さんが北條民雄の素顔に迫れているのは、ひとえに、荒井さんの読書の幅の広さと蓄積、そして学者として文献の研究手順を踏まえていることに、負っていると思います。 その本書は、ハンセン病についての概説書的な役割も果たしながら、北條の代表作である「いのちの初夜」と、その裏面である彼の日記の、両者を分析しているのですから、もともと北條の読者であった人も、これから読者になろうとしている人も、手にとって損はない書籍となっています。 特に、本書の白眉は、北條の日記の(部分的ではあるにしろ)精密な読解にあるでしょう。この読解に筆者が成功したことによって、小説からでは読み解けない北條の素顔に、読者が接近することが許されるわけです。 北條民雄の小説は、ハンセン病文学という魅力を増して無類に面白いため、近代日本文学に関心を持つ方ならば、きっと本書も楽しめると思います。 もし、本書を読み終えた方で、かつ、まだ北條の作品に親しんでいない方がいらしたら、私としては、北條の「すみれ」という、文庫本で5ページほどの掌編をお読みになることをお勧めします。本書の補完的な役割を果たしてくれると思うからです。
花木コヘレト@qohelet2025年11月7日読み終わった図書館本ハンセン病本書において、筆者の荒井さんが北條民雄の素顔に迫れているのは、ひとえに、荒井さんの読書の幅の広さと蓄積、そして学者として文献の研究手順を踏まえていることに、負っていると思います。 その本書は、ハンセン病についての概説書的な役割も果たしながら、北條の代表作である「いのちの初夜」と、その裏面である彼の日記の、両者を分析しているのですから、もともと北條の読者であった人も、これから読者になろうとしている人も、手にとって損はない書籍となっています。 特に、本書の白眉は、北條の日記の(部分的ではあるにしろ)精密な読解にあるでしょう。この読解に筆者が成功したことによって、小説からでは読み解けない北條の素顔に、読者が接近することが許されるわけです。 北條民雄の小説は、ハンセン病文学という魅力を増して無類に面白いため、近代日本文学に関心を持つ方ならば、きっと本書も楽しめると思います。 もし、本書を読み終えた方で、かつ、まだ北條の作品に親しんでいない方がいらしたら、私としては、北條の「すみれ」という、文庫本で5ページほどの掌編をお読みになることをお勧めします。本書の補完的な役割を果たしてくれると思うからです。


 曖昧模糊@sukonbu_uo_ou_2025年10月20日読み始めた荒井さんの本は、ハッとさせられる問いかけが散りばめられていて、読むたびに足元から崩れるような衝撃を感じる。立ち止まって自分の足元を確認し、自分は何を感じ、考えるのかこれまでを立ち返る瞬間が毎回ある。
曖昧模糊@sukonbu_uo_ou_2025年10月20日読み始めた荒井さんの本は、ハッとさせられる問いかけが散りばめられていて、読むたびに足元から崩れるような衝撃を感じる。立ち止まって自分の足元を確認し、自分は何を感じ、考えるのかこれまでを立ち返る瞬間が毎回ある。




 ましろ@massirona2025年9月20日読み終わったそうせざるを得ないこと、そうせざるを得ない人への理解と寄り添いに感じ入る。丹念に追い、丁寧に見つめるからこその埋められない空白。客観的な知に留められない衝動と文学研究の醍醐味。問いにくい問い、せめぎ合う思いに人の姿を読む。
ましろ@massirona2025年9月20日読み終わったそうせざるを得ないこと、そうせざるを得ない人への理解と寄り添いに感じ入る。丹念に追い、丁寧に見つめるからこその埋められない空白。客観的な知に留められない衝動と文学研究の醍醐味。問いにくい問い、せめぎ合う思いに人の姿を読む。

 くりこ@kurikomone2025年8月27日読み終わった北条民雄の大ファンなので一気に読んだ! 彼の代表作『いのちの初夜』で、北条が「僕等」/「あの人たち」と線引きし「他の人と違う自分」を書いているという事、気が付かなかった。(これは私が北条を推しすぎて冷静に読めてなかったとこがある、反省) 後半、彼の日記を読むと「敵とすべき無いものを敵として、北条は自らを痛め虐げ、自らの地獄へと転げる」と言う言葉がしっくりくる。でもやっぱり私は死を常に意識しながらも書くことで自らを生きながらえようとする彼の姿勢に惹かれるし、「絶望しもがいている時こそ解放の始まりだ」と強く感じる。同じハンセン病患者をとげとげしく表現していたのも、もがいている渦中にあるからであって、もっと彼が生きながらえていたら本来の敵を撃つこともできたのではないかと思う。
くりこ@kurikomone2025年8月27日読み終わった北条民雄の大ファンなので一気に読んだ! 彼の代表作『いのちの初夜』で、北条が「僕等」/「あの人たち」と線引きし「他の人と違う自分」を書いているという事、気が付かなかった。(これは私が北条を推しすぎて冷静に読めてなかったとこがある、反省) 後半、彼の日記を読むと「敵とすべき無いものを敵として、北条は自らを痛め虐げ、自らの地獄へと転げる」と言う言葉がしっくりくる。でもやっぱり私は死を常に意識しながらも書くことで自らを生きながらえようとする彼の姿勢に惹かれるし、「絶望しもがいている時こそ解放の始まりだ」と強く感じる。同じハンセン病患者をとげとげしく表現していたのも、もがいている渦中にあるからであって、もっと彼が生きながらえていたら本来の敵を撃つこともできたのではないかと思う。





 くりこ@kurikomone2025年8月27日まだ読んでる北条民雄大好きだったのでずっと読みたかった本!やっと借りてきた! p.52 コロナの感染症拡大を防ぐための措置が患者の人権と抵触することや私たちが感染者に向けた眼差しが、 過去のハンセン病者への差別や偏見を反省したのものになっていないという指摘は大変重要だと思う ーーー P.169 北條にしても、彼が生み出した佐柄木にしても、「無意味なんかじゃない自分」を証明しようとして、苛酷な無限ループを走り続けているような節があります。 「自分の生命に意味がない」ということに抗いたくて小説を書くのだけれど、そもそも、その生命自体が小説のネタにもならないほど無意味なものかもしれない。でも、自分の生命が無意味なことは否定したいから小説を書く。でも、やはりそこに意味なんてないのかもしれない。果たして、自分は「生きる意味のある生命」を生きているのだろうか 自分の生命が無意味なものとして扱われる絶望と、自分の生命を無意味なものにしたくないという抗い。北條民雄の文学作品には、この二つの激しいせめぎ合いが通奏低音のように流れているわけです。
くりこ@kurikomone2025年8月27日まだ読んでる北条民雄大好きだったのでずっと読みたかった本!やっと借りてきた! p.52 コロナの感染症拡大を防ぐための措置が患者の人権と抵触することや私たちが感染者に向けた眼差しが、 過去のハンセン病者への差別や偏見を反省したのものになっていないという指摘は大変重要だと思う ーーー P.169 北條にしても、彼が生み出した佐柄木にしても、「無意味なんかじゃない自分」を証明しようとして、苛酷な無限ループを走り続けているような節があります。 「自分の生命に意味がない」ということに抗いたくて小説を書くのだけれど、そもそも、その生命自体が小説のネタにもならないほど無意味なものかもしれない。でも、自分の生命が無意味なことは否定したいから小説を書く。でも、やはりそこに意味なんてないのかもしれない。果たして、自分は「生きる意味のある生命」を生きているのだろうか 自分の生命が無意味なものとして扱われる絶望と、自分の生命を無意味なものにしたくないという抗い。北條民雄の文学作品には、この二つの激しいせめぎ合いが通奏低音のように流れているわけです。




 ヒナタ@hinata6251412025年8月4日読み終わった評伝は読むのに時間のかかるイメージだけど荒井さんの文章はやっぱり読みやすくて、文学者としてよりも一人の孤独な若者としての北條民雄のことを知ることができてよかった。北條の作品もこの夏のうちに読んでおきたいな。
ヒナタ@hinata6251412025年8月4日読み終わった評伝は読むのに時間のかかるイメージだけど荒井さんの文章はやっぱり読みやすくて、文学者としてよりも一人の孤独な若者としての北條民雄のことを知ることができてよかった。北條の作品もこの夏のうちに読んでおきたいな。




 ズゴ子@zugocco2025年8月3日読み終わった読了 ラストのページを3度読み返す いまよりもずっと不寛容な時代の差別 差別のなかにある友情や恋 後付けの純粋や崇高をふりかけるんじゃなく 当時のリアルを冷静にさぐるからこその力強さに 現代にもいきる勇気があるよな
ズゴ子@zugocco2025年8月3日読み終わった読了 ラストのページを3度読み返す いまよりもずっと不寛容な時代の差別 差別のなかにある友情や恋 後付けの純粋や崇高をふりかけるんじゃなく 当時のリアルを冷静にさぐるからこその力強さに 現代にもいきる勇気があるよな



 すべての本読み読み委員会@nadare2025年6月30日読み終わった同じ病気を持つ人々に対し「自分は"あいつら"とは違う」と優位に立ちたがる言動について。ここは深堀りしたい。長島愛生園に行きたい。3年前に行った多磨全生園の静けさと力強さ。あれは大事な思い出。
すべての本読み読み委員会@nadare2025年6月30日読み終わった同じ病気を持つ人々に対し「自分は"あいつら"とは違う」と優位に立ちたがる言動について。ここは深堀りしたい。長島愛生園に行きたい。3年前に行った多磨全生園の静けさと力強さ。あれは大事な思い出。




 つばめ@swallow32025年6月7日読み終わったコロナ禍の最初の頃、感染した人の行動履歴がこと細かに発表されて叩かれてたり、他県ナンバーの車に「県内在住です。」と張り紙してあったりしたのを見て、こんなに明確な差別が目の前にあらわれたことに驚いたのを思い出した。 コロナという未知の感染症だったとしても、感染してしまった人、リスクの高い人にここまで敵意を出せるとは… 差別はいけないと頭では分かっていても、自分も当時は人が多いところへ頻繁に外出する人に嫌悪感があったし、程度の大小はあれその差別に加担していたと思う。 とはいえ自分は人をバッシングしてまではないし…と、自分はまだマシな方だと正当化してしまうのは、そういうバイアスがあるのだろうか。 近いうちにハンセン病についての資料館に行きたいと思う。
つばめ@swallow32025年6月7日読み終わったコロナ禍の最初の頃、感染した人の行動履歴がこと細かに発表されて叩かれてたり、他県ナンバーの車に「県内在住です。」と張り紙してあったりしたのを見て、こんなに明確な差別が目の前にあらわれたことに驚いたのを思い出した。 コロナという未知の感染症だったとしても、感染してしまった人、リスクの高い人にここまで敵意を出せるとは… 差別はいけないと頭では分かっていても、自分も当時は人が多いところへ頻繁に外出する人に嫌悪感があったし、程度の大小はあれその差別に加担していたと思う。 とはいえ自分は人をバッシングしてまではないし…と、自分はまだマシな方だと正当化してしまうのは、そういうバイアスがあるのだろうか。 近いうちにハンセン病についての資料館に行きたいと思う。







 JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月24日読み終わった就寝前読書@ 自宅最後まで読む。「はじめに」で示された以下の疑問への答えが示される。 〈差別された人が、傷つけられた自尊心をなんとか守りたいと思った時、同じような境遇にある人たちに対して、居丈高になったり、意地悪になったりすることは認められるのか。/あるいは、自分が「差別されている集団」に所属していたとして、その苦しみから逃れるために「自分だけは違う」と言ったり考えたりすることは許されるのか。〉(17-18頁) さしあたりの結論を見て、嗚呼、荒井さんの本だなぁ、とにんまりしてしまった。 それにしても、第八章〜第一〇章の北條民雄の日記の読み解き、より正確には『全集』及び『定本』に収録された日記と原本(自筆本)とを比較しながらの読み解きが、とても面白かった。 北條にとって「作家」の条件とは何だったのか(第八章)、日記には何が、どのように書かれていたのか(第九章)、療友であり親友でもあった東條は、なぜ日記を書き換えたのか(第一〇章)。 テクストをつぶさに読み込むだけでなく、それが書きつけられた物や筆跡にも目を凝らす姿勢に、やっぱり荒井さんだなぁ、と嬉しくなる。 当初は結構、この本の「ですます調」の文体がやさしすぎる気がしていたのだけど(最初の何章かは基本的な解説パートが続くこともあり)、日記パートに辿り着く頃には、この文体は北條にかけられた〈崇高〉のヴェールをはがし、人間として向き合うために選び取られたものだったのかもしれないと、納得できる瞬間があった。 〈大切なのは、一人の人間が見せる振れ幅をきちんと捉えることでしょう。〉(230頁) 北條の振れ幅を知ることを通して、自分という一人の読者の中にある振れ幅をも大切に思える読書となった。 余談:第15回「(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞」の受賞スピーチで、荒井さんが以下のように語っていたけど、第一〇章の最後のほうの想像力の働かせ方には、こういう地道な経験が根底あるのでは、と思ったりもした(このスピーチは柏書房のwebマガジンで読めます)。 〈ハンセン病療養所では「昔の患者の言葉を書き写す」ということを、よくやっていました。私自身、昔の患者の残した言葉とどう向き合っていいのか分らなかったので、とにかく「書き写す」ということをしました。昭和初期の患者の手書きの原稿用紙が800枚くらい出てきたことがありました。それを一文字一文字、ワードファイルで書き写しました。[...]とにかく、患者の言葉をなぞることからはじめたのです。〉(「かしわもち」2022年5月2日より)
JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月24日読み終わった就寝前読書@ 自宅最後まで読む。「はじめに」で示された以下の疑問への答えが示される。 〈差別された人が、傷つけられた自尊心をなんとか守りたいと思った時、同じような境遇にある人たちに対して、居丈高になったり、意地悪になったりすることは認められるのか。/あるいは、自分が「差別されている集団」に所属していたとして、その苦しみから逃れるために「自分だけは違う」と言ったり考えたりすることは許されるのか。〉(17-18頁) さしあたりの結論を見て、嗚呼、荒井さんの本だなぁ、とにんまりしてしまった。 それにしても、第八章〜第一〇章の北條民雄の日記の読み解き、より正確には『全集』及び『定本』に収録された日記と原本(自筆本)とを比較しながらの読み解きが、とても面白かった。 北條にとって「作家」の条件とは何だったのか(第八章)、日記には何が、どのように書かれていたのか(第九章)、療友であり親友でもあった東條は、なぜ日記を書き換えたのか(第一〇章)。 テクストをつぶさに読み込むだけでなく、それが書きつけられた物や筆跡にも目を凝らす姿勢に、やっぱり荒井さんだなぁ、と嬉しくなる。 当初は結構、この本の「ですます調」の文体がやさしすぎる気がしていたのだけど(最初の何章かは基本的な解説パートが続くこともあり)、日記パートに辿り着く頃には、この文体は北條にかけられた〈崇高〉のヴェールをはがし、人間として向き合うために選び取られたものだったのかもしれないと、納得できる瞬間があった。 〈大切なのは、一人の人間が見せる振れ幅をきちんと捉えることでしょう。〉(230頁) 北條の振れ幅を知ることを通して、自分という一人の読者の中にある振れ幅をも大切に思える読書となった。 余談:第15回「(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞」の受賞スピーチで、荒井さんが以下のように語っていたけど、第一〇章の最後のほうの想像力の働かせ方には、こういう地道な経験が根底あるのでは、と思ったりもした(このスピーチは柏書房のwebマガジンで読めます)。 〈ハンセン病療養所では「昔の患者の言葉を書き写す」ということを、よくやっていました。私自身、昔の患者の残した言葉とどう向き合っていいのか分らなかったので、とにかく「書き写す」ということをしました。昭和初期の患者の手書きの原稿用紙が800枚くらい出てきたことがありました。それを一文字一文字、ワードファイルで書き写しました。[...]とにかく、患者の言葉をなぞることからはじめたのです。〉(「かしわもち」2022年5月2日より)







 JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月24日読み始めた@ 電車朝4時起きで前橋へ。移動時間が長いのでかさばらない本をお供に。一章一章が短く、ですます調のやさしい語り口なのですいすい読めてしまう。第六章まで読んだところで帰宅。 「いのちの初夜」で語られる〈いのち〉とはそもそも何なのか。本作に含まれる「崇高さ」だけでなく「毒っぽさ」にもきちんと目を向けること。荒井さんがある方に教えてもらったという〈バット〉(タバコのゴールデンバットのこと)の読みがすごく面白い。 このまま一気に読み終えたい。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月24日読み始めた@ 電車朝4時起きで前橋へ。移動時間が長いのでかさばらない本をお供に。一章一章が短く、ですます調のやさしい語り口なのですいすい読めてしまう。第六章まで読んだところで帰宅。 「いのちの初夜」で語られる〈いのち〉とはそもそも何なのか。本作に含まれる「崇高さ」だけでなく「毒っぽさ」にもきちんと目を向けること。荒井さんがある方に教えてもらったという〈バット〉(タバコのゴールデンバットのこと)の読みがすごく面白い。 このまま一気に読み終えたい。

 JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月24日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第七章。「いのちの初夜」で佐柄木の語る〈廃人〉になるとはどういう事態か。北條が「自ら命を断つ」こと、すなわち〈自死〉という行為にどんな意味を見出していたのか。〈自分の生命が無意味なものとして扱われる絶望と、自分の生命を無意味なものにしたくないという抗い〉(169頁)に目を凝らす荒井さん手つきが良い。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年5月24日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第七章。「いのちの初夜」で佐柄木の語る〈廃人〉になるとはどういう事態か。北條が「自ら命を断つ」こと、すなわち〈自死〉という行為にどんな意味を見出していたのか。〈自分の生命が無意味なものとして扱われる絶望と、自分の生命を無意味なものにしたくないという抗い〉(169頁)に目を凝らす荒井さん手つきが良い。