

読書猫
@bookcat
にんげんのことばやくらしをまなぶために本をよんで、すきなところをめもしています。
さいきん、にくきゅうでぺーじをめくるのがうまくなってきました。
2025/3/7-
- 2026年2月14日
 読み終わった(本文抜粋) “並んだ十七分を捨てられず、九分かけて手に入れた日陰から鳩を見ている。炎天下、路上のゲロをつついて輝く二羽の無表情。腹こわさんか? だいじょぶか。食えるから食ってんだろという野生なるものへの信頼がある。本能にしたがえ。第一感が結局正しい。思考を吸いとる本質めいたことばに、僕はよわい。何度裏切られてもすがってしまう。” “勝つと対局が増え、負けると強制的に自由時間が与えられる。研究をしてもいい、ひたすら眠りこけていてもいい。漫画を読むだけで一日が終わってもいい、遊び歩いてもいい、あてのない日々を仕事にしてくれるのは結果だけだ。勝てば、怠惰に過ごした時間さえも正しかったことになる。” “研究の差は、結局のところ関心の差だ。 僕は、そんなにも途方もない世界に関心がもてない。うまくいったらすごいだろうということはわかる。あたらしい世界が広がる可能性をおもしろそうだとも思う。でも、その先に思考が伸びていかない。” “いまとなってはおなじみのきもち。逃してはいけないと自分で決めたものを逃してしまうことに慣れたのはいつからだろう。逃せば、感情の持って行き場がなくなる。けれど思考でおさまりはつく。無意味な願かけだったと否定して、なかったことにすればいいだけだ。自分ルールをつくっては、つくった過去の自分ごと笑い流しているうちに、ルールは効力を失っていた。それでも僕は、何度でも強いことばで自分を追いこむふりをする。ぬるい決意とやすい絶望。” “例会からの帰り道、北参道駅の階段の途中でうずくまっている男を見かけたことがある。 ひと目で、おなじ三段のやつだとわかった。できるだけ離れて通りすぎようと思った瞬間サラリーマンが舌打ちするのが聞こえて、気づけば僕はどうしたと声をかけていた。 おりかたがわからない、とそいつは言った。” “こんなによわいのに好きなんて、かわいそうだな、おまえ。” “まちがえたくない、とおまえは思う。ぜったいにまちがえたくない。まちがえれば、過去の自分が否定される。あのみじめさがあったからこそ、いまの自分がある。架空の未来を使っていまに意味をもたせる前借りのロジック。けれど借りはいつか返さなければならない。つじつまを合わせなければならない。 勝たなければ、過去を編集し直さなければならなくなる。” “芝とは小学生の頃からのつき合いだったが、芝の誕生日を知ったのはこのときが初めてだった。 なぜなら、奨励会においては、誕生日の話題はタブーだったからだ。 一つ歳を取れば、それだけ年齢制限に近づく。誕生日をめでたいものだと考えている人間など奨励会には一人もおらず、誰もがその忌まわしき日を心底恐れていた。”
読み終わった(本文抜粋) “並んだ十七分を捨てられず、九分かけて手に入れた日陰から鳩を見ている。炎天下、路上のゲロをつついて輝く二羽の無表情。腹こわさんか? だいじょぶか。食えるから食ってんだろという野生なるものへの信頼がある。本能にしたがえ。第一感が結局正しい。思考を吸いとる本質めいたことばに、僕はよわい。何度裏切られてもすがってしまう。” “勝つと対局が増え、負けると強制的に自由時間が与えられる。研究をしてもいい、ひたすら眠りこけていてもいい。漫画を読むだけで一日が終わってもいい、遊び歩いてもいい、あてのない日々を仕事にしてくれるのは結果だけだ。勝てば、怠惰に過ごした時間さえも正しかったことになる。” “研究の差は、結局のところ関心の差だ。 僕は、そんなにも途方もない世界に関心がもてない。うまくいったらすごいだろうということはわかる。あたらしい世界が広がる可能性をおもしろそうだとも思う。でも、その先に思考が伸びていかない。” “いまとなってはおなじみのきもち。逃してはいけないと自分で決めたものを逃してしまうことに慣れたのはいつからだろう。逃せば、感情の持って行き場がなくなる。けれど思考でおさまりはつく。無意味な願かけだったと否定して、なかったことにすればいいだけだ。自分ルールをつくっては、つくった過去の自分ごと笑い流しているうちに、ルールは効力を失っていた。それでも僕は、何度でも強いことばで自分を追いこむふりをする。ぬるい決意とやすい絶望。” “例会からの帰り道、北参道駅の階段の途中でうずくまっている男を見かけたことがある。 ひと目で、おなじ三段のやつだとわかった。できるだけ離れて通りすぎようと思った瞬間サラリーマンが舌打ちするのが聞こえて、気づけば僕はどうしたと声をかけていた。 おりかたがわからない、とそいつは言った。” “こんなによわいのに好きなんて、かわいそうだな、おまえ。” “まちがえたくない、とおまえは思う。ぜったいにまちがえたくない。まちがえれば、過去の自分が否定される。あのみじめさがあったからこそ、いまの自分がある。架空の未来を使っていまに意味をもたせる前借りのロジック。けれど借りはいつか返さなければならない。つじつまを合わせなければならない。 勝たなければ、過去を編集し直さなければならなくなる。” “芝とは小学生の頃からのつき合いだったが、芝の誕生日を知ったのはこのときが初めてだった。 なぜなら、奨励会においては、誕生日の話題はタブーだったからだ。 一つ歳を取れば、それだけ年齢制限に近づく。誕生日をめでたいものだと考えている人間など奨励会には一人もおらず、誰もがその忌まわしき日を心底恐れていた。” - 2026年2月13日
- 2026年2月12日
 消費される階級酒井順子読み終わった(本文抜粋) “加齢によって余儀なくされる様々な衰えを自覚した者にとって、艶やかな髪や弾力のある肌を目の当たりにした時に感嘆の声をあげるのは、自然な反応ではあるのです。しかしあまりに若さを寿ぐ声が強いせいで、年をとることに対する忌避感が強まりすぎている気も、するのでした。” “「若い」は、年齢が低いことを形容する言葉です。が、年齢が高いことを示す言葉は、「老いる」「老ける」のように、動詞。このことは、人は年をとることはできるけれど、決して若くなることはできないという事実を示しています。” “おたくの人々の多幸感の源は、「好かれる」ことに無関心、というところにあるのではないかと、私は思っています。思う存分に「好く」ことさえできれば、好かれなくてもおたく達は平気。” “美を追求する活動は、昭和時代よりもずっと先鋭化しています。かつては、「自分が他人からどう見えるか気にしている」との感覚を持つのは恥ずかしいこととされていましたが、誰もがネット上に自分の姿を晒すようになってその見栄えが問われるようになると、そのような感覚を持つのは当然のことに。と言うよりも、「より美しく自分を見せる」という行為が、マナーの一環のようになってきたのです。”
消費される階級酒井順子読み終わった(本文抜粋) “加齢によって余儀なくされる様々な衰えを自覚した者にとって、艶やかな髪や弾力のある肌を目の当たりにした時に感嘆の声をあげるのは、自然な反応ではあるのです。しかしあまりに若さを寿ぐ声が強いせいで、年をとることに対する忌避感が強まりすぎている気も、するのでした。” “「若い」は、年齢が低いことを形容する言葉です。が、年齢が高いことを示す言葉は、「老いる」「老ける」のように、動詞。このことは、人は年をとることはできるけれど、決して若くなることはできないという事実を示しています。” “おたくの人々の多幸感の源は、「好かれる」ことに無関心、というところにあるのではないかと、私は思っています。思う存分に「好く」ことさえできれば、好かれなくてもおたく達は平気。” “美を追求する活動は、昭和時代よりもずっと先鋭化しています。かつては、「自分が他人からどう見えるか気にしている」との感覚を持つのは恥ずかしいこととされていましたが、誰もがネット上に自分の姿を晒すようになってその見栄えが問われるようになると、そのような感覚を持つのは当然のことに。と言うよりも、「より美しく自分を見せる」という行為が、マナーの一環のようになってきたのです。” - 2026年2月12日
 カキフライが無いなら来なかったせきしろ,又吉直樹読み終わった(本文抜粋) “登山服の老夫婦に席を譲っても良いか迷う(又吉)” “ほうとうの底からカボチャが張り切ってでてくる(せきしろ)” “落ち着いても温泉に行かない(又吉)” “何かに使えると思ってた容器まとめて捨てる(せきしろ)” “居酒屋のトイレで一旦酔っていないふりをする(又吉)” “独りだから静電気を無視する(又吉)” “ちりとりを呼ぶ声が教室に響く(又吉)” “誘われるまで帰るふりをする普通に普通に(又吉)”
カキフライが無いなら来なかったせきしろ,又吉直樹読み終わった(本文抜粋) “登山服の老夫婦に席を譲っても良いか迷う(又吉)” “ほうとうの底からカボチャが張り切ってでてくる(せきしろ)” “落ち着いても温泉に行かない(又吉)” “何かに使えると思ってた容器まとめて捨てる(せきしろ)” “居酒屋のトイレで一旦酔っていないふりをする(又吉)” “独りだから静電気を無視する(又吉)” “ちりとりを呼ぶ声が教室に響く(又吉)” “誘われるまで帰るふりをする普通に普通に(又吉)” - 2026年2月12日
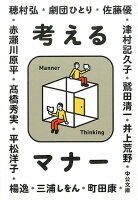 考えるマナー中央公論新社読み終わった(本文抜粋) “世の中の趨勢とは逆に、他人に伝えないことを増やすようにしてから、わたしはかなり気が楽になった。「誰にも言ってないので共感されようがない」という状況に自分を持っていくと、「共感されたいけどしてもらえない」苦しみから距離を置けるのである。” (津村記久子「日記のマナー」より) “断念によって心のステージが変わる。そのときはじめて、土俵から最後まで降りずに、この苦しい果てしのない時間を共有してくれた相手への思いやりがかすかに芽生える。ともにもがき苦しんだその時間を確認したあとにしか、納得は起こらない。そのあとである。「理解はできないけれど納得はできる」という言葉がふと漏れもするのは。” (鷲田清一「納得のマナー」より) “その場にいる人が皆同じ年齢だと、自分の成長の度合いがよく見える。でも同時に、何もかも持っている必要はないと感じた。わたしが持たない特質を、他の誰かが持っていて、その逆もまたある。それでいい。しがらみのない社会の縮図を改めて眺めるとそう思う。たくさんの他者がいるんだから、自分はさして足りなくてもいいのだ。そして皆が、懸命に生活している。” (津村記久子「同い年のマナー」より)
考えるマナー中央公論新社読み終わった(本文抜粋) “世の中の趨勢とは逆に、他人に伝えないことを増やすようにしてから、わたしはかなり気が楽になった。「誰にも言ってないので共感されようがない」という状況に自分を持っていくと、「共感されたいけどしてもらえない」苦しみから距離を置けるのである。” (津村記久子「日記のマナー」より) “断念によって心のステージが変わる。そのときはじめて、土俵から最後まで降りずに、この苦しい果てしのない時間を共有してくれた相手への思いやりがかすかに芽生える。ともにもがき苦しんだその時間を確認したあとにしか、納得は起こらない。そのあとである。「理解はできないけれど納得はできる」という言葉がふと漏れもするのは。” (鷲田清一「納得のマナー」より) “その場にいる人が皆同じ年齢だと、自分の成長の度合いがよく見える。でも同時に、何もかも持っている必要はないと感じた。わたしが持たない特質を、他の誰かが持っていて、その逆もまたある。それでいい。しがらみのない社会の縮図を改めて眺めるとそう思う。たくさんの他者がいるんだから、自分はさして足りなくてもいいのだ。そして皆が、懸命に生活している。” (津村記久子「同い年のマナー」より) - 2026年2月11日
 科学と科学者のはなし寺田寅彦,池内了読み終わった(本文「科学者とあたま」より抜粋) “頭のいい人は、いわば富士の裾野まで来て、そこから頂上を眺めただけで、それで富士の全体をのみこんで東京へ引き返すという心配がある。富士はやはり登ってみなければわからない。” “頭の悪い人は、頭のいい人が考えて、はじめからだめにきまっているような試みを、一生懸命につづけている。やっと、それがだめだとわかるころには、しかしたいてい何かしらだめでない他のものの糸口を取り上げている。”
科学と科学者のはなし寺田寅彦,池内了読み終わった(本文「科学者とあたま」より抜粋) “頭のいい人は、いわば富士の裾野まで来て、そこから頂上を眺めただけで、それで富士の全体をのみこんで東京へ引き返すという心配がある。富士はやはり登ってみなければわからない。” “頭の悪い人は、頭のいい人が考えて、はじめからだめにきまっているような試みを、一生懸命につづけている。やっと、それがだめだとわかるころには、しかしたいてい何かしらだめでない他のものの糸口を取り上げている。” - 2026年2月10日
 レトリック感覚佐藤信夫読み終わった(本文抜粋) “ふだん文章に接するとき、人は決して言葉の模様を《観察する》のではなく、たいていは無心に《読む》。けれども、知らず識らず、私たちはそのことばづかいによって、快感をおぼえたり、退屈したり、ときには反感をいだいたりする。そこにレトリックがある。” “ゆうべ、あなたひとり《だけ》が、たった一回《しか》体験しなかったことがらには、名まえがついていない。” “ことばは思考の衣装ではなく思考の肉体そのものである、と言う中村雄二郎は、哲学の知に新しい活力を与えよみがえらせるためには、ことばにイメージをとりもどすことが必要だと主張する。” “あっさり「雪」と言ってもよさそうなところを、わざわざ「白いもの」と言う。筆者はちょっと気取ってみたかったのか。いくぶんかは、そうだろう。 しかし、この文のなかでは「雪」より「白いもの」のほうがいっそう正確だったのだ。” “数にかぎりのあることばをたよりにしてかぎりない事象に対処しなければならない、言語の宿命が比喩を必要とする……とは、これまでもくどいほど強調してきた事実だが、そのための人々のさまざまの工夫がつもりつもって、辞書のなかの単語たちは、すこぶる弾力的な意味のひろがりをもっている。” “「うれしい」と言うとき、人はたんにうれしいのであろう。それに対して、 「かなしくはない」と言う表現は、うれしさのかたわらに、存在しないかなしみの映像を成立させる。”
レトリック感覚佐藤信夫読み終わった(本文抜粋) “ふだん文章に接するとき、人は決して言葉の模様を《観察する》のではなく、たいていは無心に《読む》。けれども、知らず識らず、私たちはそのことばづかいによって、快感をおぼえたり、退屈したり、ときには反感をいだいたりする。そこにレトリックがある。” “ゆうべ、あなたひとり《だけ》が、たった一回《しか》体験しなかったことがらには、名まえがついていない。” “ことばは思考の衣装ではなく思考の肉体そのものである、と言う中村雄二郎は、哲学の知に新しい活力を与えよみがえらせるためには、ことばにイメージをとりもどすことが必要だと主張する。” “あっさり「雪」と言ってもよさそうなところを、わざわざ「白いもの」と言う。筆者はちょっと気取ってみたかったのか。いくぶんかは、そうだろう。 しかし、この文のなかでは「雪」より「白いもの」のほうがいっそう正確だったのだ。” “数にかぎりのあることばをたよりにしてかぎりない事象に対処しなければならない、言語の宿命が比喩を必要とする……とは、これまでもくどいほど強調してきた事実だが、そのための人々のさまざまの工夫がつもりつもって、辞書のなかの単語たちは、すこぶる弾力的な意味のひろがりをもっている。” “「うれしい」と言うとき、人はたんにうれしいのであろう。それに対して、 「かなしくはない」と言う表現は、うれしさのかたわらに、存在しないかなしみの映像を成立させる。” - 2026年2月8日
 ザ・エッセイ万博万城目学読み終わった(本文抜粋) “レジ前には長蛇の列が発生していた。しかし、レジの女性は非常にゆっくりと作業をする方だった。順番が来て彼女の前に立ったとき、我慢できなくなった母親がつい口を挟んだ。 「あの、もう少し、テキパキやってくれません?」 その瞬間、レジの女性が手にしたペナントをパキッと折った。 いっさい無言のまま実行された怒りの発露に、私と母親は度肝を抜かれ、何も言い返せぬまま会計を終え、回復不能の折り目がついたペナントを受け取った。その後、別に苦情や交換を申し出るわけでもなく、まあ、あんなこと言ったら、そういう反応もあり得るわな、とどこか納得しつつ大阪に持ち帰り、私の勉強机の前には、折り目のくっきりついたペナントが飾られ続けた──。” “さいわい、私の小説の井戸は当分の間、頼りなくも水脈を保ち続けてくれそうだ。 それでも、いつか枯れる日はくるかもしれない。今回の経験のように、内なる井戸が自分でも気づかないうちに「無」の状態になってしまうことは、どんな対象にだって起こり得る。 ただし、完全に枯れた井戸をひとつ抱えて感じるのは、別にその人の何かが衰えたわけではない、ということだ。 ピアノの井戸が生きていた間に、私が表現した音楽は、すべて自分の内側から湧き上がってきたものだ。その事実と、井戸が今後持続するかどうかという問題は、その人の豊かさを計るにおいて実は何の関係もない。単に人生の一コマを人知れず通過した、それだけの話に過ぎない。” “私は創作論といった類をほとんど持たない人間だが、「おもしろさ」についてだけは一個の持論がある。 それは「第一発想がすべて」というものだ。 パッとしないアイディアは、その後どれだけの英知が集まったところで、よいものに化けることはない。”
ザ・エッセイ万博万城目学読み終わった(本文抜粋) “レジ前には長蛇の列が発生していた。しかし、レジの女性は非常にゆっくりと作業をする方だった。順番が来て彼女の前に立ったとき、我慢できなくなった母親がつい口を挟んだ。 「あの、もう少し、テキパキやってくれません?」 その瞬間、レジの女性が手にしたペナントをパキッと折った。 いっさい無言のまま実行された怒りの発露に、私と母親は度肝を抜かれ、何も言い返せぬまま会計を終え、回復不能の折り目がついたペナントを受け取った。その後、別に苦情や交換を申し出るわけでもなく、まあ、あんなこと言ったら、そういう反応もあり得るわな、とどこか納得しつつ大阪に持ち帰り、私の勉強机の前には、折り目のくっきりついたペナントが飾られ続けた──。” “さいわい、私の小説の井戸は当分の間、頼りなくも水脈を保ち続けてくれそうだ。 それでも、いつか枯れる日はくるかもしれない。今回の経験のように、内なる井戸が自分でも気づかないうちに「無」の状態になってしまうことは、どんな対象にだって起こり得る。 ただし、完全に枯れた井戸をひとつ抱えて感じるのは、別にその人の何かが衰えたわけではない、ということだ。 ピアノの井戸が生きていた間に、私が表現した音楽は、すべて自分の内側から湧き上がってきたものだ。その事実と、井戸が今後持続するかどうかという問題は、その人の豊かさを計るにおいて実は何の関係もない。単に人生の一コマを人知れず通過した、それだけの話に過ぎない。” “私は創作論といった類をほとんど持たない人間だが、「おもしろさ」についてだけは一個の持論がある。 それは「第一発想がすべて」というものだ。 パッとしないアイディアは、その後どれだけの英知が集まったところで、よいものに化けることはない。” - 2026年2月6日
 無気力の心理学 改版波多野誼余夫,稲垣佳世子読み終わった(本文抜粋) “わたしたちは、好きな活動に従事しているとき、自分の活動を支配しているのは、ほかならぬこの自分であるという実感がある。その活動はいつはじめてもよいし、いつやめてもよい。どんなふうなやり方でやろうと自分の自由である。しかし、ひとたび賞や外的評価が導入されるや、賞を得るために、あるいは外的評価の基準に合うように、行動を組織化しなおそうとする傾向が強くなる。そしてそれに関わる過程で、次第に、行動の源泉が自分ではないという感じが強くなるのではないだろうか。” “効力感を発達させるためには、これまでの章で考察してきたことに加えて、さらに二つの条件が必要とされる。ひとつは、本人が自己向上を実感しうる、ということである。向上の判断基準が外部にあるかぎり、成功の喜びも、せいぜい一時的なものにとどまり、意欲的な生き方を導くものではありえない。もうひとつは、自己向上が本人にとって、価値のある、真に「好ましい」ものでなければならない、ということである。” “人々の実存的な要求の様相が創造と愛と自己統合の三つであるとすれば、これをもたらすような熟達の過程こそ、その人にとって最も好ましいということになる。” “スペシャリスト(たとえば医者、芸術家、弁護士)は、熟達を彼らの「自由」のよりどころにしている。彼らは、いわば「現代化された」職人であり、その高度な熟達のゆえに、企業体に対してある程度の独立を達成し、かつ一定の地位と収入とを「保証」されている。これらの人々が、権力やお金の亡者にならないかぎり、内発的な動機づけに目を向けることは十分考えられる。彼らは、熟達にいっそう磨きをかけることで、「自分ならでは」の仕事を遂行し、しかもそれによって他者に貢献しうる、と信じている。この人たちが、労働をとおして効力感を得やすいことは確かであろう。”
無気力の心理学 改版波多野誼余夫,稲垣佳世子読み終わった(本文抜粋) “わたしたちは、好きな活動に従事しているとき、自分の活動を支配しているのは、ほかならぬこの自分であるという実感がある。その活動はいつはじめてもよいし、いつやめてもよい。どんなふうなやり方でやろうと自分の自由である。しかし、ひとたび賞や外的評価が導入されるや、賞を得るために、あるいは外的評価の基準に合うように、行動を組織化しなおそうとする傾向が強くなる。そしてそれに関わる過程で、次第に、行動の源泉が自分ではないという感じが強くなるのではないだろうか。” “効力感を発達させるためには、これまでの章で考察してきたことに加えて、さらに二つの条件が必要とされる。ひとつは、本人が自己向上を実感しうる、ということである。向上の判断基準が外部にあるかぎり、成功の喜びも、せいぜい一時的なものにとどまり、意欲的な生き方を導くものではありえない。もうひとつは、自己向上が本人にとって、価値のある、真に「好ましい」ものでなければならない、ということである。” “人々の実存的な要求の様相が創造と愛と自己統合の三つであるとすれば、これをもたらすような熟達の過程こそ、その人にとって最も好ましいということになる。” “スペシャリスト(たとえば医者、芸術家、弁護士)は、熟達を彼らの「自由」のよりどころにしている。彼らは、いわば「現代化された」職人であり、その高度な熟達のゆえに、企業体に対してある程度の独立を達成し、かつ一定の地位と収入とを「保証」されている。これらの人々が、権力やお金の亡者にならないかぎり、内発的な動機づけに目を向けることは十分考えられる。彼らは、熟達にいっそう磨きをかけることで、「自分ならでは」の仕事を遂行し、しかもそれによって他者に貢献しうる、と信じている。この人たちが、労働をとおして効力感を得やすいことは確かであろう。” - 2026年2月5日
 パンチラインの言語学川添愛読み終わった(本文抜粋) (『タッチ』について)」 「めざせカッちゃん甲子園」の語順の良さ (『パルプ・フィクション』について) ギャングに追われる立場になったボクサーのブッチ(ブルース・ウィリス)が、逃亡のために利用したタクシーの運転手エスメラルダ(アンジェラ・ジョーンズ)に口止めをしようとして、「もし誰かが君に今晩誰を乗せたか聞いてきたら、何と答える?」と尋ねる場面がある。普通だったら、「あなたのことは言わないから安心して」とか言いそうなところだが、エスメラルダは「本当のことを言うわ。身なりのいい、ほろ酔い加減のメキシコ人を三人乗せた、って」と答える。エスメラルダがブッチの意図を汲み取っているだけではなく、すでにウソの返答を用意しているところ、またそれを「本当のこと」と言っているところに「只者ではない感じ」がにじみ出ている。 (『ドラえもん』について) 今読み返して気づくのは、セリフの表記の面白さだ。藤子・F・不二雄先生の他の漫画にも通じる特徴だが、日本語の長母音(長く伸ばす音)を表記する際に長音符「ー」ではなく、「あ」行を使うことが多い。たとえば「だれかあ! たすけてえ‼︎」のように、「か」を伸ばした音を「かあ」、「て」を伸ばした音を「てえ」と表記する。「だれかー! たすけてー‼︎」ではないのである。個人的な感覚だが、「ー」だとそのまま伸ばす感じになるが、「あ」行だと独自のピッチアクセント(音の高低差)が生まれて、独特のおかしみが出るように思う。
パンチラインの言語学川添愛読み終わった(本文抜粋) (『タッチ』について)」 「めざせカッちゃん甲子園」の語順の良さ (『パルプ・フィクション』について) ギャングに追われる立場になったボクサーのブッチ(ブルース・ウィリス)が、逃亡のために利用したタクシーの運転手エスメラルダ(アンジェラ・ジョーンズ)に口止めをしようとして、「もし誰かが君に今晩誰を乗せたか聞いてきたら、何と答える?」と尋ねる場面がある。普通だったら、「あなたのことは言わないから安心して」とか言いそうなところだが、エスメラルダは「本当のことを言うわ。身なりのいい、ほろ酔い加減のメキシコ人を三人乗せた、って」と答える。エスメラルダがブッチの意図を汲み取っているだけではなく、すでにウソの返答を用意しているところ、またそれを「本当のこと」と言っているところに「只者ではない感じ」がにじみ出ている。 (『ドラえもん』について) 今読み返して気づくのは、セリフの表記の面白さだ。藤子・F・不二雄先生の他の漫画にも通じる特徴だが、日本語の長母音(長く伸ばす音)を表記する際に長音符「ー」ではなく、「あ」行を使うことが多い。たとえば「だれかあ! たすけてえ‼︎」のように、「か」を伸ばした音を「かあ」、「て」を伸ばした音を「てえ」と表記する。「だれかー! たすけてー‼︎」ではないのである。個人的な感覚だが、「ー」だとそのまま伸ばす感じになるが、「あ」行だと独自のピッチアクセント(音の高低差)が生まれて、独特のおかしみが出るように思う。 - 2026年2月4日
 急に具合が悪くなる宮野真生子,磯野真穂読み終わった(本文抜粋) “(宮野)今ある自分の人生とはまったく別の一生を思い浮かべてみる。私が旅に出る醍醐味はこれに尽きます。今の人生に不満がある、というわけではありません。むしろ満足している。けれどもそれでも、自分の人生がまったく別のものであった可能性を考えてみることは、私が自分の人生というものを引き受ける上で、大切な思考の手がかりである気がします。” “(宮野)そもそも「選ぶ」って何だろうと思うのです。合理的に比較検討することはできるけど、私たちは本当に合理的に「選ぶ」ことなんてできるのだろうか。そんなふうに「選ぶ」ことが「選ぶ」ということなのだろうか、と。結局のところ、何かに動かされるようにしてしか決めることができないのなら、選ぶとは能動的に何かをするというよりも、ある状態にたどりつき、落ち着くような、なじむような状態で、それは合理的な知性の働きというよりも快適さや懐かしさといった身体感覚に近いのではないか、そして身体感覚である以上、自分ではいかんともしがたい受動的な側面があるのではないか、と。” “(宮野)合理性に則った資本主義的な生き方の一番大きな特徴を一言で表すなら、コントロールの欲求と言えるでしょう。” “(宮野) 問い「私は不幸なのか?」 答え「不運ではあるが、不幸ではない」” “(磯野)アカデミックな文章を書くときには乱発が禁じられているはずの、言葉にされない、「そういえば」や「ところで」で、会話は埋め尽くされている。お互い違う場所と人生の中に身を置きながら、相手の言葉を受け取り、それを自分の中に引き入れてから相手に投げる。相手の言葉を受け止めつつ、同時に自分の身体の中かに走る思考や現在進行形の身振りから、浮かんだ言葉を相手に投げる。互いの間にある、こういったある種の間隙が、リズムの良い話題の転換を作っているのだと思います。” “(宮野)話の中身も大切だけど、ある程度の時間、だらっと喋っていることも必要なのだと思います。私たちはそうやって、相手を知り、関係を深めてゆく、こうした関係のなかにいる自分って、書き言葉で切り取られたかっこいい私とはまったく違うものです。” “(宮野)自分の人生に完璧な責任をとれる人などいるのでしょうか。果たしてそういう人がいたとして、それは好ましいことなのでしょうか。 (中略) 私の生は何かの途中で打ち切られざるをえない。人生は完成することなく、人間はつねに「自分の未然」──つまり、まだ達していない途上──を生きる存在なのです。そんな存在がどうやって完璧に責任をとるというのでしょう。” “(磯野)宮野さんはよく哲学者の業と言いますが、人類学者にも同じものがあるとするのなら、他人の人生をテキストに変換し、社会的意義とかいいながら、本当はただ自分のために、陳列物として並べることなのでしょう。8便で宮野さんはおぞましいという言葉を使っていましたが、物語の中で生きることと、それを聞き取って描き、果ては業績にすることの本質的な違いを身を以て感じる今、私は自分のやってきたことのおぞましさを痛感します。” “(宮野)選ぶことで自分を見出すのです。選ぶとは、「それはあなたが決めたことだから」ではなく、「選び、決めたこと」の先で「自分」と言う存在が産まれてくる、そんな行為だと言えるでしょう。” “(宮野)偶然を生み出すことが出来たのは、自然発生だけではなく、そこに私たちがいたからです。”
急に具合が悪くなる宮野真生子,磯野真穂読み終わった(本文抜粋) “(宮野)今ある自分の人生とはまったく別の一生を思い浮かべてみる。私が旅に出る醍醐味はこれに尽きます。今の人生に不満がある、というわけではありません。むしろ満足している。けれどもそれでも、自分の人生がまったく別のものであった可能性を考えてみることは、私が自分の人生というものを引き受ける上で、大切な思考の手がかりである気がします。” “(宮野)そもそも「選ぶ」って何だろうと思うのです。合理的に比較検討することはできるけど、私たちは本当に合理的に「選ぶ」ことなんてできるのだろうか。そんなふうに「選ぶ」ことが「選ぶ」ということなのだろうか、と。結局のところ、何かに動かされるようにしてしか決めることができないのなら、選ぶとは能動的に何かをするというよりも、ある状態にたどりつき、落ち着くような、なじむような状態で、それは合理的な知性の働きというよりも快適さや懐かしさといった身体感覚に近いのではないか、そして身体感覚である以上、自分ではいかんともしがたい受動的な側面があるのではないか、と。” “(宮野)合理性に則った資本主義的な生き方の一番大きな特徴を一言で表すなら、コントロールの欲求と言えるでしょう。” “(宮野) 問い「私は不幸なのか?」 答え「不運ではあるが、不幸ではない」” “(磯野)アカデミックな文章を書くときには乱発が禁じられているはずの、言葉にされない、「そういえば」や「ところで」で、会話は埋め尽くされている。お互い違う場所と人生の中に身を置きながら、相手の言葉を受け取り、それを自分の中に引き入れてから相手に投げる。相手の言葉を受け止めつつ、同時に自分の身体の中かに走る思考や現在進行形の身振りから、浮かんだ言葉を相手に投げる。互いの間にある、こういったある種の間隙が、リズムの良い話題の転換を作っているのだと思います。” “(宮野)話の中身も大切だけど、ある程度の時間、だらっと喋っていることも必要なのだと思います。私たちはそうやって、相手を知り、関係を深めてゆく、こうした関係のなかにいる自分って、書き言葉で切り取られたかっこいい私とはまったく違うものです。” “(宮野)自分の人生に完璧な責任をとれる人などいるのでしょうか。果たしてそういう人がいたとして、それは好ましいことなのでしょうか。 (中略) 私の生は何かの途中で打ち切られざるをえない。人生は完成することなく、人間はつねに「自分の未然」──つまり、まだ達していない途上──を生きる存在なのです。そんな存在がどうやって完璧に責任をとるというのでしょう。” “(磯野)宮野さんはよく哲学者の業と言いますが、人類学者にも同じものがあるとするのなら、他人の人生をテキストに変換し、社会的意義とかいいながら、本当はただ自分のために、陳列物として並べることなのでしょう。8便で宮野さんはおぞましいという言葉を使っていましたが、物語の中で生きることと、それを聞き取って描き、果ては業績にすることの本質的な違いを身を以て感じる今、私は自分のやってきたことのおぞましさを痛感します。” “(宮野)選ぶことで自分を見出すのです。選ぶとは、「それはあなたが決めたことだから」ではなく、「選び、決めたこと」の先で「自分」と言う存在が産まれてくる、そんな行為だと言えるでしょう。” “(宮野)偶然を生み出すことが出来たのは、自然発生だけではなく、そこに私たちがいたからです。” - 2026年2月2日
 ペドロ・パラモフアン・ルルフォ,増田義郎,杉山晃読み終わった(本文抜粋) “「この町はいろんなこだまでいっぱいだよ。壁の穴や、石の下にそんな音がこもっているのかと思っちまうよ。歩いていると、誰かにつけられてるような感じがするし、きしり音や笑い声が聞こえたりするんだ。それは古くてくたびれたような笑い声さ。声も長いあいだに擦り切れてきたって感じでね。そういうのが聞こえるんだよ。いつか聞こえなくなる日が来るといいけどね」” “空気がほしくて外に出た。だが、暑苦しさは依然として体にまといついて離れなかった。 というのも空気がどこにもなかったからだ。八月の酷暑に熱せられて、けだるい淀んだ闇しかなかった。 空気がなかった。口から吐き出される息が四散しないうちに手のひらでおさえ、もう一度吸い込まねばならなかった。そうやって吐いたり吸ったりするうちに空気がだんだん薄れていった。とうとうかすかになったいきまで指の間から洩れて、永久になくなってしまった。 そう、永久になくなってしまったのだ。” “男たちが行ってしまうと、おまえは、ひざまずいて、母さんの顔が埋まっているあたりの地面に口づけした。もしわたしが声をかけなかったら、おまえはそこに穴まで開けてしまったかもしれない。「行きましょう、フスティナ。母さんは別のところにいるのよ。ここにあるのは、ただの死んだ体なんだから」”
ペドロ・パラモフアン・ルルフォ,増田義郎,杉山晃読み終わった(本文抜粋) “「この町はいろんなこだまでいっぱいだよ。壁の穴や、石の下にそんな音がこもっているのかと思っちまうよ。歩いていると、誰かにつけられてるような感じがするし、きしり音や笑い声が聞こえたりするんだ。それは古くてくたびれたような笑い声さ。声も長いあいだに擦り切れてきたって感じでね。そういうのが聞こえるんだよ。いつか聞こえなくなる日が来るといいけどね」” “空気がほしくて外に出た。だが、暑苦しさは依然として体にまといついて離れなかった。 というのも空気がどこにもなかったからだ。八月の酷暑に熱せられて、けだるい淀んだ闇しかなかった。 空気がなかった。口から吐き出される息が四散しないうちに手のひらでおさえ、もう一度吸い込まねばならなかった。そうやって吐いたり吸ったりするうちに空気がだんだん薄れていった。とうとうかすかになったいきまで指の間から洩れて、永久になくなってしまった。 そう、永久になくなってしまったのだ。” “男たちが行ってしまうと、おまえは、ひざまずいて、母さんの顔が埋まっているあたりの地面に口づけした。もしわたしが声をかけなかったら、おまえはそこに穴まで開けてしまったかもしれない。「行きましょう、フスティナ。母さんは別のところにいるのよ。ここにあるのは、ただの死んだ体なんだから」” - 2026年1月31日
 陰謀論と排外主義 分断社会を読み解く7つの視点古谷経衡,山崎リュウキチ,清義明,藤倉善郎,藤倉善郎ほか,藤倉善郎他,選挙ウォッチャーちだい,黒猫ドラネコ読み終わった
陰謀論と排外主義 分断社会を読み解く7つの視点古谷経衡,山崎リュウキチ,清義明,藤倉善郎,藤倉善郎ほか,藤倉善郎他,選挙ウォッチャーちだい,黒猫ドラネコ読み終わった - 2026年1月31日
 英米文学のわからない言葉金原瑞人読み終わった(本文抜粋) “時代も変われば変わるもんだなと思う。しかし、タバコはやっぱり煙が出ないとなあ……。電子タバコ吸ってる不良って、様にならないと思ってしまうのは、古いんだろうか。” “「メリー・クリスマス」などとほざく連中は、みんなプディングといっしょにゆであげて、心臓にヒイラギの枝を突き刺して地面に埋めてやりたいもんだ!」 ──チャールズ・ディケンズ『クリスマス・キャロル』”
英米文学のわからない言葉金原瑞人読み終わった(本文抜粋) “時代も変われば変わるもんだなと思う。しかし、タバコはやっぱり煙が出ないとなあ……。電子タバコ吸ってる不良って、様にならないと思ってしまうのは、古いんだろうか。” “「メリー・クリスマス」などとほざく連中は、みんなプディングといっしょにゆであげて、心臓にヒイラギの枝を突き刺して地面に埋めてやりたいもんだ!」 ──チャールズ・ディケンズ『クリスマス・キャロル』” - 2026年1月30日
 読み終わった(本文抜粋) “2023年12月1日、刑事司法の世界にドラスティックな変化をもたらす制度が始まった。 それは受刑中の加害者に、刑務所や少年院を介して被害者や遺族の心情=こころを伝えることができる制度である。「殺された側」から「殺した側」へ、「殺した側」から「殺された側」へ、文書による交通を法律が担保するのだ。法律の正式名称は「刑の執行段階等における被害者等への心情等の聴取・伝達制度」(『心情等伝達制度』)という。” “「加害者に答えを求めてもムダなんですよ。それでは私にとっては全然足らんのです。わかりますか? 全然足らんのです。うちの子どもは加害者に殺されているのだから、加害者がどれだけ苦しもうが足りないんです」” “全体数から見ると、「心情等伝達制度」が利用されたケースは氷山の一角にすぎない。利用されない理由はさまざまだろうが、「被害者の言葉が通じない」「関わりたくない」「逆恨みされるのではないか」等の理由で、諦め、怒り、泣き寝入りをしている相当数の被害者が「暗数」として存在していると私は予想する。”
読み終わった(本文抜粋) “2023年12月1日、刑事司法の世界にドラスティックな変化をもたらす制度が始まった。 それは受刑中の加害者に、刑務所や少年院を介して被害者や遺族の心情=こころを伝えることができる制度である。「殺された側」から「殺した側」へ、「殺した側」から「殺された側」へ、文書による交通を法律が担保するのだ。法律の正式名称は「刑の執行段階等における被害者等への心情等の聴取・伝達制度」(『心情等伝達制度』)という。” “「加害者に答えを求めてもムダなんですよ。それでは私にとっては全然足らんのです。わかりますか? 全然足らんのです。うちの子どもは加害者に殺されているのだから、加害者がどれだけ苦しもうが足りないんです」” “全体数から見ると、「心情等伝達制度」が利用されたケースは氷山の一角にすぎない。利用されない理由はさまざまだろうが、「被害者の言葉が通じない」「関わりたくない」「逆恨みされるのではないか」等の理由で、諦め、怒り、泣き寝入りをしている相当数の被害者が「暗数」として存在していると私は予想する。” - 2026年1月30日
 マルテの手記リルケ読み終わった(本文抜粋) “人間はどこからかやって来て、一つの生活を見つけだす。できあいの生活。ただ人間はそのできあいの服に手を通せばよいのだ。しばらくすると、やがてこの世から去らねばならぬ。否応なしに出てゆかねばならぬ。しかし、人々はなんの苦労もいらない。──もしもし、それが君の死ですよ。──あ、さようですか。そして、人間はやって来たと同じように無造作に立去ってゆく。” “詩は人の考えるように感情ではない。詩がもし感情だったら、年少にしてすでにあり余るほど持っていなければならぬ。詩はほんとうは経験なのだ。” “僕はもう少し書こう。もう少し書いて、何もかも言ってしまいたい。いつか、僕の手が僕から切り放されて、何か書けと命令すれば、僕の考えもせぬ言葉を書くようなことがあるかもしれぬ。” “「このごろは、誰も心に願いを持つなんてことはなくなってしまいました。けれども、マルテ、おまえは心に願いを持つことを忘れてはいけませんよ。願いごとは、ぜひ持たなければなりません。それは、願いのかなうことはないかもわからないわ。けれども、本当の願いごとは、いつまでも、一生涯、持っていなければならぬものよ。かなえられるかどうかなぞ、忘れてしまうくらい、長く長く持っていなければならぬのですよ」” “この世の中には、何一つ想像だけで済ますことのできるものはない。どんなにつまらぬことでも、想像だけで済むものなんか一つもないのだ。僕たちの予想も許さぬ一つ一つの細かなことが無数に存在し、それが集まって、あらゆるものができているのだ。想像だけだと、ただ大急ぎでどしどし走りすぎるばかりだから、つい一つ一つ細かなことは迂闊に見過されて、見過したことにさえ気づかぬことがある。しかし、現実そのものはたいへんゆっくりした流れで、おそろしく多様なものをいっぱい詰めこんでいるのだ。”
マルテの手記リルケ読み終わった(本文抜粋) “人間はどこからかやって来て、一つの生活を見つけだす。できあいの生活。ただ人間はそのできあいの服に手を通せばよいのだ。しばらくすると、やがてこの世から去らねばならぬ。否応なしに出てゆかねばならぬ。しかし、人々はなんの苦労もいらない。──もしもし、それが君の死ですよ。──あ、さようですか。そして、人間はやって来たと同じように無造作に立去ってゆく。” “詩は人の考えるように感情ではない。詩がもし感情だったら、年少にしてすでにあり余るほど持っていなければならぬ。詩はほんとうは経験なのだ。” “僕はもう少し書こう。もう少し書いて、何もかも言ってしまいたい。いつか、僕の手が僕から切り放されて、何か書けと命令すれば、僕の考えもせぬ言葉を書くようなことがあるかもしれぬ。” “「このごろは、誰も心に願いを持つなんてことはなくなってしまいました。けれども、マルテ、おまえは心に願いを持つことを忘れてはいけませんよ。願いごとは、ぜひ持たなければなりません。それは、願いのかなうことはないかもわからないわ。けれども、本当の願いごとは、いつまでも、一生涯、持っていなければならぬものよ。かなえられるかどうかなぞ、忘れてしまうくらい、長く長く持っていなければならぬのですよ」” “この世の中には、何一つ想像だけで済ますことのできるものはない。どんなにつまらぬことでも、想像だけで済むものなんか一つもないのだ。僕たちの予想も許さぬ一つ一つの細かなことが無数に存在し、それが集まって、あらゆるものができているのだ。想像だけだと、ただ大急ぎでどしどし走りすぎるばかりだから、つい一つ一つ細かなことは迂闊に見過されて、見過したことにさえ気づかぬことがある。しかし、現実そのものはたいへんゆっくりした流れで、おそろしく多様なものをいっぱい詰めこんでいるのだ。” - 2026年1月26日
 43歳頂点論(新潮新書)角幡唯介読み終わった(本文抜粋) “思いつきというのは本人の意志を超えたものであり、制御不能である。それが真におのれの人生に根ざしたものであれば、思いついた瞬間に、その人は、その思いつきにより開かれた未来に否応なく運命を投じられてしまうのだ。 思いつきにみられるこうした意志と超越した状況を、私は<事態>と呼び、これこそ人生をうごかすダイナミズムだととらえた。過去の履歴と偶然のきっかけの化学反応がうみだす、そのときどきの事態にのみこまれることで、人生はあらぬ方向に進み、結果として各人はそれぞれ固有の生き方を歩むことになる。 人間とは何か。それはこのような思いつきをうみだす場である。” “では偶然とは何か。 それは世界でその人のみに固有の出来事のことである。 言い方をかえれば、それは世界で私だけに帰属する出来事のことでもある。そのような固有の出来事がきっかけで人は何かをやろうと思いつくのである。 そしてこの偶然による思いつきというものは、何度か述べたが意志を超越した制御不能な力をもつ。” “四十にもなると何者かになり惑わなくなる。これが中年の自由の正体だ。それまで行動を押しとどめていた様々なものからの解放。自由になった結果、二十代の頃のような自己存在証明のための行動は不必要となり、ギリギリとしたストイシズムからも解放される。 年齢を重ね、自分というものが固まってきて、自己存在証明が必要なくなると、何かに届こうとして頑張る必要がなくなる。 そのときはじめて、ただ面白いからそれをやる、という純粋行為の世界が広がる。”
43歳頂点論(新潮新書)角幡唯介読み終わった(本文抜粋) “思いつきというのは本人の意志を超えたものであり、制御不能である。それが真におのれの人生に根ざしたものであれば、思いついた瞬間に、その人は、その思いつきにより開かれた未来に否応なく運命を投じられてしまうのだ。 思いつきにみられるこうした意志と超越した状況を、私は<事態>と呼び、これこそ人生をうごかすダイナミズムだととらえた。過去の履歴と偶然のきっかけの化学反応がうみだす、そのときどきの事態にのみこまれることで、人生はあらぬ方向に進み、結果として各人はそれぞれ固有の生き方を歩むことになる。 人間とは何か。それはこのような思いつきをうみだす場である。” “では偶然とは何か。 それは世界でその人のみに固有の出来事のことである。 言い方をかえれば、それは世界で私だけに帰属する出来事のことでもある。そのような固有の出来事がきっかけで人は何かをやろうと思いつくのである。 そしてこの偶然による思いつきというものは、何度か述べたが意志を超越した制御不能な力をもつ。” “四十にもなると何者かになり惑わなくなる。これが中年の自由の正体だ。それまで行動を押しとどめていた様々なものからの解放。自由になった結果、二十代の頃のような自己存在証明のための行動は不必要となり、ギリギリとしたストイシズムからも解放される。 年齢を重ね、自分というものが固まってきて、自己存在証明が必要なくなると、何かに届こうとして頑張る必要がなくなる。 そのときはじめて、ただ面白いからそれをやる、という純粋行為の世界が広がる。” - 2026年1月25日
 自分は「底辺の人間」です 京都アニメーション放火殺人事件京都新聞取材班読み終わった(本文抜粋) “「なんで風化させてくれないの。悲しみを覚えておけと言うのか」 父親の声は大きくなった。 「風化させなくてどうするんですか。さらしものになるだけじゃないですか。よう言うわ」 事件が起きたという事実、犯人を生み出した背景。それらを風化させないために記録するのは「勝手にやればいい」と父親は言う。「死んだ者を忘れないで、とはこれっぽっちも思っていない。むしろ忘れていただいた方が話のネタにならずに幸い」。そう告げて、父親は黙り込んだ。” “「今日、あなたを責めるつもりは全くありません。ただ、青葉さんの本当の気持ちを、腹をわった話を聞きたいのです。本当の気持ちであるがゆえに、私が傷つくとか、不適切な表現ではないか、といった気遣いは一切無用です。ありのままの気持ちを、しゃべってください」”
自分は「底辺の人間」です 京都アニメーション放火殺人事件京都新聞取材班読み終わった(本文抜粋) “「なんで風化させてくれないの。悲しみを覚えておけと言うのか」 父親の声は大きくなった。 「風化させなくてどうするんですか。さらしものになるだけじゃないですか。よう言うわ」 事件が起きたという事実、犯人を生み出した背景。それらを風化させないために記録するのは「勝手にやればいい」と父親は言う。「死んだ者を忘れないで、とはこれっぽっちも思っていない。むしろ忘れていただいた方が話のネタにならずに幸い」。そう告げて、父親は黙り込んだ。” “「今日、あなたを責めるつもりは全くありません。ただ、青葉さんの本当の気持ちを、腹をわった話を聞きたいのです。本当の気持ちであるがゆえに、私が傷つくとか、不適切な表現ではないか、といった気遣いは一切無用です。ありのままの気持ちを、しゃべってください」” - 2026年1月25日
 生きるための表現手引き渡邉康太郎読み終わった(本文抜粋) “人間は、普遍を認識することができるが、実存としてはただいちどの人生しか生きることができない。 ──東浩紀「人文学と反復不可能性」『テーマパーク化する地球』” “「オリジナリティとは、聞いたことは覚えていながら、どこで聞いたかは忘れてしまう芸当をいう」 ──ローレンス・J・ピーター” “自分の身体、自分の経験を映し出す一本の線は、いくら練習しても他者の線にはなり得ない。必ず「自分の線」しか残らない。その差異こそが、隠そうとしてもにじみ出る個性の根拠です。” “「単一の物語は偏見をかたちづくります。偏見の物語は、それが間違っているということではなく、不完全だということです。偏見は、ひとつの物語を唯一の物語にしてしまう」 ──チママンダ・アディーチェ” “いわゆる頭のいい人は、言わば足の早い旅人のようなものである。人より先に人のまだ行かない所へと行き着くこともできる代わりに、途中の道ばたあるいはちょっとしたわき道にある肝心なものを見落とす恐れがある。頭の悪い人足ののろい人がずっとあとからおくれて来てわけもなくそのだいじな宝物を拾って行く場合がある。 寺田寅彦「科学者とあたま」『寺田寅彦随筆集 第4巻』”
生きるための表現手引き渡邉康太郎読み終わった(本文抜粋) “人間は、普遍を認識することができるが、実存としてはただいちどの人生しか生きることができない。 ──東浩紀「人文学と反復不可能性」『テーマパーク化する地球』” “「オリジナリティとは、聞いたことは覚えていながら、どこで聞いたかは忘れてしまう芸当をいう」 ──ローレンス・J・ピーター” “自分の身体、自分の経験を映し出す一本の線は、いくら練習しても他者の線にはなり得ない。必ず「自分の線」しか残らない。その差異こそが、隠そうとしてもにじみ出る個性の根拠です。” “「単一の物語は偏見をかたちづくります。偏見の物語は、それが間違っているということではなく、不完全だということです。偏見は、ひとつの物語を唯一の物語にしてしまう」 ──チママンダ・アディーチェ” “いわゆる頭のいい人は、言わば足の早い旅人のようなものである。人より先に人のまだ行かない所へと行き着くこともできる代わりに、途中の道ばたあるいはちょっとしたわき道にある肝心なものを見落とす恐れがある。頭の悪い人足ののろい人がずっとあとからおくれて来てわけもなくそのだいじな宝物を拾って行く場合がある。 寺田寅彦「科学者とあたま」『寺田寅彦随筆集 第4巻』” - 2026年1月24日
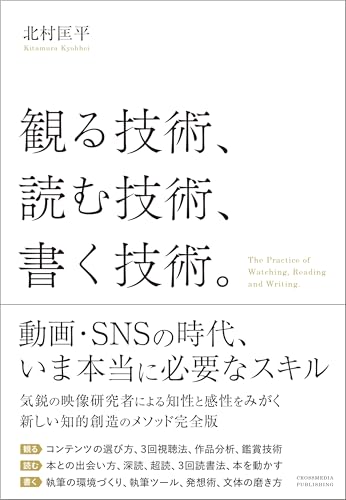 観る技術、読む技術、書く技術。北村匡平読み終わった(本文抜粋) “私たちは本当の意味で映画やドラマを「観る」ことができているのでしょうか。ただ単に物語の筋を「情報」として消費しているだけになっていないでしょうか。” “物書きにとって必要な能力の一つに積極的に「バカになる」力があるように思います。昔は完璧な文章を求めすぎて書けなくなってしまうこともありました。ですが、理想が高くなりすぎると本当に何も書けなくなるのです。” “意識的に偶然性を取り入れることは、情報洪水時代の現代を生き抜くための知的なアンチテーゼでもあります。自ら進んで予測不能な情報や異なる視点に触れることで、興味や関心の幅を広げ、これまで気づかなかった発想やつながりに出会うことができます。”
観る技術、読む技術、書く技術。北村匡平読み終わった(本文抜粋) “私たちは本当の意味で映画やドラマを「観る」ことができているのでしょうか。ただ単に物語の筋を「情報」として消費しているだけになっていないでしょうか。” “物書きにとって必要な能力の一つに積極的に「バカになる」力があるように思います。昔は完璧な文章を求めすぎて書けなくなってしまうこともありました。ですが、理想が高くなりすぎると本当に何も書けなくなるのです。” “意識的に偶然性を取り入れることは、情報洪水時代の現代を生き抜くための知的なアンチテーゼでもあります。自ら進んで予測不能な情報や異なる視点に触れることで、興味や関心の幅を広げ、これまで気づかなかった発想やつながりに出会うことができます。”
読み込み中...
