

さーちゃん
@cong_mei
本を読んで感じたことを、そのままにしないで、言葉に残していきたいです。
- 2026年1月16日
- 2025年11月6日
 感情労働の未来恩蔵絢子読み始めたp1〜37 感情の特徴 ・感情は初めての時に一番大きく動く ・感情が動いた時は強く記憶される ・感情は速い ・感情には個人差、文化差がある 最近よく聞く「情動」という言葉の意味もわかった。何かが起こった時に、身体の反応として出るのが情動で、その反応に対する自覚を感情と呼ぶらしい。 例えば蛇(または一見蛇のように見えるベルト)を見た時に、うわっ!と思って即座に飛び退いたり冷や汗をかいたりするのが情動、その後に「冷や汗かいてる、私は怖かったんだ」と恐怖を自覚するのが感情ということ。 その他にも、意思決定は理性で行なっていると思っているけれど感情が影響してて、道徳的判断にも感情が関わっている、という話も書かれていた。 脳科学から考えた感情。今までの「感情」のイメージを覆される。
感情労働の未来恩蔵絢子読み始めたp1〜37 感情の特徴 ・感情は初めての時に一番大きく動く ・感情が動いた時は強く記憶される ・感情は速い ・感情には個人差、文化差がある 最近よく聞く「情動」という言葉の意味もわかった。何かが起こった時に、身体の反応として出るのが情動で、その反応に対する自覚を感情と呼ぶらしい。 例えば蛇(または一見蛇のように見えるベルト)を見た時に、うわっ!と思って即座に飛び退いたり冷や汗をかいたりするのが情動、その後に「冷や汗かいてる、私は怖かったんだ」と恐怖を自覚するのが感情ということ。 その他にも、意思決定は理性で行なっていると思っているけれど感情が影響してて、道徳的判断にも感情が関わっている、という話も書かれていた。 脳科学から考えた感情。今までの「感情」のイメージを覆される。 - 2025年10月28日
 読み終わったオープンダイアローグとは、フィンランドの病院で生まれた精神療法なのだという。 患者さん(と患者さんの周囲の人)が相談をする。患者さんの治療チームが、患者さんや患者さんを取り巻く状況について話す。その様子を患者さんは外から見ている。というのを、日をあけて何度も繰り返すそうだ。 この本では、その手法に少しずつ改変を加えて、オープンダイアローグ的対話実践を試みた様子が描かれている。 この手法では、相談者が独特の幸福感に包まれるという。それは味わってみないとわからないものではあるけれど、自分の話を真剣に聞いてくれ、真摯に考えてくれている空間というのは、心地よいものであるだろうことは想像がつく。 それにはきっと、半年以上かけて作ってきたというルールが上手く作用しているんだろう。相談者を傷つけず、全員の心理的安全性が保たれるようみんなが最大限努力する場所。 私は、ルールの中でも特に、「不確実性に耐える」という項目が印象に残った。対話の中で何が起こるかわからない。もしかしたら予期しないことが起こるかもしれない。動揺したとしてもそのことを他の参加者に伝え、支え合いながら対処する。 これをみんなが心がけてくれているのは安心だろうなあ。
読み終わったオープンダイアローグとは、フィンランドの病院で生まれた精神療法なのだという。 患者さん(と患者さんの周囲の人)が相談をする。患者さんの治療チームが、患者さんや患者さんを取り巻く状況について話す。その様子を患者さんは外から見ている。というのを、日をあけて何度も繰り返すそうだ。 この本では、その手法に少しずつ改変を加えて、オープンダイアローグ的対話実践を試みた様子が描かれている。 この手法では、相談者が独特の幸福感に包まれるという。それは味わってみないとわからないものではあるけれど、自分の話を真剣に聞いてくれ、真摯に考えてくれている空間というのは、心地よいものであるだろうことは想像がつく。 それにはきっと、半年以上かけて作ってきたというルールが上手く作用しているんだろう。相談者を傷つけず、全員の心理的安全性が保たれるようみんなが最大限努力する場所。 私は、ルールの中でも特に、「不確実性に耐える」という項目が印象に残った。対話の中で何が起こるかわからない。もしかしたら予期しないことが起こるかもしれない。動揺したとしてもそのことを他の参加者に伝え、支え合いながら対処する。 これをみんなが心がけてくれているのは安心だろうなあ。 - 2025年10月27日
 学びをつくる問いと対話のデザイン福島創太読み始めた"聞く"ということ、のところで印象に残ったフレーズ。 「自分の意見や考えに固執しない」ではなく、「むしろ進んで影響を受けて変わろうとする」 私は「固執しないようにしよう」「自分の意見を押し付けないようにしよう」という方に意識が向いていたかも。 確かに「変わろう!」っていう方が自分を抑えつけるものもないし、変化する自分に対しても怖がらずにいられそう。
学びをつくる問いと対話のデザイン福島創太読み始めた"聞く"ということ、のところで印象に残ったフレーズ。 「自分の意見や考えに固執しない」ではなく、「むしろ進んで影響を受けて変わろうとする」 私は「固執しないようにしよう」「自分の意見を押し付けないようにしよう」という方に意識が向いていたかも。 確かに「変わろう!」っていう方が自分を抑えつけるものもないし、変化する自分に対しても怖がらずにいられそう。 - 2025年10月23日
- 2025年10月23日
 メメンとモリヨシタケシンスケ借りてきた読み終わったやっぱりヨシタケシンスケさんの本は、気持ちが軽くなる。 どんな気分でいることも、どんな生き方をすることも、自分で選ぶことができる、というメッセージを受け取った。 メメンが作ったお皿を割ってしまって、モリがメメンに謝る場面で、「ものはいつか壊れてしまう。それより、一緒に何をしたかが大事」と言って、お皿でケーキを運んだり、なめたり、お皿を洗ったりしている絵が印象的だった。 「物はいつか壊れる」というのは私も親から言われて育ったので思っていることだったけど、「物と一緒に何をしたか」という観点はなかったかも。特にお皿のような「道具」については(ぬいぐるみとか、何か自分が大切にしているものはそういう感覚を持っているかもしれないけど)。物を大切にする、というより、普段使いの用具と共に過ごす日常も積み重なって思い出となる、という考え方はいいな。 それから、崩れかけていく汚い雪だるまに思いを馳せるのがヨシタケシンスケさんだなあと思った。そうだよね、人間になって旅をできたら面白いね。なくなっていくもの、儚いもの。それも、そこにいる。 それと、次の文も心に残った。 「自分の中のイメージ」と「現実」は、どうしてもずれちゃうのよ。/だから人はいつも、予想がはずれてびっくりしてる。/つまり人は、「思ってたのとちがう!」ってびっくりするために生きてるのよ。/思ってたのとちがうから、世界はつらいし、きびしいし、たのしいし、うつくしい。 そう捉えると、理想と現実が違うことを「そういうものか」「きたー!」みたいな感じで捉えられるのかな。「びっくりいただきました」みたいな笑。 すぐ読めるけど、何度も取り出して読みたい本。
メメンとモリヨシタケシンスケ借りてきた読み終わったやっぱりヨシタケシンスケさんの本は、気持ちが軽くなる。 どんな気分でいることも、どんな生き方をすることも、自分で選ぶことができる、というメッセージを受け取った。 メメンが作ったお皿を割ってしまって、モリがメメンに謝る場面で、「ものはいつか壊れてしまう。それより、一緒に何をしたかが大事」と言って、お皿でケーキを運んだり、なめたり、お皿を洗ったりしている絵が印象的だった。 「物はいつか壊れる」というのは私も親から言われて育ったので思っていることだったけど、「物と一緒に何をしたか」という観点はなかったかも。特にお皿のような「道具」については(ぬいぐるみとか、何か自分が大切にしているものはそういう感覚を持っているかもしれないけど)。物を大切にする、というより、普段使いの用具と共に過ごす日常も積み重なって思い出となる、という考え方はいいな。 それから、崩れかけていく汚い雪だるまに思いを馳せるのがヨシタケシンスケさんだなあと思った。そうだよね、人間になって旅をできたら面白いね。なくなっていくもの、儚いもの。それも、そこにいる。 それと、次の文も心に残った。 「自分の中のイメージ」と「現実」は、どうしてもずれちゃうのよ。/だから人はいつも、予想がはずれてびっくりしてる。/つまり人は、「思ってたのとちがう!」ってびっくりするために生きてるのよ。/思ってたのとちがうから、世界はつらいし、きびしいし、たのしいし、うつくしい。 そう捉えると、理想と現実が違うことを「そういうものか」「きたー!」みたいな感じで捉えられるのかな。「びっくりいただきました」みたいな笑。 すぐ読めるけど、何度も取り出して読みたい本。 - 2025年10月22日
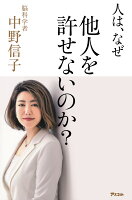 人は、なぜ他人を許せないのか?中野信子読んでる「許せない」「バカなやつだ」と思ってしまうことを、「他人を構うことができる程度にはゆとりがあると考える」という考え方はポジティブ。 自分の暮らしと身の回りの人々のことで精一杯だったら他人のことは考えられない。明日の食料の心配をしなくていい、生活のために遠くから水を汲んでこなくていい、他人のことを考えられる。 それだけで結構幸せじゃないかな。
人は、なぜ他人を許せないのか?中野信子読んでる「許せない」「バカなやつだ」と思ってしまうことを、「他人を構うことができる程度にはゆとりがあると考える」という考え方はポジティブ。 自分の暮らしと身の回りの人々のことで精一杯だったら他人のことは考えられない。明日の食料の心配をしなくていい、生活のために遠くから水を汲んでこなくていい、他人のことを考えられる。 それだけで結構幸せじゃないかな。 - 2025年10月20日
- 2025年10月19日
 山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る山中伸弥,成田奈緒子読み終わった乗り越える力(レジリエンス)は、 ・自己肯定感 ・社会性 ・ソーシャルサポート の3つの要素から成ると実験で出ているらしい。(この実験、どんな実験なのか知りたい。) 自己肯定感と社会性は自分で上げるのは難しいけれど、ソーシャルサポートというのはつまり、「助けて、手を貸して」と言える力のことだそう。周りも、「何があっても助けるよ、大丈夫だよ」と伝えることが大切なんだって。 「自立とは、周りに助けを求められること」というのは、逆説的だけれど、確かにそうだな、と思う。全部自分でやることなんてできない。できる人、得意な人の力を借りて、自分ができること、得意なことはやってあげて。そうすることで、満足感とか肯定感、感謝の気持ちが芽生える。循環なんだよなあ。 同級生だけあって、二人ともリラックスして話しているのが伝わるラフな対談。山中教授の人柄の良さが伝わってきました。
山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る山中伸弥,成田奈緒子読み終わった乗り越える力(レジリエンス)は、 ・自己肯定感 ・社会性 ・ソーシャルサポート の3つの要素から成ると実験で出ているらしい。(この実験、どんな実験なのか知りたい。) 自己肯定感と社会性は自分で上げるのは難しいけれど、ソーシャルサポートというのはつまり、「助けて、手を貸して」と言える力のことだそう。周りも、「何があっても助けるよ、大丈夫だよ」と伝えることが大切なんだって。 「自立とは、周りに助けを求められること」というのは、逆説的だけれど、確かにそうだな、と思う。全部自分でやることなんてできない。できる人、得意な人の力を借りて、自分ができること、得意なことはやってあげて。そうすることで、満足感とか肯定感、感謝の気持ちが芽生える。循環なんだよなあ。 同級生だけあって、二人ともリラックスして話しているのが伝わるラフな対談。山中教授の人柄の良さが伝わってきました。 - 2025年10月17日
 母の最終講義最相葉月気になる図書館の新刊の棚に並んでいて、パラパラと読んでみた。 著者のことを知らなかったのだけれど、新聞の悩み相談のコーナーを担当しているらしい。 その中で、相談内容の最後に「自分がどんな心の持ちようで過ごしたらいいか」と書かれているお便りが多くなったことが気になると書いていた。心の持ちようより先に、解決に向かうよう方法を探すことができるのではないか、と。 これは、「自己責任」の考え方が蔓延しているからではないか。私自身も、結構自分の捉え方でなんとかしようとしがち。 個人の責任ではなくて、社会全体の仕組みとして捉えて、社会をより良くする方にエネルギーを使いたい。 タイトルにある、お母さんの介護の内容も気になるので、今度借りてみよう。
母の最終講義最相葉月気になる図書館の新刊の棚に並んでいて、パラパラと読んでみた。 著者のことを知らなかったのだけれど、新聞の悩み相談のコーナーを担当しているらしい。 その中で、相談内容の最後に「自分がどんな心の持ちようで過ごしたらいいか」と書かれているお便りが多くなったことが気になると書いていた。心の持ちようより先に、解決に向かうよう方法を探すことができるのではないか、と。 これは、「自己責任」の考え方が蔓延しているからではないか。私自身も、結構自分の捉え方でなんとかしようとしがち。 個人の責任ではなくて、社会全体の仕組みとして捉えて、社会をより良くする方にエネルギーを使いたい。 タイトルにある、お母さんの介護の内容も気になるので、今度借りてみよう。 - 2025年10月17日
 歩くこと、または飼いならされずに詩的な人生を生きる術トマス・エスペダル,枇谷玲子気になる
歩くこと、または飼いならされずに詩的な人生を生きる術トマス・エスペダル,枇谷玲子気になる - 2025年10月16日
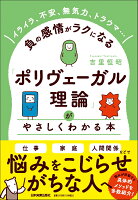 読み終わったとても分かりやすい本だった。交感神経と副交感神経があり、副交感神経がリラックスした状態だということは今までも知っていたけれど、このポリヴェーガル理論では、副交感神経をさらに2つに分けるらしい。赤(交感神経)と青(副交感神経・背側迷走神経複合体)と緑(副交感神経・腹側迷走神経複合体)という色分けがまた簡単でいい。 大事なのは、体の状態を整えること。がんばり過ぎちゃう赤と、無気力な青が悪いわけではない。安心や安全を感じられる緑を増やしましょうと言っている。 体を整えると考えると、問題の捉え方も変わる。多動の子を「落ち着きのない子」と見るのではなく、「落ち着かない体となんとか頑張って一緒に暮らしている子」と捉えるという例を読んで、人に対しても自分に対しても優しくなれる考え方だと感じた。 緑は相手に移っていくらしい。私も緑を意識して生活したい。
読み終わったとても分かりやすい本だった。交感神経と副交感神経があり、副交感神経がリラックスした状態だということは今までも知っていたけれど、このポリヴェーガル理論では、副交感神経をさらに2つに分けるらしい。赤(交感神経)と青(副交感神経・背側迷走神経複合体)と緑(副交感神経・腹側迷走神経複合体)という色分けがまた簡単でいい。 大事なのは、体の状態を整えること。がんばり過ぎちゃう赤と、無気力な青が悪いわけではない。安心や安全を感じられる緑を増やしましょうと言っている。 体を整えると考えると、問題の捉え方も変わる。多動の子を「落ち着きのない子」と見るのではなく、「落ち着かない体となんとか頑張って一緒に暮らしている子」と捉えるという例を読んで、人に対しても自分に対しても優しくなれる考え方だと感じた。 緑は相手に移っていくらしい。私も緑を意識して生活したい。 - 2025年10月15日
 かずをはぐくむ森田真生,西淑読み始めたp18 「大人が子どもに何かを問いかけるとき、あらかじめ返ってくるべき答えを、こちらで決めてしまっていることがある。本来、問いかけは未知の対話への入り口のはずなのに、気づけば、こちらで想定しておいた暗黙の結論に、子の発想を閉ざそうとしてしまうのである。だが、そんな大人の賢しらな狙いを、子どもは見事に裏切ってくれる。」 こういうことってよくあるなあ、と思う。問いかけの様相を呈しているけれど、実はコントロールするための質問だったり。だから、違う答えが返ってくると苛立ったり。「問いかけは未知の対話への入り口」であることを忘れたくない。
かずをはぐくむ森田真生,西淑読み始めたp18 「大人が子どもに何かを問いかけるとき、あらかじめ返ってくるべき答えを、こちらで決めてしまっていることがある。本来、問いかけは未知の対話への入り口のはずなのに、気づけば、こちらで想定しておいた暗黙の結論に、子の発想を閉ざそうとしてしまうのである。だが、そんな大人の賢しらな狙いを、子どもは見事に裏切ってくれる。」 こういうことってよくあるなあ、と思う。問いかけの様相を呈しているけれど、実はコントロールするための質問だったり。だから、違う答えが返ってくると苛立ったり。「問いかけは未知の対話への入り口」であることを忘れたくない。 - 2025年10月15日
 つくるをほぐす山内佑輔読み始めた「折り紙モデル」と「砂場モデル」の考え方はなるほど!と思った。 折り紙モデルは完成形があって、きれいにできることがゴール。評価しやすい。一人で作ることが基本。 砂場モデルは、トンネルだったりお城だったり、それを作っている過程が大事。コミュニケーションが生まれる。 この砂場モデルの中にも学びがあるよね、というのが筆者が伝えたいことみたい。紙コップ10000個の授業、面白そう!
つくるをほぐす山内佑輔読み始めた「折り紙モデル」と「砂場モデル」の考え方はなるほど!と思った。 折り紙モデルは完成形があって、きれいにできることがゴール。評価しやすい。一人で作ることが基本。 砂場モデルは、トンネルだったりお城だったり、それを作っている過程が大事。コミュニケーションが生まれる。 この砂場モデルの中にも学びがあるよね、というのが筆者が伝えたいことみたい。紙コップ10000個の授業、面白そう! - 2025年10月15日
 やさしいがつづかない稲垣諭読んでる「やさしい」の定義は、 ①自分のコントロール権を手放し、相手に委ねること ②その結果起こることの責任は引き受けること ①は割と簡単にできる。人は、人に対して善意で行動できる小さなやさしさ(筆者は「マイクロ・カインドネス」と呼んでいる)があるから。 でも②が難しい。仕事を「任せる」と言いながら、起こったことの責任を取らない上司の例が出てくる。
やさしいがつづかない稲垣諭読んでる「やさしい」の定義は、 ①自分のコントロール権を手放し、相手に委ねること ②その結果起こることの責任は引き受けること ①は割と簡単にできる。人は、人に対して善意で行動できる小さなやさしさ(筆者は「マイクロ・カインドネス」と呼んでいる)があるから。 でも②が難しい。仕事を「任せる」と言いながら、起こったことの責任を取らない上司の例が出てくる。 - 2025年10月14日
- 2025年10月14日
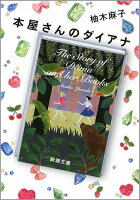 本屋さんのダイアナ柚木麻子読み終わったダイアナが、育ちのいい彩子に憧れる気持ちもわかる。彩子に、ダイアナがキラキラと輝いて見えるのもわかる。ないものねだりと言ってしまえばそれまでなんだけれど、本人たちにとっては切実な憧れ。 だからこそ、けんか別れしてしまったことがつらい。全然違う道を行くことになってしまったけれど、心の奥底で痛みを抱えながら、それでも相手との思い出を大切にしまって過ごしている。二人がもがいている様子がとても愛おしい。 小説ならではの、こんなに上手くいくかな?ってところもあるけれど、読み終わったあとはとても明るい気持ちになった。 「ダイアナはどこまでも明るい一本道が自分の中にも伸びていくのがわかった。」という一文が好き。
本屋さんのダイアナ柚木麻子読み終わったダイアナが、育ちのいい彩子に憧れる気持ちもわかる。彩子に、ダイアナがキラキラと輝いて見えるのもわかる。ないものねだりと言ってしまえばそれまでなんだけれど、本人たちにとっては切実な憧れ。 だからこそ、けんか別れしてしまったことがつらい。全然違う道を行くことになってしまったけれど、心の奥底で痛みを抱えながら、それでも相手との思い出を大切にしまって過ごしている。二人がもがいている様子がとても愛おしい。 小説ならではの、こんなに上手くいくかな?ってところもあるけれど、読み終わったあとはとても明るい気持ちになった。 「ダイアナはどこまでも明るい一本道が自分の中にも伸びていくのがわかった。」という一文が好き。 - 2025年10月13日
 うけいれるにはクララ・デュポン=モノ,松本百合子読み終わったフランスのセヴェンヌ地方が舞台となり、石が語り手となって話を進めていく。その設定に少し驚いたけれど、調べてみたらそこは、石灰岩大地で渓谷と山岳地帯が美しい、ユネスコの文化遺産に指定されたところなのだそう。行ってみたい。 両親と長男、長女の家庭に子どもが生まれるのだけれど、その子どもには障がいがあった。その子どもをめぐる、一言で言えば家族の喪失と再生の物語、というところなのだろうけれど、そんなありふれた言葉でまとめてしまうにはもったいない、とても繊細で力強いお話だった。 小説全体が、山あいのセヴェンヌ地方の静けさが流れているようなトーンに抑えている。だからこそ、家族の感情の強さが時折浮かび上がってきて、胸を衝かれる。 それと、表現がとても美しい。「風によってめくれた小さな葉が金箔のようにキラキラと輝くポプラの木のささやき」とか、「澄んだ黄金色が空中を流れるような秋」とか。 とても満足感のある小説だった。たまたま図書館で目に入ってきてよかった。
うけいれるにはクララ・デュポン=モノ,松本百合子読み終わったフランスのセヴェンヌ地方が舞台となり、石が語り手となって話を進めていく。その設定に少し驚いたけれど、調べてみたらそこは、石灰岩大地で渓谷と山岳地帯が美しい、ユネスコの文化遺産に指定されたところなのだそう。行ってみたい。 両親と長男、長女の家庭に子どもが生まれるのだけれど、その子どもには障がいがあった。その子どもをめぐる、一言で言えば家族の喪失と再生の物語、というところなのだろうけれど、そんなありふれた言葉でまとめてしまうにはもったいない、とても繊細で力強いお話だった。 小説全体が、山あいのセヴェンヌ地方の静けさが流れているようなトーンに抑えている。だからこそ、家族の感情の強さが時折浮かび上がってきて、胸を衝かれる。 それと、表現がとても美しい。「風によってめくれた小さな葉が金箔のようにキラキラと輝くポプラの木のささやき」とか、「澄んだ黄金色が空中を流れるような秋」とか。 とても満足感のある小説だった。たまたま図書館で目に入ってきてよかった。 - 2025年10月13日
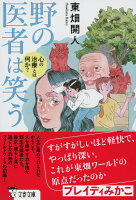 読み終わった文庫本まえがきに、「ここに描かれているのは、愚かな若者が愚かな自分に気がつき、そして世界の広さに打ちのめされる物語だ」とあった。私も明確にそんな時があったことを思い出せる。 筆者は、心の治療は時代の生んだ病いに対処し、時代に合わせた治療を提供するものなのだと書いている。今は「軽薄でないと息苦しい時代」に生きており、「だから、軽薄なものが癒やしになる」のだそう。単行本は2015年に出版されているけれど、今はもっとひどくなっているかもしれない。 読書は、そういう意味では逆をいく行為なのだと思った。問いを抱え、ネガティブケイパビリティを育てる。自分の根っこを増やし、太くしていく。 ヒーリングやスピリチュアルなものを否定する気持ちは決してないし、何かに救われるのであればそれが何であっても良いと思う。ただ、筆者が「臨床心理学」をなぜ選んだのかを自覚するくだりで、私はホッとする気持ちを覚えた。 「学問というのは本質的に常識を疑い、自分自身を疑うものだ。(中略)学問は常識が疑われ、地面がゆらゆらと不安定になったときこそ、逞しく成長することができる。臨床心理学もまた、そうやって発展してきたのだ。この打たれ強さこそが、学問と呼ばれる文化のいいところであり、野の医者文化とは違うところである。」 私も、常識を疑い、自分自身を疑える人間でいたい。無理にポジティブに考えようとするのではなく、素の自分を受け入れ、人の話をよく聴ける心を持っていたい。そんなことを考えた本だった。
読み終わった文庫本まえがきに、「ここに描かれているのは、愚かな若者が愚かな自分に気がつき、そして世界の広さに打ちのめされる物語だ」とあった。私も明確にそんな時があったことを思い出せる。 筆者は、心の治療は時代の生んだ病いに対処し、時代に合わせた治療を提供するものなのだと書いている。今は「軽薄でないと息苦しい時代」に生きており、「だから、軽薄なものが癒やしになる」のだそう。単行本は2015年に出版されているけれど、今はもっとひどくなっているかもしれない。 読書は、そういう意味では逆をいく行為なのだと思った。問いを抱え、ネガティブケイパビリティを育てる。自分の根っこを増やし、太くしていく。 ヒーリングやスピリチュアルなものを否定する気持ちは決してないし、何かに救われるのであればそれが何であっても良いと思う。ただ、筆者が「臨床心理学」をなぜ選んだのかを自覚するくだりで、私はホッとする気持ちを覚えた。 「学問というのは本質的に常識を疑い、自分自身を疑うものだ。(中略)学問は常識が疑われ、地面がゆらゆらと不安定になったときこそ、逞しく成長することができる。臨床心理学もまた、そうやって発展してきたのだ。この打たれ強さこそが、学問と呼ばれる文化のいいところであり、野の医者文化とは違うところである。」 私も、常識を疑い、自分自身を疑える人間でいたい。無理にポジティブに考えようとするのではなく、素の自分を受け入れ、人の話をよく聴ける心を持っていたい。そんなことを考えた本だった。 - 2025年10月8日
読み込み中...




