きみはメタルギアソリッド5:ファントムペインをプレイする

きみはメタルギアソリッド5:ファントムペインをプレイする
ジャミル・ジャン・コチャイ
矢倉喬士
河出書房新社
2025年2月27日
95件の記録
 べべ@b_ebe2026年2月17日読み終わった大傑作だった……。今年のベスト10に入る。作者は92年生まれなので次回作も期待。訳者後書きにて、『もういい!』発表当時アメリカが自ら弾圧したアフガニスタンから観察される事への忌避があった事を知り阿呆が過ぎるぜ。
べべ@b_ebe2026年2月17日読み終わった大傑作だった……。今年のベスト10に入る。作者は92年生まれなので次回作も期待。訳者後書きにて、『もういい!』発表当時アメリカが自ら弾圧したアフガニスタンから観察される事への忌避があった事を知り阿呆が過ぎるぜ。
 ekmiico@ek-wine19722026年1月24日読み終わった凄く面白かった!表題作、読み始めてすぐこれは凄くいいぞ…と思う。名作。どの短篇もいい。矢倉喬士さんの翻訳も解説も素晴らしい。たくさん読まれて次の翻訳に繋がりますように。
ekmiico@ek-wine19722026年1月24日読み終わった凄く面白かった!表題作、読み始めてすぐこれは凄くいいぞ…と思う。名作。どの短篇もいい。矢倉喬士さんの翻訳も解説も素晴らしい。たくさん読まれて次の翻訳に繋がりますように。

 miki@mikis2025年12月28日読み終わったゲームと現実の境界線があいまいになっていく標題作。 部屋の中で戦争ゲームをするその外では現実の紛争が絶えないという不気味さ。 政治、宗教、紛争…が人生を決定づける世界が同じ世界にあるということ。 選択できる世界にいるからこそ 誠実に選択していきたい。 イーユン・リーのお弟子さんと聞き気軽に手に取ったが、考えさせられる事の多い一冊だった。
miki@mikis2025年12月28日読み終わったゲームと現実の境界線があいまいになっていく標題作。 部屋の中で戦争ゲームをするその外では現実の紛争が絶えないという不気味さ。 政治、宗教、紛争…が人生を決定づける世界が同じ世界にあるということ。 選択できる世界にいるからこそ 誠実に選択していきたい。 イーユン・リーのお弟子さんと聞き気軽に手に取ったが、考えさせられる事の多い一冊だった。





 ktr@ktrrr2025年10月19日読み終わった今年ベストの読書体験。 アフガンの過去と現在と未来、インターネット、家族、動物など、短編集を読む中で考えるべきキーワードがたくさんあった。「サルになったダリーの話」と「巡礼者ホタクの呪い」が中でもお気に入り。
ktr@ktrrr2025年10月19日読み終わった今年ベストの読書体験。 アフガンの過去と現在と未来、インターネット、家族、動物など、短編集を読む中で考えるべきキーワードがたくさんあった。「サルになったダリーの話」と「巡礼者ホタクの呪い」が中でもお気に入り。

- 垣本@kakimoto2025年9月21日読み終わった普段翻訳文学を読むとは言いつつほぼキリスト教圏なので味わいがかなり違って面白かった あと翻訳が上手い気がする タイトルに釣られて買ったけど良かった 「きみはメタルギアソリッド〜」と「もういい!」と「ヤギの寓話」と「巡礼者ホタクの呪い」が好き 長めの話は前提知識がないからしっかり読めてない気はする

 yt@yt2025年8月14日読み終わった「チクショウ、だってコジマだぜ、メタルギアだぜ」(p9) イギリスからもソ連からも侵攻され。 さらに良かれと思って侵攻してきたアメリカが何千回と爆撃を繰り返すアフガニスタンの短篇集。 この世界の片隅でも生活は続く。 実験的な形式で描かれた現実が重すぎてつらい。 「職務内容は以下の通り」を読むだけで過酷だ。 イスラム文化を知れるのが常に紛争の合間であることもつらい。 サルに戦争させるとか、何やってんだ。 ドローン兵器をドローンで撃ち落とすとか、何やってんだ。 LLMに書かせた文章をLLMに要約させるとか、何やってんだ。 インシャーラーとしか祈れない。
yt@yt2025年8月14日読み終わった「チクショウ、だってコジマだぜ、メタルギアだぜ」(p9) イギリスからもソ連からも侵攻され。 さらに良かれと思って侵攻してきたアメリカが何千回と爆撃を繰り返すアフガニスタンの短篇集。 この世界の片隅でも生活は続く。 実験的な形式で描かれた現実が重すぎてつらい。 「職務内容は以下の通り」を読むだけで過酷だ。 イスラム文化を知れるのが常に紛争の合間であることもつらい。 サルに戦争させるとか、何やってんだ。 ドローン兵器をドローンで撃ち落とすとか、何やってんだ。 LLMに書かせた文章をLLMに要約させるとか、何やってんだ。 インシャーラーとしか祈れない。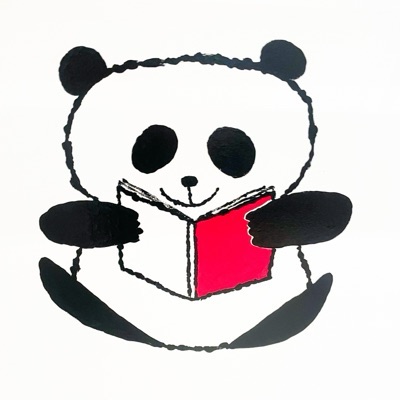









 ヨネヤマゼン@zen2025年7月14日ちょっと開いたGOAT文学賞に応募した作品は二人称で書いてみたんだけど、そのとき一番向き合ったのはこの表題作だった やっぱり二人称の小説はまだまだ可能性があると思う……今は飛び道具と思われてるが、そのうちジャンルになっていくはず おれたちフォロワーが熱心に書けばね 今回の発見は、「あなた」より「きみ」の方がフラットな二人称なのでは、ということだった やっぱ訳も良いんだろうなあこれ
ヨネヤマゼン@zen2025年7月14日ちょっと開いたGOAT文学賞に応募した作品は二人称で書いてみたんだけど、そのとき一番向き合ったのはこの表題作だった やっぱり二人称の小説はまだまだ可能性があると思う……今は飛び道具と思われてるが、そのうちジャンルになっていくはず おれたちフォロワーが熱心に書けばね 今回の発見は、「あなた」より「きみ」の方がフラットな二人称なのでは、ということだった やっぱ訳も良いんだろうなあこれ oheso@oheso2025年7月5日読み終わった@ 自宅作者のジャミル・ジャン・コチャイはパキスタンの難民キャンプが出生地の1992年生まれ。ゲームやネットなど我々の目の前にあるポップカルチャーと、今も続く紛争やアメリカとイスラム教圏の関係性含む作者のルーツを接続していくような短編集。
oheso@oheso2025年7月5日読み終わった@ 自宅作者のジャミル・ジャン・コチャイはパキスタンの難民キャンプが出生地の1992年生まれ。ゲームやネットなど我々の目の前にあるポップカルチャーと、今も続く紛争やアメリカとイスラム教圏の関係性含む作者のルーツを接続していくような短編集。
 ヨネヤマゼン@zen2025年7月4日ちょっと開いたふと短編小説が書きたくなり、GOATに応募することに決めた 気持ちが熱いうちに急いで書こう 最近読んだこの表題作を読み直す お題は「素顔」 これと、エルヴェ・ル・テリエ『異常』と、あと映画『サブスタンス』をくっつけたようなお話にしたい 6000字なら書けるだろう やるぞ
ヨネヤマゼン@zen2025年7月4日ちょっと開いたふと短編小説が書きたくなり、GOATに応募することに決めた 気持ちが熱いうちに急いで書こう 最近読んだこの表題作を読み直す お題は「素顔」 これと、エルヴェ・ル・テリエ『異常』と、あと映画『サブスタンス』をくっつけたようなお話にしたい 6000字なら書けるだろう やるぞ 雨氷@supercooling2025年6月12日まだ読んでる✔︎「差出人に返送」を読み終える ✍️彼女はドアの方へ駆け出すと、廊下に、マットの上に、また小さなダンボール箱を見つけた。今度は耳だった。片方だけの耳。指のときと同じく、きれいな切断面で、外科手術を受けたみたいで、 最初は動かなかったけれど、アミナが肉屋の包み紙(ブッチャー・ペーパー)に包まれたその耳を拾い上げて口もとに近づけ、 「あなたの残りはどこにいるの?」とささやくと、彼女の手のひらで耳が脈打ったように感じられた。(pp.32-33) ✍️一緒に、肉と肉を、刺しては縫って、裂いては結びつけて、そうするうちにアミナとユスフの二人は、ある考えに達するのだった。この先彼らは二度とカブールを離れることはないだろうと。ここが彼らの家なのだと。(p.42)
雨氷@supercooling2025年6月12日まだ読んでる✔︎「差出人に返送」を読み終える ✍️彼女はドアの方へ駆け出すと、廊下に、マットの上に、また小さなダンボール箱を見つけた。今度は耳だった。片方だけの耳。指のときと同じく、きれいな切断面で、外科手術を受けたみたいで、 最初は動かなかったけれど、アミナが肉屋の包み紙(ブッチャー・ペーパー)に包まれたその耳を拾い上げて口もとに近づけ、 「あなたの残りはどこにいるの?」とささやくと、彼女の手のひらで耳が脈打ったように感じられた。(pp.32-33) ✍️一緒に、肉と肉を、刺しては縫って、裂いては結びつけて、そうするうちにアミナとユスフの二人は、ある考えに達するのだった。この先彼らは二度とカブールを離れることはないだろうと。ここが彼らの家なのだと。(p.42)
 雨氷@supercooling2025年6月10日まだ読んでる✔︎「きみはメタルギアソリッドⅤ:ファントムペインをプレイする」を読み終える ーーーーーーーーーー ✍️ 父さんは色黒でがっしりしていて、きみとは全然似ていなかったから、小さい頃のきみは、いつかハグリッドがやってきて、お前さんは「穢れた血」の生まれだと教えてくれて、そこから本当の人生が、つまり、父さんの人生の痛みとか罪とか絶望とか無力感とか裁判とか恥辱とか、そういうものの重みに縛られない本当の人生が始まるんだと思っていた。(pp.11-12) ✍️ きみは愛国者ではなく、民族主義者でもなく、帽子(パコル)とカミーズを身に着けて歩き回り、民族楽器のタブラを叩き、お気に入りの歌手はアフマド・ザヒールと答えるようなアフガニスタン人の一員でもないわけだが、ゲーム史上で一番の伝説となり、芸術の観点からしても重要なシリーズ最後の舞台が一九八○年代のアフガニスタンときたものだから、いざそれを手にするきみはいっそうワクワクしていて、それもそのはず、きみは長いこと『コール オブ デューティ』(一人称視点のシューティングゲームの一つ)でアフガン人たちを撃ち殺してきたわけで、父さんによく似た顔の軍人たちが次から次へと襲い来るのを初めて虐殺したときには自己嫌悪にも陥ったけど、今では不思議と免疫がついてしまった。(p.13) 💭ハグリッドのくだりは正直おもしろいと思ってしまった(私も11歳になったらホグワーツに行けると期待していた時期があったので)が、私たち(どこまで含むのか曖昧な言葉!)が普段触れる「世界で人気のエンタメ作品」の多くは西側諸国の考え方を基盤に作られており、でも西側諸国の筆頭であるアメリカにも異なる文化圏から来た人が暮らしており、「世界で人気のエンタメ作品」を楽しんでおり、でもそこには自分と作り手の差異を感じるような表現も含まれており、逃げ切れるものではないのだろうと思う。私(これは他の誰でもない自分自身のこと)だって、不意打ちのように作り手との差異を気づかされることはあるし、そもそもこの本を読むこと自体がそういう体験になっている。 ーーーーーーーーーー ✍️夜、闇にまぎれてきみは父さんの屋敷へと潜入(スニーク)して、十五フィートの土壁をよじ登って屋根の上を這って進み、屋敷の一番高い位置に到着すると、そこでは父さんが戦闘機や爆撃に備える警戒任務にあたっていて、その背中にきみは麻酔銃を二発撃ち、父さんが気絶して倒れていくところを両手で抱きとめて、父さんを、といってもこの場合は今のきみと同い年くらいなわけだけど、闇の中で、この戦争でこれから失われることになる屋敷の屋根の上で、きみは父さんを抱きしめて、その体はまだ強くて元気で、心も壊れていないのを感じながら、そっと静かに寝かせてあげる。空に飲み込まれてしまわないように。(p.12) 💭「ファントムペイン」とは「幻肢痛(すでに切断された手や足がまだあるように思われ、痛みを感じる状態※)」のことだから、父の故郷であるアフガニスタンのマップをゲーム内で進めながら、喪われた痛みを追体験する物語を描いたのかな。 ※デジタル大辞林(小学館)より
雨氷@supercooling2025年6月10日まだ読んでる✔︎「きみはメタルギアソリッドⅤ:ファントムペインをプレイする」を読み終える ーーーーーーーーーー ✍️ 父さんは色黒でがっしりしていて、きみとは全然似ていなかったから、小さい頃のきみは、いつかハグリッドがやってきて、お前さんは「穢れた血」の生まれだと教えてくれて、そこから本当の人生が、つまり、父さんの人生の痛みとか罪とか絶望とか無力感とか裁判とか恥辱とか、そういうものの重みに縛られない本当の人生が始まるんだと思っていた。(pp.11-12) ✍️ きみは愛国者ではなく、民族主義者でもなく、帽子(パコル)とカミーズを身に着けて歩き回り、民族楽器のタブラを叩き、お気に入りの歌手はアフマド・ザヒールと答えるようなアフガニスタン人の一員でもないわけだが、ゲーム史上で一番の伝説となり、芸術の観点からしても重要なシリーズ最後の舞台が一九八○年代のアフガニスタンときたものだから、いざそれを手にするきみはいっそうワクワクしていて、それもそのはず、きみは長いこと『コール オブ デューティ』(一人称視点のシューティングゲームの一つ)でアフガン人たちを撃ち殺してきたわけで、父さんによく似た顔の軍人たちが次から次へと襲い来るのを初めて虐殺したときには自己嫌悪にも陥ったけど、今では不思議と免疫がついてしまった。(p.13) 💭ハグリッドのくだりは正直おもしろいと思ってしまった(私も11歳になったらホグワーツに行けると期待していた時期があったので)が、私たち(どこまで含むのか曖昧な言葉!)が普段触れる「世界で人気のエンタメ作品」の多くは西側諸国の考え方を基盤に作られており、でも西側諸国の筆頭であるアメリカにも異なる文化圏から来た人が暮らしており、「世界で人気のエンタメ作品」を楽しんでおり、でもそこには自分と作り手の差異を感じるような表現も含まれており、逃げ切れるものではないのだろうと思う。私(これは他の誰でもない自分自身のこと)だって、不意打ちのように作り手との差異を気づかされることはあるし、そもそもこの本を読むこと自体がそういう体験になっている。 ーーーーーーーーーー ✍️夜、闇にまぎれてきみは父さんの屋敷へと潜入(スニーク)して、十五フィートの土壁をよじ登って屋根の上を這って進み、屋敷の一番高い位置に到着すると、そこでは父さんが戦闘機や爆撃に備える警戒任務にあたっていて、その背中にきみは麻酔銃を二発撃ち、父さんが気絶して倒れていくところを両手で抱きとめて、父さんを、といってもこの場合は今のきみと同い年くらいなわけだけど、闇の中で、この戦争でこれから失われることになる屋敷の屋根の上で、きみは父さんを抱きしめて、その体はまだ強くて元気で、心も壊れていないのを感じながら、そっと静かに寝かせてあげる。空に飲み込まれてしまわないように。(p.12) 💭「ファントムペイン」とは「幻肢痛(すでに切断された手や足がまだあるように思われ、痛みを感じる状態※)」のことだから、父の故郷であるアフガニスタンのマップをゲーム内で進めながら、喪われた痛みを追体験する物語を描いたのかな。 ※デジタル大辞林(小学館)より
 m@kyri2025年5月6日読み終わった@ 図書館すごくおもしろかった!大好きなイーユン・リーのお弟子さんということに惹かれて買って、イスラム系文学もマジック・リアリズム文学もほとんど縁がなかったけど一気に読めた。 表題作も好きだったけど「ハラヘリー・リッキー・ダディ」がすごかった。まさに今読むべき短編がたくさん詰まった本だった。
m@kyri2025年5月6日読み終わった@ 図書館すごくおもしろかった!大好きなイーユン・リーのお弟子さんということに惹かれて買って、イスラム系文学もマジック・リアリズム文学もほとんど縁がなかったけど一気に読めた。 表題作も好きだったけど「ハラヘリー・リッキー・ダディ」がすごかった。まさに今読むべき短編がたくさん詰まった本だった。


 it_shine@it_shine2025年4月23日読み終わったアフガニスタンとアメリカの関係とか、紛争とか、戦争とか、いろんなことを考えてしまう。移民とか。宗教とか。 そこには人が生きていて、いろんな思いを持っている。あっけなく殺されてしまうことだってあるし、そういうことがこの小説には描かれている部分もある。 平和な日本に生きて生活しているとそういうことは、他山の石というか他人事になってしまいがちだけど、小説を通して感じるものは少なからずある。 なんというか、いたたまれない気持ちになる。 マジック・リアリズムだったり、読点全然なく何ページも続いたり、いろんな手法で書かれているけれど、それが本質では多分なくて。 タイトルのゲームの話題に釣られて読んだけれど、もっと違うところに連れてこられてしまって、戸惑っているというか。生きている。それも平和に。平和だからできることがあるし、平穏だからできることがある。明日死ぬように生きるなんて難しいことだけど、それでも、そうやって生を紡いでいる人がいて、そういう人が文学をやっていることだってあるんだということに気がついたというか、目を見開かされたというか。
it_shine@it_shine2025年4月23日読み終わったアフガニスタンとアメリカの関係とか、紛争とか、戦争とか、いろんなことを考えてしまう。移民とか。宗教とか。 そこには人が生きていて、いろんな思いを持っている。あっけなく殺されてしまうことだってあるし、そういうことがこの小説には描かれている部分もある。 平和な日本に生きて生活しているとそういうことは、他山の石というか他人事になってしまいがちだけど、小説を通して感じるものは少なからずある。 なんというか、いたたまれない気持ちになる。 マジック・リアリズムだったり、読点全然なく何ページも続いたり、いろんな手法で書かれているけれど、それが本質では多分なくて。 タイトルのゲームの話題に釣られて読んだけれど、もっと違うところに連れてこられてしまって、戸惑っているというか。生きている。それも平和に。平和だからできることがあるし、平穏だからできることがある。明日死ぬように生きるなんて難しいことだけど、それでも、そうやって生を紡いでいる人がいて、そういう人が文学をやっていることだってあるんだということに気がついたというか、目を見開かされたというか。


 it_shine@it_shine2025年4月22日読んでる読点が何ページにも渡ってない文とか、物語の形式になっていない掌編とかが入ってて、先鋭的、実験的。小説を壊そうとしているかのよう。テーマ的に共感できるかというとそんなことはあまりなくて、自分とは離れた人たちの話で、入っていきにくい。アフガニスタンでの戦争、アメリカに渡る、ということがどのくらい困難なことなのか、想像できないでいる。 知らない世界を垣間見せてくれる小説ではある。
it_shine@it_shine2025年4月22日読んでる読点が何ページにも渡ってない文とか、物語の形式になっていない掌編とかが入ってて、先鋭的、実験的。小説を壊そうとしているかのよう。テーマ的に共感できるかというとそんなことはあまりなくて、自分とは離れた人たちの話で、入っていきにくい。アフガニスタンでの戦争、アメリカに渡る、ということがどのくらい困難なことなのか、想像できないでいる。 知らない世界を垣間見せてくれる小説ではある。
 it_shine@it_shine2025年4月21日読んでるゲームがどう出てくるのかな、と思って手に取ってみたら、アフガニスタンとアメリカについての掌編小説集だった。 イスラム文化、マジックリアリズム的な要素のあるものもある。 イスラムのこと、ほとんど知らなかったけれど、宗教が違うというだけで、彼らも同じ人間なんだと思い知らされる。 この本をきっかけにイスラム文化に興味を持ちました。
it_shine@it_shine2025年4月21日読んでるゲームがどう出てくるのかな、と思って手に取ってみたら、アフガニスタンとアメリカについての掌編小説集だった。 イスラム文化、マジックリアリズム的な要素のあるものもある。 イスラムのこと、ほとんど知らなかったけれど、宗教が違うというだけで、彼らも同じ人間なんだと思い知らされる。 この本をきっかけにイスラム文化に興味を持ちました。
 読谷 文@fumi_yomitani2025年3月18日読み終わったアフガニスタン系米国人の作者による短編集。 イーユン・リーのお弟子さんによる移民文学とくれば、読まずにはいられない! 川名潤さんの装丁・造本もとてもクールでカッコいい。 ブログに感想を書きました👇 https://fumi-yomitani.hatenablog.com/entry/kimimeta
読谷 文@fumi_yomitani2025年3月18日読み終わったアフガニスタン系米国人の作者による短編集。 イーユン・リーのお弟子さんによる移民文学とくれば、読まずにはいられない! 川名潤さんの装丁・造本もとてもクールでカッコいい。 ブログに感想を書きました👇 https://fumi-yomitani.hatenablog.com/entry/kimimeta








































































