
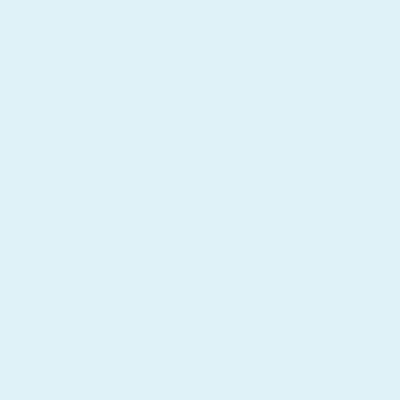
あむ
@Petrichor
読書感想文を書きます
- 2026年2月22日
 雷龍楼の殺人新名智読み終わった冒頭の「読者への挑戦」。 一連の殺人事件の犯人を先に明かしているミステリーがあると知り、だとすれば受けようという気持ちでページをめくった。 結果、見事にしてやられた。 この物語すべてを通して私という読者が試されていたのだとしたら、 結果は「完敗」と言えるだろう。 以下ネタバレ含みます ---------------------------------- 徐々に散りばめられていく小さな違和感。 これが作者による意図的なものであるとわかっていながらも、私は最後まで真相に気づけなかった。 わかった上で読み返してみれば、違和感のある行動ばかり。 霞は自分の置かれた状況を、触って、感じとって、そして決して、何も「見て」いなかった。 その核心たるポイントを「パンダ」で持っていく様はページ送りの構成を含めて秀逸。 物語を読んで感動したり後味が悪くなったり、そんな感情が渦巻くことが定番の中で、こんなにも素直でまっすぐな「悔しい」という感情を抱えたのははじめて。 新名智先生の完璧で穴のない挑戦状を、また受け取ってみたいものだ。
雷龍楼の殺人新名智読み終わった冒頭の「読者への挑戦」。 一連の殺人事件の犯人を先に明かしているミステリーがあると知り、だとすれば受けようという気持ちでページをめくった。 結果、見事にしてやられた。 この物語すべてを通して私という読者が試されていたのだとしたら、 結果は「完敗」と言えるだろう。 以下ネタバレ含みます ---------------------------------- 徐々に散りばめられていく小さな違和感。 これが作者による意図的なものであるとわかっていながらも、私は最後まで真相に気づけなかった。 わかった上で読み返してみれば、違和感のある行動ばかり。 霞は自分の置かれた状況を、触って、感じとって、そして決して、何も「見て」いなかった。 その核心たるポイントを「パンダ」で持っていく様はページ送りの構成を含めて秀逸。 物語を読んで感動したり後味が悪くなったり、そんな感情が渦巻くことが定番の中で、こんなにも素直でまっすぐな「悔しい」という感情を抱えたのははじめて。 新名智先生の完璧で穴のない挑戦状を、また受け取ってみたいものだ。 - 2026年1月23日
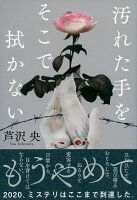 汚れた手をそこで拭かない芦沢央読み終わった誰かに嘘をついてしまったとき、後ろめたい事実を抱えてしまったとき、誰しもが思ったことがあるのではないか。 「この心のざらつきから、はやく逃れたい」と。 人はざらつきから逃げるために嘘に嘘を重ね、その結果ざらつきは無情にも増していく。 そんな心の「ざらつき」が、音もなく忍び寄り気づけばがんじがらめにまとわりつく、こんな読書体験ははじめてである。 この短編集のテーマは「秘密」と「金」 どんな事情があれど嘘はつくものではないし、一番大切なものはなんなのか、その嘘で自分は何を失うのか、常に冷静でいたいところである。
汚れた手をそこで拭かない芦沢央読み終わった誰かに嘘をついてしまったとき、後ろめたい事実を抱えてしまったとき、誰しもが思ったことがあるのではないか。 「この心のざらつきから、はやく逃れたい」と。 人はざらつきから逃げるために嘘に嘘を重ね、その結果ざらつきは無情にも増していく。 そんな心の「ざらつき」が、音もなく忍び寄り気づけばがんじがらめにまとわりつく、こんな読書体験ははじめてである。 この短編集のテーマは「秘密」と「金」 どんな事情があれど嘘はつくものではないし、一番大切なものはなんなのか、その嘘で自分は何を失うのか、常に冷静でいたいところである。 - 2026年1月12日
 薬指の標本小川洋子,小川洋子(1962-)読み終わった作中ですべてを語りすぎないからこそ、自分も物語の中で心を奪われ酔っていくようだった。考察が捗りそう。 以下ネタバレ含みます -------------------------------- 活字のシーンの狂気が忘れられない。 絶対的な「支配」と「洗脳」、「陶酔」の様を一切の言葉を交わすことなく、暴力や血を流すことなく表現する手腕に鳥肌が立つ。 ありふれた1人の少女が、自分にぴったりと合った靴、そして愛と嫉妬で容易く自ら自由を手放す。 助言やヒントは耳に入らず、その場所に留まることこそが史上の幸せと思うその盲目さは、自分にも思い当たる節があり少し胸がピリリと痛んだ。
薬指の標本小川洋子,小川洋子(1962-)読み終わった作中ですべてを語りすぎないからこそ、自分も物語の中で心を奪われ酔っていくようだった。考察が捗りそう。 以下ネタバレ含みます -------------------------------- 活字のシーンの狂気が忘れられない。 絶対的な「支配」と「洗脳」、「陶酔」の様を一切の言葉を交わすことなく、暴力や血を流すことなく表現する手腕に鳥肌が立つ。 ありふれた1人の少女が、自分にぴったりと合った靴、そして愛と嫉妬で容易く自ら自由を手放す。 助言やヒントは耳に入らず、その場所に留まることこそが史上の幸せと思うその盲目さは、自分にも思い当たる節があり少し胸がピリリと痛んだ。 - 2025年12月27日
- 2025年12月24日
 透明な夜の香り千早茜読み終わったハーブの香りのようにすっと脳に染み込む文章で読みやすく、久々にスピーディーに読了。こういう唯一無二の出会いの物語は無性にその出会いを羨んでしまうから困る。この本に出会った時点でそれも「唯一無二」ではあるのだけれど。 以下ネタバレ含みます -------------------------------- 執着と愛着の違い 一香はラスト、もう一度洋館で働くことを選ばなかった それはきっと朔にとって予想していた選択ではなかったけれど、朔はそれを喜んだ 「相手が変化しても、自分の思い通りの選択をしなくても、それでも相手のそばにいたいと思うこと」 それが愛着なのだとしたら、 いままで相手の望む通りに全てを合わせて、相手の望む形に変化することでしか繋がりを形成できなかった私は、未だ「愛着」で他人と繋がったことがないのだろうなと思った。 何かに従うのは楽だ。 従った上で自分の存在意義を認めてもらえるのなら、私はいくらでも従いたい。 不誠実な人間といつ終わるかわからない関係を築くくらいなら、誠実な獣に支配されたい。 結末を読んでもそう思ってしまう私のことも、朔さんの香りなら解放できるのだろうか。
透明な夜の香り千早茜読み終わったハーブの香りのようにすっと脳に染み込む文章で読みやすく、久々にスピーディーに読了。こういう唯一無二の出会いの物語は無性にその出会いを羨んでしまうから困る。この本に出会った時点でそれも「唯一無二」ではあるのだけれど。 以下ネタバレ含みます -------------------------------- 執着と愛着の違い 一香はラスト、もう一度洋館で働くことを選ばなかった それはきっと朔にとって予想していた選択ではなかったけれど、朔はそれを喜んだ 「相手が変化しても、自分の思い通りの選択をしなくても、それでも相手のそばにいたいと思うこと」 それが愛着なのだとしたら、 いままで相手の望む通りに全てを合わせて、相手の望む形に変化することでしか繋がりを形成できなかった私は、未だ「愛着」で他人と繋がったことがないのだろうなと思った。 何かに従うのは楽だ。 従った上で自分の存在意義を認めてもらえるのなら、私はいくらでも従いたい。 不誠実な人間といつ終わるかわからない関係を築くくらいなら、誠実な獣に支配されたい。 結末を読んでもそう思ってしまう私のことも、朔さんの香りなら解放できるのだろうか。 - 2025年12月16日
 レモネードに彗星灰谷魚読み終わった1行読んだその瞬間、「あ、当たりだ」と思った。 本における「面白い」の定義は様々で、 人生観に影響を与える学びがあるとか、 精巧なトリックが仕組まれているとか。 そんな中で私が大切にしているのは「読む手が止まらなくなること」であり、先が気になって仕方ない物語を探し求めていた。 はじめ、私はこれが短編集と知らなかったのだ。 この物語の続きが読めたら、そう思う感覚は久しい。 大層な学びや教えは描かなくていい、灰谷魚さんにはこれからも「面白い」物語をただ綴っていてほしいと切に思う。
レモネードに彗星灰谷魚読み終わった1行読んだその瞬間、「あ、当たりだ」と思った。 本における「面白い」の定義は様々で、 人生観に影響を与える学びがあるとか、 精巧なトリックが仕組まれているとか。 そんな中で私が大切にしているのは「読む手が止まらなくなること」であり、先が気になって仕方ない物語を探し求めていた。 はじめ、私はこれが短編集と知らなかったのだ。 この物語の続きが読めたら、そう思う感覚は久しい。 大層な学びや教えは描かなくていい、灰谷魚さんにはこれからも「面白い」物語をただ綴っていてほしいと切に思う。 - 2025年12月5日
 トリツカレ男 (新潮文庫)いしいしんじ読み終わったこのアプリをはじめていなければ絶対に出会わなかっただろうし、絶対に手にとらなかったであろうジャンルの物語。クスっと笑えて心があったかくなる瞬間は大人にも必要だなとしみじみ。 以下ネタバレ含みます --------------------------- とりつかれて、とりつかれ終わって、そのものに興味がもてなくなったとしても、ジュゼッペは決してそれらを捨てたり無下に扱ったりしなかった。 ネズミとは生涯友であり続けたし、集めたコレクションは綺麗に保存していた。 それがきっと彼が愛される理由であり、最後に報われることになった理由なのだと思う。 なにかにとりつかれてそれしか見えなくなってしまうことを多くの人は愚かと思うかもしれないが、生涯互いにとりつかれあう相手を見つけて、自分がこれまでとりつかれてきたもの全てをかけてその相手を幸せにできるなら、そんな人生を生きてみたいと思った。
トリツカレ男 (新潮文庫)いしいしんじ読み終わったこのアプリをはじめていなければ絶対に出会わなかっただろうし、絶対に手にとらなかったであろうジャンルの物語。クスっと笑えて心があったかくなる瞬間は大人にも必要だなとしみじみ。 以下ネタバレ含みます --------------------------- とりつかれて、とりつかれ終わって、そのものに興味がもてなくなったとしても、ジュゼッペは決してそれらを捨てたり無下に扱ったりしなかった。 ネズミとは生涯友であり続けたし、集めたコレクションは綺麗に保存していた。 それがきっと彼が愛される理由であり、最後に報われることになった理由なのだと思う。 なにかにとりつかれてそれしか見えなくなってしまうことを多くの人は愚かと思うかもしれないが、生涯互いにとりつかれあう相手を見つけて、自分がこれまでとりつかれてきたもの全てをかけてその相手を幸せにできるなら、そんな人生を生きてみたいと思った。 - 2025年11月28日
 流れ星が消えないうちに橋本紡読み終わった恋愛小説の顔をしながらも、この物語が持つ意図はもっと深いところにある。巻末の重松清先生の解説がその解像度をさらに深めてくれたような気がする。 以下ネタバレ含みます ----------------------------- 20歳は大人のようでまだまだ子供だ。 そう思うのは自分が20歳をとうに超えているからなのだろうか。 10代の頃の私から見た20歳は大人だったか? 今はもうあまり覚えていない。 これは20歳という年齢の奈緒子と巧が子供から大人へ変化していく物語だったと思う。 過去に囚われ、大切なことは口に出せず、まわりくどく不器用にもがく2人は私から見れば「子供」そのものであった。 しかし、物語終盤で自分なりの答えを見出し、様々な事実を動じず受け入れる2人はまさしく「大人」であった。 最後まで隠され続けた絵葉書の内容に、この物語の結末が何も左右されなかったことがその証拠だろう。 忘れられない傷も、忘れられないことすら受け入れて、生きてゆく。 それに20歳の私は果たして気づいていただろうか。 そう考えると、ひどく幼く感じていた物語序盤の2人だって、私よりずっと大人なのかもしれない。
流れ星が消えないうちに橋本紡読み終わった恋愛小説の顔をしながらも、この物語が持つ意図はもっと深いところにある。巻末の重松清先生の解説がその解像度をさらに深めてくれたような気がする。 以下ネタバレ含みます ----------------------------- 20歳は大人のようでまだまだ子供だ。 そう思うのは自分が20歳をとうに超えているからなのだろうか。 10代の頃の私から見た20歳は大人だったか? 今はもうあまり覚えていない。 これは20歳という年齢の奈緒子と巧が子供から大人へ変化していく物語だったと思う。 過去に囚われ、大切なことは口に出せず、まわりくどく不器用にもがく2人は私から見れば「子供」そのものであった。 しかし、物語終盤で自分なりの答えを見出し、様々な事実を動じず受け入れる2人はまさしく「大人」であった。 最後まで隠され続けた絵葉書の内容に、この物語の結末が何も左右されなかったことがその証拠だろう。 忘れられない傷も、忘れられないことすら受け入れて、生きてゆく。 それに20歳の私は果たして気づいていただろうか。 そう考えると、ひどく幼く感じていた物語序盤の2人だって、私よりずっと大人なのかもしれない。 - 2025年11月17日
 惑星木原音瀬読み終わった宇宙人の話だと思って読んだらきっと楽なのだと思う 私は読みながらすごく苦しかったから、きっと宇宙人ではないのだろうな 以下ネタバレ含みます ----------------------------------- 自由を対価に身の安全と食事を保証してもらう生き方は楽なのかもしれない ただ、その手綱を自分が握ることはできなくて、一緒にいたくないと言われたらもう、おしまい 宇宙人の話だったらよかった 人の形をして生まれてきてしまった宇宙人が生きることはこんなにも難しい 食べて、寝て、テレビをみる生活が難しい カンさんとのシーンはあたたかくて、私の頭の嫌な気持ちもなくなるみたいだった 頭をぶつけるんじゃなくて、近くにいるだけで嫌なことを忘れられる人に会いたい そこがきっと自分の帰る星なんだと思う
惑星木原音瀬読み終わった宇宙人の話だと思って読んだらきっと楽なのだと思う 私は読みながらすごく苦しかったから、きっと宇宙人ではないのだろうな 以下ネタバレ含みます ----------------------------------- 自由を対価に身の安全と食事を保証してもらう生き方は楽なのかもしれない ただ、その手綱を自分が握ることはできなくて、一緒にいたくないと言われたらもう、おしまい 宇宙人の話だったらよかった 人の形をして生まれてきてしまった宇宙人が生きることはこんなにも難しい 食べて、寝て、テレビをみる生活が難しい カンさんとのシーンはあたたかくて、私の頭の嫌な気持ちもなくなるみたいだった 頭をぶつけるんじゃなくて、近くにいるだけで嫌なことを忘れられる人に会いたい そこがきっと自分の帰る星なんだと思う - 2025年11月8日
 だから捨ててと言ったのに岡崎隼人,潮谷験,真下みこと,講談社,須藤古都離,黒澤いづみ読み終わったさまざまな種類のお菓子が入ったアソートボックス。 ひとりで楽しむのも好きだが、私は誰かとつまんでどれがいちばん好きだったか話すのが好きだ。 これは物語のアソートボックス。 あまりに人生観に関わる物語や政治、宗教に関わる物語は親しい友人との感想交換をためらうこともあるが、これならば楽しく語り合えるだろう。 本を1冊書き上げることは私には想像もつかぬ難しさなのだと想像するが、一方で「短い物語」はまた別の難しさがあるような気がする。 伝えたいことの深みがあればあるほど少ない文字数では伝えきれず、結果として難儀になってしまったり 一方で伝えきることを意識しすぎて展開が読めてしまったり。 その点で 「パルス、またたき、脳挫傷」 「重政の電池」 「靴」 「久闊を叙す」 「切れたミサンガ」 がよかったなぁと思う。 このへんの好みが合う人とはぜひ話してみたいものだ。
だから捨ててと言ったのに岡崎隼人,潮谷験,真下みこと,講談社,須藤古都離,黒澤いづみ読み終わったさまざまな種類のお菓子が入ったアソートボックス。 ひとりで楽しむのも好きだが、私は誰かとつまんでどれがいちばん好きだったか話すのが好きだ。 これは物語のアソートボックス。 あまりに人生観に関わる物語や政治、宗教に関わる物語は親しい友人との感想交換をためらうこともあるが、これならば楽しく語り合えるだろう。 本を1冊書き上げることは私には想像もつかぬ難しさなのだと想像するが、一方で「短い物語」はまた別の難しさがあるような気がする。 伝えたいことの深みがあればあるほど少ない文字数では伝えきれず、結果として難儀になってしまったり 一方で伝えきることを意識しすぎて展開が読めてしまったり。 その点で 「パルス、またたき、脳挫傷」 「重政の電池」 「靴」 「久闊を叙す」 「切れたミサンガ」 がよかったなぁと思う。 このへんの好みが合う人とはぜひ話してみたいものだ。 - 2025年11月6日
 リカーシブル米澤穂信読み終わった本当に恐いのは人間、とはよく言ったものだ。 この物語は恐い、でも私はもう一度読みたい。 晴れやかな気持ちで、だ。 以下ネタバレ含みます ---------------------------- ずっと、ずっとザワザワしていた。 そのざらつきはハルカも絶対にはじめから感じていたはず。 しかし終盤に至るまで、様々なヒントは散りばめられていたにも関わらず、ハルカは何も疑おうとしなかった。 ママを、リンカを、町を、信じていた。 人を疑うことにすっかり侵食されてしまった私からすれば、そんなハルカの姿にはときに苛立ちすらも覚えた。 絶対におかしいのに、なぜおかしいと思おうとしないのか。 私はそれをずっとハルカがまだ中学一年生で幼いからという理由で片付けていたが、その理由すらも終盤で納得させてくる技術は流石としか言いようがない。 狂信は時に法となり悪を正当化する。 1回目はそのじわじわ迫り来る恐怖を楽しんだのだから、2回目は作られた世界の違和感をひとつひとつ辿って身を震わそうと思う。
リカーシブル米澤穂信読み終わった本当に恐いのは人間、とはよく言ったものだ。 この物語は恐い、でも私はもう一度読みたい。 晴れやかな気持ちで、だ。 以下ネタバレ含みます ---------------------------- ずっと、ずっとザワザワしていた。 そのざらつきはハルカも絶対にはじめから感じていたはず。 しかし終盤に至るまで、様々なヒントは散りばめられていたにも関わらず、ハルカは何も疑おうとしなかった。 ママを、リンカを、町を、信じていた。 人を疑うことにすっかり侵食されてしまった私からすれば、そんなハルカの姿にはときに苛立ちすらも覚えた。 絶対におかしいのに、なぜおかしいと思おうとしないのか。 私はそれをずっとハルカがまだ中学一年生で幼いからという理由で片付けていたが、その理由すらも終盤で納得させてくる技術は流石としか言いようがない。 狂信は時に法となり悪を正当化する。 1回目はそのじわじわ迫り来る恐怖を楽しんだのだから、2回目は作られた世界の違和感をひとつひとつ辿って身を震わそうと思う。 - 2025年10月25日
 読み終わった友人に勧められて。 読書好きでない人を読書好きに引きずり込めるほど「本」という媒体をうまく使った巧妙な物語なのだが読書好きでない人は序盤で諦めてしまうのではないかと思い、そこが歯がゆい。後悔はしないので、ぜひ最後まで。 以下ネタバレ含みます ----------------------- 忘れられない話だと思った。 この話になにか人生の価値観を揺るがされたわけでもないし、涙を流したわけでもない。 でも、この先私はボブ・ディランを聴く度に、ブータンという国の話を見聞きする度に、レッサーパンダを見る度に、この話を思い出すのだろうと思った。 常識や正しさとは切り離して、この物語をただ好きだなぁと思わせるのはすごいことだ。 きっと河崎という人間が実際に私の目の前に現れたら、同じ感想を抱くのだろうと思った。 私以外の人間がこの物語にどんな感想を抱くのか知り得ないが、私はおそらく「怖いもの見たさでしばらく付き合ってみたいタイプ」の変人が好きな部類なのだろうなということはわかった。
読み終わった友人に勧められて。 読書好きでない人を読書好きに引きずり込めるほど「本」という媒体をうまく使った巧妙な物語なのだが読書好きでない人は序盤で諦めてしまうのではないかと思い、そこが歯がゆい。後悔はしないので、ぜひ最後まで。 以下ネタバレ含みます ----------------------- 忘れられない話だと思った。 この話になにか人生の価値観を揺るがされたわけでもないし、涙を流したわけでもない。 でも、この先私はボブ・ディランを聴く度に、ブータンという国の話を見聞きする度に、レッサーパンダを見る度に、この話を思い出すのだろうと思った。 常識や正しさとは切り離して、この物語をただ好きだなぁと思わせるのはすごいことだ。 きっと河崎という人間が実際に私の目の前に現れたら、同じ感想を抱くのだろうと思った。 私以外の人間がこの物語にどんな感想を抱くのか知り得ないが、私はおそらく「怖いもの見たさでしばらく付き合ってみたいタイプ」の変人が好きな部類なのだろうなということはわかった。 - 2025年10月22日
 読み終わったそれぞれの物語に登場する芸術作品が展示されている場所に、この物語も一緒に展示されていたらどんなにいいかと思った。いや、この本を持って作品に会いに世界中を旅するのもいいかもしれない。 以下ネタバレ含みます ---------------------------- 壮大な愛の物語や生き方を見つめ直すような作品ばかりを読んでいると、ついつい自分もそうであるべきと思いがちだった。 生涯支え合える伴侶を見つけることが最大の幸せのように思えたり、 誰かを助けたり、大きなことを成し遂げることが人生の醍醐味に思えたり。 この短編集を読んでいると、そんながんじがらめの心がふわっと軽くなるような気がする。 伴侶がいなくても、歳を重ねても、自分のことを誇れなくても、失敗しても、大切なものを失っても。 常設展示室にふらっと立ち寄ったときに1つの作品に目を奪われたり、その中に物語を見つけたり、動きも喋りもしない芸術にただ没頭できればそれでいいのではないかと思える。 美しいものを美しいと、綺麗なものを綺麗だと、魅力的なものを魅力的だと、そう思えるだけでいいのだ。 それだけで、きっとこの先も強く歩いていける。 逆に言えば、そんな感情すらも失う人間にはならないように、生きていきたいと思った。
読み終わったそれぞれの物語に登場する芸術作品が展示されている場所に、この物語も一緒に展示されていたらどんなにいいかと思った。いや、この本を持って作品に会いに世界中を旅するのもいいかもしれない。 以下ネタバレ含みます ---------------------------- 壮大な愛の物語や生き方を見つめ直すような作品ばかりを読んでいると、ついつい自分もそうであるべきと思いがちだった。 生涯支え合える伴侶を見つけることが最大の幸せのように思えたり、 誰かを助けたり、大きなことを成し遂げることが人生の醍醐味に思えたり。 この短編集を読んでいると、そんながんじがらめの心がふわっと軽くなるような気がする。 伴侶がいなくても、歳を重ねても、自分のことを誇れなくても、失敗しても、大切なものを失っても。 常設展示室にふらっと立ち寄ったときに1つの作品に目を奪われたり、その中に物語を見つけたり、動きも喋りもしない芸術にただ没頭できればそれでいいのではないかと思える。 美しいものを美しいと、綺麗なものを綺麗だと、魅力的なものを魅力的だと、そう思えるだけでいいのだ。 それだけで、きっとこの先も強く歩いていける。 逆に言えば、そんな感情すらも失う人間にはならないように、生きていきたいと思った。 - 2025年10月18日
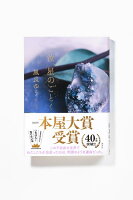 汝、星のごとく凪良ゆう読み終わったエピローグを読んだあとにプロローグを読み返したとき、受ける印象がまったく違う。 愛と人生の選択の「正しさ」とは何かを考えさせられる作品でした。 以下ネタバレ含みます ----------------------------- 「友達がやめた方がいいという相手とは恋愛しない方がいい」という言葉をよく聞く。 自分がその最中にいるときはそんなの嘘だと思う。友達に自分の何がわかるのだ、たとえこの愛が間違った形だったとしても、私は今この愛に救われているのだと。 そしてその愛が悪い形で終わったとき、やはりその言葉は正しいよなと思う。次は友達に祝福してもらえるような愛を育まねばと。 そんな理屈をずっとこねてきたけれど、この物語を読んで思ったことがある。 自分で選んだ場所であればいいのだ。 正しくても、正しくなくても。 正直この物語の登場人物は皆少しずつ歪んでいて、暁海の言う「島民共有の現在進行形リアル・エンタテインメント」になるような、世間からはおかしいと糾弾されるような人間ばかりだ。 ただ、自分の大切にしたいものをまっすぐに大切にして、誰になんと言われようとそれを貫き通す人々は、私には美しく眩しく見えた。 美しく眩しく見えるように、描いているのかもしれない。 自分の人生における重要な選択が、世間からしても正しいものであればラッキーだなと思う。 ただ、それが正しくなかったとしても、やっぱり正しい方を選べばよかったと後悔するのではなく、暁海のように、北原先生のように、瞳子さんのように、それでいいのだと、それが自分の選んだ道なのだと、胸を張れる自分でいたいと思った。
汝、星のごとく凪良ゆう読み終わったエピローグを読んだあとにプロローグを読み返したとき、受ける印象がまったく違う。 愛と人生の選択の「正しさ」とは何かを考えさせられる作品でした。 以下ネタバレ含みます ----------------------------- 「友達がやめた方がいいという相手とは恋愛しない方がいい」という言葉をよく聞く。 自分がその最中にいるときはそんなの嘘だと思う。友達に自分の何がわかるのだ、たとえこの愛が間違った形だったとしても、私は今この愛に救われているのだと。 そしてその愛が悪い形で終わったとき、やはりその言葉は正しいよなと思う。次は友達に祝福してもらえるような愛を育まねばと。 そんな理屈をずっとこねてきたけれど、この物語を読んで思ったことがある。 自分で選んだ場所であればいいのだ。 正しくても、正しくなくても。 正直この物語の登場人物は皆少しずつ歪んでいて、暁海の言う「島民共有の現在進行形リアル・エンタテインメント」になるような、世間からはおかしいと糾弾されるような人間ばかりだ。 ただ、自分の大切にしたいものをまっすぐに大切にして、誰になんと言われようとそれを貫き通す人々は、私には美しく眩しく見えた。 美しく眩しく見えるように、描いているのかもしれない。 自分の人生における重要な選択が、世間からしても正しいものであればラッキーだなと思う。 ただ、それが正しくなかったとしても、やっぱり正しい方を選べばよかったと後悔するのではなく、暁海のように、北原先生のように、瞳子さんのように、それでいいのだと、それが自分の選んだ道なのだと、胸を張れる自分でいたいと思った。 - 2025年10月12日
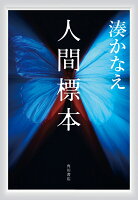 人間標本湊かなえ読み終わった「途中で読むのをやめようかと思ったけど、最後まで読んでよかった」 そんなレビューを見て、私はこの本を手に取ることに決めた。 読了後に溢れ出る感動でも絶望でもないこの感情が、この本を手に取って本当によかったと、猛烈にそう思わせる。 同時に、1つ1つの章が、それらを構成する言葉が、文字が、この順番この内容でなければそうは思えなかっただろうとも思う。 全てが、正解。 これが湊かなえ先生が湊かなえ先生たる実力かとひれ伏す気分である。 以下ネタバレ含みます ------------------- 今思い返せば全てが出来すぎていた榊史朗著の人間標本。湊かなえ先生の作品はよく映像化されているから、これを映像化したいという者が現れたら、制作に関わる者が皆究極の芸術の狂気に酔ってしまうんじゃないかなぁと呑気なことを考えていた。 それに対するSNSの評価を読んでいるとき、そこではじめて、話題の中で自分がその手記を読んでしまった民衆の追体験をさせられていたことに気づかされた。しかもこともあろうに、添付された写真から先に見てしまったという、最悪な形で、だ。映像化云々などと考えていた私のこの姿でさえも、湊かなえ先生の世界の一部、登場人物だったのだ。 そして、至の自由研究。息子である至も父親と同じ観察眼を持っていたということか、などと思ううちに徐々に怪しくなる雲行き。まさか、そうはなってほしくない、と最悪の事態を想像しつつもそうならないことを願いながら読み進める気持ちは、史朗と同じだったのかもしれない。 そして全ての答え合わせがされる、独房、面会室。 最後の解析結果は、救いだったと思う。 父親が罪を被り自分を手にかけることを見越して、自分が亡き後も父親を守る至。 斧を振り下ろすその瞬間、人間ではなくなったと、そう思わなかった者はいなかった。 究極の芸術のためなら殺人は必然だと、史朗はそう創作したが、 史朗も、至も、杏奈も、 殺人をしたという自責の念に苦しめられていた。 史朗が至に杭を打ち込んだ衝撃がずっと身体にまとわりついているように。至が自分を標本にしてほしいと望んだように。杏奈が出来上がった作品を「おぞましいだけのもの」と評したように。 では、留美はどうだったのだろうか。 全ての首謀者でありながら唯一斧を振り下ろしていない留美は、自分がもし作品作りを自分の手で実行できていたとき、どう思ったのだろうか。 「人間標本」という狂気の芸術を、 実は誰も狂気のままに完成させていない。 それがまたこの物語の美しいところなのだろうなと思った。
人間標本湊かなえ読み終わった「途中で読むのをやめようかと思ったけど、最後まで読んでよかった」 そんなレビューを見て、私はこの本を手に取ることに決めた。 読了後に溢れ出る感動でも絶望でもないこの感情が、この本を手に取って本当によかったと、猛烈にそう思わせる。 同時に、1つ1つの章が、それらを構成する言葉が、文字が、この順番この内容でなければそうは思えなかっただろうとも思う。 全てが、正解。 これが湊かなえ先生が湊かなえ先生たる実力かとひれ伏す気分である。 以下ネタバレ含みます ------------------- 今思い返せば全てが出来すぎていた榊史朗著の人間標本。湊かなえ先生の作品はよく映像化されているから、これを映像化したいという者が現れたら、制作に関わる者が皆究極の芸術の狂気に酔ってしまうんじゃないかなぁと呑気なことを考えていた。 それに対するSNSの評価を読んでいるとき、そこではじめて、話題の中で自分がその手記を読んでしまった民衆の追体験をさせられていたことに気づかされた。しかもこともあろうに、添付された写真から先に見てしまったという、最悪な形で、だ。映像化云々などと考えていた私のこの姿でさえも、湊かなえ先生の世界の一部、登場人物だったのだ。 そして、至の自由研究。息子である至も父親と同じ観察眼を持っていたということか、などと思ううちに徐々に怪しくなる雲行き。まさか、そうはなってほしくない、と最悪の事態を想像しつつもそうならないことを願いながら読み進める気持ちは、史朗と同じだったのかもしれない。 そして全ての答え合わせがされる、独房、面会室。 最後の解析結果は、救いだったと思う。 父親が罪を被り自分を手にかけることを見越して、自分が亡き後も父親を守る至。 斧を振り下ろすその瞬間、人間ではなくなったと、そう思わなかった者はいなかった。 究極の芸術のためなら殺人は必然だと、史朗はそう創作したが、 史朗も、至も、杏奈も、 殺人をしたという自責の念に苦しめられていた。 史朗が至に杭を打ち込んだ衝撃がずっと身体にまとわりついているように。至が自分を標本にしてほしいと望んだように。杏奈が出来上がった作品を「おぞましいだけのもの」と評したように。 では、留美はどうだったのだろうか。 全ての首謀者でありながら唯一斧を振り下ろしていない留美は、自分がもし作品作りを自分の手で実行できていたとき、どう思ったのだろうか。 「人間標本」という狂気の芸術を、 実は誰も狂気のままに完成させていない。 それがまたこの物語の美しいところなのだろうなと思った。 - 2025年10月8日
 ボトルネック米澤穂信読み終わった自分という人間が生きることで他にどんな影響を与えるのか? その意味がわかったとき「生まれてきてよかったのか否か」がわかるのだと思う 私はそれを知りたいとも、知りたくないとも強く思った 米澤穂信先生「らしさ」が凝縮された一冊です 以下ネタバレ含みます -------------------------- 米澤穂信先生の作品は高校生のときに「儚い羊たちの祝宴」を読んだときからずっと好きだ。 先生の物語には無駄がない。 1文1文、いや、1文字1文字にちゃんと意味があって、なおかつ初見では絶対にそれに気づかせない。 それがわかっているのに、つい推理を忘れて夢中で読んでしまって、先生の仕掛けにどんどん気づかされて、慌ててページを戻る時間がなにより好きだ。 そして先生の作品のラストはいつだって残酷だ。 それもわかっていたはずなのに、今回もギリギリまで希望を抱いて、そして打ちのめされた。 この無力感 でもそれを上回る満足感 ひとつも零さず回収された伏線の納得感 やはり私は一番好きな作家を変えられないようだ。 物語が紐解かれるにつれて、ずっとうっすら滲むリョウの「生まれてこなければよかった」の想いが苦しかった。 それを必死に気づかないように、自覚しないようにする様子もまた、とても痛々しくて。 軽快に進む間違い探しのストーリーがリョウを絶望させるカウントダウンだっただなんて誰が予想する? リョウが異世界で過ごした3日間はもしかしたら長い長い夢だったのかもしれない。 ノゾミの死をきっかけに知らず知らずの内にリョウは心を病み、夢と現実の区別がつかないほどに追いつめられていたのかもしれない。 リョウにとってサキは自分の想像上の理想の姿だったのかもしれない。 これは救いの考え方だ。 そして、リョウが自分の世界に戻ってきたとき、正気に戻るきっかけがあったこともまた、救いだった。 きっと、リョウが3日間見た夢は、あのまま曲がりくねった道を戻り、苦しみながらも生き方を変えるきっかけになるはずだった。 でも、それでも彼を救えない。 なぜなら最後に彼を追いつめたのは「夢の剣」でもなんでもなく、 ただの現実だったのだから。
ボトルネック米澤穂信読み終わった自分という人間が生きることで他にどんな影響を与えるのか? その意味がわかったとき「生まれてきてよかったのか否か」がわかるのだと思う 私はそれを知りたいとも、知りたくないとも強く思った 米澤穂信先生「らしさ」が凝縮された一冊です 以下ネタバレ含みます -------------------------- 米澤穂信先生の作品は高校生のときに「儚い羊たちの祝宴」を読んだときからずっと好きだ。 先生の物語には無駄がない。 1文1文、いや、1文字1文字にちゃんと意味があって、なおかつ初見では絶対にそれに気づかせない。 それがわかっているのに、つい推理を忘れて夢中で読んでしまって、先生の仕掛けにどんどん気づかされて、慌ててページを戻る時間がなにより好きだ。 そして先生の作品のラストはいつだって残酷だ。 それもわかっていたはずなのに、今回もギリギリまで希望を抱いて、そして打ちのめされた。 この無力感 でもそれを上回る満足感 ひとつも零さず回収された伏線の納得感 やはり私は一番好きな作家を変えられないようだ。 物語が紐解かれるにつれて、ずっとうっすら滲むリョウの「生まれてこなければよかった」の想いが苦しかった。 それを必死に気づかないように、自覚しないようにする様子もまた、とても痛々しくて。 軽快に進む間違い探しのストーリーがリョウを絶望させるカウントダウンだっただなんて誰が予想する? リョウが異世界で過ごした3日間はもしかしたら長い長い夢だったのかもしれない。 ノゾミの死をきっかけに知らず知らずの内にリョウは心を病み、夢と現実の区別がつかないほどに追いつめられていたのかもしれない。 リョウにとってサキは自分の想像上の理想の姿だったのかもしれない。 これは救いの考え方だ。 そして、リョウが自分の世界に戻ってきたとき、正気に戻るきっかけがあったこともまた、救いだった。 きっと、リョウが3日間見た夢は、あのまま曲がりくねった道を戻り、苦しみながらも生き方を変えるきっかけになるはずだった。 でも、それでも彼を救えない。 なぜなら最後に彼を追いつめたのは「夢の剣」でもなんでもなく、 ただの現実だったのだから。 - 2025年10月1日
 光のとこにいてね一穂ミチ読み終わった異なる環境で育った人間の、歳を重ねるにつれての思考の移り変わりの描き方がとても繊細で丁寧。フィクションであるのにまるで別の人生をまるまる体感したようなリアルさと満足感がありました。 以下ネタバレ含みます ------------------------------ 人の数だけ地獄がある。 他人から見てどんなに羨ましいものを持っていたとしても、その人が地獄を抱えていないとは限らない。 たとえば、「何不自由なく生活していける財力」 たとえば、「誰もが認める美しさ」 結珠と果遠は平凡な私からしたら十分すぎるほど非凡で価値のあるものを持っていたけれど、2人は等しく地獄を経験してきたのだと思う。 わかっていても他人を羨み、自分が一番不幸だと思ってしまう自分の弱さを、この物語から改めて突きつけられた気がした。 「もう、想像の中のあなたに『なぜ』や『どうして』を投げかけない。欲しくても与えられなかったものの残像を見て指をくわえるのをやめる。」 諦めても諦めきれない「欲しかったもの」が私にはたくさんある。 きっと今でもずっとそれに執着しているんだと思う。 作中の2人がそれぞれの人生に結論を出すように、私もそんな執着に決着がつけられたらと思う。 その上で、何もかも捨てたってそれでも大切な人間と、私も出会いたい。
光のとこにいてね一穂ミチ読み終わった異なる環境で育った人間の、歳を重ねるにつれての思考の移り変わりの描き方がとても繊細で丁寧。フィクションであるのにまるで別の人生をまるまる体感したようなリアルさと満足感がありました。 以下ネタバレ含みます ------------------------------ 人の数だけ地獄がある。 他人から見てどんなに羨ましいものを持っていたとしても、その人が地獄を抱えていないとは限らない。 たとえば、「何不自由なく生活していける財力」 たとえば、「誰もが認める美しさ」 結珠と果遠は平凡な私からしたら十分すぎるほど非凡で価値のあるものを持っていたけれど、2人は等しく地獄を経験してきたのだと思う。 わかっていても他人を羨み、自分が一番不幸だと思ってしまう自分の弱さを、この物語から改めて突きつけられた気がした。 「もう、想像の中のあなたに『なぜ』や『どうして』を投げかけない。欲しくても与えられなかったものの残像を見て指をくわえるのをやめる。」 諦めても諦めきれない「欲しかったもの」が私にはたくさんある。 きっと今でもずっとそれに執着しているんだと思う。 作中の2人がそれぞれの人生に結論を出すように、私もそんな執着に決着がつけられたらと思う。 その上で、何もかも捨てたってそれでも大切な人間と、私も出会いたい。 - 2025年9月23日
 今日のハチミツ、あしたの私寺地はるな読み終わった人生に迷ったときに読み返したい大切な本がまたひとつ増えました。 以下ネタバレ含みます ------------------------------- 読みながら、イライラしていた。 ひどい仕打ちを受けてもなお、安西を手放さない碧の気持ちが理解できなかった。 けれどその苛立ちはきっと、自分を見ているようだからなのだと思う。 客観的に見ればわかるのに、絶対に幸せになれないとわかるのに、自分のことになると途端にわからなくなる。 だからこそわからないなりにもがき、自分の力で他人を頼らず根を張り、 「幸福も不幸も単なる人生のオプションである」 とまで言った碧は私にとってとても眩しく、美しかった。 碧は家も仕事も失い土壇場に立ったから変われたのか? 私はそうではないから変われないのか? そうではない、そう思いたい。 真百合が言った「自分の手で勝ちとる」こと、 自分の幸せに他人をあてにしないこと。 それは今の自分にも、きっとできる。 偶然の出会いを偶然に終わらせず、もらった言葉の真偽ではなく価値だけを大切にしながら生きていきたい。 そんな人生の教訓をこの物語から教わることができたのだから。
今日のハチミツ、あしたの私寺地はるな読み終わった人生に迷ったときに読み返したい大切な本がまたひとつ増えました。 以下ネタバレ含みます ------------------------------- 読みながら、イライラしていた。 ひどい仕打ちを受けてもなお、安西を手放さない碧の気持ちが理解できなかった。 けれどその苛立ちはきっと、自分を見ているようだからなのだと思う。 客観的に見ればわかるのに、絶対に幸せになれないとわかるのに、自分のことになると途端にわからなくなる。 だからこそわからないなりにもがき、自分の力で他人を頼らず根を張り、 「幸福も不幸も単なる人生のオプションである」 とまで言った碧は私にとってとても眩しく、美しかった。 碧は家も仕事も失い土壇場に立ったから変われたのか? 私はそうではないから変われないのか? そうではない、そう思いたい。 真百合が言った「自分の手で勝ちとる」こと、 自分の幸せに他人をあてにしないこと。 それは今の自分にも、きっとできる。 偶然の出会いを偶然に終わらせず、もらった言葉の真偽ではなく価値だけを大切にしながら生きていきたい。 そんな人生の教訓をこの物語から教わることができたのだから。 - 2025年9月18日
 じっと手を見る窪美澄読み終わった夢もドラマもない、ただただ、現実。 それでも私はこの物語をつまらないとは思わなかったし、他者との境界線に悩む私が今、読むべき作品だったと思う。 以下ネタバレ含みます ----------------------------- 苦しいとき、どうして人は他人をあてにするのだろう。 どうして他人が自分を苦しみから逃がしてくれると思うのだろう。 人間に傷つけられて心を閉ざしても、人間はまた人間を求める。 永遠にも感じられるような愛のあっけない終わりと、それが引き起こす執着、そしてそれに囚われる人間の現実を、1冊を通じてただただわからせられるような、そんな読書体験だった。 私はこの物語を読んでそんな人間生活に絶望し、そしてまた、人間を頼らずにはいられないのだろうと思った。 たった1人で乗り越えて、たった1人で生涯を全うできる強さがあればどれだけいいかと思う。 そんな生涯を送れたとき、私はもっと他者と関わればよかったと後悔するのだろうか。 それもまた、わからなかった。
じっと手を見る窪美澄読み終わった夢もドラマもない、ただただ、現実。 それでも私はこの物語をつまらないとは思わなかったし、他者との境界線に悩む私が今、読むべき作品だったと思う。 以下ネタバレ含みます ----------------------------- 苦しいとき、どうして人は他人をあてにするのだろう。 どうして他人が自分を苦しみから逃がしてくれると思うのだろう。 人間に傷つけられて心を閉ざしても、人間はまた人間を求める。 永遠にも感じられるような愛のあっけない終わりと、それが引き起こす執着、そしてそれに囚われる人間の現実を、1冊を通じてただただわからせられるような、そんな読書体験だった。 私はこの物語を読んでそんな人間生活に絶望し、そしてまた、人間を頼らずにはいられないのだろうと思った。 たった1人で乗り越えて、たった1人で生涯を全うできる強さがあればどれだけいいかと思う。 そんな生涯を送れたとき、私はもっと他者と関わればよかったと後悔するのだろうか。 それもまた、わからなかった。 - 2025年9月14日
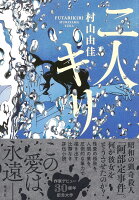 二人キリ村山由佳読み終わったまずは何も知らずに読んでほしい。 読んだ後、必ずとある「事実」が気になるはずだから、思う存分調べてほしい。 フィクションと事実が折り重なって自分の思考を広げていく不思議な感覚に、読了後も支配される美しい作品です。 以下ネタバレ含みます ------------------------- 私はこの物語を、事実ではなくフィクションとして読む。 そうしたときに、この物語に登場する人物の誰もが不完全な人間であり、自分の都合のいいように捻じ曲げた真実を抱えて生きている。それぞれの正義に共感して寄り添えば、それぞれが犯した時に小さく時に大きな罪を、「それも仕方がなかった」と思えるようにまとめてある展開は、とても美しいと思った。 誰にでもバックグラウンドがあって、その中のなにかひとつの出来事が1人の人間を歪ませることなどザラである。そのきっかけが別の誰かにとっては些細なことであっても。 その中で見出した救いも、幸せも、誰に正しいと評価される筋合いもないのだ。 世間の目に晒され、時に誰かを不幸にし、時に笑い物にされ、エンタメとして消化されてきた2人の愛も、私は異常だとも狂っているとも思わない。 こんな私の個人的な評価も、お定さんが読んだら「勝手なことを」と怒られてしまうだろうか。 この事件の真相など、正義など、その正解はお定さんだけのものだし、吉さんだけのものである。 それでもなお、私は私の正義を正当化するためにも、この物語を美談にしたいのかもしれないと思った。
二人キリ村山由佳読み終わったまずは何も知らずに読んでほしい。 読んだ後、必ずとある「事実」が気になるはずだから、思う存分調べてほしい。 フィクションと事実が折り重なって自分の思考を広げていく不思議な感覚に、読了後も支配される美しい作品です。 以下ネタバレ含みます ------------------------- 私はこの物語を、事実ではなくフィクションとして読む。 そうしたときに、この物語に登場する人物の誰もが不完全な人間であり、自分の都合のいいように捻じ曲げた真実を抱えて生きている。それぞれの正義に共感して寄り添えば、それぞれが犯した時に小さく時に大きな罪を、「それも仕方がなかった」と思えるようにまとめてある展開は、とても美しいと思った。 誰にでもバックグラウンドがあって、その中のなにかひとつの出来事が1人の人間を歪ませることなどザラである。そのきっかけが別の誰かにとっては些細なことであっても。 その中で見出した救いも、幸せも、誰に正しいと評価される筋合いもないのだ。 世間の目に晒され、時に誰かを不幸にし、時に笑い物にされ、エンタメとして消化されてきた2人の愛も、私は異常だとも狂っているとも思わない。 こんな私の個人的な評価も、お定さんが読んだら「勝手なことを」と怒られてしまうだろうか。 この事件の真相など、正義など、その正解はお定さんだけのものだし、吉さんだけのものである。 それでもなお、私は私の正義を正当化するためにも、この物語を美談にしたいのかもしれないと思った。
読み込み中...
