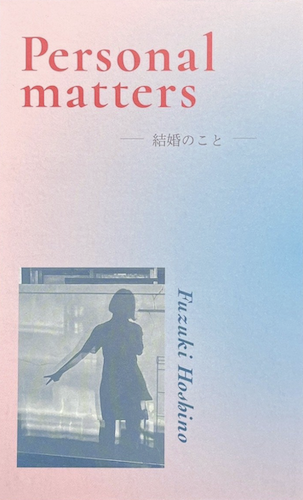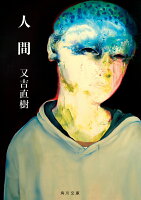もん
@_mom_n
- 2026年1月12日
 本が繋ぐ木村綾子読み終わった@ 自宅
本が繋ぐ木村綾子読み終わった@ 自宅 - 2026年1月10日
- 2026年1月6日
- 2026年1月5日
 おわりの雪ユベール・マンガレリ,田久保麻理読み終わった心に残る一節@ 自宅はじめての白水Uブックス。繊細で密やかで寂しくて、とてもよかった。 p.42 ぼくはトビに会いにブレシア通りへむかい、途中でつや消しガラスの電球を買った。その電球は、ちょっと梨に似ていた。四十ワットの梨だ。ぼくはそれをポケットにしまった。 p.101 ベッドに横になった。水滴のしたたりおちる音がした。目をつむった。するとそのとき、目をつむることと水滴の音とのあいだに密接な関係のようなものが生まれて、ぼくの気持ちをしずめてくれた。ぼくはしばらくのあいだ、しずかな気持ちでいられた。ズボンから水気がなくなってしまうまでは。 p.143 いまでもときどき考えることがある。あれはぼくが実際にしたことなのか、それともしたいと思っただけなのかと。どちらでもおなじことだ、そう思うのがぼくは好きだ。そして、そう思って満足する。 p.149 (訳者あとがき) マンガレリの作品に登場する少年たちは、現実そのものを変えることはできない子供ではあっても、空想によって、世界を味気ないものから生き生きしたものへと変えることができる。マンガレリ的世界において、空想力とは現実から逃避するためのすべではなく、現実を生きていくために子供にそなわった逞しい力である。
おわりの雪ユベール・マンガレリ,田久保麻理読み終わった心に残る一節@ 自宅はじめての白水Uブックス。繊細で密やかで寂しくて、とてもよかった。 p.42 ぼくはトビに会いにブレシア通りへむかい、途中でつや消しガラスの電球を買った。その電球は、ちょっと梨に似ていた。四十ワットの梨だ。ぼくはそれをポケットにしまった。 p.101 ベッドに横になった。水滴のしたたりおちる音がした。目をつむった。するとそのとき、目をつむることと水滴の音とのあいだに密接な関係のようなものが生まれて、ぼくの気持ちをしずめてくれた。ぼくはしばらくのあいだ、しずかな気持ちでいられた。ズボンから水気がなくなってしまうまでは。 p.143 いまでもときどき考えることがある。あれはぼくが実際にしたことなのか、それともしたいと思っただけなのかと。どちらでもおなじことだ、そう思うのがぼくは好きだ。そして、そう思って満足する。 p.149 (訳者あとがき) マンガレリの作品に登場する少年たちは、現実そのものを変えることはできない子供ではあっても、空想によって、世界を味気ないものから生き生きしたものへと変えることができる。マンガレリ的世界において、空想力とは現実から逃避するためのすべではなく、現実を生きていくために子供にそなわった逞しい力である。 - 2025年11月19日
 すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読み終わった心に残る一節@ 図書館こんな人間になりたいと思うほど憧れている人におすすめしてもらい、すぐに積読から引っ張り出して読んだ。 あまりの文章の美しさに、読みながら何度もため息が漏れた。 詩のようでもあり、エッセイのようでもあり、でも小説。初めての読み心地だった。これはすごい本だ。 p.34 闇の中で、あるものたちは白く見える。 ぼんやりとした光が闇の中へ分け入っていくとき、さほど白くなかったものまでが青ざめた白い光を放つ。 p.67 遠くで水面が立ち上がる。そこから冬の海が走ってくる。もっと近くへ、もっと力強く、追ってくる。最大限に高くそそり立った瞬間、波は真っ白に砕け散る。 海が粉々に割れ、砂浜を滑ってきてまた後方へとしりぞく。 p.81 ある日彼女は、一つかみの粗塩をよくよく眺めてみた。白っぽい影を宿したでこぼこの塩の粒子はひんやりと美しい。何かを腐らせずに守る力、消毒し、癒やす力がこの物質に宿っていることが、実感できた。 p.87 寒さが兆しはじめたある朝、唇から滑れ出る息が初めて白く凝ったら、それは私たちが生きているという証。私たちの体が温かいという証。冷気が肺腑の闇の中に吸い込まれ、体温でぬくめられ、白い息となって吐き出される。私たちの生命が確かな形をとって、ほの白く虚空に広がっていくという奇跡。
すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読み終わった心に残る一節@ 図書館こんな人間になりたいと思うほど憧れている人におすすめしてもらい、すぐに積読から引っ張り出して読んだ。 あまりの文章の美しさに、読みながら何度もため息が漏れた。 詩のようでもあり、エッセイのようでもあり、でも小説。初めての読み心地だった。これはすごい本だ。 p.34 闇の中で、あるものたちは白く見える。 ぼんやりとした光が闇の中へ分け入っていくとき、さほど白くなかったものまでが青ざめた白い光を放つ。 p.67 遠くで水面が立ち上がる。そこから冬の海が走ってくる。もっと近くへ、もっと力強く、追ってくる。最大限に高くそそり立った瞬間、波は真っ白に砕け散る。 海が粉々に割れ、砂浜を滑ってきてまた後方へとしりぞく。 p.81 ある日彼女は、一つかみの粗塩をよくよく眺めてみた。白っぽい影を宿したでこぼこの塩の粒子はひんやりと美しい。何かを腐らせずに守る力、消毒し、癒やす力がこの物質に宿っていることが、実感できた。 p.87 寒さが兆しはじめたある朝、唇から滑れ出る息が初めて白く凝ったら、それは私たちが生きているという証。私たちの体が温かいという証。冷気が肺腑の闇の中に吸い込まれ、体温でぬくめられ、白い息となって吐き出される。私たちの生命が確かな形をとって、ほの白く虚空に広がっていくという奇跡。 - 2025年11月14日
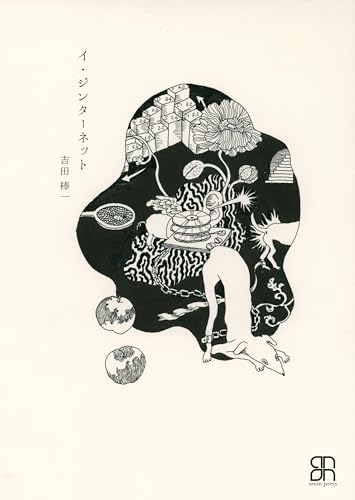 読み終わった心に残る一節@ カフェGOAT meetsをきっかけに購入したZINE。 ゲラゲラ笑いながら読み進めていたら、思わず泣きそうになるほどぐっとくる作品に出くわしたりして、とても楽しい読書体験だった。 『10 to 10 past 10』と『夜 in outer space』が特に好き。 ハッピーターンと味しらべの類似性については私も以前から気になっていたので、小説で取り上げられていて面白かった(ちなみに私は味しらべ派)。 p.18 息子がランドセルを殴っている。言葉を話すようになって、かえって何を考えているのかわからなくなった。学校でいじめに遭っているらしい。低学年のくせに同級生全員がサグラダファミリアを知っていると妻から聞かされた。オキは笑った。息子はランドセルを殴っている。 p.81 「人の営みのなかでは音楽がいちばん天国に近い。言語は保存と再現のための記号に過ぎない」 p.112 生きている意味は生きている日々だ、と誰かは言った。誰だって自分が選んだ生き方を今さら否定したくない。 p.124 生き返って欲しい人がいる。それが無理ならずっと眠っていたいと思う。眠りは死の隣人で、ずっと眠っていたいという願望は死ねば叶う。
読み終わった心に残る一節@ カフェGOAT meetsをきっかけに購入したZINE。 ゲラゲラ笑いながら読み進めていたら、思わず泣きそうになるほどぐっとくる作品に出くわしたりして、とても楽しい読書体験だった。 『10 to 10 past 10』と『夜 in outer space』が特に好き。 ハッピーターンと味しらべの類似性については私も以前から気になっていたので、小説で取り上げられていて面白かった(ちなみに私は味しらべ派)。 p.18 息子がランドセルを殴っている。言葉を話すようになって、かえって何を考えているのかわからなくなった。学校でいじめに遭っているらしい。低学年のくせに同級生全員がサグラダファミリアを知っていると妻から聞かされた。オキは笑った。息子はランドセルを殴っている。 p.81 「人の営みのなかでは音楽がいちばん天国に近い。言語は保存と再現のための記号に過ぎない」 p.112 生きている意味は生きている日々だ、と誰かは言った。誰だって自分が選んだ生き方を今さら否定したくない。 p.124 生き返って欲しい人がいる。それが無理ならずっと眠っていたいと思う。眠りは死の隣人で、ずっと眠っていたいという願望は死ねば叶う。 - 2025年11月12日
 乳と卵川上未映子読み終わった心に残る一節@ 自宅最近は川上未映子さんの小説を集中的に読みたいと思っており、デビュー作に続いて芥川賞受賞作を読了。 女性らしさを嫌悪し、子どもが欲しいという気持ちを理解できないまま大人になった自分には、純粋な緑子の言葉が刺さりまくった。こういう小説が存在していることは救いだ。 p.32 あたしは勝手にお腹がへったり、勝手に生理になったりするようなこんな体があって、その中に閉じ込められてるって感じる。んで生まれてきたら最後、生きてご飯を食べ続けて、お金をかせいで生きていかなあかんことだけでもしんどいことです。 p.33 それに、生理がくるってことは受精ができるってことでそれは妊娠ということで、それはこんなふうに、食べたり考えたりする人間がふえるってことで、そのことを思うとなんで、と絶望的な、おおげさな気分になってしまう、ぜったいに子どもなんか生まないとあたしは思う。 p.63 今日まだ一言も口をきかない緑子の唇のなかには、真っ赤な血がぎゅっとつまっていてうねっていて集められ、薄い粘膜一枚でそこにたっぷりと留められてある、針の本当の先端で刺したぐらいの微小な穴から、スープの中に血が一滴、二滴と落ちて、しかし緑子はそれには気づかず、白いスープのゆるい底に丸い血は溶けることなくそのまま滑り沈んでいくのに、やっぱりそれに気がつかずにその陶器の中身の全部を自分ですべて飲みほしてしまう。 p.69 ちょっと考えたらこれはとてもおそろしいことで、生まれるまえからあたしのなかに人を生むもとがあるということ。大量にあったということ。生まれるまえから生むをもってる。ほんで、これは、本のなかに書いてあるだけのことじゃなくて、このあたしのお腹の中にじっさいほんまに、今、起こってあることやと、いうことを思うと、生まれるまえの生まれるもんが、生まれるまえのなかにあって、かきむしりたい、むさくさにぶち破りたい気分になる、なんやねんなこれは。
乳と卵川上未映子読み終わった心に残る一節@ 自宅最近は川上未映子さんの小説を集中的に読みたいと思っており、デビュー作に続いて芥川賞受賞作を読了。 女性らしさを嫌悪し、子どもが欲しいという気持ちを理解できないまま大人になった自分には、純粋な緑子の言葉が刺さりまくった。こういう小説が存在していることは救いだ。 p.32 あたしは勝手にお腹がへったり、勝手に生理になったりするようなこんな体があって、その中に閉じ込められてるって感じる。んで生まれてきたら最後、生きてご飯を食べ続けて、お金をかせいで生きていかなあかんことだけでもしんどいことです。 p.33 それに、生理がくるってことは受精ができるってことでそれは妊娠ということで、それはこんなふうに、食べたり考えたりする人間がふえるってことで、そのことを思うとなんで、と絶望的な、おおげさな気分になってしまう、ぜったいに子どもなんか生まないとあたしは思う。 p.63 今日まだ一言も口をきかない緑子の唇のなかには、真っ赤な血がぎゅっとつまっていてうねっていて集められ、薄い粘膜一枚でそこにたっぷりと留められてある、針の本当の先端で刺したぐらいの微小な穴から、スープの中に血が一滴、二滴と落ちて、しかし緑子はそれには気づかず、白いスープのゆるい底に丸い血は溶けることなくそのまま滑り沈んでいくのに、やっぱりそれに気がつかずにその陶器の中身の全部を自分ですべて飲みほしてしまう。 p.69 ちょっと考えたらこれはとてもおそろしいことで、生まれるまえからあたしのなかに人を生むもとがあるということ。大量にあったということ。生まれるまえから生むをもってる。ほんで、これは、本のなかに書いてあるだけのことじゃなくて、このあたしのお腹の中にじっさいほんまに、今、起こってあることやと、いうことを思うと、生まれるまえの生まれるもんが、生まれるまえのなかにあって、かきむしりたい、むさくさにぶち破りたい気分になる、なんやねんなこれは。 - 2025年11月9日
- 2025年11月9日
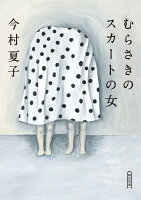 むらさきのスカートの女今村夏子読み終わった心に残る一節@ 自宅最近人と本の話をした時にこの本が話題に上がり、未読だったことを恥じて積読から引っ張り出した。 不穏な空気と先入観を揺さぶられる感覚がたまらず、(おもしれ〜!)と思いながらあっという間に読み終えてしまった。 p.58 その数分後、誰もいなくなった公園に、オレンジが一個、転がっていた。わたしは専用シートの下に落ちていたそれを拾い上げ、その場で皮ごとかぶりついた。ガブリ、ガブリ、と、先ほどのリンゴみたいに。一口目では果肉に届かなかったが、次第に甘酸っぱい果汁が口のなかに溢れ出てきた。 わたしは夢中で食べた。見学していただけなのに、のどがからからに渇いてい
むらさきのスカートの女今村夏子読み終わった心に残る一節@ 自宅最近人と本の話をした時にこの本が話題に上がり、未読だったことを恥じて積読から引っ張り出した。 不穏な空気と先入観を揺さぶられる感覚がたまらず、(おもしれ〜!)と思いながらあっという間に読み終えてしまった。 p.58 その数分後、誰もいなくなった公園に、オレンジが一個、転がっていた。わたしは専用シートの下に落ちていたそれを拾い上げ、その場で皮ごとかぶりついた。ガブリ、ガブリ、と、先ほどのリンゴみたいに。一口目では果肉に届かなかったが、次第に甘酸っぱい果汁が口のなかに溢れ出てきた。 わたしは夢中で食べた。見学していただけなのに、のどがからからに渇いてい - 2025年11月6日
 わたくし率 イン 歯ー、または世界川上未映子読み終わった心に残る一節@ 図書館まさに純文学。とにかく力が漲っている。奇妙で独特な文体は難しくて体力が要るけれど、なんとか食らいついて理解したいと思わされる。ラストの勢いも凄まじい。 p.23 ところで言葉というのはすごいわね。これはまえにも云ったけど言葉にすれば象もこんなに小さくなるのやよ。 p.33 子供のころも、道で人とすれ違うようなときも、ああ、あの人が見ているものをあの人の視力を使ってお母さんはぜったいに見ることはできないのだなあ、そのようなことをぼーと考えていると、なにかとてつもなく大きな大きな鉄板のようなものが青空に蓋をするようにゆっくり降りてきて、わけがわからなくなって恐ろしくなって、それでそのままぎゅうと押されてぺらぱらになってしまうような、そんな気持ちになったものです。 p.99 そうや、わたしは、いつもこうやってきたんやった、痛かったり悲しかったりどうしようもないもんがわたしに入ってきたときは、誰にも絶対潰されへん、わたしがどんなに傷つけられてもぜったい傷つけられへん私を入れた、勝手に決めた奥歯の中に、痛みの全部を移動させてぜんぶ閉じこめてきたんやった、わたしは歯が痛くなったことがないのやから、そこに痛みを入れてしまえば、わたしはどっこも痛くなくなる
わたくし率 イン 歯ー、または世界川上未映子読み終わった心に残る一節@ 図書館まさに純文学。とにかく力が漲っている。奇妙で独特な文体は難しくて体力が要るけれど、なんとか食らいついて理解したいと思わされる。ラストの勢いも凄まじい。 p.23 ところで言葉というのはすごいわね。これはまえにも云ったけど言葉にすれば象もこんなに小さくなるのやよ。 p.33 子供のころも、道で人とすれ違うようなときも、ああ、あの人が見ているものをあの人の視力を使ってお母さんはぜったいに見ることはできないのだなあ、そのようなことをぼーと考えていると、なにかとてつもなく大きな大きな鉄板のようなものが青空に蓋をするようにゆっくり降りてきて、わけがわからなくなって恐ろしくなって、それでそのままぎゅうと押されてぺらぱらになってしまうような、そんな気持ちになったものです。 p.99 そうや、わたしは、いつもこうやってきたんやった、痛かったり悲しかったりどうしようもないもんがわたしに入ってきたときは、誰にも絶対潰されへん、わたしがどんなに傷つけられてもぜったい傷つけられへん私を入れた、勝手に決めた奥歯の中に、痛みの全部を移動させてぜんぶ閉じこめてきたんやった、わたしは歯が痛くなったことがないのやから、そこに痛みを入れてしまえば、わたしはどっこも痛くなくなる - 2025年11月4日
 ぬるい毒本谷有希子読み終わった心に残る一節@ 自宅以前から小説に登場するクズな男を好きになりがちだが、まんまと向伊を好きになってしまって悔しい。結局私は地獄のような男女の関係性に一番ときめきを感じてしまう。 解説にあった「弱火でずっと沸騰している感覚」という言葉にわかるわかる、と頷く。 p.13 ほとんど祈る気持ちで顔の欠点を探した。どんな些細なことでもよかった。目でも鼻でも口でも。やっとのことで顔色の悪さに辿り着いてほっとしかけたあと、激しい爆発が私を襲った。欠点さえ魅力として完璧に存在する人間に出会った衝撃だった。 p.80 だから、私は決めた。もし地獄に戻るときがきても、私は伸ばした手で向伊のシャツを摑み、そのまま奈落の底へ一緒に引きずり込まれよう。 p.149 自分がただ生きて、ただ死んでいく悲しみを、私は一人で受け止められない。
ぬるい毒本谷有希子読み終わった心に残る一節@ 自宅以前から小説に登場するクズな男を好きになりがちだが、まんまと向伊を好きになってしまって悔しい。結局私は地獄のような男女の関係性に一番ときめきを感じてしまう。 解説にあった「弱火でずっと沸騰している感覚」という言葉にわかるわかる、と頷く。 p.13 ほとんど祈る気持ちで顔の欠点を探した。どんな些細なことでもよかった。目でも鼻でも口でも。やっとのことで顔色の悪さに辿り着いてほっとしかけたあと、激しい爆発が私を襲った。欠点さえ魅力として完璧に存在する人間に出会った衝撃だった。 p.80 だから、私は決めた。もし地獄に戻るときがきても、私は伸ばした手で向伊のシャツを摑み、そのまま奈落の底へ一緒に引きずり込まれよう。 p.149 自分がただ生きて、ただ死んでいく悲しみを、私は一人で受け止められない。 - 2025年11月1日
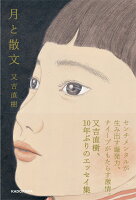 月と散文又吉直樹読み終わった心に残る一節@ 自宅小説と並行してちびちび読み進めていた又吉さんのエッセイ。 やっぱりどうしても又吉さんの言葉が好きだ! p.18 生まれ方も死に方も選べないけれど、生き方は選べる」ということに僕が気付いたのは最近のことだけど、それもみんな当然のことだと知っていたのだろうか。 p.88 時間が有り余っていた自分にとって、古書店と自動販売機だけが、自分を何者かにしてくれる装置として、機能していたのだ。缶珈琲を持っていると僕は珈琲を飲んでいる人になれたし、古書店で本の背表紙を眺めていると、本を選ぶ人にもこれから本を読む人にもなることができた。 p.220 「月、落としましたよ」 私が声を掛ける。 「俺のじゃないです」 その人は振り返らずに答える。そっか、月はみんなのもんやもんね。 p.349 徒歩三十分というのは歩き続けた場合の話であって、立ち止まって哀愁を蒐集していたのでは、どこにも辿り着けない。悪い癖だ。ゆっくりと歩き始める。
月と散文又吉直樹読み終わった心に残る一節@ 自宅小説と並行してちびちび読み進めていた又吉さんのエッセイ。 やっぱりどうしても又吉さんの言葉が好きだ! p.18 生まれ方も死に方も選べないけれど、生き方は選べる」ということに僕が気付いたのは最近のことだけど、それもみんな当然のことだと知っていたのだろうか。 p.88 時間が有り余っていた自分にとって、古書店と自動販売機だけが、自分を何者かにしてくれる装置として、機能していたのだ。缶珈琲を持っていると僕は珈琲を飲んでいる人になれたし、古書店で本の背表紙を眺めていると、本を選ぶ人にもこれから本を読む人にもなることができた。 p.220 「月、落としましたよ」 私が声を掛ける。 「俺のじゃないです」 その人は振り返らずに答える。そっか、月はみんなのもんやもんね。 p.349 徒歩三十分というのは歩き続けた場合の話であって、立ち止まって哀愁を蒐集していたのでは、どこにも辿り着けない。悪い癖だ。ゆっくりと歩き始める。 - 2025年10月28日
 体の贈り物レベッカ・ブラウン,柴田元幸読み終わった心に残る一節@ カフェこんな人間になりたいと思うほど憧れている人が教えてくれた本。 翻訳小説が苦手な自分でもするすると読めて、一つ一つの言葉がじんわりと染み入る感覚があった。美しくて悲しくてしみじみと良かった。 この本が人生のベスト3に入るくらい好きだと語るあの人への憧れが増してしまった。 p.13 彼の体に巻いた両腕に私は力をこめた。そんなことをしたって、病気を絞り出せるわけではないのだけれど。 p.74 誰もそばにいてほしくないのは、誰にも見られなくないからだ。 p.153 誰か知りあいが病気だと知るのは、病気だから知りあった人の場合とは違う。誰か、思ってもいなかった人が、まさかあの人がと信じていたような人がそうだと知るのは、たぶんそうなると思っていた人の場合とは違う。そんな違いがあるべきではない。でもあるのだ。かかった人はみな、かつてはかかっていなかったのであり、かかった人はみな、ひとつの喪失なのに。
体の贈り物レベッカ・ブラウン,柴田元幸読み終わった心に残る一節@ カフェこんな人間になりたいと思うほど憧れている人が教えてくれた本。 翻訳小説が苦手な自分でもするすると読めて、一つ一つの言葉がじんわりと染み入る感覚があった。美しくて悲しくてしみじみと良かった。 この本が人生のベスト3に入るくらい好きだと語るあの人への憧れが増してしまった。 p.13 彼の体に巻いた両腕に私は力をこめた。そんなことをしたって、病気を絞り出せるわけではないのだけれど。 p.74 誰もそばにいてほしくないのは、誰にも見られなくないからだ。 p.153 誰か知りあいが病気だと知るのは、病気だから知りあった人の場合とは違う。誰か、思ってもいなかった人が、まさかあの人がと信じていたような人がそうだと知るのは、たぶんそうなると思っていた人の場合とは違う。そんな違いがあるべきではない。でもあるのだ。かかった人はみな、かつてはかかっていなかったのであり、かかった人はみな、ひとつの喪失なのに。 - 2025年10月23日
 あのときマカロンさえ買わなければカツセマサヒコ,カツセ・マサヒコ読み終わった@ カフェめっっっっっちゃよかった。本当によかった。 好きな文章やエピソードがありすぎて付箋だらけになり、サイン会でカツセさんご本人に「付箋すごいじゃん!英単語帳みたくなってる!」と笑ってもらったのもよい思い出。 この本の読書会を開催してほしいくらい語りたいことがありすぎる。全部好きなのは大前提として、#8 #22 #39が特にお気に入り。
あのときマカロンさえ買わなければカツセマサヒコ,カツセ・マサヒコ読み終わった@ カフェめっっっっっちゃよかった。本当によかった。 好きな文章やエピソードがありすぎて付箋だらけになり、サイン会でカツセさんご本人に「付箋すごいじゃん!英単語帳みたくなってる!」と笑ってもらったのもよい思い出。 この本の読書会を開催してほしいくらい語りたいことがありすぎる。全部好きなのは大前提として、#8 #22 #39が特にお気に入り。 - 2025年10月23日
- 2025年10月10日
 悪意の手記中村文則読み終わった心に残る一節@ 自宅自分の好きな小説を列挙して「私の好きそうな小説を教えて!」とChatGPTに質問し、おすすめされた作品のうちの一つ。 罪を背負いながら人間の屑として生きていくことを決意する主人公なんて好きに決まってるな…と思い、迷わず購入。 やっぱり私は一人称視点で感情や思考を深掘りするような小説が好きだと再認識した。ゼミの討論で感情をぶちまける場面が特に好き。 p.16 私はまず、人間というものを、死にたくないと思い続けながら必ず死ぬ存在、と定義し、結局のところ一つの動物に過ぎず、喜んだり悲しんだりはするが、他の生命体を殺して肉を食らい、排泄を繰り返す、ポンプのような容器に過ぎない、と考えた。 p.101 「よくわからないけど、君の法律だったら守ってもいいような気がするな」
悪意の手記中村文則読み終わった心に残る一節@ 自宅自分の好きな小説を列挙して「私の好きそうな小説を教えて!」とChatGPTに質問し、おすすめされた作品のうちの一つ。 罪を背負いながら人間の屑として生きていくことを決意する主人公なんて好きに決まってるな…と思い、迷わず購入。 やっぱり私は一人称視点で感情や思考を深掘りするような小説が好きだと再認識した。ゼミの討論で感情をぶちまける場面が特に好き。 p.16 私はまず、人間というものを、死にたくないと思い続けながら必ず死ぬ存在、と定義し、結局のところ一つの動物に過ぎず、喜んだり悲しんだりはするが、他の生命体を殺して肉を食らい、排泄を繰り返す、ポンプのような容器に過ぎない、と考えた。 p.101 「よくわからないけど、君の法律だったら守ってもいいような気がするな」 - 2025年10月6日
 火花又吉直樹読み終わった@ カフェ『劇場』があまりにも良く、今更ながら『火花』も読んだ。やっぱり又吉さんの文章がとても好きだと痛感した。普段“泣ける本”と銘打った本でも泣かないことが多いが、この作品の終盤は感極まって泣いてしまった。
火花又吉直樹読み終わった@ カフェ『劇場』があまりにも良く、今更ながら『火花』も読んだ。やっぱり又吉さんの文章がとても好きだと痛感した。普段“泣ける本”と銘打った本でも泣かないことが多いが、この作品の終盤は感極まって泣いてしまった。 - 2025年9月30日
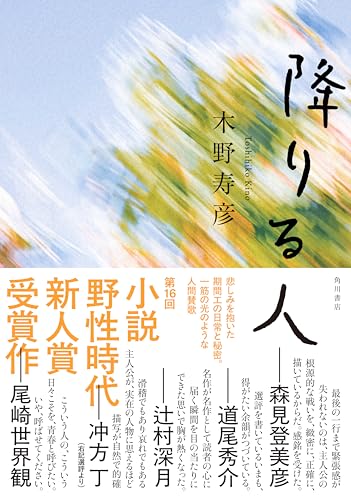 降りる人木野寿彦読み終わった心に残る一節@ カフェ普段純文学を好んで読んでいるのもあり、今まで小説野性時代新人賞に触れたことはなかったが、好きな作家が「めちゃくちゃ純文学だった」と言っていたので気になって購入。 裏の帯にある「この小説に救われる人が、必ずいる」という担当編集さんの言葉通り、人生に絶望しながら逃避するように読み始めたのに読み終える頃には救われていて、もうちょっと生きてみるか〜と思えた。本当に読めてよかった。 p.50 日記を書こうかと思ったが、何を書いていいか分からなかった。いや、何を書かないでいるべきか分からなかった。書かないでいれば、存在しないことにできるのだろうか。布団に横になった。発泡酒のアルコール成分が嫌な具合に体をめぐり、眠りの訪れを妨げ続けた。 p.73 彼らの言う「教育」がよく分からなかった。僕がこのありさまなのは、教育が悪かったからではなく、生まれたときから備わっていた何かが、見つかることも教育されることもなく放置され続けてきたからだと思っている。 p.213 「僕はどんな風に生きたらいいか分からないよ」 浜野はあくびをしながら、 「しれっと生きればいいだろ」 と言った。
降りる人木野寿彦読み終わった心に残る一節@ カフェ普段純文学を好んで読んでいるのもあり、今まで小説野性時代新人賞に触れたことはなかったが、好きな作家が「めちゃくちゃ純文学だった」と言っていたので気になって購入。 裏の帯にある「この小説に救われる人が、必ずいる」という担当編集さんの言葉通り、人生に絶望しながら逃避するように読み始めたのに読み終える頃には救われていて、もうちょっと生きてみるか〜と思えた。本当に読めてよかった。 p.50 日記を書こうかと思ったが、何を書いていいか分からなかった。いや、何を書かないでいるべきか分からなかった。書かないでいれば、存在しないことにできるのだろうか。布団に横になった。発泡酒のアルコール成分が嫌な具合に体をめぐり、眠りの訪れを妨げ続けた。 p.73 彼らの言う「教育」がよく分からなかった。僕がこのありさまなのは、教育が悪かったからではなく、生まれたときから備わっていた何かが、見つかることも教育されることもなく放置され続けてきたからだと思っている。 p.213 「僕はどんな風に生きたらいいか分からないよ」 浜野はあくびをしながら、 「しれっと生きればいいだろ」 と言った。 - 2025年9月26日
 スウスウとチャッポンくどうれいん,コンドウ・アキ読み終わった@ 自宅『飛ぶ教室』に掲載された時から大好きだった作品が絵本になって本当に嬉しい。 かつてエッセイで“お風呂がだいきらい”と書いていたれいんさんがバスタブと掃除機の気持ちを書いている微笑ましさよ…。 「よいせの、せ!」という掛け声がとても可愛らしくて好き。
スウスウとチャッポンくどうれいん,コンドウ・アキ読み終わった@ 自宅『飛ぶ教室』に掲載された時から大好きだった作品が絵本になって本当に嬉しい。 かつてエッセイで“お風呂がだいきらい”と書いていたれいんさんがバスタブと掃除機の気持ちを書いている微笑ましさよ…。 「よいせの、せ!」という掛け声がとても可愛らしくて好き。 - 2025年9月26日
 傷と雨傘カツセマサヒコ読み終わった心に残る一節@ カフェラジオ『NIGHT DIVER』が最終回を迎えてしまったことが本当に本当に寂しく、この本を読みながらぼろぼろ泣いた。 『偶然がいくつか重なると、奇跡や運命みたくなる』と『絶望したとき、誰が頭に浮かびますか?』が特に好き。 p.84 「息抜きの仕方を忘れたら、無駄遣いをするのがいいですよ。お金か、時間か、体力か。無駄だなあ、とわかっていながら、それを消費してみる。もしくは、作ってみるんです。完成したところで意味を成さないものや、第三者には到底理解されないものでもいい。効率的な社会だからこそ、無駄なものに価値があると、私は思います」 p.115 「人は、死さえも慣れる。俺たちは今日もたまたま生きられただけで、そこに一番の価値があるはずなのに、そのことすら忘れる」
傷と雨傘カツセマサヒコ読み終わった心に残る一節@ カフェラジオ『NIGHT DIVER』が最終回を迎えてしまったことが本当に本当に寂しく、この本を読みながらぼろぼろ泣いた。 『偶然がいくつか重なると、奇跡や運命みたくなる』と『絶望したとき、誰が頭に浮かびますか?』が特に好き。 p.84 「息抜きの仕方を忘れたら、無駄遣いをするのがいいですよ。お金か、時間か、体力か。無駄だなあ、とわかっていながら、それを消費してみる。もしくは、作ってみるんです。完成したところで意味を成さないものや、第三者には到底理解されないものでもいい。効率的な社会だからこそ、無駄なものに価値があると、私は思います」 p.115 「人は、死さえも慣れる。俺たちは今日もたまたま生きられただけで、そこに一番の価値があるはずなのに、そのことすら忘れる」
読み込み中...