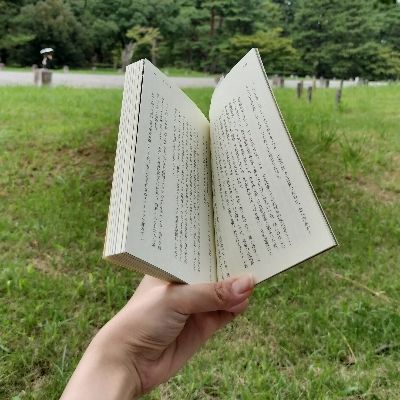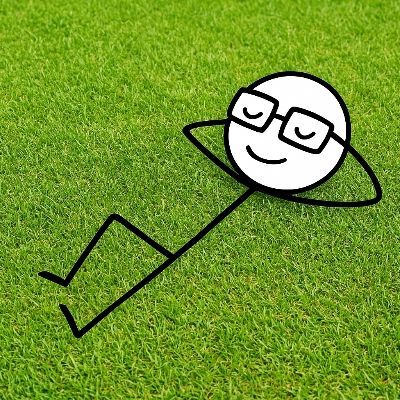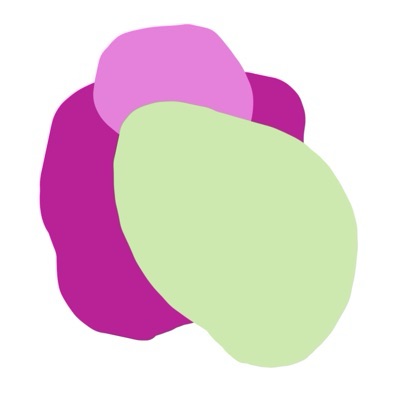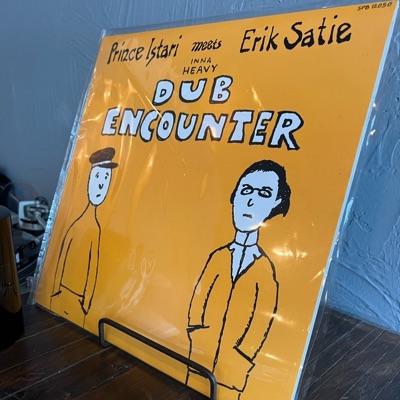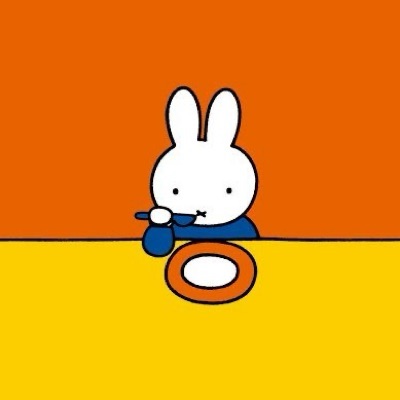社会は「私」をどうかたちづくるのか

92件の記録
 445@00labo2025年12月11日読み始めた読み終わったまた読みたいち、ちくまプリマー新書ですか?これ?本当に? 返却期限が近づいて慌てて読み始めたら、難しくて心が折れそうになった。 少なくとも大学レベルの内容。表現は中高生でもわかる平易さ。 あとがきでも言及があるように、自己と社会にまつわる社会学的観点のガイドブックという感じで、ああそういう流れとして分析されてるのかあと概論を掴むには良かった。 また読みたい。 個人的に感銘を受けたのは著者の研究スタンスへの言及部分で、満遍なく盲点のないものを作ろうとするより、盲点が見えてくるくらい絞って考え抜いたものを作るほうがいい(意訳。いかんせん流し読みなので多分ニュアンスは違う)というところ。 研究に限らず、モノづくりってそうだよな……と響いた。自分の糧になると信じてやれることをやっていこう。
445@00labo2025年12月11日読み始めた読み終わったまた読みたいち、ちくまプリマー新書ですか?これ?本当に? 返却期限が近づいて慌てて読み始めたら、難しくて心が折れそうになった。 少なくとも大学レベルの内容。表現は中高生でもわかる平易さ。 あとがきでも言及があるように、自己と社会にまつわる社会学的観点のガイドブックという感じで、ああそういう流れとして分析されてるのかあと概論を掴むには良かった。 また読みたい。 個人的に感銘を受けたのは著者の研究スタンスへの言及部分で、満遍なく盲点のないものを作ろうとするより、盲点が見えてくるくらい絞って考え抜いたものを作るほうがいい(意訳。いかんせん流し読みなので多分ニュアンスは違う)というところ。 研究に限らず、モノづくりってそうだよな……と響いた。自分の糧になると信じてやれることをやっていこう。




 あるる@aru_booklog2025年12月5日読んでるまだ序盤だけれど、これを中学生〜高校生のあたりに読めていれば...と思った。自分を取り巻く環境と社会と定義しているものをどう解釈するか、その方法を教えてくれる気がする。高校生の私には難しかったかもしれないけど、世論の捉え方や指標の扱い方がもっと広くわかって、少しだけ解釈の幅が広がる事で息ができたかもしれません。
あるる@aru_booklog2025年12月5日読んでるまだ序盤だけれど、これを中学生〜高校生のあたりに読めていれば...と思った。自分を取り巻く環境と社会と定義しているものをどう解釈するか、その方法を教えてくれる気がする。高校生の私には難しかったかもしれないけど、世論の捉え方や指標の扱い方がもっと広くわかって、少しだけ解釈の幅が広がる事で息ができたかもしれません。

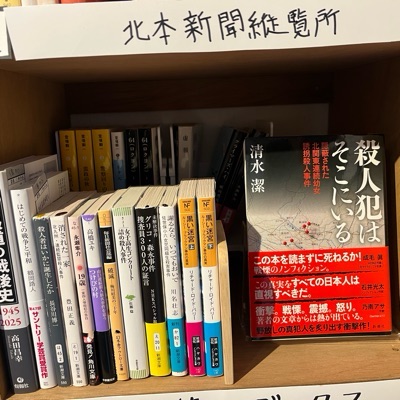 北本新聞縦覧所@kitamoto_juran2025年10月30日読み終わったYoutubeで三宅香帆さんが「社会学の教科書本」として強くオススメされていたため購入。 結果、面白過ぎたため、2回読みました。 自己と社会の関係について様々な角度で理解できます。 入門書的立ち位置なだけあって、難解な用語も平易に分かりやすく、それだけでなく社会学の奥深さも感じられました。 私が日頃思っていることや感じていることには、昔の学者先生や社会学的な名称が付けられているんだな、とその点でも面白く感じます。 フーコーが気になったのですが、著作に手を出すのはハードルが高そうなので、同じような入門書ないしは教科書本を読んでみたい。 参考文献にも面白そうな本が多く、社会学の沼にはまりそうです。
北本新聞縦覧所@kitamoto_juran2025年10月30日読み終わったYoutubeで三宅香帆さんが「社会学の教科書本」として強くオススメされていたため購入。 結果、面白過ぎたため、2回読みました。 自己と社会の関係について様々な角度で理解できます。 入門書的立ち位置なだけあって、難解な用語も平易に分かりやすく、それだけでなく社会学の奥深さも感じられました。 私が日頃思っていることや感じていることには、昔の学者先生や社会学的な名称が付けられているんだな、とその点でも面白く感じます。 フーコーが気になったのですが、著作に手を出すのはハードルが高そうなので、同じような入門書ないしは教科書本を読んでみたい。 参考文献にも面白そうな本が多く、社会学の沼にはまりそうです。

 445@00labo2025年10月28日気になる『働くための〜』で、 社会に出て仕事の文章を書くのが難しくなるのは主語があいまいになるからで、それは関係性の中の自己をうまく捉えられないから。 と言うような趣旨のことが書いてあり、関わり合いは自己を捉えることにおいてどのような作用をしてるのか知りたくなった。
445@00labo2025年10月28日気になる『働くための〜』で、 社会に出て仕事の文章を書くのが難しくなるのは主語があいまいになるからで、それは関係性の中の自己をうまく捉えられないから。 と言うような趣旨のことが書いてあり、関わり合いは自己を捉えることにおいてどのような作用をしてるのか知りたくなった。 にわか読書家@niwakadokushoka2025年6月6日読み終わった@ 自宅こういうのも社会学か。広い。 少なくとも、経営・採用・人事、各種マネジャーは、こういう知識を持っておいた方が、うまくいきそうだと思う。
にわか読書家@niwakadokushoka2025年6月6日読み終わった@ 自宅こういうのも社会学か。広い。 少なくとも、経営・採用・人事、各種マネジャーは、こういう知識を持っておいた方が、うまくいきそうだと思う。

 文庫のある生活♪@bunko_mylife2025年5月25日読み終わった牧野智和『社会は「私」をどうかたちづくるのか』(ちくまプリマー新書)を読了。 私とは何だろう?という根源的な問い。 社会学者らは、社会の中に私の表れを見出してきた。 社会学における「自己論」の変遷を丹念に紹介してくれる一冊だ。 読了後、次に読まなきゃならん本がたくさん出てきたぞ!!
文庫のある生活♪@bunko_mylife2025年5月25日読み終わった牧野智和『社会は「私」をどうかたちづくるのか』(ちくまプリマー新書)を読了。 私とは何だろう?という根源的な問い。 社会学者らは、社会の中に私の表れを見出してきた。 社会学における「自己論」の変遷を丹念に紹介してくれる一冊だ。 読了後、次に読まなきゃならん本がたくさん出てきたぞ!!