

haku
@itllme
小説を読むのが好きです。
質のいい夜更かしを。
- 2026年2月24日
 フィッシュストーリー(新潮文庫)伊坂幸太郎読み終わった近所の古本屋で買った本。 伊坂さんの作品は緩やかに正義を伝えてくる。 とても緩やかに。 この作品はどれも中短編集だったけれどどこに出てくる登場人物もキャラが濃ゆくて読みやすかった。 やっぱり印象的だったのは黒澤さんかな。 いやバンドマンの話も良かったな。 "人を信じるということは人生の有意義なイベントの一つだ" p.131 黒澤さんの言葉は泥棒なはずなのに心に残るよ。
フィッシュストーリー(新潮文庫)伊坂幸太郎読み終わった近所の古本屋で買った本。 伊坂さんの作品は緩やかに正義を伝えてくる。 とても緩やかに。 この作品はどれも中短編集だったけれどどこに出てくる登場人物もキャラが濃ゆくて読みやすかった。 やっぱり印象的だったのは黒澤さんかな。 いやバンドマンの話も良かったな。 "人を信じるということは人生の有意義なイベントの一つだ" p.131 黒澤さんの言葉は泥棒なはずなのに心に残るよ。 - 2026年2月9日
 パーフェクト・ブルー【新装版】宮部みゆき読み終わったタイトルと青いカバーに惹かれて手に取った。 ソロモンの偽証以来の宮部みゆきさんの作品。 どの登場人物も際立っていて最初の情景からページを捲る手が止まらなかった。 克彦、進也。 この兄弟の2人だけの空気感は私の脳内に色々な記憶を蘇らせた。 殺人事件のはずなのに記憶に残るのは彼ら2人真っ直ぐな姿なのが自分でも不思議でならない。 わからないけど、目頭が熱くてそして2人のことを忘れないだろうと思った。
パーフェクト・ブルー【新装版】宮部みゆき読み終わったタイトルと青いカバーに惹かれて手に取った。 ソロモンの偽証以来の宮部みゆきさんの作品。 どの登場人物も際立っていて最初の情景からページを捲る手が止まらなかった。 克彦、進也。 この兄弟の2人だけの空気感は私の脳内に色々な記憶を蘇らせた。 殺人事件のはずなのに記憶に残るのは彼ら2人真っ直ぐな姿なのが自分でも不思議でならない。 わからないけど、目頭が熱くてそして2人のことを忘れないだろうと思った。 - 2026年2月8日
 本なら売るほど 2児島青読み終わった第2巻 これを読むと無性に古本屋に行きたくなるね。 本を買う人、売る人、読む人、読まない人、書く人、編集する人 たくさんの人たちの手を通って、数えきれないほどの本とともに私の目の前に現れた1冊。 歴戦のサバイバーなんて言葉をみたら、もっと特別に感じてしまいそうだと思った。 古本屋に行きたい。
本なら売るほど 2児島青読み終わった第2巻 これを読むと無性に古本屋に行きたくなるね。 本を買う人、売る人、読む人、読まない人、書く人、編集する人 たくさんの人たちの手を通って、数えきれないほどの本とともに私の目の前に現れた1冊。 歴戦のサバイバーなんて言葉をみたら、もっと特別に感じてしまいそうだと思った。 古本屋に行きたい。 - 2026年2月8日
 本なら売るほど 1児島青読み終わった書店で見つけた瞬間、今日はこれを買う!と決めました。 カバーから伝わってくる本本本! 読みたいってなりましたね。久しぶりのコミック購入です。 十月堂に訪れる人たちの本との物語 出てくる登場人物みんな好きになっちゃいそうです。 一巻のお気に入りは、、 沢山ある!! どうしよう、第6話までしかないのに 1.2.3.4、、全部に。 「妄想逞しい女は強いんだから」 第3話 アヴェ•マリア p.78 こんな言葉まであるなんて!笑
本なら売るほど 1児島青読み終わった書店で見つけた瞬間、今日はこれを買う!と決めました。 カバーから伝わってくる本本本! 読みたいってなりましたね。久しぶりのコミック購入です。 十月堂に訪れる人たちの本との物語 出てくる登場人物みんな好きになっちゃいそうです。 一巻のお気に入りは、、 沢山ある!! どうしよう、第6話までしかないのに 1.2.3.4、、全部に。 「妄想逞しい女は強いんだから」 第3話 アヴェ•マリア p.78 こんな言葉まであるなんて!笑 - 2026年2月7日
 西の魔女が死んだ(新潮文庫)梨木香歩読み終わった死んだというタイトルには合わないくらいの暖かい表紙だなと思った。 魔女という言葉に反応してしまうのはきっと私の大好きな作品のせいだけれど、その言葉は私に何かを投げかけてくれるという確信も同時にあったと思う。 主人公のまいが学校に対して思っていることも母と父への解像度もゲンジさんへの誤解と偏見。 それは子どもだからね何て言葉では片付けられない。何故なら自分にも思い当たる節があったから。 まいは大人びているけれど大人ではなくて、おばあちゃんもお父さんもお母さんは大人だけれど、大人ではなかった。 それは見た目や年齢とその人の内側にあるひっかかりの年齢だと思う。 ずっとどこかに眠っていた自分へ そして今もなお迷える自分へ 私もおばあちゃんの家に行っていた気がした。
西の魔女が死んだ(新潮文庫)梨木香歩読み終わった死んだというタイトルには合わないくらいの暖かい表紙だなと思った。 魔女という言葉に反応してしまうのはきっと私の大好きな作品のせいだけれど、その言葉は私に何かを投げかけてくれるという確信も同時にあったと思う。 主人公のまいが学校に対して思っていることも母と父への解像度もゲンジさんへの誤解と偏見。 それは子どもだからね何て言葉では片付けられない。何故なら自分にも思い当たる節があったから。 まいは大人びているけれど大人ではなくて、おばあちゃんもお父さんもお母さんは大人だけれど、大人ではなかった。 それは見た目や年齢とその人の内側にあるひっかかりの年齢だと思う。 ずっとどこかに眠っていた自分へ そして今もなお迷える自分へ 私もおばあちゃんの家に行っていた気がした。 - 2025年12月23日
 私はスカーレット(下)林真理子読み終わった読み終わった。 私はまだアメリカ南北戦争時代にいる気がする。 スカーレットの1人語りは時に我儘のように感じたし、そこまでアシュレにこだわるなよと、メアリーの優しさに気づきなよと言いたくなった。 けれど、それ以上に、スカーレットは強く、真っ直ぐで、私がこの物語で彼女に出会ったときと変わらない輝きがあった。 それは私を惹きつけ、話さなかった。 どん底まで味わった彼女がそれでも自分を信じる姿は今振り返ってもかっこいい。 かっこよすぎる。 そしてスカーレットに魅了された1人。 レットバトラー。 私は貴方の紳士さと、頭の良さと、何よりもスカーレットを愛するその姿に惹きつけられました。 林真理子さんにはこの作品への想いと林さん自身のスカーレットとの思い出が綴ってあった。 多分、林さんがこうして書いてくれなければ、私は「風と共に去りぬ」と出逢っていなかったと思う。 私はまだ、スカーレット•オハラに見向きもされないような人だけどそれでも貴方のように強く、輝いていたいと思った。 映画と原作を手に取らないといけない。 惹きつけられるように手に取ったこの作品。出会えてよかった。
私はスカーレット(下)林真理子読み終わった読み終わった。 私はまだアメリカ南北戦争時代にいる気がする。 スカーレットの1人語りは時に我儘のように感じたし、そこまでアシュレにこだわるなよと、メアリーの優しさに気づきなよと言いたくなった。 けれど、それ以上に、スカーレットは強く、真っ直ぐで、私がこの物語で彼女に出会ったときと変わらない輝きがあった。 それは私を惹きつけ、話さなかった。 どん底まで味わった彼女がそれでも自分を信じる姿は今振り返ってもかっこいい。 かっこよすぎる。 そしてスカーレットに魅了された1人。 レットバトラー。 私は貴方の紳士さと、頭の良さと、何よりもスカーレットを愛するその姿に惹きつけられました。 林真理子さんにはこの作品への想いと林さん自身のスカーレットとの思い出が綴ってあった。 多分、林さんがこうして書いてくれなければ、私は「風と共に去りぬ」と出逢っていなかったと思う。 私はまだ、スカーレット•オハラに見向きもされないような人だけどそれでも貴方のように強く、輝いていたいと思った。 映画と原作を手に取らないといけない。 惹きつけられるように手に取ったこの作品。出会えてよかった。 - 2025年11月24日
 私はスカーレット(上)林真理子読み終わったタイトルに惹かれた。 自分に迷いが付き纏って本屋さんに行ったとき私を導くように目に入った。 タイトルからして力強い。 "生きている"と誰かが言っているんだと思った。 人種差別、戦争、女性、子ども、富、貧困、そのどれもが目に見えてわかった時代。当たり前にあった時代。 どの立場からスカーレットが生きているのかなんてことは考えなかった。 ただただ、1人のお姫様から強くなって生きようとする姿にわたしは目を見張っていた。 きっと私はスカーレットに臆病者と言われるに違いないと思った。
私はスカーレット(上)林真理子読み終わったタイトルに惹かれた。 自分に迷いが付き纏って本屋さんに行ったとき私を導くように目に入った。 タイトルからして力強い。 "生きている"と誰かが言っているんだと思った。 人種差別、戦争、女性、子ども、富、貧困、そのどれもが目に見えてわかった時代。当たり前にあった時代。 どの立場からスカーレットが生きているのかなんてことは考えなかった。 ただただ、1人のお姫様から強くなって生きようとする姿にわたしは目を見張っていた。 きっと私はスカーレットに臆病者と言われるに違いないと思った。 - 2025年10月26日
 新装版 翼をください原田マハ読み終わった手に取る気は全くなかった。 だけど、この本が置いてある場所を通るたびにチラチラ目に入るようなカバーだった。 どこまでも続いてそうな青い空柄描かれていた。 まさか世界一周することになるなんて思ってもなかった。 わたしもこの本の登場人物のように空を飛ぶことにロマンを持ったことがある。 今もなのかもしれない。 好きな映画の主人公は必ずと言っても空を飛んでいる。それは広い世界を見てみたいという願いときっとその世界は繋がっているという希望なのだと思う。 エミリーが1人で飛ぶことを決めたとき、 山田たちが彼女を8人目の乗組員と言ったとき、思い返すだけでわたしもそこのいたように感じる。 航空機という沢山のロマンが詰まった人間の創造にある夢が詰まっていた。 そして、それと同時に夢だけではないという現実を突きつけてきた。光と影。 わたしには何ができるのか、息を呑むようにして沢山の空を超えてきたからこそ考えなければいけないのだと思った。 諦めないという原田マハさんの想いが伝わらないわけがなかった。 良かった。 この本は、登場人物たちを介して未来への願いが込められていた。 最後のページにあった、「ニッポン」の乗組員の方の写真には少しテンションが上がった。
新装版 翼をください原田マハ読み終わった手に取る気は全くなかった。 だけど、この本が置いてある場所を通るたびにチラチラ目に入るようなカバーだった。 どこまでも続いてそうな青い空柄描かれていた。 まさか世界一周することになるなんて思ってもなかった。 わたしもこの本の登場人物のように空を飛ぶことにロマンを持ったことがある。 今もなのかもしれない。 好きな映画の主人公は必ずと言っても空を飛んでいる。それは広い世界を見てみたいという願いときっとその世界は繋がっているという希望なのだと思う。 エミリーが1人で飛ぶことを決めたとき、 山田たちが彼女を8人目の乗組員と言ったとき、思い返すだけでわたしもそこのいたように感じる。 航空機という沢山のロマンが詰まった人間の創造にある夢が詰まっていた。 そして、それと同時に夢だけではないという現実を突きつけてきた。光と影。 わたしには何ができるのか、息を呑むようにして沢山の空を超えてきたからこそ考えなければいけないのだと思った。 諦めないという原田マハさんの想いが伝わらないわけがなかった。 良かった。 この本は、登場人物たちを介して未来への願いが込められていた。 最後のページにあった、「ニッポン」の乗組員の方の写真には少しテンションが上がった。 - 2025年10月20日
 小説秒速5センチメートル新海誠読み終わった思い当たる節があって、 始まりもその途中も結末も。 でも、その結末はわたしが望んでるものとは違って。 映画をアニメと実写どちらも見て、それでも本屋さんに足を運んでた。 情景も言葉も 貴樹の心情も何回読んでも噛み砕けなかった。切なくてリアルで、うっときて。 グッとじゃなくて、ウッときた。 それでもわたしは出逢えて良かったと思った。貴樹が、明里が、花苗が思ったみたいに。わたしにもそう思える人がいることを静かに思い出した。 そんな作品だった。
小説秒速5センチメートル新海誠読み終わった思い当たる節があって、 始まりもその途中も結末も。 でも、その結末はわたしが望んでるものとは違って。 映画をアニメと実写どちらも見て、それでも本屋さんに足を運んでた。 情景も言葉も 貴樹の心情も何回読んでも噛み砕けなかった。切なくてリアルで、うっときて。 グッとじゃなくて、ウッときた。 それでもわたしは出逢えて良かったと思った。貴樹が、明里が、花苗が思ったみたいに。わたしにもそう思える人がいることを静かに思い出した。 そんな作品だった。 - 2025年9月28日
 革命前夜須賀しのぶ読み終わった出会ってしまった。 小説を読み終えてこんな感覚になったのはいつぶりだろうか。 わたしはこの1冊を古本屋の隅で目に入って購入を決めた自分にありがとうと言いたい。 この物語は眞山柊史が東ドイツに音楽留学するところから始まる。 まだドイツが東と西に分けられていた時代のときの話。 わたしはこの時のことを勿論全然知らなかった。確かに学生の頃に教科書でベルリンの壁に登る人々の姿を写真で見たことはあったけれど、それだけだった。 この物語は、そのわたしの中ではたった教科書の一部分でしかなかった光景を読み終わった後、そこから沢山の視点を与え、背景を想像させた。 言葉なのに音楽が聴こえてくる。 本当に読みながらふと気づくのだ。 音楽はなっていないことに。 留学生として自分の音楽に向き合い、自分よりも才能を持つ人々と出会い、苦しみ、逃げて、それでも戦った眞山柊史の姿は今のわたしにとって人ごとではなかった。 自分の音楽を見つけた瞬間の彼を私は讃えずにいられなかった。 "僕は手を下ろし、目を閉じた。何度も深く、呼吸をする。" p.226 そして、物語に出てくる2人の秀才。 ヴェンツェルとイェンツ。 この2人の音楽への想いと国への想いが交差していくのを読み進めるたびに感じた。 自分を貫き通すことを彼らはそれぞれの立場で体現していたように思う。 それは彼らにとっては"自分の音を貫く"ということだった。 そう言った、ヴェンツェルとクリスタ。 それを体現した、イェンツとガビィ。 時代の背景も音楽のことも何一つ知らなかったけれど、読み終わった今、静かに蝋燭に焔を灯していた人々のことを思い出さずにはいられない。 そしてドレスデンの音楽大学にいた彼らが見つけていく音を想像せずにはいられない。 この作品はわたしの2025年の1冊になった。 "人はいつか必ず、戦う。破壊せねばならない。その時を迎えたと、僕はおそらく知っていたのだ。戦わなければ、平穏は手に入らないのだから。" p.327
革命前夜須賀しのぶ読み終わった出会ってしまった。 小説を読み終えてこんな感覚になったのはいつぶりだろうか。 わたしはこの1冊を古本屋の隅で目に入って購入を決めた自分にありがとうと言いたい。 この物語は眞山柊史が東ドイツに音楽留学するところから始まる。 まだドイツが東と西に分けられていた時代のときの話。 わたしはこの時のことを勿論全然知らなかった。確かに学生の頃に教科書でベルリンの壁に登る人々の姿を写真で見たことはあったけれど、それだけだった。 この物語は、そのわたしの中ではたった教科書の一部分でしかなかった光景を読み終わった後、そこから沢山の視点を与え、背景を想像させた。 言葉なのに音楽が聴こえてくる。 本当に読みながらふと気づくのだ。 音楽はなっていないことに。 留学生として自分の音楽に向き合い、自分よりも才能を持つ人々と出会い、苦しみ、逃げて、それでも戦った眞山柊史の姿は今のわたしにとって人ごとではなかった。 自分の音楽を見つけた瞬間の彼を私は讃えずにいられなかった。 "僕は手を下ろし、目を閉じた。何度も深く、呼吸をする。" p.226 そして、物語に出てくる2人の秀才。 ヴェンツェルとイェンツ。 この2人の音楽への想いと国への想いが交差していくのを読み進めるたびに感じた。 自分を貫き通すことを彼らはそれぞれの立場で体現していたように思う。 それは彼らにとっては"自分の音を貫く"ということだった。 そう言った、ヴェンツェルとクリスタ。 それを体現した、イェンツとガビィ。 時代の背景も音楽のことも何一つ知らなかったけれど、読み終わった今、静かに蝋燭に焔を灯していた人々のことを思い出さずにはいられない。 そしてドレスデンの音楽大学にいた彼らが見つけていく音を想像せずにはいられない。 この作品はわたしの2025年の1冊になった。 "人はいつか必ず、戦う。破壊せねばならない。その時を迎えたと、僕はおそらく知っていたのだ。戦わなければ、平穏は手に入らないのだから。" p.327 - 2025年9月18日
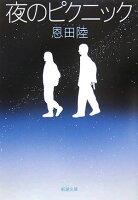 夜のピクニック恩田陸読み終わった読み終わった瞬間、夜が明けた気がした。 2日間の歩行祭。 たった、1つの学校行事のはずなのに、この本を読んだ満足感が本当に1つの出来事の話だったのかと疑ってる。 甲田貴子と西脇融。 最初は、そんなに目線を合わせてどういうことなの!? ってまるで忍のように高見のように思ってたけれど最後には私の気持ちもスッキリしていた。 融と貴子、どちらの語りも繊細で冷静でそれでいて、まだ高校生で。 融が自分の青春に気づいた時は少し嬉しく思った。 今の私も融みたいに未来に生き急いでしまっている気がした。 忍も美和子も杏奈も千秋も皆んなうちに秘めてる想いがあって、それぞれがこの歩行祭だからこそ語る言葉がわたしがるこの本を読む夜に溶け込んでいくようだった。 なんか、私も歩きながら、缶コーヒーで乾杯しながら何かを語り明かしたい気持ちになった。 このなんともないけど、特別なことはないこんな夜が彼らの青春なんだと思った。 そして多分こんなものを貴子が言うように青春だというのならきっと私にもあったと思った。 兎にも角にも忍の遠慮がちなくせに、熱い語りをしてたあの道がわたしには印象深く残っている。 いつか、この夜に戻りたくなる日がきっとあると思う。
夜のピクニック恩田陸読み終わった読み終わった瞬間、夜が明けた気がした。 2日間の歩行祭。 たった、1つの学校行事のはずなのに、この本を読んだ満足感が本当に1つの出来事の話だったのかと疑ってる。 甲田貴子と西脇融。 最初は、そんなに目線を合わせてどういうことなの!? ってまるで忍のように高見のように思ってたけれど最後には私の気持ちもスッキリしていた。 融と貴子、どちらの語りも繊細で冷静でそれでいて、まだ高校生で。 融が自分の青春に気づいた時は少し嬉しく思った。 今の私も融みたいに未来に生き急いでしまっている気がした。 忍も美和子も杏奈も千秋も皆んなうちに秘めてる想いがあって、それぞれがこの歩行祭だからこそ語る言葉がわたしがるこの本を読む夜に溶け込んでいくようだった。 なんか、私も歩きながら、缶コーヒーで乾杯しながら何かを語り明かしたい気持ちになった。 このなんともないけど、特別なことはないこんな夜が彼らの青春なんだと思った。 そして多分こんなものを貴子が言うように青春だというのならきっと私にもあったと思った。 兎にも角にも忍の遠慮がちなくせに、熱い語りをしてたあの道がわたしには印象深く残っている。 いつか、この夜に戻りたくなる日がきっとあると思う。 - 2025年9月13日
 絶対泣かない山本文緒読み終わったわたしの決意みたいなのものを表してるタイトルだった。 そして、表紙についてる帯に書いてあった、"これから仕事と向き合う方へ"という言葉に手に取らずにはいられなかった。 16くらいある短編に出てくる働く女性たちの職業は全て違っていた。 でも、それぞれの苦悩や楽しさに気づく瞬間は全部彼女たちのもので、彼女たちの選択の上にあった。 それはその仕事を選んだことに誇りを持つ瞬間でもあった。 分からない、自分にどんな仕事があってるのか、好きなことを仕事にするべきなのか、それで満足できるのか。 分からないけれど、わたしが悩み悩んだ選択がいつか自分の好きな仕事になるのかもしれないって思った。 山本さんがあとがきで "一人一人が持っている世界は狭いものだけれど、もしそれが広大だったら手におえないよな、手におえる範囲で生きているのは自然なことなんだな、と安堵のようなものを感じました"(p.166)と綴っていた。 わたしはその言葉が自分の仕事に対する気持ちの1つになっているきがする。 世界は広いし、今は"世界へ"という言葉を聞くことが多いけれどその"世界"は、それぞれの小さな生活の、日々の集合体なんじゃ無いかと思った。 そう思えた。 そしたら少しだけこころが軽くなった気がする。 また、何かに迷ったときに開きたい1冊。 わたしのお気に入りは "花のような人•••フラワーデザイナー" "ものすごく見栄っぱり•••体育教師" "今年はじめての半袖•••デパート店員"
絶対泣かない山本文緒読み終わったわたしの決意みたいなのものを表してるタイトルだった。 そして、表紙についてる帯に書いてあった、"これから仕事と向き合う方へ"という言葉に手に取らずにはいられなかった。 16くらいある短編に出てくる働く女性たちの職業は全て違っていた。 でも、それぞれの苦悩や楽しさに気づく瞬間は全部彼女たちのもので、彼女たちの選択の上にあった。 それはその仕事を選んだことに誇りを持つ瞬間でもあった。 分からない、自分にどんな仕事があってるのか、好きなことを仕事にするべきなのか、それで満足できるのか。 分からないけれど、わたしが悩み悩んだ選択がいつか自分の好きな仕事になるのかもしれないって思った。 山本さんがあとがきで "一人一人が持っている世界は狭いものだけれど、もしそれが広大だったら手におえないよな、手におえる範囲で生きているのは自然なことなんだな、と安堵のようなものを感じました"(p.166)と綴っていた。 わたしはその言葉が自分の仕事に対する気持ちの1つになっているきがする。 世界は広いし、今は"世界へ"という言葉を聞くことが多いけれどその"世界"は、それぞれの小さな生活の、日々の集合体なんじゃ無いかと思った。 そう思えた。 そしたら少しだけこころが軽くなった気がする。 また、何かに迷ったときに開きたい1冊。 わたしのお気に入りは "花のような人•••フラワーデザイナー" "ものすごく見栄っぱり•••体育教師" "今年はじめての半袖•••デパート店員" - 2025年9月12日
 ファースト・プライオリティー山本文緒,片岡忠彦読み終わった山本文緒さんの作品。 ずっと読みたくて、でも中々手に取らなくて。 読みたい本として温めていた作品ではない1冊を購入した。 本屋さんの山本文緒さんの列にある本を見ながらタイトルに惹かれて手に取った。 31歳の女性たちに取ってのファースト•プライオリティーが短編で幾つも散りばめられている。 わたしがわたしの中で持っている大切なものってなんだろうって思いながら、短編ごとのタイトルに予想外のものもあって驚かされた。 でも、その物語に出てくる主人公たちはどの人もリアルだった。 一生懸命で、美しくて、ときに醜くて。 主人公の大切なものへの想いがかっこよかった。だって、ファースト•プライオリティーだもんね。わざわざ、"ファースト"が付けられるのだもの。 短編全ての世界にまんまと引き摺り込まれた1冊だった。 読みやすくて、入りやすくて。山本さんの紡ぐ言葉や人間模様が好きだなと思った。 わたしのお気に入りの一編は、"冒険"。 最後の主人公のセリフがカッコよくって。 主人公の年齢は全員31歳だけど今のわたしもこんな風に自分の大切なものを想ったり、ときに憎く想ったり、片想いをしてるのかな と思った。まだ気づいていないだけで。 自分の少し先の未来が楽しみになって、また読み返したいと思った。 "片思いは苦くもどかしい。夫にも、好きな人にも、小説にも。そのもどかしさが自分を動かす宝物だったと私は混んだ東海道新幹線の中で知った。"p.317
ファースト・プライオリティー山本文緒,片岡忠彦読み終わった山本文緒さんの作品。 ずっと読みたくて、でも中々手に取らなくて。 読みたい本として温めていた作品ではない1冊を購入した。 本屋さんの山本文緒さんの列にある本を見ながらタイトルに惹かれて手に取った。 31歳の女性たちに取ってのファースト•プライオリティーが短編で幾つも散りばめられている。 わたしがわたしの中で持っている大切なものってなんだろうって思いながら、短編ごとのタイトルに予想外のものもあって驚かされた。 でも、その物語に出てくる主人公たちはどの人もリアルだった。 一生懸命で、美しくて、ときに醜くて。 主人公の大切なものへの想いがかっこよかった。だって、ファースト•プライオリティーだもんね。わざわざ、"ファースト"が付けられるのだもの。 短編全ての世界にまんまと引き摺り込まれた1冊だった。 読みやすくて、入りやすくて。山本さんの紡ぐ言葉や人間模様が好きだなと思った。 わたしのお気に入りの一編は、"冒険"。 最後の主人公のセリフがカッコよくって。 主人公の年齢は全員31歳だけど今のわたしもこんな風に自分の大切なものを想ったり、ときに憎く想ったり、片想いをしてるのかな と思った。まだ気づいていないだけで。 自分の少し先の未来が楽しみになって、また読み返したいと思った。 "片思いは苦くもどかしい。夫にも、好きな人にも、小説にも。そのもどかしさが自分を動かす宝物だったと私は混んだ東海道新幹線の中で知った。"p.317 - 2025年8月14日
 何者(新潮文庫)朝井リョウ読み終わった学生のときに映画を見に行った作品。 父の本棚にあったものをとって読んだ。 あの時は訳がわからなくて、ただ知っている俳優さんが出ているだけだった。 読み終わった今は少しドキドキしている。 それは楽しい感じではなくて、自分の心の深部を綺麗に覗かれた感覚。 拓人目線で語られていくこの物語は拓人に没入しないことはできず、どんどん息を止めていく感覚がある。 瑞月と光太郎。 彼らの言葉と姿は自分には持ってないものであるということを認められない。 ずっと、ずっと、否定的な拓人をわたしはいつしか俯瞰して見ることができなくなっていた。 最後の理香の言葉と拓人のラスト。 それはわたしの深部でもあり、ラストでもあった。 何者なのか? という問いならば拓人こそ出てくる登場人物の中で1番何者でもなかったのではなかろうかと思う。 泥臭くって臭い事が前提だよと思った。 かっこわるくても踠き続けるって難しくて、ときに嫉妬するほど眩しい。 "本当の「がんばる」は、インターネットやSNS上のどこにも転がっていない。すぐに止まってしまう各駅停車の中で、寒すぎる二月の強すぎる暖房の中で、ぽろんと転がり落ちるものだ。"p.138
何者(新潮文庫)朝井リョウ読み終わった学生のときに映画を見に行った作品。 父の本棚にあったものをとって読んだ。 あの時は訳がわからなくて、ただ知っている俳優さんが出ているだけだった。 読み終わった今は少しドキドキしている。 それは楽しい感じではなくて、自分の心の深部を綺麗に覗かれた感覚。 拓人目線で語られていくこの物語は拓人に没入しないことはできず、どんどん息を止めていく感覚がある。 瑞月と光太郎。 彼らの言葉と姿は自分には持ってないものであるということを認められない。 ずっと、ずっと、否定的な拓人をわたしはいつしか俯瞰して見ることができなくなっていた。 最後の理香の言葉と拓人のラスト。 それはわたしの深部でもあり、ラストでもあった。 何者なのか? という問いならば拓人こそ出てくる登場人物の中で1番何者でもなかったのではなかろうかと思う。 泥臭くって臭い事が前提だよと思った。 かっこわるくても踠き続けるって難しくて、ときに嫉妬するほど眩しい。 "本当の「がんばる」は、インターネットやSNS上のどこにも転がっていない。すぐに止まってしまう各駅停車の中で、寒すぎる二月の強すぎる暖房の中で、ぽろんと転がり落ちるものだ。"p.138 - 2025年8月13日
 パリ行ったことないの山内マリコ読み終わった@ カフェタイトルよりも表紙に惹かれたのかもしれない。 いや、タイトルかな。 わたしもパリに行ったことがない。 行けない理由というよりもあまりパリに憧れを抱いていない。いなかった。 印象に残っているのは最後の "わたしはエトランゼ"かな。 これまでの物語が一つになる感じがとても素敵だと思った。 色んな女性たちの姿があった。 まだ共感できないことの方が多かったけれど、パリに憧れて実際に行くことになる決断をしたのを見ると、かっこいいなという気持ちを持った。 わたしはこの本を読んでフィガロジャポンを調べたし、パリで煙草を吸ってポイっと道端に捨ててみたいと思ったし、5週間のバカンスはなんて素敵なのと思ってしまった。 頭の中でゆったりと時間が流れるパリ。 このままだとわたしも猫を言い訳にパリに行かないままになりそう。 "C' est la vie" どこに行っても律儀な日本人。 それでもパリに憧れてしまった。南仏の方が行きたいかも?
パリ行ったことないの山内マリコ読み終わった@ カフェタイトルよりも表紙に惹かれたのかもしれない。 いや、タイトルかな。 わたしもパリに行ったことがない。 行けない理由というよりもあまりパリに憧れを抱いていない。いなかった。 印象に残っているのは最後の "わたしはエトランゼ"かな。 これまでの物語が一つになる感じがとても素敵だと思った。 色んな女性たちの姿があった。 まだ共感できないことの方が多かったけれど、パリに憧れて実際に行くことになる決断をしたのを見ると、かっこいいなという気持ちを持った。 わたしはこの本を読んでフィガロジャポンを調べたし、パリで煙草を吸ってポイっと道端に捨ててみたいと思ったし、5週間のバカンスはなんて素敵なのと思ってしまった。 頭の中でゆったりと時間が流れるパリ。 このままだとわたしも猫を言い訳にパリに行かないままになりそう。 "C' est la vie" どこに行っても律儀な日本人。 それでもパリに憧れてしまった。南仏の方が行きたいかも? - 2025年8月3日
 砂漠伊坂幸太郎読み終わったもう、登場人物達の名前を覚えてしまった。 西嶋、東堂、鳥井、北村、南 ついでに莞爾、古賀さん、鳩麦さんとか? ハラハラもしたしドキドキもしたしグッとくる時もあった。 印象に残っているのは最初の合コン終わりのボウリング。 飲み会のときには嫌悪感を抱いた西嶋にわたしはこの時から既になんだこの人は!?と思っていた。 張り込みをするときはドキドキしたし、 鳥井のことはドキッとした。 東堂と西嶋については今ではどちらも最高に好きだ。 無愛想なん感じも、なのに西嶋なのも。 登場人物の言葉も性格も一人一人がある意味で辛辣で優しくて我があって。 鳥瞰型から近視眼型に変わる北村もいい味だった。 最初は西嶋がどうなることかと思ったがあの西嶋に惹かれていく、4人がわたしは心底羨ましく、それに感謝する西嶋にさらに惚れた。 わたしも砂漠に出ていくときに懐かしむようなオアシスがあるのだろうか。 この1冊を読んで今すぐにでも確率と中国語の勉強をしたいものだと思った。 なんてことは、まるでない。
砂漠伊坂幸太郎読み終わったもう、登場人物達の名前を覚えてしまった。 西嶋、東堂、鳥井、北村、南 ついでに莞爾、古賀さん、鳩麦さんとか? ハラハラもしたしドキドキもしたしグッとくる時もあった。 印象に残っているのは最初の合コン終わりのボウリング。 飲み会のときには嫌悪感を抱いた西嶋にわたしはこの時から既になんだこの人は!?と思っていた。 張り込みをするときはドキドキしたし、 鳥井のことはドキッとした。 東堂と西嶋については今ではどちらも最高に好きだ。 無愛想なん感じも、なのに西嶋なのも。 登場人物の言葉も性格も一人一人がある意味で辛辣で優しくて我があって。 鳥瞰型から近視眼型に変わる北村もいい味だった。 最初は西嶋がどうなることかと思ったがあの西嶋に惹かれていく、4人がわたしは心底羨ましく、それに感謝する西嶋にさらに惚れた。 わたしも砂漠に出ていくときに懐かしむようなオアシスがあるのだろうか。 この1冊を読んで今すぐにでも確率と中国語の勉強をしたいものだと思った。 なんてことは、まるでない。 - 2025年8月1日
 海辺のカフカ(下巻)村上春樹読み終わった田村カフカが歩いた数週間の高知での夏をわたしは誰と一緒に歩いていたのか読み終わった今わからない。 主人公は田村カフカだと思うのだけど、わたしはホシノ青年や大島さんが印象に残っている。 佐伯さんと図書館を見守ってきた大島さんとナカタさんと使命を共にすることになったホシノさん。 2人の言葉はカフカとナカタが私であるとするならば振り返りたくなるようなものばかりだった。 ナカタサンの途中の旅に出てくる登場人物との会話も楽しかった。運転手のハギタサンとか。今度パーキングエリアに止まることがあったら食堂に行きたい。 読み終わった今、わたしはあの山小屋に、高知に、いや、図書館に、あの海に行ってみたい。 「大公トリオ」を聞きたいし、「海辺のカフカ」の歌詞を読みなおしたい。 表紙の絵も読み終わった今は、懐かしい記憶のように思えるのです。 "すべては想像力の問題なのだ。僕らの責任は想像力の中から始まる" 大島さん 8月の初日にこの本に触れられてわたしは少し冒険チックなタフな夏を過ごせる気がします。
海辺のカフカ(下巻)村上春樹読み終わった田村カフカが歩いた数週間の高知での夏をわたしは誰と一緒に歩いていたのか読み終わった今わからない。 主人公は田村カフカだと思うのだけど、わたしはホシノ青年や大島さんが印象に残っている。 佐伯さんと図書館を見守ってきた大島さんとナカタさんと使命を共にすることになったホシノさん。 2人の言葉はカフカとナカタが私であるとするならば振り返りたくなるようなものばかりだった。 ナカタサンの途中の旅に出てくる登場人物との会話も楽しかった。運転手のハギタサンとか。今度パーキングエリアに止まることがあったら食堂に行きたい。 読み終わった今、わたしはあの山小屋に、高知に、いや、図書館に、あの海に行ってみたい。 「大公トリオ」を聞きたいし、「海辺のカフカ」の歌詞を読みなおしたい。 表紙の絵も読み終わった今は、懐かしい記憶のように思えるのです。 "すべては想像力の問題なのだ。僕らの責任は想像力の中から始まる" 大島さん 8月の初日にこの本に触れられてわたしは少し冒険チックなタフな夏を過ごせる気がします。 - 2025年7月29日
 海辺のカフカ(上巻)村上春樹読み終わった読み出したら止まらなかった。 夏の暑さと出てくる登場人物に戸惑ったのも束の間だった。 私はまだこの時点では上巻しか読んでいないのであらゆる事についてわからない。 故に早く下巻に手を伸ばしたいと思っている。 図書館の一角で暮らすカフカと四国に向かうナカタと。 まるで今の私も2つに分けられてともに走っているように感じているのです。
海辺のカフカ(上巻)村上春樹読み終わった読み出したら止まらなかった。 夏の暑さと出てくる登場人物に戸惑ったのも束の間だった。 私はまだこの時点では上巻しか読んでいないのであらゆる事についてわからない。 故に早く下巻に手を伸ばしたいと思っている。 図書館の一角で暮らすカフカと四国に向かうナカタと。 まるで今の私も2つに分けられてともに走っているように感じているのです。 - 2025年7月25日
 本へのとびら宮崎駿読み終わった@ 自宅1人で三鷹の森ジブリ美術館に行ったときに購入した。 ジブリ美術館に行って、グッズを買うことになるだろうと思っていたけれど、グッズは買わずに、近くにあるジブリに関する図書閲覧室「トライホークス」に長い時間いた。そして、迷った末に購入した1冊。 読み始めるのに時間がかかったけれど、読み始めれば一瞬だった。 ジブリ作品を好きと言いながら宮崎駿監督について知らないことばかりであった。 最初の方にある、宮崎さんが選んだ児童文学50選。紹介文がどれも心惹かれるもので読みたい本に入ってしまった笑 これまでの作品への向き合い方、特に児童文学について。 わたしは児童文学について深く考えたことがなかったのでとても新鮮な視点がたくさん転がっていた。 これからの児童文学、作品への向き合い方については宮崎さんの経験とともに冷静にそして、葛藤があったように思う。 子どもたちにどんな言葉を、物語を説くのか、この問いはこれから忙しなく、冷たい現実を歩こうとする私にも問いかけられている気がした。 "「子どもにむかって絶望を説くな」ということなんです。子どもの問題になったときに、僕らはそうならざるを得ません。"
本へのとびら宮崎駿読み終わった@ 自宅1人で三鷹の森ジブリ美術館に行ったときに購入した。 ジブリ美術館に行って、グッズを買うことになるだろうと思っていたけれど、グッズは買わずに、近くにあるジブリに関する図書閲覧室「トライホークス」に長い時間いた。そして、迷った末に購入した1冊。 読み始めるのに時間がかかったけれど、読み始めれば一瞬だった。 ジブリ作品を好きと言いながら宮崎駿監督について知らないことばかりであった。 最初の方にある、宮崎さんが選んだ児童文学50選。紹介文がどれも心惹かれるもので読みたい本に入ってしまった笑 これまでの作品への向き合い方、特に児童文学について。 わたしは児童文学について深く考えたことがなかったのでとても新鮮な視点がたくさん転がっていた。 これからの児童文学、作品への向き合い方については宮崎さんの経験とともに冷静にそして、葛藤があったように思う。 子どもたちにどんな言葉を、物語を説くのか、この問いはこれから忙しなく、冷たい現実を歩こうとする私にも問いかけられている気がした。 "「子どもにむかって絶望を説くな」ということなんです。子どもの問題になったときに、僕らはそうならざるを得ません。" - 2025年7月18日
 あたしたちよくやってる山内マリコ読み終わった@ カフェエッセイ、コラム記事、短編小説、色んな文章が詰まった一冊。 この作品を読んでもっと山内さんの1冊を読みたくなった。 どの文章もわたしの心をほんの少し動かしてくれた。笑ったり、背中を押されたり、 共感したり。 読み終わって印象に残っているのは 「あこがれ」「わたしの京都、喫茶店物語」「50歳」の3つ。 これはきっと、読んだ時期やそのときの悩みによっても変わるのだと思う。 「あこがれ」 は実際に会ってみたあこがれの人が想像とは違うっていう話だけど、共感だった笑 笑っちゃったな。 「わたしの京都、喫茶店物語」 この文章を読んだからでしょうか。わたしはもれなく今、喫茶店にいます。 そして、京都に住みたいのです。 「50歳」 わたしは多分、この文章を柏原さんの目線で読んでいたと思う。 牧野が柏原さんに言った言葉、いや、エールかな。 "「少しでもやりたいって思えることをやらないと、もったいないから。若いんだから、自己中に生きていいよ」 そしてそのツケは、あとで返せばいい。" "自分のために生きたいと思える、迷える若い女性に幸あれ。" そして、こうやって言葉にした自分のことを"まだまだわたしは、本当の大人とは言い切れない、ちょっとだけ変な大人なのでした" と牧野が締めくくるところまでとても好きなのです。
あたしたちよくやってる山内マリコ読み終わった@ カフェエッセイ、コラム記事、短編小説、色んな文章が詰まった一冊。 この作品を読んでもっと山内さんの1冊を読みたくなった。 どの文章もわたしの心をほんの少し動かしてくれた。笑ったり、背中を押されたり、 共感したり。 読み終わって印象に残っているのは 「あこがれ」「わたしの京都、喫茶店物語」「50歳」の3つ。 これはきっと、読んだ時期やそのときの悩みによっても変わるのだと思う。 「あこがれ」 は実際に会ってみたあこがれの人が想像とは違うっていう話だけど、共感だった笑 笑っちゃったな。 「わたしの京都、喫茶店物語」 この文章を読んだからでしょうか。わたしはもれなく今、喫茶店にいます。 そして、京都に住みたいのです。 「50歳」 わたしは多分、この文章を柏原さんの目線で読んでいたと思う。 牧野が柏原さんに言った言葉、いや、エールかな。 "「少しでもやりたいって思えることをやらないと、もったいないから。若いんだから、自己中に生きていいよ」 そしてそのツケは、あとで返せばいい。" "自分のために生きたいと思える、迷える若い女性に幸あれ。" そして、こうやって言葉にした自分のことを"まだまだわたしは、本当の大人とは言い切れない、ちょっとだけ変な大人なのでした" と牧野が締めくくるところまでとても好きなのです。
読み込み中...