咲
@lunar_mare
- 1900年1月1日
 美しい星三島由紀夫三島由紀夫わたしは数年ごとに金閣寺と美しい星を行ったり来たりして、好きを深めて興奮する趣味があるらしい。 ◉の話。破滅の話。美の話。 白鳥座三人衆との議論が凄まじい。 人類の5つの美点。 「彼らは嘘をつきっぱなしについた。彼らは吉凶につけて花を飾った(幸福が瞬時であることは認めながら、同時に不幸も瞬時であってほしいと望んだ)。彼らはよく小鳥を飼った。彼らは約束の時間にしばしば遅れた。そして彼らはよく笑った(虚無がいちいち道化た形姿を示すたびに、彼らは笑った)。」 こんな眺めが宇宙から消えるのは、残り惜しいことではないだろうか。 「人間は全然、生きたいという意志など持ってはいない。 生きる意志の欠如と楽天主義との、世にも怠惰な結びつきが人間というものだ。 『ああ、もう死んでしまいたい。しかし私は結局死なないだろう』これがすべての健康な人間の生活の歌なのだ」 「人間はもうおしまいだ」 「救済は決して来ない」 「いなくなった人類万歳!」 物語の終焉。 銀灰色の円盤が、息づくように、緑いろに、又あざやかな橙いろに、かわるがわるその下辺の光りの色を変えているのが眺められた。 三島由紀夫が広げる思想の大風呂敷に包まれて、呆気にとられたまま崩折れる。 好きだ。
美しい星三島由紀夫三島由紀夫わたしは数年ごとに金閣寺と美しい星を行ったり来たりして、好きを深めて興奮する趣味があるらしい。 ◉の話。破滅の話。美の話。 白鳥座三人衆との議論が凄まじい。 人類の5つの美点。 「彼らは嘘をつきっぱなしについた。彼らは吉凶につけて花を飾った(幸福が瞬時であることは認めながら、同時に不幸も瞬時であってほしいと望んだ)。彼らはよく小鳥を飼った。彼らは約束の時間にしばしば遅れた。そして彼らはよく笑った(虚無がいちいち道化た形姿を示すたびに、彼らは笑った)。」 こんな眺めが宇宙から消えるのは、残り惜しいことではないだろうか。 「人間は全然、生きたいという意志など持ってはいない。 生きる意志の欠如と楽天主義との、世にも怠惰な結びつきが人間というものだ。 『ああ、もう死んでしまいたい。しかし私は結局死なないだろう』これがすべての健康な人間の生活の歌なのだ」 「人間はもうおしまいだ」 「救済は決して来ない」 「いなくなった人類万歳!」 物語の終焉。 銀灰色の円盤が、息づくように、緑いろに、又あざやかな橙いろに、かわるがわるその下辺の光りの色を変えているのが眺められた。 三島由紀夫が広げる思想の大風呂敷に包まれて、呆気にとられたまま崩折れる。 好きだ。 - 1900年1月1日
 花嫁化鳥寺山修司寺山修司の紀行文というだけで気持ちが高揚し、飲み込まれるようにして読んだ。 老婆と子どもしかいない島。 夕暮れ時のかくれんぼ。 鯨の子どもに戒名をつけて墓に入れる。 「イエス・キリストが青森で死んだ」という一文を読んだときには、人目も気にせず仰け反って笑ってしまった。 恐山の盲目の巫女がキリストの口寄せをする。 寺山修司の修辞にかかれば、虚構が現実に侵入する。 どこまで本当か分からないのに、彼の歩いたその土地で、私も夢を見たくなる。 話して歩いて蒐集し、金田一氏のごとく推理を組み立てるのが憎いところ。 楽しい読書だった。
花嫁化鳥寺山修司寺山修司の紀行文というだけで気持ちが高揚し、飲み込まれるようにして読んだ。 老婆と子どもしかいない島。 夕暮れ時のかくれんぼ。 鯨の子どもに戒名をつけて墓に入れる。 「イエス・キリストが青森で死んだ」という一文を読んだときには、人目も気にせず仰け反って笑ってしまった。 恐山の盲目の巫女がキリストの口寄せをする。 寺山修司の修辞にかかれば、虚構が現実に侵入する。 どこまで本当か分からないのに、彼の歩いたその土地で、私も夢を見たくなる。 話して歩いて蒐集し、金田一氏のごとく推理を組み立てるのが憎いところ。 楽しい読書だった。 - 1900年1月1日
 鳩の撃退法(下)佐藤正午上巻の始めからずっと、あなた、あなたと、読者は小説から呼びかけられながら読み進める。 そして終盤。 「な、聞こえているか。僕のことばは、あなたに届いているか?」 「読者のつかない小説は、書いても書いても未完成か?この小説の存在は、無か?ひとに読まれない小説をなんのために書いているのか、理由がわからない。わからないままここまで来てしまったと、あなたには伝えておきたいのだ。伝えておきたいのだ、と強く書いても、読むひとがいなければどこのだれにも伝わらないわけだが、それでもあなたに聞いてほしいのだ」 孤独な小説家は、よりにもよってひねくれて、大衆に愛された「ピーターパンとウェンディ」の引用を、この、誰が読んでくれるかもわからない小説のいたるところに散りばめた。 ピーターパンは、そこに大勢の読者がいると疑いもなく信じ、子どもたちに向かって「もし、きみたちが信じてくれるなら、手をたたいてください。ティンクを殺さないでください」と呼びかける。 そして、当然のように、ティンカーベルは息を取り戻す。 そんなことを信じて小説を書けたならば、どんなに世界は違って見えることか。 表紙にコーヒーの染みがついたピーターパンは、紛失しても、手放しても、そのたびに津田伸一の手もとに戻ってきた。 伝書鳩のように。 運命は丸い池を作る。 池を回るものはどこかで落ち合わなければならぬ。 事実を曲げて書いた小説が、つまり現実から遠ざかろうとしたストーリーが、一周して現実の先へと出てしまう。 気がつくと、うしろから現実が抜き返そうと追ってくる。 本書もぐるぐると時系列を何周も回り、最後はまた、何も知らなかった頃の津田伸一に戻ってくる。 同じところを回りながら、微妙にずれた軌道を描き、雪上の轍は深さを増していく。
鳩の撃退法(下)佐藤正午上巻の始めからずっと、あなた、あなたと、読者は小説から呼びかけられながら読み進める。 そして終盤。 「な、聞こえているか。僕のことばは、あなたに届いているか?」 「読者のつかない小説は、書いても書いても未完成か?この小説の存在は、無か?ひとに読まれない小説をなんのために書いているのか、理由がわからない。わからないままここまで来てしまったと、あなたには伝えておきたいのだ。伝えておきたいのだ、と強く書いても、読むひとがいなければどこのだれにも伝わらないわけだが、それでもあなたに聞いてほしいのだ」 孤独な小説家は、よりにもよってひねくれて、大衆に愛された「ピーターパンとウェンディ」の引用を、この、誰が読んでくれるかもわからない小説のいたるところに散りばめた。 ピーターパンは、そこに大勢の読者がいると疑いもなく信じ、子どもたちに向かって「もし、きみたちが信じてくれるなら、手をたたいてください。ティンクを殺さないでください」と呼びかける。 そして、当然のように、ティンカーベルは息を取り戻す。 そんなことを信じて小説を書けたならば、どんなに世界は違って見えることか。 表紙にコーヒーの染みがついたピーターパンは、紛失しても、手放しても、そのたびに津田伸一の手もとに戻ってきた。 伝書鳩のように。 運命は丸い池を作る。 池を回るものはどこかで落ち合わなければならぬ。 事実を曲げて書いた小説が、つまり現実から遠ざかろうとしたストーリーが、一周して現実の先へと出てしまう。 気がつくと、うしろから現実が抜き返そうと追ってくる。 本書もぐるぐると時系列を何周も回り、最後はまた、何も知らなかった頃の津田伸一に戻ってくる。 同じところを回りながら、微妙にずれた軌道を描き、雪上の轍は深さを増していく。 - 1900年1月1日
 鳩の撃退法(上)佐藤正午佐藤正午は、Web岩波「たねをまく」の「小説家の四季」にて、2022年夏と秋に「小説家の不親切」をぼやいている。 言行一致。 本作でも津田伸一をとおして、あらゆる固有名詞とその付属物を、言葉を尽くして説明させる。 周囲の人間の言葉を使って「悪い癖だよ、どうでもいいことにこだわるなよ」と繰り返し批判させながらも、その書き方をやめない。 この人は、読者が小説内で新奇な単語に出くわしてまごつかないように、過保護なまでに抽象度を下げる。読者が言葉どおりに、つまりは作者の意図どおりに小説を受け取ることを、強く望んでいる。 何度となく読んでは、小説の面白さに惹き込まれる。 佐藤正午は好きだ。 石井桃子訳のピーターパンとウェンディ、父親を「ヒデヨシ」と呼ぶ娘と一家三人神隠し事件、飛んでいった鳩、何でも燃やしてくれるクリーンセンター、大雪の2月28日夜。 謎めいて魅力的な部品が散りばめられて目移りするが、この小説のテーマは「小説」だ。 幸地秀吉がミスタードーナツで読んでいた新刊小説の帯には「別の場所でふたりが出会っていれば、幸せになれたはずだった」との謳い文句があった。 津田伸一はそれに対して「だったら、小説家は別の場所でふたりを出会わせるべきだろうな」と言った。 たらればが有効なのは、現実の取り返しのつかない一回きりの人生においてのみだ。 小説家は小説を心ゆくまで書き直すことができる。 津田伸一は事実を書いているのではない。 事実をもととしながらそうあってほしいと望むストーリーとその結末を、言葉によって創造している。
鳩の撃退法(上)佐藤正午佐藤正午は、Web岩波「たねをまく」の「小説家の四季」にて、2022年夏と秋に「小説家の不親切」をぼやいている。 言行一致。 本作でも津田伸一をとおして、あらゆる固有名詞とその付属物を、言葉を尽くして説明させる。 周囲の人間の言葉を使って「悪い癖だよ、どうでもいいことにこだわるなよ」と繰り返し批判させながらも、その書き方をやめない。 この人は、読者が小説内で新奇な単語に出くわしてまごつかないように、過保護なまでに抽象度を下げる。読者が言葉どおりに、つまりは作者の意図どおりに小説を受け取ることを、強く望んでいる。 何度となく読んでは、小説の面白さに惹き込まれる。 佐藤正午は好きだ。 石井桃子訳のピーターパンとウェンディ、父親を「ヒデヨシ」と呼ぶ娘と一家三人神隠し事件、飛んでいった鳩、何でも燃やしてくれるクリーンセンター、大雪の2月28日夜。 謎めいて魅力的な部品が散りばめられて目移りするが、この小説のテーマは「小説」だ。 幸地秀吉がミスタードーナツで読んでいた新刊小説の帯には「別の場所でふたりが出会っていれば、幸せになれたはずだった」との謳い文句があった。 津田伸一はそれに対して「だったら、小説家は別の場所でふたりを出会わせるべきだろうな」と言った。 たらればが有効なのは、現実の取り返しのつかない一回きりの人生においてのみだ。 小説家は小説を心ゆくまで書き直すことができる。 津田伸一は事実を書いているのではない。 事実をもととしながらそうあってほしいと望むストーリーとその結末を、言葉によって創造している。 - 1900年1月1日
 世に棲む患者中井久夫対話編「アルコール症」が好き。 サン・テグジュペリの「星の王子さま」にアル中の星が出てくる。 「恥ずかしい、恥ずかしい、アル中であることが恥ずかしいのです」と言って、またぐいと一杯ひっかける。 アルコール症は恥の文化。 辱しめに敏感であると同時に、傷口に塩をすりこむように自虐的に恥にまみれることを求める。 「あなたはアルコール中毒だ」と医師が断定することは、そのような蟻地獄的自虐に加担し、倒錯的快感を高めるばかり。 それならば、底つき体験を経て自身の無力を自覚し委ねる流れは、自意識を病に寄せてしまう、危険なステップだ。 できることならば、底をつくことなく、生き延びて回復をしていただきたいところだが、如何。 患者の病以外の部分に関心を向けるのが上手な方だと知ってはいたが、まさか、患者のお髭事情にまで言及があるとは。 驚いて、可笑しい。 治療中の患者がヒゲをたてるのは良い兆候なので間違っても母や妻が剃らせないこと、 そのような剃髭の強制は去勢に近い意味を持つこと、ヒゲを剃れという周囲の圧力に抗する能力(剃髭圧力抵抗能力)と酒を飲まずにいられる能力は平行するという考察など、 臨床的視点というものはここまで及ぶのか!と、愉快で笑ってしまった。 さすが中井久夫先生。
世に棲む患者中井久夫対話編「アルコール症」が好き。 サン・テグジュペリの「星の王子さま」にアル中の星が出てくる。 「恥ずかしい、恥ずかしい、アル中であることが恥ずかしいのです」と言って、またぐいと一杯ひっかける。 アルコール症は恥の文化。 辱しめに敏感であると同時に、傷口に塩をすりこむように自虐的に恥にまみれることを求める。 「あなたはアルコール中毒だ」と医師が断定することは、そのような蟻地獄的自虐に加担し、倒錯的快感を高めるばかり。 それならば、底つき体験を経て自身の無力を自覚し委ねる流れは、自意識を病に寄せてしまう、危険なステップだ。 できることならば、底をつくことなく、生き延びて回復をしていただきたいところだが、如何。 患者の病以外の部分に関心を向けるのが上手な方だと知ってはいたが、まさか、患者のお髭事情にまで言及があるとは。 驚いて、可笑しい。 治療中の患者がヒゲをたてるのは良い兆候なので間違っても母や妻が剃らせないこと、 そのような剃髭の強制は去勢に近い意味を持つこと、ヒゲを剃れという周囲の圧力に抗する能力(剃髭圧力抵抗能力)と酒を飲まずにいられる能力は平行するという考察など、 臨床的視点というものはここまで及ぶのか!と、愉快で笑ってしまった。 さすが中井久夫先生。 - 1900年1月1日
 あゝ、荒野寺山修司,鈴木成一寺山修司は、私の「特別」だ。 いつだって、頭の中に血をぎゅんぎゅんと巡らせてくれる。視界がチカチカと眩むほどに、過剰な血を供給する。あゝ。 寺山修司は、この、生まれてはじめての長篇小説を、歌謡曲の一節、スポーツ用語、方言、小説や詩のフレーズなどの「手垢にまみれた言葉」をコラージュすることで作り上げた。 ラストシーンには惚れ惚れする。 「一発、二発、三発、四発、五発、六発、七発!」 八十九発まで連なる、この、単なる数字の羅列が、どうしようもなく「詩」だ。 一発一発を、殴り、殺すようにして、心を揺らしながら全て書き写す。 「私は近頃、「ことば」でも「性」でもなく「暴力」というものに興味を持つようになってきた。暴力という伝達行為。暴力という連帯方法。これはいかがなものであろうか?何人も、戦場に於ける兵士のようにきびしく「相手」を見張ることは出来ないし「相手」の一挙手一投足に興味を持つことは出来ない。そんなことから、私はボクシングに心魅かれるようになった。あの、殴りながら相手を理解してゆくという悲しい暴力行為。相手を傷つけずに相手を愛することなどできる訳がない。勿論、愛さずに傷つけることだって、できる訳がないのである。」 「いかにして新宿新次を憎むか。憎まなければ新次と試合をすることは出来ないし、試合しなければ「新次に勝つ」ことは出来ないだろう。そしてそれなしでは、彼は自分自身の人生の意味を解説することができないという気がするのである。」 「あいつはたぶん、俺に殴り倒されようとたくらんでいるのだ。俺の手で徹底的に打ちのめされ、血まみれになって倒れることによって、俺とのっぴきならない関係を持とうとしているのだ。」 「俺はとうとう「憎む」ということができなかった一人のボクサーです。俺は皆が好きだ。俺は「愛するために愛されたい」」 目の前が 一望の 荒野だ
あゝ、荒野寺山修司,鈴木成一寺山修司は、私の「特別」だ。 いつだって、頭の中に血をぎゅんぎゅんと巡らせてくれる。視界がチカチカと眩むほどに、過剰な血を供給する。あゝ。 寺山修司は、この、生まれてはじめての長篇小説を、歌謡曲の一節、スポーツ用語、方言、小説や詩のフレーズなどの「手垢にまみれた言葉」をコラージュすることで作り上げた。 ラストシーンには惚れ惚れする。 「一発、二発、三発、四発、五発、六発、七発!」 八十九発まで連なる、この、単なる数字の羅列が、どうしようもなく「詩」だ。 一発一発を、殴り、殺すようにして、心を揺らしながら全て書き写す。 「私は近頃、「ことば」でも「性」でもなく「暴力」というものに興味を持つようになってきた。暴力という伝達行為。暴力という連帯方法。これはいかがなものであろうか?何人も、戦場に於ける兵士のようにきびしく「相手」を見張ることは出来ないし「相手」の一挙手一投足に興味を持つことは出来ない。そんなことから、私はボクシングに心魅かれるようになった。あの、殴りながら相手を理解してゆくという悲しい暴力行為。相手を傷つけずに相手を愛することなどできる訳がない。勿論、愛さずに傷つけることだって、できる訳がないのである。」 「いかにして新宿新次を憎むか。憎まなければ新次と試合をすることは出来ないし、試合しなければ「新次に勝つ」ことは出来ないだろう。そしてそれなしでは、彼は自分自身の人生の意味を解説することができないという気がするのである。」 「あいつはたぶん、俺に殴り倒されようとたくらんでいるのだ。俺の手で徹底的に打ちのめされ、血まみれになって倒れることによって、俺とのっぴきならない関係を持とうとしているのだ。」 「俺はとうとう「憎む」ということができなかった一人のボクサーです。俺は皆が好きだ。俺は「愛するために愛されたい」」 目の前が 一望の 荒野だ - 1900年1月1日
 「特にしつけのやかましい家庭に育った訳でもないのに、私は大人になったら「名作童話に復讐してやりたい」と思っていた。ピノキオがポルノだったり、はだかの王さまが形而上学者だったり、赤ずきんがニンフォマニアックだったりする、という事実を「実話雑誌」風に暴露し、それらが「大人にとって都合のいい子供にしつけるための教材にすぎない」と言いたかったのだ」 星の王子さま然り、寺山修司には「復讐してやりたい物語」がいっぱいあるのだな、と可笑しい。 物語への最大の復讐とは何か? それは、物語を「書き直してしまうこと」なのだ。 「事実を事実としてだけ受け入れていても、あっというまに月日は流れる。風車を巨人に見立てる位の想像力でもなければおもしろくもおかしくもない」 新しい歌をおぼえてみる、ちょっと風変わりなドレスを着てみる、気に入った男の子とキスをしてみる。 世界と出会い直すこと、世界を物語化することの尽きない魅力を、寺山修司が何度も教え直してくれる。 天井桟敷で観客たちや市民をスポットライトの下に引っ張り上げたように、読書においてさえ、この人は、決して読者を受取手に留めてくれず、穴埋め問題や続きの公募によって関与を強いてくれるのだ。
「特にしつけのやかましい家庭に育った訳でもないのに、私は大人になったら「名作童話に復讐してやりたい」と思っていた。ピノキオがポルノだったり、はだかの王さまが形而上学者だったり、赤ずきんがニンフォマニアックだったりする、という事実を「実話雑誌」風に暴露し、それらが「大人にとって都合のいい子供にしつけるための教材にすぎない」と言いたかったのだ」 星の王子さま然り、寺山修司には「復讐してやりたい物語」がいっぱいあるのだな、と可笑しい。 物語への最大の復讐とは何か? それは、物語を「書き直してしまうこと」なのだ。 「事実を事実としてだけ受け入れていても、あっというまに月日は流れる。風車を巨人に見立てる位の想像力でもなければおもしろくもおかしくもない」 新しい歌をおぼえてみる、ちょっと風変わりなドレスを着てみる、気に入った男の子とキスをしてみる。 世界と出会い直すこと、世界を物語化することの尽きない魅力を、寺山修司が何度も教え直してくれる。 天井桟敷で観客たちや市民をスポットライトの下に引っ張り上げたように、読書においてさえ、この人は、決して読者を受取手に留めてくれず、穴埋め問題や続きの公募によって関与を強いてくれるのだ。 - 1900年1月1日
 寺山修司著作集(第3巻)寺山修司,山口昌男寺山修司という現象に、なぜ私は、こんなにも惹かれるのだろうか。そもそもは、釧路の北海岸で弓子を探す「白夜」を読みたくて、思い切って買った。 それから、ことあるごとに、繰り返し少しずつ読んできた。幼少期から林檎が嫌いだが実家の母が林檎をくれた年末、「アダムとイヴ、私の犯罪学」を読んだ。三島由紀夫の文学館で美輪明宏の「黒蜥蜴」のポスターを見た帰り道、「毛皮のマリー」を読んだ。引っ越し先で偶々、天井桟敷という酒場を見つけ、隅っこのカウンターで「観客席」を読んだ。宮沢賢治を読んで背徳感を抱きつつ「奴婢訓」を読んだ。 「ほうら、事実が死んだ!」「生れてくる赤ちゃんの背中に、あたしの肉のお墓を立てて下さい」「遅い。もう手遅れだ。「前から六列目、右から五番目」に坐った人が今夜の主役になるって台本に指定されてある。あんたはもう個人じゃない、今夜の「事件」なんだ」「林檎はこの世で一番小さな地球!片手にでものせられる「創世記」のいれもの。毎日毎日、林檎を食って食って食いまくってやる…」「観客席は、安全じゃありません。(全員)そう、安全じゃない!」「何がかくされているかわからない。(全員)そう、わからない!」 「たしかにわれわれは日常生活の中で、つねに何かを演じつづけている。人生というものは数十年におよぶ一幕劇であり、その中での虚像と実像との葛藤というのは、そのまま生きるための条理の略奪戦を思わせる何かがあるようである」 「この戯曲は、新宿歌舞伎町を舞台にした私版の聖書である。トイレットペーパーに書かれた雅歌であるとともに、憎しみのバラードでもある。欲深くなったイヴと老いたるアダム。彼ら「作られた人びと」が、自らもう一つの天地を創る日のためにこの一幕を捧ぐ」
寺山修司著作集(第3巻)寺山修司,山口昌男寺山修司という現象に、なぜ私は、こんなにも惹かれるのだろうか。そもそもは、釧路の北海岸で弓子を探す「白夜」を読みたくて、思い切って買った。 それから、ことあるごとに、繰り返し少しずつ読んできた。幼少期から林檎が嫌いだが実家の母が林檎をくれた年末、「アダムとイヴ、私の犯罪学」を読んだ。三島由紀夫の文学館で美輪明宏の「黒蜥蜴」のポスターを見た帰り道、「毛皮のマリー」を読んだ。引っ越し先で偶々、天井桟敷という酒場を見つけ、隅っこのカウンターで「観客席」を読んだ。宮沢賢治を読んで背徳感を抱きつつ「奴婢訓」を読んだ。 「ほうら、事実が死んだ!」「生れてくる赤ちゃんの背中に、あたしの肉のお墓を立てて下さい」「遅い。もう手遅れだ。「前から六列目、右から五番目」に坐った人が今夜の主役になるって台本に指定されてある。あんたはもう個人じゃない、今夜の「事件」なんだ」「林檎はこの世で一番小さな地球!片手にでものせられる「創世記」のいれもの。毎日毎日、林檎を食って食って食いまくってやる…」「観客席は、安全じゃありません。(全員)そう、安全じゃない!」「何がかくされているかわからない。(全員)そう、わからない!」 「たしかにわれわれは日常生活の中で、つねに何かを演じつづけている。人生というものは数十年におよぶ一幕劇であり、その中での虚像と実像との葛藤というのは、そのまま生きるための条理の略奪戦を思わせる何かがあるようである」 「この戯曲は、新宿歌舞伎町を舞台にした私版の聖書である。トイレットペーパーに書かれた雅歌であるとともに、憎しみのバラードでもある。欲深くなったイヴと老いたるアダム。彼ら「作られた人びと」が、自らもう一つの天地を創る日のためにこの一幕を捧ぐ」 - 1900年1月1日
 恩田陸一群れの百合。 鈍く光る白い百合の中から、芯のある香りが漂い出している。 この香り。 決して逃れることのできない、どこまでも迫ってくる香り。 魔女の住む屋敷。 おおきな魔女は死んでしまった。 美しい祖母。 美しい叔母。 美しい理瀬。 この家の2階には妖精が住んでいる。 百合の花は妖精が好きな花だから、この家には百合を飾るんだ。 不穏を強く含んだ香りにまとわりつかれて、くらくらする。 理瀬の少女時代が終わる。 訣別して、旅立つ。 一緒に飛んでいってあげられたらよかったけれど、残念ながら無理みたい。 理瀬シリーズの続編に進もう。 「悪は全ての源なのだ。 善など、しょせん悪の上澄みの一部に過ぎない。 悪を引き立てる、ハンカチの縁の刺繍でしかないのだ。 でなければ、善がいつもあんなに弱く、嘘くさく、脆く儚いことの説明がつかない。」
恩田陸一群れの百合。 鈍く光る白い百合の中から、芯のある香りが漂い出している。 この香り。 決して逃れることのできない、どこまでも迫ってくる香り。 魔女の住む屋敷。 おおきな魔女は死んでしまった。 美しい祖母。 美しい叔母。 美しい理瀬。 この家の2階には妖精が住んでいる。 百合の花は妖精が好きな花だから、この家には百合を飾るんだ。 不穏を強く含んだ香りにまとわりつかれて、くらくらする。 理瀬の少女時代が終わる。 訣別して、旅立つ。 一緒に飛んでいってあげられたらよかったけれど、残念ながら無理みたい。 理瀬シリーズの続編に進もう。 「悪は全ての源なのだ。 善など、しょせん悪の上澄みの一部に過ぎない。 悪を引き立てる、ハンカチの縁の刺繍でしかないのだ。 でなければ、善がいつもあんなに弱く、嘘くさく、脆く儚いことの説明がつかない。」 - 1900年1月1日
 恩田陸奇妙な場所で、酒を飲みながら読んだ。私は今回の旅で、ひたすらに読んでいる。巨大なクスノキが生えた寺院の頭上を、人工物が走っていく。坂道の多い細い道を、呼吸を乱しながら登った。空が青い暑い日。猫の多い道。まんまるの石に猫の絵が描かれ、そこかしこに置かれている。たくさんの目に見られている。梟の店でビールを頼み、縁側みたいな席でずっと飲んでずっと読んだ。何をしているのかしら、私は。歩き続け、登り続ける彼らに同化したかったのかしら。なんと魅力的な旅。なんと素敵な4人組。美しき謎と過去への思索の旅。森は続いている。 「心なんてもの、愛なんてものを発明したのはどこのどいつだろう?そいつはとっくに首を吊られて処刑されているに違いない。いつごろから愛がこれほど幅を利かせるようになったのだろう。不思議でならない。歌が下手だったら歌手になれるはずはないし、成績が悪ければ行ける大学が限られてくることは誰もが納得する。なせ愛に限っては自分もいつか素晴らしいものを与えられるはずだと無邪気に信じることができるのだろう。どいつもこいつも愛乞食だ。」 蒔生の傲慢な利己は揺らがない。蒔生の根元にはたくさんの人間が埋まり、鮮やかな桜が咲く。 鹿が出てくる。鹿。いつも道の先にいる。行く手に立っていて、さっと消える。思わせぶりで、何か意味がありそうに感じてしまう。 啓示だと言うなら、私は、この本を抱えて入ったこじんまりとした書店を思い出す。珈琲を飲みながら本棚を眺められる小さな家。買うと名刺の裏に、女性が、リクエストを受けた絵を描いてくれる。何がいいですか?と穏やかに尋ねられて、私は、鹿を頼んだのだった。木々に身を隠しながらこちらを眺める、角に金色の混じった、大きな目の鹿を描いてくれたのだった。 なぜ私、あの時、ほんの少し迷って、鹿を選んだのかしら。
恩田陸奇妙な場所で、酒を飲みながら読んだ。私は今回の旅で、ひたすらに読んでいる。巨大なクスノキが生えた寺院の頭上を、人工物が走っていく。坂道の多い細い道を、呼吸を乱しながら登った。空が青い暑い日。猫の多い道。まんまるの石に猫の絵が描かれ、そこかしこに置かれている。たくさんの目に見られている。梟の店でビールを頼み、縁側みたいな席でずっと飲んでずっと読んだ。何をしているのかしら、私は。歩き続け、登り続ける彼らに同化したかったのかしら。なんと魅力的な旅。なんと素敵な4人組。美しき謎と過去への思索の旅。森は続いている。 「心なんてもの、愛なんてものを発明したのはどこのどいつだろう?そいつはとっくに首を吊られて処刑されているに違いない。いつごろから愛がこれほど幅を利かせるようになったのだろう。不思議でならない。歌が下手だったら歌手になれるはずはないし、成績が悪ければ行ける大学が限られてくることは誰もが納得する。なせ愛に限っては自分もいつか素晴らしいものを与えられるはずだと無邪気に信じることができるのだろう。どいつもこいつも愛乞食だ。」 蒔生の傲慢な利己は揺らがない。蒔生の根元にはたくさんの人間が埋まり、鮮やかな桜が咲く。 鹿が出てくる。鹿。いつも道の先にいる。行く手に立っていて、さっと消える。思わせぶりで、何か意味がありそうに感じてしまう。 啓示だと言うなら、私は、この本を抱えて入ったこじんまりとした書店を思い出す。珈琲を飲みながら本棚を眺められる小さな家。買うと名刺の裏に、女性が、リクエストを受けた絵を描いてくれる。何がいいですか?と穏やかに尋ねられて、私は、鹿を頼んだのだった。木々に身を隠しながらこちらを眺める、角に金色の混じった、大きな目の鹿を描いてくれたのだった。 なぜ私、あの時、ほんの少し迷って、鹿を選んだのかしら。 - 1900年1月1日
 恩田陸「過去」の中にこそ本物のミステリーがあるのだ。時間に、記憶に、街角に、蔵の隅に、音もなく埋もれていくものの中に「美しい謎」がある。我々は過去を取り戻すために旅をする。 この旅のテーマは「非日常」。サブテーマは「安楽椅子探偵紀行」。4人の男女が集まる。Y島を歩く。しきりに喋る、喋る、喋る。日常会話ではない会話をする。 今まで見た映画で何が一番好き?−長谷川和彦の「太陽を盗んだ男」。結婚する前に相手に一つだけ質問できるとしたら?何が起きても、私のことを理解しようとしないでくれますか。一番怖い物は?紫陽花。 ただ、森の中を4人で歩くだけ。歩く。話す。食べる。飲む。眠る。日常から離れたところで、いくら話しても何も変わらない過去を、謎を、ただ話し、考え、解いていく。 「森は生きている、というのは嘘だ。いや、嘘というよりも、正しくない、と言うべきだろう。森は死者でいっぱいだ。森の中には生者と死者とが混在している。足元には死者が堆積し、木々の梢からは赤ん坊の笑い声が降る。気の遠くなるような時間の蓄積を目の当たりにして、我々は森に圧倒され、畏怖を覚えるのだ。」 寛いでいる人間を前にして感じる気まずさや気後れはなんだろう。 西へ、西へと移動をしながら読んだのだ。暑いと聞いていたものだから、覚悟して薄着で行ったところ、どこもかしこも冷房で、かえって寒かったことが、肉体に刻まれた印象だった。飛行機で、電車で、読んで読んで読んで。歩いている人たちを読みながら、私はただ座って、凄い速さではるばる遠くまで運ばれてしまったのだった。移動した先で何もしないで過ごす。1日中本屋にいた。 ただ、1週間ずっと、本を読んでいた。
恩田陸「過去」の中にこそ本物のミステリーがあるのだ。時間に、記憶に、街角に、蔵の隅に、音もなく埋もれていくものの中に「美しい謎」がある。我々は過去を取り戻すために旅をする。 この旅のテーマは「非日常」。サブテーマは「安楽椅子探偵紀行」。4人の男女が集まる。Y島を歩く。しきりに喋る、喋る、喋る。日常会話ではない会話をする。 今まで見た映画で何が一番好き?−長谷川和彦の「太陽を盗んだ男」。結婚する前に相手に一つだけ質問できるとしたら?何が起きても、私のことを理解しようとしないでくれますか。一番怖い物は?紫陽花。 ただ、森の中を4人で歩くだけ。歩く。話す。食べる。飲む。眠る。日常から離れたところで、いくら話しても何も変わらない過去を、謎を、ただ話し、考え、解いていく。 「森は生きている、というのは嘘だ。いや、嘘というよりも、正しくない、と言うべきだろう。森は死者でいっぱいだ。森の中には生者と死者とが混在している。足元には死者が堆積し、木々の梢からは赤ん坊の笑い声が降る。気の遠くなるような時間の蓄積を目の当たりにして、我々は森に圧倒され、畏怖を覚えるのだ。」 寛いでいる人間を前にして感じる気まずさや気後れはなんだろう。 西へ、西へと移動をしながら読んだのだ。暑いと聞いていたものだから、覚悟して薄着で行ったところ、どこもかしこも冷房で、かえって寒かったことが、肉体に刻まれた印象だった。飛行機で、電車で、読んで読んで読んで。歩いている人たちを読みながら、私はただ座って、凄い速さではるばる遠くまで運ばれてしまったのだった。移動した先で何もしないで過ごす。1日中本屋にいた。 ただ、1週間ずっと、本を読んでいた。 - 1900年1月1日
 恩田陸物語だ。謎に「日常」を侵食されるのが、震えるほど面白い。知る人ぞ知る「三月は深き紅の淵を」という私家本。噂ばかりが囁かれて人々の興味を煽り、存在そのものにたくさんの物語が加わって、知らぬ間に成長していく謎めいた本。第一部「黒と茶の幻想」第二部「冬の湖」第三部「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」第四部「鳩笛」ずるずると引きずり込まれてしまう小説。ああ、読みたい。そんな、現実が曖昧になるような、甘美な読書に没頭したい。たかが一個人の表現手段に使われるほど、物語は小さくない。物語は物語自身のために存在する。 この小説は箱物。千一夜物語みたいに、物語の中に物語が入れ子になって、中に中に沈んでいくと思いきやいつの間にか裏返って、現実世界を物語が食ってしまう。本書の最後、第四章「回転木馬」。書き手が今まさに小説を書き始める場面で、書き出しの文句をあれやこれやと試行する。その本の名前は「三月は深き紅の淵を」。第一章は「黒と茶の幻想」。書き出しはこんな風に始まる。「森は生きている、というのは嘘だ。いや、嘘というよりも、正しくない、と言うべきだろう。」。最後の行まで読み終え、物語に酔ったまま、書店の恩田陸の棚に足を運ぶ。ずらりと並んた文庫の中に「黒と茶の幻想(上)(下)」の背表紙が目に留まる。おいおい待ってくれよ、と、予感に震えながら手にとる。その本の第一章の書き出しは、「森は生きている、というのは嘘だ。いや、嘘というよりも、正しくない、と言うべきだろう。」。嗚呼。これは。 物語が終わっても、物語から抜け出せない。これだから読書は、もう、たまらなく面白いんだ。物語を続けよう。
恩田陸物語だ。謎に「日常」を侵食されるのが、震えるほど面白い。知る人ぞ知る「三月は深き紅の淵を」という私家本。噂ばかりが囁かれて人々の興味を煽り、存在そのものにたくさんの物語が加わって、知らぬ間に成長していく謎めいた本。第一部「黒と茶の幻想」第二部「冬の湖」第三部「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」第四部「鳩笛」ずるずると引きずり込まれてしまう小説。ああ、読みたい。そんな、現実が曖昧になるような、甘美な読書に没頭したい。たかが一個人の表現手段に使われるほど、物語は小さくない。物語は物語自身のために存在する。 この小説は箱物。千一夜物語みたいに、物語の中に物語が入れ子になって、中に中に沈んでいくと思いきやいつの間にか裏返って、現実世界を物語が食ってしまう。本書の最後、第四章「回転木馬」。書き手が今まさに小説を書き始める場面で、書き出しの文句をあれやこれやと試行する。その本の名前は「三月は深き紅の淵を」。第一章は「黒と茶の幻想」。書き出しはこんな風に始まる。「森は生きている、というのは嘘だ。いや、嘘というよりも、正しくない、と言うべきだろう。」。最後の行まで読み終え、物語に酔ったまま、書店の恩田陸の棚に足を運ぶ。ずらりと並んた文庫の中に「黒と茶の幻想(上)(下)」の背表紙が目に留まる。おいおい待ってくれよ、と、予感に震えながら手にとる。その本の第一章の書き出しは、「森は生きている、というのは嘘だ。いや、嘘というよりも、正しくない、と言うべきだろう。」。嗚呼。これは。 物語が終わっても、物語から抜け出せない。これだから読書は、もう、たまらなく面白いんだ。物語を続けよう。 - 1900年1月1日
 ブラック・ベルベット恩田陸恩田陸おっもしろ。 恵弥シリーズ大好き。 濃密な言葉をジリジリと浴びてすっかり満足してしまう。 登場人物の思想思考知恵知識に圧倒されて、ついつい、自分の頭を使うのが億劫になって、自分の語彙が情けなくなって、もう感想の言語化は放棄した。 本筋とは全く関係はないが、T共和国のエフェソス遺跡での会話。 「この太陽、ちょっと殺気を感じるわね」 「『異邦人』か?」 「太陽が眩しすぎて、人を殺すどころかこっちが熱中症で死んじゃうわ」 こういうやりとり、学生時代から好き。 中身のない、知識を玩具みたいに雑にする会話の妙、堪らん。
ブラック・ベルベット恩田陸恩田陸おっもしろ。 恵弥シリーズ大好き。 濃密な言葉をジリジリと浴びてすっかり満足してしまう。 登場人物の思想思考知恵知識に圧倒されて、ついつい、自分の頭を使うのが億劫になって、自分の語彙が情けなくなって、もう感想の言語化は放棄した。 本筋とは全く関係はないが、T共和国のエフェソス遺跡での会話。 「この太陽、ちょっと殺気を感じるわね」 「『異邦人』か?」 「太陽が眩しすぎて、人を殺すどころかこっちが熱中症で死んじゃうわ」 こういうやりとり、学生時代から好き。 中身のない、知識を玩具みたいに雑にする会話の妙、堪らん。 - 1900年1月1日
 クレオパトラの夢新装版恩田陸恩田陸「あたしはねえ、夢を探しに来たの。 この素敵な北の大地にね。 やっぱり北の大地はロマンでしょ? ここには見果てぬ夢があるわ。 できればその夢を見つけ出したいと思っているの」 クレオパトラの夢。 クレオパトラは、毒蛇に自分を噛ませて自殺した。 「クレオパトラ」とは何か? またしても、恩田陸の描く北海道。 女言葉を操る端整なウイルスハンター神原恵弥シリーズの二作目。 函館。 昭和九年三月二十一日に函館で発生した史上最大の大火。 吹きさらしの地で炎は広がり続け、市の三分の二を焼き尽くした。 函館の地図と史実を織り込んだ謎解きに心が躍る。 北の国の香りに、かすかに混じる古い異国の香り。 本当に、この土地は、こんな歴史を持っているのかもしれないわって思っちゃう。 史実の裏にこんな、綱渡りみたいにスレスレの研究が、災害が、あったのではないかしら、と。 神原恵弥は、やはりひたすらに魅力的。
クレオパトラの夢新装版恩田陸恩田陸「あたしはねえ、夢を探しに来たの。 この素敵な北の大地にね。 やっぱり北の大地はロマンでしょ? ここには見果てぬ夢があるわ。 できればその夢を見つけ出したいと思っているの」 クレオパトラの夢。 クレオパトラは、毒蛇に自分を噛ませて自殺した。 「クレオパトラ」とは何か? またしても、恩田陸の描く北海道。 女言葉を操る端整なウイルスハンター神原恵弥シリーズの二作目。 函館。 昭和九年三月二十一日に函館で発生した史上最大の大火。 吹きさらしの地で炎は広がり続け、市の三分の二を焼き尽くした。 函館の地図と史実を織り込んだ謎解きに心が躍る。 北の国の香りに、かすかに混じる古い異国の香り。 本当に、この土地は、こんな歴史を持っているのかもしれないわって思っちゃう。 史実の裏にこんな、綱渡りみたいにスレスレの研究が、災害が、あったのではないかしら、と。 神原恵弥は、やはりひたすらに魅力的。 - 1900年1月1日
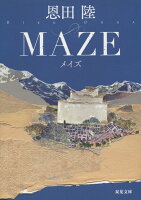 MAZE新装版恩田陸恩田陸恩田陸の幻想世界は、地下から空まで根気よく丁寧に構築されているので、安心してその世界に入り込み、不安になれる。 微睡んで頭を飛ばしながら読むのが気持ち良い。 「深い青、それは、見上げているうちに魂まで抜かれてしまいそうな空の色だ。 遥かな高みから見下ろしている誰かの存在を意識する、ほとんど狂気に近い歓喜の色。 そこにあるのは、直方体をした白っぽい建物だった。 丘のてっぺんに白い箱がちょこんと載っているように見える。 窓も柱もない、のっぺりとした白い箱」 導入の情景描写に連れ去られる。 青と白の眩しさと不穏。 人間が消える。 「じゃあ、正式に要請しましょう。 あんたは、この人里離れた山奥の聖地で、安楽椅子探偵をやるために呼ばれたの。 これでよろしいかしら?」 わくわくする。面白い。 神原恵弥が魅力的だ。 「ジェンダーなんて相対的なものよね。 女きょうだいが多いと、中で必ず誰かが男役を引き受けるようになる。 男である、女であるというアイデンティティなんて曖昧なものだわ。 みんな男と女という割り振られた役を演じてるだけ」 艶やかな女言葉を使いこなす、精悍な男。 この男の続編「クレオパトラの夢」を読むためにこの本を手に取った。 本懐を果たそう。
MAZE新装版恩田陸恩田陸恩田陸の幻想世界は、地下から空まで根気よく丁寧に構築されているので、安心してその世界に入り込み、不安になれる。 微睡んで頭を飛ばしながら読むのが気持ち良い。 「深い青、それは、見上げているうちに魂まで抜かれてしまいそうな空の色だ。 遥かな高みから見下ろしている誰かの存在を意識する、ほとんど狂気に近い歓喜の色。 そこにあるのは、直方体をした白っぽい建物だった。 丘のてっぺんに白い箱がちょこんと載っているように見える。 窓も柱もない、のっぺりとした白い箱」 導入の情景描写に連れ去られる。 青と白の眩しさと不穏。 人間が消える。 「じゃあ、正式に要請しましょう。 あんたは、この人里離れた山奥の聖地で、安楽椅子探偵をやるために呼ばれたの。 これでよろしいかしら?」 わくわくする。面白い。 神原恵弥が魅力的だ。 「ジェンダーなんて相対的なものよね。 女きょうだいが多いと、中で必ず誰かが男役を引き受けるようになる。 男である、女であるというアイデンティティなんて曖昧なものだわ。 みんな男と女という割り振られた役を演じてるだけ」 艶やかな女言葉を使いこなす、精悍な男。 この男の続編「クレオパトラの夢」を読むためにこの本を手に取った。 本懐を果たそう。 - 1900年1月1日
 潮騒 (新潮文庫)三島由紀夫三島由紀夫@ 神島三島由紀夫「潮騒」を携えて、舞台となった三重の神島へ行った。 快晴の暑い日。 八代神社だけ駆け上がって、あとはのんびり潮騒を読み返して過ごそうと思っていたところ、 あとから思い返すとなぜ?というくらい単純な道を間違えて、一気に灯台まで辿り着いた。 今さら引っ込みがつかなくなって、ワンピースにヒールのサンダルという場違いな格好で、虫たちや森そのものに恐れおののきながら、山道を掻き分け掻き分けて、ぜえはあ言いつつ汗だくで、かの有名な「その火を飛び越して来い」の監的哨にも、初江と新治の母親が鮑とり対決をしたニワの浜にも行ってしまった。 三島由紀夫が、私にこの島を一周させたのだと、私は勝手にそう思った。 衝動は楽しい。 読書は楽しい。
潮騒 (新潮文庫)三島由紀夫三島由紀夫@ 神島三島由紀夫「潮騒」を携えて、舞台となった三重の神島へ行った。 快晴の暑い日。 八代神社だけ駆け上がって、あとはのんびり潮騒を読み返して過ごそうと思っていたところ、 あとから思い返すとなぜ?というくらい単純な道を間違えて、一気に灯台まで辿り着いた。 今さら引っ込みがつかなくなって、ワンピースにヒールのサンダルという場違いな格好で、虫たちや森そのものに恐れおののきながら、山道を掻き分け掻き分けて、ぜえはあ言いつつ汗だくで、かの有名な「その火を飛び越して来い」の監的哨にも、初江と新治の母親が鮑とり対決をしたニワの浜にも行ってしまった。 三島由紀夫が、私にこの島を一周させたのだと、私は勝手にそう思った。 衝動は楽しい。 読書は楽しい。
- 1900年1月1日
 愛の渇き (新潮文庫)三島由紀夫三島由紀夫だめなのよ。 誰もあたくしを苦しめてはいけませんの。 誰もあたくしを苦しめることなぞできませんの。 恕して頂戴。あたくしは苦しんだのよ。こうする他なかったのよ。 素足で歩いては足が傷ついてしまう。歩くためには靴が要るように、生きてゆくためには何か出来合いの「思い込み」が要るの。 あたくしの、あたくしだけの、「思い込み」。 それを邪魔する者は、世界から喪われ、捻じ曲がる。 「それでも私は幸福だ。私は幸福だ。誰もそれを否定できはしない。第一、証拠がない。」 見える物を見ないことで生まれる、星の王子様的幸福論がここにあるのね。 「何もかも呑み込んでしまわねば。何もかもしゃにむに目をつぶって是認してしまわねば。この苦痛をおいしそうに喰べてしまわねば。 砂金採りは砂金ばかり掬い上げることはできはしないし、また、しもしないのだわ。盲滅法に河底の砂を掬い上げる、その砂のなかに砂金がないかもしれないし、またあるかもしれないのだわ。その在不在を前以て選ぶ権利は誰にもありはしないのだわ。 そうして更に確実な幸福は、海に注ぐ大河の水をのこらず呑み込んでしまうことだ。 私は今までそれをやって来た。今後もやるだろう。 私の胃の腑はきっとそれに耐えるだろう。」 悦子の幸福は、求めてやまない男に狂おしく求められ、それを素気無く拒絶し、別の男からそれを嫉妬され、嫉妬のあまり殺されること、だったのではないかしら。 あの時、鍬の矛先は、全方向に落とされる可能性を持っていた。
愛の渇き (新潮文庫)三島由紀夫三島由紀夫だめなのよ。 誰もあたくしを苦しめてはいけませんの。 誰もあたくしを苦しめることなぞできませんの。 恕して頂戴。あたくしは苦しんだのよ。こうする他なかったのよ。 素足で歩いては足が傷ついてしまう。歩くためには靴が要るように、生きてゆくためには何か出来合いの「思い込み」が要るの。 あたくしの、あたくしだけの、「思い込み」。 それを邪魔する者は、世界から喪われ、捻じ曲がる。 「それでも私は幸福だ。私は幸福だ。誰もそれを否定できはしない。第一、証拠がない。」 見える物を見ないことで生まれる、星の王子様的幸福論がここにあるのね。 「何もかも呑み込んでしまわねば。何もかもしゃにむに目をつぶって是認してしまわねば。この苦痛をおいしそうに喰べてしまわねば。 砂金採りは砂金ばかり掬い上げることはできはしないし、また、しもしないのだわ。盲滅法に河底の砂を掬い上げる、その砂のなかに砂金がないかもしれないし、またあるかもしれないのだわ。その在不在を前以て選ぶ権利は誰にもありはしないのだわ。 そうして更に確実な幸福は、海に注ぐ大河の水をのこらず呑み込んでしまうことだ。 私は今までそれをやって来た。今後もやるだろう。 私の胃の腑はきっとそれに耐えるだろう。」 悦子の幸福は、求めてやまない男に狂おしく求められ、それを素気無く拒絶し、別の男からそれを嫉妬され、嫉妬のあまり殺されること、だったのではないかしら。 あの時、鍬の矛先は、全方向に落とされる可能性を持っていた。 - 1900年1月1日
 音楽三島由紀夫三島由紀夫「先生、どうしてなんでしょう。私、音楽がきこえないんです」 美しく冷たい訴え。冷感症の女。嘘つきで、思わせぶりで、酷薄で、可哀想な女。 精神分析の言葉や思想は、三島由紀夫を介して美しい不感症の女として実体化すると、こんなにも生き生きと美しく人間を語るのか。 学問として眺めてきた人間精神の神話が、夢の象徴と分析が、転移と逆転移が、言葉の装飾できらきらと飾られ、誘惑的に輝いていた。 『オンガクオコル オンガクタユルコトナシ』 永遠に咲く造花のように、豪奢な言葉で作った物語が美しい。 「麗子はただそのいかにも燃えやすい材料ばかりでできたような美しい豊かな裸体を、彼の傍らに横たえているだけだった。花井の不能は次第に燃えさかる不能になった。麗子は、融けるほど心優しかったが、肉体は氷のようだった」
音楽三島由紀夫三島由紀夫「先生、どうしてなんでしょう。私、音楽がきこえないんです」 美しく冷たい訴え。冷感症の女。嘘つきで、思わせぶりで、酷薄で、可哀想な女。 精神分析の言葉や思想は、三島由紀夫を介して美しい不感症の女として実体化すると、こんなにも生き生きと美しく人間を語るのか。 学問として眺めてきた人間精神の神話が、夢の象徴と分析が、転移と逆転移が、言葉の装飾できらきらと飾られ、誘惑的に輝いていた。 『オンガクオコル オンガクタユルコトナシ』 永遠に咲く造花のように、豪奢な言葉で作った物語が美しい。 「麗子はただそのいかにも燃えやすい材料ばかりでできたような美しい豊かな裸体を、彼の傍らに横たえているだけだった。花井の不能は次第に燃えさかる不能になった。麗子は、融けるほど心優しかったが、肉体は氷のようだった」 - 1900年1月1日
 午後の曳航三島由紀夫三島由紀夫「男」は危険な死や栄光を目掛け海へと去っていく存在であり、「女」は完璧な美しさと肉の重さを持って港に残される存在であらねばならぬ。「汽笛」の音が宿命を告げ、ふたりは引き裂かれる。 それでこそ美しい。 それだから美しい。 それなのに。 「男」は、「海」より「栄光」より「死」より、「結婚」を望んだ。 「女」とともに「陸」に残り、瞬く間に「生活」の匂いにまみれ、世界の悪の形そのものである「父親」になった。 子どもは、それを、許さない。 世界の空洞を満たす「死」。 「死」を行使することで、子どもは、存在に対する実権を獲得する。 「刑法第四十一条、十四歳二満タザル者ノ行為ハ之ヲ罰セズ。これが大体、僕たちの父親どもが、彼らの信じている架空の社会が、僕たちのために決めてくれた法律なんだ。僕たちには何もできないという油断のおかげで、ここにだけ、ちらと青空の一ㇳかけらを、絶対の自由の一ㇳかけらを覗かせたんだ。それはいわば、大人たちの作った童話だけど、ずいぶん危険な童話を作ったもんだな。まあいいさ。今までのところ、なにしろ僕たちは、可愛い、かよわい、罪を知らない児童なんだからね。」
午後の曳航三島由紀夫三島由紀夫「男」は危険な死や栄光を目掛け海へと去っていく存在であり、「女」は完璧な美しさと肉の重さを持って港に残される存在であらねばならぬ。「汽笛」の音が宿命を告げ、ふたりは引き裂かれる。 それでこそ美しい。 それだから美しい。 それなのに。 「男」は、「海」より「栄光」より「死」より、「結婚」を望んだ。 「女」とともに「陸」に残り、瞬く間に「生活」の匂いにまみれ、世界の悪の形そのものである「父親」になった。 子どもは、それを、許さない。 世界の空洞を満たす「死」。 「死」を行使することで、子どもは、存在に対する実権を獲得する。 「刑法第四十一条、十四歳二満タザル者ノ行為ハ之ヲ罰セズ。これが大体、僕たちの父親どもが、彼らの信じている架空の社会が、僕たちのために決めてくれた法律なんだ。僕たちには何もできないという油断のおかげで、ここにだけ、ちらと青空の一ㇳかけらを、絶対の自由の一ㇳかけらを覗かせたんだ。それはいわば、大人たちの作った童話だけど、ずいぶん危険な童話を作ったもんだな。まあいいさ。今までのところ、なにしろ僕たちは、可愛い、かよわい、罪を知らない児童なんだからね。」 - 1900年1月1日
 美徳のよろめき三島由紀夫三島由紀夫「ちゃんと着物を着て御飯を喰べるのって不味いな。僕は真裸で喰べるのが好きなんだ」 「一人で?」 「君って子供なんだね」と土屋は偉そうに言った。 この一言はかなりあとまで節子に影響を与えた。 そんな情景は今までの彼女には想像も及ばぬ奇観であった。 節子の躾が、無邪気に讃嘆の叫びをあげていた。 何というすばらしいお行儀のわるさ! 二人は体の上に焼けたパンの粉を平気でこぼし、銀の珈琲ポットの熱さにあわてて脇腹を引込めたりしながら、朝食を摂った。 それは決して淫らな食事ではなかった。 むしろ子供らしい無垢な朝食だったと云っていい。 私には、時折、生身のものからすべからく距離を取りたい衝動がやってくる。 そういうときに三島由紀夫が救ってくれる。 こんなにも浮世を離れた男女の描写って、ない。 情欲によろめき不貞をはたらくことを、こんなにも潔癖なほど陽の光にさらして書き起こしてしまえるのは、なぜなのだろう。 「女神」に、女が美しく見えるのは見る側に欲望があるからだ、という描写があった。 その言葉に乗るのであれば、三島由紀夫が女を見るときにこれっぽっちもその目に欲望を乗せていなかったということがわかってしまう。
美徳のよろめき三島由紀夫三島由紀夫「ちゃんと着物を着て御飯を喰べるのって不味いな。僕は真裸で喰べるのが好きなんだ」 「一人で?」 「君って子供なんだね」と土屋は偉そうに言った。 この一言はかなりあとまで節子に影響を与えた。 そんな情景は今までの彼女には想像も及ばぬ奇観であった。 節子の躾が、無邪気に讃嘆の叫びをあげていた。 何というすばらしいお行儀のわるさ! 二人は体の上に焼けたパンの粉を平気でこぼし、銀の珈琲ポットの熱さにあわてて脇腹を引込めたりしながら、朝食を摂った。 それは決して淫らな食事ではなかった。 むしろ子供らしい無垢な朝食だったと云っていい。 私には、時折、生身のものからすべからく距離を取りたい衝動がやってくる。 そういうときに三島由紀夫が救ってくれる。 こんなにも浮世を離れた男女の描写って、ない。 情欲によろめき不貞をはたらくことを、こんなにも潔癖なほど陽の光にさらして書き起こしてしまえるのは、なぜなのだろう。 「女神」に、女が美しく見えるのは見る側に欲望があるからだ、という描写があった。 その言葉に乗るのであれば、三島由紀夫が女を見るときにこれっぽっちもその目に欲望を乗せていなかったということがわかってしまう。
読み込み中...