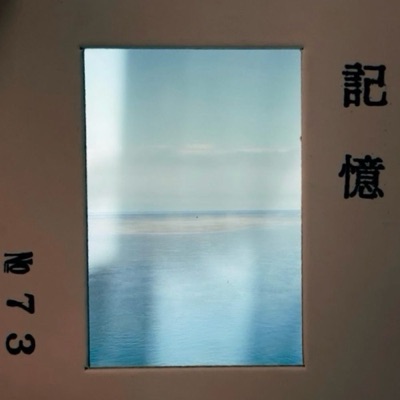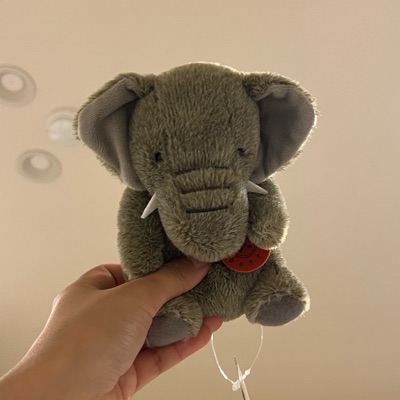詩の構造についての覚え書

81件の記録
- アステリズム@rn_asterism2026年1月2日読み始めた読んでる読み始めてみたが、わかるようなわからないような感覚が続いている たまにむっちゃ腑に落ちる(ように錯覚する?)ので、とりあえず読み進めてみる 夏目漱石が自然主義サイドから〈拵えもの〉として批判されたことを思い出すなど
- 62yen@62yen2025年8月3日読み終わった途中で著者の執拗(マジで執拗)な問題意識への関心が保てなくなってしまい、後半は流し読み。ただ、「詩は表現ではない」という前提には納得感はあった。 誰もが日常的に使用・受容する言語を、それとは異なるレベルで運用するという点に、詩や詩人や読者の困難さ、わからなさが滲み出ている……ような本かも。
 読書猫@bookcat2025年4月4日読み終わった(本文抜粋) “「詩は表現ではない」ということを、今一度言い直せば「詩作品は、伝達の手段ではない」ということだが、ここでいささか補足をしておくと、《マッチ棒を耳かきとして使い、とがったつららを凶器として用いる》といった意味でなら(つまり部分の機能を意識的に誤用──あるいは活用すれば)伝達手段であり得る場合もあろうと言っておくべきかもしれぬ。けれども、一つ一つの詩作品そのものの本来の任務は、やはり伝達という点にはないと言わねばならない。 では、一歩を進めて、「詩作品は手段ではない」と言えるだろうか。さらにそれを裏返して、「手段ではなく、それ自体が目的なのだ」と言えないか。あるいはこう言いかえることも考えられる。「手段でなくて、言葉で作られてそれ自体で完結した一つの世界、一つの事物、つまりオブジェである」と。”
読書猫@bookcat2025年4月4日読み終わった(本文抜粋) “「詩は表現ではない」ということを、今一度言い直せば「詩作品は、伝達の手段ではない」ということだが、ここでいささか補足をしておくと、《マッチ棒を耳かきとして使い、とがったつららを凶器として用いる》といった意味でなら(つまり部分の機能を意識的に誤用──あるいは活用すれば)伝達手段であり得る場合もあろうと言っておくべきかもしれぬ。けれども、一つ一つの詩作品そのものの本来の任務は、やはり伝達という点にはないと言わねばならない。 では、一歩を進めて、「詩作品は手段ではない」と言えるだろうか。さらにそれを裏返して、「手段ではなく、それ自体が目的なのだ」と言えないか。あるいはこう言いかえることも考えられる。「手段でなくて、言葉で作られてそれ自体で完結した一つの世界、一つの事物、つまりオブジェである」と。” YT@FireWalkWithMe2025年3月18日買ったかつて読んだ入沢の詩に初めて触れたのは、二十歳のころ、師・Tさんが授業の導入に「キラキラヒカル」を使用した時だったと思う。それ以来おれにとって入沢の詩とその詩論は、映画と同じくらい重要なものとなった。いまでもその考えは変わらない、特に「詩の構造〜」は六八年以後の詩論における最重要文献のひとつと思う。文庫化を寿ぐ。
YT@FireWalkWithMe2025年3月18日買ったかつて読んだ入沢の詩に初めて触れたのは、二十歳のころ、師・Tさんが授業の導入に「キラキラヒカル」を使用した時だったと思う。それ以来おれにとって入沢の詩とその詩論は、映画と同じくらい重要なものとなった。いまでもその考えは変わらない、特に「詩の構造〜」は六八年以後の詩論における最重要文献のひとつと思う。文庫化を寿ぐ。 むらた@L4stboy2025年3月13日気になる読みたい買った評判がよかったこともあり、詩が気になることもありの本棚イン。詩の楽しさすごさは、遠いように思われる二項の間に同じ構造をぎゅっとつかんで軽やかに結び付けられることだと今のところ思っているので、そんな認識がどう変わっていくか楽しみ。
むらた@L4stboy2025年3月13日気になる読みたい買った評判がよかったこともあり、詩が気になることもありの本棚イン。詩の楽しさすごさは、遠いように思われる二項の間に同じ構造をぎゅっとつかんで軽やかに結び付けられることだと今のところ思っているので、そんな認識がどう変わっていくか楽しみ。

 鷹緒@takao_tanka2025年3月10日気になるちょっと前に、Xの短歌界隈で「作中主体」という語の是非(というか取り扱いかた?)について意見が飛び交っていた。 自分でもちょっと改めて考えたいトピックなので、この本が気になる🤔 しかしわたし自身はわりと「短歌は短歌、詩は詩」と切り分けて考えがちなので、参考になるかな〜……
鷹緒@takao_tanka2025年3月10日気になるちょっと前に、Xの短歌界隈で「作中主体」という語の是非(というか取り扱いかた?)について意見が飛び交っていた。 自分でもちょっと改めて考えたいトピックなので、この本が気になる🤔 しかしわたし自身はわりと「短歌は短歌、詩は詩」と切り分けて考えがちなので、参考になるかな〜……