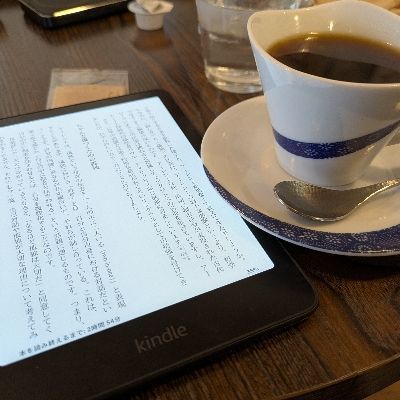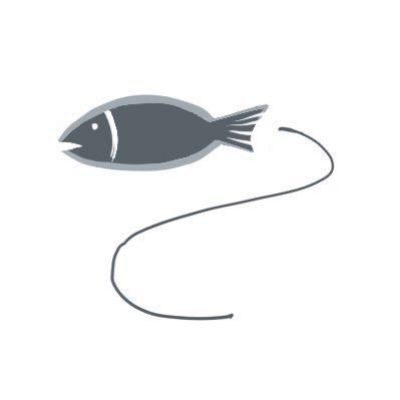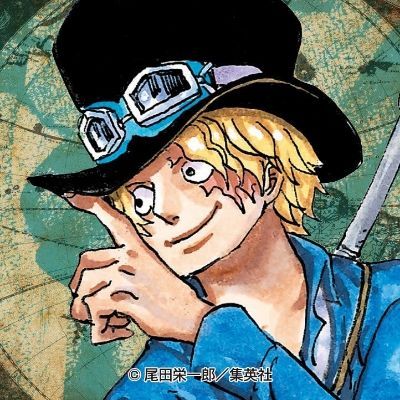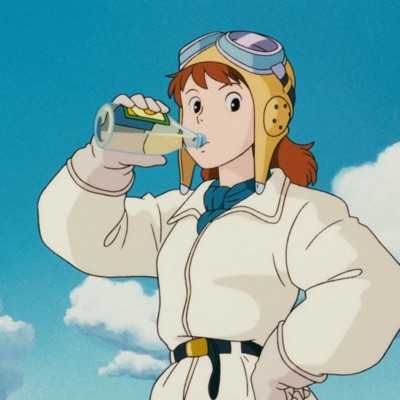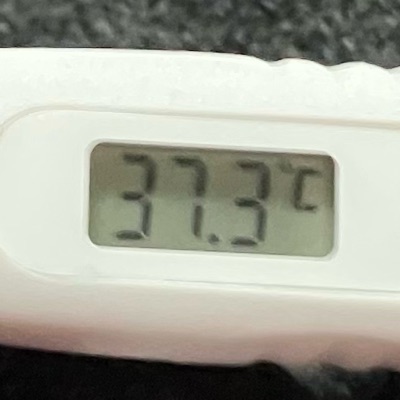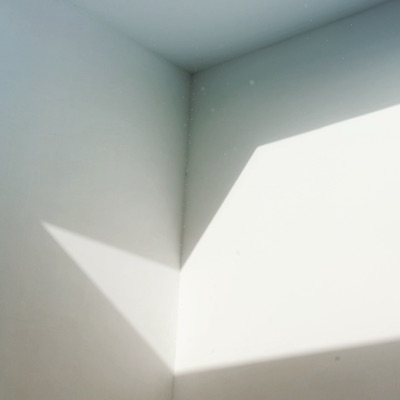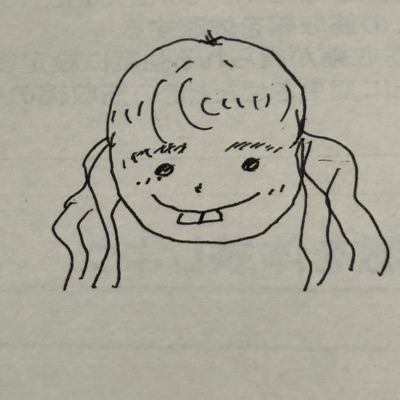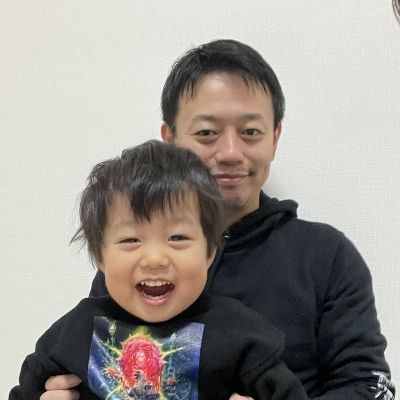なぜ働いていると本が読めなくなるのか (集英社新書)

160件の記録
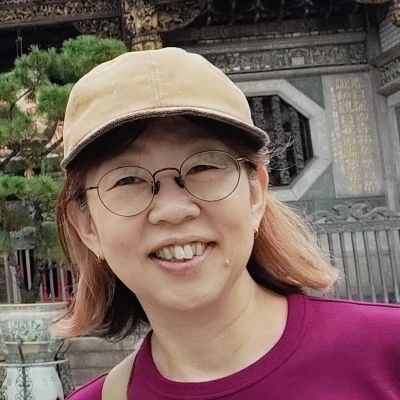 わらびもち@warabimochi2026年2月19日読み終わったaudibleざっと読んだので、ひとまずよしとします。 タイトルを見た時「働いていると本が読めなくなる理由って実はコレなんですよ!」みたいなことを教えてくれる本かと思ったら全然違うから、アレレ?😮となった。 内容は悪くないけど、なんかだまされた気分で、あまり気持ちよくはない。
わらびもち@warabimochi2026年2月19日読み終わったaudibleざっと読んだので、ひとまずよしとします。 タイトルを見た時「働いていると本が読めなくなる理由って実はコレなんですよ!」みたいなことを教えてくれる本かと思ったら全然違うから、アレレ?😮となった。 内容は悪くないけど、なんかだまされた気分で、あまり気持ちよくはない。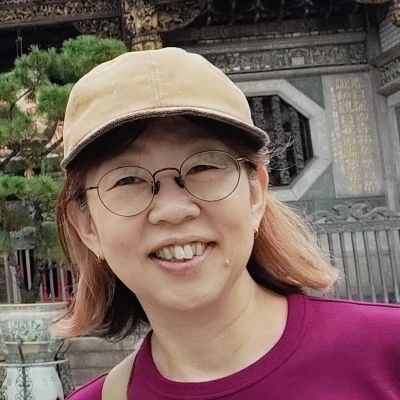 わらびもち@warabimochi2026年2月19日読み始めたaudible話題の本なのでチラ見 題名と違って主な内容は「読書の歴史」なんですね。「働いていると本が読めなくなる意外な理由…」みたいなのが書いてあるのかと思ったら全然そんなんじゃなかったw 働いていると「本が読めなくなる」というより「趣味ができなくなる」ということかな?と思った。 あとがきの、「働きながら本を読むコツ」私だったら絶対 audibleをおすすめする😊
わらびもち@warabimochi2026年2月19日読み始めたaudible話題の本なのでチラ見 題名と違って主な内容は「読書の歴史」なんですね。「働いていると本が読めなくなる意外な理由…」みたいなのが書いてあるのかと思ったら全然そんなんじゃなかったw 働いていると「本が読めなくなる」というより「趣味ができなくなる」ということかな?と思った。 あとがきの、「働きながら本を読むコツ」私だったら絶対 audibleをおすすめする😊 もなか@monaka2026年1月7日買った読み終わった言わずと知れたベストセラーですが、本屋さんで手に取ってみたら面白そうだったので。 結論部分よりも、意外と前半の、明治以降の読書と労働の関係、人が本に求めるものが変遷し、それがベストセラーに表れている、というあたりが読んでいて面白かったです。
もなか@monaka2026年1月7日買った読み終わった言わずと知れたベストセラーですが、本屋さんで手に取ってみたら面白そうだったので。 結論部分よりも、意外と前半の、明治以降の読書と労働の関係、人が本に求めるものが変遷し、それがベストセラーに表れている、というあたりが読んでいて面白かったです。 ルイス@lou2s2026年1月5日読み終わった冒頭の一句に引き込まれた。同作者が別作で説いた技法を、見事に実践している。 しかし、期待とは裏腹に、本書の大半を占める社会の仕組みと読書姿勢についての歴史的考察は、自分には合わなかった。タイトルの本題「なぜ」に興味を持って、実用的なヒントを求めていた読者にとって、半冊近くにわたる歴史講座は正直言って退屈で、途中で読むのをやめようかと何度も思った。歴史好きには魅力的な内容かもしれないが。 作者の説によれば、それこそが「ノイズ」らしい。作者の定義では、ノイズとは歴史や他作品の文脈、想定外の展開を指す。意外にこの前半部分がそれに当たるわけだ。後半で展開される「ノイズ」の概念や「半身」という考え方は確かに示唆に富んでおり、論としては納得できる。 理屈では分かる。だが正直なところ、これがノイズなら、もう少し心地よいホワイトノイズやピンクノイズのような受け入れやすさが欲しかった。
ルイス@lou2s2026年1月5日読み終わった冒頭の一句に引き込まれた。同作者が別作で説いた技法を、見事に実践している。 しかし、期待とは裏腹に、本書の大半を占める社会の仕組みと読書姿勢についての歴史的考察は、自分には合わなかった。タイトルの本題「なぜ」に興味を持って、実用的なヒントを求めていた読者にとって、半冊近くにわたる歴史講座は正直言って退屈で、途中で読むのをやめようかと何度も思った。歴史好きには魅力的な内容かもしれないが。 作者の説によれば、それこそが「ノイズ」らしい。作者の定義では、ノイズとは歴史や他作品の文脈、想定外の展開を指す。意外にこの前半部分がそれに当たるわけだ。後半で展開される「ノイズ」の概念や「半身」という考え方は確かに示唆に富んでおり、論としては納得できる。 理屈では分かる。だが正直なところ、これがノイズなら、もう少し心地よいホワイトノイズやピンクノイズのような受け入れやすさが欲しかった。

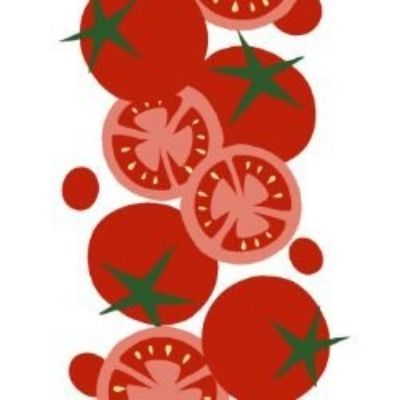


 ユッキオ@morningstar2026年1月5日読み終わった読書のためには余裕が必要、長時間労働・重労働・ハラスメント許すまじの気持ちになった。 スマホ画面をスワイプしながらの無限スクロールの罠も、その気軽さ、快さから。 (あとXのたまにグッとくるポストが射倖心?を持たせると思う。面白ポストを待ってスクロールがやめられない。そして思惑どおり現れるとドーパミンが出てますますエンドレス) 精神的に追い詰められた個人ならそれを追ってしまうのは仕方ない…花に水を、労働者に余裕を!
ユッキオ@morningstar2026年1月5日読み終わった読書のためには余裕が必要、長時間労働・重労働・ハラスメント許すまじの気持ちになった。 スマホ画面をスワイプしながらの無限スクロールの罠も、その気軽さ、快さから。 (あとXのたまにグッとくるポストが射倖心?を持たせると思う。面白ポストを待ってスクロールがやめられない。そして思惑どおり現れるとドーパミンが出てますますエンドレス) 精神的に追い詰められた個人ならそれを追ってしまうのは仕方ない…花に水を、労働者に余裕を!
 葉鳥@kihariko2026年1月4日買った読み始めた働きながらでも趣味時間を捻出しようと思えばできるけど、その空いた時間をスマホでつい浪費してしまうのは何故なのか?今よりも労働時間が長かった明治以降の近代は読書とどう向き合っていたのか?気になる。読んでいたら分かるかな? ざっと目次を見た感じ、第五、七、九章に興味あり。
葉鳥@kihariko2026年1月4日買った読み始めた働きながらでも趣味時間を捻出しようと思えばできるけど、その空いた時間をスマホでつい浪費してしまうのは何故なのか?今よりも労働時間が長かった明治以降の近代は読書とどう向き合っていたのか?気になる。読んでいたら分かるかな? ざっと目次を見た感じ、第五、七、九章に興味あり。
 ルイス@lou2s2026年1月3日読んでる全然ワクワクしないし、面白くなくて無理して読んでるのがつらい。この本を開くたびに口角が下がっていることに気づく。早く終わらせて次の本に行きたい。 いっそ途中でやめちゃった方がいいかな?
ルイス@lou2s2026年1月3日読んでる全然ワクワクしないし、面白くなくて無理して読んでるのがつらい。この本を開くたびに口角が下がっていることに気づく。早く終わらせて次の本に行きたい。 いっそ途中でやめちゃった方がいいかな?
 kubomi@kubomi2026年1月3日読み終わった📝読書して得る知識にはノイズ――偶然性が含まれる。教養と呼ばれる古典的な知識や、小説のようなフィクションには、読者が予想していなかった展開や知識が登場する。文脈や説明のなかで、読者が予期しなかった偶然出会う情報を、私たちは知識と呼ぶ。 📝大切なのは、他者の文脈をシャットアウトしないことだ。仕事のノイズになるような知識を、あえて受け入れる。仕事以外の文脈を思い出すこと。そのノイズを、受け入れること。それこそが、私たちが働きながら本を読む一歩なのではないだろうか。 📝本のなかには、私たちが欲望していることを知らない知が存在している。知は常に未知であり、私たちは「何を知りたいのか」を知らない。何を読みたいのか、私たちは分かっていない。何を欲望しているのか、私たちは分かっていないのだ。だからこそ本を読むと、他者の文脈に触れることができる。自分から遠く離れた文脈に触れること――それが読書なのである。 📝私たちは、そろそろ「半身」の働き方を当然とすべきではないか。いや、働き方だけではない。さまざまな分野において、「半身」を取り入れるべきだ。「全身」に傾くのは容易だ。しかし「全身」に傾いている人は、他者にもどこかで「全身」を求めたくなってしまう。「全身」社会に戻るのは楽かもしれない。しかし持続可能ではない。そこに待ち受けるのは、社会の複雑さに耐えられない疲労した身体である。「半身」とは、さまざまな文脈に身をゆだねることである。読書が他者の文脈を取り入れることだとすれば、「半身」は読書を続けるコツそのものである。
kubomi@kubomi2026年1月3日読み終わった📝読書して得る知識にはノイズ――偶然性が含まれる。教養と呼ばれる古典的な知識や、小説のようなフィクションには、読者が予想していなかった展開や知識が登場する。文脈や説明のなかで、読者が予期しなかった偶然出会う情報を、私たちは知識と呼ぶ。 📝大切なのは、他者の文脈をシャットアウトしないことだ。仕事のノイズになるような知識を、あえて受け入れる。仕事以外の文脈を思い出すこと。そのノイズを、受け入れること。それこそが、私たちが働きながら本を読む一歩なのではないだろうか。 📝本のなかには、私たちが欲望していることを知らない知が存在している。知は常に未知であり、私たちは「何を知りたいのか」を知らない。何を読みたいのか、私たちは分かっていない。何を欲望しているのか、私たちは分かっていないのだ。だからこそ本を読むと、他者の文脈に触れることができる。自分から遠く離れた文脈に触れること――それが読書なのである。 📝私たちは、そろそろ「半身」の働き方を当然とすべきではないか。いや、働き方だけではない。さまざまな分野において、「半身」を取り入れるべきだ。「全身」に傾くのは容易だ。しかし「全身」に傾いている人は、他者にもどこかで「全身」を求めたくなってしまう。「全身」社会に戻るのは楽かもしれない。しかし持続可能ではない。そこに待ち受けるのは、社会の複雑さに耐えられない疲労した身体である。「半身」とは、さまざまな文脈に身をゆだねることである。読書が他者の文脈を取り入れることだとすれば、「半身」は読書を続けるコツそのものである。
 ちくわ@stuntman-kent2025年12月31日読み終わった自分も「花恋」に何か共鳴するものを感じてしまった口で、ロマンポルシェ。のロマンさんが紹介していたのがきっかけで手に取った。明治時代から今日に至るまでの労働と読書の関係性を丁寧に紐解いていて、語り口がフェアでなんとなく著者はこの人のこと嫌いなんだろうなぁくらいのが垣間見られる程度だから、つっかかるところなくすいすい読めてしまう。 標題に対しての著者の提案。全身全霊からの脱却、疲れたら一旦読書から離れる、仕事帰りに喫茶店で読書してみるといったことが、自分は既に体得していて、この辺は新たな知見に触れるというより自分の生き方に少し自信が持てるような、そんな後味の良さがあった。あとは自分が自己啓発本に対して抱いているうさんくささのようなものをしっかり言語化してくれている。 仕事と子育ての一番多忙な時期をようやく超えて、読書や映画といった他者の文脈により触れることを欲している今、麦くんでいうところのパズドラ(自分はウマ娘のゲーム)をこの際消してしまおうと決断させてくれた本でもあった。さよならネイチャ…
ちくわ@stuntman-kent2025年12月31日読み終わった自分も「花恋」に何か共鳴するものを感じてしまった口で、ロマンポルシェ。のロマンさんが紹介していたのがきっかけで手に取った。明治時代から今日に至るまでの労働と読書の関係性を丁寧に紐解いていて、語り口がフェアでなんとなく著者はこの人のこと嫌いなんだろうなぁくらいのが垣間見られる程度だから、つっかかるところなくすいすい読めてしまう。 標題に対しての著者の提案。全身全霊からの脱却、疲れたら一旦読書から離れる、仕事帰りに喫茶店で読書してみるといったことが、自分は既に体得していて、この辺は新たな知見に触れるというより自分の生き方に少し自信が持てるような、そんな後味の良さがあった。あとは自分が自己啓発本に対して抱いているうさんくささのようなものをしっかり言語化してくれている。 仕事と子育ての一番多忙な時期をようやく超えて、読書や映画といった他者の文脈により触れることを欲している今、麦くんでいうところのパズドラ(自分はウマ娘のゲーム)をこの際消してしまおうと決断させてくれた本でもあった。さよならネイチャ…
 食いしん坊ちぇりぃ@yummyyummycherry2025年12月20日読み終わった家族の積読になっていたので先に読んでみた。タイトルと内容にギャップを感じて挫折しそうになりつつも、近代以降の労働と読書の関係性を辿った先にどんな「なぜ」への答えが書かれているのか気になって読み進め読了。 私がちゃんと読めていないのか…結論としては「なぜ働いていると本が読めなくなるのか、なぜなら働いているからです」というトートロージー的なところに帰結している気がして、ちょっとズコーとなっちゃった。個人的な体感としては、労働より育児の方が読書との噛み合わせは悪い。 今回読んで違和感を感じたところをまた違うタイミングで読み返してみたいので備忘メモ: ⭐︎「労働者の読書」や「カルチャーセンター受講」の動機として、コンプレックスを補うためという建て付けが度々用いられていて、やや抵抗感があった…純粋な知識欲や好奇心、“ノイズ”を積極的に取り入れたい前向きな姿勢を認めず、n数の限られたサンプルをもって特定のクラスターに「コンプレックスを抱く人々」という視線を向けているところが気になった。その視線が私にも向けられているような気がしたから気になったのかな…? ⭐︎ 教養的なノイズとは異なるものの、ネットはマーケターがフィードしてくるノイズに満ちている気がする。ネットでノイズをどの程度排除できるかはサイトのアルゴリズムや個人の検索リテラシーに依存するような…ネットからはノイズのない情報、本からはノイズを含んだ知識を得られると単純化できるのだろうか。ノイズの意味を私が取り違えてる…? ⭐︎ひとつのことだけをするのが楽…?仕事だけしていることや育児だけしていることを楽とは全く思わなかったけど、言わんとしていることはなんとなく分かる。楽というより気持ちよくなれる、という感じかな。有限リソースを一極集中で投入すると効率良く成果を上げられてドーパミンで脳が気持ちよくなって、その中毒性から逃れられなくてひとつのことだけしちゃうっていうのはあるかもね。若いハイパフォーマーの子は特に。 **2026年1月29日追記** この本を読んで考えたことを音声配信しています https://stand.fm/episodes/697b19e8ca2973e1d360fbd3
食いしん坊ちぇりぃ@yummyyummycherry2025年12月20日読み終わった家族の積読になっていたので先に読んでみた。タイトルと内容にギャップを感じて挫折しそうになりつつも、近代以降の労働と読書の関係性を辿った先にどんな「なぜ」への答えが書かれているのか気になって読み進め読了。 私がちゃんと読めていないのか…結論としては「なぜ働いていると本が読めなくなるのか、なぜなら働いているからです」というトートロージー的なところに帰結している気がして、ちょっとズコーとなっちゃった。個人的な体感としては、労働より育児の方が読書との噛み合わせは悪い。 今回読んで違和感を感じたところをまた違うタイミングで読み返してみたいので備忘メモ: ⭐︎「労働者の読書」や「カルチャーセンター受講」の動機として、コンプレックスを補うためという建て付けが度々用いられていて、やや抵抗感があった…純粋な知識欲や好奇心、“ノイズ”を積極的に取り入れたい前向きな姿勢を認めず、n数の限られたサンプルをもって特定のクラスターに「コンプレックスを抱く人々」という視線を向けているところが気になった。その視線が私にも向けられているような気がしたから気になったのかな…? ⭐︎ 教養的なノイズとは異なるものの、ネットはマーケターがフィードしてくるノイズに満ちている気がする。ネットでノイズをどの程度排除できるかはサイトのアルゴリズムや個人の検索リテラシーに依存するような…ネットからはノイズのない情報、本からはノイズを含んだ知識を得られると単純化できるのだろうか。ノイズの意味を私が取り違えてる…? ⭐︎ひとつのことだけをするのが楽…?仕事だけしていることや育児だけしていることを楽とは全く思わなかったけど、言わんとしていることはなんとなく分かる。楽というより気持ちよくなれる、という感じかな。有限リソースを一極集中で投入すると効率良く成果を上げられてドーパミンで脳が気持ちよくなって、その中毒性から逃れられなくてひとつのことだけしちゃうっていうのはあるかもね。若いハイパフォーマーの子は特に。 **2026年1月29日追記** この本を読んで考えたことを音声配信しています https://stand.fm/episodes/697b19e8ca2973e1d360fbd3



 いろは@1234ki22025年12月14日読み終わった最近流行りの脳科学的視点ではなく、歴史的・社会学的な視点から、サラリーマンが本を読めなくなる理由を論じていたところが面白かった。 この本をきっかけに、読書熱が再燃した。 以下、メモ ・江戸:音読、家族に読み聞かせる ・明治:黙読、個人で読むため@活版印刷 ・読む人はインテリ層 ・大衆向け図書館:大正時代@識字率 ・大正時代:サラリーマンの誕生 ・『知人の愛』疲れたサラリーマン向け ・関東大震災後:円本(1円予約全集) ・装丁が美麗 ・書斎で見せるためのもの ・80〜90年代:心理学の流行 ・90年代半ば:行動 ・00年代:自己啓発書 ・バブル崩壊後:自己分析マニュアル増大 「片付け本」という名の自己啓発書は、コントローラブルな〈部屋〉をときめくもので埋め尽くすことによって〈人生〉を社会から守ろうとさせるP179 「自己が日々関係を切り結ぶはずの「社会」を忌まわしいものとして、あるいは関連のないものとして遠ざけてしまうような、そのような生との対峙の形式 ・自己実現=仕事 ・読書=ノイズ どこまでがアイデンティティ? 自分とは何か? その問いすらも時代の産物
いろは@1234ki22025年12月14日読み終わった最近流行りの脳科学的視点ではなく、歴史的・社会学的な視点から、サラリーマンが本を読めなくなる理由を論じていたところが面白かった。 この本をきっかけに、読書熱が再燃した。 以下、メモ ・江戸:音読、家族に読み聞かせる ・明治:黙読、個人で読むため@活版印刷 ・読む人はインテリ層 ・大衆向け図書館:大正時代@識字率 ・大正時代:サラリーマンの誕生 ・『知人の愛』疲れたサラリーマン向け ・関東大震災後:円本(1円予約全集) ・装丁が美麗 ・書斎で見せるためのもの ・80〜90年代:心理学の流行 ・90年代半ば:行動 ・00年代:自己啓発書 ・バブル崩壊後:自己分析マニュアル増大 「片付け本」という名の自己啓発書は、コントローラブルな〈部屋〉をときめくもので埋め尽くすことによって〈人生〉を社会から守ろうとさせるP179 「自己が日々関係を切り結ぶはずの「社会」を忌まわしいものとして、あるいは関連のないものとして遠ざけてしまうような、そのような生との対峙の形式 ・自己実現=仕事 ・読書=ノイズ どこまでがアイデンティティ? 自分とは何か? その問いすらも時代の産物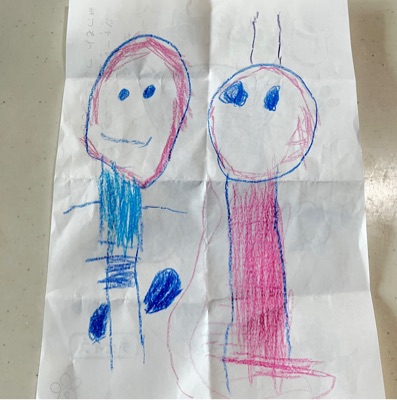
 とり@torikawaniku2025年11月14日読み終わった最初の方は「で…本題は…??」と思いつつ読み進んでたけど、確かにいつから読書って文化ができていったのかとか、戦前と戦後にかけてどうなっていったのかとか全然知らんかったし考えたこともなかった。 最後結論?てきな話読んでる時ははあ〜なるほどねえと思った。なんかこう、それが証明された感じではなく、私はそう思いますって感じで述べられてる印象だった。う〜ん、そういう働き方、生き方ができたらいいんすよけどねえ…と思って読み終わった。
とり@torikawaniku2025年11月14日読み終わった最初の方は「で…本題は…??」と思いつつ読み進んでたけど、確かにいつから読書って文化ができていったのかとか、戦前と戦後にかけてどうなっていったのかとか全然知らんかったし考えたこともなかった。 最後結論?てきな話読んでる時ははあ〜なるほどねえと思った。なんかこう、それが証明された感じではなく、私はそう思いますって感じで述べられてる印象だった。う〜ん、そういう働き方、生き方ができたらいいんすよけどねえ…と思って読み終わった。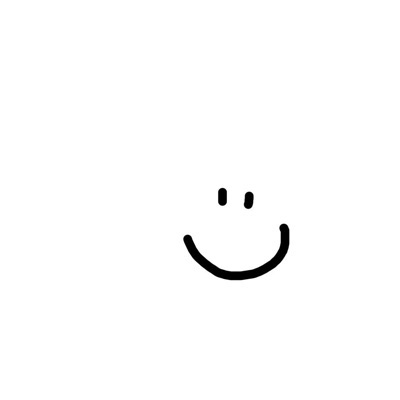
- ふる@ful_352025年11月10日読み終わった著者と自分は生きている世界が違うのだろうか。 以下、感じたこと。 <本のタイトル> “なぜ働いていると本が読めなくなるのか”という問に対しての内容は少ないので、連載時のサブタイトル”労働と読書の近代史を読む”が本当のタイトルだと思って読むとしっくりくる。 <内容、構成> よく調べられていて感心する。一方で文献からの引用が多く、言語化する技術の本を書いた人なのに著者の言葉が少ない?と感じた。 元々が連載であるため仕方がないのかもしれないが、ところどころ話の繋がりが不自然というのか、ぶつ切り感があるというか…自分がこのような本を読み慣れていないだけかもしれないが、読み辛く感じた。 自分は文系の論文を読んだことがないが、この本のような感じなのかなと思った(自分の主張を先に述べ、裏付けとなる文献を持ってくる) <結論> “働きすぎ”というありきたりな結論でがっかりだった。改めて言われなくてもみんな感じているのでは。(”大正時代から残業は多かった、働きすぎは今に始まったことではない。”ような文脈だったのにこの結論?) “半身で働く”も上野千鶴子氏の言葉だし、著者が導き出した答えというより乗っかっただけでは。そもそも、それができれば苦労はしない。仕事をほどほどにプライベートの時間を確保しよう、というのは誰でも思い付く発想で、それができないからみなタイトルに釣られてこの本を手に取ったのではないだろうか。 著者は役所•病院•電気ガス水道通信などのインフラに関わる人たちの前で”仕事を頑張り過ぎです、半身で働きましょう”と言えるのだろうか。 “本”というエンタメとも言える業界で、原稿が遅れてもごめんなさいで済む業界で、”半身で働く”ことが許される環境に身を置いた人間のポジショントークでは。そんな想像力のない人が自分に酔った文章を書き、ベストな答えに辿り着いたと良い気分に浸っているのか… と、ネガティブ思考になってしまい反省しているところ。 人口減少だけど仕事は減らないから働き方改革(有給5日間、ペーパーレス、テレワーク、フレックスetc)、副業、外国人労働者、育休など、労働力を確保するために労働環境を改善して持続可能な社会を目指すための取り組みはとっくに始まっており、国も企業も浸透し始めていると私は感じている。5年前に比べれば確実にプライベートを犠牲にしないで済むようになっている。 ”みんなで頑張り過ぎない社会にしませんか”というのが著者の提言だが、そのためのアクションは既に始まっているのに今更そのフェーズの話をするの?と思ってしまった。著者と自分は生きている世界が違うのだろうか。




 ゆにこ@unico03102025年10月22日過去から現在に至るまで読書の歴史をその時代ごとの流れとともに教えてくれる本。 昔の話はざっくりと流していたが後半の自分も通ってきた時代に入ると納得しながらスイスイ読めた。 結局忙しい人は本が読めない。 私は忙しくないので本が読める。
ゆにこ@unico03102025年10月22日過去から現在に至るまで読書の歴史をその時代ごとの流れとともに教えてくれる本。 昔の話はざっくりと流していたが後半の自分も通ってきた時代に入ると納得しながらスイスイ読めた。 結局忙しい人は本が読めない。 私は忙しくないので本が読める。

 ゆう@langern_19992025年10月5日子供の頃から本が好きだった。本を読んで夜更かししたり、ジャケ買いした小説に涙したり、ちゃんと好きだった、はずだった。 大学生・社会人になってからだろうか。勉強や教養のために専門書や難しい新書、純文学を“読まないとダメだ”自分よりたくさん本を読む人達には“敵わない”と勝手に考えるようになり、だんだん読書が辛いものになってしまった。 そんな折、「最近また本が読めないから、何かリハビリによい本はないだろうか」と考えて立ち寄った本屋で出会ったのがこの本。 内容は、労働と読書を歴史的な背景から関連付けて、労働者が本が読めなくなってしまう理由を紐解くというもの。仕事が自己実現となり、様々な娯楽に溢れる現代では、確かに本は求められていないのかもしれない。また、この著書の内容は読書に限らず「自分の趣味」に置き換えても考えられる。 この本を読んで良かったのが、作者である三宅香帆さんを知れた事。本を読んだあとに作者について調べてみたら、ユーチューブで様々な本の紹介や読書論を行っているので動画を見てみた。とても楽しそうに本について語っている内容だった。 その時以来、「難しい本じゃなくても、たくさん読めなくても読書が好きでいいじゃん」と思えるようになった。 後日、このコペルニクス的大発見を本好きの友人に話したら「読書なんて楽しいものじゃん、何バカなこと言ってるの」と笑われてしまった。
ゆう@langern_19992025年10月5日子供の頃から本が好きだった。本を読んで夜更かししたり、ジャケ買いした小説に涙したり、ちゃんと好きだった、はずだった。 大学生・社会人になってからだろうか。勉強や教養のために専門書や難しい新書、純文学を“読まないとダメだ”自分よりたくさん本を読む人達には“敵わない”と勝手に考えるようになり、だんだん読書が辛いものになってしまった。 そんな折、「最近また本が読めないから、何かリハビリによい本はないだろうか」と考えて立ち寄った本屋で出会ったのがこの本。 内容は、労働と読書を歴史的な背景から関連付けて、労働者が本が読めなくなってしまう理由を紐解くというもの。仕事が自己実現となり、様々な娯楽に溢れる現代では、確かに本は求められていないのかもしれない。また、この著書の内容は読書に限らず「自分の趣味」に置き換えても考えられる。 この本を読んで良かったのが、作者である三宅香帆さんを知れた事。本を読んだあとに作者について調べてみたら、ユーチューブで様々な本の紹介や読書論を行っているので動画を見てみた。とても楽しそうに本について語っている内容だった。 その時以来、「難しい本じゃなくても、たくさん読めなくても読書が好きでいいじゃん」と思えるようになった。 後日、このコペルニクス的大発見を本好きの友人に話したら「読書なんて楽しいものじゃん、何バカなこと言ってるの」と笑われてしまった。


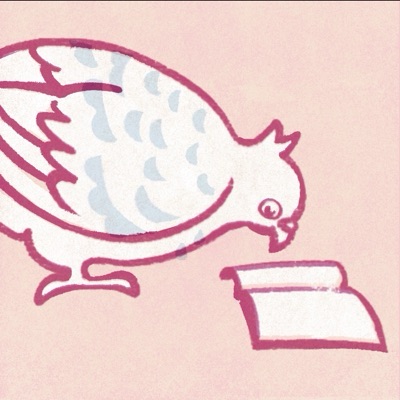

 煮た武士@nitabushi242025年9月14日半身で働く。とても大事な働き方だと思う。 人生何があるかわからないし、全てを仕事にコミットすることはできない場面も多い。(自他の病気、介護など)。 働く以外にもやりたいことはたくさんあって、どのことも楽しめる状態になるのがいいなと思う。 全身の仕事を半身にするにはどうすればいいんだろうね? 個人と組織の両軸の動きがないと半身社会の実現は難しいなぁと感じる。 個人が仕事を効率化して余暇を作り出そうとする動きと同時に、上司や組織がジョブスクリプションで定義されている以上の仕事を振らないという仕組みが必要そう。
煮た武士@nitabushi242025年9月14日半身で働く。とても大事な働き方だと思う。 人生何があるかわからないし、全てを仕事にコミットすることはできない場面も多い。(自他の病気、介護など)。 働く以外にもやりたいことはたくさんあって、どのことも楽しめる状態になるのがいいなと思う。 全身の仕事を半身にするにはどうすればいいんだろうね? 個人と組織の両軸の動きがないと半身社会の実現は難しいなぁと感じる。 個人が仕事を効率化して余暇を作り出そうとする動きと同時に、上司や組織がジョブスクリプションで定義されている以上の仕事を振らないという仕組みが必要そう。



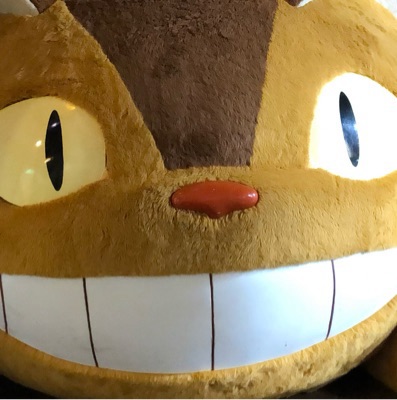
 Phoebe@Phoebe2025年8月28日読み終わった確か6月くらいに買ったと思うが、読み始めては寝落ちして間が空いてまた最初から…を何度も繰り返し、ようやく読み終わった自分自身そのものを指したようなタイトルだなと思う。 ざっくり書きすぎ?と思ったところもあったが、明治時代から現代まで、人々が読書とどう関わってきたかを概観できた。読書が修養なのか教養なのかの違い、戦前の社会学者が演劇・映画・寄席を「受動的な趣味」として読書をそこに含めていなかった話、2000年代末〜2010年代は労働をテーマにした小説が勃興したのに対し2010年代後半〜2020年代は「推し」の小説が脚光を浴びたという指摘、情報だけ欲しい人には読書で得られる知識はノイズになるという話…などが面白かった。
Phoebe@Phoebe2025年8月28日読み終わった確か6月くらいに買ったと思うが、読み始めては寝落ちして間が空いてまた最初から…を何度も繰り返し、ようやく読み終わった自分自身そのものを指したようなタイトルだなと思う。 ざっくり書きすぎ?と思ったところもあったが、明治時代から現代まで、人々が読書とどう関わってきたかを概観できた。読書が修養なのか教養なのかの違い、戦前の社会学者が演劇・映画・寄席を「受動的な趣味」として読書をそこに含めていなかった話、2000年代末〜2010年代は労働をテーマにした小説が勃興したのに対し2010年代後半〜2020年代は「推し」の小説が脚光を浴びたという指摘、情報だけ欲しい人には読書で得られる知識はノイズになるという話…などが面白かった。- ちゃび@cabin2025年8月19日読み終わったなぜなのか?という歴史を辿っていくのは超長くて、じゃあどうしたらいいのか?という部分はかなりあっさりしていた。 ラストに記載された、読むためのコツの部分はかなり端的。 新書を読んだのはとても久しぶりだったので、新書ってこんなに読みやすかったかなぁ。読みやすい文章でサクサク読めたので読書欲も満たされた。





 hifumii@higufumi2025年8月11日読み終わった飛ぶ鳥を落とす勢いの三宅香帆さん。題名が秀逸で、内容に沿った『労働と読書史』とかそんな題名だったら買ってなかった。なぜ読めないのかは自己の内面の問題ではなく、働きすぎでゆとりのない社会にあるという結論のため、なかなか個人の努力で変えていくのは難しそうだ。そうなるといいけど。読書にはノイズがあるというけど、ネット上にもいらない広告や不確かな情報が沢山あって、そっちの方が不快なノイズなのにだらだら見てしまうんですけど。やはり本を読んでいきたい。
hifumii@higufumi2025年8月11日読み終わった飛ぶ鳥を落とす勢いの三宅香帆さん。題名が秀逸で、内容に沿った『労働と読書史』とかそんな題名だったら買ってなかった。なぜ読めないのかは自己の内面の問題ではなく、働きすぎでゆとりのない社会にあるという結論のため、なかなか個人の努力で変えていくのは難しそうだ。そうなるといいけど。読書にはノイズがあるというけど、ネット上にもいらない広告や不確かな情報が沢山あって、そっちの方が不快なノイズなのにだらだら見てしまうんですけど。やはり本を読んでいきたい。

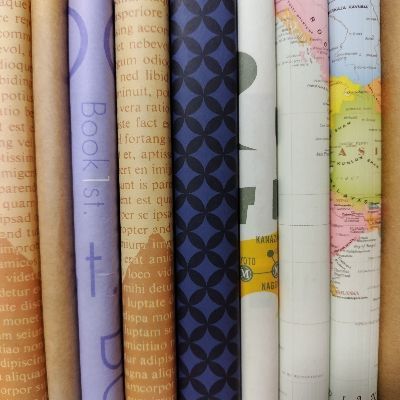 六輪花@rokurinka2025年8月8日読み始めた重要人文書だ、これは。 『問題は、読書という、偶然性に満ちたノイズありきの趣味を、私たちはどうやって楽しむことができるのか、というところにある。』208ページより。
六輪花@rokurinka2025年8月8日読み始めた重要人文書だ、これは。 『問題は、読書という、偶然性に満ちたノイズありきの趣味を、私たちはどうやって楽しむことができるのか、というところにある。』208ページより。
 MURDERBEAR@tb2025年6月28日読み終わった読書メモ読書日記@ 自宅オーディブルにて。 最近読書する余力がない。本を読むことは好きなのに。 こんな私に、あとがきは優しかった。 読書史的なことも書かれており、興味深かった。
MURDERBEAR@tb2025年6月28日読み終わった読書メモ読書日記@ 自宅オーディブルにて。 最近読書する余力がない。本を読むことは好きなのに。 こんな私に、あとがきは優しかった。 読書史的なことも書かれており、興味深かった。





- Nippa@xinkent2025年6月17日読み終わった読書は現代を生きる上でノイズである、だから読書ができない、というのはまさにだと思った。 働いていて時間がないから読書ができないのではなくて、仕事以外の文脈を取り込む余裕がない。確かに思い当たるなあ。 一方でそのノイズこそが人生を豊かにしてくれるものなので、読書は努力してでも続けたいと思った。




 3am_sp@3am_sp2025年5月29日読み終わった歴史を踏まえて、現代を見つめて、未来の社会を考える、とてもコンパクトで良い構成。「ノイズ」の話がとてもよく理解できた。オモコロ原宿さんがしきりに引用する「半身」の話もとても良かった。 あと「本を読みたいけど、労働によって読めなくなってしまった人たち」、つまりこの本の読者層のこともきっちり刺してきてすごかった。奴は本気だ。
3am_sp@3am_sp2025年5月29日読み終わった歴史を踏まえて、現代を見つめて、未来の社会を考える、とてもコンパクトで良い構成。「ノイズ」の話がとてもよく理解できた。オモコロ原宿さんがしきりに引用する「半身」の話もとても良かった。 あと「本を読みたいけど、労働によって読めなくなってしまった人たち」、つまりこの本の読者層のこともきっちり刺してきてすごかった。奴は本気だ。

- 英恵@natsurei2025年5月14日読み終わった結論と内容があまり噛み合ってないようにも感じたが、読書とは結論のための材料を知るだけでなく一見寄り道かもしれない内容を取り入れることこそ肝要なのだろう、と思わせてくれるような充実した内容だったと思う。
 陽奈@hina___2025年4月29日読み終わった@ 自宅タイトルみたとき、忙しい中で本を読むコツがわかるのかなと思い買ってみた。読んだら実はほとんどが日本における読書史で最後社会問題に繋がっていくという感じだった。予期せぬ文脈、これが“ノイズ”なのか、!!
陽奈@hina___2025年4月29日読み終わった@ 自宅タイトルみたとき、忙しい中で本を読むコツがわかるのかなと思い買ってみた。読んだら実はほとんどが日本における読書史で最後社会問題に繋がっていくという感じだった。予期せぬ文脈、これが“ノイズ”なのか、!!



 空色栞@reads_2025032025年4月16日聴き終わったaudible で再生済み。 全身全霊で働くのをやめよう。「半身」で働こう。 深く頷きながら聴いた。「あとがき」の中で本を読むコツを提案しているのでやってみよう。
空色栞@reads_2025032025年4月16日聴き終わったaudible で再生済み。 全身全霊で働くのをやめよう。「半身」で働こう。 深く頷きながら聴いた。「あとがき」の中で本を読むコツを提案しているのでやってみよう。




 はな@hana-hitsuji052025年4月16日まだ読んでる借りてきた読みながらこれいつかEテレとか真面目な取り上げ方で映像化みたいなのされそうだなと思った。 日本の歴史を追いながらその時代を生きた人たちとその頃そばにいた本たちのことを思い浮かべる。 『売れすぎである』の言葉に笑った。 この作者は本当に本が好きなんだな。
はな@hana-hitsuji052025年4月16日まだ読んでる借りてきた読みながらこれいつかEテレとか真面目な取り上げ方で映像化みたいなのされそうだなと思った。 日本の歴史を追いながらその時代を生きた人たちとその頃そばにいた本たちのことを思い浮かべる。 『売れすぎである』の言葉に笑った。 この作者は本当に本が好きなんだな。







 はな@hana-hitsuji052025年4月16日読み始めた借りてきた読書会で同じテーブルになった人から借りた! 読書することや本のことが本当に好きな人がこれを書いているのが伝わる文章。 読めない…どうして?を歴史から紐解いていく章はなんだかドラえもんのタイムマシンに乗った気分だし、引用で登場する本まで気になる。 今のところ石川啄木と句読点と明治時代が出現中。 面白い〜!!
はな@hana-hitsuji052025年4月16日読み始めた借りてきた読書会で同じテーブルになった人から借りた! 読書することや本のことが本当に好きな人がこれを書いているのが伝わる文章。 読めない…どうして?を歴史から紐解いていく章はなんだかドラえもんのタイムマシンに乗った気分だし、引用で登場する本まで気になる。 今のところ石川啄木と句読点と明治時代が出現中。 面白い〜!!




 塔海@__colza2025年4月15日読み終わった「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という問いを、明治時代から現代まで、ベストセラー本をもとに、階級や性別などの視座も入れながら読書傾向を追っている本で、読書を起点とした時代論としても面白かった。 「好き」を言語化する技術のさらっと読めてわかりやすい文体に比較して、かなり論文調の本でもある。おもしろいレポート読んでるみたいな気持ち。半身で働くを提言した本がここまで話題になり、多くの人の手に渡るというのは大きなことだと思う。 巻末尾の対比図、半身労働社会で男性中心からジェンダーフリーへ、というのが説明なく記載されているが、ここはちょっと乱暴な気もした……気もしたけど、男性中心社会だからこそ労働の仕組み自体が全身全霊になっている、の指摘がないから急な感じがしたのかも。(フェミニズムの文脈に入るので、今回の本ではそれこそノイズなのかもしれないが)男性中心社会と資本主義の共通性みたいなとこに触れてたらよかったかも。(似た言及はあったけど
塔海@__colza2025年4月15日読み終わった「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という問いを、明治時代から現代まで、ベストセラー本をもとに、階級や性別などの視座も入れながら読書傾向を追っている本で、読書を起点とした時代論としても面白かった。 「好き」を言語化する技術のさらっと読めてわかりやすい文体に比較して、かなり論文調の本でもある。おもしろいレポート読んでるみたいな気持ち。半身で働くを提言した本がここまで話題になり、多くの人の手に渡るというのは大きなことだと思う。 巻末尾の対比図、半身労働社会で男性中心からジェンダーフリーへ、というのが説明なく記載されているが、ここはちょっと乱暴な気もした……気もしたけど、男性中心社会だからこそ労働の仕組み自体が全身全霊になっている、の指摘がないから急な感じがしたのかも。(フェミニズムの文脈に入るので、今回の本ではそれこそノイズなのかもしれないが)男性中心社会と資本主義の共通性みたいなとこに触れてたらよかったかも。(似た言及はあったけど



 サカグチ@hisuissugi2025年3月27日読み置き働き始める前に読んでみる。 まだ読みかけだが、 「全身全霊で働いていると死ぬので、半身で働こう」的な論理展開になりそうなので楽しみ。 おれは多分読書も仕事の一部として定着させてしまう気がする。本当の余暇とは何なのか。
サカグチ@hisuissugi2025年3月27日読み置き働き始める前に読んでみる。 まだ読みかけだが、 「全身全霊で働いていると死ぬので、半身で働こう」的な論理展開になりそうなので楽しみ。 おれは多分読書も仕事の一部として定着させてしまう気がする。本当の余暇とは何なのか。






- ショア@tresor1352025年3月20日読み終わった多忙で読書量が減っているため本書を手に取る。読書とは他者の文脈を受け入れるものであるため余裕がない状況では自分に直接的ではない文脈をノイズとして受け入れられなくなる。結果、知りたいこと興味にストレートなSNSなどに流れてしまう。資本主義消費社会による右肩上がり成長で全身全霊の仕事スタイルを社会全体で見直すべきという主張は大いに賛同。読書ができない状態は周りを見渡す余裕がない状態を示すバロメーター。本書の半分は近代のベストセラー分析だがそこを楽しめていない時点で余裕はなくなっているのだろう。休もう


 ✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年2月17日読み終わった労働と本の歴史がとてもわかりやすくて全部面白いのだけれど、9章と最終章が本当に素晴らしかった。読んでないけど興味はあるけど本読む元気ない人は、とりあえず9章と最終章だけでも読んでほしい。
✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年2月17日読み終わった労働と本の歴史がとてもわかりやすくて全部面白いのだけれど、9章と最終章が本当に素晴らしかった。読んでないけど興味はあるけど本読む元気ない人は、とりあえず9章と最終章だけでも読んでほしい。
 じむじむ@testjmjm2024年5月29日読み終わった★★☆正直タイトルに関する話とは内容がだいぶ異なっている感は否めない。 愛社精神がどうこうも実際のエンゲージメントとかは日本は他国に比べてだいぶ低くでたりするのも知っていたので、そのへんも胡乱 読み物としてはまずまず
じむじむ@testjmjm2024年5月29日読み終わった★★☆正直タイトルに関する話とは内容がだいぶ異なっている感は否めない。 愛社精神がどうこうも実際のエンゲージメントとかは日本は他国に比べてだいぶ低くでたりするのも知っていたので、そのへんも胡乱 読み物としてはまずまず