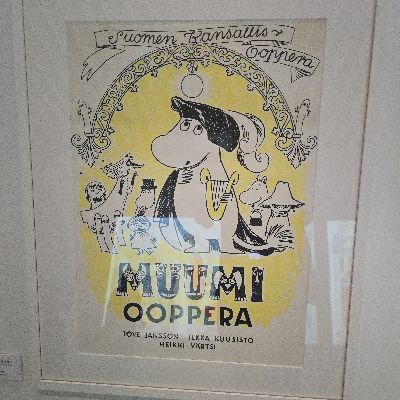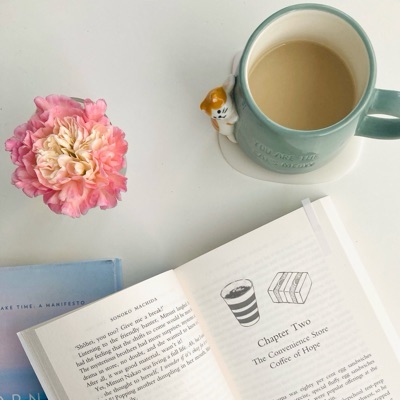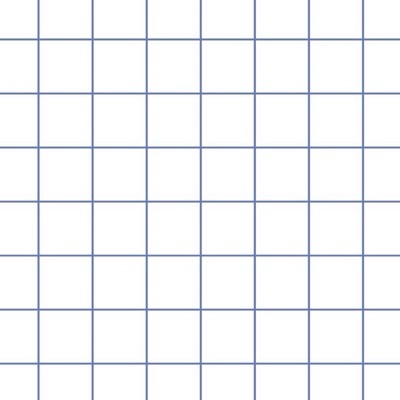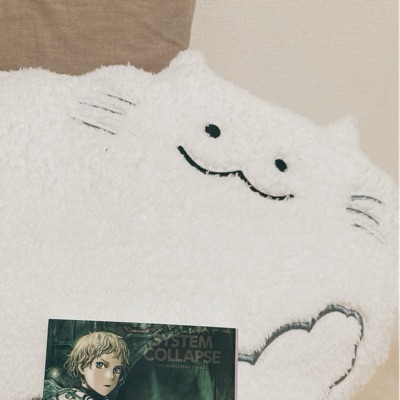世界は私たちのために作られていない

94件の記録
 よみ@lesen_buecher2026年2月9日読み終わった借りてきたASDの当事者がいかに疲弊し、傷つきながら生きているか、それはどのようなメカニズムで発生しているのかを一当事者の事例として詳細に記している。 基礎的な事前知識を持っていたせいか分からないが、軽快で読みやすい文章。 ASDの要素を持っていれば、この世の中で生きづらくても当然か、と少し肩の力が落ちるような本だと思う。
よみ@lesen_buecher2026年2月9日読み終わった借りてきたASDの当事者がいかに疲弊し、傷つきながら生きているか、それはどのようなメカニズムで発生しているのかを一当事者の事例として詳細に記している。 基礎的な事前知識を持っていたせいか分からないが、軽快で読みやすい文章。 ASDの要素を持っていれば、この世の中で生きづらくても当然か、と少し肩の力が落ちるような本だと思う。


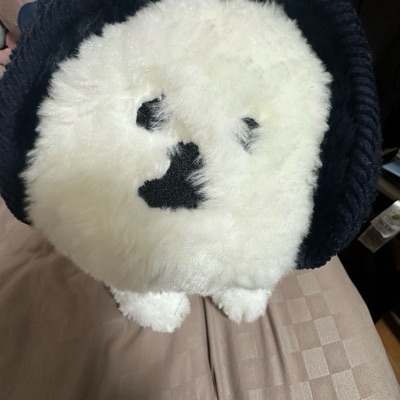
 よみ@lesen_buecher2026年2月2日読み始めた借りてきた東田直樹さんの著書を読んで、別の方の話も読んでみたくなったため読み始めた。 英語圏でも暗示によって欲求を伝えるコミュニケーションがあるのには驚いた。
よみ@lesen_buecher2026年2月2日読み始めた借りてきた東田直樹さんの著書を読んで、別の方の話も読んでみたくなったため読み始めた。 英語圏でも暗示によって欲求を伝えるコミュニケーションがあるのには驚いた。

 植月 のぞみ@nozomi_uetsuki_r4102025年11月16日読んでる@ 自宅積読になっていたこの本を今日から再び読み始めている。 わたしはASD(自閉スペクトラム)当事者なので、この本を読むと「そうそう!」と共感する。 世界や日本のASD当事者を励ます本であり、ASD当事者が、現代社会からいかに爪弾きされているかがわかる本。
植月 のぞみ@nozomi_uetsuki_r4102025年11月16日読んでる@ 自宅積読になっていたこの本を今日から再び読み始めている。 わたしはASD(自閉スペクトラム)当事者なので、この本を読むと「そうそう!」と共感する。 世界や日本のASD当事者を励ます本であり、ASD当事者が、現代社会からいかに爪弾きされているかがわかる本。







 かにょ@reads_kanyo2025年11月2日読み終わった@ 自宅ASDの著者が書いた本の中で初めて読み切れた。 著者の体験や語りにときに頷き、ときに首を傾げたが、自閉スペクトラムは一般化されるものではないので当たり前と言えるだろう。 ASD者として生きるうえでのつらさを語ってくれる友人のような本だった。 しばしば混ざるジョークもとても魅力的だ。 良書。
かにょ@reads_kanyo2025年11月2日読み終わった@ 自宅ASDの著者が書いた本の中で初めて読み切れた。 著者の体験や語りにときに頷き、ときに首を傾げたが、自閉スペクトラムは一般化されるものではないので当たり前と言えるだろう。 ASD者として生きるうえでのつらさを語ってくれる友人のような本だった。 しばしば混ざるジョークもとても魅力的だ。 良書。





 445@00labo2025年10月22日読み終わった著者のことあんまり調べないで読んだらツイッタラー(死語)だった。 とにかくASD者が生きていくにあたりこの世界がいかに大変かと言うのを、良くて小さじいっぱいくらいのユーモアを添えるのみで吶々と語っていくので途中で気が滅入ってしまった。 ただ二次障害で大変なところまで行った人だし、茶化さずにその痛切さを訴えるのは大事なことだから、その辺は読み手の自分が調整するしかなかろうと途中でギアチェンジして読み切り。 結果としてツイッタラーの書いた本だし、正しい付き合い方だったかもしれない。 世界がASD者のために作られていないって言うのはその通りで、そもそもASD者が世界を積極的に作る側にいない(入れない)から対象から漏れてるし、その上ASD者が「守られている」感覚は現状の社会が提供してるものとはズレてるから噛み合わないんだろうね。 わかるわかるーとあんまわかんないーと言うところがあったけど後半に出てくる運転の話は、同じこと考えてる人初めて見た!と嬉しくなった。 > 生活の他の領域におけるコミュニケーションとの差異は、運転の世界でも無縁ではない。 他の人が路上でどう言う挙動になるかわからないから、危機感を保つために剥き出しで、何かあっても対応できるように機動力が比較的高いバイクに乗っているわたし。 一般車で法定速度を守るのが皆無な日本の路上は本当にクレイジーだと思ってる。 複雑でややこしい世界に疲弊して、単純なロジックを振り翳す集団に取り込まれやすいと言うのは切ない話だよ。 その辺を踏まえるとマスキングの精度を上げるとかよりも、曖昧なものを曖昧に持ち続ける、曖昧さ耐性をつける訓練をすると自分の人生にはいいのかなーという気がする。
445@00labo2025年10月22日読み終わった著者のことあんまり調べないで読んだらツイッタラー(死語)だった。 とにかくASD者が生きていくにあたりこの世界がいかに大変かと言うのを、良くて小さじいっぱいくらいのユーモアを添えるのみで吶々と語っていくので途中で気が滅入ってしまった。 ただ二次障害で大変なところまで行った人だし、茶化さずにその痛切さを訴えるのは大事なことだから、その辺は読み手の自分が調整するしかなかろうと途中でギアチェンジして読み切り。 結果としてツイッタラーの書いた本だし、正しい付き合い方だったかもしれない。 世界がASD者のために作られていないって言うのはその通りで、そもそもASD者が世界を積極的に作る側にいない(入れない)から対象から漏れてるし、その上ASD者が「守られている」感覚は現状の社会が提供してるものとはズレてるから噛み合わないんだろうね。 わかるわかるーとあんまわかんないーと言うところがあったけど後半に出てくる運転の話は、同じこと考えてる人初めて見た!と嬉しくなった。 > 生活の他の領域におけるコミュニケーションとの差異は、運転の世界でも無縁ではない。 他の人が路上でどう言う挙動になるかわからないから、危機感を保つために剥き出しで、何かあっても対応できるように機動力が比較的高いバイクに乗っているわたし。 一般車で法定速度を守るのが皆無な日本の路上は本当にクレイジーだと思ってる。 複雑でややこしい世界に疲弊して、単純なロジックを振り翳す集団に取り込まれやすいと言うのは切ない話だよ。 その辺を踏まえるとマスキングの精度を上げるとかよりも、曖昧なものを曖昧に持ち続ける、曖昧さ耐性をつける訓練をすると自分の人生にはいいのかなーという気がする。


 445@00labo2025年10月22日読んでる作者の訴え方がめちゃくちゃ悲痛で、真面目に読んでると気落ちしてどうにもならなくなったので、さらさら読んでいくことにした。 多分、考えることに過度にリソースを割きすぎてしまう個体、なのが社会で足を引っ張るんじゃないかなあ。 更にその考えは外界と共有可能な言語を用いて行われているとも限らず、どこから、何を、どのように外界に発するのかも定まらず、みたいな。 読みながら棋士の羽生さんの本の内容を思い出した。 棋士は序盤では展開をなんて先まで読んで、なんてことはせず、ある程度のところまでは経験からくる「大体このへん」という感覚で指し進めていくそうな。で、展開が絞れてきてから先の先まで読み進め始めると。 脳みそのリソースは有限なんだから、確かにそうするのが合理的に見える。 多分ASD者は最初っから何手先まで読む行為を、普段の生活の些細なことでもしてしまいがちなんだろうね。それで他の人とテンポがズレるし、すぐキャパオーバーにもなってしまう。 別にこの世界が定型発達のために作られているとも思わないし、単純に、作ってる参加者に定型発達が多くてコンセンサス取りやすいところで決めていったらこうなっただけなんだろうとも考えてるけど、結局そのフワッとしたコンセンサスの皺寄せがASD者に直撃(と自覚がないのかもだけど定型発達自身にも)しているから、やってらんねーやってことは山のようにありますわな。
445@00labo2025年10月22日読んでる作者の訴え方がめちゃくちゃ悲痛で、真面目に読んでると気落ちしてどうにもならなくなったので、さらさら読んでいくことにした。 多分、考えることに過度にリソースを割きすぎてしまう個体、なのが社会で足を引っ張るんじゃないかなあ。 更にその考えは外界と共有可能な言語を用いて行われているとも限らず、どこから、何を、どのように外界に発するのかも定まらず、みたいな。 読みながら棋士の羽生さんの本の内容を思い出した。 棋士は序盤では展開をなんて先まで読んで、なんてことはせず、ある程度のところまでは経験からくる「大体このへん」という感覚で指し進めていくそうな。で、展開が絞れてきてから先の先まで読み進め始めると。 脳みそのリソースは有限なんだから、確かにそうするのが合理的に見える。 多分ASD者は最初っから何手先まで読む行為を、普段の生活の些細なことでもしてしまいがちなんだろうね。それで他の人とテンポがズレるし、すぐキャパオーバーにもなってしまう。 別にこの世界が定型発達のために作られているとも思わないし、単純に、作ってる参加者に定型発達が多くてコンセンサス取りやすいところで決めていったらこうなっただけなんだろうとも考えてるけど、結局そのフワッとしたコンセンサスの皺寄せがASD者に直撃(と自覚がないのかもだけど定型発達自身にも)しているから、やってらんねーやってことは山のようにありますわな。

 445@00labo2025年10月21日読み始めた小さく区切られた社会の中に存在すると、人狼ゲームの人狼をやっている気持ちになる。 積極的にそうしてるわけではないのだけど、普通にしているとうっかり一晩ひとりのペースで噛んでしまう、そう言う生き物だと自分のことを認識している。 アオーン。 世界を革命する力は残念ながらないので、自分たちのために作られていない世界を各人どうサバイブしているのか知りたい。
445@00labo2025年10月21日読み始めた小さく区切られた社会の中に存在すると、人狼ゲームの人狼をやっている気持ちになる。 積極的にそうしてるわけではないのだけど、普通にしているとうっかり一晩ひとりのペースで噛んでしまう、そう言う生き物だと自分のことを認識している。 アオーン。 世界を革命する力は残念ながらないので、自分たちのために作られていない世界を各人どうサバイブしているのか知りたい。





 このあいだ@choge592025年10月9日読んでる借りてきた精神科でASD傾向ありと診断されている。 「これASDだったのか!」と理解することが多数! 誰かに水をもらえないかと頼むくらいなら、喉が渇いて死んだほうがましである。 わかる!! 電話が苦手な理由をイマイチ言語化できてなかったけど、初めて言葉にしてもらった。
このあいだ@choge592025年10月9日読んでる借りてきた精神科でASD傾向ありと診断されている。 「これASDだったのか!」と理解することが多数! 誰かに水をもらえないかと頼むくらいなら、喉が渇いて死んだほうがましである。 わかる!! 電話が苦手な理由をイマイチ言語化できてなかったけど、初めて言葉にしてもらった。


 ばぶちゃん@babuchan2025年9月14日読み終わった借りてきた@ 自宅始めはふむふむと読んでいたけど、だんだん長いな…ちょっとしつこいな…と思い飛ばしながら読み終えた。 「自閉スペクトラム症の人たちが生きる新しい世界」の方が実践的で私は好き。 どちらも同じ訳者の方で、どちらも読みやすい! 特性は様々なので当たり前だけど、当てはまることもあれば全然当てはまらないことも多くて、「これをASDのほとんどが〜」と言うのは強すぎるのでは、と疑問を抱く部分も多かった。 例えば「人との身体接触はよほど親密な人以外はすごく嫌:関係性の薄い人との身体接触は確かに嫌だけど親しい人むしろ安心するし好きなのでこの書き方ほどの拒否感ではないな」、「空の旅はASDにとって苦痛(旅行自体良さがわからないみたいなことも書かれていた):海外文化も海外旅行も飛行機も好き。飛行機の苦手な部分はあるけど好きなことなのでなんとか乗り切っている」など。本当に人それぞれ違うし、いわゆるステレオタイプには重ならない人は山ほどいるんだろうな〜と思う。
ばぶちゃん@babuchan2025年9月14日読み終わった借りてきた@ 自宅始めはふむふむと読んでいたけど、だんだん長いな…ちょっとしつこいな…と思い飛ばしながら読み終えた。 「自閉スペクトラム症の人たちが生きる新しい世界」の方が実践的で私は好き。 どちらも同じ訳者の方で、どちらも読みやすい! 特性は様々なので当たり前だけど、当てはまることもあれば全然当てはまらないことも多くて、「これをASDのほとんどが〜」と言うのは強すぎるのでは、と疑問を抱く部分も多かった。 例えば「人との身体接触はよほど親密な人以外はすごく嫌:関係性の薄い人との身体接触は確かに嫌だけど親しい人むしろ安心するし好きなのでこの書き方ほどの拒否感ではないな」、「空の旅はASDにとって苦痛(旅行自体良さがわからないみたいなことも書かれていた):海外文化も海外旅行も飛行機も好き。飛行機の苦手な部分はあるけど好きなことなのでなんとか乗り切っている」など。本当に人それぞれ違うし、いわゆるステレオタイプには重ならない人は山ほどいるんだろうな〜と思う。
 いくら@unagi_oishiiyo2025年9月12日挫折著者にとってのASDあるあるを羅列しているな〜という印象。 いかに世界は生きづらく、学校は過ごしづらく、会社には馴染めないか、というような内容。 ASDに対する理解を深めるための本と書いてあるが、この内容だと健常者とASDの相互理解よりは健常者批判だろ……と思った。読み切れず、挫折。
いくら@unagi_oishiiyo2025年9月12日挫折著者にとってのASDあるあるを羅列しているな〜という印象。 いかに世界は生きづらく、学校は過ごしづらく、会社には馴染めないか、というような内容。 ASDに対する理解を深めるための本と書いてあるが、この内容だと健常者とASDの相互理解よりは健常者批判だろ……と思った。読み切れず、挫折。
 Hoshiduru@lilimoe2025年9月9日読み終わった私は自分がどう適応するか〜っていうのを知りたかった気がするからそこまでfor meな内容では無いんだけれど、ここまで内面の働きをじっくり言語化されると気持ちがいいな〜!というのがいちばんの感想!
Hoshiduru@lilimoe2025年9月9日読み終わった私は自分がどう適応するか〜っていうのを知りたかった気がするからそこまでfor meな内容では無いんだけれど、ここまで内面の働きをじっくり言語化されると気持ちがいいな〜!というのがいちばんの感想!



 Hoshiduru@lilimoe2025年9月9日読んでる「仮に面接で『5年後の自分はどうなっていると思いますか』と聞かれたら、『生きてたらいいんですけどね』としか答えようがない。」←同じことやったことあるので、ひゃ〜〜となった(ASDというよりADHDの特徴として解釈されてるけど)
Hoshiduru@lilimoe2025年9月9日読んでる「仮に面接で『5年後の自分はどうなっていると思いますか』と聞かれたら、『生きてたらいいんですけどね』としか答えようがない。」←同じことやったことあるので、ひゃ〜〜となった(ASDというよりADHDの特徴として解釈されてるけど)

 amy@note_15812025年8月23日読み終わった感想ASDここ1年ぐらいうっすらASDの気があるのかもしれないと思いつつ、ASDに関する本は対処法とか、すでに診断を受けている人向けが多いように思われて、読みたくなる本がなかったので何となくそのまま過ごしてきてしまった 読んでみて、著者の日々の"困りごと"にわかるわかると頷いたのでやっぱり私にはASDの特性が出ている部分があるのだと思う 著者も言っているけれど学校の先生たちや企業の人たちにも読んでほしい。まあ本邦では読んでもらったところで、余計にASDの方たちがめんどくさいものとされ、煙たがられる様子しか想像できないけれど 自分の社会に対する感覚を紐解いていて、身近な人に該当者がいたり、自分自身がそうなのではと考えている人にとっては良い本だと思う
amy@note_15812025年8月23日読み終わった感想ASDここ1年ぐらいうっすらASDの気があるのかもしれないと思いつつ、ASDに関する本は対処法とか、すでに診断を受けている人向けが多いように思われて、読みたくなる本がなかったので何となくそのまま過ごしてきてしまった 読んでみて、著者の日々の"困りごと"にわかるわかると頷いたのでやっぱり私にはASDの特性が出ている部分があるのだと思う 著者も言っているけれど学校の先生たちや企業の人たちにも読んでほしい。まあ本邦では読んでもらったところで、余計にASDの方たちがめんどくさいものとされ、煙たがられる様子しか想像できないけれど 自分の社会に対する感覚を紐解いていて、身近な人に該当者がいたり、自分自身がそうなのではと考えている人にとっては良い本だと思う
 vocalise@vocalise_0072025年8月10日読み終わった書評を見て手に取った本。失敗した場面をしつこく脳内再生し続けて眠れない日が続くのは、自分のくよくよしがちな性格に由来があるのかと思っていたら、障害由来かもしれないと分かって少し勇気が出た。傾向を知って工夫することで、自信をなくしがちな日々の生活を改善したい。
vocalise@vocalise_0072025年8月10日読み終わった書評を見て手に取った本。失敗した場面をしつこく脳内再生し続けて眠れない日が続くのは、自分のくよくよしがちな性格に由来があるのかと思っていたら、障害由来かもしれないと分かって少し勇気が出た。傾向を知って工夫することで、自信をなくしがちな日々の生活を改善したい。


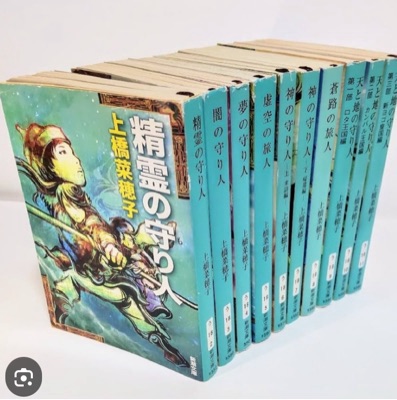



- じゅんぺい@jump2025年8月3日読み終わった驚いた。 これまで生きづらいなと感じることがよくあったけど、あまりに自分が普段抱えている悩みや感じ方と同じことが書いてある。 確かに私は仮面を被っている。



- paindrop@paindrop1900年1月1日読み終わったASDの困り感などがよく言語化されてまとまっていて、当事者としてはとても共感できる。ただ、アドボカシーとしての読み物の面が強くて、そういう目的で書かれているとはいえ、社会へ改善や変革を強く要求する論調が、少ししんどくもあった。