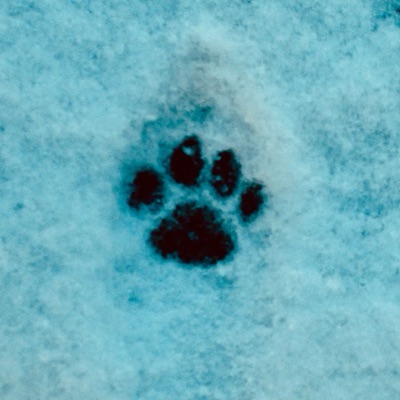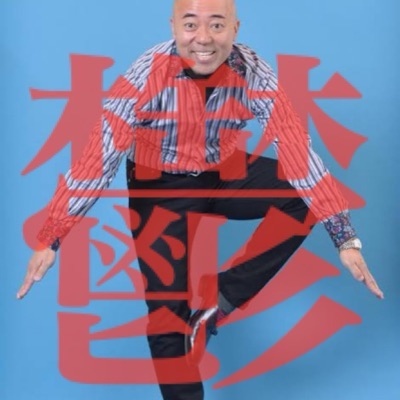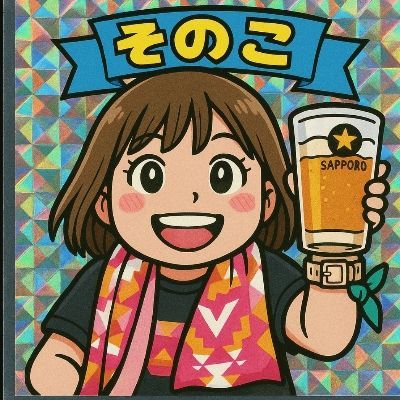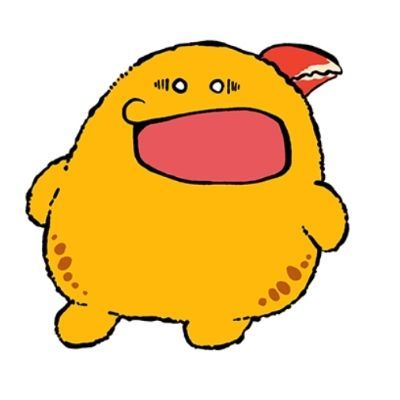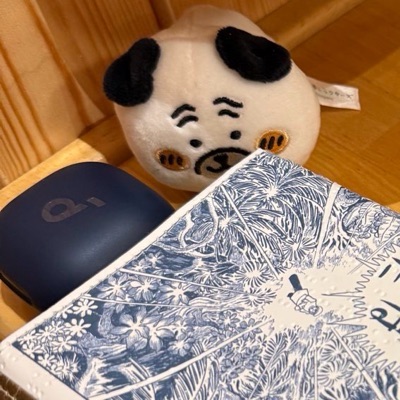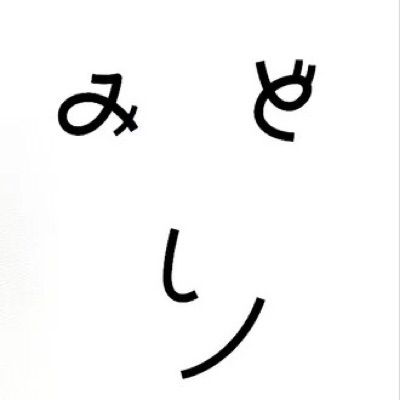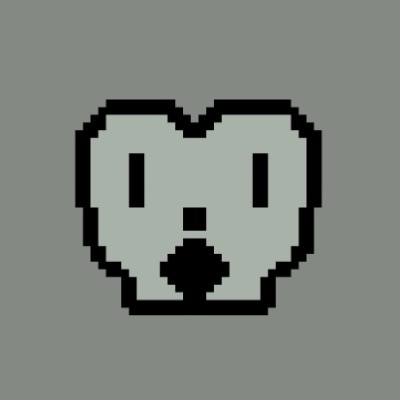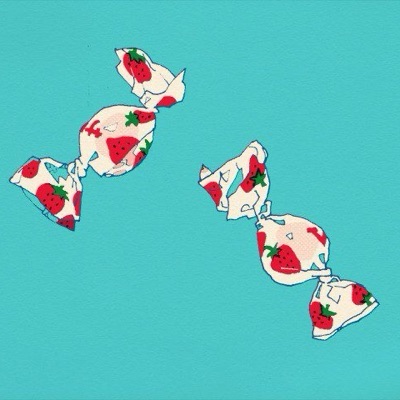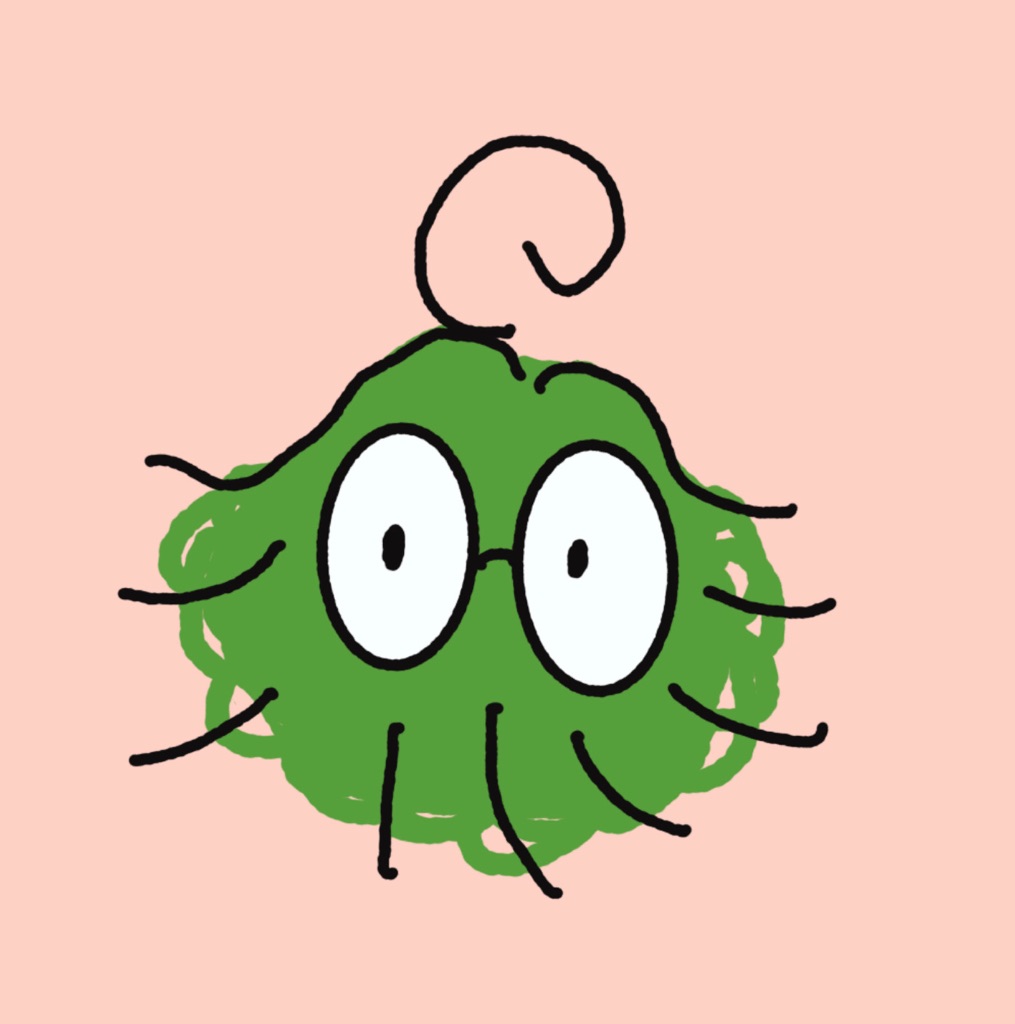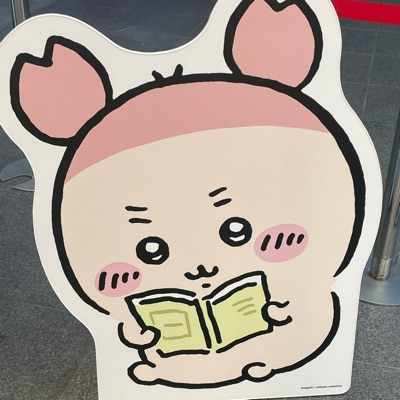ネット怪談の民俗学

140件の記録
 むらさき@mamimu_0122026年2月23日読み終わった民俗学の立場から「ネット怪談」の歴史を四半世紀にわたって俯瞰し、整理した一冊。 『変な家』や『近畿地方のある場所について』を読んで、令和ホラーブームの元ネタを知りたくて手に取りました。先の小説のみならず、SCPや「8番出口」など、最近の流行の源流がここにあったのかと面白く読みました。 「怪談(伝説)」と「ホラー(創作)」を分けて考えたことがない初心者でしたが、おかげで解像度が上がった気がします。本書で言及されていた『ジャパン・ホラーの現在地』にも興味が湧きました。
むらさき@mamimu_0122026年2月23日読み終わった民俗学の立場から「ネット怪談」の歴史を四半世紀にわたって俯瞰し、整理した一冊。 『変な家』や『近畿地方のある場所について』を読んで、令和ホラーブームの元ネタを知りたくて手に取りました。先の小説のみならず、SCPや「8番出口」など、最近の流行の源流がここにあったのかと面白く読みました。 「怪談(伝説)」と「ホラー(創作)」を分けて考えたことがない初心者でしたが、おかげで解像度が上がった気がします。本書で言及されていた『ジャパン・ホラーの現在地』にも興味が湧きました。 乖離@karu2026年2月11日読み終わった私は、ネット怪談はまとめサイトで知り、それらの文脈を踏まえた二次創作を読み、最近はショート動画でリミナルスペース画像を浴びるという生活をしている。 本書は、ネット怪談が黎明期から今日に至るまで、テクノロジーやメディアに応じてどのように変化し伝播してきたのかを(おそらくかなり)網羅的に紹介している。 私自身、多少はリアルタイムでネット怪談が伝播するさまを体感していた筈だが、今は無きまとめサイトの魚拓など取っていないし、試しに十年ほど前にブックマークしたホラー作品を遡ってみると多くは非公開か削除されていた。 民俗学という学問の営為をありありと体感できる本だった。 「こういう話、ことがあったはず」という覚えはうっすらとあるのに、ネットのアーカイブも人の記憶も、多くの人が覚えた恐怖という感情もとても儚い。 インターネット老人会の儚い記憶を記録することも、いつか価値を持つかもしれないと思った。
乖離@karu2026年2月11日読み終わった私は、ネット怪談はまとめサイトで知り、それらの文脈を踏まえた二次創作を読み、最近はショート動画でリミナルスペース画像を浴びるという生活をしている。 本書は、ネット怪談が黎明期から今日に至るまで、テクノロジーやメディアに応じてどのように変化し伝播してきたのかを(おそらくかなり)網羅的に紹介している。 私自身、多少はリアルタイムでネット怪談が伝播するさまを体感していた筈だが、今は無きまとめサイトの魚拓など取っていないし、試しに十年ほど前にブックマークしたホラー作品を遡ってみると多くは非公開か削除されていた。 民俗学という学問の営為をありありと体感できる本だった。 「こういう話、ことがあったはず」という覚えはうっすらとあるのに、ネットのアーカイブも人の記憶も、多くの人が覚えた恐怖という感情もとても儚い。 インターネット老人会の儚い記憶を記録することも、いつか価値を持つかもしれないと思った。

- パワースポット好きな旅人@blue1232026年1月30日読み終わった@ 自宅ネットの進化に合わせて、怪談の表現も多様になって凄いね!って思いまた。 昔は掲示板で文字だけが、画像が簡単にアップできるようになれば画像で表現を、YouTubeみたいに動画が簡単にアップできるようになれば動画で、またプラットフォームでの表現とか。進化する怪談技法!
 ランタナ@lantana262026年1月20日読み終わったくねくね、きさらぎ駅など有名なものから、ろっぽんぞーという今では著者の記憶にしかないものまで紹介されている。ネットの書き込みについて初出を特定するのは難しいが可能な限りで調べていたり、田舎の因習については差別的なイメージがあると指摘するなど、丁寧でよかった。
ランタナ@lantana262026年1月20日読み終わったくねくね、きさらぎ駅など有名なものから、ろっぽんぞーという今では著者の記憶にしかないものまで紹介されている。ネットの書き込みについて初出を特定するのは難しいが可能な限りで調べていたり、田舎の因習については差別的なイメージがあると指摘するなど、丁寧でよかった。




- ムジカペッコリーノ@musica1302026年1月11日読み終わった筆者は真面目な研究者なんだけど、2ちゃんに入り浸っていた人なんだということがひしひしと伝わってくる本だった。(「そうだけど、そうじゃないんだよなァ〜〜」ということがなく、流れを把握し、空気感込みで伝えてくれている) いずれVR怪談についても書いていただきたい。


 ぱち@suwa_deer2025年12月8日読み終わったぼくは怖いのが苦手で知識が全くないまま読み進めたのだけど、ざっくりとネット怪談の変遷と事例を知れたのがまず良かった。 それと、怖いものを求める人のことというかその気持ちがこれまで全然想像できなかったのだけども、ネット怪談の投稿にレスしたり実際に現地に行ってそれを報告する人が出てきたりと、肝試し的なちょっと危険な遊びを楽しむような感覚でネット怪談を楽しんでいるんだろうなというのが少し分かってそれも良かった。 因習村系から世界系的なホラーへのシフトが現代社会の価値観を反映しているのではという指摘も面白かった。
ぱち@suwa_deer2025年12月8日読み終わったぼくは怖いのが苦手で知識が全くないまま読み進めたのだけど、ざっくりとネット怪談の変遷と事例を知れたのがまず良かった。 それと、怖いものを求める人のことというかその気持ちがこれまで全然想像できなかったのだけども、ネット怪談の投稿にレスしたり実際に現地に行ってそれを報告する人が出てきたりと、肝試し的なちょっと危険な遊びを楽しむような感覚でネット怪談を楽しんでいるんだろうなというのが少し分かってそれも良かった。 因習村系から世界系的なホラーへのシフトが現代社会の価値観を反映しているのではという指摘も面白かった。

 夜永@gooska_pi_2025年9月21日読み終わったインターネットでお馴染みの怪談や、その広まりの変遷を俯瞰する内容。 インターネットに浸かって生きてきた人間なので、多くの怪談やミームを見てきたけれど、その流布の背景に目をつけたことはなく、面白く読めた。 学生の頃や社会に出てすぐの頃は小説ばかり読んでいたけれど、それ以外のジャンルも読んでみようとしてる今日この頃。 最近は美術と民俗学に興味がある。
夜永@gooska_pi_2025年9月21日読み終わったインターネットでお馴染みの怪談や、その広まりの変遷を俯瞰する内容。 インターネットに浸かって生きてきた人間なので、多くの怪談やミームを見てきたけれど、その流布の背景に目をつけたことはなく、面白く読めた。 学生の頃や社会に出てすぐの頃は小説ばかり読んでいたけれど、それ以外のジャンルも読んでみようとしてる今日この頃。 最近は美術と民俗学に興味がある。 yomitaos@chsy71882025年9月3日読み終わった@ 自宅世代的には、コトリバコやきさらぎ駅のようなネット怪談にたっぷり浸かっていてもおかしくない年齢だが、一切触れることのないままここまで生きてきた。2ちゃんねるやそれをまとめたブログの類を嫌悪していたため、意図的に避けていた節もある。 それでもこの本を手に取ったのは、逆行的オステンションという概念との関わりについて、民俗学的観点から専門家が解説している点に興味を惹かれたからだ。 逆行的オステンションとはフォークホラーの概念の一つで、もともと伝説や根拠がないものに対して、意図的に情報(写真、体験談、噂など)を発信し、あたかも古くから存在したかのように見せかけるプロセス。 伝統や慣習を背景にした因習ものが多かったネット黎明期から、異世界ものへと移り変わっている現代への流れを丁寧に解説されており、著者がネット怪談の見取り図をつくると述べていただけあって、これは学術的にも意義のある本だと思う。 ある種、こういった情報不確かな物事を物語化してしまって処理するのが人間というものなので、情報の受容史としても読み解けるのではないか。
yomitaos@chsy71882025年9月3日読み終わった@ 自宅世代的には、コトリバコやきさらぎ駅のようなネット怪談にたっぷり浸かっていてもおかしくない年齢だが、一切触れることのないままここまで生きてきた。2ちゃんねるやそれをまとめたブログの類を嫌悪していたため、意図的に避けていた節もある。 それでもこの本を手に取ったのは、逆行的オステンションという概念との関わりについて、民俗学的観点から専門家が解説している点に興味を惹かれたからだ。 逆行的オステンションとはフォークホラーの概念の一つで、もともと伝説や根拠がないものに対して、意図的に情報(写真、体験談、噂など)を発信し、あたかも古くから存在したかのように見せかけるプロセス。 伝統や慣習を背景にした因習ものが多かったネット黎明期から、異世界ものへと移り変わっている現代への流れを丁寧に解説されており、著者がネット怪談の見取り図をつくると述べていただけあって、これは学術的にも意義のある本だと思う。 ある種、こういった情報不確かな物事を物語化してしまって処理するのが人間というものなので、情報の受容史としても読み解けるのではないか。
 ゆき@yuki10242025年8月23日読み終わったホラーと差別は密接な問題としてよく語られているけれど、恥ずかしながら私はその問題に対する解像度が低かった。 この本のp.89〜辺りで澤村伊智氏が指摘しているように、長らくネット怪談・ホラーで人気だった「因習村」などのジャンルが田舎に対する謂れのない差別に繋がる、という視点は目から鱗だった。 そういった視点を持ったうえで怪談・ホラー作品を思い返すと、地方、病気、障害、宗教など、差別を助長する懸念なく楽しめるホラー作品は大概少ないのではないかと思えてくる。 昨今のネット怪談・ホラーからは、ナラティブが欠落しつつあるという記述もあったけれど、差別を助長せず人々を惹きつけるような怖いナラティブを構築するのって、格段に難しいように思える…ゆえに、ナラティブのないホラーが流行ったりするのであろうか…。
ゆき@yuki10242025年8月23日読み終わったホラーと差別は密接な問題としてよく語られているけれど、恥ずかしながら私はその問題に対する解像度が低かった。 この本のp.89〜辺りで澤村伊智氏が指摘しているように、長らくネット怪談・ホラーで人気だった「因習村」などのジャンルが田舎に対する謂れのない差別に繋がる、という視点は目から鱗だった。 そういった視点を持ったうえで怪談・ホラー作品を思い返すと、地方、病気、障害、宗教など、差別を助長する懸念なく楽しめるホラー作品は大概少ないのではないかと思えてくる。 昨今のネット怪談・ホラーからは、ナラティブが欠落しつつあるという記述もあったけれど、差別を助長せず人々を惹きつけるような怖いナラティブを構築するのって、格段に難しいように思える…ゆえに、ナラティブのないホラーが流行ったりするのであろうか…。
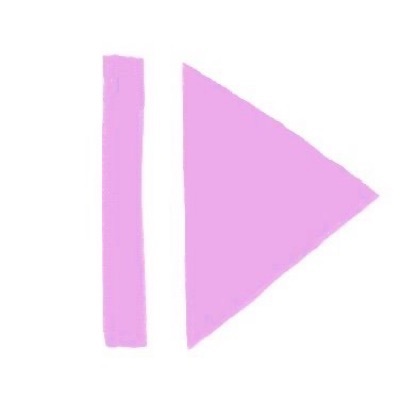




 数奇@suuqi2025年7月31日読み終わったインターネットの進化に合わせてネット怪談がどのように変化していったかが体系的に解説されていてとても面白かった。インターネット老人である自分としては「懐かしいなあ」という気持ちでも単純に楽しめるし、海外ミームなどの知らない情報に関しても「そんなことがあったんだ……」と興味深く読むことができた。全く知識がない人でも楽しめると思うが、逆にとても詳しい人からすると目新しさはないのかもしれない。読みやすいのでサクッと読めるが、ネットの発展によって怪談からナラティブが欠落していくという視点はかなり鋭く、興味深い。
数奇@suuqi2025年7月31日読み終わったインターネットの進化に合わせてネット怪談がどのように変化していったかが体系的に解説されていてとても面白かった。インターネット老人である自分としては「懐かしいなあ」という気持ちでも単純に楽しめるし、海外ミームなどの知らない情報に関しても「そんなことがあったんだ……」と興味深く読むことができた。全く知識がない人でも楽しめると思うが、逆にとても詳しい人からすると目新しさはないのかもしれない。読みやすいのでサクッと読めるが、ネットの発展によって怪談からナラティブが欠落していくという視点はかなり鋭く、興味深い。



 ( ˘ω˘ )@nnn2025年7月26日読み終わった都市伝説解体センターで脳を焼かれたものの、元ネタを結構知らなかったのでこれは読まねばと。他の方も書いてるけど、次のページになんか…怖そうな画像ある…と怯えながら(パラパラめくったときにガッツリ見ちゃってヒンッ‼︎てなった)読了。時代と共に媒体も系統も移り変わっていくの面白いねぇ
( ˘ω˘ )@nnn2025年7月26日読み終わった都市伝説解体センターで脳を焼かれたものの、元ネタを結構知らなかったのでこれは読まねばと。他の方も書いてるけど、次のページになんか…怖そうな画像ある…と怯えながら(パラパラめくったときにガッツリ見ちゃってヒンッ‼︎てなった)読了。時代と共に媒体も系統も移り変わっていくの面白いねぇ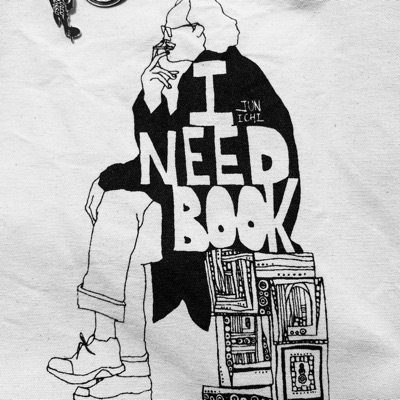 ゆかこ@crosscounter_ubk2025年7月26日読み終わった図書館本ネット怪談をあらゆる角度から考察、検証した本。 なるほど、面白い。ネット怪談はどのようにして話が出来て語り継がれていくのか。伝えていくだけでなく、共同で構築していくことがポイントなのだなと。 海外のネット怪談話もあって聞いたことない話や、名前だけ知ってるような話の出自や経緯をしれて(意味わからず知っていた2ちゃん用語も)興味深かった。 あくまで考察なので、そんなに怖くないのがありがたい。(怪談の概要は書いているので、もちろんその辺りは話に触れることにはなる) 近年のやってみた系動画やAIについても触れており、ネット怪談の現時点についてわかった。 読みやすい文体だが、タイトルに民俗学とある通り論文チックに感じる雰囲気もある。個人的には好みなわかりやすいよい本だった。 【追記】 最近のネット怪談は物語を必要としない、という記述におもしろいなと思うとともに、昔の話を思い出したので備忘で追記。 昔小学生の時、臨海学校的なので小学校に泊まって肝試しをしたとき、保護者が学校の各場所に隠れてお化け役をしてくれてたのだが、ある場所では途中から保護者は隠れずにそのままにしてたらしい。曰く、人がおどかすより、何もない空間の方が勝手に怖がってくれるとのこと。 何もないけど何か不気味な空間に、各々が想像力を働かせて物語を作ってしまうのは時代問わずなのかなあと思った。
ゆかこ@crosscounter_ubk2025年7月26日読み終わった図書館本ネット怪談をあらゆる角度から考察、検証した本。 なるほど、面白い。ネット怪談はどのようにして話が出来て語り継がれていくのか。伝えていくだけでなく、共同で構築していくことがポイントなのだなと。 海外のネット怪談話もあって聞いたことない話や、名前だけ知ってるような話の出自や経緯をしれて(意味わからず知っていた2ちゃん用語も)興味深かった。 あくまで考察なので、そんなに怖くないのがありがたい。(怪談の概要は書いているので、もちろんその辺りは話に触れることにはなる) 近年のやってみた系動画やAIについても触れており、ネット怪談の現時点についてわかった。 読みやすい文体だが、タイトルに民俗学とある通り論文チックに感じる雰囲気もある。個人的には好みなわかりやすいよい本だった。 【追記】 最近のネット怪談は物語を必要としない、という記述におもしろいなと思うとともに、昔の話を思い出したので備忘で追記。 昔小学生の時、臨海学校的なので小学校に泊まって肝試しをしたとき、保護者が学校の各場所に隠れてお化け役をしてくれてたのだが、ある場所では途中から保護者は隠れずにそのままにしてたらしい。曰く、人がおどかすより、何もない空間の方が勝手に怖がってくれるとのこと。 何もないけど何か不気味な空間に、各々が想像力を働かせて物語を作ってしまうのは時代問わずなのかなあと思った。






 こんめ@conconcocon2025年5月15日まだ読んでる内容の三分の一くらい、当時私が卒論でやりたかったことが、書いてあって、うわぁぁぁあああぁぁ〜〜〜ってなってしまった。 著者プロフィールを見てみたら、見事に同世代で、そして著者自身大学生時代にネット怪談で卒論を書いたらしく、ですよね〜〜!そこ興味持ちますよね〜!と勝手にシンパシー。 インターネットと2ちゃんねる、が盛り上がっていくその右肩上がりに乗っかっていた世代としては、従来の怪談、怖い話、にインターネットが介在したことによる現象に、新しさというか、疑問というかを、感じてしまうのかもしれない。 そして私が卒論でやろうとしてたことに関しては、まだ時期尚早というか、資料もケースも収集するだけの数がなかったんだなぁ…としみじみ反省してしまったのであった…
こんめ@conconcocon2025年5月15日まだ読んでる内容の三分の一くらい、当時私が卒論でやりたかったことが、書いてあって、うわぁぁぁあああぁぁ〜〜〜ってなってしまった。 著者プロフィールを見てみたら、見事に同世代で、そして著者自身大学生時代にネット怪談で卒論を書いたらしく、ですよね〜〜!そこ興味持ちますよね〜!と勝手にシンパシー。 インターネットと2ちゃんねる、が盛り上がっていくその右肩上がりに乗っかっていた世代としては、従来の怪談、怖い話、にインターネットが介在したことによる現象に、新しさというか、疑問というかを、感じてしまうのかもしれない。 そして私が卒論でやろうとしてたことに関しては、まだ時期尚早というか、資料もケースも収集するだけの数がなかったんだなぁ…としみじみ反省してしまったのであった… よつや@hiyayotuya2025年4月23日読み終わった@ カフェ雨宿りで入ったカフェにて。 ネットにあるものは十数年も経つとすぐ探すのが難しくなる気がする。 いつでも読めるネット怪談も、一応紙媒体で持っておきたかった。
よつや@hiyayotuya2025年4月23日読み終わった@ カフェ雨宿りで入ったカフェにて。 ネットにあるものは十数年も経つとすぐ探すのが難しくなる気がする。 いつでも読めるネット怪談も、一応紙媒体で持っておきたかった。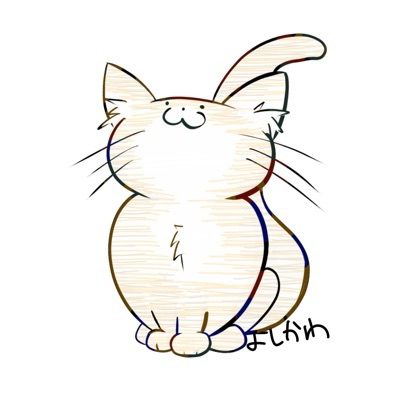
 FUKUKOZY@fukukozy2025年4月8日読み終わった「きさらぎ駅」「くねくね」などインターネットを介して広まった著名な怪談を民俗学の視点から考察。 自分は「洒落怖」として雑に受容していたので、引用元明記しつつまとめられていて、長く参考になりそう。 個人的にはバックルームやリミナルスペースが気になるので、その辺りもまとめられていてよかった。あとがきで触れられなかった、として書いていたVRChatなどメタバースの怪談はどんなのがあるんだろう……
FUKUKOZY@fukukozy2025年4月8日読み終わった「きさらぎ駅」「くねくね」などインターネットを介して広まった著名な怪談を民俗学の視点から考察。 自分は「洒落怖」として雑に受容していたので、引用元明記しつつまとめられていて、長く参考になりそう。 個人的にはバックルームやリミナルスペースが気になるので、その辺りもまとめられていてよかった。あとがきで触れられなかった、として書いていたVRChatなどメタバースの怪談はどんなのがあるんだろう……



 mq@365co2025年3月25日読み終わった@ 電車読み終わった!面白かった。出版されてすぐに買って読んでたけどなんか全然集中できなくてしばらく寝かせてから読んだらするすると読めた。新書を全部読めたの初めてかもしれない。 怖い画像が載っててちょっと怖かった。画像がある予感がする度にドキドキしながらページをめくっててある意味昔よく流れてきたスクロールしたらびっくり画像みたいな体験を今私は紙の本でやってるんだ……となった。
mq@365co2025年3月25日読み終わった@ 電車読み終わった!面白かった。出版されてすぐに買って読んでたけどなんか全然集中できなくてしばらく寝かせてから読んだらするすると読めた。新書を全部読めたの初めてかもしれない。 怖い画像が載っててちょっと怖かった。画像がある予感がする度にドキドキしながらページをめくっててある意味昔よく流れてきたスクロールしたらびっくり画像みたいな体験を今私は紙の本でやってるんだ……となった。

- のーとみ@notomi2025年3月10日かつて読んだ廣田龍平「ネット怪談の民俗学」読んだ。この本がいいのは、パソコン通信時代の怪談や、インターネット初期の90年代に生まれた因習系の怪異譚が、どのように広がり、従来のフィクションとしてのホラー小説や映画とは、何が違い、それがどのように広がっていったかというところから丁寧に事例を拾っていることと、個人の創作としての「ネットホラー」と、ネットという双方向メディアによって拡散し変容しながら語り継がれる「ネット怪談」を明確に別物として扱っていること。 それによって、ナラティブな物語がユーザーによって作り上げられていく因習系怪談や村の怪異から、不穏さがただ積み重なっていく物語を必要としない恐怖へと変わっていくネット怪談の歴史がハッキリと見えてくる。それはまるで、三遊亭圓朝に代表される因果物語や、四谷怪談や雨月物語などの幽霊譚から、無意味に恐怖だけが存在する岡本綺堂型のモダンホラーへの推移と重なる。まあ、だからと言って綺堂怪談が、その後の怪談の主流になった訳ではなく、未だ、怪異に原因を求める物語は多く作られているのだけど、それは恐怖を「物語」という枠に収めて商品化する以上、仕方ないことではある。そこをネットが軽々と飛び越えていく過程を、民俗学の手法できちんと解説しているのが、この本の面白さ。 それは言葉による怪異と映像による怪異の違いでもあるし、創作の面白さと、(擬似)体験の面白さの違いでもあって、その違いが、実はとても遠いことを、怪談という表現が露わにしてしまうという面白さでもあると思う。人は何を怖がりたいのか、何故、怖がりたいのかについての基礎研究みたいな本が凄く売れてるというのが何とも面白いというか、もしかすると、この本をネット怪談のカタログ本と間違ってるんじゃないかという心配もあるけど、それもまたネット怪談的で、存在自体面白いと言えるかもw


 amy@note_15812025年3月6日かつて読んだ著者いわく1990年代末~2020年代前半までの約四半世紀ぶんの日のんのネット怪談の大まかな見取り図を提示することを目的として書かれた本。目的の通り日本におけるネット怪談の流れやその時々におけるネット怪談の主流となったテーマやその要因などの論考がある。 インターネットのたとえば掲示板や2ちゃんねる、まとめブログ、Twitterなどのツールの変遷やそれによって可能になったことと照らし合わせながらまとめているところもわかりやすかったし、一時期ネット怪談を読むのにハマっていた身としてもあーそうだった!と懐かしい気持ちになった。 また1点気になったのは第四章の再媒介化もしくはネット怪談の衰退(創作発表の場の変化)に関わることだと思うのだが、たとえば二次創作のアイテムとしてネット怪談が使われているというのは著者の廣田龍平氏はどういう分類をするのだろうと考えた。 私はアニメや漫画の二次創作をよく見るけどpixivでキャラクターがきさらぎ駅に巻き込まれる話もあり、しかも創作のかたちもちゃんねる系というテンプレートがあって2ちゃんねるみたいにスレッドでやりとりしているかたちと小説が組み合わせたようなかたちになっている。 こういうかたちを著者の廣田龍平氏は知っており、そのうえで特に特筆するようなことがなくてスルーしたのかそもそも彼の観測外だったのかはわからないが、どういう分類になるのかは聞いてみたい
amy@note_15812025年3月6日かつて読んだ著者いわく1990年代末~2020年代前半までの約四半世紀ぶんの日のんのネット怪談の大まかな見取り図を提示することを目的として書かれた本。目的の通り日本におけるネット怪談の流れやその時々におけるネット怪談の主流となったテーマやその要因などの論考がある。 インターネットのたとえば掲示板や2ちゃんねる、まとめブログ、Twitterなどのツールの変遷やそれによって可能になったことと照らし合わせながらまとめているところもわかりやすかったし、一時期ネット怪談を読むのにハマっていた身としてもあーそうだった!と懐かしい気持ちになった。 また1点気になったのは第四章の再媒介化もしくはネット怪談の衰退(創作発表の場の変化)に関わることだと思うのだが、たとえば二次創作のアイテムとしてネット怪談が使われているというのは著者の廣田龍平氏はどういう分類をするのだろうと考えた。 私はアニメや漫画の二次創作をよく見るけどpixivでキャラクターがきさらぎ駅に巻き込まれる話もあり、しかも創作のかたちもちゃんねる系というテンプレートがあって2ちゃんねるみたいにスレッドでやりとりしているかたちと小説が組み合わせたようなかたちになっている。 こういうかたちを著者の廣田龍平氏は知っており、そのうえで特に特筆するようなことがなくてスルーしたのかそもそも彼の観測外だったのかはわからないが、どういう分類になるのかは聞いてみたい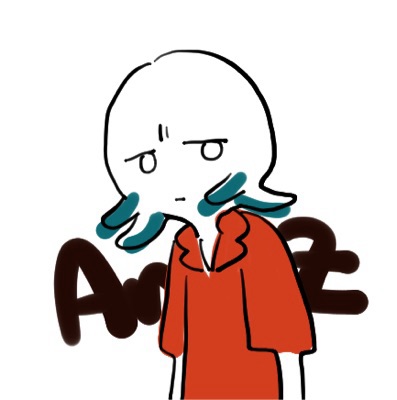 永倉あんず@Anzngkr2025年2月15日読み終わった夜中にトイレに起きた時の自宅の『リミナルスペース』感、あるよな~。 オチが『因習』系のミステリ風の小説、なんかヤなんだよな~。 とか考えながら読んでた(もう少し突っ込んだ話がされています)。 一般向けの新書なのに巻末の文献欄すごい。20ページ以上あった。
永倉あんず@Anzngkr2025年2月15日読み終わった夜中にトイレに起きた時の自宅の『リミナルスペース』感、あるよな~。 オチが『因習』系のミステリ風の小説、なんかヤなんだよな~。 とか考えながら読んでた(もう少し突っ込んだ話がされています)。 一般向けの新書なのに巻末の文献欄すごい。20ページ以上あった。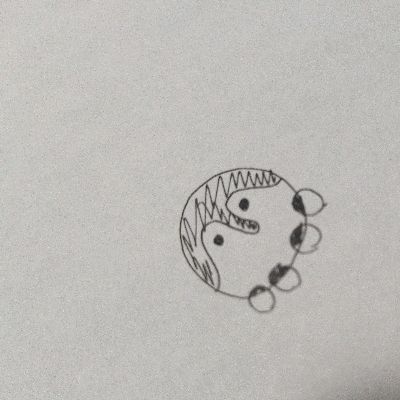 kryk@kykyky1900年1月1日かつて読んだお気に入り民俗学に興味を持ったタイミングで目について読んだ本。 自分がネット掲示板文化が醸成されていく渦中に入れたので当事者である自認で読めた。 民俗学のスタンスについての言及している文があり、素晴らしい視座だと感じた。
kryk@kykyky1900年1月1日かつて読んだお気に入り民俗学に興味を持ったタイミングで目について読んだ本。 自分がネット掲示板文化が醸成されていく渦中に入れたので当事者である自認で読めた。 民俗学のスタンスについての言及している文があり、素晴らしい視座だと感じた。