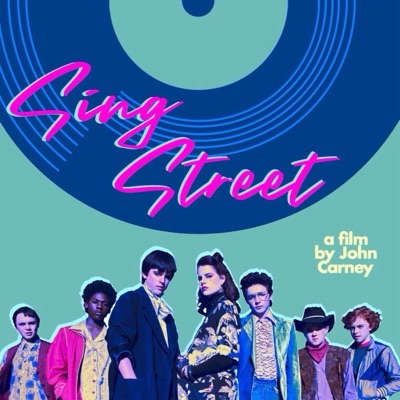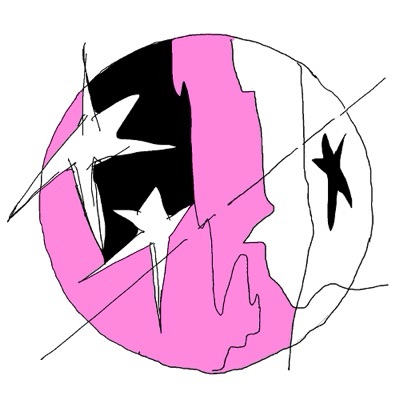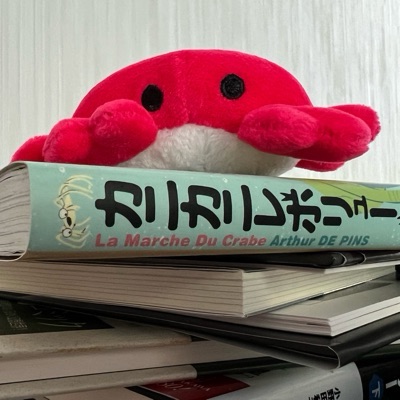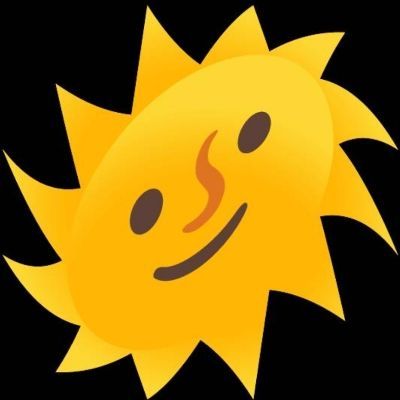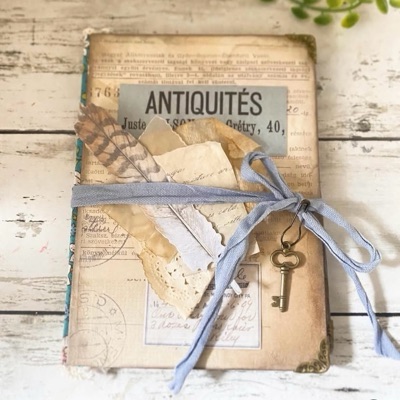私が諸島である カリブ海思想入門

93件の記録
 K@klkmrn2026年2月22日読んでる半分くらい読んだけどめちゃくちゃおもしろくてわくわくする。こんなに知らんことがあるかというほど知らないカリブ海諸島の話、「分散する海」の考え方はいろんなところにつながる気がする。
K@klkmrn2026年2月22日読んでる半分くらい読んだけどめちゃくちゃおもしろくてわくわくする。こんなに知らんことがあるかというほど知らないカリブ海諸島の話、「分散する海」の考え方はいろんなところにつながる気がする。
 jaguchi@jaguchi872026年1月14日読み終わった・植民地主義は、カリブ海をヨーロッパ、アフリカ、アジアから様々な社会的、文化的、宗教的、人種的背景を持つ集団が衝突、接触する舞台に変えた。(……)人々は、前列のない言語、民族、文化の混淆を経験している。p.170 カリブ海の思想家たちは、自分たちを「他者」とし歴史の外に追いやる欧米中心主義に「カリブ海の」思想でもって力強く対抗してきた。 その上で、この本はカリビアン・フェミニズム、またはカリビアン・クィア・スタディーズの観点から指摘されるこれまでのカリブ海思想の問題点をも紹介している。何だかまさに海のうねりみたいに。 日本という国は西洋的価値観を内面化しているのと同時に、西洋的価値観によって(カリブ海と同じように)他者化されているのだと感じた。
jaguchi@jaguchi872026年1月14日読み終わった・植民地主義は、カリブ海をヨーロッパ、アフリカ、アジアから様々な社会的、文化的、宗教的、人種的背景を持つ集団が衝突、接触する舞台に変えた。(……)人々は、前列のない言語、民族、文化の混淆を経験している。p.170 カリブ海の思想家たちは、自分たちを「他者」とし歴史の外に追いやる欧米中心主義に「カリブ海の」思想でもって力強く対抗してきた。 その上で、この本はカリビアン・フェミニズム、またはカリビアン・クィア・スタディーズの観点から指摘されるこれまでのカリブ海思想の問題点をも紹介している。何だかまさに海のうねりみたいに。 日本という国は西洋的価値観を内面化しているのと同時に、西洋的価値観によって(カリブ海と同じように)他者化されているのだと感じた。

 3am_sp@3am_sp2025年10月11日読み始めたpodcast「女子校の後輩と話し始める『脱植民地化』」で挙げられていたので読む メモ: 「神話は、共同体の単一の起源を回想的に喚起する」 「『発見』において優位なのは、常に『発見者』なのだ」
3am_sp@3am_sp2025年10月11日読み始めたpodcast「女子校の後輩と話し始める『脱植民地化』」で挙げられていたので読む メモ: 「神話は、共同体の単一の起源を回想的に喚起する」 「『発見』において優位なのは、常に『発見者』なのだ」


 別@Romkioften2025年10月6日読み終わった地理的には西洋に近いながらも、そこに住む人びとは明確な線引きのもとに西洋からの視点により他者化され、思想のレベルにおいても周縁化される。カリブ海とはそのような地域であるが、ならばそのカリブ海を中心にした世界というのが如何なるものなのかというと、実際に自分の目で見て確かめるか本書を読むしか知る術はないように思われる。日本において理解が進まないどころかほとんど関心が払われないこの地域の思想家たちの肩に乗るのは現在主に言語の壁がネックとなってなかなか容易ではないが、この本の出版と重版を機に日本でも翻訳が広まればまたカリブ海の渦潮に触れてみたい。良書。
別@Romkioften2025年10月6日読み終わった地理的には西洋に近いながらも、そこに住む人びとは明確な線引きのもとに西洋からの視点により他者化され、思想のレベルにおいても周縁化される。カリブ海とはそのような地域であるが、ならばそのカリブ海を中心にした世界というのが如何なるものなのかというと、実際に自分の目で見て確かめるか本書を読むしか知る術はないように思われる。日本において理解が進まないどころかほとんど関心が払われないこの地域の思想家たちの肩に乗るのは現在主に言語の壁がネックとなってなかなか容易ではないが、この本の出版と重版を機に日本でも翻訳が広まればまたカリブ海の渦潮に触れてみたい。良書。


 とめ@m_ake2025年9月5日読み終わったちょっと難しそうかな…としばらく積んでいたのだけど、読み始めたら一章も短く読みやすく、そしてめちゃくちゃおもしろく、一気に読んだ。 これまでぼやーっと「ラテンアメリカの一部?」と思ってたカリブ海のあたりが、はっきりしたように思う。 「ドラゴンは踊れない」に登場するインド人(自転車壊される…)、「母を失うこと」で描かれる奴隷船、「ことばと国家」で描かれた母語が生まれる瞬間……など、いろんなことが「私が諸島である」を読んだことで、すごく腑に落ちたし、あるべき場所にしまい直せたように思う。 新刊も読んでみたいし、参考文献もいろいろ気になる…。読みたい本ばかり増えていく。。
とめ@m_ake2025年9月5日読み終わったちょっと難しそうかな…としばらく積んでいたのだけど、読み始めたら一章も短く読みやすく、そしてめちゃくちゃおもしろく、一気に読んだ。 これまでぼやーっと「ラテンアメリカの一部?」と思ってたカリブ海のあたりが、はっきりしたように思う。 「ドラゴンは踊れない」に登場するインド人(自転車壊される…)、「母を失うこと」で描かれる奴隷船、「ことばと国家」で描かれた母語が生まれる瞬間……など、いろんなことが「私が諸島である」を読んだことで、すごく腑に落ちたし、あるべき場所にしまい直せたように思う。 新刊も読んでみたいし、参考文献もいろいろ気になる…。読みたい本ばかり増えていく。。


 なかちきか@susie_may41412025年7月26日気になる買った@ くまざわ書店 田園調布店『君たちの記念碑はどこにある?』が気になるなと思ったら、みなさんこちらを読んで良かったと言っていて、知らなかったから、こちらも読みたい。 7/27見つけて購入。
なかちきか@susie_may41412025年7月26日気になる買った@ くまざわ書店 田園調布店『君たちの記念碑はどこにある?』が気になるなと思ったら、みなさんこちらを読んで良かったと言っていて、知らなかったから、こちらも読みたい。 7/27見つけて購入。 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月21日読み終わった『私が諸島である』を読み終えて満足。このタイミングで読めてよかった。なんか元気になる。包摂を謳ったカリブ海思想であっても、当人たちのそして時代的な制約という限界もあって、なんらかの存在を排除してしまうことがある。20世紀にはそれが女性の不在であると批判され、21世紀に入るとクィアの不在であると批判される。しかしそれはさらなるアップデートのチャンスである。アップデートのチャンスだからといってすべてが許されるわけではないが、直線的ではなく円環的に差異と反復を繰り返しながら包摂性を高めていくカリブ海思想のありかたは、やはり好きなタイプのユートピア思想だった。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月21日読み終わった『私が諸島である』を読み終えて満足。このタイミングで読めてよかった。なんか元気になる。包摂を謳ったカリブ海思想であっても、当人たちのそして時代的な制約という限界もあって、なんらかの存在を排除してしまうことがある。20世紀にはそれが女性の不在であると批判され、21世紀に入るとクィアの不在であると批判される。しかしそれはさらなるアップデートのチャンスである。アップデートのチャンスだからといってすべてが許されるわけではないが、直線的ではなく円環的に差異と反復を繰り返しながら包摂性を高めていくカリブ海思想のありかたは、やはり好きなタイプのユートピア思想だった。




 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月19日まだ読んでる直線的で、攻撃や支配や競争の標的となる他者を必要とするミサイル的価値観。円環的で、相互歓待の姿勢を基本とするカプセル的価値観。前者を西洋的、後者をカリブ海的とする論が展開される第9章。 ミサイル的価値観は「敵」を必要とするナショナリズム/ファシズム理論とも軌を一にするように思える。ここ数日で地獄度合いを増しているイスラエルの動きも同様で、パレスチナのみならずイランまでをも攻撃対象として認識し、文字どおりにミサイルを撃ち込んでしまっている。 しかしここで思うのは、おそらくイスラエルは自らをミサイル=攻撃や簒奪の主体としてではなく、むしろその被害を受けている側として自らを認識しているのだろう、ということだ。つまり、奪われているから奪い返しているだけだ、と考えている。これは「日本人ファースト」的な言説に期待をしてしまう者らにも共通する認識なのだと思う。かれらはミサイルを撃つ側ではなく撃ち込まれている側だと感じている(「我々の日本に外国人が侵入している」という認識なのだから、その理路が行き着く先としては必然とも言える)。 そうなると、イスラエルや排外感情を募らせている者らに「ミサイルを撃ち込むなんてどう考えてもダメだとわかるでしょう」と言っても伝わらない、ということになる。これは強硬的なシオニストや排外主義者たちだけの認識ではない。後者に的を絞れば、大多数の日本人が、ミサイルが撃ち込まれている存在を「自分たち」だと誤認している。どうすれば伝わるか、誤認をあらためてもらえるか、いままでと同じやりかたでは状況は変えられない。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月19日まだ読んでる直線的で、攻撃や支配や競争の標的となる他者を必要とするミサイル的価値観。円環的で、相互歓待の姿勢を基本とするカプセル的価値観。前者を西洋的、後者をカリブ海的とする論が展開される第9章。 ミサイル的価値観は「敵」を必要とするナショナリズム/ファシズム理論とも軌を一にするように思える。ここ数日で地獄度合いを増しているイスラエルの動きも同様で、パレスチナのみならずイランまでをも攻撃対象として認識し、文字どおりにミサイルを撃ち込んでしまっている。 しかしここで思うのは、おそらくイスラエルは自らをミサイル=攻撃や簒奪の主体としてではなく、むしろその被害を受けている側として自らを認識しているのだろう、ということだ。つまり、奪われているから奪い返しているだけだ、と考えている。これは「日本人ファースト」的な言説に期待をしてしまう者らにも共通する認識なのだと思う。かれらはミサイルを撃つ側ではなく撃ち込まれている側だと感じている(「我々の日本に外国人が侵入している」という認識なのだから、その理路が行き着く先としては必然とも言える)。 そうなると、イスラエルや排外感情を募らせている者らに「ミサイルを撃ち込むなんてどう考えてもダメだとわかるでしょう」と言っても伝わらない、ということになる。これは強硬的なシオニストや排外主義者たちだけの認識ではない。後者に的を絞れば、大多数の日本人が、ミサイルが撃ち込まれている存在を「自分たち」だと誤認している。どうすれば伝わるか、誤認をあらためてもらえるか、いままでと同じやりかたでは状況は変えられない。









 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月18日まだ読んでる第3水曜日でおやすみなのでゆっくり起き出してゆっくり過ごす。 ボウが言うように、カリブ海作家たちは、「我々に自分たちの歴史認識の検討もしくは再検討、つまり何が歴史であるのかという問題を見直させるだけでなく、何が達成となるのかという我々の考え方も検討させる」のである。(p.136) 『仕事文脈 vol.26』でインタビューした温泉マークも、達成=成功とはなにかを検討させる活動をしていた。温泉マークはカリブ海だった。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月18日まだ読んでる第3水曜日でおやすみなのでゆっくり起き出してゆっくり過ごす。 ボウが言うように、カリブ海作家たちは、「我々に自分たちの歴史認識の検討もしくは再検討、つまり何が歴史であるのかという問題を見直させるだけでなく、何が達成となるのかという我々の考え方も検討させる」のである。(p.136) 『仕事文脈 vol.26』でインタビューした温泉マークも、達成=成功とはなにかを検討させる活動をしていた。温泉マークはカリブ海だった。






 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月17日まだ読んでるカリブ海諸国は西洋各国の統治によって、異なる言語経験を持っている。しかしそのことによってカリブ海文化が完全に消滅したわけではなく、それらはブラスウェイトの言う「海面下」に「沈み込む」ことによって生き延びている。そしてグリッサンが言うには、カリブ海は「分散する海」であり、「集中する海」としての地中海≒西洋的思想と区別する。統一ではなく分散。しかし同時にブラスウェイトの言う「統一は海面下にある」という理論にもグリッサンは共鳴し、「カリブ海における海面下的統一は、集中による一ではなく、分散による多なのである」(p.119)と宣言する。 これまでに見てきた景色といま見ている景色は各々異なっていて当然である。ゆえにそれらの積み重ねにも違いはあらわれ、各々が判断する正しさにも違いが生じる。だからこそ正しさを追求する者どうしでも軋轢が生じるわけで、その軋轢を乗り越えるには各々の見てきた/見ている景色を、そしてその違いから生じるさまざまな解答や方法論の違いを、批判しつつも認めあうことが必要になるのだろう。しかし、各々の「景色」は海面下に沈み込んでいるため共有されにくい。集中による一ではなく分散による多を実現するためには、各々の持つ「景色」を海面下から引き上げる必要がある。しかしそれは簡単ではない。沈み込ませたままにしたい景色もある。だからこそ、海面下に沈んだままのなにかがそこにあることを、我々は想像しなくてはならない。意見(=海面上に表出したもの)の相違は、積み重ねてきた経験(=海面下に沈み込んでいるもの)の相違であり、後者にこそ意識を集中させなくてはならない。そして前者の否定は後者の否定にも繋がる。だからこそ、我々は深く傷つくのかもしれない。否定されたのは「いまあらわれた意見」ではなく、「これまで積み重ねてきた経験」だからだ。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月17日まだ読んでるカリブ海諸国は西洋各国の統治によって、異なる言語経験を持っている。しかしそのことによってカリブ海文化が完全に消滅したわけではなく、それらはブラスウェイトの言う「海面下」に「沈み込む」ことによって生き延びている。そしてグリッサンが言うには、カリブ海は「分散する海」であり、「集中する海」としての地中海≒西洋的思想と区別する。統一ではなく分散。しかし同時にブラスウェイトの言う「統一は海面下にある」という理論にもグリッサンは共鳴し、「カリブ海における海面下的統一は、集中による一ではなく、分散による多なのである」(p.119)と宣言する。 これまでに見てきた景色といま見ている景色は各々異なっていて当然である。ゆえにそれらの積み重ねにも違いはあらわれ、各々が判断する正しさにも違いが生じる。だからこそ正しさを追求する者どうしでも軋轢が生じるわけで、その軋轢を乗り越えるには各々の見てきた/見ている景色を、そしてその違いから生じるさまざまな解答や方法論の違いを、批判しつつも認めあうことが必要になるのだろう。しかし、各々の「景色」は海面下に沈み込んでいるため共有されにくい。集中による一ではなく分散による多を実現するためには、各々の持つ「景色」を海面下から引き上げる必要がある。しかしそれは簡単ではない。沈み込ませたままにしたい景色もある。だからこそ、海面下に沈んだままのなにかがそこにあることを、我々は想像しなくてはならない。意見(=海面上に表出したもの)の相違は、積み重ねてきた経験(=海面下に沈み込んでいるもの)の相違であり、後者にこそ意識を集中させなくてはならない。そして前者の否定は後者の否定にも繋がる。だからこそ、我々は深く傷つくのかもしれない。否定されたのは「いまあらわれた意見」ではなく、「これまで積み重ねてきた経験」だからだ。








 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月16日まだ読んでるラヴレイスの言う「歓待」という概念をどのように敷衍できるかを考えている。カリブ海諸国に西洋諸国によって連れてこられたアフリカ系奴隷と、同じく西洋によって連れてこられたインド系の労働者(実質的には奴隷だ)は、西洋の政治機構=植民地支配によって憎みあわされてしまった。本来の敵は植民地支配をした西洋の政治機構だ。しかし西洋は「アフリカとインドは本質的に敵どうしだ」と規定することで、政治によって意図的に作られた対立を隠蔽する。 そこで「歓待」が必要になる。そしてこの意図的に作られた対立構造は、たとえば「在日外国人と各種貧困に苦しむ日本人」という構図とも類似するものがあるかもしれない。この二者は本来、敵どうしではない。政治によって作られた対立構造である。ならば、どのように「歓待」を生じさせることができるのか。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月16日まだ読んでるラヴレイスの言う「歓待」という概念をどのように敷衍できるかを考えている。カリブ海諸国に西洋諸国によって連れてこられたアフリカ系奴隷と、同じく西洋によって連れてこられたインド系の労働者(実質的には奴隷だ)は、西洋の政治機構=植民地支配によって憎みあわされてしまった。本来の敵は植民地支配をした西洋の政治機構だ。しかし西洋は「アフリカとインドは本質的に敵どうしだ」と規定することで、政治によって意図的に作られた対立を隠蔽する。 そこで「歓待」が必要になる。そしてこの意図的に作られた対立構造は、たとえば「在日外国人と各種貧困に苦しむ日本人」という構図とも類似するものがあるかもしれない。この二者は本来、敵どうしではない。政治によって作られた対立構造である。ならば、どのように「歓待」を生じさせることができるのか。






 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月13日読み始めた今月下旬の新刊に向けて遅まきながら予習。まさに「イギリスの」英文学を履修していた者として、やはり遅まきながらでも読まなくてはならない1冊である。本屋として、ふだん仕入れの判断をするときに「売れるかどうか」はとても大事なのだけど、その観点からすると本書はまさに「売れない」と判断されがちな地域の話あるいは文学作品についての本ということになる。「売れない」からといって店頭から弾くことが、さらに周縁化された状況=売れないを作り出すという循環に、私は常に加担していると言える。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月13日読み始めた今月下旬の新刊に向けて遅まきながら予習。まさに「イギリスの」英文学を履修していた者として、やはり遅まきながらでも読まなくてはならない1冊である。本屋として、ふだん仕入れの判断をするときに「売れるかどうか」はとても大事なのだけど、その観点からすると本書はまさに「売れない」と判断されがちな地域の話あるいは文学作品についての本ということになる。「売れない」からといって店頭から弾くことが、さらに周縁化された状況=売れないを作り出すという循環に、私は常に加担していると言える。









 ビスケットアパート@powerfulfranny2025年5月8日読み終わった解呪の詩学…!!グリッサンの『関係の<詩学>』と紹介されていた文学も読んでみたい。全部を含んでいる気に勝手なって、より広義の言葉を求めて使ってしまっていたことを読みながら何度も反省した 「…1492以降、「人間であるとは何か」を記述する言説を、西洋は自分たちの「人間」の認識によって支配してきた。それにより「他者」を表象する枠組みに長年押し込められてきたカリブ海の人々は、自ら筆を執り、自らの言葉で自信を語り始めた。西洋によって独占されていた「人間」の意味に抵抗し、自分たちの思想によって存在を再考・再定義しら植民地支配によって奪われた主体性を取り戻さんとするのである。」
ビスケットアパート@powerfulfranny2025年5月8日読み終わった解呪の詩学…!!グリッサンの『関係の<詩学>』と紹介されていた文学も読んでみたい。全部を含んでいる気に勝手なって、より広義の言葉を求めて使ってしまっていたことを読みながら何度も反省した 「…1492以降、「人間であるとは何か」を記述する言説を、西洋は自分たちの「人間」の認識によって支配してきた。それにより「他者」を表象する枠組みに長年押し込められてきたカリブ海の人々は、自ら筆を執り、自らの言葉で自信を語り始めた。西洋によって独占されていた「人間」の意味に抵抗し、自分たちの思想によって存在を再考・再定義しら植民地支配によって奪われた主体性を取り戻さんとするのである。」



- さみ@futatabi2025年5月8日4章まで 「「発見」において優位なのは、常に「発見者」なのだ」 わたしもそのようにして自分の意識の中で、優劣がつくかたちで他者(ひとでなくても)を対象化してしまっていると思う。それに気づきたい。

 mkt@mkthnsk2025年5月3日読んでる4章、5章 面白く(と言っていいのか?)なってきた。 否定でなく希望を! 書いてあることとズレるかもしれないけど、希望を持つこと自体が抵抗になりうるなと思う。
mkt@mkthnsk2025年5月3日読んでる4章、5章 面白く(と言っていいのか?)なってきた。 否定でなく希望を! 書いてあることとズレるかもしれないけど、希望を持つこと自体が抵抗になりうるなと思う。



 mkt@mkthnsk2025年3月17日ちょっと開いたなんとか確定申告終えてコロコロしながら先日手に入れたこの本をパラリとめくってみる。序章の2ページでかなり期待が膨らむ。引用された文で泣きそう。 今読んでる"暗黙知の次元"読み終えてから、ゆっくりじっくり読みたい。
mkt@mkthnsk2025年3月17日ちょっと開いたなんとか確定申告終えてコロコロしながら先日手に入れたこの本をパラリとめくってみる。序章の2ページでかなり期待が膨らむ。引用された文で泣きそう。 今読んでる"暗黙知の次元"読み終えてから、ゆっくりじっくり読みたい。