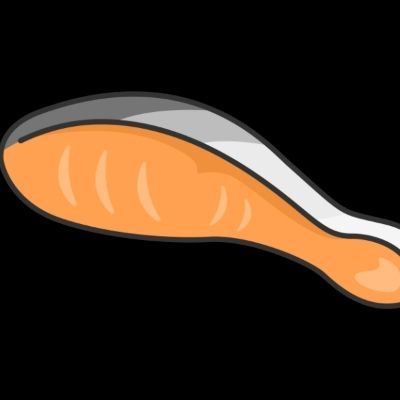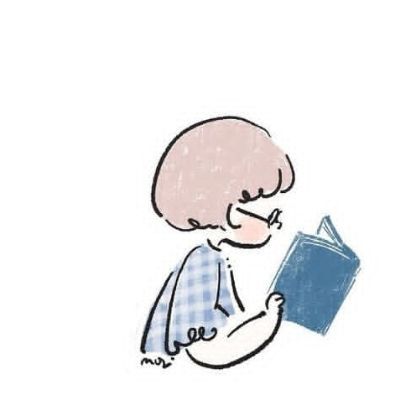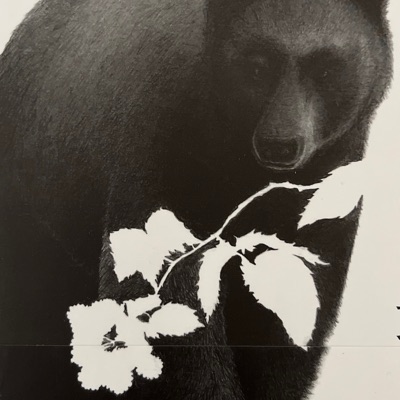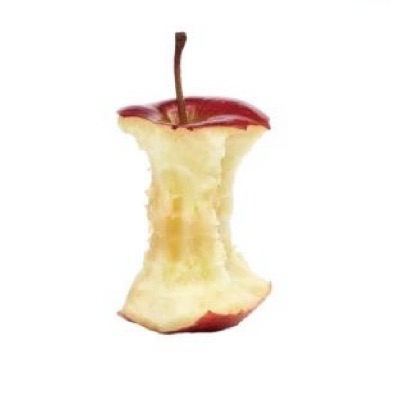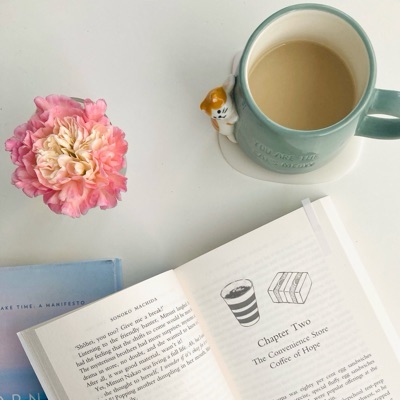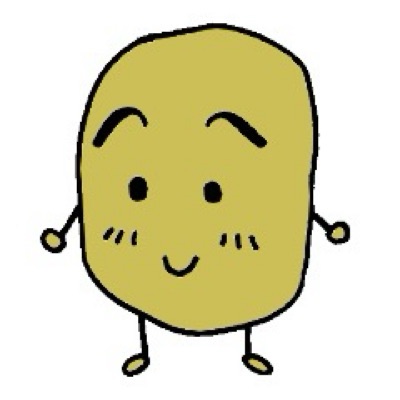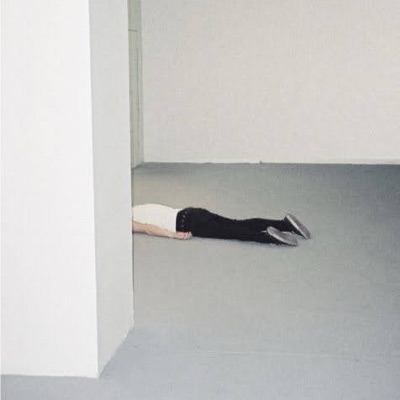まとまらない言葉を生きる

139件の記録
- メルキー@dogandbook2026年2月11日読み終わったエッセイ読んでよかった-2026@ 自宅これは、読んだ方が良いなあ。 この本で取り上げられている出来事について知ろうとする人、考える人が増えれば良いのに。 初版が出たのは2021年とそう昔のことでもないはずなのに、そこからたった5年でとんでもないフェーズにまで日本は来てしまったと感じる。 ここに書かれていることに他人事でいられる人は、今の日本にはほとんどいないのではないだろうか。 はっとさせられる瞬間が、表情が渋くなる瞬間が幾度となくあった。 前提、誰のことも傷つけないで生きることは不可能だと思っているが、自分が認識の有無に関わらず誰かのことを傷つけてしまう可能性があることを心に留めておくだけでも、発言する前に立ち止まれる。 取り上げられている出来事についてしっかり焦点を当てた上で当事者の言葉を引用するから、いわゆる「名言」みたいな一人歩きしている言葉じゃなくて、血の通った言葉に感じる。 特に、第十一話が素晴らしかった。 --- ムードというのは、マジョリティにとっては空気みたいなものだけれど、マイノリティにとっては檻みたいなもの。 心の病を治すという表現には慎重にならなければいけない。 心を病むって、その人の心が問題なのではなくて取り巻く周りの環境が問題なのでは? 環境や人間関係が病んでいて、それが立場の弱い人を通して噴出しているということもあるんじゃないのか? 「癒す」というのは、この「なんとか」「どうにか」「それでも」とつぶやくときの、そのつぶやきにこもった祈りに近い感覚だ。 「自己責任」という言葉が「人を孤立させる言葉」だとしたら、「人を孤立させない言葉」を探し、分かち合っていくことが必要だ。 ↑ 分かち合うって、大事だよね。発信は、分かち合う手段。



 kirakira30@kirakira302026年1月30日読み終わったまたいつか〈ぼくらは絶対に侵害してはならない一線を守る言葉を、急いで積み上げなければならない。誰かの一線を軽んじる社会は、最終的に、誰の一線も守らないのだから。〉p145 この本が書かれた時よりもより切実になってきている。もう待ったなしで本当に。
kirakira30@kirakira302026年1月30日読み終わったまたいつか〈ぼくらは絶対に侵害してはならない一線を守る言葉を、急いで積み上げなければならない。誰かの一線を軽んじる社会は、最終的に、誰の一線も守らないのだから。〉p145 この本が書かれた時よりもより切実になってきている。もう待ったなしで本当に。

 kirakira30@kirakira302026年1月21日再読中〈強権的で抑圧的な社会もいうのは、いくつかの段階がある。 まずは、誰かに対して「役に立たないという烙印」を押すことをためらわなくなる。 次に、そうした人たちを迫害して、排除して、黙らせる。 黙らせたことで、今度は逆に語らせる。 「こうしたことを言えば、仲間として認めてやらなくもないんだけど」という具合に、「強制」することなく、あくまでも「自発的」に語らせる。 こうして「強制的に語らせた人」の責任は問われることなく、「自発的に語ってしまった人」だけが傷ついていく。〉p106
kirakira30@kirakira302026年1月21日再読中〈強権的で抑圧的な社会もいうのは、いくつかの段階がある。 まずは、誰かに対して「役に立たないという烙印」を押すことをためらわなくなる。 次に、そうした人たちを迫害して、排除して、黙らせる。 黙らせたことで、今度は逆に語らせる。 「こうしたことを言えば、仲間として認めてやらなくもないんだけど」という具合に、「強制」することなく、あくまでも「自発的」に語らせる。 こうして「強制的に語らせた人」の責任は問われることなく、「自発的に語ってしまった人」だけが傷ついていく。〉p106

 よし子@7242026年1月16日読み終わったタイトルのまとまらない言葉とは、言葉にならない、もどかしい言葉という意味かと思っていたが、まとめられない、要約されない言葉、という意味らしい。 終盤の著者自身のエピソードと、時折挟まれる現代社会への憂いを踏まえると、この人には「正しさ」への志向が抜けがたくあるんじゃないかという気がする。
よし子@7242026年1月16日読み終わったタイトルのまとまらない言葉とは、言葉にならない、もどかしい言葉という意味かと思っていたが、まとめられない、要約されない言葉、という意味らしい。 終盤の著者自身のエピソードと、時折挟まれる現代社会への憂いを踏まえると、この人には「正しさ」への志向が抜けがたくあるんじゃないかという気がする。- wakepota720@wakeru7202026年1月5日読み終わった「言葉が壊れてきた」と思う。いや、言葉そのものが勝手に壊れることはないから、「壊 されてきた」という方が正確かもしれない。 こう書くと、若者の言葉遣いが乱れてきたとか、古き良き日本語表現が忘れられていく とか、そうした類いの苦言や小言に受け取られてしまうかもしれない。でも、ここで考えたいのは、もう少し深刻で、たぶん陰鬱な問題だ。 日々の生活の場でも、その生活を作る政治の場でも、負の力に満ち満ちた言葉というか、 人の心を削る言葉というか、とにかく「生きる」ということを楽にも楽しくもさせてくれ ないような言葉が増えて、言葉の役割や存在感が変わってしまったように思うのだ。 この本は、こうした「言葉の壊れ」について考える本だ。 できれば、それに抗うための 本でありたい。




- nishii_books@nishii_books2026年1月5日読書会読書会課題本やったー! 来週からこの本で読書会スタートします🙂 昨年買って、紹介しての決定 来週から楽しみ 読書会後に感想を更新

 kirakira30@kirakira302026年1月4日再読中〈言葉には「降り積もる」という性質がある。放たれた言葉は、個人の中にも、社会の中にも降り積もる。そうした言葉の蓄積が、ぼくたちの価値観の基を作っていく。〉p26 - - - - - - - 新年早々、また信じられないことが起きている。 ようやくその事を時間をとって報道してくれたニュース番組を観た。国際法を軽んじることに対する問題提起は、ほぼなかったと言っていいと思う。その深刻さに、うちひしがれてしまった。まだ何を考えていけばいいのか…立ち尽くすことしかできない。追い打ちをかけるように、それに対する一国の総理大臣である人が発信した言葉に、言葉を失った。そんな時に、本棚のこの本が目に止まった。 絶望しないように、ゆっくり読んでいこうと思う。
kirakira30@kirakira302026年1月4日再読中〈言葉には「降り積もる」という性質がある。放たれた言葉は、個人の中にも、社会の中にも降り積もる。そうした言葉の蓄積が、ぼくたちの価値観の基を作っていく。〉p26 - - - - - - - 新年早々、また信じられないことが起きている。 ようやくその事を時間をとって報道してくれたニュース番組を観た。国際法を軽んじることに対する問題提起は、ほぼなかったと言っていいと思う。その深刻さに、うちひしがれてしまった。まだ何を考えていけばいいのか…立ち尽くすことしかできない。追い打ちをかけるように、それに対する一国の総理大臣である人が発信した言葉に、言葉を失った。そんな時に、本棚のこの本が目に止まった。 絶望しないように、ゆっくり読んでいこうと思う。
 おいしいごはん@Palfa0462025年12月27日読み始めた表紙を捲ったところに以下の文があってグッときた。 言葉が「降り積もる」とすれば、 あなたは、 どんな言葉が降り積もった社会を 次の世代に引き継ぎたいですか?
おいしいごはん@Palfa0462025年12月27日読み始めた表紙を捲ったところに以下の文があってグッときた。 言葉が「降り積もる」とすれば、 あなたは、 どんな言葉が降り積もった社会を 次の世代に引き継ぎたいですか?
 JUMPEI AMANO@Amanong22025年12月2日再読編集した@ 自宅会社で流行語大賞の報に触れ卒倒しかけたので、帰宅後、自分にとっての宝物のような言葉を噛み締めた。 † ある視点からすればいわゆる気が狂う状態とてもそれが抑圧に対する反逆として自然にあらわれるかぎり、それじたい正常なのです。 [...]吉田おさみは黙っていなかった。心を病むのは〈抑圧に対する反逆〉として〈正常〉なのだと言い切った。この言葉のすごいところは、返す刀で「では異常なのは何? 誰?」という問いを突きつけてくるところだ。 当たり前だけれど、環境や条件さえ整えば、誰の心だって壊れうる。だとしたら、「心を壊しにかかってくるもの」の方が問題だ。この言葉を知ると、人の心が壊れうることへの想像力のない人が社会のあり方を決めていくことの恐ろしさがわかるだろう。(28-29頁)
JUMPEI AMANO@Amanong22025年12月2日再読編集した@ 自宅会社で流行語大賞の報に触れ卒倒しかけたので、帰宅後、自分にとっての宝物のような言葉を噛み締めた。 † ある視点からすればいわゆる気が狂う状態とてもそれが抑圧に対する反逆として自然にあらわれるかぎり、それじたい正常なのです。 [...]吉田おさみは黙っていなかった。心を病むのは〈抑圧に対する反逆〉として〈正常〉なのだと言い切った。この言葉のすごいところは、返す刀で「では異常なのは何? 誰?」という問いを突きつけてくるところだ。 当たり前だけれど、環境や条件さえ整えば、誰の心だって壊れうる。だとしたら、「心を壊しにかかってくるもの」の方が問題だ。この言葉を知ると、人の心が壊れうることへの想像力のない人が社会のあり方を決めていくことの恐ろしさがわかるだろう。(28-29頁)





 JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月20日再読編集した@ 自宅長いけれど引用。9-10頁より。 † こうした言葉は、中身があるのかどうかはわからないけれど、発信者の威勢の良いときには価値がありそうに見える。あるいは、威勢の良さだけが価値を担保しているとも言える。なんだか「軍票」(軍が発行する特殊な通貨、「軍用手票」の略)みたいだ。 ああした言葉に「頼もしさ」や「雄々しさ」を感じてしまったとしたら、一度立ち止まって、深呼吸してみて、自分がつかまされているのが本当に軍票じゃないかどうかを確認した方がいいだろう。 [...] 軍票的な言葉は、自分の価値が下がらないように、本当は自分に価値なんてないことがバレないように、常に敵を作り、対立をあおり、気勢を上げる無限ループを走り続ける。 そうした言葉が、言葉を壊していく。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年11月20日再読編集した@ 自宅長いけれど引用。9-10頁より。 † こうした言葉は、中身があるのかどうかはわからないけれど、発信者の威勢の良いときには価値がありそうに見える。あるいは、威勢の良さだけが価値を担保しているとも言える。なんだか「軍票」(軍が発行する特殊な通貨、「軍用手票」の略)みたいだ。 ああした言葉に「頼もしさ」や「雄々しさ」を感じてしまったとしたら、一度立ち止まって、深呼吸してみて、自分がつかまされているのが本当に軍票じゃないかどうかを確認した方がいいだろう。 [...] 軍票的な言葉は、自分の価値が下がらないように、本当は自分に価値なんてないことがバレないように、常に敵を作り、対立をあおり、気勢を上げる無限ループを走り続ける。 そうした言葉が、言葉を壊していく。

 花木コヘレト@qohelet2025年10月31日読み終わった図書館本文学障害者まず、amazonでもreadsでも、びっくりするくらいの評が付いていて、驚きました。障害者福祉にも関心を持つ方が多いのは、ハンセン病に関心のある私にとっては、うれしい驚きです。 次に、不満点を述べておくと、著者の問題意識のあり方が、ステレオタイプかなあと思いました。語り口が柔らかいのは、文章が読みやすくなるので良いのですが、問題点を鋭く言葉で掴むのに、問題意識の曖昧な出発点は、分かりやすいリベラル一般の意識のそれでした。だから、著者の言葉は、充分過ぎるほどマジョリティのもので、決して「まとまらない言葉」ではないのではないか?と疑問を持ちました。本書に示された問題意識は、著者の独自の問題意識とは呼べないと思います。歴史的に繰り返されてきている問題意識、と言えると思います。 にも関わらず、著者の優れた点は、歴史に埋もれている言葉を丁寧に拾い上げている点と、鋭い問題提起を提出できる点にある、と思います。特に後者の問題提起については、p136にある「文学者の仕事は「無い言葉」を探すことだ」という鋭い指摘があります。著者の非凡な能力を示す指摘だと思います。僕は詩を書く人間なのですが、まさに詩とは「この世にまだ無い言葉」を造形する作業だと思いますので、著者の鋭さには深く唸らされたところです。
花木コヘレト@qohelet2025年10月31日読み終わった図書館本文学障害者まず、amazonでもreadsでも、びっくりするくらいの評が付いていて、驚きました。障害者福祉にも関心を持つ方が多いのは、ハンセン病に関心のある私にとっては、うれしい驚きです。 次に、不満点を述べておくと、著者の問題意識のあり方が、ステレオタイプかなあと思いました。語り口が柔らかいのは、文章が読みやすくなるので良いのですが、問題点を鋭く言葉で掴むのに、問題意識の曖昧な出発点は、分かりやすいリベラル一般の意識のそれでした。だから、著者の言葉は、充分過ぎるほどマジョリティのもので、決して「まとまらない言葉」ではないのではないか?と疑問を持ちました。本書に示された問題意識は、著者の独自の問題意識とは呼べないと思います。歴史的に繰り返されてきている問題意識、と言えると思います。 にも関わらず、著者の優れた点は、歴史に埋もれている言葉を丁寧に拾い上げている点と、鋭い問題提起を提出できる点にある、と思います。特に後者の問題提起については、p136にある「文学者の仕事は「無い言葉」を探すことだ」という鋭い指摘があります。著者の非凡な能力を示す指摘だと思います。僕は詩を書く人間なのですが、まさに詩とは「この世にまだ無い言葉」を造形する作業だと思いますので、著者の鋭さには深く唸らされたところです。



- DaDa@tub2025年9月9日読み終わったまえがきの書き出しにはこう書かれています。 「 「言葉が壊れてきた」と思う。 いや、言葉そのものが勝手に壊れることはないから、「壊された」という方が正確かもしれない」 また「言葉が壊される」の定義を 「言葉が壊されるというのは、ひとつには、人の尊厳を傷つけるような言葉が発せられること、そうした言葉が生活圏にまぎれ込んでいることへの恐れやためらいの感覚が薄くなってきた、ということだ」としています。 人は言葉によって救われる事もあるが、立ち直れないほど傷付ける事、大袈裟でなく他者や私を殺す事も充分に可能なものです。 安倍政権以降の政治家の無責任な態度・言説が吐かれ、SNSの普及からヘイトスピーチが蔓延、他者への軽重内混ぜの憎悪が可視化される事で、言葉の軽さや不信感が空気となって私達の取り囲んでいる。 著者はその空気に抵抗する為、悔しがる為、 現在まで出会い拾い上げた言葉や彼に贈られた言葉達を、日々遭遇する状況や生じた感情を起点に引き出しエピソードと共に書き記しています。 本書は著者が出会う言葉に立ち止まり考え続ける姿が、言葉の贈り主への感謝と私達への祈りが刻まれているのが感じられると思います。


 さゆり@happyoukai2025年8月18日読み終わった生きていく中で感じていた漠然とした違和感に輪郭を与えてくれた本。 生きている限り違和感は解消されることはないと思う。けど、この本の言葉たちを忘れずにいたら、解消はしなくても歩み寄ることはできて、最悪の状態よりはいい状態にいられると思った。 排除されないために排除しない! あと、「川の字に寝るっていうんだね」は一生忘れることはないと思った。 この本を薦めてくれた人に本当に感謝している。
さゆり@happyoukai2025年8月18日読み終わった生きていく中で感じていた漠然とした違和感に輪郭を与えてくれた本。 生きている限り違和感は解消されることはないと思う。けど、この本の言葉たちを忘れずにいたら、解消はしなくても歩み寄ることはできて、最悪の状態よりはいい状態にいられると思った。 排除されないために排除しない! あと、「川の字に寝るっていうんだね」は一生忘れることはないと思った。 この本を薦めてくれた人に本当に感謝している。



 ☁️@mmccxx2025年8月9日読み終わった再読。 ・戦後80年という節目の年かつ終戦の日が近いこともあり、戦時中の障害者の話にものすごく打ちひしがれてしまった。 “戦時中の障害者たちは、「お国の役に立たない」ということで、ものすごく迫害された。「国家の恥」「米食い虫」なんていう言葉で罵られた。そうした迫害に苦しんだ人たちだからこそ、「障害者を苦しめる戦争反対!」とはならない。むしろ、なれないのだ。迫害されている人は、これ以上迫害されないように、世間の空気を必死に感じ取ろうとする。どういった言動をとればいじめられずに済むか、自分をムチ打つ手をゆるめてもらえるかを必死になって考える。“『第七話 「お国の役」に立たなかった人』P104-105 ・本書中で触れられていた新潮社の杉田水脈氏の件から7年もの月日が経っていたのにも関わらず、直近に高山正之氏のコラムの件があり、会社として何も変わっていないことになんだか本当に愕然としてしまった。 ・しかし、そういう最悪とも呼べることがあっても、差別や「言葉の壊れ」に抗い続けたいと思える本なのがこの本の良い所だよな……と思う。 “障害があろうが、病気があろうが、子供だろうが、ルーツが違っていようが、人には絶対に侵害してはならない一線というものがある。でも、ここ最近、この一線を乱暴に踏み越えたり、立場の弱い人たちの一線の幅を勝手に挟めようとする動きがある。しかもお金があったり、権力があったり、影響力を持っている人たちが、この一線を軽んじてきている。特に文学者として悲しいのは、ずっと文学を支えてきた老舗の出版社でさえ、この一線を軽んじる言葉の片棒を担ぐようになってしまったということだ。こうした言葉が降り積った社会を、次の世代(つまり、いまの子どもたち)に引き継げというのか。それは、どうしたって許せない。ぼくらは絶対に侵害してはいけない一線を守る言葉を、急いで積み上げなければならない。誰かの一線を軽んじる社会は、最終的に、誰の一線も守らないのだから。“『第十話 一線を守る言葉』P144-145
☁️@mmccxx2025年8月9日読み終わった再読。 ・戦後80年という節目の年かつ終戦の日が近いこともあり、戦時中の障害者の話にものすごく打ちひしがれてしまった。 “戦時中の障害者たちは、「お国の役に立たない」ということで、ものすごく迫害された。「国家の恥」「米食い虫」なんていう言葉で罵られた。そうした迫害に苦しんだ人たちだからこそ、「障害者を苦しめる戦争反対!」とはならない。むしろ、なれないのだ。迫害されている人は、これ以上迫害されないように、世間の空気を必死に感じ取ろうとする。どういった言動をとればいじめられずに済むか、自分をムチ打つ手をゆるめてもらえるかを必死になって考える。“『第七話 「お国の役」に立たなかった人』P104-105 ・本書中で触れられていた新潮社の杉田水脈氏の件から7年もの月日が経っていたのにも関わらず、直近に高山正之氏のコラムの件があり、会社として何も変わっていないことになんだか本当に愕然としてしまった。 ・しかし、そういう最悪とも呼べることがあっても、差別や「言葉の壊れ」に抗い続けたいと思える本なのがこの本の良い所だよな……と思う。 “障害があろうが、病気があろうが、子供だろうが、ルーツが違っていようが、人には絶対に侵害してはならない一線というものがある。でも、ここ最近、この一線を乱暴に踏み越えたり、立場の弱い人たちの一線の幅を勝手に挟めようとする動きがある。しかもお金があったり、権力があったり、影響力を持っている人たちが、この一線を軽んじてきている。特に文学者として悲しいのは、ずっと文学を支えてきた老舗の出版社でさえ、この一線を軽んじる言葉の片棒を担ぐようになってしまったということだ。こうした言葉が降り積った社会を、次の世代(つまり、いまの子どもたち)に引き継げというのか。それは、どうしたって許せない。ぼくらは絶対に侵害してはいけない一線を守る言葉を、急いで積み上げなければならない。誰かの一線を軽んじる社会は、最終的に、誰の一線も守らないのだから。“『第十話 一線を守る言葉』P144-145




 芙柚@mint_2025年4月28日読み終わったp.66 宛先を特定できない負の感情は、結局、個々人の中で処理せざるをえなくなる。その処理費用として、多額の自尊心が支払われていく。「社会と闘う」「社会に抗う」ことのむずかしさは、こういったところにある。 自分がいかに社会に目を向けられていないかを痛感させられた。誰かを傷つける言葉が蔓延る今の社会、それに慣れてしまっている自分。 言葉が壊れていく社会で、私はどうするのか、どうしたいのか。考え続けていきたいと思えた。
芙柚@mint_2025年4月28日読み終わったp.66 宛先を特定できない負の感情は、結局、個々人の中で処理せざるをえなくなる。その処理費用として、多額の自尊心が支払われていく。「社会と闘う」「社会に抗う」ことのむずかしさは、こういったところにある。 自分がいかに社会に目を向けられていないかを痛感させられた。誰かを傷つける言葉が蔓延る今の社会、それに慣れてしまっている自分。 言葉が壊れていく社会で、私はどうするのか、どうしたいのか。考え続けていきたいと思えた。



 ︎︎文 華@opurinchan2025年4月14日読み終わった教えてもらい読みたいと思った一冊。 途中空けちゃったので一年ぐらいかかったけれど、ゆっくりこの本と向き合えて本当によかったと思った。 それはつまり、言葉と向き合い考えることができる時間だったということ。 著者のお話から言葉の在り方や重み、想像力を養うことの重要性を改めて感じた。 日頃から自分が思っていることや感じていることとも重なり、自分事としても受け取りやすく、きっと何度も読み返すであろう一冊。
︎︎文 華@opurinchan2025年4月14日読み終わった教えてもらい読みたいと思った一冊。 途中空けちゃったので一年ぐらいかかったけれど、ゆっくりこの本と向き合えて本当によかったと思った。 それはつまり、言葉と向き合い考えることができる時間だったということ。 著者のお話から言葉の在り方や重み、想像力を養うことの重要性を改めて感じた。 日頃から自分が思っていることや感じていることとも重なり、自分事としても受け取りやすく、きっと何度も読み返すであろう一冊。

 曖昧模糊@sukonbu_uo_ou_2025年3月23日読んでるかつて読んだずっと大事に読むずっと読み続けるこれからもずっと読む障害者運動家などの非抑圧者の表現を研究している荒井裕樹さんによる言葉にまつわるエッセイ。 「言葉が壊されてきた」ことに警鐘を鳴らし、それについて考え、抗う一冊。荒井さんが関わった人や読んだ本の中の言葉など、いろいろな人の言葉から、言葉が持つ尊厳や力を見つめ直す。 何年先もずっと大切に読みたい。 何かはわからないけど、大事なものが自分から抜け落ちている気がする時に開くようにしている(それは大体疲れて余裕がないとき)。 第四話 「負の感情」の処理費用 p67 田中美津さんの言葉や 第九話 ムードに消される声 p128 内田みどりさんの言葉は何度も本を開いて繰り返し読んで心に刻んでいる。
曖昧模糊@sukonbu_uo_ou_2025年3月23日読んでるかつて読んだずっと大事に読むずっと読み続けるこれからもずっと読む障害者運動家などの非抑圧者の表現を研究している荒井裕樹さんによる言葉にまつわるエッセイ。 「言葉が壊されてきた」ことに警鐘を鳴らし、それについて考え、抗う一冊。荒井さんが関わった人や読んだ本の中の言葉など、いろいろな人の言葉から、言葉が持つ尊厳や力を見つめ直す。 何年先もずっと大切に読みたい。 何かはわからないけど、大事なものが自分から抜け落ちている気がする時に開くようにしている(それは大体疲れて余裕がないとき)。 第四話 「負の感情」の処理費用 p67 田中美津さんの言葉や 第九話 ムードに消される声 p128 内田みどりさんの言葉は何度も本を開いて繰り返し読んで心に刻んでいる。

 okaeri@b0c9e12025年1月16日買った読み終わったまた読みたいずっと大事に読む『実際にそこにいるのはさまざまな事情を抱えた一人ひとりの人間だ。だから、ひとつの言葉が全員の心にぴったりと当てはまるなんてことがあるはずない。「その言葉は今の心情にそぐわない」という人がいれば、そのたびに言葉を探すことが必要だ。』
okaeri@b0c9e12025年1月16日買った読み終わったまた読みたいずっと大事に読む『実際にそこにいるのはさまざまな事情を抱えた一人ひとりの人間だ。だから、ひとつの言葉が全員の心にぴったりと当てはまるなんてことがあるはずない。「その言葉は今の心情にそぐわない」という人がいれば、そのたびに言葉を探すことが必要だ。』


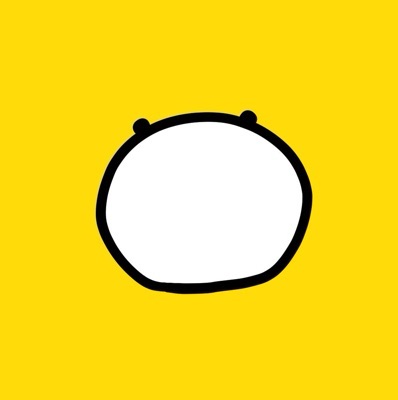
 sasai@sasai_742024年8月17日かつて読んだ端的な表現で共感させたり激昂させたりすることが評価してもらうための入口、みたいな流れの中にいるなって思う。そもそも誰かに決めつけられたり自分で押し込めるものでもないのに。その流れに身を任せて、立ち止まったり立ち向かったりすることを放棄している自分はあまりにも無神経だ。 諦めることは不動ではなくて言葉への、使われ方や自分を含めた使う人への加害になるかもしれない。できるだけ忘れないようにしたいし、忘れたらまた読み返す。
sasai@sasai_742024年8月17日かつて読んだ端的な表現で共感させたり激昂させたりすることが評価してもらうための入口、みたいな流れの中にいるなって思う。そもそも誰かに決めつけられたり自分で押し込めるものでもないのに。その流れに身を任せて、立ち止まったり立ち向かったりすることを放棄している自分はあまりにも無神経だ。 諦めることは不動ではなくて言葉への、使われ方や自分を含めた使う人への加害になるかもしれない。できるだけ忘れないようにしたいし、忘れたらまた読み返す。