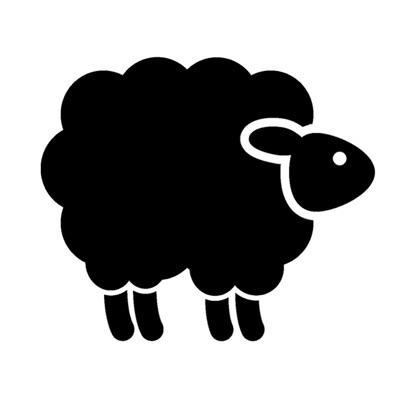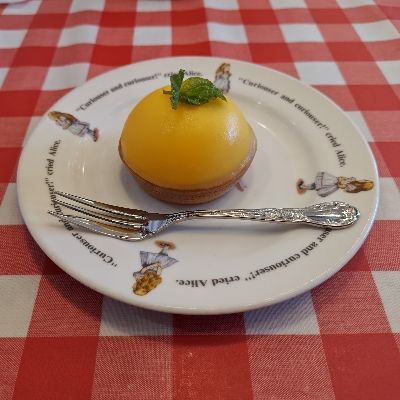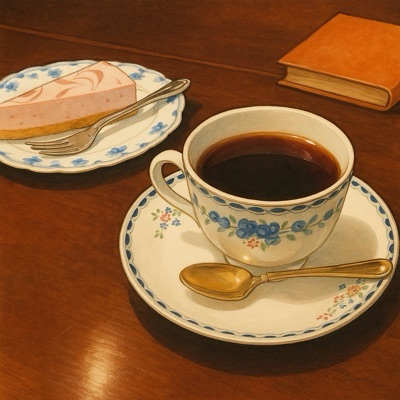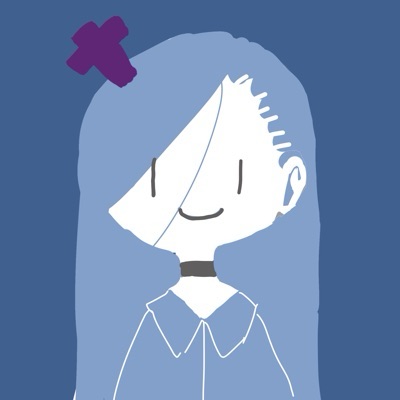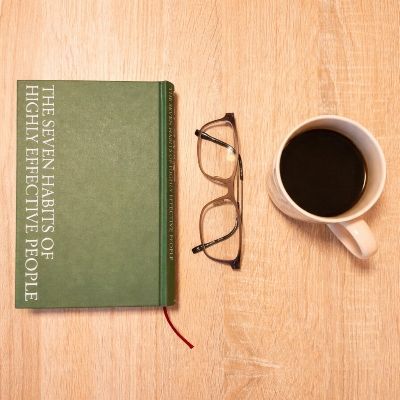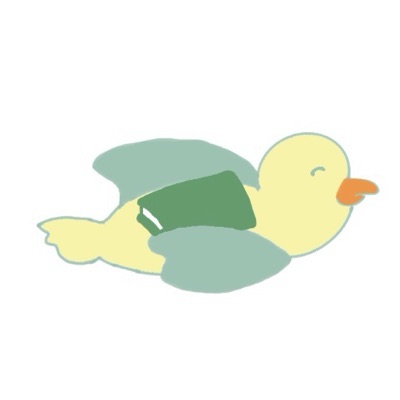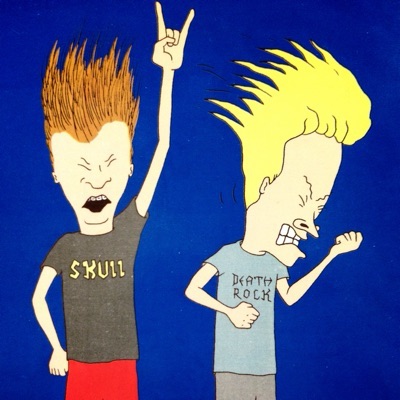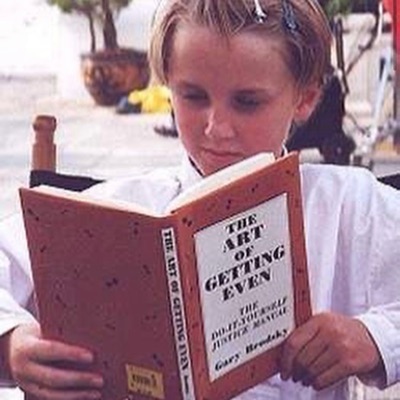休養学
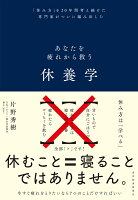
213件の記録
 atwf@atwf_13322026年2月8日読み終わった借りてきた平日のあとの土日に休むのではなく、 土日に休んだ分で平日働くという視点 以下、覚え書き 疲れる前に活力を補給する 運動タイプの休息 血の巡りを整えるための軽微な運動 ヨガ、ストレッチ、ウォーキング、入浴 サルコペニア 錆び付く 栄養タイプの休息 消化器系を休ませる、老廃物を排出、デトックス、 無理に食べない 軽くすませる 朝食の時間を固定 親交タイプの休息 言葉を交わす 交流、触れ合い 一秒間に15センチ手を動かす→撫でる動作 オキシトシン 娯楽タイプの休息 ゆっくりした音楽 副交感神経 ゲームは一定時間内で 気分の良くなる趣味嗜好 造形・創造タイプの休息 詩を書く ブログを書く 集中する 瞑想、マインドフルネス 転換タイプの休養 旅行、模様替え、着替え、買い物、外食 複合的に組み合わせる いいとこどり 料理をすれば造形タイプ それを食べて栄養タイプ 誰かと作れば親交タイプ 公園で食べれば運動タイプ 休養難民
atwf@atwf_13322026年2月8日読み終わった借りてきた平日のあとの土日に休むのではなく、 土日に休んだ分で平日働くという視点 以下、覚え書き 疲れる前に活力を補給する 運動タイプの休息 血の巡りを整えるための軽微な運動 ヨガ、ストレッチ、ウォーキング、入浴 サルコペニア 錆び付く 栄養タイプの休息 消化器系を休ませる、老廃物を排出、デトックス、 無理に食べない 軽くすませる 朝食の時間を固定 親交タイプの休息 言葉を交わす 交流、触れ合い 一秒間に15センチ手を動かす→撫でる動作 オキシトシン 娯楽タイプの休息 ゆっくりした音楽 副交感神経 ゲームは一定時間内で 気分の良くなる趣味嗜好 造形・創造タイプの休息 詩を書く ブログを書く 集中する 瞑想、マインドフルネス 転換タイプの休養 旅行、模様替え、着替え、買い物、外食 複合的に組み合わせる いいとこどり 料理をすれば造形タイプ それを食べて栄養タイプ 誰かと作れば親交タイプ 公園で食べれば運動タイプ 休養難民 メリル@tkno7302026年2月1日読み終わった休みに合わせて買ってみた。寝たりゴロゴロしたりすることだけが休みではないのはわかっていたが、楽しいことをしないと勿体無いと思っていた自分の思考も休めていなさそうだなと思った。
メリル@tkno7302026年2月1日読み終わった休みに合わせて買ってみた。寝たりゴロゴロしたりすることだけが休みではないのはわかっていたが、楽しいことをしないと勿体無いと思っていた自分の思考も休めていなさそうだなと思った。
- Daisuke@Daisuke2026年1月12日読み終わった@ 自宅「攻めの休養」っていい言葉。 ダラダラ過ごすよりも何か目的を持って過ごすと気分転換になっていいなぁ、くらいの感覚だったのが、この本では色々と分かりやすい語り口で、新たに気がつくこともあったりしてとても楽しめました。 (くれぐれも詰め込み過ぎには気をつけたいけれど)より前向きに休養を楽しむ気持ちになれる、そんな一冊でした。

 青山@aoyama9122026年1月6日読み終わった面白かった2026年1月読了本なぜ疲れるのか、疲れるとどうなるか、疲れを取るにはどうすればいいか。 疲れを取るには休養が大事だが、休養とはただ睡眠を取ったり横になったりすることではなく、「攻めの休養」も必要。 疲れとは?休養とは?を分かりやすく丁寧に解説してくれている。 なお、疲れている人向けの本なので大事な部分がマーカーされており、マーカー部分の拾い読みだけでも十分理解できる親切仕様。 色も、文字の黒とマーカーの目に優しい色合いの黄色だけしか使っていないので、視覚的にも読んでいて楽。疲れた人にとことん配慮している本だと思う。 個人的には、「疲労の原因は乳酸」「12時からはシンデレラタイム」が現在は否定されているという話が興味深かった。 常識は時代とともに変わる。 少しずつ読もうと思ったのに、読みやすく興味深い内容ばかりだったのであっという間に読んでしまった。
青山@aoyama9122026年1月6日読み終わった面白かった2026年1月読了本なぜ疲れるのか、疲れるとどうなるか、疲れを取るにはどうすればいいか。 疲れを取るには休養が大事だが、休養とはただ睡眠を取ったり横になったりすることではなく、「攻めの休養」も必要。 疲れとは?休養とは?を分かりやすく丁寧に解説してくれている。 なお、疲れている人向けの本なので大事な部分がマーカーされており、マーカー部分の拾い読みだけでも十分理解できる親切仕様。 色も、文字の黒とマーカーの目に優しい色合いの黄色だけしか使っていないので、視覚的にも読んでいて楽。疲れた人にとことん配慮している本だと思う。 個人的には、「疲労の原因は乳酸」「12時からはシンデレラタイム」が現在は否定されているという話が興味深かった。 常識は時代とともに変わる。 少しずつ読もうと思ったのに、読みやすく興味深い内容ばかりだったのであっという間に読んでしまった。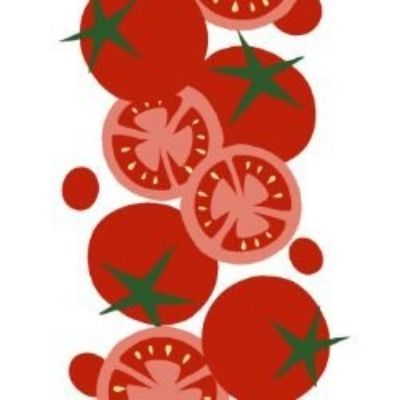
- you1@you12026年1月2日読み終わった待ち合わせまで1時間ほどあったのでさーっと立ち読み。 どこかで読んだ話が多いものの、疲労とパフォーマンスについては何度でも意識したいなと思った。 活力に関してはあまり意識したことは無かったので取り入れていきたいなと思う。
- 王英次@OAG2025年11月24日買った読み終わったコーヒー・甘いもの・睡眠という日課が帯にバッテンされてて思わず購入。もちろん睡眠も大事なのは前提で、どう疲れているからどう回復していくか、という内容。この手の話は、数年後には違うと判明しているかもしれないけど、当たり前ながら疲労を感じていない事と疲れていない事はイコールではないという当たり前の原点を改めて認識して、肉体以外の疲労について考え直してもいいかなと思った。 でも、コーヒー飲まないと職場で耐えられないんだよな。それが原因で元々弱い胃腸にダメージがいくという悪循環なのもわかるんだけど。

 おじょ@dstn18c2025年11月20日読み終わった読んでいる途中で、私が疲労や疲労回復に関して論文を漁っていた時に読んでいた論文たちと同じことが書いていて、「参考文献同じじゃん」と笑ってしまった一冊。
おじょ@dstn18c2025年11月20日読み終わった読んでいる途中で、私が疲労や疲労回復に関して論文を漁っていた時に読んでいた論文たちと同じことが書いていて、「参考文献同じじゃん」と笑ってしまった一冊。 きなこ@kinako20252025年11月13日読み終わった疲れは、ただゴロゴロと横になるだけでとれるものではない。「疲れ」とはどういう状態をいうのか。 「人はなぜ疲れるのか」「疲れても無理をして休まずにいると、人間の体はどうなるのか」「どんな休み方をすれば最も効果的に疲れがとれるのか」をデータ等とともに分かりやすく解説した本。
きなこ@kinako20252025年11月13日読み終わった疲れは、ただゴロゴロと横になるだけでとれるものではない。「疲れ」とはどういう状態をいうのか。 「人はなぜ疲れるのか」「疲れても無理をして休まずにいると、人間の体はどうなるのか」「どんな休み方をすれば最も効果的に疲れがとれるのか」をデータ等とともに分かりやすく解説した本。 tommy@tommy892025年11月1日読み終わった教養年々疲れが取れなくなってきているので… 休養をしっかりとってフル充電にして日々過ごすためには活力をどう取り入れられるかということで、私も攻めの休養を意識したいと思います。
tommy@tommy892025年11月1日読み終わった教養年々疲れが取れなくなってきているので… 休養をしっかりとってフル充電にして日々過ごすためには活力をどう取り入れられるかということで、私も攻めの休養を意識したいと思います。
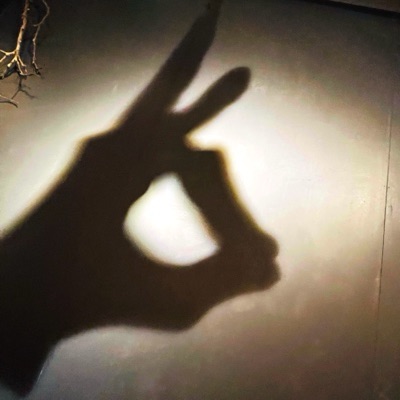
 5yndr0m3@5yndr0m32025年10月8日読み終わった感想紹介ただ寝るだけが休養ではなく、活力を得る休養をすること。 活力を得る休養は、忙しかったけど楽しかったと思え、また明日から頑張ろうと思えるような休養。 休養には休息、運動、栄養、親交、娯楽、造形・想像・転換の7つのタイプがある。 それぞれを組み合わせて体と心を休めることで活力を得られる。 次の休みはダラダラとスマホを見て過ごすのは辞める。
5yndr0m3@5yndr0m32025年10月8日読み終わった感想紹介ただ寝るだけが休養ではなく、活力を得る休養をすること。 活力を得る休養は、忙しかったけど楽しかったと思え、また明日から頑張ろうと思えるような休養。 休養には休息、運動、栄養、親交、娯楽、造形・想像・転換の7つのタイプがある。 それぞれを組み合わせて体と心を休めることで活力を得られる。 次の休みはダラダラとスマホを見て過ごすのは辞める。
 ヨハネくん@plaudite_opera2025年8月27日読み終わった正直、知ってる内容が多く満足感は低め ただ、実践出来てるかどうかは別なので改めて読む価値はあった しかし1650円するので、他の本を買った方が良いかも
ヨハネくん@plaudite_opera2025年8月27日読み終わった正直、知ってる内容が多く満足感は低め ただ、実践出来てるかどうかは別なので改めて読む価値はあった しかし1650円するので、他の本を買った方が良いかも ヨハネくん@plaudite_opera2025年8月23日読み始めたちょっと開いた文字が大きめだし節も短く区切られてるから取り掛かりやすい これなら疲れてても読めるかな 1週間ぐらいでの読了を目安に頑張ります
ヨハネくん@plaudite_opera2025年8月23日読み始めたちょっと開いた文字が大きめだし節も短く区切られてるから取り掛かりやすい これなら疲れてても読めるかな 1週間ぐらいでの読了を目安に頑張ります ちょこれーと*@5_ogd2025年8月20日読んでる■ATP(アデノシン三リン酸) …傷ついた細胞を修復するためのエネルギー →脂質・タンパク質・糖質(炭水化物)の三大栄養素からつくられるが、ビタミン・ミネラルなどの補酵素がなければ変換されない。 『疲労回復のためには、いわゆるバランスのよい食事をとることが大事』 『痛み・発熱・疲労は、体の異常を知らせる三大生体アラート』
ちょこれーと*@5_ogd2025年8月20日読んでる■ATP(アデノシン三リン酸) …傷ついた細胞を修復するためのエネルギー →脂質・タンパク質・糖質(炭水化物)の三大栄養素からつくられるが、ビタミン・ミネラルなどの補酵素がなければ変換されない。 『疲労回復のためには、いわゆるバランスのよい食事をとることが大事』 『痛み・発熱・疲労は、体の異常を知らせる三大生体アラート』 ちょこれーと*@5_ogd2025年8月20日また読み始めた■プレゼンティーズム(Presenteeism) →疾病就業。頭痛や胃腸の不調、軽度のうつ、花粉症などのアレルギー症といった「つらくても無理をすれば出社できる程度の疾病」。 ■アブセンティーズム(Absenteeism) →病欠。プレゼンティーズムの状態がさらに進んで、出社できない状態。 『グーグル翻訳で「お疲れさま」を英語に翻訳してみると、「Thank you for your hard work.」と出ます。直訳すると、重労働をしてくれてありがとう、というような意味です。』 ★日本疲労学会による疲労の定義 「過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退した状態である」 『考えてみれば、われわれビジネスパーソンもアスリートのようなものです。やらなければいけない仕事や家事があり、育児や介護など、人それぞれ果たさなければいけない責任があります。』 言われてみればその通りだと思った。しかもアスリートとは違いわれわれにはトレーナーはついていない。自分自身が自分のことに目を配り、オーバートレーニング症候群に陥らないよう的確に疲労を解消していくことが求められる。 ■オーバートレーニング症候群 →疲労が回復していない、パフォーマンスが低下した状態でも休まずにトレーニングを続け、どんどんパフォーマンスが下がる負のスパイラルのこと。
ちょこれーと*@5_ogd2025年8月20日また読み始めた■プレゼンティーズム(Presenteeism) →疾病就業。頭痛や胃腸の不調、軽度のうつ、花粉症などのアレルギー症といった「つらくても無理をすれば出社できる程度の疾病」。 ■アブセンティーズム(Absenteeism) →病欠。プレゼンティーズムの状態がさらに進んで、出社できない状態。 『グーグル翻訳で「お疲れさま」を英語に翻訳してみると、「Thank you for your hard work.」と出ます。直訳すると、重労働をしてくれてありがとう、というような意味です。』 ★日本疲労学会による疲労の定義 「過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退した状態である」 『考えてみれば、われわれビジネスパーソンもアスリートのようなものです。やらなければいけない仕事や家事があり、育児や介護など、人それぞれ果たさなければいけない責任があります。』 言われてみればその通りだと思った。しかもアスリートとは違いわれわれにはトレーナーはついていない。自分自身が自分のことに目を配り、オーバートレーニング症候群に陥らないよう的確に疲労を解消していくことが求められる。 ■オーバートレーニング症候群 →疲労が回復していない、パフォーマンスが低下した状態でも休まずにトレーニングを続け、どんどんパフォーマンスが下がる負のスパイラルのこと。
 um@__um__g2025年8月11日読み終わった健康の三大要素の一つ、休養に焦点を当てた書籍。週末休んでもぐったりしてる、休んだ気がしない、といった社会人でもパフォーマンスを高めるにはどうしたらいいか、ということを休養に焦点を当てて分かりやすくまとめられていた。 攻めの休養、という逆の意味にも聞こえる考え方は私にとって新鮮だったし、ただ休むだけでは100%回復しておらず活動→疲労→休養のサイクルに"活力"を加えることで100%に近いところまで持って行く、というのはとても学びだった。言われてみればただゴロゴロしたりダラダラ寝たりしていても疲れが取れるどころか余計疲れたりする(ゴロゴロ過ごすことで気持ちが楽になることはあるから全く否定したくはないけど)。 週末ゆっくりしたりリフレッシュしても月曜日の朝のしんどさは全然取れないからどうしたものか…と悩んでいたので今出会えて良かった一冊。 休むことは手を抜くことに思えてしまうから仕事も詰め詰めで頑張ってしまうけれど、本書を繰り返し読んで休養が自分の中で当たり前になるようにしたい。
um@__um__g2025年8月11日読み終わった健康の三大要素の一つ、休養に焦点を当てた書籍。週末休んでもぐったりしてる、休んだ気がしない、といった社会人でもパフォーマンスを高めるにはどうしたらいいか、ということを休養に焦点を当てて分かりやすくまとめられていた。 攻めの休養、という逆の意味にも聞こえる考え方は私にとって新鮮だったし、ただ休むだけでは100%回復しておらず活動→疲労→休養のサイクルに"活力"を加えることで100%に近いところまで持って行く、というのはとても学びだった。言われてみればただゴロゴロしたりダラダラ寝たりしていても疲れが取れるどころか余計疲れたりする(ゴロゴロ過ごすことで気持ちが楽になることはあるから全く否定したくはないけど)。 週末ゆっくりしたりリフレッシュしても月曜日の朝のしんどさは全然取れないからどうしたものか…と悩んでいたので今出会えて良かった一冊。 休むことは手を抜くことに思えてしまうから仕事も詰め詰めで頑張ってしまうけれど、本書を繰り返し読んで休養が自分の中で当たり前になるようにしたい。

 +oRu@tn022025年8月8日読み終わった必死に働いてきたけど、休むことを忘れていた。スマン自分。 プレゼンティーズム(疾病就業) アブセンティーズム(病欠) 脱・休まない美徳、働く美徳 →キリスト教では、働くのは罪を負ってるから。 「自分の体力−疲労=自分が出せるパフォーマンス」 アスリートのオーバートレーニング症候群と同じ考え。 疲労感は、これ以上活動を続けると危険というサイン(アラート、警告) 痛み、発熱、疲労が3大生体アラート 疲労感は、一時的にマスキングされてしまう。 ストレッサーは、5種類(物理、化学、心理、生物学、社会) ①内分泌系 ストレス→脳下垂体→副腎皮質(肉まんの皮)→コルチゾール ②自律神経系 ストレス→脊髄→副腎髄質(肉まんの中身)→アドレナリン 活動→疲労→休養→⭐︎活力(攻めの休養)で満充電 ストレスコーピングリストの作成 脳の老廃物アミロイドβは、ノンレム睡眠時に脳外へ排出 寝過ぎない意識も大事 仕事がひと段落しなくても休む。 長期休の予定を先にいれる。 疲労しそうだから先に休む。 疲労をレコーディングする。 休む時はしっかり休む。
+oRu@tn022025年8月8日読み終わった必死に働いてきたけど、休むことを忘れていた。スマン自分。 プレゼンティーズム(疾病就業) アブセンティーズム(病欠) 脱・休まない美徳、働く美徳 →キリスト教では、働くのは罪を負ってるから。 「自分の体力−疲労=自分が出せるパフォーマンス」 アスリートのオーバートレーニング症候群と同じ考え。 疲労感は、これ以上活動を続けると危険というサイン(アラート、警告) 痛み、発熱、疲労が3大生体アラート 疲労感は、一時的にマスキングされてしまう。 ストレッサーは、5種類(物理、化学、心理、生物学、社会) ①内分泌系 ストレス→脳下垂体→副腎皮質(肉まんの皮)→コルチゾール ②自律神経系 ストレス→脊髄→副腎髄質(肉まんの中身)→アドレナリン 活動→疲労→休養→⭐︎活力(攻めの休養)で満充電 ストレスコーピングリストの作成 脳の老廃物アミロイドβは、ノンレム睡眠時に脳外へ排出 寝過ぎない意識も大事 仕事がひと段落しなくても休む。 長期休の予定を先にいれる。 疲労しそうだから先に休む。 疲労をレコーディングする。 休む時はしっかり休む。 1neko.@ichineko112025年6月17日読み終わった休養のバリエーションを豊富にしたい😊 寝るだけの休養だけでなく、食べ過ぎないで、体を休めることも大切だな。と思う。 「体」と「休」って、似てる。 一画違い。と いまさら、気づく。
1neko.@ichineko112025年6月17日読み終わった休養のバリエーションを豊富にしたい😊 寝るだけの休養だけでなく、食べ過ぎないで、体を休めることも大切だな。と思う。 「体」と「休」って、似てる。 一画違い。と いまさら、気づく。


 加非@chioneko2025年6月15日読み終わった全人類が多種多様なストレスに晒される現代。 ただ眠るだけの消極的休養では疲れは取れない。だからこそ、積極的休養を使いこなそう!という内容。 基本的には、どこかで聞き覚えのある知識が並んでいるのだけれど、そこから眠る以外の休養を取り入れるにはどうするのか?という展開が面白かった。 特に、疲れたから休むのではなく、先の疲れを予想して休養を取り準備する、という考え方は今まで場当たり的にしたことはあるけれど、計画的に利用しようと考えたことは無く面白かった。
加非@chioneko2025年6月15日読み終わった全人類が多種多様なストレスに晒される現代。 ただ眠るだけの消極的休養では疲れは取れない。だからこそ、積極的休養を使いこなそう!という内容。 基本的には、どこかで聞き覚えのある知識が並んでいるのだけれど、そこから眠る以外の休養を取り入れるにはどうするのか?という展開が面白かった。 特に、疲れたから休むのではなく、先の疲れを予想して休養を取り準備する、という考え方は今まで場当たり的にしたことはあるけれど、計画的に利用しようと考えたことは無く面白かった。

 ari@3211342025年5月6日読み終わった予定を入れず、部屋着のまま寝溜めをすることが自分にとっては休息だったけど、この本を読んで、いろんなタイプの休養を組み合わせてみようと思った。 人やペットに触れる時、1秒間に5~10㎝くらいの割合で手を動かすとオキシトシンが分泌されやすくなるそう。あとは森林浴の話も興味深かった。
ari@3211342025年5月6日読み終わった予定を入れず、部屋着のまま寝溜めをすることが自分にとっては休息だったけど、この本を読んで、いろんなタイプの休養を組み合わせてみようと思った。 人やペットに触れる時、1秒間に5~10㎝くらいの割合で手を動かすとオキシトシンが分泌されやすくなるそう。あとは森林浴の話も興味深かった。

- 小魚小骨@KoboneKozakana2025年4月6日読み終わった能動的な休養が肝。少し負荷をかけることも。運動が良いことは分かっているがなかなか…と思っていたが、寝るにしてもダラダラ寝るより「今日は寝る!」と能動的に寝ることが良いと知った。日本の平均労働時間が意外にも低いことに驚いた。



 萌生@moet-17152025年3月22日読み始めた読んでほしい人が周りにいすぎるし、何より最近疲れている私自身が急ぎ読みたい。上手く休めてないと思うんだよね、肉体的にも精神的にも。これを読んで「休養」の最適解を得たい。
萌生@moet-17152025年3月22日読み始めた読んでほしい人が周りにいすぎるし、何より最近疲れている私自身が急ぎ読みたい。上手く休めてないと思うんだよね、肉体的にも精神的にも。これを読んで「休養」の最適解を得たい。
 夏の季語@natsunokigo2025年3月18日読み終わった良いことは書いてあるけど、リカバリーウェアを作って売っている人が書いている宣伝本かと思ったらなんか急に冷めちゃったな。それはそれとして、内容的には良い本です。いまの日本に必要な本。こういう本は10万部も売れているというのが一つの希望ですらある。有害なマッチョイズムで疲れていてもゴリゴリ命を削って働く思想から、もうみんな降りたいんだよね本当は。
夏の季語@natsunokigo2025年3月18日読み終わった良いことは書いてあるけど、リカバリーウェアを作って売っている人が書いている宣伝本かと思ったらなんか急に冷めちゃったな。それはそれとして、内容的には良い本です。いまの日本に必要な本。こういう本は10万部も売れているというのが一つの希望ですらある。有害なマッチョイズムで疲れていてもゴリゴリ命を削って働く思想から、もうみんな降りたいんだよね本当は。









 つばめ@swallow32025年3月16日読み終わった疲れを取るためにずっと家にいてゴロゴロするより、体を動かしたりどこかへ出かけたりした方が回復したなと思うのは間違いじゃなかったんだと気付けた。 休養モデルを組み合わせることが大事。 転換、造形・想像、娯楽、親交、栄養、運動、休息
つばめ@swallow32025年3月16日読み終わった疲れを取るためにずっと家にいてゴロゴロするより、体を動かしたりどこかへ出かけたりした方が回復したなと思うのは間違いじゃなかったんだと気付けた。 休養モデルを組み合わせることが大事。 転換、造形・想像、娯楽、親交、栄養、運動、休息


 あやめ@ayame0814192025年3月7日買った読み終わった学び!まださらっと一読しただけだしこれから機会ごとに読み込む(はず)。 7つの方法はどれも言われてみればたしかに、と納得するけど「さぁ休んで!」と言われた時には取らないものもあったから、「そうか、これもありなんだ」と思えただけで私にとっては収穫あった。
あやめ@ayame0814192025年3月7日買った読み終わった学び!まださらっと一読しただけだしこれから機会ごとに読み込む(はず)。 7つの方法はどれも言われてみればたしかに、と納得するけど「さぁ休んで!」と言われた時には取らないものもあったから、「そうか、これもありなんだ」と思えただけで私にとっては収穫あった。 針山@hasco2025年3月4日読み終わった東京に雪が降った日。 午前中は仕事をして、午後はサボって六本木にJSB3 CLASSを観に行く。会期が終わりに近づいているせいか、館内はわりと混んでいた。 会場を出ると雨が降り始め、最寄り駅に着くとボトボトとした重たいみぞれになっていた。スタバに寄ってカフェミストを飲んでから家に帰る。 長女が週末から部活のLINEでトラブルを起こしていたが、それについては解決したようで、明るい顔で帰ってきた。よかったね。 次女は雪が気になるのか、何度も玄関を開けて外を確認していた。寒いのやだな〜と言いつつ、嬉しさの方が大きい表情で可愛い。 この本はそんなに目新しいことは書いてなかったのですが、推し活は正しい休養だとわかりましたので、これからも心置きなく推しを推していこうと思いました。
針山@hasco2025年3月4日読み終わった東京に雪が降った日。 午前中は仕事をして、午後はサボって六本木にJSB3 CLASSを観に行く。会期が終わりに近づいているせいか、館内はわりと混んでいた。 会場を出ると雨が降り始め、最寄り駅に着くとボトボトとした重たいみぞれになっていた。スタバに寄ってカフェミストを飲んでから家に帰る。 長女が週末から部活のLINEでトラブルを起こしていたが、それについては解決したようで、明るい顔で帰ってきた。よかったね。 次女は雪が気になるのか、何度も玄関を開けて外を確認していた。寒いのやだな〜と言いつつ、嬉しさの方が大きい表情で可愛い。 この本はそんなに目新しいことは書いてなかったのですが、推し活は正しい休養だとわかりましたので、これからも心置きなく推しを推していこうと思いました。


 coto@namakemono2025年2月17日読み終わったほほーん!おもしろい! 生理的、心理的、社会的に休養の仕方が7タイプあって、うまく組み合わせて休養しましょう。そんでもって、活力を高めるために上手に負荷をかけましょう、とのこと。土曜日から1週間のスケジュールを考えることにより「平日のあとの土日で休む」から「土日に休んだ分だけ働く」に変わる。これ良い! 日本人は、世界平均より年間145時間働いてる時間が少ないのにも関わらず、睡眠時間はワースト1位。疲労感感じ出る人は80%。=休むのが下手くそ!頑張ると同じくらい、休むことにも力を入れましょう!
coto@namakemono2025年2月17日読み終わったほほーん!おもしろい! 生理的、心理的、社会的に休養の仕方が7タイプあって、うまく組み合わせて休養しましょう。そんでもって、活力を高めるために上手に負荷をかけましょう、とのこと。土曜日から1週間のスケジュールを考えることにより「平日のあとの土日で休む」から「土日に休んだ分だけ働く」に変わる。これ良い! 日本人は、世界平均より年間145時間働いてる時間が少ないのにも関わらず、睡眠時間はワースト1位。疲労感感じ出る人は80%。=休むのが下手くそ!頑張ると同じくらい、休むことにも力を入れましょう!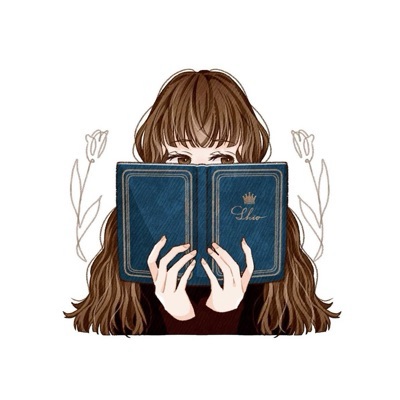
 パモちゃん@pamochan_01252025年2月8日買った読み終わった読書日記SNSで話題になってたから読んでみた なんとなく自分で思ってた休養の感覚が正しかったんだなぁと再確認できたし、より意識しよって思った この人YouTubeでもアナウンサーと対談しててそっち見てもよき
パモちゃん@pamochan_01252025年2月8日買った読み終わった読書日記SNSで話題になってたから読んでみた なんとなく自分で思ってた休養の感覚が正しかったんだなぁと再確認できたし、より意識しよって思った この人YouTubeでもアナウンサーと対談しててそっち見てもよき